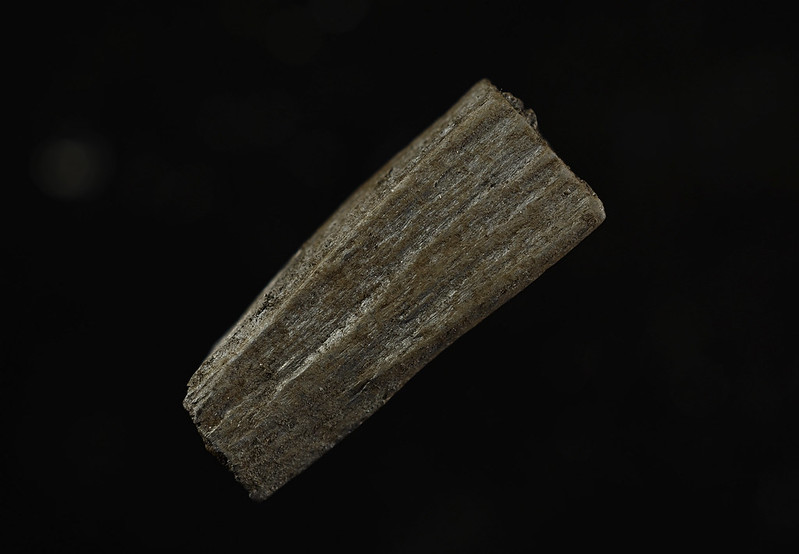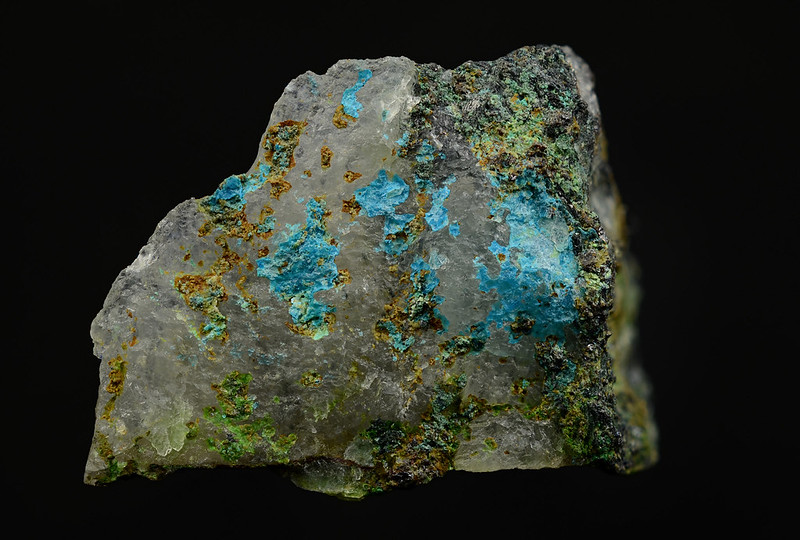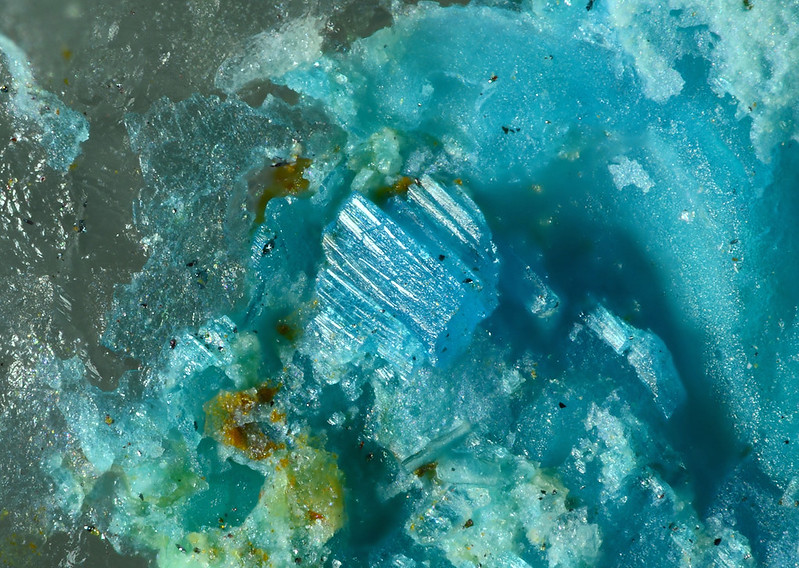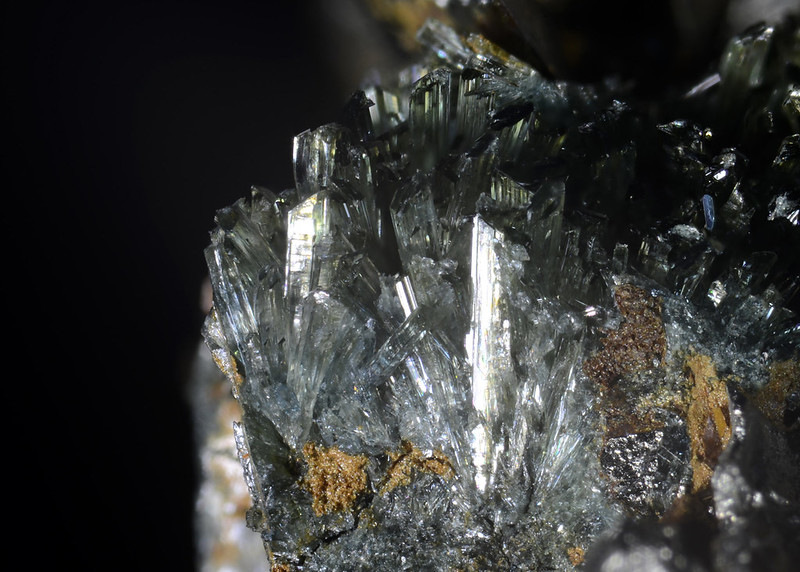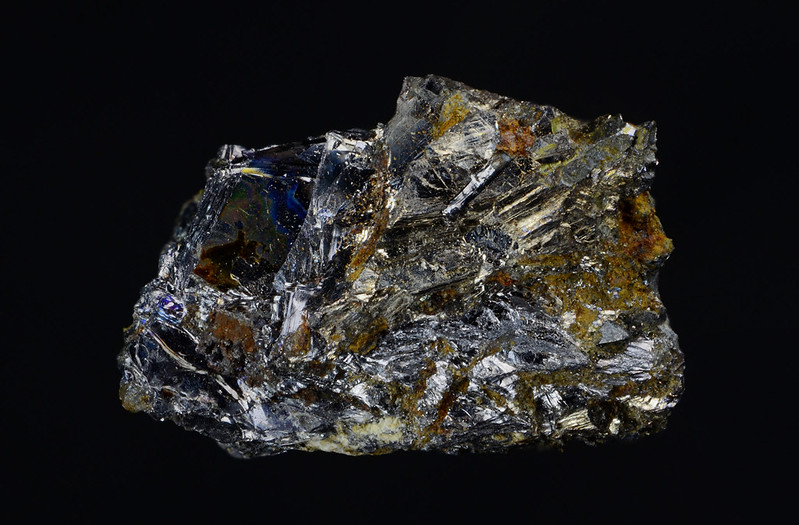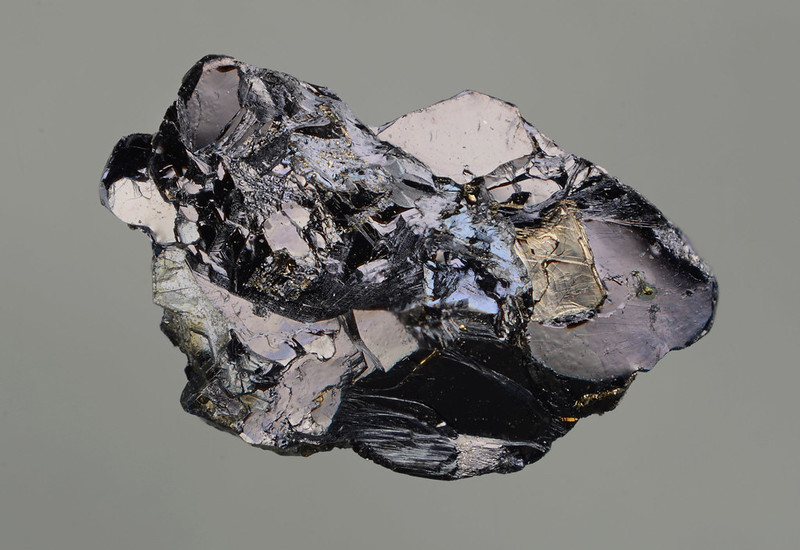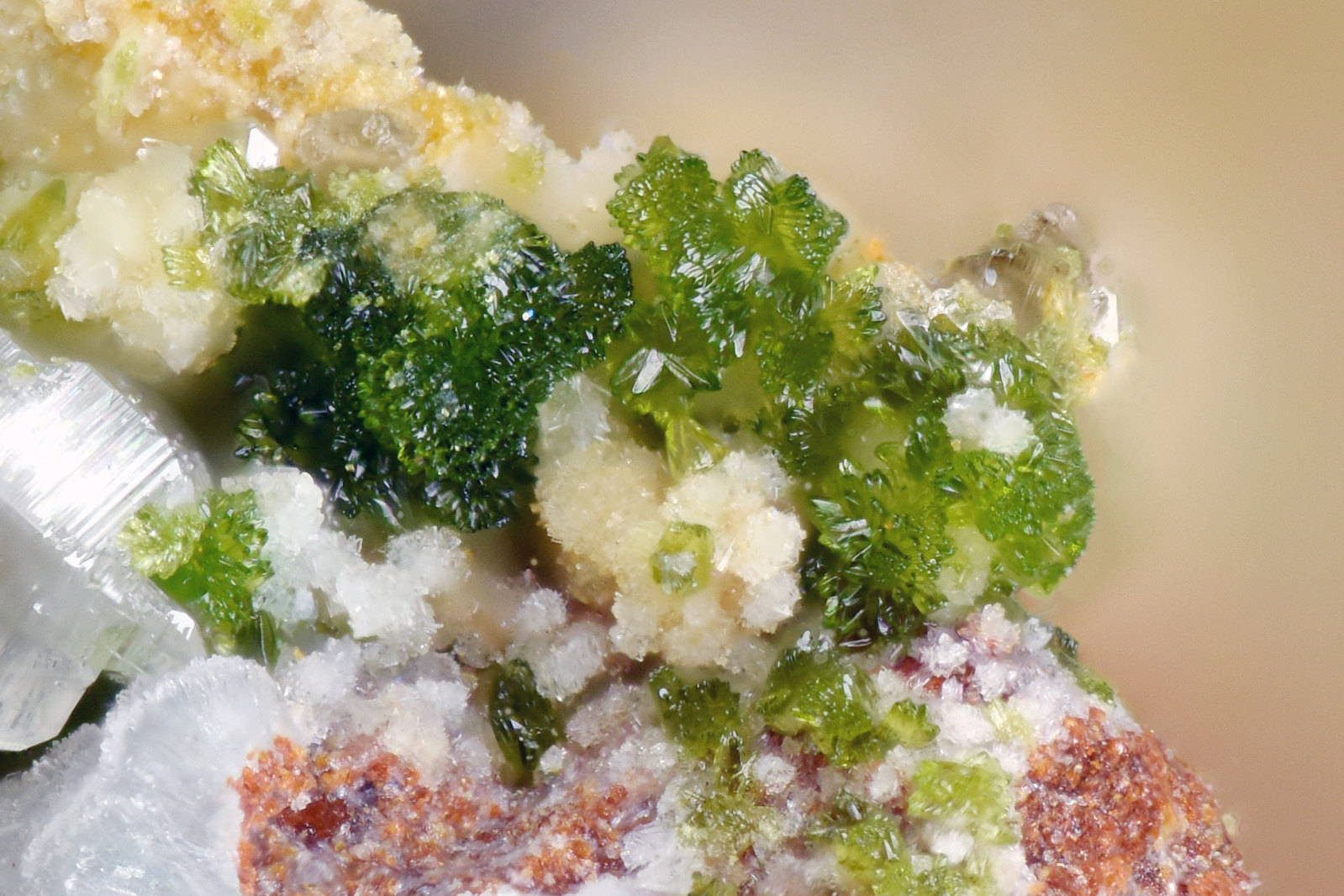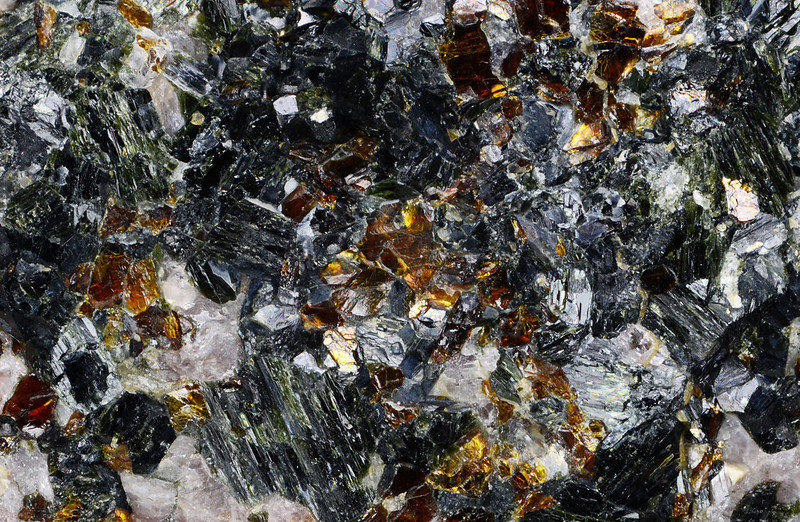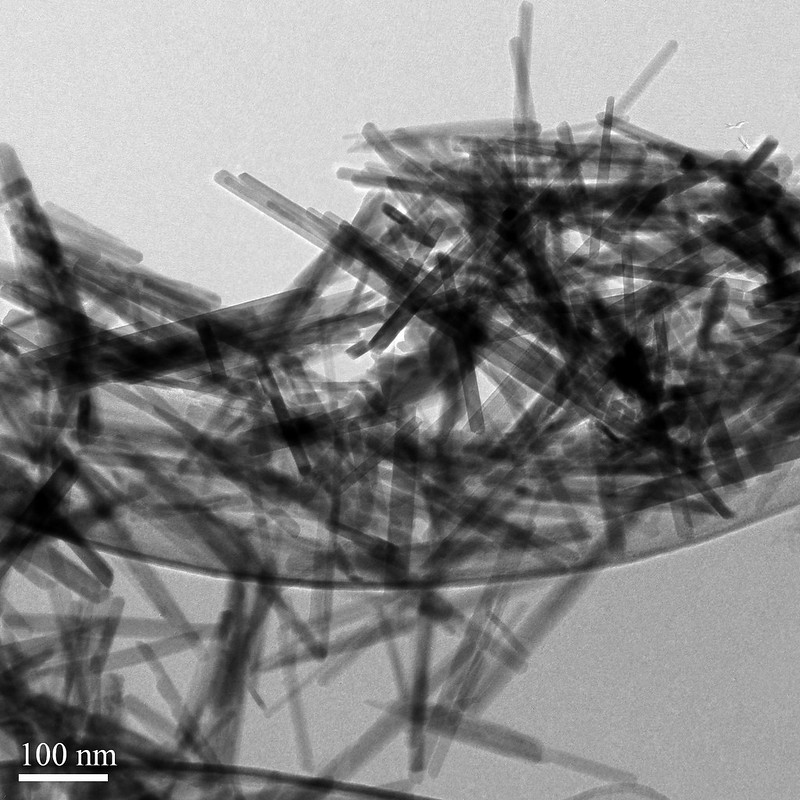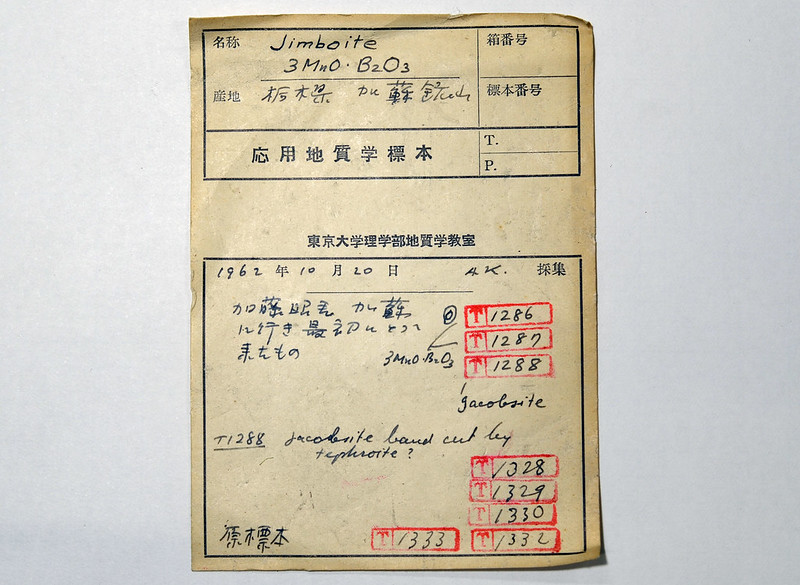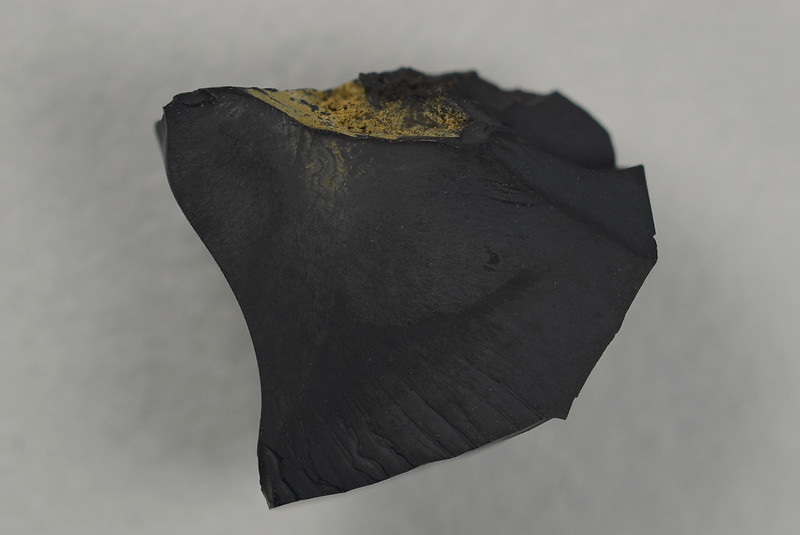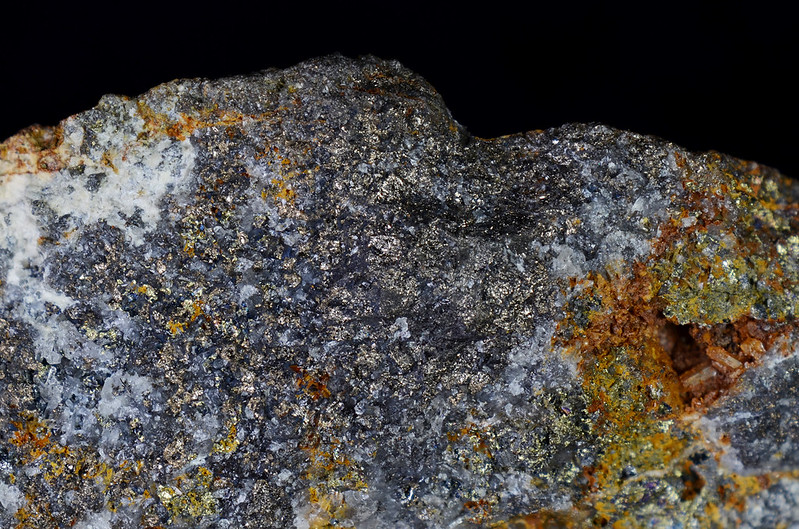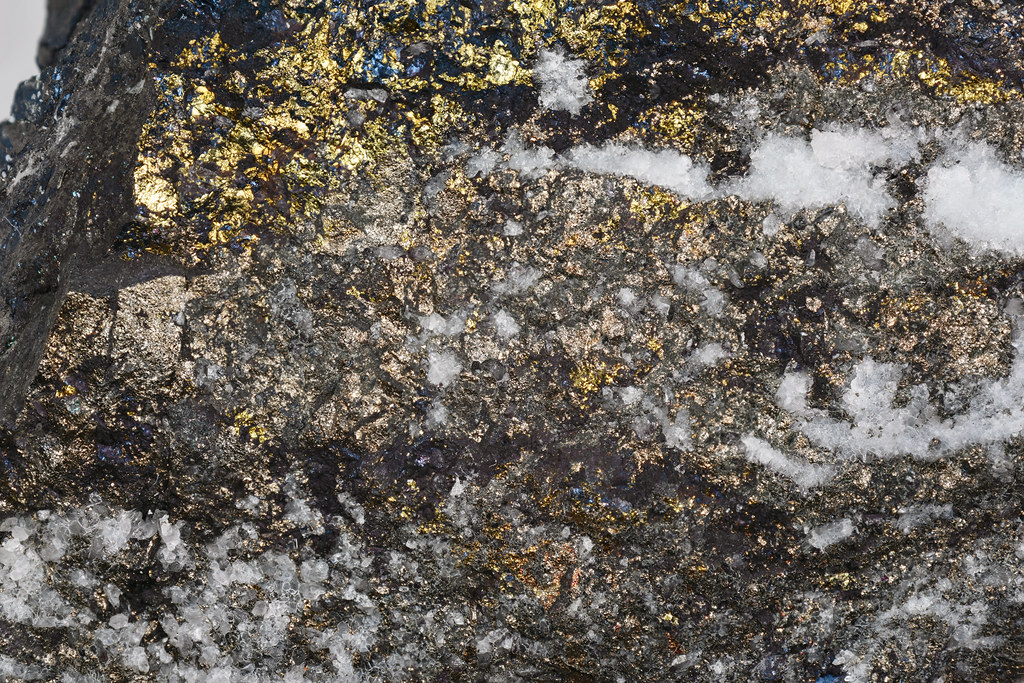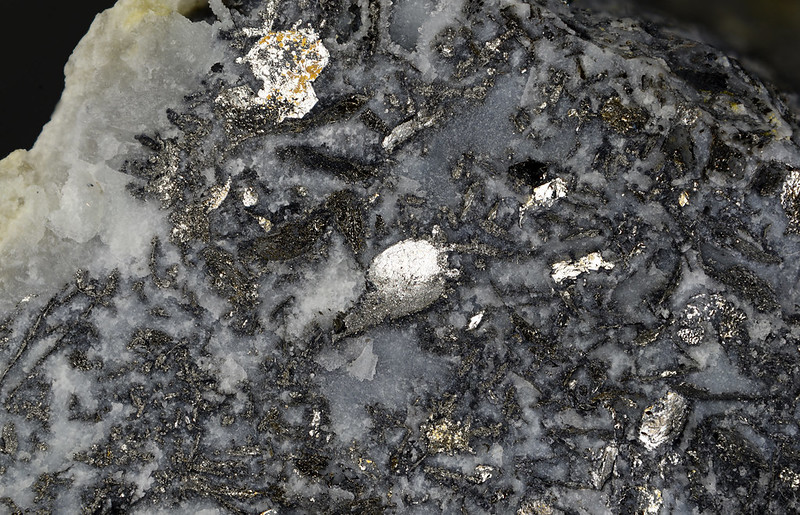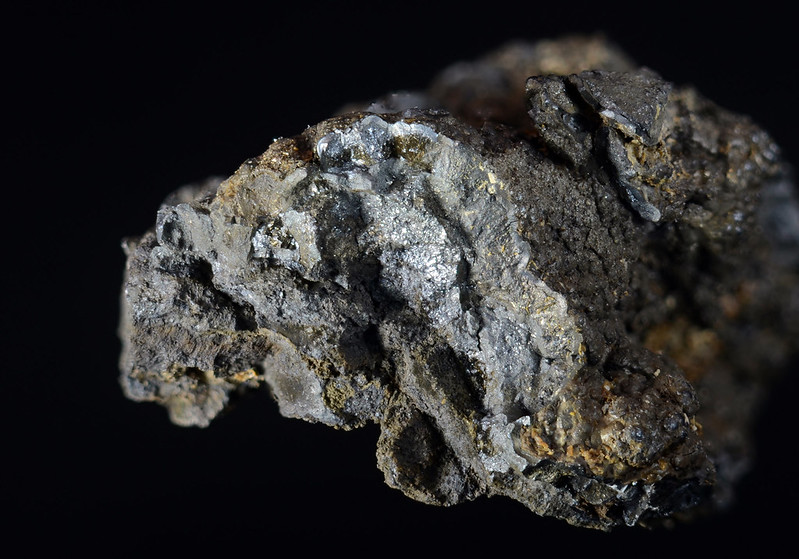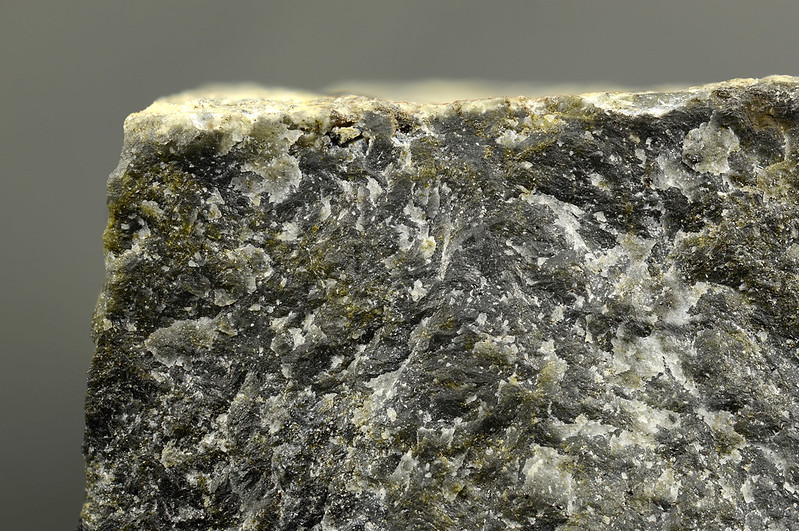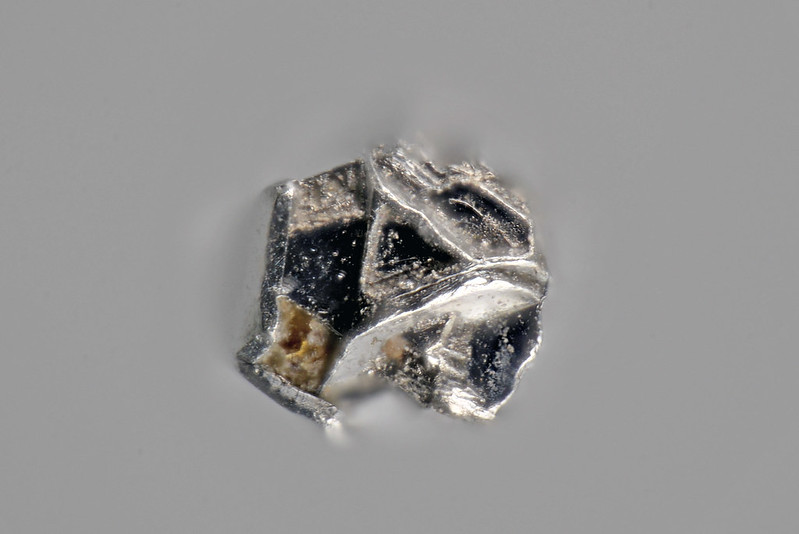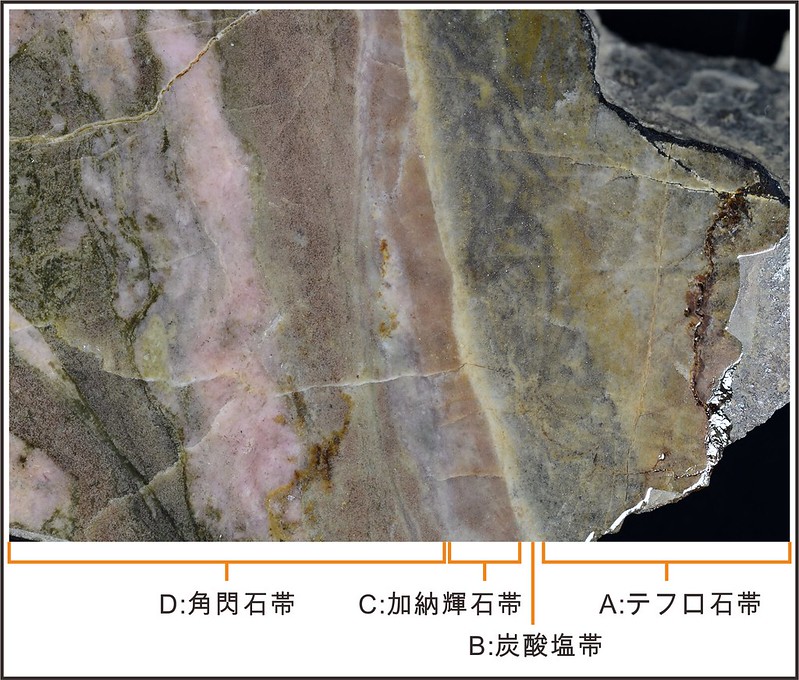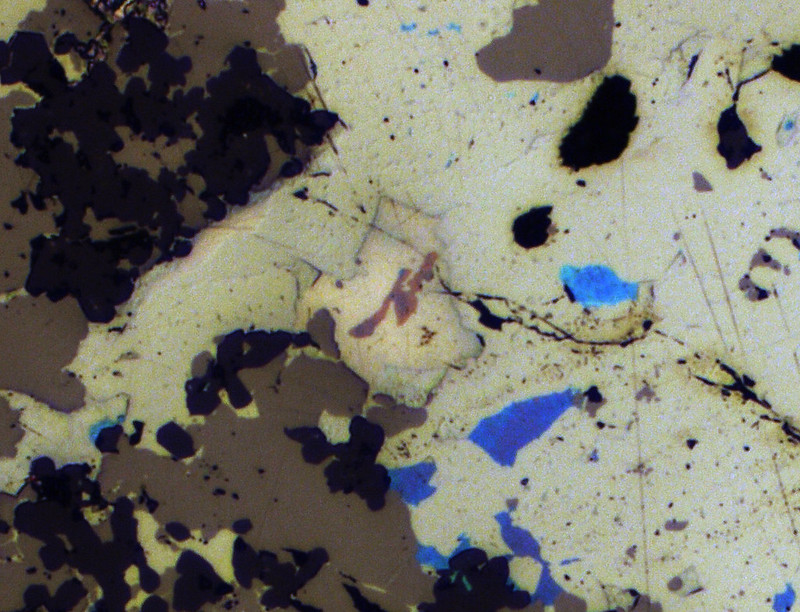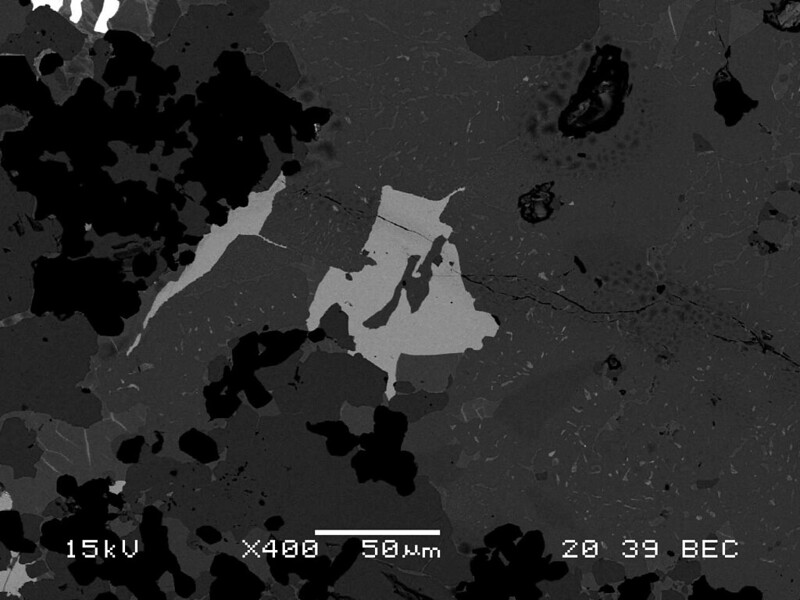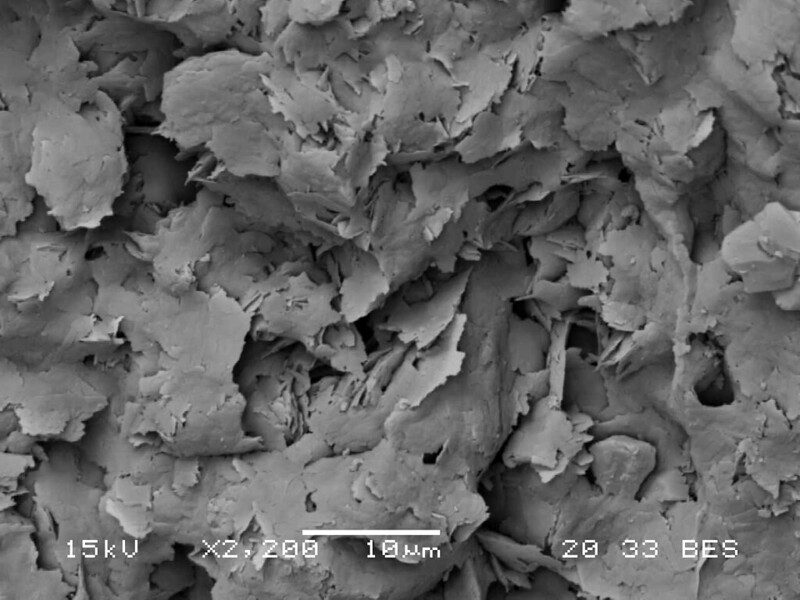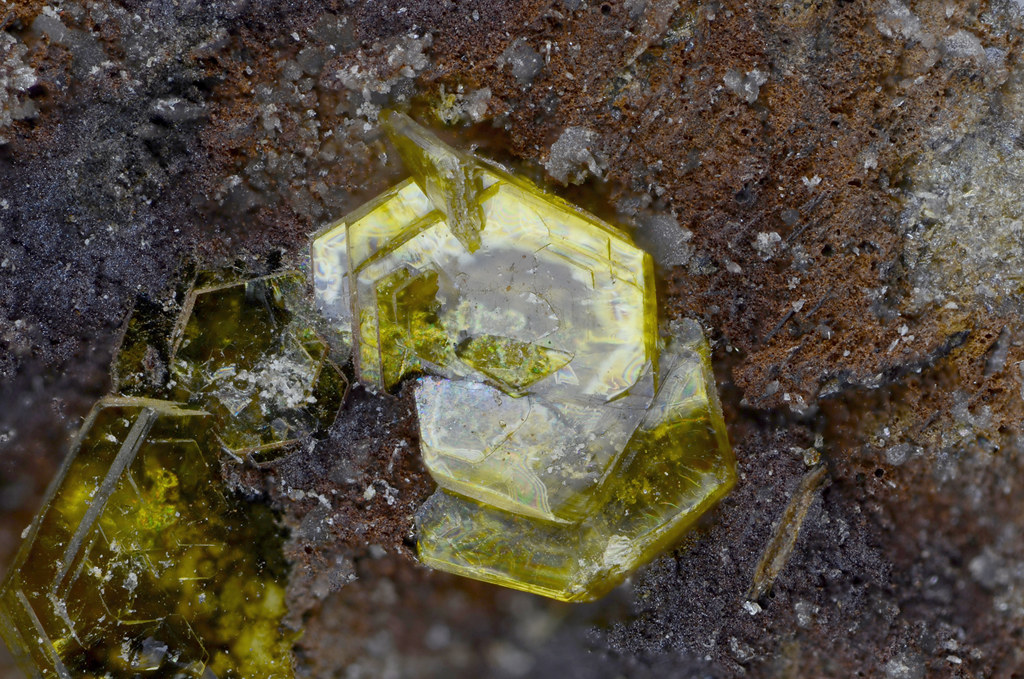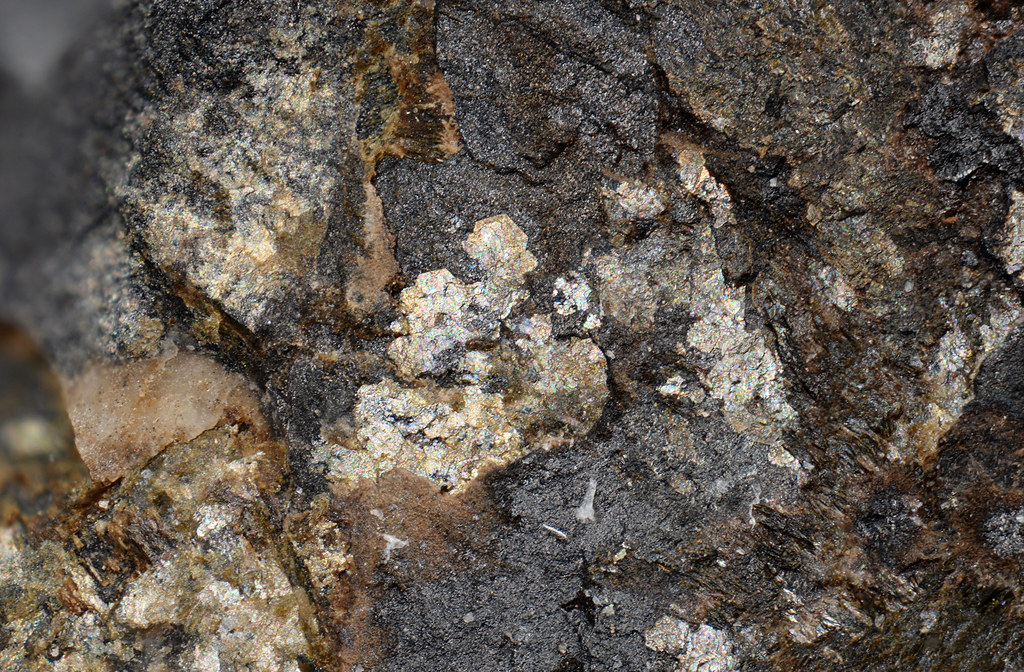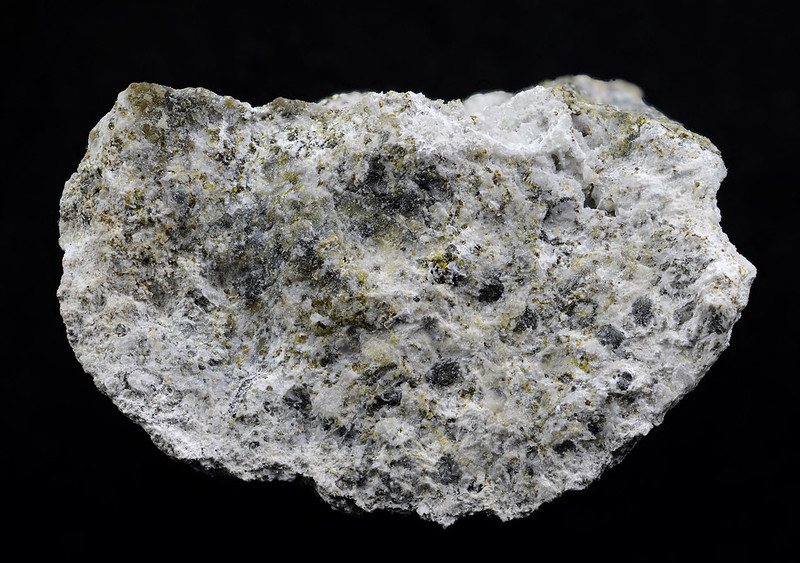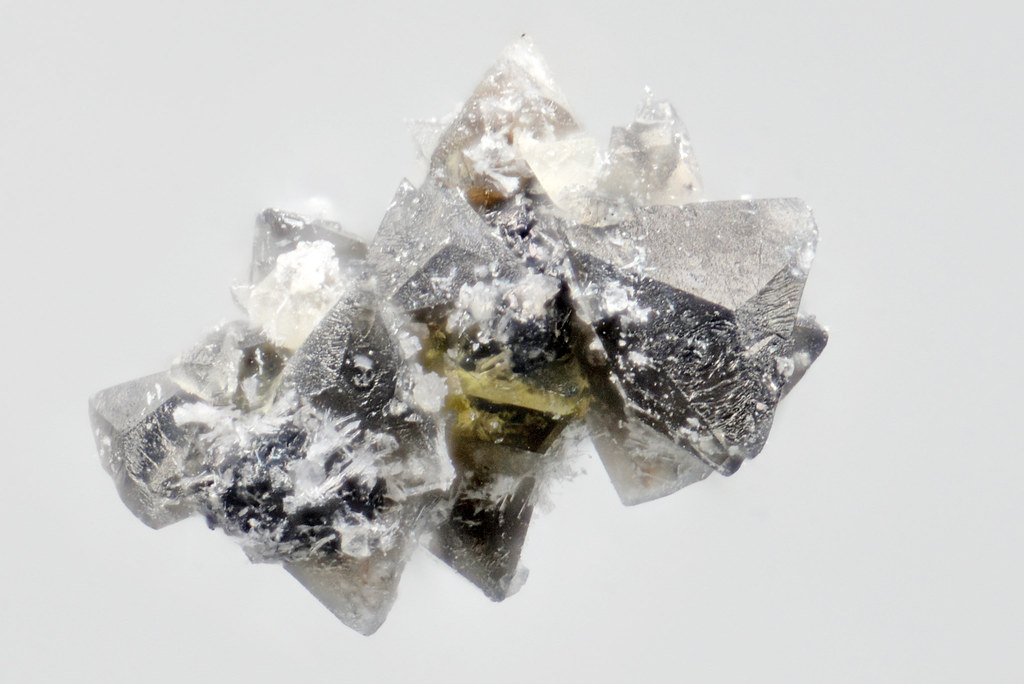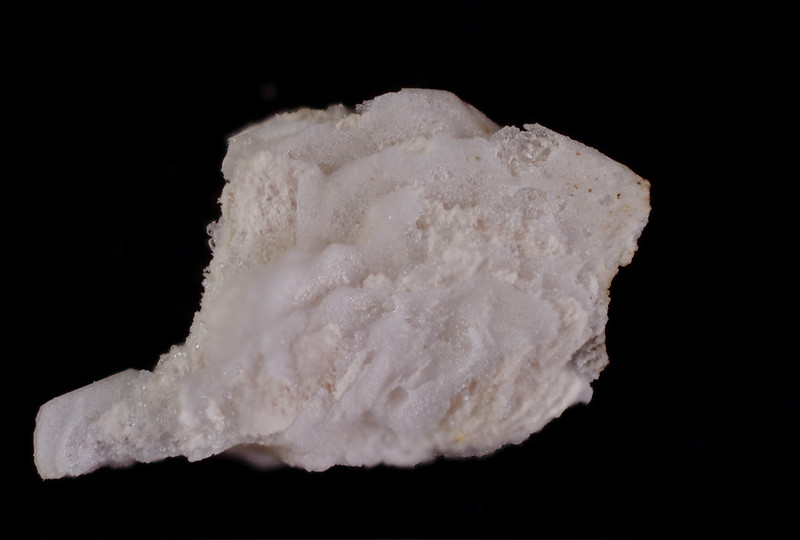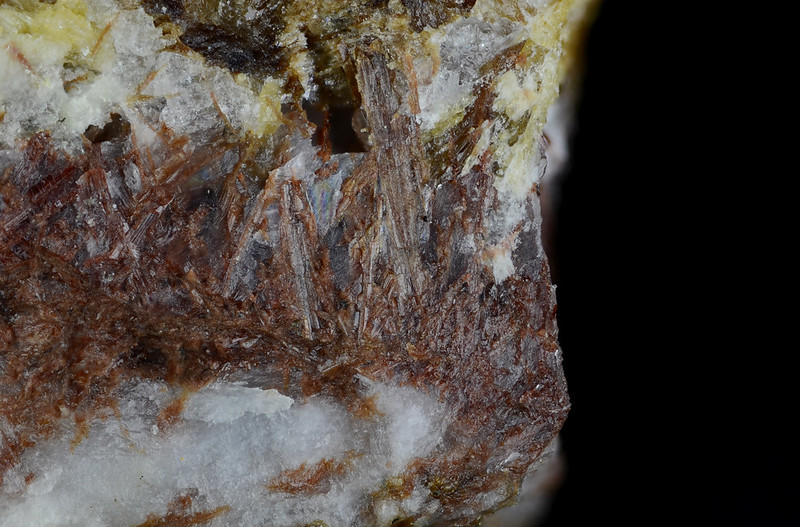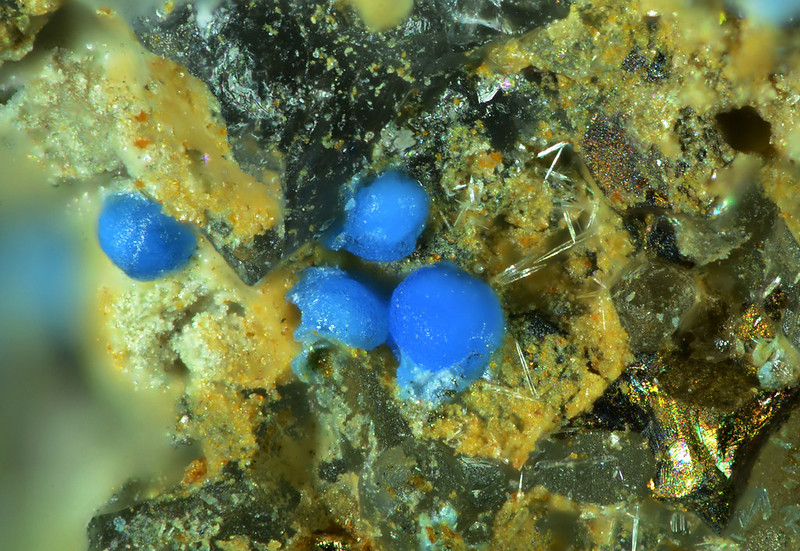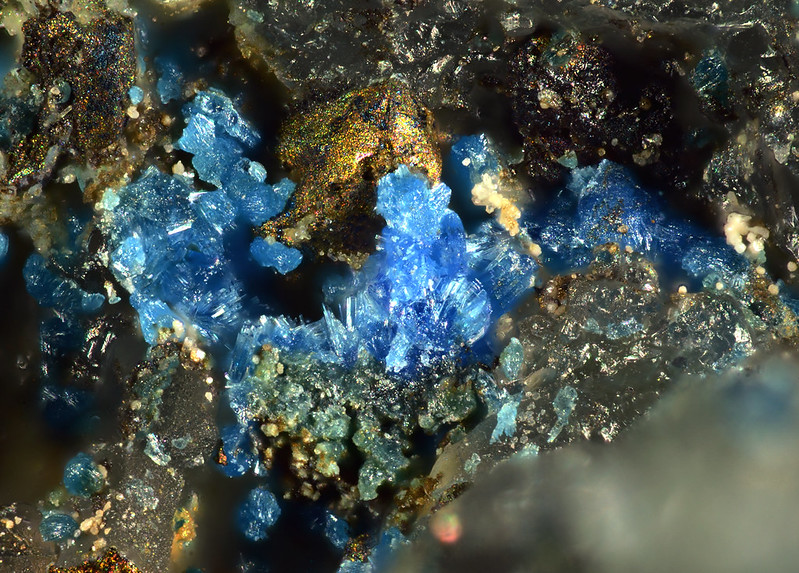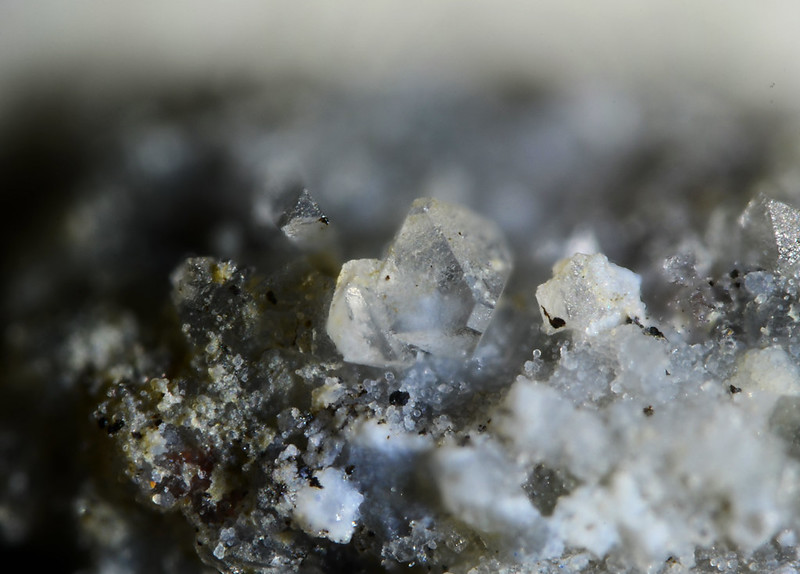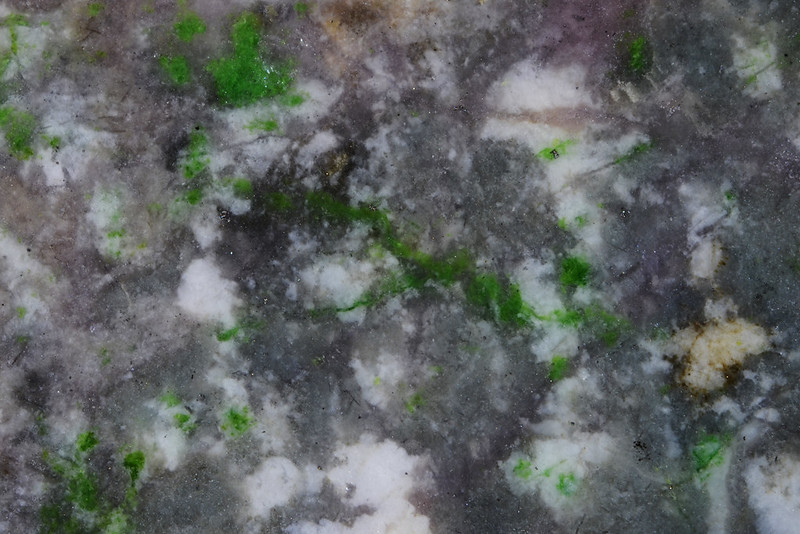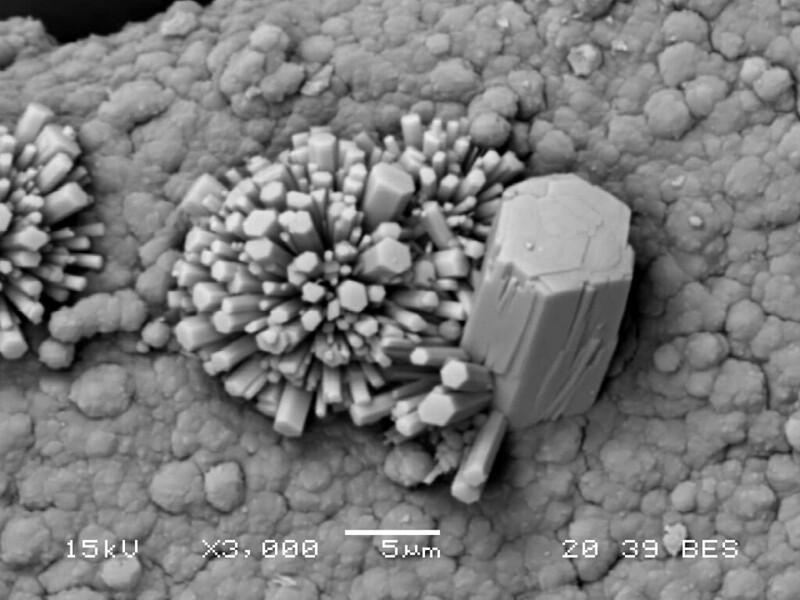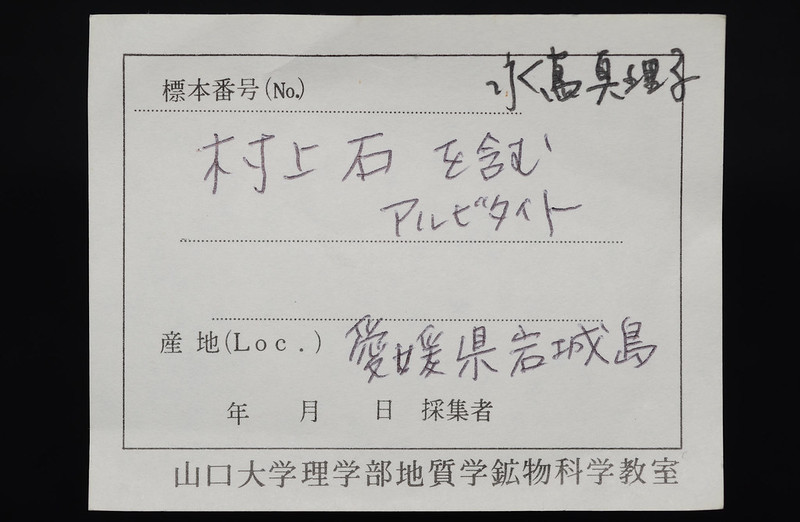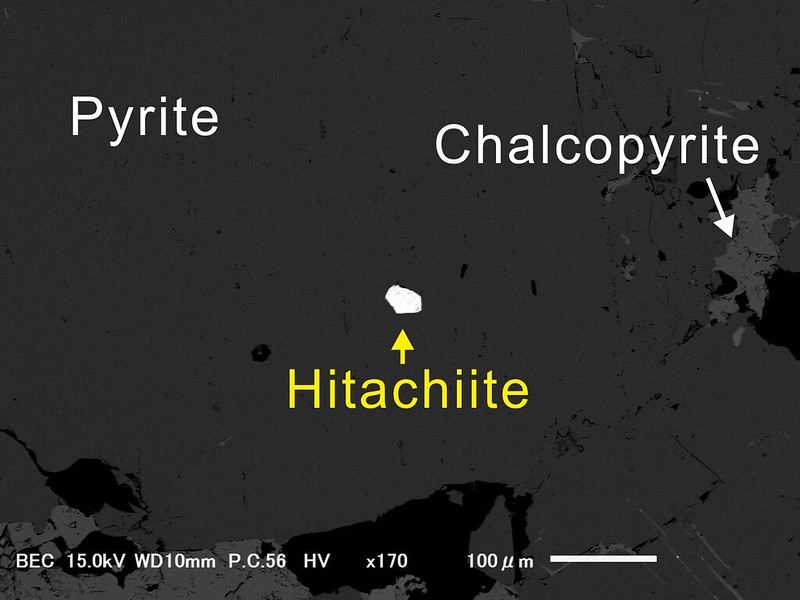IMA No./year: オフィシャルリストに掲載されている年に準拠。改訂があるものは「発見年(リストに記載の数字)」としてある。年の後についている「s.p.」は再定義・再命名・再承認などがあったことを意味している。
IMA Status: 承認の状態。A = approved(IMAが設立された後に承認された鉱物)、G = grandfathered(IMA設立以前に発見されており現在でも有効と見なせる鉱物)、Rd = redefined(すでに存在していたが規約が改訂された鉱物)、Rn = renamed(すでに存在していたが名前が変更された鉱物)、Q = questionable(情報が少なくて存在が疑わしい鉱物)。
模式標本: 模式標本の所在および登録番号など。
名前は「和名 / 学名」で掲載。
化学組成と模式地も掲載。
オフィシャルリストに最大で二つ引用されている文献を模式地の下に提示。
関連論文はレビュー内で引用する。
命名規約の成立や更新などで掲載する鉱物種の移動があり得る。
未申請・未承認・取消しされたものや怪しいものは日本の新鉱物(その他)にまとめた。
学名はオフィシャルリストに準拠するが、和名はなじみのあるものを採用している。
一覧表の鉱物をクリックすれば該当の記事へリンクする。
写真はクリックすれば保存先のFlickrからフルサイズが得られる。
2025/10/10現在で162種が有効な日本産の鉱物種として認識でき、その内158種の写真を掲載(予定)。
写真をまず掲載し、年代順にレビューを作成しているところ。
最新の記事は森本ざくろ石 / Morimotoite (1992-017)
写真の利用はhamane*へお問い合わせください(*@issp.u-tokyo.ac.jp)。
_
__
__
__
総評_1960s以前
日本で初めて新鉱物が発表されたのは1877年(明治10年)の紅礬土鉱と緑礬土鉱となる。そして1878年にはライン鉱が発表された。また三ノ岳鉱(1885年)、桜石(1888年)なども年季の入った愛石家なら聞いたことがあるだろう。しかしこれらはいずれも新鉱物としての独立性を否定されて久しい。このようにいったん新鉱物として発表されたが後の再検討で独立性を否定されるというケースが1960年代より前には多く認められる。そういった鉱物は南部松夫が1978年に記した「日本から記載された新鉱物」[1]によくまとめられているのでこの文献を参照してほしい。ここでは現代のオフィシャルリストに掲載がある鉱物を取り扱う。
1960年代以前に発表された新鉱物のうち、現時点(2018年11月)においてオフィシャルリストで産地が「Japan」で登録されているものは合計で31種ある。そしてそれぞれに登録されている最大2つの文献と、その他の学術文献を参照しながら内容を検証した。その結果として問題があると判断した鉱物については日本の新鉱物(その他)へ分類した。あとは発表当時に産地は日本領だったが現在は異なるケース、公式には認められていないが国立科学博物館叢書として出版された日本産鉱物型録では日本産の新鉱物として扱われているケースなども存在する。そういった鉱物も日本の新鉱物(その他)へ分類している。この記事を執筆している時点(2018年11月)で有効な日本産新鉱物は27種と判断した。その中で最も古い日本産の新鉱物は1922年に発表された石川石であった。
しかしそれもまた変更があった。2023年にコルンブ石超族の命名規約が成立した。それと共に石川石の立ち位置はQ(questionable)へと追いやられた。そのため、最新(2024年2月)の情報では、有効な日本産鉱物種は26種で、最も古いものは轟石となっている。古い時代に記載された新鉱物はどうしても情報が不完全で、立場が揺らぎやすい。
1958年に設立された国際鉱物学連合は、1959年に新鉱物に関わる委員会を立ち上げ、1962年から論文に先だって審査を行うようになった。それ以降はIMA no.が登録され、日本の新鉱物で初めてIMA no.が付与されたのは赤金鉱(1962-004)になる。それ以前に発表された新鉱物については、発表された年や再定義された年が登録されている。また新鉱物としての申請はされていないが、命名規約の成立・改訂などで新鉱物として改めて登録されたものもいくつかある。
鉱物を定義づける化学組成や結晶構造を得るために、この年代はとてつもない苦労があったように感じる。現代でも通用する質の高いデータで確立された新鉱物もあれば、いくつかは命名規約の改定など何か再検証を受けた際に抹消される可能性があると認識している。また委員会の承認は受けているが、正式な記載論文としては出版が確認できないケースもある。
この時代の新鉱物は稼働中の鉱山から得られたものが多く、最初の発見も研究者自身や鉱山関係者であることが多い。また名前に関しては現在では特別な理由がない場合は学名の最後は「ite」で終わるのだが、この時代は「lite」となる鉱物が多い。この理由は文献上からは読み取れないが、昔は「lite」がむしろ好まれたということを古老の研究者から聞いている。それもまたこの年代の特徴であろう。
[1] 南部松夫 (1978) 日本から記載された新鉱物. 渡辺万次郎先生米寿記念論集, 82-100.
IMA No./year: 1934(1962s.p.)
IMA Status: A (approved)
模式標本:Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 106214; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA (Hand book of Mineralogyから引用)
轟石 / Todorokite
(Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O
模式地:北海道赤井川村轟鉱山
第一文献:Yoshimura T. (1934) “Todorokite”, a new manganese mineral from the Todoroki mine, Hokkaido, Japan. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido Imperial University, Series IV, Geology and Mineralogy, 2, 289-297.
第二文献:Post J.E., Heaney P.J., Hanson J. (2003) Synchrotron X-ray diffraction study of the structure and dehydration behavior of todorokite. American Mineralogist, 88, 142-150.
轟石は北海道大学の吉村豊文によって1934年(昭和9年)に報告された新鉱物で、北海道赤井川村にある轟鉱山から発見されことから、模式地にちなんで命名された。轟石はマンガン(Mn)を主成分とする新鉱物であるが、轟鉱山はマンガンを主体に採掘していた鉱山ではなく、金(Au)を目的に開発されたいわゆる金山である。そして、「秀逸」と名付けられた石英脈にはしばしば黒色のマンガン鉱が伴われることが知られるようになると、そのことに興味を抱いた吉村豊文が轟鉱山を訪問し、試料を得て発見した新鉱物が轟石である[1]。
電子線分析装置とX線回折装置が普及する以前、鉱物の分析はしばしば困難であった。そのため同定が不完全でありながらも論文が提出され、同じ鉱物ながらも別の名前を付けられるということがよくあった。轟石もその例に漏れない。例えば1958年にキューバから産出したデラトレ石(Delatorreite)が新鉱物として名乗りを上げた[2]。その当時は新鉱物であるか否かのチェックは著者らに委ねられており、著者らの精査が足りなければ既存鉱物を新鉱物と誤認する事態が生じる。そして、後の調査でデラトレ石は轟石と同一であることが判明し[3]、後発のデラトレ石は抹消となった[4]。轟石の日本産新鉱物の地位が固まったのは1962年のことで、この年に改めて有効な鉱物種として轟石が文献に記されている[4]。
轟石は黒色のわさっとした集合体で産出し、明瞭な結晶となることはない。また集合体はほかの鉱物を巻き込むこともしばしばあって、轟石の理想化学組成と結晶構造は長らく判明しなかった。轟石の結晶構造は放射光X線を用いて2003年に明らかにされ、それをもとに理想化学組成もまた現在のように改定されている[5]。
写真は模式地である轟鉱山のほかに、青森県丸山鉱山、および静岡県池代鉱山の轟石になる。その標本はいずれも真っ黒な土状~繊維状の集合体であり、柄の大きな標本だと結晶集合の断面に樹脂光沢がみえることがある。また轟石は海底の堆積物からも報告されており、マンガンノジュールの主要構成鉱物であることが知られている。また本鉱を記載した吉村豊文は後に吉村石(Yohimuraite)として新鉱物にその名を残すことになる。
[1] 第一文献
[2] Simon F.S., Straczek J.A. (1958) Geology of the manganese deposits of Cuba. U.S. Geological Survey Bulletin, 1057.
[3] Frondel C., Marvin U.B., Ito J. (1960) New occurrences of todorokite. American Mineralogist, 45, 1167-1173
[4] International Mineralogical Association (1962) Mineralogical Magazine, 33, 260-263.
[5] 第二文献
IMA No./year: 1938(1966s.p.)
IMA Status: Rn (renamed)
模式標本:不明
阿武隈石 / Britholite-(Y)(原記載では阿武隈石/Abukumalite)
(Y,Ca)5(SiO4)3(OH)
模式地:福島県川俣町飯坂水晶山
第一文献:Hata S. (1938) Abukumalite, a new yttrium mineral. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research, 34, 1018-1023.
第二文献:Noe D.C., Hughes J.M., Mariano A.N., Drexler J.W., Kato A. (1993) The crystal structure of monoclinic britholite-(Ce) and britholite-(Y). Zeitschrift für Kristallographie, 206, 233-246.
阿武隈石は理化学研究所の畑晋(はたすすむ)によって福島県水晶山のペグマタイト岩脈から発見された新鉱物で、理化学研究所が発行する科学誌において記載された[1]。論文では化学組成分析によって阿武隈石はイットリウム(Y)が主体のケイ酸塩であることが示されており、X線回折で得られた軸率なども総合して鉱物種について考察が行われている。結論として、ブリソ石(Britholite)に似た性質と化学組成であるものの、セリウム(Ce)を主成分とするブリソ石に対して、イットリウムに富む阿武隈石という分け方が可能ということで、新鉱物である旨が主張されている。この記載論文は単名で書かれているものの試料採集や分析には幾人かの協力があったようで、名前は理化学研究所の飯盛里安が提案したことが記されている。阿武隈地域からの産出を理由として、新鉱物は阿武隈石(Abukumalite)と名付けられた。後年、畑晋は阿武隈石の発見の業績により櫻井賞の第6号メダルを受賞することになる。
希土類元素を含む鉱物の名前については「ルートネーム-(REE)」とするというルールが1966年に制定され[2]、それを受けて阿武隈石の名前は再検討されることになる。阿武隈石はそれより先に発見されていたセリウムを主成分とするブリソ石と比べたとき、イットリウムを主成分とする点のみが異なる鉱物であった。つまり阿武隈石よりも先にブリソ石が存在していたということで、根源名(ルートネーム)についてはブリソ石に優先権があった。そしてブリソ石はセリウムブリソ石(Britholite-(Ce)に、阿武隈石はイットリウムブリソ石(Britholite-(Y))へそれぞれ改名となった。その経緯を受けて、阿武隈石のIMA StatusはRn (renamed)と設定され、IMA No./yearについても1966s.p.がオフィシャルリストに登録されている。ただし論文が1938年に出版されていることから、ここでは1960年以前の鉱物として並べている。また日本においては和名を用いる文化があるので、和名としての阿武隈石の名称まで変更する必要は無いだろう。
1993年になるとセリウムブリソ石と阿武隈石について結晶構造解析が行われ、いずれも燐灰石型構造であることが報告された[3]。その研究に使われた阿武隈石は福島県水晶山から産したもので、国立科学博物館から提供されている。そして、畑晋によって記載された阿武隈石は水酸基(OH)が卓越する鉱物であったが、この論文中で使用された阿武隈石はフッ素(F)が卓越している。そのため阿武隈石はそのフッ素置換体となるまた別の新鉱物(イットリウムフッ素ブリソ石)が存在すると指摘されていた[4]。そして2009年になりイットリウムフッ素ブリソ石(Fluorbritholite-(Y))がノルウェイを模式地として誕生した[5]。
写真は福島県水晶山から産出した阿武隈石であり、かけらであるために燐灰石超族をうかがわせる結晶外形などは残っていない。この標本についてはフッ素はほとんど検出されなかったため、水酸基型、つまりは最初の記載どおりの阿武隈石になる。ただし、いわゆる阿武隈石と言われている標本にはフッ素卓越体(イットリウムフッ素ブリソ石)がそこそこ含まれていることには注意したい。
[1] 第一文献
[2] Levinson A.A. (1966) A system of nomenclature for rare-earth minerals. American Mineralogist. 51, 152-158.
[3] 第二文献
[4] Jambor J.L., Roberts A.C., Puziewicz J. (1994) New mineral names. American Mineralogist. 79, 570-574.
[5] Pekov I.V., Zubkova N.V., Chukanov N.V., Husdal T.A., Zadov A.E., Pushcharovsky D.Y. (2011) Fluorbritholite-(Y), (Y,Ca,Ln)5[(Si,P)O4]3F, a new mineral of the britholite group, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 188, 191-197.
IMA No./year: 1939
IMA Status: G (grandfathered)
模式標本:北海道大学博物館; Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, 94749.(Handbook of Mineralogyから引用)
手稲石 / Teineite
Cu2+Te4+O3·2H2O
模式地:北海道札幌市手稲鉱山
第一文献:Yosimura T. (1939) Teineite, a new tellurate mineral from the Teine mine, Hokkaidō, Japan. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido Imperial University, Series IV, Geology and Mineralogy, 465-470.
第二文献:Effenberger H. (1977) Verfeinerung der kristallstruktur von synthetischem teineit CuTeO3•2H2O. Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 24, 287-298.

Gråurdfjellet, Oppdal, Trøndelag, Norway
手稲石は北海道大学の吉村豊文により記載された新鉱物で、北海道手稲鉱山から発見されたことから学名が定められている[1]。この当時、吉村は原田準平教授の主催する地質鉱物学第四講座の助教授として勤務していた。のちに日本鉱物学会が櫻井賞を設立して表彰を始めると、吉村は手稲石を発見した業績において櫻井賞第4号メダルを受賞することになる。
後に手稲石となる標本は原田準平によって得られたようで、1936年に瀧之澤と名付けられた鉱脈から採集されている。それは藍青色を呈する柱状結晶であり、その姿はかつて吉村が宮崎県土呂久鉱山から報告したカレドニア石(Caledonite)によく似ていた。そのために吉村が研究を主導することになったのだろう。ともかく研究が始まって早々に光学的特徴がカレドニア石とは異なることが判明している。つまり新鉱物の可能性がでてきたので分析に進むべきところであったが、この当時の分析は多量の試料を必要とする湿式分析であったことが難点となり、研究は一時停滞した。しかし、その後に同じく北海道大学の助教授であった渡辺武男がまとまった量の標本を採集することに成功し、その標本を用いて化学組成分析を行えることになった。この当時は結晶構造まで求められる時代ではなかったので、理想化学式もまたこの段階では確定までには至っていない。詳細な研究は後世に行われ、1977年にようやく理想化学式と構造が確定している[2]。発見から確定までおおむね40年というところだろう。
手稲石の第二産地はなかなか見つからなかったが、1968年に静岡県河津鉱山から産出が報告された[3]。手稲鉱山も河津鉱山も自然テルルを産出する浅熱水性金属鉱床という点で共通しており、この二つの産地は出てくる鉱物種も類似性がある。自然テルルを含む鉱床など日本ではこの二つ以外にはほぼ無いため、手稲石の新しい産地もまた期待できないところであったが、2000年代に入り全く予想外の産出が報告された。それが和歌山県岩出市山崎であり、一般的な三波川変成岩を母岩としながらも石英の裂傷に手稲石やマックアルパイン石(Mcalpineite)といったテルル酸塩鉱物が伴われていた[4]。現時点ではこの3地点が日本における手稲石の産地である。海外ではベルギー、ノルウェイ、ロシア、アメリカ、メキシコで産出の報告がある。最初の標本のように藍青色を呈する柱状結晶が最上の標本になり、博物館などでは立派な結晶を見ることができる。一方で、不定形なもの、結晶の一部が見えているだけの標本も多く、これだとなかなか手稲石と鑑定できるポイントは少なく、結局は産地の情報も併せて判断することになるだろう。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] Kato A., Sakurai K. (1968) The occurrence of teineite from the Kawazu (Rendaiji) mine, Shizuoka Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 5, 285.
[4] 藤原卓, 岸野正直, 小原正顕, 松原聰, 宮脇律郎 (2002) 和歌山県、三波川変成岩中の手稲石ほかテルル鉱物. 日本鉱物学会講演要旨,KA10, P34.
MA No./year: 1950(1987s.p.)
IMA Status: A (approved)
模式標本:不明
イットリウム河辺石 / Kobeite-(Y)
(Y,U)(Ti,Nb)2(O,OH)6(?)
模式地:京丹後市大宮町河辺(旧:河邊村白石)
第一文献:田久保實太郎,鵜飼保郎,港種雄(1950)含稀元素鉱物の研究(其の11)京都府中郡河邊村白石産河邊石. 地質学雑誌, 56, 509-513.
第二文献:Masutomi K., Nagashima K., Kato A. (1961) Kobeite from the Ushio mine, Kyoto Prefecture, Japan and re-examination of kobeite. Mineralogical Journal, 3, 139-147.
イットリウム河辺石は京都大学の田久保實太郎らによって、京丹後市大宮町河辺のペグマタイトから見いだされた新鉱物であり、発見地にちなんで命名された[1]。そのペグマタイトは戦前にガラス原料を目的としてほんの1年程度だけ採掘されたようで、今となっては堀跡すら定かでないほど山に帰っていると聞いている。
イットリウム河辺石の組成的な特徴はイットリウム(Y)とチタン(Ti)を主成分とし、ニオブ(Nb)やタンタル(Ta)にも富むと記されている。記載論文ではXZ2O6型の化学組成に近似するということで、「(Y,Ca,U)(Ti,Nb+Ta)2(O,OH)」の組成式が報告された。しかし、この時代の分析は湿式分析であり、累帯構造が大きい鉱物については正しい組成を導くことが難しかった。そして残念ながらイットリウム河辺石は累帯構造の著しい鉱物であり、今となっては田久保らによって提示された化学組成は正しいとは考えられていない。そのため公式の鉱物リストに掲載されている上記の化学組成には「?」が付されている。
結晶構造についてはイットリウムユークセン石(Euxenite-(Y):(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6)との関連が示唆されている[1]。しかしながらこれもまたぼんやりとした内容である。模式地のイットリウム河辺石はウラン(U)を含むことによってメタミクト状態にあり、加熱によって結晶構造を回復させたところ、何となくイットリウムユークセン石ぽいピークが得られたという程度であった。現代ではこうした状態では新種として認められることはないが、この時代はX線結晶学が未発達であり、必然的に結晶構造に関する情報は決定的な判断基準になっていないかったように見える。むしろ化学組成的に(あいまいながらも)新規であったことが重要であったように思える。ともかくこの時代は国際鉱物学連合が立ち上がっておらず、新種は著者の判断によって主張されるものであった。
イットリウム河辺石の再検討は日本人の手によって行われる。1961年に発表されたその論文はイットリウム河辺石の加熱再結晶実験と粉末X線回折実験を報告している[2]。ただし、結晶構造については決定打がなく、ジルケライト(zirkelite: (Ti,Ca,Zr)O2-x)やジルコノライト(zirconolite: (Ca,Y)Zr(Ti,Mg,Al)2O7)との関連が示唆されるにとどまる。その一方でジルケライトもジルコノライトも命名規約がありながらも明確な定義が固まっていない困った鉱物であり[3]、それと比定したところでイットリウム河辺石の構造は不明なままであった。
結果的に、現時点においてさえイットリウム河辺石は化学組成・結晶構造ともに確たるものがない状態である。しかし、これまで特にその存在を否定するような論文は出ておらず、1987年に主成分の希土類元素を「-(REE)」としましょうというアナウンスがあった程度である[4]。それでも2010年代になってイットリウム河辺石について3O型ジルコノライトに近いX線回折パターンが得られたという報告があがってきている[5,6]。化学組成も再検討され、それはジルコノライトと同様にO=7で規格化した構造式が提案されている。いずれにせよイットリウム河辺石の化学組成と結晶構造のいずれも更新されるべきであることは間違いない。イットリウム河辺石の産出は稀なほうであるが、その標本は模式地のモノであっても手に入らないというほどではないので、研究が進展してイットリウム河辺石の定義(理想化学組成と結晶構造)が固まることを願ってやまない。
イットリウム河辺石は模式地のほかに広島県と宮崎県で見いだされている。標本としてのツラ構えはそれぞれ異なるが、イットリウム河辺石だけに注目するとほとんど似通った姿かたちをしており、黒色で棒状から板状の結晶がスッと伸びた形状になり、それはやや束状にも見えようかという姿である。いずれも長石中に埋没する産状を示す。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] Bayliss P., Mazzi F., Munno R., White T.J. (1989) Mineral nomenclature: Zirconolite. Mineralogical Magazine, 53, 565-569.
[4] Nickel E.H., Mandarino J.A. (1987) Procedures involving the IMA Commission on New Minerals and Mineral Names and guidelines on mineral nomenclature. American Mineralogist, 72, 1031.
[5] 藤井勇樹, 上原誠一郎 (2011) 宮崎県大崩山花崗岩ペグマタイト中に産するレアアース鉱物. 日本鉱物科学会講演要旨集,R1-P13.
[6] 福本辰巳, 皆川鉄雄 (2012) Kobeiteの記載鉱物学的再検討. 日本鉱物科学会講演要旨集,R1-06.
IMA No./year: 1952(1997s.p.)
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館; National School of Mines, Paris, France; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 106164, 106931.(Handbook of Mineralogyから引用)
湯河原沸石 / Yugawaralite
Ca(Si6Al2)O16·4H2O
模式地:神奈川県湯河原町不動ノ滝
第一文献:Sakurai K., Hayashi A. (1952) “Yugawaralite”, a new zeolite, Science Reports of the Yokohama National University, 1, 69-77.
第二文献:Kvick Å., Artioli G., Smith J.V. (1986) Neutron diffraction study of the zeolite yugawaralite at 13 K. Zeitschrift für Kristallographie, 174, 265-281.
湯河原沸石は鉱物研究家の櫻井欽一と横浜国立大学の林瑛により見いだされた沸石族の新種であり、神奈川県の湯河原温泉不動ノ滝から見いだされた[1]。櫻井が試料を採集したのは1930年(昭和5年)のことで、そのときすでに既存の沸石種とは異なることに気づいていたようだが、研究が進展したのは戦後であった。1948年(昭和23年)になり横浜国立大の林瑛の協力を得てこの見慣れない沸石の研究が再開され、ついに模式地の名を冠する新鉱物・Yugawaraliteが誕生した。なお、沸石族の和名は「・・・沸石」とする慣習があり、本鉱の和名は湯河原沸石となる。現時点で、湯河原沸石は神奈川県で唯一の新鉱物となっている。
湯河原沸石のその後の研究については、おもに結晶学的な観点から勧められた。最終的には1968年に結晶構造が完全に解明され、それを受けて理想化学式も今の形に収まった[2]。結晶構造中でシリコン(Si)とアルミニウム(Al)はきっちり秩序化していることが確認されている[3]。
公式リストには1997s.p.が年代として掲載されており、これは1997年の沸石族命名規約の改訂があったことに由来する[4]。沸石族はシリコン(Si)、アルミニウム(Al)、酸素(O)からなる籠を組み合わせた骨格を持っており、籠の中に電荷調整のための陽イオンを含む。そして、同じ骨格で籠の中の陽イオンが異なるだけの場合にはサフィックス(接尾語)を用いて種類(学名)を区別することになった。たえば束沸石だと、カリウム(K)がもっとも多い種はカリ束沸石(Stilbite-K)が、 カルシウム(Ca)だと灰束沸石(Stilbite-Ca)が正式な名称となる。湯河原沸石の場合だと、記載された湯河原沸石はカルシウム優占種である。一方でそのほかの元素をもつ湯河原沸石は発見されていない。こういった場合は接尾語なしで、「Yugawaraite」だけで正式な学名となる。
櫻井欽一は家業(神田の老舗の鳥鍋屋「ぼたん」)を切り盛りするかたわらで鉱物学を修め、この湯河原沸石の業績で東京大学から理学博士を取得した。そして、1973年には櫻井欽一の還暦を記念して新鉱物の発見に貢献した研究者をたたえる櫻井賞が設立される。その際に櫻井はこの湯河原沸石の業績で第一号の受賞者となった。
湯河原沸石は模式地での採集はもはや望めない。しかしその後にいくつか産地が見いだされており、大柄な結晶は静岡県の大洞林道から産した。また、岩手県雫石町葛根田からも発見されている。
[1] 第一文献
[2] Leimer H., Slaughter M. (1969) The determination and refinement of the crystal structure of yugawaralite. Zeitschrift für Kristallographie, 130, 88-111.
[3] 第二文献
[4] Coombs D.S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J.D., Liebau F., Mandarino J.A., Minato H., Nickel E.H., Passaglia E., Peacor D.R., Quartieri S., Rinaldi .R, Ross M., Sheppard R.A., Tillmanns E., Vezzalini G., (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names, The Canadian Mineralogist, 35, 1571-1606.
IMA No./year: 1954
IMA Status: G (grandfathered)
模式標本:国立科学博物館 M24052(Handbook of Mineralogyから引用)
亜砒藍鉄鉱 / Parasymplesite
Fe2+3(AsO4)2·8H2O
模式地:大分県佐伯市木浦鉱山(旧:宇目町)
第一文献:Ito T., Minato H., Sakurai K. (1954) Parasymplesite, a new mineral polymorphous with symplesite. Proceedings of the Japan Academy, 30, 318-324.
第二文献: Cesbron F., Sichère M.C., Vachey H. (1977) Propriétés cristallographiques et comportment thermique des termes de la série koettigite–parasymplésite. Bull. Minéral., 100, 310–314 (in French with English abs.).
亜砒藍鉄鉱は東京大学の伊藤貞一らにより発見された大分県木浦鉱山からの新鉱物で、その記載論文は1954年(昭和29年)に公表された[1]。一方で亜砒藍鉄鉱は記載論文に先立ち、別の形で文献に登場している[2,3]。
東京大学の伊藤貞市らは、栃木県足尾銅山産の藍鉄鉱(Vivianite)と大分県木浦鉱山からの砒藍鉄鉱(Symplesite)の結晶構造を解くことに世界で初めて成功したことを1949年から1950年にかけて報告した[2,3]。藍鉄鉱はリン(P)を主成分とし、砒藍鉄鉱はヒ素(As)を主成分とする鉱物で、両者の違いはこのように化学組成だけであり、対称性はどちらも共通の単斜晶系という結論であった。しかしこの結果は以前の報告と相容れなかった。これまでの研究では、砒藍鉄鉱は三斜晶系として報告されていたのだった[4]。この当時、対称性の違いは種を分ける基準として用いられており、木浦鉱山産の砒藍鉄鉱は新種の可能性をはらんでいたことになる。
しかしながら、作業仮説として、これまでの研究が間違いで原産地の砒藍鉄鉱も実は単斜晶系であったなら、木浦鉱山産の砒藍鉄鉱が新種である可能性は潰えてしまう。そこで伊藤らは原産地(ドイツ)の砒藍鉄鉱を取り寄せ、それと木浦鉱山産の砒藍鉄鉱と比較研究を行った[1]。結果的に原産地の砒藍鉄鉱は従来の報告通り三斜晶系を示したことから、やはり木浦鉱山産の砒藍鉄鉱はそれとは対称性の異なる新種であることが明らかとなった。伊藤らは木浦鉱山産の新鉱物の学名に「para」の接頭語を当てた。それは和名では「亜」が該当する。そして既存鉱物の砒藍鉄鉱(Symplesite)に対して、木浦鉱山産の新鉱物は亜砒藍鉄鉱(Parasymplesite)と名付けられることになった。1977年にはメキシコからも亜砒藍鉄鉱の産出が報告されている[5]
現在は対称性の違いだけで種を隔てることはないので、もし砒藍鉄鉱と亜砒藍鉄鉱の本質的な結晶構造が同様であったなら、両者は同一の鉱物と見なされるだろう。そのため、亜砒藍鉄鉱の独立性は今後も安泰ということはなく、砒藍鉄鉱の結晶構造がどうであるかによる。しかし、現時点において実は砒藍鉄鉱の結晶構造は未解明のままとなっている。亜砒藍鉄鉱については最近であっても研究結果が報告されるなど、日々詳細の解明が進んでいる[6]
写真はいずれも模式地の木浦鉱山から産した亜砒藍鉄鉱の標本となる。駄積形尾(だつがたお)において廃棄された硫砒鉄鉱を主体とする鉱石を割ると、ヒ酸塩の二次鉱物とともにたまに顔を出す。亜砒藍鉄鉱は時間が経過すると鉄分の酸化により色がくすむため新鮮な状態の保存が難しい。写真の標本は残念ながら本来の色ではないが、下の写真は比較的新鮮な時期に撮影したので本来の色に近いと思われる。また、ある個人の所蔵標本では割り出してすぐの標本をほっかいろと共にパックしていた。ほっかいろが酸素を吸って試料の酸化が防がれる。その標本は本来の透き通った淡緑色が保たれていた。
[1] 第一文献
[2] Ito T. (1949) Structure of vivianite and symplesite. Nature, 164, 449-450.
[3] Mori H., Ito T. (1950) The structure of vivianite and symplesite. Acta Crystallographica, 3, 1-6.
[4] Wolf C.W. (1940) Classification of minerals of the type A3(XO4)2·nH2O. American Mineralogist, 25, 738.
[5] 第二文献
[6] Hongu H., Yoshiasa A., Kitahara G., Miyano Y., Han K., Momma K., Miyawaki R., Tokuda M., Sugiyama K. (2021) Crystal structure refinement and crystal chemistry of parasymplesite and vivianite. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 116, 183-192.
IMA No./year: 1956
IMA Status: G (grandfathered)
模式標本:Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, 104744(Handbook of Mineralogyから引用)
大隅石 / Osumilite
KFe2+2(Al5Si10)O30
模式地:鹿児島県垂水市咲花平(さっかびら)
第一文献:Miyashiro A. (1956) Osumilite, a new silicate mineral, and its crystal structure. American Mineralogist, 41, 104-116.
第二文献: Armbruster T., Oberhänsli R. (1988) Crystal chemistry of double-ring silicates: structural, chemical, and optical variation in osumilites. American Mineralogist, 73, 585-594.
大隅石は東京大学の都城秋穂によって発見された新鉱物で、1956年にAmerican Mineralogist誌において発表された[1]。鹿児島県大隅地域からの産出であったことから、東京大学の久野久が大隅石の名称を提案したとされる。
鹿児島県の地形図を眺めると、桜島と大隅半島が陸続きとなっているあたりはやや高台となっており、そこは咲花平(さっかびら)と呼ばれている。大隅石はその高台を模式地としている。大隅石の最初に見いだしたのは益富壽之助と伝わっており、その記述は1948年に公表された森本良平の論文中に見て取れる[2]。遅くとも1942年の11月には標本が益富から森本へ渡っていることが記されていた。森本は和文論文も記しているが[3]、いずれの論文においても菫青石(Cordierite)として発表された。論文は化学組成分析も行い菫青石には含まれることのないカリウム(K)が検出されており、さらには「ほとんど光学的一軸性の特徴を持つものがある」という記述がある。菫青石は本来は光学的二軸性であり、それとも異なることにすでに気付いている描写があるものの、新種という言及はついに認められなかった。
次に東京大学の都城がこの一軸性光学特徴をもつ菫青石に注目し、森本らから資料の提供を受けて、1951年には新種であることに確信を抱いたと思われる[4]。続いて発表された記載論文[1]では構造解析に主眼が置かれ、都城は他産地のいわゆる菫青石のいくつかは大隅石であろうと予測している。
さらに後に結晶構造の再検討が行われ、結晶構造および化学式が現在のように改められた[5, 6]。このときの研究で使用された試料には鉄(Fe)側の端成分とマグネシウム(Mg)側の端成分の両方の試料があったが、それらは特に区別されていない。それでも彼らが分析した咲花平からの試料は鉄端成分であったため、大隅石とは鉄端成分の鉱物ということになった。ただし、都城の分析値だとマグネシウム端成分となることを注釈しておく。
いつしかマグネシウム端成分は苦土大隅石(Osumilite-(Mg))と呼ばれることになった。その初出は1973年だろう。アイルランド産の大隅石がOsumilite-(K、Mg)と記述された[7]。日本だと大分県万年山からの大隅石に対し、「マグネシウム大隅石と呼んだ方が合理的」と記述があったりもする[8]。そしていつのまにかIMAのオフィシャルリストにOsumilite-(Mg)が登場することとなる。ただし、それには明確な文献が提示されていなかった。
ロシアの研究チームはそこに注目した。彼らは苦土大隅石には正式な記載論文が無いことを理由にしてドイツ産のものを改めてOsumilite-(Mg)(IMA-No.2011-083)として申請を行い、承認を得た。これはしてやられたというべきだろう。苦土大隅石の記載論文は2012年に公表された[9]。
写真は模式地の大隅石(一枚目)および宮城県本砂金から産した菫青石(二枚目)となる。分析手段が発達していない時代にこれらの鉱物が混同されたのは致し方ない。それくらい両者は似ている。益富壽之助がだれよりも早くにこれらが同一ではないと気づいたという逸話が愛石家らに伝わっている。いずれにしても益富の産地発見がこの大隅石の誕生の端緒となっていることは確かで、益富は大隅石の発見に貢献したことにより櫻井賞の第3号メダルを受賞している。
[1] 第一文献
[2] Morimoto (1948) On the Modes of Occurrence of Cordierite from Sakkabira, Town Taru-mizu, Kimo-tsuki Province, Kagoshima Prefecture, Japan. Bulletin of the Earthquake Research Institute, 25, 33-35.
[3] 森本,湊 (1949) 鹿皃島縣肝屬郡垂水町早崎咲花平産菫青石の産出状態. 岩石鉱物鉱床学会誌, 33, 51-61.
[4] Miyashiro (1953) Osumilite, a new mineral, and cordierite in volcanic rocks. Proceedings of the Japan Academy, 29, 321-323.
[5] Brown, Gibbs (1969) Refinement of the crystal structure of osumilite. American Mineralogrst, 54, 101-116.
[6] 第二文献
[7] Chinner, Dixon (1973) Irish osumilite. Mineralogical Magazine, 39, 189-192.
[8] 横溝, 宮地 (1978) 万年山熔岩中の大隅石の化学組成. 73, 180-182.
[9] Chukanov, Pekov, Rastsvetaeva, Aksenov, Belakovskiy, Van, Schuller, Ternes (2012) Osumilite-(Mg): Validation as a mineral species and new data. Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva, 141, 27-36.
IMA No./year: 1959(1962s.p.)
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M15837; The Natural History Museum, London, England.(Handbook of Mineralogyから引用)
生野鉱 / Ikunolite
Bi4S3
模式地:兵庫県朝来市生野鉱山(旧:生野町)
第一文献: Kato A. (1959) Ikunolite, a new bismuth mineral from the Ikuno mine, Japan. Mineralogical Journal, 2, 397-407
第二文献: 設定なし

図1.Bi-(S+Se)-Te系の産出鉱物(一部省略)
文献[4]を一部改訂。日本産の新鉱物は太字で示した。
生野鉱は東京大学の加藤昭によって記載された新鉱物で、学名は模式地である生野鉱山に由来する[1]。より具体的な産地は、金香瀬(かながせ)鉱床群の千珠前𨫤(ヒ)だと伝わる。生野鉱山に勤務していた堀川国治を通じてその標本が加藤に渡たり、生野鉱が見出された。生野鉱の記載論文は1959年に発表され、1960年にはAmerican Mineralogist誌上で新鉱物として紹介されている[2]。その後に国際鉱物学連合が設立されると、これまでに発表された新鉱物の資格審査が行われ、生野鉱については1962年に独立種としてのお墨付きが与えられて、公式リストには1962s.p.が表示されている[3]。
生野鉱はBi4S3の化学組成をもち、硫テルル蒼鉛鉱(Tetradymite: Bi2Te2S)の関連鉱物である。ビスマス(Bi)を主成分として、テルル(Te)、硫黄(S)、セレン(Se)を含む鉱物を「硫テルル蒼鉛鉱族」と呼ぶこともあり、国産の新鉱物だと、都茂鉱(Tsumoite: BiTe)や河津鉱(Kawazilite: Bi2Te2S)もその仲間として知られている。ただ、硫テルル蒼鉛鉱族はまだ命名規約がまだなく、その適用範囲は必ずしも明確でない。これらの鉱物たちはBi-(S+Se)-Teを頂点にした三角形組成内にプロットされ、一連の鉱物は図内でいくつかの線上に位置する(図1)。この組成系列の鉱物はひとまとめにして図で見た方がわかりやすい。
生野鉱の化学組成は三角図の左上にあり、ホセ鉱A(Joséite-A:)とは水平線上の右隣となる。その差は微々たるもので、生野鉱がBi4S3であるのに対して、一つの硫黄(S)をテルル(Te)にしたものがホセ鉱A(Bi4TeS2)となる。加藤は論文中でホセ鉱AとのX線回折パターン、物理・光学特性の対比を行っているのだが、それらで両者は区別できない。現状、ホセ鉱Aと生野鉱の区別は化学組成分析によることになるが、ホセ鉱A(Bも)のIMA Statusは「Q」となっておりその存在を証明するデータに疑いがもたれている。ホセ鉱AはTeに富む生野鉱として分類されることで、いずれ消滅する可能性をはらんでいる。
生野鉱山は平安時代初期に開発が始まったとされる鉱山で、生野「銀山」としての呼び名もあるように、日本を代表する銀山でもあった。コレクターとして多様な金属硫化物を産出する点で魅力的な産地であり、生野鉱は生野鉱山からの最初の日本産新鉱物となった。のちに生野鉱は近隣の明延鉱山、それから大きく離れた栃木県足尾銅山からも産出が知られた。産地ごとにすこし輝きが異なるようで、模式地の生野鉱は銀白色に輝いているが、特に足尾銅山の生野鉱はなぜか青光りが強い。ただそのおかげで共生することのある自然ビスマスとの区別が容易となっている。
[1] 第一文献
[2] Fleischer M. (1960) New mineral names. American Mineralogist, 45, 476-480.
[3] International Mineralogical Association (1962) International Mineralogical Association: Commission on new minerals and mineral names. Mineralogical Magazine, 33, 260-263.
IMA No./year: 1959(1962s.p.)
IMA Status: A (approved)
模式標本:The Natural History Museum, London, England, 1960,92; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 113822, 115885.(Handbook of Mineralogyから引用)
人形石 / Ningyoite
(U,Ca,Ce)2(PO4)2·1-2H2O
模式地:鳥取県三朝町人形峠鉱山
第一文献:Muto T., Meyrowitz R., Pommer A.M., Murano T. (1959) Ningyoite, a new uranous phosphate mineral from Japan. American Mineralogist, 44, 633-650.
第二文献:Boyle D R, Littlejohn A L, Roberts A C, Watson D M (1981) Ningyoite in uranium deposits of south–central British Columbia: first North American occurrence., The Canadian Mineralogist, 19, 325-331.
人形石は原子力燃料公社の武藤正らにより見いだされた新鉱物で、鳥取県と岡山県の県境に位置する人形峠鉱山を模式地とする。第一文献によると鳥取県と記されているので、行政区分では三朝町になるだろう。原子力燃料公社はかつて存在した日本の原子力関連組織であり、1955年に人形峠で有望なウラン鉱床が発見されたことを受けて1956年に発足している。当時、人形峠は日本では最大級のウラン鉱床だった。
人形峠のウラン鉱床は後生堆積型と呼ばれ、堆積岩中に発達する。基盤には花崗岩類が存在しているが、それがかつて人形峠湖盆や古人形谷と呼ばれる水域にあった時に基盤岩の上に泥砂が堆積した。それが地上にもたらされて侵食を受けた際に、花崗岩類から溶け出したウラン溶液が堆積岩中に濃集したと考えられている。鉱石はリン灰ウラン石が当初の主体であったが、1957年にはより放射能の強い黒色鉱石もまた発見された。それはタールのような外観をしており一見して結晶粒は見当たらない鉱物である。武藤らはこのタール様で強い放射能をもつ鉱物の同定を試み、それは既知の鉱物とは一致しないことが判明する。主要なデータ収集は主にアメリカ地質調査所で行われ、化学組成についてはU1-xCa1-xREE2x(PO4)2・1-2H2Oが得られている。今となってはこの化学組成は曖昧と感じられるが、その当時、ウラン(U)と希土類元素(REE)を主成分とするリン酸塩鉱物は新鉱物の資格を有していた。結晶構造については格子定数までが得られており、合成相であるCaU(PO4)2・1.5H2Oと非常に近い値となっている。そして、CaU(PO4)2・1.5H2Oについてはラブドフェン関連構造であることから、人形石もまた同様にラブドフェン関連構造である考えられている[1]。武藤は人形石を見いだした功績において櫻井賞(第9号メダル)を受賞した。
後年になり、第二文献は模式地標本をEPMAで再分析しており、REEとしてはセリウム(Ce)を検出している。それを受けて人形石の理想化学式は(U,Ca,Ce)2 (PO4)2・1-2H2Oと設定されている。結晶構造については少しだけ理解が進み、ブラベ格子について第一文献ではP格子ということだったが、第二文献ではより対称性の高いC格子を予想している[2]。
今となっては人形石は世界で多くの産地が知られているが、その多くは微視的な存在に過ぎない。そのため見てそれとわかる標本として、模式地の人形石は優れていると言えるだろう。写真は宮久三千年によって模式地から得られた人形石の標本となる。人形石は黒色タール状の部分で結晶は非肉眼的である。第一文献では数ミクロンの針~板結晶と記載されているが、私の標本ではSEMで観察しても明瞭な結晶は観察されなかった。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
IMA No./year: 1961(1997s.p.)
IMA Status: Rd (redefined)
模式標本:国立科学博物館 M-15598(Handbook of Mineralogyから引用)
尾去沢石 / Osarizawaite
Pb(Al2Cu2+)(SO4)2(OH)6
模式地:秋田県鹿角市尾去沢鉱山
第一文献:Taguchi Y. (1961) On osarizawaite, a new mineral of the alunite group, from the Osarizawa mine, Japan. Mineralogical Journal, 3, 181-194.
第二文献:Giuseppetti G. & Tadini C. (1980) The crystal structure of osarizawaite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, 1980, 401-407.
尾去沢石は三菱金属工業の研究員である田口靖郎によって記載された新鉱物で、秋田県尾去沢鉱山から発見されたことで産地にちなんで命名された。第一文献には尾去沢石は鉱山の正徳樋(ひ)および卯酉樋の酸化帯から発見されたことが記されている。尾去沢石を発見した功績について、田口には櫻井賞(第7号メダル)が授与されている。
一般に銅鉱床は少なからず酸化帯を伴い、酸化帯は採掘コストが低いためにかつては盛んに採掘された。酸化帯は二次鉱物の宝庫とも言え、褐鉄鉱が主体となりつつも色鮮やかで多彩な鉱物もまた多く伴われるほか、場所によっては沈殿銅として自然銅が生じることもある。尾去沢鉱山も基本的には同様で、平安期から開発が始まっていることからまずは酸化帯から採掘が始まった鉱山だと推測されている。そして1978年(昭和53年)に閉山するまで1300年近い歴史を有し、日本の近代化に大きく貢献した銅鉱山でもある。尾去沢石が見いだされたのは1961年のことであり、鉱山としてはほぼおわりという時期であろう。分析に用いられた尾去沢石は正徳樋(ひ)の6b-2脈において粉末から土状の標本として得られている。
尾去沢石の理想化学式はPbCuAl2(SO4)2(OH)6として記されている。この時代の鉱物は後年に理想化学式の修正を受けることも多いが、尾去沢石についてカッコの括りができただけでほとんど当時のまま残るなど、分析レベルの高さがうかがえる。そしてこの分析は東京大学の渡辺武男と加藤昭によって執り行われている[1]。結晶構造については粉末X線回折法によって格子定数が報告されており、総合的に尾去沢石はビーバー石(現、銅ビーバー石)から見て、三価鉄(Fe3+)アルミニウム(Al)に置き換えた、明礬石族の新鉱物として記されている。後に模式地の標本を用いて結晶構造の精密化が行われている[2]。後年になり、明礬石超族の命名規約が作られる際に尾去沢石と銅ビーバー石についてはその独立性について議論があったが、最終的にいずれも独立の鉱物種として認められている [3]。
写真は秋田県亀山盛鉱山(上)と新潟県三川鉱山(下)から得られた尾去沢石の標本で、いずれも銅鉱床の酸化帯に生じた尾去沢石である。亀山盛鉱山の尾去沢石は走査型電子顕微鏡では数ミクロンの結晶の集合体であるものの、実体顕微鏡では黄土色の被膜としてみえる。一方で三川鉱山からの標本は石英の晶洞に生じた尾去沢石の結晶であり、翠緑色の犬牙状結晶が放射状に集合した姿となっている。組成的には三川鉱山の標本が理想値に近く、亀山盛鉱山の標本はリン(P)に富みヒシンダル石との境界に近い。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] Jambor J.L. (1999) Nomenclature of the alunite supergroup. The Canadian Mineralogist 37, 1323-1341.
IMA No./year: 1961(2016s.p.)
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M15110; The Natural History Museum, London, England; Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 106170; National
Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 107416.(Handbook of Mineralogyから引用)
吉村石 / Yoshimuraite
Ba2Mn2+2Ti(Si2O7)(PO4)O(OH)
模式地:岩手県野田村野田玉川鉱山
第一文献:Watanabe T., Takéuchi Y., Ito J. (1961) The minerals of the Noda-Tamagawa mine, Iwaté Prefecture, Japan. III. Yoshimuraite, a new barium-titanium-manganese silicate mineral. Mineralogical Journal, 3, 156-167
第二文献:Sokolova E., Cámara F. (2014) From structure topology to chemical composition. XVII. Fe3+ versus Ti4+: The topology of the HOH layer in ericssonite-2O, Ba2Fe3+2Mn4(Si2O7)2O2(OH)2, ferroericssonite, Ba2Fe3+2Fe2+4(Si2O7)2O2(OH)2, and yoshimuraite, Ba4Ti4+2Mn4(Si2O7)2(PO4)2O2(OH)2. The Canadian Mineralogist, 52, 569-576
吉村石は東京大学の渡辺武男らによって記載された岩手県野田玉川鉱山を模式地とする新鉱物で、九州大学で教鞭をとっていた吉村豊文教授(1905-1990)にちなんで命名された。記載論文が発表されたのは1961年であるが、1959年にはすでに名前が決まっていたことがうかがえる。まだ名前がつかない状態の未知鉱物としての発見は1953年だった[1]。
吉村石は未知鉱物として発見されてすぐに詳細な調査が始まったものの、結晶構造解析を担当していた東京大学の森博が急逝したこともあり、研究の進展は必ずしもスムーズではなかったのだろう。それでも丁寧な湿式分析によって、ケイ酸塩分について(SiO4)2もしくは(Si2O7)Oのどちらかであることが示された[2]。そして2000年になり、吉村石の結晶構造を解明したとする論文が登場し、(Si2O7)Oのほうだと判明した[4]。そして、2017年になりセイドゼル石(Seidozerite)超族が誕生し、吉村石はその下位分類にあたるバフェルチ石(Bafertisite)族の一員に分類されることになった[5,6]。
ただ、ここまでの過程で二つ問題が生じたと思っている。まずは組成のすり替わりであり、具体的にはリン(P)と硫黄(S)の問題。オリジナルである野田玉川鉱山の吉村石はS>Pの組成であった。しかし、結晶構造解析に使用された田口鉱山の吉村石はP>Sの組成。そして、田口鉱山の吉村石を使って構造解析が行われ、それをもとに理想化学式が決められたので、吉村石とはP>Sの組成と定義されてしまった。こうなると、もともとの野田玉川鉱山の吉村石(S>Pの組成)は、もはや吉村石でないことなる。もう一つの問題は、構造解析を実施した論文がMnの位置について誤りを含むこと。吉村石はどこかで一度問題を整理して、再検討されてもいい。
吉村石は褐色でバラ輝石などと共に産出することからそのコントラストは明瞭で、また葉片状結晶という特徴からもわかりやすい新鉱物である。産地については模式地の野田玉川鉱山の他に愛知県田口鉱山と岩手県田野畑鉱山が知られる。田口鉱山の吉村石はかなり発見が早く、1958年には見いだされ、論文も1963年には出版されている[7]。一方で岩手県田野畑鉱山からは多産するようで、今のところ最も手に入りやすい。それにしても田野畑鉱山の吉村石がいつ頃に知られるようになったのだろうか。ざっと文献を調べたが不明で、田野畑鉱山の吉村石は論文として発表されていないのかもしれない。
写真は模式地の野田玉川鉱山、田野畑鉱山、田口鉱山からの吉村石となる。ここでは組成の問題は認識しつつも、すべて吉村石としてあつかう。吉村石自体は褐色の葉片状結晶で、産地を問わず似通った外観で出現する。一方で共生鉱物関係は産地ごとに異なっているようで、模式地ではバラ輝石が目立つものの、田野畑鉱山では石英が、田口鉱山では角閃石が目に付く。岩手県肘葛鉱山からも吉村石の産出があるようだが、その標本は残念ながら手に入らなかった。
[1] Watanabe T. (1959) The minerals of the Noda-Tamagawa mine, Iwate Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 2, 408-421.
[2] 第一文献
[3] International Mineralogical Association (1967) Commission on new minerals and mineral names. Mineralogical Magazine, 36, 131-136
[4] McDonald A.M., Grice J.D., Chao G.Y. (2000) The crystal structure of yoshimuraite, a layered Ba–Mn–Ti silicophosphate, with comments on five–coordinated Ti4+. The Canadian Mineralogist, 38, 649-656.
[5] 第二文献
[6] Sokolova E., Cámara F. (2017) The seidozerite supergroup of TS-block minerals: nomenclature and classification, with change of the following names: rinkite to rinkite-(Ce), mosandrite to mosandrite-(Ce), hainite to hainite-(Y) and innelite-1T to innelite-1A. Mineralogical Magazine, 81, 1457-1487.
[7] 広渡文利,磯野清 (1963) 愛知県田口鉱山の吉村石について. 鉱物学雑誌, 6, 230-243.
IMA No./year: 1962(1987s.p.)
IMA Status: Rd (redefined)
模式標本:不明
芋子石 / Imogolite
Al2SiO3(OH)4
模式地:熊本県人吉市
第一文献:Yoshinaga N., Aomine S. (1962) Allophane in some Ando soils. Soil Science and Plant Nutrition, 8, 6-13.
第二文献:Bayliss P. (1987) Mineralogical notes: mineral nomenclature: imogolite, Mineralogical Magazine, 51, 327.
芋子石は九州大学の吉永長則と青峰重範によって熊本県人吉地方の火山灰土壌から見出された新鉱物である[1]。現在では有効な鉱物種として確立されているが、過去にいったんリジェクト(否定)された後に復活したという経緯がある[2]。
芋子石の名前は記載論文に先立って登場している[3]。吉永と青峰は熊本県上村・長陽村、東京都岡本および北海道河西群から得られた火山灰からアロフェン(Allophane)を分離しその諸性質を調べている過程で、熊本県の試料からアロフェンとは性質の異なるコロイド状物質を見出した。これが後の新鉱物・芋子石である。熊本県上村産の試料から最初に見出され、この試料はこの地方では「芋子(いもご)」と呼ばれている黄色い火山灰土壌の塊であったことから、この新鉱物は芋子石と名付けられた。芋子自体は芋子石のほかにアロフェン、石英、クリストバル石、ギブス石、バーミキュライトなどから構成されている。
芋子石の記載論文では諸性質が報告されている[1]。一方でこの時点で得られた化学組成や結晶的性質はやや不完全であり、著者ら自身も「この鉱物を芋子石として暫定的に指名した」と弱めの表現を使っている。1963年になってAmerican Mineralogistの新鉱物レビューで芋子石が紹介されているが、同時に「データは新鉱物としては不適切」というコメントが付いている[4]。そしてIMAが設立してから始まった鉱物の洗い直しおいて、1967年にリジェクト(否定)が宣言されてしまった[5]。この時点で芋子石は公式には鉱物ではなくなっているので、論文では独立の鉱物のようにあつかってはいけないのだが、芋子石の名称は粘土関連雑誌では独立種のように引き続き使用された。
芋子石を含む粘土鉱物の記載については長らく問題になっていて、それをどうするかという委員会は1950年頃に立ち上がっていた。この委員会で粘土鉱物の命名規約などが議論され、1980年にその要旨が複数の関連雑誌で紹介されている[6-8]。その中には芋子石の項があり、1969年に東京で会合が開かれた際に委員会レベルでは芋子石の名前が改めて承認されたことが記してある。1983年に「Glossary of Mineral Species」という鉱物名と出典をまとめた本にはアロフェンの亜種として芋子石が紹介されている[9]。IMAからの再承認は1986年であった旨が第二文献に紹介されており、この第二文献の出版された1987年がオフィシャルリストには掲載されている[2]。復活までに芋子石の諸性質の解明が進んでいたこともその一助になったと思う。芋子石の化学組成と構造は1972年には明らかとなっており[10]、この論文には吉永が参加している。
写真は芋子石を含む土壌で、これがいわゆる「芋子」の標本。芋子石はカーボンナノチューブに似た特徴的な構造から様々な応用が期待され多くの分野で研究が進んでいる。トムソン・ロイター社の論文検索システムWeb of Scienceで芋子石を検索すると700件近くもヒットする。芋子石の学術的なインパクトは非常に大きいと言えるだろう。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] Yoshinaga Y. and Aomine S. (1962) Allophane in some Ando soils. Soil Science and Plant Nutrition, 8, 6-13.
[4] Fleischer M. (1963) New mineral names. American Mineralogist, 48, 433-437.
[5] International Mineralogical Association (1967) Commission on new minerals and mineral names. Mineralogical Magazine, 36, 131-136.
[6] Bailey S.W. (1980) Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee. Calys and Clay Minerals, 28, 73-78.
[7] Bailey S.W. (1980) Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee. Caly Minerals, 15, 85-93.
[8] Bailey S.W. (1980) Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee. American Mineralogist, 65, 1-7.
[9] Fleischer M. (1983) Glossary of Mineral Species. Mineralogical Record, Tucson, AZ.
[10] Cradwick P.D.G., Farmer V.C., Russell J.D., Masson C.R., Wada K., Yoshinaga N. (1972) Imogolite, a hydrated aluminium silicate of tubular structure. Nature Physical Science, 240, 187-189.
IMA No./year: 1962-004
IMA Status: Rn (renamed)
模式標本:不明
赤金鉱 / Akaganeite
(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1.25·nH2O
模式地:岩手県江刺市赤金鉱山
第一文献: Mackay A.L. (1962) ß-ferric oxyhydroxide-akaganéite. Mineralogical Magazine, 33, 270-280.
第二文献: Post J.E., Heaney P.J., von Dreele R.B., Hanson J.C. (2003) Neutron and temperature-resolved synchrotron X-ray powder diffraction study of akaganéite. American Mineralogist, 88, 782-788.
赤金鉱は東北大学の南部松夫により岩手県赤金鉱山から見いだされた新鉱物で、赤金鉱山の名称から命名された。南部はほかにも萬次郎鉱、神津閃石、高根鉱、上国石という国産の新鉱物について筆頭で研究をまとめている。赤金鉱は南部にとって最初の新鉱物であるものの論文の公表は次の萬次郎鉱より後であった。南部による赤金鉱の記載論文は1968年に岩石鉱物鉱床学会誌に掲載されている[1]。この論文で謝辞に名を挙げられている谷田勝俊は分析を担当し、その貢献により谷田には櫻井賞の第25号メダルが授けられた。
まずは発見の経緯をまとめておこう。1956年に赤金鉱山において松森磁硫鉄鉱鉱床の露頭から褐鉄鉱様の二次鉱物が採集され、それは合成実験で知られていたβ-FeOOH相に該当することが判明する[2]。それは天然では初めての産出、つまりは新種に相当することから南部はこの鉱物に赤金鉱(Akaganeite)の名前を与え、それを1959年の三鉱学会連合学術講演会(仙台)で発表した[3]。1962年に新鉱物の申請が行われたようで、年内には承認が与えられている(IMA 1962-004)[4]。赤金鉱は国際鉱物学連合が新鉱物について審査・承認を行うようになって以降では最初の国産新鉱物ということになるだろう。一方でその模式標本は記載論文にも記述が無いため、その所在を追うことができない。
公式リストに掲載されている第一文献は南部らの記載論文ではなく、海外の研究者の論文となってる[5]。この論文は南部から標本の提供を受け、電子線回折によって赤金鉱がβ-FeOOH相であることを再確認した。ところがこの論文はやっかいごとも内包していた。この論文はタイトルで赤金鉱をAkaganéiteとつづり、eにアキュート・アクセントがついている。これは明らかに誤ったつづりであるのだが、かなり長い間この誤ったほうがオフィシャルリスト上にあった。今となってはアキュート・アクセントのついたつづりが誤りであることはすでに宣言されているのだが[6]、いかんせん遅すぎる。もはや収拾がつかないほどこの誤ったスペリングは学術業界内に蔓延してしまい、正しいAkaganeiteよりもむしろ間違っているAkaganéiteほうが論文には多いという事態となっている。しかし改めて書いておく。学名の正しいつづりは「Akaganeite」であってアキュート・アクセントをつけてはいけないのだ。そういった経緯でIMA StatusはRn(renamed)である。
赤金鉱の化学組成はざっくり示せばFeOOHではあるのだが、それは正確ではなく実際には塩素が必須である。南部もそれは認識していたが試料が乏しいことから定量はできず、模式地の標本では塩素は0.5wt%以下であると推測するにとどまっている。一方でオフィシャルリストに掲載されている赤金鉱の化学組成ではニッケルも入っている。これについて違和感を覚えたので調べたところ、これは第二文献および同じ著者の先行論文が元になっているようだ[7、8]。赤金鉱は様々な場所や産状で産出が報告されており、鉄ニッケル隕石の酸化皮膜を成す産状も知られるようになる [7、8]。第二文献はその赤金鉱を分析したところ多量のニッケルを固溶していたことから、第二文献を元にしているオフィシャルリストの組成式にはニッケルが入っている。ただしニッケルは必須成分ではないだろう。模式地の赤金鉱についてはニッケルの固溶はない[1]。
赤金鉱もまた研究例の多い国産新鉱物の一つである。例によってWeb of ScienceでAkaganeite(Akaganéite)を検索すると600件近い結果が出てくる。赤金鉱はいわゆるβ-FeOOH相なのでこれも含めて検索すると1100件を越え、赤金鉱もまたインパクトのある国産新鉱物といえる。
写真の標本は模式地の赤金鉱山から産出した標本となる。初め桜井欽一が手に入れ、それが山田滋夫に渡り、その一部を恵与していただいた。見た目は褐鉄鉱の粉末で不定形結晶の集合かと思われたが、透過型電子顕微鏡で観察するとナノスケールの針~剣状結晶であった。電子線回折から全て赤金鉱であることが確認できた。
[1] 南部松夫 (1968) 岩手県赤金鉱山産新鉱物赤金鉱(β-FeOOH)について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 59, 143-151.
[2] 南部松夫 (1957) 岩手県赤金鉱山における磁硫鉄鉱の酸化. 鉱山地質, 7, 290 (1957年度地下資源関係学協会合同秋期大会の要旨)
[3] 南部松夫 (1960) 新鉱物赤金鉱(β-Fe2O3・H2O)について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 44, 62 (昭和34年度学術講演会講演要旨)
[4] Commission on New Minerals and Mineral Names = CNMMNは1959年に設立され,この委員会は主に新鉱物のデータと名前に関して審査と承認を行っている。鉱物の分類や命名規約を検討する委員会はCommission on Classification of Minerals = CCMというものがあって別で活動していたが,2006年に合併してCommission on New Minerals, Nomenclature and Classification = CNMNCとなり,そこでは新鉱物の審査だけでなく命名規約についても一括で取り扱うようになっている。
[5] 第一文献
[6] Burke E.A.J. (2008) Tidying up mineral names: An IMA scheme for suffixes, hyphens and diacritical marks. Mineralogical Record, 39, 131-135.
[7] Post J.E., Buchwald V.F. (1991) Crystal structure refinement of akaganeite. American Mineralogist, 76, 272-277.
[8] 第二文献
IMA No./year: 1963(1967s.p.)
IMA Status: A (approved)
模式標本:Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, 114576(Handbook of Mineralogyから引用)
園石 / Sonolite
Mn2+9(SiO4)4(OH)2
模式地:京都府和束町園鉱山 他
第一文献: Yoshinaga M. (1963) Sonolite, a new manganese silicate mineral. Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu Imperial University, Series D, 14, 1-21.
第二文献: Kato T., Ito Y., Hashimoto N. (1989) The crystal structures of sonolite and jerrygibbsite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, 1989, 410-430.
園石は九州大学の吉永真弓により発見された新鉱物で、発見地の京都府和束町園鉱山の名称から命名されている。記載論文は1963年に九州大學理學部紀要で発表され[1]、同年の内にAmerican Mineralogist誌でも紹介されている[2]。オフィシャルリストに記してある年代は1967年で、これはIMAが設立後に改めて承認された年となる[3]。
吉永の記載論文によれば、アレガニー石(Alleghanyite)や他の含マンガン珪酸塩鉱物を研究する過程で、1960年に園鉱山の鉱石中から最初に見出され、それに続いて多くの産地が見つかったようだ。論文で挙げられている園鉱山以外の産地は、岩手県花輪鉱山、茨城県鷹峰鉱山、栃木県加蘇鉱山、愛知県田口鉱山、滋賀県五百井鉱山、京都府向山鉱山、山口県和木鉱山、山口県高森鉱山、山口県久杉鉱山が挙げられており、国外の産地として台湾蘇澳鉱山も記されている。
園石はバラ輝石、パイロクロアイト、ガラクス石などを密接に伴い、それらは園石の結晶中にも包有される。こういった包有物の存在は湿式分析が主な分析手段だったこの時代ではたいへん悩ましいことで、不純物の少ない試料は常に望まれていた。園石は名前こそ園鉱山の名称から命名されているが、諸性質の解明に使用されたのは主に花輪鉱山と久杉鉱山からの試料であった。この二つの鉱山から産出する園石は不純物(包有物)が少ないことが記してある。
園石は単斜ヒューム石(Clinohumite)のマグネシウム(Mg)をマンガン(Mn)に置き換えた鉱物であることが論文中には記されている[1]。ただ、今では単斜ヒューム石はフッ素(F)優占種であることが明らかとなっているので、現在の基準で見ると、園石は単斜ヒューム石のマグネシウムをマンガンに、フッ素を水酸基に置き換えた鉱物ということになる。後に園石の結晶構造解析も行われ、改めて単斜ヒューム石と同構造であることが確認された[4]。
写真は福井県藤井鉱山と京都府和束町からの標本となる。記載論文に挙げられた以外にも多くの産地が知られている。園石は国内の産地ではいずこでも肉眼的に鈍い赤褐色で、アレガニー石とはぱっと見で判別はできない。海外では数センチの単結晶が産出する。
[1] 第一文献
[2] Fleischer M. (1963) New mineral names. American Mineralogist, 48, 1413-1421.
[3] International Mineralogical Association (1967) Commission on new minerals and mineral names. Mineralogical Magazine, 36, 131-136
[4] 第二文献
IMA No./year: 1963-002
IMA Status: A (approved)
模式標本:National Science Museum, Tokyo, Japan, M15-112; The Natural History Museum, London, England.(Handbook of Mineralogyから引用。ただし研究に使用された標本は東大博物館に現存している)
神保石 / Jimboite
Mn2+3(BO3)2
模式地:栃木県鹿沼市加蘇鉱山
第一文献: Watanabe T., Kato A., Matsumoto T., Ito J. (1963) Jimboite, Mn3(BO3)2, a new mineral from the Kaso mine, Tochigi Prefecture, Japan. Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, 39, 170-175.
第二文献: Sadanaga R., Nishimura T., Watanabe T. (1965) The structure of jimboite, Mn3(BO3)2 and relationship with the structure kotoite. Mineralogical Journal, 4, 380-388.

模式地標本 東京大学総合博物館標本
黒い脈はヤコブス鉱で,それ以外はほぼ神保石。

群馬県利東鉱山東小中鉱床
含神保石マンガン鉱石で中央の白い繊維状結晶はマンガン硼素酸塩鉱物のウイゼル石。
神保石は東京大学の渡辺武男らによって栃木県加蘇鉱山から見いだされた新鉱物で、東京帝国大学鉱物学教室の教授であった神保小虎の名にちなんで命名された。神保石の記載論文は日本学士院が発行するProceedings of the Japan Academy において1963年に発表された[1]。その一つ前の論文も渡辺によるもので、本邦初産となる小藤石[2]の記載論文となっている[3]。
神保小虎(1867-1924)は東京帝国大学地質学科を卒業し、北海道庁で勤務した後にベルリン大学に留学した。留学先では古生物学を専攻すると共に鉱物学・岩石学・地理学についても学んだとされる[4]。助教授で東京大学に着任した後に、新たに設置された鉱物学教室の初代教授となる。「日本鉱物誌 第二版」の著者の一人であり、第三版も企画していたとされる[5、6]。詳しい経歴や業績、人物についてのエピソードなど、詳しく知りたい方は引用先を当たってほしい[例えば7-9]。
神保石の発見や研究の経緯については渡辺自らが記した解説文が残っており[10]、内容を紹介しておこう。小藤石の研究を行っていた頃にスウェーデンのLångban鉱山からピナキオ石(Pinakiolite: (Mg,Mn)2(Mn3+,Sb5+)O2(BO3))というマンガン硼酸塩鉱物が産出することを知り、小藤石(Kotoite: Mg3 (BO3)2)のマンガン置換体の存在を期待するようになったという。もしそれが産出するなら第一候補は尾平・大崩山地方のマンガン鉱床、他の候補として北上産地のマンガン鉱床を想定していたようだ。そうした中で、鉱物学教室に所属していた加藤昭が鉱物研究家の櫻井欽一らと共に栃木県加蘇鉱山に赴き、珍しい鉱石を採集してきた。当初の観察で光学顕微鏡下での特徴が小藤石に似ていると半ば冗談で話し合っていたらしい。ところが分析をしてみると、それは長年探し求めていた小藤石のマンガン置換体であることが判明する。そこから新鉱物申請に向けてデータを集めはじめ、近代化された設備や周囲の助力もあってほんの4ヶ月で研究がまとまったと記してある。この年代には国際鉱物学連合の体系も固まって新鉱物の審査委員会もできあがっており、神保石は万票(満場一致)で承認された。模式地標本を用いた構造解析の結果も直後に報告された[11]。
神保石は顕微鏡下ではほぼ無色だが、肉眼的な結晶だと紫赤褐色の鉱物である。東大博物館にある模式地標本をみると確かにそのとおりだ。そして今手に入る神保石と言われる標本もそんな色をしており、期待して調べてみたが神保石は入っていなかった。実は神保石不在の標本が神保石っぽく見えるのはテフロ石とガラクサイトによって醸し出されている。そしてそれは肉眼ではほとんど判別不能である。下に神保石不在の標本を掲載した。東大博物館のホンモノと見比べてみてもほとんど同じに見えるのにこれらには神保石は入っていない。神保石が見つかった唯一の石は利東鉱山の東小中鉱床から産出する鉱石で、ウイゼル石(Wiserite)を伴う標本にだけ神保石がわずかに確認できた。
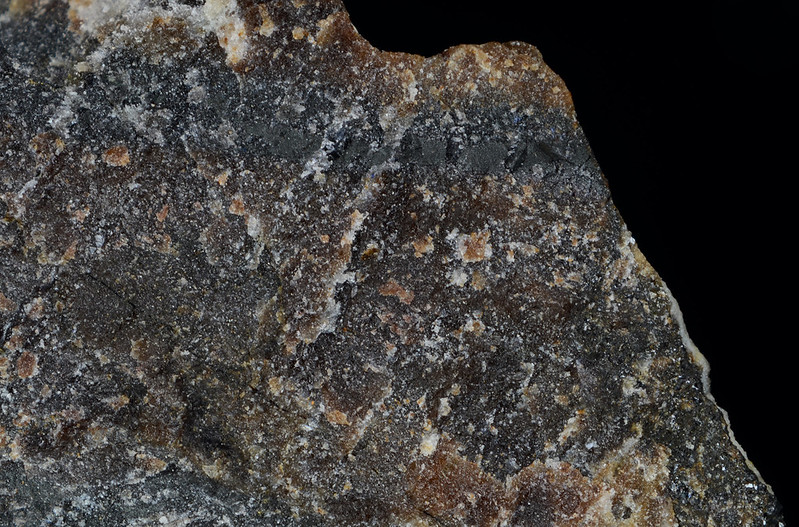
神保石不在標本その1。
手に入れた模式地の岩石標本。調べたところこれはテフロ石が主体で多量の微小ガラクサイトが含まれている。菱マンガン鉱もあるがこれは細脈で来ており肉眼的にはわからない。黒い帯はアラバンド鉱。どれだけ探しても神保石はみつからず、硼酸塩鉱物の気配すらなかった。

神保石不在標本その2。
群馬県利東鉱山東小中鉱床の岩石標本。これもテフロ石、ガラクサイト、菱マンガン鉱の集合。やはり神保石はこういう標本にはいなかった。経験的にテフロ石がいるとあきらめざるを得ない。色が神保石のようであっても劈開がルーズな標本は軒並みダメのようである。
[1] 第一文献
[2] 小藤石(kotoite): Mg3(BO3)2。神保石から見てMn→Mg置換体に相当する。渡辺武男によって北朝鮮笏洞鉱山から見いだされた新鉱物で,神保石よりも前に発見されている。
[3] Watanabe T., Kato A., Katura T. (1963) Kotoite, Mg3(BO3)2 from the Neichi Mine, Iwate Prefecture, Japan. Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, 39, 164-169.
[4] 佐藤傳藏 (1924) 神保理學博士を弔す. 地学雑誌, 36, 179-182.
[5] 和田維四郎, 神保小虎, 瀧本鐙三, 福地信世 (1916) 日本鉱物誌 第2版, pp.357.
[6] 和田維四郎, 伊藤貞一, 桜井欽一 (1947) 日本鉱物誌 第3版 上巻, pp.368.
[7] 浜崎健児 (2011) ユーラシア大陸を駆け抜けた神保小虎-その人物と神保をめぐる人たち. 地質学史談話会会報, 36, 27-28.
[8] 日本地質学会メールマガジン No250.
[9] 日本地質学会メールマガジン No254.
[10] 渡辺武男 (1963) 新鉱物を見いだすまで-小藤石と神保石の場合-. 科学, 33, 461-467.
[11] 第二文献
IMA No./year: 1963-011
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M15111(Handbook of Mineralogyから引用。ただし研究に使用された標本は東大博物館に現存している。)
原田石 / Haradaite
SrV4+Si2O7
模式地:岩手県野田村野田玉川鉱山 & 鹿児島県大和村大和鉱山
第一文献:Takéuchi Y., Joswig W. (1967) The structure of haradaite and a note on the Si-O bond lengths in silicates. Mineralogical Journal, 5, 98-123.
第二文献:Watanabe T., Kato A., Ito J., Yoshimura T., Momoi H., Fukuda K. (1982) Haradaite, Sr2V4+2[O2 Si4O12], from the Noda Tamagawa mine, Iwate Prefecture and the Yamato mine, Kagoshima Prefecture, Japan. Proceedings of the Japan Academy 58 B, 21-24.
原田石は東京大学の渡辺武男らによって岩手県野田玉川鉱山と鹿児島県大和鉱山から発見された新鉱物で、北海道大学の原田準平の業績をたたえて命名された。IMAno.を見るに1963年に申請され、年内には承認されたと思われるが、記載論文の公表は20年近く後になっている。記載論文に先立って構造解析の論文が1967年に発表され[1]、記載論文の公表は1982年であった[2]。
原田石はほぼ同時期に二つの鉱山から別々の研究グループによって見いだされたと伝わる。1962年の地質学会において九州大学の吉村らが鹿児島県大和鉱山からの本鉱を報告したことが、記録上では初出になるだろう[3]。記載論文では野田玉川鉱山から福田皎二が1960年に標本を「採集した」ことが記されている。一方で記載論文に先立って公表された1967年の構造解析の論文では1960年に渡辺と加藤が「発見した」という記述になっており[1]、食い違いがある。優先権争いがあったという話を聞いているので、そういった事情が反映されたのだろう。それでも1974年には二つの研究グループは連名で国際学会において発表している[4]。このあたりにはわだかまりは解けたのかもしれない。二つの研究グループの筆頭であった渡辺武男と吉村豊文は北海道大学において原田と共に勤務しており、原田の還暦記念論文集にも二人の名前が見られる。
鉱物名の元になった原田準平(1898-1992)は1924年に東京帝国大学を卒業している。すぐさま理学部の助手となり、翌年には熊本高等工業学校および第五高等学校の教授を兼務し、熊本医科大学予科講師も務めている。1928年から文部省在外研究員としてヨーロッパ・アメリカに留学し、1931年に北海道帝国大学の助教授に着任する。翌年には地質学鉱物学第四講座の教授となる。そしてこの第四講座は地球惑星物質学研究グループと名を変え、今も存続している。原田に続く第四講座の歴代教授は、八木健三、針谷有、藤野清志、永井隆哉となる。
原田石はストロンチウム(Sr)と4価のバナジウム(V4+)を主成分とするケイ酸塩鉱物で、翠緑色の非常に美しい鉱物である。天然で最初に見つかり、1965年には伊藤順によって合成された[5]。野田玉川鉱山の原田石は粗粒のバラ輝石に伴われる石英の集合中に5ミリに達する平板状結晶で産出したようだ。大和鉱山ではゴールドマンざくろ石・バラ輝石・石英を伴って塊状のマンガン鉱石を切る脈として産出したという記述がある。その他、愛知県田口鉱山[6]と高知県松尾鉱山[7]からも産出が知られる。原田石を伴う鉱石はいずれも低品位鉱である。
写真は岩手県野田玉川鉱山、鹿児島県大和鉱山、高知県松尾鉱山から産した原田石で、いずれも特徴的な翠緑色が美しい。これらは何とか手に入った。だが愛知県田口鉱山の原田石はひときわ稀なのかその標本をみたことすらない。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] Yoshimura T., Shirozu H., Momoi H. (1962) Jour. Geol. Soc. Japan, 68, 397 (abstr.) (in Japanese)
[4] Watanabe T., Kato A., Ito J., Yoshimora T., Momoi H., Fukuda K. (1974) Haradaite, Sr2V2(O2)(Si4O12), a new mineral from the Noda Tamagawa mine, Iwate Prefecture, and the Yamato mine, Kagoshima Prefecture, Japan. 9th General Meeting of the International Mineralogical Association, Berlin Germany, 9, 97-97.
[5] Ito J. (1965) Synthesis of vanadium silicates: haradaite, goldmanite and roscoelite. Mineralogical Journal, 4, 299-316.
[6] 松山文彦,小林暉子(1993) 愛知県田口鉱山産原田石. 地学研究,42,2-4
[7] 広渡文利,松枝太治,吉村豊文(1972) 高知県松尾鉱山の原田石. 三鉱学会要旨集,p12.
IMA No./year: 1965-017
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M15843; National School of Mines, Paris, France; Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 108788; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 120592.(Handbook of Mineralogyから引用); 国立科学博物館 MSN-M18000(門馬ら[4]はこれをタイプ標本と記述している)
櫻井鉱 / Sakuraiite
(Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4
模式地:兵庫県朝来市生野町生野鉱山
第一文献:加藤昭 (1965) 新鉱物「櫻井鉱」. 地学研究,桜井欽一博士紫綬褒章記念号,1-5.
第二文献:Shimizu M., Kato A., Shiozawa T. (1986) Sakuraiite: chemical composition and extent of (Zn,Fe)In-for-CuSn substitution. The Canadian Mineralogist, 24, 405-409.

模式地標本
やや緑色を帯びた黒灰鋼色部に櫻井鉱とぺトラック鉱が含まれる。
櫻井鉱は国立科学博物館の加藤昭によって記載された新鉱物で、本邦鉱物学の発展に貢献したことで紫綬褒章を受章した櫻井欽一にちなんで命名された[1]。模式標本は国立科学博物館に収蔵され、記載論文は地学研究の桜井欽一博士紫綬褒章記念号の巻頭に掲載された。その論文に続いて櫻井鉱が誕生するまでの経緯が述べられている[2]。
文献[2]によれば、櫻井の紫綬褒章受章が決まった昭和39年11月に、東京大学の渡辺武男は記念として新鉱物に献名したいと述べたと伝わる。加藤もまた同意であったものの、櫻井の業績にふさわしい立派な新鉱物になる候補はその時点では見いだせていなかった。そうした中、11月下旬に兵庫県生野鉱山から一つの同定依頼が舞い込んでくる。加藤は気乗りがしないながらも予備実験として分析を行うとその試料には多量のインジウム(In)が認められた。その当時、インジウムを主成分とする鉱物は2つのみであった。そして、期待と不安を交えながら行われたX線回折実験の結果はこれまでのインジウム鉱物とは異なるパターンを示したのだった。これが櫻井鉱が確実に認識された瞬間である。
加藤は櫻井鉱の化学組成を(Cu,Fe)2Zn(In,Sn)S4とまとめるつもりであったが、研究の仕上げの段階になり渡辺は化学組成の作り方について次のように指摘した。櫻井鉱の結晶構造は解明されていないのだから、(Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4という形にするべきだという提案である。加藤はその意見を入れ渡辺の提案した化学組成を採用した。これが今のオフィシャルリストに掲載されている。渡辺の意見はやや消極的な理由から来ているように思えるが、結果的に、渡辺が提案した化学組成は最新の研究結果と調和的である。例えば、清水らはCu-Zn-Fe置換に一定の傾向を確認し[3]、結晶構造解析からはCu-Zn-Feは完全固溶であることが報告されている[4]。
一方で、単結晶X線プリセッション写真と化学組成分析を根拠に、櫻井鉱は立方晶系で(Cu,Zn,Fe,In,Sn)Sとする鉱物だという論文は古くからある[5]。この報告を受けて櫻井鉱の定義が「立方晶系の(Cu,Zn,Fe,In,Sn)S」へ改訂された。しかしその是非について検証がされないまま、2013年に石原鉱(Ishiharaite: (Cu,Ga,Fe,In,Zn)S、立方晶系)が新鉱物として承認されてしまった。端成分で考えるとどちらもCuSになってしまい区別ができない。さらには立方晶系で格子定数もほぼ共通という困った事態が生じた。混乱に拍車をかけるようにこの時点ではどちらも結晶構造の詳細が明らかでなかった。そこで2014年に櫻井鉱の化学組成を元の(Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4へ戻すという対応が行われた。
櫻井鉱の結晶構造は頂点を共有した四面体がただひたすら並んだ姿をしている。これはつまり閃亜鉛鉱と同じであり、将来的に閃亜鉛鉱超族ができたとすると櫻井鉱は間違いなくその一員に組み込まれる。閃亜鉛鉱超族(仮)は陽イオンの秩序タイプで細分されると思われ、今のところ閃亜鉛鉱型(F-43m)、黄錫鉱型(I-42m)、亜鉛黄錫鉱型(I-42m or I-4)、黄銅鉱型(I-42d)、硫砒銅鉱型(Pmn21)が知られている。しかしまだ未解明の秩序タイプもありそうで、完全には解明されていない。櫻井鉱もまた実は未解明の秩序タイプだったようで、第一文献は黄錫鉱型で解析したが、最近に行われた単結晶構造解析ではいずれとも異なる新しい型になる可能性が報告されている[4]。確立されればそれは櫻井鉱型(P-42m)と呼ばれることになるだろう。また、櫻井鉱の模式標本にはZn > Cuとなる領域が存在することもまた報告されており、これらの研究成果が論文として出版されることが望まれる。
写真は模式地の生野鉱山から産した標本を恵与していただいた。肉眼ではわからないが電子顕微鏡でみると櫻井鉱とペトラック鉱が複雑に混在している。豊羽鉱山やアルゼンチンからも櫻井鉱は見つかっている。
[1] 第一文献
[2] 加藤昭 (1965) 「櫻井鉱」誕生まで. 地学研究,桜井欽一博士紫綬褒章記念号,6-9.
[3] 第二文献
[4] 門馬綱一,宮脇律朗,松原聰,重岡昌子,加藤昭,清水正明,長瀬敏郎 (2015) 櫻井鉱の結晶化学的再検討. 日本鉱物科学会2015年年会講演要旨集,R1-09, p.43.
[5] Kissin S.A., Owens D.R. (1986) The crystallography of sakuraiite. The Canadian Mineralogist, 24, 679-683.
IMA No./year: 1966-009
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M15748(Handbook of Mineralogyから引用)
萬次郎鉱 / Manjiroite
Na(Mn4+7Mn3+)O16
模式地:岩手県軽米町小晴鉱山
第一文献:南部松夫, 谷田勝俊 (1967) 岩手県小晴鉱山産新鉱物萬次郎鉱について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 58, 39-54.
萬次郎鉱は東北大学の南部松夫と谷田勝俊によって発見された新鉱物で、本邦の鉱物学および鉱床学の進歩発展に貢献した東北大学名誉教授の渡邉萬次郎にちなんで命名された[1]。論文は邦文で記載されており「萬」の漢字を使用しているためここではそれに従う。萬次郎鉱の化学組成は当初(Na,K)Mn4+8O16・nH2Oと設定されたが、後にホランド鉱超族の一員に分類され、命名規約が設定された2013年からNa(Mn4+7Mn3+)O16へ改訂されている[2]。萬次郎鉱発見の功績により南部へは櫻井賞(第8号メダル)が授けられた。
渡邉萬次郎(1891-1980)は福島県出身の鉱床学者で、東北大学で教鞭を執った後に秋田大学学長となり、3期10年を勤めた。金属鉱床学が専門の研究者だが火山の研究も行い、随筆、画集、歌集も執筆するなど幅広い分野で活躍している。渡邉萬次郎については島津による紹介文[3]がくわしいほか、自身の著作もある[4]。また日本鉱物科学会は、鉱物学関連分野で卓越した研究業績を有してかつ長年にわたり分野の発展に貢献した人物を表彰するために「渡邊萬次郎賞」を設けている。これは渡邊萬次郎からの寄付金が基金となっている。
南部らは東北地方のマンガン鉱山から採集した多数の二酸化マンガン鉱について、X線回折測定を行っていた。その中でクリプトメレン鉱、K(Mn4+7Mn3+)O16、と同構造を示す50試料について化学組成分析を行ったところ、6産地(岩手県小晴、小玉川、舟小沢、立川、川井、滝ノ沢鉱山)の12試料については「ナトリウム>カリウム」となることが判明する。すなわち、クリプトメレン鉱のナトリウム置換体の新鉱物として萬次郎鉱は承認された。最も端成分に近い小晴鉱山の試料を模式標本として記載論文は記されている[1]。
ホランド鉱超族の結晶構造は筒のようになっており、マンガン(Mn)と酸素(O)がその筒を構成し、萬次郎鉱なら筒の中身にナトリウム(Na)が、クリプトメレン鉱ならカリウム(K)といったぐあいになっている。筒の中身はそれだけでなく二価陽イオンや水(H2O)もまた入りうる。そして最近になって萬次郎鉱を再検討した研究が発表された[5]。萬次郎鉱の模式標本は日本に在るはずだが、その一部が個人や海外にも流出しているようで、その標本が研究に使用されている。そして、その標本はいずれもナトリウムではなく水が最も卓越していた。つまり萬次郎鉱ではないことが明らかとなっている。ただし、この標本が本当は模式標本の一部ではない可能性や、南部らが研究した標本とは異なっている可能性など述べられている。それでも、水が卓越しているとなるとそれは新鉱物に相当する。今後、萬次郎鉱の定義が置き換わるのか、それとも別の新種として申請されることになるかはわからない。
写真はいずれも模式地の小晴鉱山から産した標本となる。上の方は国内の方から恵与していただいたが、下の方はロシアからの出戻り標本である。萬次郎鉱は見た目だけではクリプトメレン鉱と区別が出来ない。分析でいずれもナトリウム>カリウムであることは確認できているが、水は分析できないためそれとの比較はできていない。
[1] 第一文献
[2] Biagioni C., Capalbo C., Pasero M. (2013) Nomenclature tunings in the hollandite supergroup. European Journal of Mineralogy, 25, 85-90.
[3] 島津光夫(2008)渡辺萬次郎-もの書きが好きだった金属鉱床学者. 地球科学, 62, 297-302.
[4] 渡辺萬次郎(著), 菊池ヒサ子(編)(1980) 思い出の記 : 一人の一生
[5] Post J.E., Heaney P.J., Fischer T.B., Ilton E.S. (2022) Manjiroite or hydrous hollandite ?. American Mineralogist, 107, 564-571.
IMA No./year: 1967-009
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M15937; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 135971(Handbook of Mineralogyから引用)
福地鉱 / Fukuchilite
Cu3FeS8
模式地:秋田県鹿角市花輪鉱山
第一文献:Kajiwara Y. (1969) Fukuchilite, Cu3FeS8, a new mineral from the Hanawa mine, Akita Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 5, 399-416.
第二文献:Bayliss P. (1989) Crystal chemistry and crystallography of some minerals within the pyrite group. American Mineralogist 74, 1168-1176.

模式地標本 緑礬(ろうは)に埋もれた一見なんだかよくわからない黒色塊(中央やや左)に福地鉱は含まれる。黄色塊(ほぼ黄鉄鉱)には福地鉱は全く含まれていなかった。
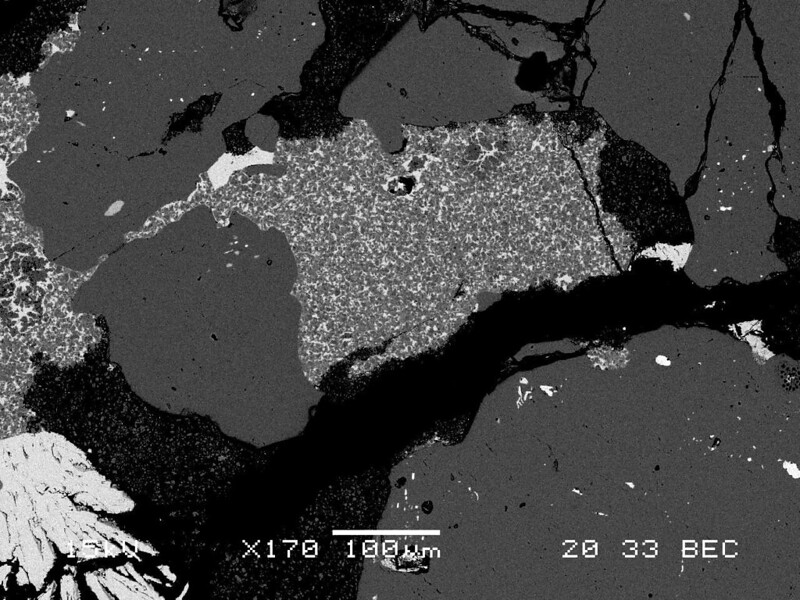
SEM写真1 中央の複雑の組織を示す部分に福地鉱は含まれている。明るい灰色はコベリン。暗い灰色は黄鉄鉱。
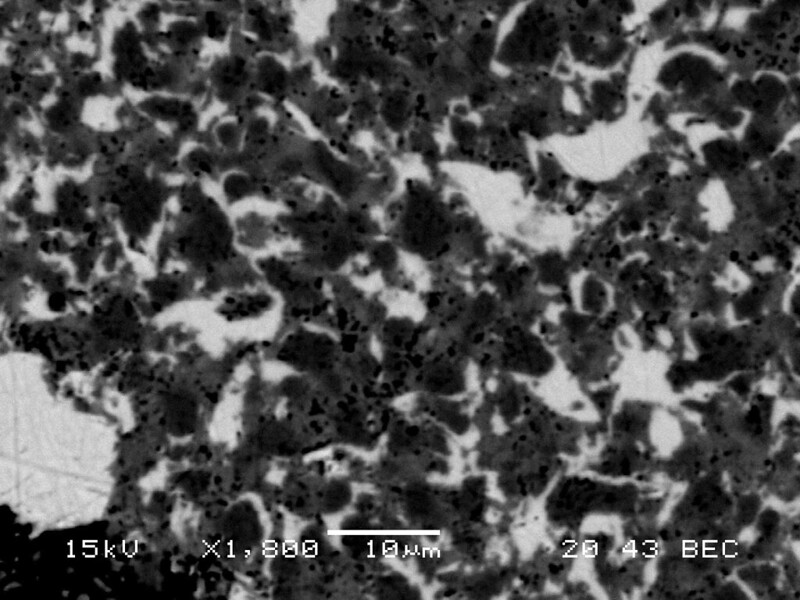
さらに拡大してコントラストを強調したSEM写真。一番明るい灰色はコベリン。最も暗いところは黄鉄鉱。それらの中間色が福地鉱。基本的に数ミクロン程度であるため分析が困難だが、なんとか分析してみるとCu2.96-3.03Fe0.98-1.27S8という化学組成だった。
福地鉱は東京大学の大学院生だった梶原良道によって岩手県花輪鉱山から発見され、鉱物学・地質学者の福地信世に因み命名された。記載論文は梶原が東京教育大学(筑波大学の前身)に就職した後の1969年に出版されている[1]。福地鉱の発見により梶原は櫻井賞(第12号)を受賞した。
福地信世(1877-1934)は東京帝国大学を卒業し大学院に進んだ。古河鉱業に入社し、のちに東京帝国大学の講師となる。神保小虎・滝本鐙三と共にとりまとめた日本鉱物誌第二版は1916年に出版されている。福地は多くの黒鉱型鉱床を研究しその成因について一つの考えを持つに至った。黒鉱型鉱床の起源について交代鉱床という考えの方が主流派だった中で、福地は「黒鉱型鉱床=沈殿鉱床」ということを初めて指摘している(明治37年・1904年)[2]。現代では海底へ噴出した熱水から沈殿した硫化物などが黒鉱型鉱床の起源ということが明らかになっており、福地の考えは正しかった。
福地鉱の発見地である花輪鉱山は秋田県鹿角市と岩手県安代町の県境に位置するが、岩手県側に事務所があった。そのため鉱山の所在地を示す際は一般的には岩手県とされるが、福地鉱が発見された本山鉱床は秋田県側に位置するため、福地鉱の産地は秋田県として記載されている[1]。花輪鉱山は主に黒鉱から構成される明通鉱床群+女平鉱床と、黄鉱から構成される元山鉱床群に区分され、福地鉱の産地である本山鉱床は元山鉱床群に属する[3]。福地鉱は石膏・硬石膏・重晶石が主体の鉱体中に、コベリンや黄鉄鉱に伴われて産出する。
福地鉱は複数の論文で検証が行われている[4-6]。模式地の福地鉱はCalgary大学(カナダ)に渡り、そこでの検証において福地鉱はCuS2-FeS2系の固溶体として報告された。その化学組成は(Cu,Fe)S2とされ[5]、CuS2は福地鉱に先だって知られていたヴィラマニン鉱(Villamanínite)という別の鉱物の端成分となるため、化学組成だけをみると福地鉱とは区別できない。そのため福地鉱は抹消すべきだという提案が新鉱物・命名・分類委員会へ提出されたことがある[6]。しかしながら福地鉱とヴィラマニン鉱が同一であるという十分な証拠が無かったためにその提案は否決され、福地鉱は現在まで日本産の新種として存続している.このような経緯からか記載論文のCu3FeS8が福地鉱の化学組成としてオフィシャルリストに掲載されている。
写真の標本は模式地から得られた標本となる。一枚目には福地鉱を含む塊を掲載した。標本は全体としては緑礬(ろうは)であり、その中に小さな黒色塊と黄色塊が埋もれている。黄色塊は黄鉄鉱ばかりだが、黒色塊には福地鉱が入っている。二枚目に示す黒色塊の断面SEM写真で、中央にある複雑な組織を示す300-400ミクロン程度の粒中に福地鉱が認められる。それ以外ののっぺりとした灰色の部分はコベリンになる。三枚目にさらに拡大したSEM写真を示した。相当わかりにくいと思うが、もっとも明るい灰色部はコベリンで、もっとも暗い部分が黄鉄鉱、そしてそれらの中間的な色合いを示す部分が福地鉱となる。サイズはせいぜい数ミクロンしかないが過去の文献も同様である。中間色の部分を分析するとCu2.96-3.03Fe0.98-1.27S8という化学組成になり、これは梶原の提案する組成:Cu3FeS8とおおむね一致した。
[1] 第一文献
[2] 大橋良一 (1962) 黒鉱型鉱床の形態および成因.鉱山地質, 53, 172-174.
[3] 斎藤憲 (1984) 花輪鉱山. 日本鉱業会誌, 100, 882-887.
[4] Shimazaki H., Clark L.A. (1970) Synthetic FeS2-CuS2 solid solution and fukuchilite-like minerals. The Canadian Mineralogist, 10, 648-664.
[5] Yui S. (1972) Quantitative electron-probe microanalysis of sulphide minerals. In G. Shinoda, K. Kohra, and T. Ichinokawa, Eds. Proceedings, Sixth International Conference on X-ray Optics and Microanalysis, p.749-753. University of Tokyo Press, Tokyo.
[6] 第二文献
IMA No./year: 1967-033
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M16288, National Museum of Natural History; 120635, Washington, D.C., USA(Handbook of Mineralogyから引用)
イットリウム飯盛石 / Iimoriite-(Y)
Y2 (SiO4)(CO3)
模式地:福島県川俣町房又・水晶山
第一文献:Kato A., Nagashima K. (1970) Iimoriite (Y,Ca,Zr)15(Mg,Fe3+,Al)(Si,Al,P)9O34(OH)16. in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 39, 85-86.
第二文献:Hughes J.M., Foord E.E., Jai-Nhuknan J., Bell J.M. (1996) The atomic arrangement of iimoriite-(Y), Y2(SiO4)(CO3). The Canadian Mineralogist, 34, 817-820.
イットリウム飯盛石は国立科学博物館の加藤昭と筑波大学の長島弘三によって見いだされた新種の鉱物で、理化学研究所の飯盛里安(1885-1982)と飯盛武夫(1912-1943)親子にちなみ命名された。飯盛石の発見により、長島弘三は櫻井賞(第11号)を受賞している。
福島県川俣町房又および水晶山にある珪石採石所において巨大なペグマタイト鉱床が発見され、この鉱床から希元素を含む鉱物が数多く産出した。これらは飯盛親子と畑晋によって次々に記載されている[例えば1-3]。飯盛石が見いだされた石英-微斜長石ペグマタイトも房又地域にあり、この地域の希元素鉱物について先に研究業績を上げていた飯盛親子の名前を由来にして、飯盛石は命名された。
飯盛里安はかつて「長手石」という鉱物を記載している[4]。長手石は石川県羽咋市長手島の花崗閃緑岩ペグマタイトから産出した黒色柱状結晶で、リン成分を多く含む褐簾石族の鉱物である。リン成分を多く含む褐簾石は世界でもほとんど例がないのでその詳細が非常に気になるところであるが、戦災で模式標本は消失したために幻の鉱物となっている。
飯盛石の化学組成・格子定数の値は第一文献の発表の後に大きく改訂されている。1975年にアラスカから見つかった飯盛石を用いた研究によって化学組成と格子定数が現在のように改訂され、飯盛石の模式標本もラスカ産飯盛石と同じ化学組成・格子定数であったことが確認されている[6]。第一文献に記されている飯盛石の化学組成および格子定数は誤りであったが、それでも先に発見されているという一点において飯盛石は優先権があった。飯盛石の結晶構造が解明されるのは1996年のことで、アラスカ産の飯盛石が研究に用いられた[7]。
上に掲載した2枚の写真はいずれも水晶山から産出した飯盛石となる。一枚目の写真は飯盛石の集合体で、長石に似た雰囲気となっている。二枚目の写真は飯盛石の結晶で、水晶山に詳しい方から恵与いただいた。飯盛石はピンク色を帯びた透明な結晶として褐簾石の隙間に鎮座している。
[1] Iimori S., Hata S. (1938) Japanese Thorogummite and Its Parent Mineral. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research, 34, 447-454.
[2] Iimori T. (1938) Tengerite found in Iisaka, and Its Chemical Composition. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research, 34, 832-834.
[3] Hata S. (1938) Abukumalite, a new yttrium mineral. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research, 34, 1018-1023.
[4] Iimori S., Yoshimura J., Hata S. (1931) A new radioactive mineral found in Japan. Sci. Papers Inst. Phys. Chem. Research, Tokyo, 15, 83-88.
[5] Fleischer M. (1973) New Mineral Names. American Mineralogist, 58, 139-141.
[6] Foord et al. (1984) New data for iimoriite. American Mineralogist, 69, 196-199.
[7] 第二文献
IMA No./year: 1967(1997s.p.)
IMA Status: A (approved)
模式標本:不明
灰エリオン沸石 / Erionite-Ca
Ca5[Si26Al10O72]·30H2O
模式地:新潟県新潟市間瀬
第一文献:Harada K., Iwamoto S., Kihara K. (1967) Erionite, phillipsite and gonnardite in the amygdales of altered basalt from Mazé, Niigata Prefecture, Japan. American Mineralogist, 52, 1785-1794.
第二文献:Gualtieri A., Artioli G., Passaglia E., Bigi S., Viani A., Hanson J.C. (1998) Crystal structure-crystal chemistry relationships in the zeolites erionite and offretite. American Mineralogist, 83, 590-606.
灰エリオン沸石は秩父自然科学博物館の原田一雄らにより新潟県新潟市間瀬から見いだされた沸石族の鉱物である。発表では日本初産出のエリオン沸石の報告という立ち位置であり、新鉱物として発表されたわけではなかった[1]。その後、1997年に沸石超族の命名規約の変更によってエリオン沸石としては初めてのカルシウム(Ca)タイプということが再認識され、それ以降、間瀬産のエリオン沸石はErionite-Caという新種に昇格した[2]。和名ではカルシウムの和名である「灰」を頭につけて灰エリオン沸石と呼ぶ。エリオン沸石については他にナトリウム(Na)とカリウム(K)に富む種が知られている。
沸石はゼオライト(zeolite)とも表現され、それは「沸騰する石」という意味のギリシア語に基づく。沸石は水(H2O)を含んでおり、加熱するとその水が脱離してまるで沸騰しているように見えることに由来している。今となっては沸石(ゼオライト)は鉱物学的には特定のまとまりを示す名称であり、沸石超族の略称として使用されている。そして沸石は、シリコン(Si)、アルミニウム(Al)、酸素(O)で編まれた籠を組み合わせた構造となっており、シリコン-アルミニウム置換による電荷不足を中和するように陽イオンを籠の中に取り込む。鉱物分類としては、まず骨格構造によって系列(シリーズ)が分けられ、その次に陽イオンによって個別の種が確定する。カゴの中には水も含まれるが、それは鉱物種の分類には使われない。エリオン沸石の骨格は国際ゼオライト学会により「ERI」と名付けられ、優れた陽イオン交換性を有する特徴がある[3]。ただし、その結晶は鋭く尖って砕ける特徴があるために、吸引による発がん性があることが指摘されている。
エリオン沸石の歴史を振り返ってみよう。1898年にアメリカオレゴン州のDurkee Fire Opal鉱山から羊の毛のような集合体の鉱物が発見され、ギリシャ語で羊毛を意味する「εριον」にちなんでエリオン沸石(Erionite)と命名された[4]。そのエリオン沸石はナトリウム(Na)タイプであったので、沸石超族の命名規約でこれがソーダエリオン沸石(Erionite-Na)とされる。続いて1964年にアメリカオレゴン州のRomeから報告されていたエリオン沸石[5]がカリウム(K)タイプだったので、これを元にカリエリオン沸石(Erionite-K)も確立される。カルシウム(Ca)タイプはエリオン沸石の中で最も新しく、1967年に原田らが報告した新潟県間瀬のエリオン沸石が灰エリオン沸石(Erionite-Ca)という新種に再分類された。また、最初のエリオン沸石の産地、アメリカオレゴン州のDurkee Fire Opal鉱山からもカルシウムタイプが発見されている。
写真は模式地と福島県霊山町の灰エリオン沸石になる。模式地の標本には累帯構造があり、分析箇所によって灰エリオン沸石、ソーダエリオン沸石、カリエリオン沸石のいずれも出てくる。根元のほうに灰エリオン沸石が多い傾向が見られた。一方の霊山町の標本については累帯構造がなく、全体が灰エリオン沸石になる。
[1] 第一文献
[2] Coombs D.S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J.D., Liebau F., Mandarino J.A., Minato H., Nickel E.H., Passaglia E., Peacor D.R., Quartieri S., Rinaldi .R, Ross M., Sheppard R.A., Tillmanns E., Vezzalini G., (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names, The Canadian Mineralogist, 35, 1571-1606.
[3] 第二文献
[4] Eakle A.S. (1898) Erionite, a new zeolite, American Journal of Science, 156, 66-68.
[5] Eberly P.E. (1964) Absorption properties of naturally occurring erionite and its cationic-exchanged forms. American Mineralogist, 49, 30-40.
IMA No./year: 1968-004a
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M16183, National School of Mines, Paris, France; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 121005 (Handbook of Mineralogyから引用)
褐錫鉱 / Stannoidite
Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12
模式地:岡山県美作市金生鉱山
第一文献:Kato A. (1969) Stannoidite, Cu5(Fe,Zn)2SnS8, a new stannite-like mineral from the Konjo mine, Okayama Prefecture, Japan. Bulletin National Science Museum, Tokyo, 12, 165-172.
第二文献:Kudoh Y., Takéuchi Y. (1976) The superstructure of stannoidite. Zeitschrift für Kristallographie, 144, 145-160.
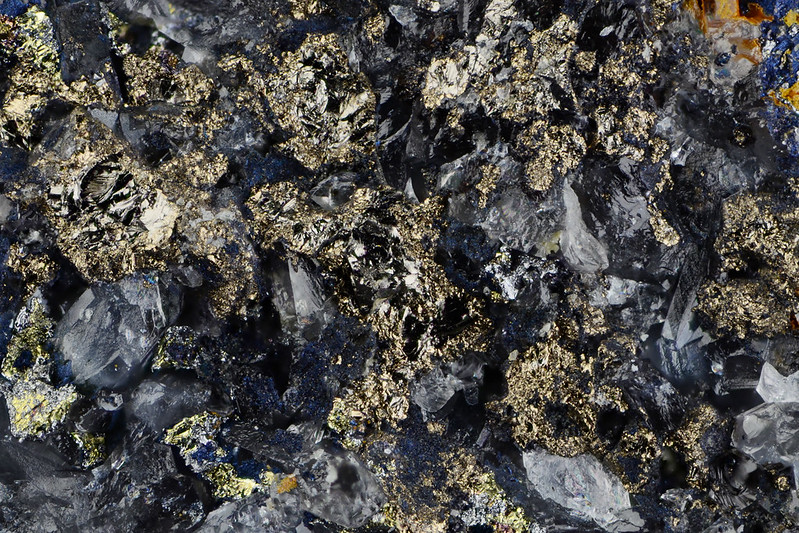
上の標本の拡大写真。
中央の大きめの割れ口を見せる褐錫鉱を金色が強めモースン鉱が取り囲む。
褐錫鉱は国立科学博物館の加藤昭によって見いだされた新鉱物で、黄錫鉱(Stannite)と物理・化学的性質が似ていることから、「類似」を表すギリシア語「eidos」(もしくはラテン語「oïda」)を併せてStannoiditeと命名された。その独特な色と化学成分から和名では褐錫鉱と呼ぶ。読みは「かっしゃくこう」である。
加藤が著した原著論文には発見の経緯が記されている[1]。それ補足する形で褐錫鉱が承認されるまでの流れを追ってみたい。まず黄錫鉱という鉱物があり、それはそうとう以前から知られていた。そして研究者らが黄錫鉱を調べている中で黄錫鉱としては異常な光学性をもつ鉱物が見いだされていくようになる。それらは「Isostannite」や「Zinnkies?」などと呼ばれていたが、1960年に「Hexastannite」と呼ばれるようになる[2]。その一方でそれは新鉱物とするにはデータが不足しており、詳細なデータがそろうまで名前だけの存在であった[3]。そして日本からもこのHexastanniteが各地の鉱山から報告されるようになっていくが、微細なため光学的性質からの同定にとどまっていた[4-6]。
そのような状況であったが、単結晶X線回折にも使える大きなHexastanniteが岡山県金生(こんじょう)鉱山から見いだされた。加藤はこのHexastanniteからデータを集め、国際鉱物学連合の新鉱物・命名・分類委員会は加藤に対して新しい名前を付けることを許可し、褐錫鉱(Stannoidite)が生まれることになった。一方で、Hexastanniteは模式標本の研究が完了するまでその名前を残すことになった。後の研究でHexastanniteは褐錫鉱と同じ鉱物であることが判明したとされるが、その具体的な文献を見つけることができなかった。国産のHexastanniteについては再検証が行われており、いずれも褐錫鉱であることが判明している[7]。また褐錫鉱の化学組成は当初はCu5(Fe,Zn)2SnS8と報告されたが、後の単結晶X線解析によってCu8(Fe,Zn)3Sn2S12へ改められた[8]。
写真はいくつかの産地からの標本となる。記載論文は褐錫鉱の独特の色を「blass brown」と表現した。粒子が大きいと褐色が強く出るためそういった標本は肉眼でも鑑定は容易だが、微細な場合はほぼ黒一色となり、見た目での鑑定が不可能になる。しばしば結晶の周囲がモースン鉱(Mawsonite: Cu6Fe2SnS8)で取り囲まれる。
[1] 第一文献
[2] Ramdohr P. (1960) Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen, 3rd Ed. P514-515.
[3] Fleischer M. (1961) New Mineral Names, American Mineralogist, 46, 1204.
[4] Nakamura T. (1961) Mineralization and wall-rock alteration at the Ashio copper mine, Japan. Jounal Institute Polytechnics, Osaka City University, ser.G., v.5, 53-127.
[5] 清水照夫, 加藤昭, 松尾源一郎 (1966) 京都府富国鉱山産の鉱物 特にコサラ鉱・ブーランジェ鉱・六方黄錫鉱・次成砒素鉱物について. 地学研究, 17, 201-209.
[6] 今井秀喜, 藤木良規, 塚越重明 (1967) 近畿地方西部の中生代後期ないし新生代初期鉱床生成区. 鉱山地質, 17, 50 (第17回学術講演要旨).
[7] Kato A. and Fujiki Y. (1969) The occurrence of stannoidites from the xenothermal ore deposits of the Akenobe, Ikuno, and Tada mines, Hyogo Prefecture, and the Fukoku mine, Kyoto Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 5, 417-433.
[8] 第二文献
IMA No./year: 1968-014
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 M16403, National School of Mines, Paris, France; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 121926, 160136 (Handbook of Mineralogyから引用)
河津鉱 / Kawazulite
Bi2Te2Se
模式地:静岡県下田市河津鉱山
第一文献: Kato A (1970) Kawazulite Bi2Te2Se, in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 39, 87-88.
第二文献:Miller R (1981) Kawazulite Bi2Te2Se, related bismuth minerals and selenian covellite from the Northwest Territories. The Canadian Mineralogist, 19, 341-348.
河津鉱は国立科学博物館の加藤昭によって記載された新鉱物で、発見地である河津鉱山から名付けられた。1969年の鉱物学会で河津鉱が発表され[1]、1970年に地質調査所から発行されたIntroduction to Japanese Mineralsでも紹介されいるものの[2]、現在までに正規の記載論文は出版されていない。また、タイプ標本は櫻井欽一の標本であることが知られる[3]。その当時、河津鉱の確実な標本は櫻井標本の一個体だけだった[4]。
河津鉱山は安山岩質岩を母岩とした中温の熱水鉱床で金を伴う。いくつかの鉱脈と支山が知られ、南西側にある大沢樋と檜沢樋では黄鉄鉱化作用を伴ったテルルに富む鉱脈を採掘していた。そのため櫻井標本の河津鉱は大沢樋もしくは檜沢樋のどちらかから産出したものと推測されるが、文献にはその詳細が書かれていない。またこれらの樋も実際は大沢樋○号坑といった様にさらに細分化されており、その何号坑かで産出鉱物組み合わせが変わってくる。そのため自分の標本ならば樋や坑といった詳細な産地もラベルに記載したい。
海外では1981年にカナダ、ノースウエスト準州にある小規模なウラン(U)-銅(Cu)鉱床から河津鉱が見いだされている[5]。その後、アメリカやロシア、日本でも寿都鉱山[6]から産出が知られるようになったが、稀少鉱物であり資源として利用もないことから、河津鉱は愛石家の間だけで主に認識される鉱物であろう。一方で物質としてのBi2Te2Seは鉱物の河津鉱より先に合成物で知られており[7]、こちらは今現在の物理業界では大変有名となっている。2016年のノーベル物理学賞を受賞した研究者によって理論的に予想されていた「トポロジカル絶縁体」、それを体現する物質の一つがBi2Te2Seであり、それは河津鉱の端成分。河津鉱は天然に生じるトポロジカル絶縁体と呼ばれた[8]。
上の写真は河津鉱山大沢樋2号坑から得られた河津鉱の標本となる。銀白色の非常に薄い板という典型的な惨状となっている。この標本は分析を行い河津鉱であることを確認してあるが、全く同様の産状で硫テルル蒼鉛鉱(Tetradymite) (Bi2Te2S)やパラグアナジュアト鉱 (Paraguanajuatite) (Bi2Se3)が産出する。また、一枚の板が河津鉱+ボーダノウィッチ鉱(Bohdanowiczite) (AgBiSe2)で構成されていることもあった。率直な感想では肉眼での鑑定はほとんど不可能に近いと思える。また下の写真は合成した河津鉱の結晶になる。天然では見かけることのない河津鉱の結晶だが、合成するのは容易である。
[1] 加藤昭 (1969) 新鉱物河津鉱(Kawazulite)Bi2Te2Se. 日本鉱物学会年会講演予講集, P33.
[2] Kato A. (1970) Kawazulite Bi2Te2S, in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 39, 87-88.
[3] Fleischer M. (1972) New mineral names. American Mineralogist, 57, 1311-1317.
[4] 加藤昭 (1973) 櫻井鉱物標本, 櫻井欽一博士還暦記念事業会, pp.177.
[5] Miller R. (1981) Kawazulite Bi2Te2Se, related bismuth minerals and selenian covellite from the Northwest Territories. The Canadian Mineralogist, 19, 341-348.
[6] Shimizu M., Schmidt S.T., Stanley C.J., Tsunoda K.(1995) Kawazulite and unnamed Bi3(Te, Se, S)4in Ag-Bi-Te-Se-S mineralization from the Suttsu mine, Hokkaido, Japan. Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, 169, 305–308.
[7] Nakajima S. (1963) The crystal structure of Bi2Te3-xSex. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 24, 479-485.
[8] Gehring P., Benia H.M., Weng Y., Dinnebier R., Ast, C.R., Burghard M., Kern K. (2013) A Natural Topological Insulator. Nano Letters, 13, 1179-1184.
IMA No./year: 1968-028(2012s.p.)
IMA Status: Rd (redefined)
模式標本:東北大学 (Handbook of Mineralogyから引用) → 産総研地質標本館GSJ M28255, GSJ M28842(坂野氏調べ)
神津閃石 / Mangano-ferri-eckermannite (原記載はKozulite)
NaNa2(Mn2+4Fe3+)Si8O22(OH)2
模式地:岩手県田野畑村田野畑鉱山松前沢鉱床
第一文献:南部松夫, 谷田勝俊, 北村強 (1969) 岩手県田野畑鉱山産新鉱物神津閃石について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 62, 311-328.
第二文献:Barkley M.C., Yang H., Downs R.T. (2010) Kôzulite, an Mn-rich alkali amphibole. Acta Crystallographica. E66, i83.

模式地標本 愛石家ほど受け入れられないかもしれないが、分析してみるとこれが神津閃石だった。神津閃石は含マンガンエッケルマン閃石と組成的に連続するので、見た目も基本的に同じ。
神津閃石は東北大学の南部松夫らによって岩手県田野畑鉱山から見いだされた新種の角閃石で、鉱物名は東北大学で岩石鉱物鉱床学教室を設立した鉱物学者・岩石学者の神津俶祐(こうづしゅくすけ)(1880-1955)にちなむ。南部は神津閃石の発見により櫻井賞第8号メダルを受賞した。
神津閃石は角閃石超族の一員である。角閃石超族はAB2C5T8O22W1-2を一般式としており、Oを除くアルファベットの部分に様々な元素が多様な置換様式で入る。その多様性により角閃石超族を構成する種は100を軽く越えており、時代を経るごとに一定の規約で種を分別することが困難になってきている。そのため角閃石の命名規約はこれまでに何度も改訂されており、現時点は2012年のものが最新である[1]。一方でこの命名規約は一律的では無い。多くの例外をもうけており、その内容は大変ややこしくなっている。いずれにしても角閃石の論文を読む際はいつの命名規約の時に書かれたものかを意識する必要がある。
神津閃石に関して言うとこれまでは神津閃石(Kozulite)という名称であったものが、2012年の改訂で化学組成の定義はそのままに名前が変更されてしまった。そのためIMA StatusはRd(redefined)となっている。この命名規約の肝を簡潔に記すと「マグネシウム(Mg)とアルミニウム(Al)を主成分とする種についてのみ根源名を認める」である。つまりマグネシウムとアルミニウムを主成分とするエッケルマン閃石からみて、神津閃石はマンガン(Mn2+)と三価鉄(Fe3+)を置換した内容となる。そして、マンガン優位を意味する「マンガノ(mangano)」と三価鉄優位を意味する「フェリ(ferri)」が根源名:エッケルマン閃石(eckermannite)の接頭語となり、結果、マンガノフェリエッケルマン閃石(Mangano-ferri-eckermannite)が現時点での正式な学名となっている。ただし日本では慣例的に和名で記すので、そこで神津閃石とすることには問題は無い。
南部らは神津閃石の産状や化学組成、X線回折パターンなど新鉱物記載には十分な鉱物学的情報を記載したが[2]、結晶構造の解析までは行っていない。2010年になり神津閃石の結晶構造解析を行ったという論文が出版されたが[3]、内容を見たら神津閃石ではなかった。この論文中で使用された結晶の化学組成の特徴をまとめるとMg > Mn2+およびFe3+ > Alであるため、これはマグネシオアルベソン閃石(Magnesio-arfvedsonite)である。田野畑産の試料を使ったことは確かなようであるが、いずれにしても客観的事実として神津閃石の結晶構造解析はいまだ行われていないことになる。
神津閃石はブラウン鉱・バラ輝石・石英などを伴い、肉眼的に帯赤黒色ないし黒色を示すことが第一文献に記されている。実際にこういったいわゆる神津閃石の標本は田野畑鉱山で多くみかける。ところがそれらを分析してみるとことごとくが神津閃石ではなかった。一方で、神津閃石は写真のようなオレンジ色の結晶の中から見つかる。このような結晶の多くは含マンガンマグネシオアルベソン閃石であるが、そこからほんのちょっと二価マンガンが増えれば神津閃石である。つまり含マンガンマグネシオアルベソン閃石と神津閃石は外観が共通し、見た目で分けることはできない。むしろ赤々黒々というのはなんらかの極端な変化が生じた結果の、まったくの別種になる。ただし、それも一筋縄ではいかず、なかなか難しい。
[1] Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist, 97, 2031-2048
[2] 第一文献
[3] 第二文献

模式地標本 一般にこうったものが神津閃石の標本とされていたが、調べた範囲では神津閃石ではないことだけは確実。一方でこういった標本は中身が複雑で鉱物種を特定することが非常に困難。とりあえずアルカリ角閃石としてラベルを書くほかない。
IMA No./year: 1968-030
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (Handbook of Mineralogyから引用)
阿仁鉱 / Anilite
Cu7S4
模式地:秋田県北秋田市阿仁鉱山(旧:阿仁町)
第一文献: Morimoto N., Koto K., Shimazaki Y. (1969) Anilite, Cu7S4, a new mineral. American Mineralogist, 54, 1256-1269.
第二文献:Koto K., Nobuo M. (1970) The crystal structure of anilite. Acta Crystallographica, B26, 915-924.
阿仁鉱は大阪大学の森本信男らによって見いだされた新鉱物で、模式地にちなんで命名された。森本は阿仁鉱の発見により櫻井賞第18号メダルを受賞している。
森本は阿仁鉱山からデュルレ鉱(Djurleite: Cu31S16)も見いだしており、これもかつて国産新鉱物と言われた。しかしそれはちょっと違う。日本産のデュルレ鉱の記載は本家の記載論文に先立って行われたための誤解であって、実際にはメキシコから先に見つかって命名されている[1,2]。それでも発見そのものはほぼ同時期だったこともまた誤解の原因であろう。デュルレ鉱はウプサラ大学の教授であったSeved Djurle(1928-2000)にちなんで命名され、阿仁鉱山においては阿仁鉱山と共通する外観のため、見た目で区別することができない。
阿仁鉱とデュルレ鉱は銅-硫黄(Cu-S)成分系の鉱物で、似たような化学組成で輝銅鉱(Chalcocite: Cu2S)と方輝銅鉱(Digenite: Cu1.8S)も知られる。これらをCuxSとして表すと、x=2が輝銅鉱、x=1.94がデュルレ鉱、x=1.8が方輝銅鉱となる。阿仁鉱はx=1.75である。一方でこれらが全部共存することはなく、生成の温度によって組み合わせが異なる。阿仁鉱はデュルレ鉱と共存することが多い[3]。ざっくり示すと、低温では阿仁鉱やデュルレ鉱が出現し、高温では輝銅鉱や方輝銅鉱が安定となる。
阿仁鉱の安定領域(とくに温度)は非常に狭い[4]。阿仁鉱は70℃以上でコベリンと方輝銅鉱へ分解してしまう。瞬間的に発生するような熱や衝撃にも非常に弱く、例えば分析用の薄片を作る際の研磨や、粉末X線回折のための乳鉢でのすりつぶしでもあっさり分解してしまう。それゆえに阿仁鉱は存在していたとしても方輝銅鉱として誤って認識されていた可能性がある。今となっては液体窒素で冷やしながら試料を加工することで阿仁鉱の粉末X線パーターンが取得できることが判明しており、多くの産地から阿仁鉱の産出が報告されている。
阿仁鉱山は元は金鉱山として開発されたが、次第に銀・銅が主な鉱石となり、享保年間には産銅日本一となったことが知られる。幾度かの休山をはさみ昭和の時代まで操業していた。写真の標本は阿仁鉱山から産出した結晶標本となる。一見では単結晶にみえる標本であっても、そのほとんどは阿仁鉱+デュルレ鉱の混合であることが知られている[3]。この標本もおそらくはそうであろう。阿仁鉱とデュルレ鉱の結晶構造では硫黄の配列がわりと似ており、その硫黄が並ぶ面を介してエピタキシャル関係が成立しやすい[3, 5]。
[1] Roseboom E.H. (1962) Djurleite, Cu1.96S, a new mineral. American Mineralogist, 47, 1181-1184.
[2] Morimoto N (1962) Djurleite, a new copper sulphide mineral. Mineralogical Journal, 3, 338-344.
[3] 第一文献
[4] Morimoto N., Koto K. (1970) Phase relations of the Cu-S system at low temperatures: stability of anilite. American Mineralogist, 55, 106-117.
[5] 第二文献
IMA No./year: 1969-024
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 MA5635; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, C252, 98012, 94600(Handbook of Mineralogyから引用)
若林鉱 / Wakabayashilite
(As,Sb)6As4S14
模式地:群馬県下仁田町西ノ牧鉱山
第一文献: Kato A., Sakurai K., Ohsumi K. (1970) Wakabayashilite (As,Sb)11S18, in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 39, 92-93.
第二文献: Bindi L, Bonazzi P, Zoppi M, Spry P G (2014) Chemical variability in wakabayashilite: a real feature or an analytical artifact?. Mineralogical Magazine, 78, 693-702.
若林鉱は国立科学博物館の加藤昭らによって群馬県西ノ牧鉱山から発見され、若林弥一郎にちなみ命名された。模式地の若林鉱について記載論文はこれまで出版されておらず、Introduction to Japanese Mineralsにおいてその概略が報告されるにとどまっている[1]。また若林鉱の二番目の産地としてアメリカのWhite Cap鉱山も同時に記されている[1]。
若林弥一郎(1874-1943)は東京帝国大学を卒業し、三菱鉱業の鉱山技師として奉職した。若林は鉱物収集家としても有名で、後に若林標本と呼ばれる鉱物コレクションを遺す。若林標本は東京大学総合博物館に寄贈され、東大出版会から型録が出版されている[2]。若林標本について実質的な標本管理を行った豊遙秋によって、「雄黄」とラベルがついた西ノ牧鉱山産の標本に若林鉱が伴われていることが見いだされた。また若林標本は古くから研究に使用されて、その成果はBirträge zur Mineralogie von Japan[3]や日本鉱物誌第三版[4]にも収録されている。
西ノ牧鉱山は昭和20年代から採掘された鉱山で、安山岩中の石英脈に伴われる鶏冠石(Realgar)や雄黄(Opiment)を鉱石としていた。いずれも砒素(As)と硫黄(S)からなる鉱物で、鶏冠石は華々しく目立つ赤色を特徴としている。雄黄もその名が示すように黄色を呈する鉱物で、通常は塊状や箔状で産出するが、西ノ牧鉱山では針状の産状が知られていた。実際はこれが若林鉱であったが、以前は深く調べられることもなく「針状雄黄」という名前で標本が流通していた。
記載論文が出版されていないためこの針状雄黄が調べられた経緯は定かではないが、加藤らの研究によってこの針状雄黄は新種であることが判明し、若林鉱と命名されて1969年に新鉱物としての承認を受けている[1]。一方で若林鉱の化学組成と結晶構造については検証が続けられ、まだ結論がついていない。2005年に化学組成と結晶構造が更新されているが[5]、最新の研究結果では若林鉱の結晶構造はAs4S5分子群のみで構成されている可能性が示唆されている[6]。
写真の標本は模式地からの標本となる。石英の晶洞には赤い鶏冠石と黄色塊状の雄黄に針状の若林鉱が伴われる。若林鉱は群馬県から発見された最初の新鉱物である。そして群馬県産の新鉱物はこれ以降も人名にちなむ例が続くことになる。
[1] 第一文献
[2] Sadanaga R., Bunno M. (1974) The Wakabayashi Mineral Collection. The University Museum, The University of Tokyo, University of Tokyo Press, pp.177.
[3] Ito T. (1937) Birträge zur Mineralogie von Japan (II). 鉱物會, pp.168.
[4] 伊藤貞一, 櫻井欽一 (1947) 日本鉱物誌第三版 上巻, 中文館書店, pp.568.
[5] Bonazzi P., Lampronti G.I., Bindi L., Zandari S. (2005) Wakabayashilite, [(As,Sb)6S9][As4S5]: crystal structure, psuedosymmetry, twinning, and revised chemical formula. American Mineralogist, 90, 1108-1114.
[6] 第二文献
総評_1970s
1970年代に見出された日本産新鉱物のうち、25種をここに掲載している。そのうちルテニイリドスミン、ソーダレビ沸石、灰単斜プチロル沸石、奴奈川石は新鉱物として申請された経緯を持たず、後世の命名規約の成立によって新鉱物に昇格した。また中宇利石についてはほぼ確実に化学組成が間違っている。格子定数すら危うい。しかしこれは情報の更新が必要であっても抹消にはならないと思われる。発見の優先権はそれほど強い。欽一石については記載された模式標本がゼーマン石であるということが判明し、ともすれば抹消される危機であったが、同時に欽一石の定義がすり替わったこともあって日本産新鉱物として生き残っている。こちらは模式標本の更新が必要になるだろう。
一方で、一旦承認されながらも後に日本産という立場が消えた鉱物が水酸エレスタド石である。それは先行研究の取り扱いにミスがあったが、審査の段階では誰も気づかず、後に命名規約を作る際の洗い直しで誤りを指摘された。結果的に水酸エレスタド石の模式地はアメリカに再設定されることになった。また一旦承認されながらも後に定まった分類ルールや命名規約によって独立種から亜種へ格下げとなった鉱物として、磐城鉱がある。そのほか、オフィシャルリストには日本産として掲載があるものの、その理由が釈然としない鉱物としてブセル石と苦土ジュルゴルド石が挙げられる。ブセル石は承認された経緯すら怪しく、苦土ジュルゴルド石については名前だけ先に設定された架空の存在にすぎない。これらが日本産新鉱物と登録されている学術的・論理的な事由を導くことはできす、オフィシャルリストが誤っているとしか断じ得ない。水酸エレスタド石、磐城鉱、ブセル石、苦土ジュルゴルド石については「日本から発見された新鉱物たち(その他)」に分類することが妥当だと判断する。
研究上の特徴としての1970年代は、電子線プローブマイクロアナライザー(EPMA)の登場が挙げられる。これは鏡面研磨された鉱物に細く絞った電子線を当て、そこから放射される特性X線から化学組成を得る技術である。その特性X線をエネルギーとして分光する手法をEDSやEDXと呼び、波長で分光することをWDSやWDXと呼ぶ。WDS(WDX)やEDS(EDX)は広義のEPMAであるが、EPMAとWDS(WDX)は同義で使用され、EDS(EDX)とは分けて呼ぶことがこの年代からすでに一般化されつつあった。いずれにしても(広義の)EPMAはこれまでたいへんに困難であった鉱物の化学組成分析を大幅に簡易化した。また導入された直後はその信頼性に疑義を持つ人は少なくなかったが、1970年代後半までには信頼性が確立されて多くの研究に採り入れられている。とりわけWDS(WDX)については現代でもその機構は全く変わっておらず、もともとかなり完成された手法だったと言える。そして(広義の)EPMAはこれまで主流だった湿式分析法を完全に駆逐してしまうことになる。
世界規模でみると(広義の)EPMAの登場によって鉱物種の数は飛躍的に増加したことは間違いない。しかし、日本においてはそんなこともない。1970年代は25種あるが、続く1980年代は19種、1990年代に至っては16種と、むしろ減っていく。これには鉱山の閉山などの側面もあるが、(広義の)EPMAの登場と発展によって研究面での幅が広がり、新鉱物の記載がむしろ鉱物学研究の主流から逸れていく過程が反映されていると認識している。それはともかくも、1970年代は平均すれば年に2個以上の新鉱物が発見されるという時代で、日本新産鉱物も次々に見つかっていた。鉱物記載を中心に据える研究者も多かった。また、産地はまだまだ荒廃しておらず、その頃から活躍していた古老の体験談は瑞々しさにあふれている。1970年代は愛石家にとっても楽しい時代だったようだ。
IMA No./year: 1970-034
IMA Status: A (approved)
模式標本:東北大学(Handbook of Mineralogyから引用)(現在は産総研地質標本館に存在すると推測される)
高根鉱 / Takanelite
(Mn2+,Ca)2xMn4+1-xO2·0.7H2O
模式地:愛媛県西予市野村鉱山(旧:野村村)
第一文献: 南部松夫, 谷田勝俊 (1971) 新鉱物高根鉱について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 65, 1-15.
第二文献: Kim S.J. (1991) New characterization of takanelite. American Mineralogist, 76, 1426-1430.
高根鉱は東北大学の南部松夫と谷田勝俊によって愛媛県野村鉱山から発見された新鉱物で、X線結晶学の進歩発展に貢献した東北大学の高根勝利(1899-1945)にちなんで命名された。当初は東北大学に模式標本が保管されていたようだが、南部の標本は地質調査所(現・産総研地質標本館)へ移管されているので[1]、現在は地質標本館に保管されているものと思われる。
高根鉱はランシー鉱(Ranciéite: (Ca,Mn2+)0.2(Mn4+,Mn3+)O2·0.6H2O)からみてカルシウム(Ca)を二価マンガン(Mn2+)へ置換した鉱物として発表された[2]。南部らは本邦におけるランシー鉱の分布を調査し、その二価マンガン置換体の存在を予想して研究に臨んだことが第一文献に記してある。そして愛媛県野村鉱山から南部が予想していた二価マンガン置換体が見いだされた。高根鉱は1967年8月に採集され、3年後の1970年に新鉱物の承認が与えられている。
愛媛県には「野村」の名を冠する鉱山が私の知るところで3カ所ある。一つはドロマイト鉱床で、旧・野村町伊勢井谷にあった。もう一つが旧・野村町植木にある野村鉱山で、キースラーガ鉱床の銅を主に採掘していた。ここの鉱石は金にも富み、鉱石1トンあたりに最大で29グラムの金が含まれたという[3]。高根鉱を産した野村鉱山は同じく旧・野村町植木にあり、キースラーガ鉱床のやや南に位置する。ここはいわゆるマンガン山で、二酸化マンガンが主な鉱石となっている。南部らが訪れた際は丸野鉱床と東官山鉱床が採掘されていた。高根鉱は丸野鉱床の最下部10号坑で見いだされている。
高根鉱は単独で産出することはなく、必ず2種類以上の鉱物が密雑して共生することが知られる。第一文献によると共生鉱物は、クリプトメレン鉱(Cryptomelane: K(Mn4+7Mn3+)O16)、軟マンガン鉱(Pyrolusite: MnO2)、エンスート鉱(Nsutite: Mn2+xMn4+1-xO2-2x(OH)2x)、バーネス鉱(Birnessite: (Na,Ca,K)0.6(Mn4+,Mn3+)2O4·1.5H2O)、および轟石(Todorokite: (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O)とされる。いずれも(含水)マンガン酸化物であり、標本の外観上の特徴と構成鉱物の一義的な対応は困難である。高根鉱の分離は試みられてものの、どうしても少量の不純物は残ってしまう。
不純物の存在と結晶性の低さに起因して、高根鉱の化学組成および結晶構造は完全には解明されてない。記載論文は含水量に関して問題点が残っていることに言及し、またX線回折線について韓国産の高根鉱を用いた研究で指数の割り振りが更新されている[4]。一方でランシー鉱については化学組成と結晶構造は決まっており[5]、高根鉱についてもその解明が期待される。
高根鉱の標本は二つ所有しており見た目は同じである。X線回折で確認してみると、ひとつは高根鉱と軟マンガン鉱が検出され、もうひとつの標本は高根鉱とエンスート鉱の共生であった。写真は軟マンガン鉱と共生している高根鉱の標本となる。
[1] 坂巻幸雄 (1988) 南部鉱石標本-山岡標本、筑波へ. 地質ニュース, 410, 9-10.
[2] 第一文献
[3] 愛媛県の金銀鉱資源. 愛媛県地下資源資料, 10, 11-24.
[4] 第二文献
[5] Ertl A., Pertlik F., Prem M., Post J.E., Kim S.J., Brandstatter F., Schuster R. (2005) Ranciéite crystals from Friesach, Carinthia, Austria. European Journal of Mineralogy, 17, 163-172.
IMA No./year: 1971-032
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館M18829(Handbook of Mineralogyから引用)
南部石 / Nambulite
LiMn2+4Si5O14(OH)
模式地:岩手県洋野町舟子沢鉱山
第一文献: Yoshii M., Aoki Y., Maeda K. (1972) Nambulite, a new lithium- and sodium-bearing manganese silicate from the Funakozawa mine, northeastern Japan. Mineralogical Journal, 7, 29-44
第二文献: Nagashima M, Armbruster T, Kolitsch U, Pettke T (2014) The relation between Li ↔ Na substitution and hydrogen bonding in five-periodic single-chain silicates nambulite and marsturite: A single-crystal X-ray study. American Mineralogist, 99, 1462-1470.
南部石は地質調査所の吉井守正らによって記載された新鉱物で、東北大学教授の南部松夫にちなみ命名された。最初の標本は岩手県舟子沢鉱山の鉱山長だった大倉嘉造によって採集されている。その鑑定が地質調査所の吉井に依頼された流れとなる。当初はバラ輝石と考えられていたが、その後の詳しい調査によってリチウム(Li)を含む新鉱物であることが判明する。吉井は南部石の発見により櫻井賞(第10号メダル)を受賞している。
南部松夫(1917-2009)は東北帝国大学岩石鉱物鉱床教室を卒業し、同大学の選鉱精錬研究所に退職まで勤めた。南部は多くの金属鉱床について研究を行い、その研究の過程で日本産新鉱物の赤金鉱、萬次郎鉱、神津閃石、高根鉱、上国石について筆頭で研究をまとめている。また東北地方の鉱物誌や鉱床誌を執筆し、収集された標本は南部標本として地質標本館などに寄贈された[2-4]。
吉井らが報告した南部石にはリチウム(Li)とナトリウム(Na)が含まれ、わずかにリチウムが多いものの、その量比はLi : Na = 1.00 : 0.98とほとんど等しかった[1]。そのため南部石として最初に提案された化学組成式はLiNaMn8Si10O28(OH)2であった。ところがこの化学組成はいきなり疑問が投げかけられる。南部石の記載論文の次ページから始まる当時ハーバード大学にいた伊藤順の論文では、合成実験の結果に基づくと南部石の化学組成式はLiMn4Si5O14(OH)となるべきだと書かれている[5]。そして大阪大学の成田らによって南部石の単結晶解析が行われ、伊藤から提案されていた化学式が正しいことが確認された[6]。この研究に使用された試料は舟子沢産の南部石である。また後にリチウム-ナトリウム置換に伴う水素結合様式の変化も報告されている[7]。
記載論文によると舟小沢鉱山で見つかった南部石の結晶は8ミリの柱状結晶でオレンジ色を帯びた赤褐色とされるが、今となってはそのような立派な標本は望めない。舟子沢のズリで得られる南部石は色も赤褐色ではなくオレンジ色が強い小さな断片程度である。世界石には稀であるが日本では近隣の鉱山や栃木県でも産出があるように、割と産地は多い。その多くはオレンジ色の塊として得られる。福島県御斎所鉱山では方解石に埋没した結晶が産出し、塩酸処理することで美しい結晶標本となる。ナミビアのKombat鉱山から産出した南部石の結晶は宝石用にカットされたことがある[8]。
[1] 第一文献
[2] 坂巻幸雄 (1988) 南部鉱石標本-山岡標本、筑波へ. 地質ニュース, 410, 9-10.
[3] 南部松夫 (1969) 福島県鉱物誌. 福島県企画開発部開発課, pp.265.
[4] 南部松夫 (1972) 宮城県鉱物誌. 宮城県商工労働部中小企業課, pp.141.
[5] Ito J. (1972) Synthesis and crystal chemistry of Li-hysro-pyroxenoids. Mineralogical Journal, 7, 45-65.
[6] Narita H., Koto K., Morimoto N., Yoshii M. (1975) The crystal structure of nambulite (Li,Na)Mn4Si5O14(OH). Acta Crystallographica, B31, 2422-2426.
[7] 第二文献
[8] 砂川一郎 (1982) 南部石と杉石 日本で新鉱物として発見され、その後宝石質の結晶が見つかっためずらしい鉱物2種. 宝石学会誌, 9, 19-23.
IMA No./year: 1973s.p.
IMA Status: Rd (redefined)
模式標本:設定なし
ルテニイリドスミン / Rutheniridosmine
(Ir,Os,Ru)
模式地:北海道鷹泊地域ほか
第一文献: Harris D.C., Cabri L.J. (1973) The nomenclature of the natural alloys of osmium, iridium and ruthenium based on new compositional data of alloys from world-wide occurrences. The Canadian Mineralogist, 12, 104-112.
第二文献: Harris D.C., Cabri L.J. (1991) Nomenclature of platinum-group-element alloys: review and revision. The Canadian Mineralogist, 29, 231-237.
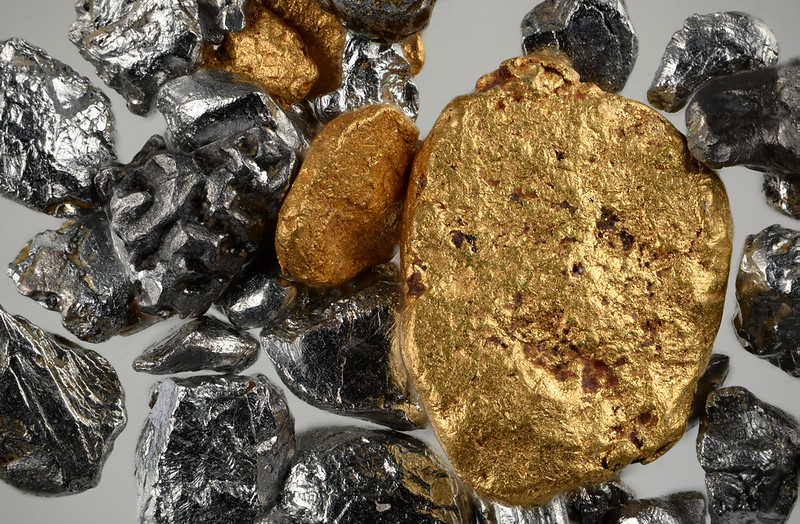
北海道雨竜川の砂金・砂白金
経験的には北海道から得られるこういった砂白金の半分以上がルテニイリドスミンであった。

北海道羽幌町愛奴沢川
ルテニイリドスミンは耐摩耗性に優れるために結晶として得られることがある。
ルテニイリドスミンは新鉱物として申請された経緯をもっておらず、白金族鉱物の命名規約が改訂された際に誕生した新鉱物である。そしてそのときに参照されたデータのなかで、日本のものがもっとも古かったためにルテニイリドスミンの模式地が日本として登録されることになった。ルテニイリドスミンの名前が文献上に登場した1973年が公式リストに登録され、その経緯からIMA StatusはRd (redefined)となっている。
1936年、東北帝国大学の青山新一は北海道鷹泊地域を流れるニセイパロマップ川(雨竜川の支流)から得られた砂白金を非常に丁寧に分別・分析し、六方晶系でルテニウム(Ru)、オスミウム(Os)、イリジウム(Ir)がちょうど等しいという化学組成を得た。それまでそのような組成比を持つ白金族鉱物は知られておらず、青山はそれを新鉱物・ルテノスミリジウム(Ruthenosmiridium)と名付けた。論文は東北帝国大学理科報告に掲載され[1]、概要は岩石鉱物鉱床学会誌の研究短報文[2]や地質学雑誌の雑報[3]で報告されている。
しかし、ルテノスミリジウムは不遇であった。1963年に成立した最初の命名規約の中で「Osmiridium」という名前は立方晶系の鉱物に対して付くものだと定義された[4]。そうなるとルテノスミリジウム(Ruthenosmiridium)は六方晶系の鉱物であるが、立方晶系を意味する名称がつくという矛盾を抱えた鉱物になった。それが嫌忌されたのか、この命名規約はルテノスミリジウムの存在を完全に無視し、言及すらしなかった。そのためにルテノスミリジウムはこれ以降の学術文献や教科書にも登場しないという事態になる。例えば1966年にStrunzが出版した著名な「Mineralogische Tabellen」という教科書の中にある鉱物名リストでも青山のルテノスミリジウムの記述は無く、代わりに「Ruthen-Iridosmium」という似ているが異なった名前が登場している[5]。さらに1970年に出版されたIntroduction to Japanese Mineralsにおいてルテノスミリジウムは「日本から最初に発見されたが疑問符が付けられた鉱物」に分類された[6]。
それでも1973年に改訂された命名規約によってルテノスミリジウムの名誉は回復されることになる[7]。この命名規約にはルテノスミリジウムの名前がこれまで不当に扱われていたことが明記され、ルテノスミリジウムは改めて一つの鉱物種として復活した[7]。その一方で名前と実体は離れて設定されてしまう。この命名規約では諸事情を考慮して、ルテノスミリジウムという名前はルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)の三角図でイリジウム側の一部に当てはめることになった(下図1)。そしてこの三角図の大部分を占める領域に対しては、新たにルテニイリドスミン(Rutheniridosmine)という名前がもうけられた(下図1)。当初ルテノスミリジウムとして発表された鉱物は、新しい定義ではルテニイリドスミンの組成領域に該当し、データとして引用されている文献の中でもっとも古いものが青山の論文であったことから、ルテニイリドスミンの模式地として日本がオフィシャルリストに掲載されることになった。
白金族鉱物の命名規約は1991年に再び改訂を受ける[8]。そこでは化学組成に対して50%で種を分け、また結晶構造についても考慮されている。結果として結晶構造の制約からルテニイリドスミンの範囲はかなり限定されることになった(下図2)。青山のデータはこの図の中でほぼ重心の位置にプロットされる。またこの時点でルテノスミリジウムは抹消となった[9]。この命名規約は全体的に完成度が高く、今後は改訂されることはないだろう。それでもこれまでに何度も命名規約が改訂された弊害は感じられ、最新の研究報告であっても未だに古い名前が登場することがある。
写真の標本は北海道雨竜川からの砂白金となる。おそらくは供給元が近いせいだろう、割と大きな粒子が存在している。砂白金は見た目での区別ができない。分析してみると自然オスミウム、自然イリジウム、ルテニイリドスミンが見つかった。ルテニイリドスミンの一部には輝イリジウム鉱(Irarsite: IrAsS)が伴われることがある。
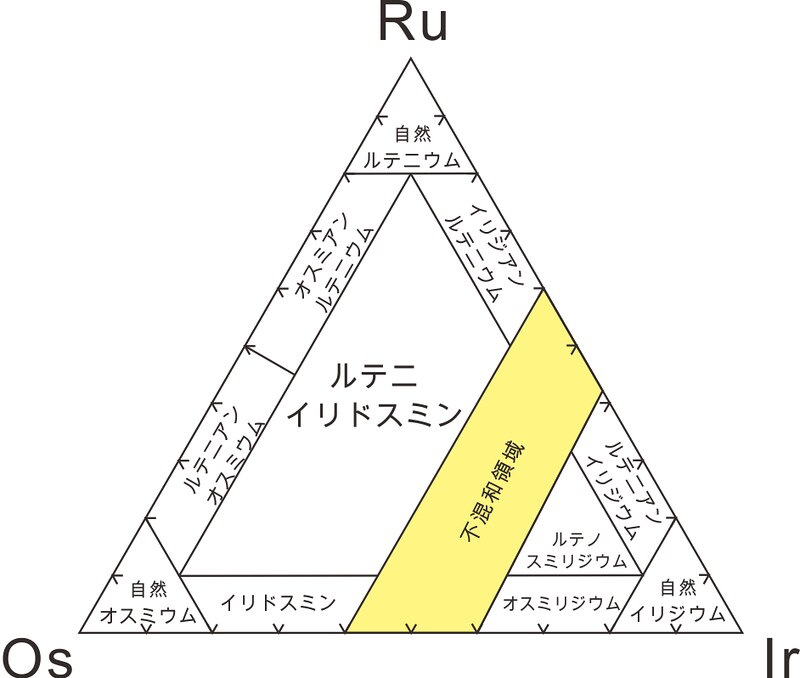
図1. 1973年当時のルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)系の鉱物種。今はこの図を元に学術的な議論してはいけないが、命名規約が改訂を繰り返したこともあって未だにこの図を元にした発表がある。
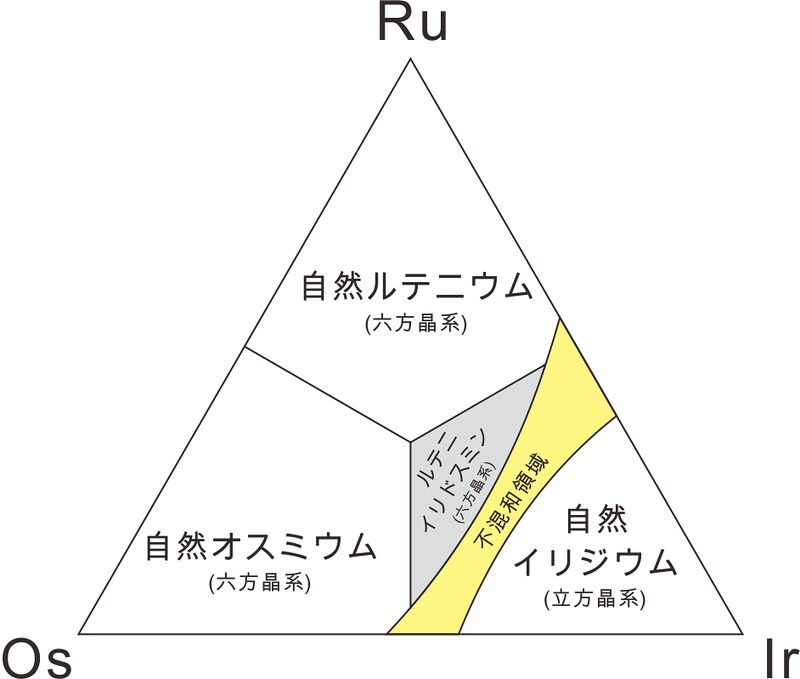
図2. 1991年から現在までのルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)系の鉱物種。合計で4種にまとめられた。今後は改訂されることは無いだろう。
[1] Aoyama S. (1936) A New mineral “Ruthenosmiridium”. The Science reports of the Tohoku Imperial University. Series 1, Mathematics, Physics, Chemistry, Anniversary Voume dedicated to Professor Kotaro Honda, 527-547.
[2] 青山新一 (1936) 新鉱物ルテノスミリヂウム(Ruthenosmiridium). 岩石鉱物鉱床学会誌, 2, 77-79.
[3] 青山新一 (1936) 新鉱物ルテノスミリヂウム(Ruthenosmiridium). 地質学雑誌, 43, 634-636.
[4] Hey M.H. (1963) The nomenclature of natural alloys of osmium and iridium. Mineralogical Magazine, 33, 712-717.
[5] Strunz H. (1966) Mineralogische Tabellen 4th edition. p93. (pp.560).
[6] Ruthenosmiridium. in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 115-116.
[7] 第一文献
[8] 第二文献
[9] Jambor J.L., Grew E.S. (1992) New mineral names. American Mineralogist, 77, 207-213.
IMA No./year: 1973-011
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館 M19511; National School of Mines, Paris, France (Handbook of Mineralogyから引用)
木下雲母 / Kinoshitalite
BaMg3(Si2Al2O10)(OH)2
模式地:岩手県野田村野田玉川鉱山
第一文献:吉井守正,前田憲二郎,加藤敏郎,渡辺武男,由井俊三,加藤昭,長島弘三(1973)岩手県野田玉川鉱山産新鉱物木下石(kinoshitalite),地学研究,24, 181-190.
第二文献:Gnos E., Armbruster T. (2000) Kinoshitalite, Ba(Mg)3(Al2Si2)O10(OH,F)2, a brittle mica from a manganese deposit in Oman: paragenesis and crystal chemistry. American Mineralogist, 85, 242-250.
木下雲母は地質調査所の吉井守正を中心とした研究チームによって記載された新鉱物で、九州大学名誉教授で鉱床学者の木下亀城(1896-1974)の栄誉を称えて命名された。木下亀城は東京帝国大学の地質学科にて黒鉱鉱床を研究し、いくつかの公的機関での勤務を経た後に九州帝国大学工学部にて教授に就任した。出版社から「鉱物」図鑑として執筆を依頼された原稿を、「鉱石」図鑑として上梓するなど徹底した鉱床屋であった。
野田玉川鉱山は堆積性の層状マンガン鉱床で花崗岩の接触により熱変成を受けている。吉村石が木下雲母に先立って記載されるように、この鉱床にはバリウム(Ba)を主成分とする鉱物の産出が知られていた。その中で吉井は鉱石中に多量に存在するマンガン(Mn)を含む金雲母に注目した。通常の金雲母と野田玉川鉱山からの金雲母ではその光学特性が逆となっていたのだ。続いて組成分析を行ったところ多量のバリウムが検出され、その一部は新鉱物に該当する化学組成であった。分析は地質調査所の前田が担当している[1]。
光学特性と化学組成の関連を議論するに当たり、バリウムに富む雲母を新鉱物として先に確立するほうが後の議論がスムーズとなる。吉井はバリウムに富む雲母を新鉱物とすべく国立科学博物館の加藤に相談したところ、渡辺・由井・加藤らも同じく野田玉川鉱山産のバリウムに富む金雲母を研究していたことが知らされた。そこでそれらの研究チームが合流し、フッ素の分析に定評のある筑波大学の長島も加わり、最終的に5研究機関にまたがる7名という多彩な顔ぶれで新鉱物の提案が行われた[1,2]。
木下雲母の結晶構造は最初に記載された時点で2種類の多形が存在することが明らかになっていたが、野田玉川鉱山産について大きい結晶の場合だとそのほとんどが1M型とされる[1]。後にオマーンのマンガン鉱床から報告された木下雲母も1M型の結晶構造であった[3]。
雲母は四面体と八面体の各シートとそれらの間にある陽イオンからなっている。そして雲母は一価の陽イオンを主成分とする純雲母(True Mica)と二価の陽イオンを主成分とする脆雲母(Brittle Mica)に分けられる[4]。二価の陽イオンのバリウムを主成分とする木下雲母は脆雲母になる。脆雲母には他にはカルシウム(Ca)を主成分とする真珠雲母(Margarite)がよく知られているが、周期律表でカルシウムとバリウムの間にあるストロンチウム(Sr)を主成分とする脆雲母は鉱物種としてはまだ確立されていない。唯一の例として糸魚川青海海岸の転石からストロンチウムに富む脆雲母の産出が報告されているのだが[5]、これは新鉱物として申請されていない。
写真に掲載した木下雲母は模式地の野田玉川鉱山から産出した標本となる。ブラウン色透明で、劈開は雲母らしく完全に発達しており、鱗片状に破断した面はガラス光沢となっている。テフロ石やバラ輝石が伴われるが肉眼的にはあまりはっきりしない。自分の標本としては京都府和束町や栃木県東小中鉱山などからも少量が見つかっている。また木下雲母の端成分にはマンガンが含まれていないが、調べた範囲内や文献ではいずれの木下雲母もマンガンを著量に含んでいることから、経験的には木下雲母の化学組成はBa(Mg,Mn2+)3(Si2Al2O10)(OH)2のように書くべきだと感じている。
[1] 第一文献
[2] 吉井守正 (1974) 最近北上産地で見つかった新しいマンガン鉱物(その2)木下石(Kinoshitalite). 地質ニュース, 237, 14-17.
[3] 第二文献
[4] Rieder M. et al. (1998) Nomenclature of the micas. The Canadian Mineralogist, 36, 905-912
[5] 宮島宏, 松原聰, 宮脇律郎 (2007) 新潟県糸魚川地方のコランダムに伴うプライスワーク雲母とストロンチウムに富む雲母. 日本鉱物科学会 2007年度年会, K8-05.
IMA No./year: 1973-006
IMA Status: A(approved)
模式標本:岡山大学理学部地球科学科 ONM-01; Institute of Geological Sciences, London, England(Handbook of Mineralogyから引用)
備中石 / Bicchulite
Ca2Al2SiO6(OH) 2
模式地:岡山県高梁市備中町布賀道路際露頭
副模式地:Carneal, Glenoe, Co. Antrim, Northern Ireland, UK
第一文献:Henmi C., Kusachi I., Henmi K., Sabine P.A., Young B.R. (1973) A new mineral bicchulite, the natural analogue of gehlenite hydrate, from Fuka, Okayama Prefecture, Japan and Carneal, County Antrim, Northern Ireland. Mineralogical Journal, 7, 243-251.
第二文献:Sahl K. (1980) Refinement of the crystal structure of bicchulite, Ca2[Al2SiO6](OH)2. Zeitschrift für Kristallographie, 152, 13-21.

模式地標本 枡形結晶はゲーレン石の仮晶と言われているが、メリライトの仮晶と言った方が妥当だろう。備中石はその内部に存在していた。
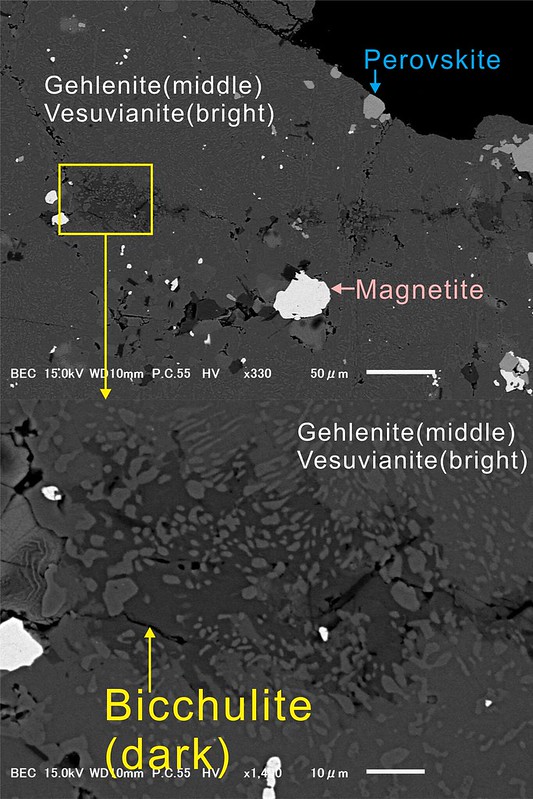
断面のSEM写真 全体的にはゲーレン石で、ゲーレン石中には数ミクロンのベスブ石の粒が網目状に散らばっている。数十ミクロン程度の比較的大きな粒は灰チタン石や磁鉄鉱。そういった中で備中石は弱線に沿って数十ミクロン程度のシミのように存在している。
備中石は岡山大学とイギリス地質科学研究所の研究チームによって記載された新鉱物で、名前は産地の備中町に因む。備中石はその名が示すとおり日本産の新鉱物という認識で間違いではないが、実は北アイルランド(Carneal)からもほぼ同時に発見されており、それぞれの模式標本は岡山大学とイギリス地質科学研究所に保管されている。
当初、備中石は岡山大学の研究者のみで新鉱物として申請されたのだが、その数日後にイギリス地質科学研究所のチームが北アイルランド産の同じ鉱物を申請してきた。ほんの数日の差であったため、新鉱物・命名・分類委員会の委員長であったMike Fleisherは二つの研究チームの合流を提案し、研究者らは委員長の提案を受け入れた[1]。このような経緯で備中石は国際研究チームで記載されることになった。名前に関しては最初に申請された備中石が採用されている。備中石発見の功績により筆頭著者である逸見千代子は櫻井賞第13号メダルを受賞した。
備中石の日本の産地である岡山県備中町布賀は高温型スカルンで特徴付けられる。まず「スカルン」とは炭酸塩岩とマグマとの反応生成物や反応そのものを指す言葉で、スカルンにはカルシウム(Ca)に富むケイ酸塩鉱物が特徴的に伴われる。そして「高温型スカルン」というと通常のスカルンよりも高い温度で変成を被ったスカルンのことを指す。一般的にスカルンは花崗岩質マグマを熱源として600℃程度以下で生成するが、高温型スカルンはより高温のマグマを熱源として温度が900℃程度にも達する。また伴われる熱水の化学組成も通常のスカルンとは異なるため、高温型スカルンには通常とは異なる珍しい鉱物群が伴われる。
高温型スカルンを代表する鉱物としてゲーレン石(Gehlenite)が知られる。日本での最初の発見は広島県久代からで、岡山県三原鉱山からも産出が確認されている[2,3]。それらに次いで岡山県備中町布賀にゲーレン石を主成分とする高温型スカルンの産出が判明した[3]。岡山県備中町布賀は広島県久代と岡山県三原鉱山に挟まれる地域である。布賀の高温型スカルンには多数の希産鉱物が伴われることが徐々に明らかとなっていき、2018年までに布賀からは12種もの新鉱物が発見されている。備中石は布賀からの最初の新鉱物である。
備中石はゲーレン石と密接に関係している。備中石とゲーレン石の関係は化学組成でみるとわかりやすく、含水の備中石(Ca2Al2SiO6 (OH) 2)に対して無水のゲーレン石(Ca2Al2SiO7)となっている。備中石はゲーレン石が生成した後、変成作用の末期に温度低下と共に備中石へ変質したと考えられている[1]。ただし天然において備中石は常にベスブ石(Vesuvianite)と共存しており、記載論文に掲載された化学組成、X線回折パターンはいずれもベスブ石で汚染されている。それでも備中石-ゲーレン石の関係は合成実験によって明らかにされていたため[4]、ベスブ石の汚染があっても備中石の同定は可能であった。備中石の結晶構造は合成物を使用して明らかにされた[5]。
これぞ備中石と言えるような、そのものをよく表現している標本は現時点で入手できていない。一方で布賀のゲーレン石には少なからず備中石が含まれるとまことしやかに言われている。ゲーレン石という標本なら一つ持っていたので、それを自分で調べてみることにした。結果的に備中石は見つかったのでその内容と考察を少し記述する。
写真の標本について、最外部は変質で乳白色化しているが、長方形の外形は正方晶系のゲーレン石を思わせる標本である。内部は濁った緑色で、電子顕微鏡でみると全体はベスブ石を包有したゲーレン石であった。ただしその組織はどう見ても離溶を示唆している。高温では系の中に水が存在していてもゲーレン石はオケルマン石(Åkermanite)との間に固溶体を形成でき、その固溶体はメリライト(Melilite)と呼ばれる。そのため内部組織から成因を考えると、結果として今はモノがゲーレン石であっても、長方形の外形はメリライトの仮晶と言うべきだろう。そして温度低下と共にメリライトはゲーレン石とゲーレン石成分を含むオケルマン石に離溶し、オケルマン石は系の中に存在していた水と反応することでベスブ石となった、そんな組織である。備中石はそういった組織の中で弱線に沿って分布している。一連の変成反応の晩期に、最後に残った水とゲーレン石が反応して生成したと思われる。
[1] 第一文献
[2] 逸見吉之助, 草地功, 沼野忠之 (1971) 広島県東城町久代産の接触鉱物. (1)ゲーレン石およびハイドログロッシュラー. 鉱物学雑誌, 10, 160-169.
[3] 逸見吉之助, 沼野忠之, 草地功, 逸見千代子 (1976) ゲーレン石, スパー石を主とするスカルンの生成. 岩石鉱物鉱床学会誌, 特別号, 1, 329-340.
[4] Carlson E.T. (1964) Hydrothermal preparation of gehlenite hydrate. Journal of Research of NIST, 68A, 449-452.
[5] 第二文献
IMA No./year: 1974(1997s.p.)
IMA Status: Rn(renamed)
模式標本:不明
ソーダレビ沸石 / Lévyne-Na
Na6(Si12Al6)O36·18H2O
模式地:長崎県壱岐島長者原
第一文献:Mizota T., Shibuya G., Shimazu M., Takeshita Y. (1974) Mineralogical studies on levyne and erionite from Japan. The Memoir of the Geological Society of Japan, 11, 283-290.
第二文献:Ballirano P., Cametti (2013) Crystal chemical and structural investigation of levyne-Na. Mineralogical Magazine, 77, 2887-2899.

模式地標本 ソーダレビ沸石は六角板状結晶(写真中央)が本来の姿であるが、この産地では表面に繊維状のソーダエリオン沸石を伴う姿が典型的な産状となっている。破断面ではソーダエリオン沸石の絹糸光沢が目立つが、その中心に存在する板はソーダレビ沸石となっている。
ソーダレビ沸石は新鉱物として申請された経歴をもっておらず、沸石族の命名規約の成立と同時に新たに定義された新鉱物である。レビ沸石の発見は古く1825年にはデンマークから見つかっている。そのレビ沸石はカルシウム(Ca)に富むタイプだったが、長崎県壱岐島の長者原(ちょうじゃばる)から産出したレビ沸石はナトリウム(Na)に富んでいた[1]。そして沸石族の命名規約が成立した際にカルシウムレビ沸石(Lévyne-Ca)とソーダレビ沸石(Lévyne-Na)が分けられ、それぞれが独立の鉱物として認められて今に至っている[2]。学名はフランスの鉱物学者であるServe-Dieu Abailard Lévy(1795-1841)に因む。
長者原からのソーダレビ沸石の最初の記載は1972年のことで、新潟大学の島津光夫と溝田忠人によって岩石鉱物鉱床学会誌で発表された[3]。このときは日本初産のレビ沸石という趣旨で記載されており、そのレビ沸石がナトリウムに富むことには特に注目されていない。1974年には溝田を筆頭著者としたより詳細な鉱物学的記載が地質学論集に掲載され、世界中のレビ沸石と比べて長者原のレビ沸石は最もナトリウム端成分に近いことが明記されている[1]。1997年に成立した沸石族の命名規約では1974年の論文を引用し[2]、それがソーダレビ沸石の論拠としてIMAのオフィシャルリストにも採用されている。オフィシャルリストに掲載されている第二文献は結晶構造を議論しており、実験には北アイルランド産の標本が使用されている[4]。
沸石族の命名規約は6つのルールからなるが、内容を簡単にまとめると沸石族は骨格構造の種類と化学組成で種を決めようという提案である[2]。沸石族の骨格構造は3個のアルファベットで表現される手法が国際ゼオライト学会により提案されており、骨格タイプコードとしてデータベース化されている。レビ沸石の場合だと骨格タイプコードは「LEV」と表現されている。これはそもそもレビ沸石の学名から採用された文字にすぎず、LやEやVに特別な意味は無い。骨格の内容は9つの四角形、5つの6角形、3つの八角形からなる大きな箱[496583]と、6つの四角形および2つの六角形からなる小さな箱[4662]が積み重なってできている。箱の骨格はシリコン(Si)、アルミニウム(Al)、酸素(O)からできており、その箱の中に水や陽イオンが入っている。鉱物名の前半はその骨格の種類に対して命名されるルート名であり、後半は最も多い陽イオンをサフィックスとして「-元素名」という形でくっつける。ソーダレビ沸石(Lévyne-Na)はLEVという3文字で代表される骨格を有したナトリウムが優勢となる沸石族鉱物である。
写真の標本は模式地である長崎県壱岐島の長者原で得られたソーダレビ沸石となる。海岸線に分布する玄武岩礫中にみられる杏仁状晶洞には、ナトリウムを主成分とする数種類の沸石が産出する。ソーダレビ沸石もそのうちの一種で、ほとんどの場合でソーダエリオン沸石 (erionite-Na)を密接に伴う。ソーダレビ沸石は6角板状結晶(写真中央)が本来の姿であるが、その表面から毛状のソーダエリオン沸石が成長しているという産状をよく見かける。これらはエピタキシャル関係であることが指摘されている[3]。
[1] 第一文献
[2] Coombs D.S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J.D., Liebau F., Mandarino J.A., Minato H., Nickel E.H., Passaglia E., Peacor D.R., Quartieri S., Rinaldi .R, Ross M., Sheppard R.A., Tillmanns E., Vezzalini G., (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names, The Canadian Mineralogist, 35, 1571-1606
[3] Shimazu M., Mizota T. (1972) Levyne and erionite from Chojabaru, Iki Island, Nagasaki Prefecture, Japan. The Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 67, 418-424.
[4] 第二文献
IMA No./year: 1974-010a
IMA Status: A(approved)
模式標本:東京大学総合博物館(第一文献から引用)
都茂鉱 / Tsumoite
BiTe
模式地:島根県益田市都茂鉱山(旧:美都町)
第一文献:Shimazaki H., Ozawa T. (1978) Tsumoite, BiTe, a new mineral from the Tsumo mine, Japan. American Mineralogist, 63, 1162-1165.
第二文献:Yamana K., Kihara K., Matsumoto T. (1979) Bismuth tellurides: BiTe and Bi4Te3. Acta Crystallographica, B35, 147-149.
都茂鉱は東京大学の島崎英彦と小沢徹によって記載された新鉱物で、島根県美都町にあった都茂鉱山から見いだされた。学名も産地である都茂鉱山に因んでいる[1]。都茂鉱の記載論文は1978年にAmerican Mineralogistに掲載され、その翌年には都茂鉱の結晶構造は解かれている[2]。島崎は都茂鉱の発見により1981年に日本鉱物学会(当時)から櫻井賞(第19号)を受賞した。
都茂鉱山は平安時代には稼働していたとされ、矢対・嵯峨谷・芋尻・旭・都茂・宝来・丸山・空山・銀山などの鉱床が知られている。1970年の時点では丸山鉱床が稼働中、宝来・都茂・旭の3鉱床が探鉱中だったようだ[3]。都茂鉱山はスカルンに伴われる金属鉱床で、島崎はこのスカルンをテーマに卒業・修士論文において鉱床学的な研究を行い、その過程で後に都茂鉱となる鉱物を採集することになる。一方で得られた試料はわずかであったため、大量の試料を消費する当時の分析法には不向きであった。そのため都茂鉱は発見から10年ほどお蔵入りとなっていた。
時代が下り、電子顕微鏡の発達に伴い微少鉱物の化学組成を決定することが容易になったことで都茂鉱の研究は進展を見せる。都茂鉱の化学組成はビスマス(Bi)とテルル(Te)が1:1という単純な割合であった。ところがその当時BiTeの化学組成をもつウェーライト(Wehrlite)という鉱物が知られていた。島崎らはこのウェーライトについてその中身を検討したところ、これはピルゼン鉱(Pilsenite)とヘッス鉱(Hessite)の混じりモノであることが判明した。そのため、BiTeの化学組成をもつ鉱物は都茂鉱が初めてということになり、都茂鉱は新鉱物として認められた。一方のウェーライトは混合物を誤認したということで抹消となった。
都茂鉱は都茂鉱床の-60mレベルのごく一部の箇所から見いだされ、それはケイ酸塩鉱物を主体とするスカルン中に都茂鉱の微少粒がまばらに伴われる産状だったとされる[1]。後に旭鉱床から都茂鉱が見つかり、比較的多産したようだ。一枚目の写真に示した標本は旭鉱床からのもので、分離結晶となる。二枚目の写真は長野県向谷鉱山からの都茂鉱で、この産地ではヘドレイ鉱 (Hedleyite)やピルゼン鉱など他のBi-Te鉱物と共生することが知られている[4]。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] 太田茁司, 赤塚政美, 本多谷雄 (1970) 都茂鉱山の地質・鉱床と探査. 鉱山地質, 102, 1-9.
[4] 松原聰, 宮脇律郎, 横山一己, 重岡昌子, 原田明, 山田隆, 川島和子, 清水孝一, 宮島 浩 (2010) 長野県茅野市向谷鉱山産Bi-Te系鉱物. 日本鉱物科学会2010年年会講演要旨集, R1-09.
IMA No./year: 1974-013
IMA Status: A(approved)
模式標本:鹿児島大学(第一文献から引用)
自然ルテニウム / Ruthenium
Ru
模式地:北海道幌加内(第一文献から引用):雨竜川(Hand book of Mineralogyから引用)
第一文献:Urashima Y., Wakabayashi T., Masaki T., Terasaki Y. (1974) Ruthenium, a new mineral from Horakanai, Hokkaido, Japan. Mineralogical Journal, 7, 438-444.
第二文献:設定なし

幌加内地域から得られた砂白金。主にイリジウム系白金族元素(Ru, Os, Ir)を主成分とし、プラチナ系白金族元素(Rh, Pd, Pt)を主成分とするものは希。
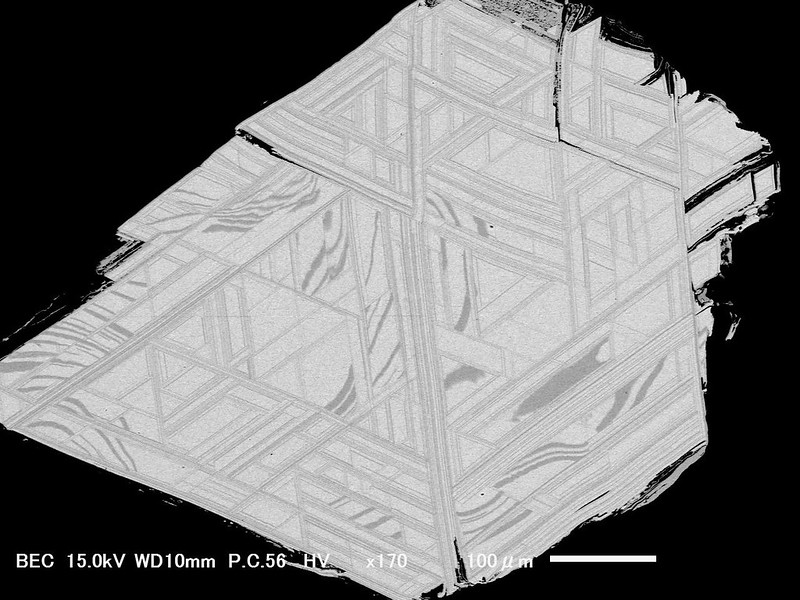
北海道留萌地域から砂白金として得られたイソフェロプラチナ鉱の断面。内部は共析組織を示し、暗い部分が自然ルテニウム。
自然ルテニウムは鹿児島大学の浦島幸世らによって見いだされた新鉱物で、ルテニウム(Ru)を端成分とする[1]。ルテニウムはロシア人化学者のKarl Ernst Claus(1796-1864)によって1844年に単離・発見・命名された白金族元素で、名称はロシアの語源となった「ルーシ」のラテン語訳「ルテニア」に因んでいる。こういった鉱物は元素名をそのまま学名とするため、英文では元素と鉱物のどちらを表現しているのか混乱することがある。一方、和文においては鉱物には「自然」の頭文字を付けて表現できるため、元素名と鉱物名を区別して扱うことが容易となっている。
ルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)を主成分とする白金族元素鉱物に対する命名規約は1973年に改訂を受け、下の図1に示す三角形で示される化学組成・名前で分けられることになった[2]。このときこの三角形には11種類もの鉱物名が記されている。そして命名規約は1991年に再度改訂を受けて今に至っている[3]。1991年の命名規約に従った三角形は下の図2に示した。これらを比較すると自然ルテニウムに該当する領域は大きく異なっていることが見て取れるだろう。
現代の基準で自然ルテニウムに該当する鉱物は1973年より前の時点でもニューギニア、カリフォルニア、ウラルから報告されている[2]。しかし1973年時の命名規約ではそれらはルテニイリドスミンに分類されており、当時の自然ルテニウムに該当する鉱物はまだ知られていない。この基準における自然ルテニウムにはRu-Os-Irの三成分系でRu成分が80%以上含まれている必要があった。
浦島らは櫻井欽一から砂白金の提供を受けて観察・分析を行ったなかで、粒の外縁に100×10マイクロメートルほどの鉱物が一粒伴われていることに気づいた。その鉱物は光学特性から六方晶系であることが推測され、分析では多量のルテニウムが検出された。そしてRu-Os-Irの三成分系にならすとその鉱物のRu成分は80%を越えていた。これはその当時の基準で未発見であった自然ルテニウムに該当した。こうして自然ルテニウムは天然に産出するルテニウムとして新種の鉱物になった。なお産地について浦島らの文献では幌加内という記述のみであるが、Hand book of Mineralogyには雨竜川という記述がある。
北海道の砂白金は今現在でも露出しているマグマ成分に枯渇したかんらん岩体を起源とするものと、具体的な起源は既に不明だが堆積岩に含まれるものがある。後者は主に留萌地域である。自分自身も砂白金を調べているところであり[4]、北海道の砂白金は産地を問わずイリジウム系白金族元素(Ru, Os, Ir)を主成分とする砂白金が主で、プラチナ系白金族元素(Rh, Pd, Pt)を主成分とする砂白金は希という特徴がある。イリジウム系白金族元素は固相に留まりやすいため[5]、堆積岩からの砂白金もその起源は枯渇したかんらん岩(蛇紋岩)なのであろう。いずれにしても北海道では自然ルテニウムは幌加内のみではなく、いろんなところで見つかる。
現在では自然ルテニウムはRu-Os-Irの三成分系においてRuが1/3を越えるものを指し、写真で紹介する自然ルテニウムもその基準に従って同定した。1枚目の写真はいわゆる砂白金であるが、こういった摩耗が進んだ姿では鉱物種を肉眼的に区別することは難しい。一方で結晶の形が見えていると簡単に判別でき、例えば2枚目の写真は北海道留萌地域から砂白金として得られた自然ルテニウムの結晶となる。また単独の粒として見つかるもの以外に、プラチナ系砂白金と共析する産状も見つけている(写真3枚目)。この共析組織と結晶の形はなんだかとてもよく似ている。

図1.1973年時点でのルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)系白金族元素鉱物の分類図。

図2.1991年以降のルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)系白金族元素鉱物の分類図。
[1] 第一文献
[2] Harris D.C., Cabri L.J. (1973) The nomenclature of the natural alloys of osmium, iridium and ruthenium based on new compositional data of alloys from world-wide occurrences. The Canadian Mineralogist, 12, 104-112.
[3] Harris D.C., Cabri L.J. (1991) Nomenclature of platinum-group-element alloys: review and revision. The Canadian Mineralogist, 29, 231-237.
[4] 浜根大輔、齋藤勝幸(2017)北海道の砂金・砂白金鉱床から見いだされた金-銀-錫鉱物、自然鉛および白金族元素含有鉱物について. 日本鉱物科学会2017年年会講演要旨集, R1-P12.
[5] Barnes S.J., Naldrett A.J., Gorton M.P. (1985) The origin of the fractionation of platinum-group elements in terrestrial magmas. Chemical Geology, 53, 303–323.
IMA No./year: 1974-031
IMA Status: A(approved)
模式標本:文献上は不明。ただし新潟大学サイエンスミュージアムに模式標本のラベルがついた標本が展示されている。
青海石 / Ohmilite
Sr3(Ti,Fe3+)(Si2O6)2(O,OH)·2H2O
模式地:新潟県糸魚川市橋立(旧:青海町)
第一文献:Komatsu M., Chihara K., Mizota T. (1973) A new strontium-titanium hydrous silicate mineral from Ohmi, Niigata Prefecture, Central Japan. Mineralogical Journal, 7, 298-301
第二文献:Mizota T., Komatsu M., Chihara K. (1983) A refinement of the crystal structure of ohmilite, Sr3(Ti,Fe3+)(O,OH)(Si2O6)2 · 2–3H2O, American Mineralogist, 68, 811-817.
青海石は新潟県青海町橋立から発見された新鉱物で、新潟大学の小松正幸、茅原一也、溝田忠人の連名による記載論文が1973年に出版された。しかしながらこの論文には青海石の名前は登場しない[1]。IMA No.は1974年の申請を意味しているため、論文が出版された後に新鉱物の申請を行ったと読み取れる。また論文中に明記されていないが学名は発見地である青海町に因んだと思われる。文献上で初めて青海石の名前が登場するのは1983年に出版された構造解析の論文となっている[2]。一連の研究を主導した茅原には、青海石発見の業績に対して1987年に櫻井賞第27号メダルが贈られた。
糸魚川地域はいわゆる翡翠が有名で、1939年に小滝地域でその存在が初めて報告された[3]。1958年には茅原によって青海地域からも翡翠の産出が報告されており[4]、これが一連の研究の始まりとなるだろう。そして青海石は1971年に見いだされたことが第一文献に記してある。具体的な産地については青海という記述しかないが、茅原が執筆した記事では橋立地域であることが読み取れる[5]。それ以上の詳細は学術文献には記載がない。また試料は川の転石かそれとも露頭から採集されたのかも明記されていない。ただし今では橋立にある金山谷が青海石の産地であることは知られている。
金山谷は蛇紋岩地帯となっている。その蛇紋岩にはヒスイ輝石岩、ロジン岩、苦土リーベック閃石と曹長石が主体となった曹長岩などが岩塊で胚胎されており、このような産状は蛇紋岩メランジュと呼ばれる。青海石が見いだされた曹長岩について茅原らは蛇紋岩を貫く岩脈と記述しているが[6]、そのような具体的な産状はいまでは見あたらない。いずれにしても金山谷の苦土リーベック閃石を伴う曹長岩は空隙に富み、その空隙にはベニト石、リューコスフェン石などの稀産鉱物が産出する。この中に針状でピンク色鉱物と、不定形な黄色鉱物が未知鉱物として見いだされた[1]。前者は青海石となり、後者は通称で奴奈川石と呼ばれる新鉱物となる。
青海石の結晶構造のモデルは溝田によって導かれ、論文は最初の記載論文と連続して掲載された[7]。そして後年により精密化された構造モデルが発表され[2]、その構造は原田石などと関連性はあるものの青海石のみが持つ独特の構造であることが明かとなった。現時点(2018年11月)で青海石と同じ構造をもつ鉱物は知られていない。またその論文に従って青海石の化学組成は現在の式に改訂されている。
写真の標本はかなり以前に採集された青海石の標本となる。青海石について論文にはピンク~ピンクブラウンの針状という記述があり、一枚目の写真は論文で言及された姿に近いのだろう。また自身で調べた範疇では白色に近い青海石も存在している(写真二枚目)。この違いはおそらくは含まれる鉄の価数による。分析をして化学組成を解析すると、ピンク系統は3価の鉄を、白系統は2価の鉄を含むと思われる。また青海石はいまだに金山谷が世界で唯一の産地であり、青海石を胚胎する曹長岩についてもどのような環境・条件で生成したかはいまだ明らかとなっていない。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] 河野義礼(1939)本邦における翡翠の新産出及び其化学的性質. 岩鉱, 22, 195-201.
[4] 茅原一也(1958)新潟県青海地方のjadeite rockについて. 藤本治義教授還暦記念論文集, 459-466.
[5] 茅原一也(1996)青海自然史博物館とヒスイ. 宝石学会誌, 21, 95-96.
[6] Chihara K., Komatsu M., Mizota T. (1974) A joaquinite-like mineral from Ohmi, Niigata Prefecture, Central Japan. Mineralogical Journal, 7, 395-399.
[7] Mizota T., Komatsu M., Chihara K. (1973) On the crystal structure of Sr3TiSi4O12(OH)・2H2O, a new mineral. Mineralogical Journal, 7, 302-305.
IMA No./year: 1974-046
IMA Status: A(approved)
模式標本:金沢大学(第一文献から引用)
益富雲母 / Masutomilite
KLiAlMn2+(Si3Al)O10(F,OH)2
模式地:滋賀県大津市田上山
第一文献:Harada K., Honda M., Nagashima K., Kanisawa S. (1976) Masutomilite, manganese analogue of zinnwaldite, with special reference to masutomilite-lepidolite-zinnwaldite series. Mineralogical Journal, 8, 95-109.
第二文献:Mizota T., Kato T., Harada K. (1986) The crystal structure of masutomilite, Mn analogue of zinnwaldite. Mineralogical Journal, 13, 13-21.
益富雲母は東京教育大学(現:筑波大学)の長島弘三を中心とした研究チームによって記載された雲母超族の新鉱物で、益富壽之助(1901-1993)の鉱物学への貢献をたたえて命名された。第一文献は原田一雄を筆頭著者として1976年に発表されているが、それに先立つ1975年には長島を筆頭著者とした和文による報告が地学研究に掲載されている[1]。
益富壽之助は薬学の研究者である一方で、少年時代における水晶採りの経験から地質・鉱物分野にも強く興味をもっていた。後年それらをほとんど独学で修め、新鉱物・大隅石の発見に貢献したことで櫻井賞(第3号メダル)を受賞し、その他にも様々な賞を受賞している。また日本鉱物趣味の会を創設し、機関誌を発行して後進の育成にも力を注いでいた。益富の興した事業は、現在は公益財団法人益富地学会館として運営が行われている。
益富雲母の模式地となっている滋賀県田上山は古くから名の通った鉱物産地で、例えば田上山のトパーズは海外に輸出されるほど非常に評価が高かった。田上山は花崗岩で構成されており、大規模なペグマタイトが見られることから日本の三大ペグマタイトと呼ばれている。田上山のペグマタイトは晶洞が多く認められ、そのなかにチンワルド雲母(Zinnwaldite)の産出が古くから知られていた。例えば1904年発行の鉱物誌にすでに言及があり、六角板状で紫~褐色という記述が確認できる[2]。
田上山のチンワルド雲母は安田若三郎によって1908年には分析が行われており、そのときすでに多量のマンガン(Mn)が検出されていた[3]。長島らはより詳細な分析を行い、安田の分析値が基本的に正しいことを再確認すると共に、そこから組み立てられる組成式はチンワルド石からみて二価マンガン(Mn2+)置換体に相当することを見出した。その雲母は益富雲母と命名され、二価鉄(Fe2+)を主成分とするチンワルド雲母の二価マンガン置換体という立ち位置で1974年に新種として認められた[4]。標本としては褐色部がチンワルド雲母で、紫色部が益富雲母に該当するとされる。研究には田上博物館の中司稔が採集・保管していた標本が使用され、それは幅10cmで厚さも1cmある結晶だった。この標本は金沢大学に保管されている。また第一文献には岐阜県蛭川村田原(現:中津川市)からの益富雲母も記載されており、この標本については東北大学が保管先であると記述されている[4]。
益富雲母の結晶構造については、初めは田上山産の標本を用いた研究が行われた[5]。後に蛭川村産の標本を用いてより詳細な内容が明らかにされたことで、益富雲母の化学式は現在のように改訂されている[6]。そして二価マンガンを主成分とする益富雲母と二価鉄を主成分とするチンワルド雲母という立ち位置はわかりやすいものであり、益富雲母の誕生からその関係性で理解されてきた。ところが1998年の雲母超族の命名規約[7]によってチンワルド雲母が消滅したことで、益富雲母の独立性は不安定なものとなっている。
チンワルド雲母の組成はKLiAlFe2+(Si3Al)O10(OH)2で表され、長らく独立の組成と認識されていた。しかしながらこの組成はKFe2+2Al(Al2Si2O10)(OH)2とKLi2Al(Si4O10)F2という2つの組成からみると足して半分に割った値に相当する。そしてそれぞれはシデロフィル雲母(Siderophyllite)とポリリシオ雲母(Polylithionite)のことであり、雲母超族の命名規約では中間成分は単独の鉱物種として取り扱わない。すなわちチンワルド雲母はシデロフィル雲母とポリリシオ雲母の固溶体(中間体)という扱いになり独立種としては抹消となった。同じ論法を適用すると益富雲母はKMn2+2Al(Al2Si2O10)(OH)2組成の雲母とポリリシオ雲母の固溶体となり、抹消やむなしの状況であった。しかしながらチンワルド雲母のケースとは異なり、益富雲母の場合は片方の組成についてそのような雲母は発見されてない。そのため、暫定的な処置として益富雲母はいまだ独立の種としてギリギリ留まっている。今後もしその新しい組成の雲母が見つかると、その時点で益富雲母は抹消となってしまう[7]。
写真は田上山の中沢晶洞から得られた益富雲母の標本となる。一般的に紫色部が益富雲母で褐色~ブラウン色がチンワルド雲母と言われているが、この標本では褐色を帯びた部分でもMn2+ > Fe2+という分析結果となり、全体が益富雲母であった。
[1] 長島弘三, 原田一雄, 本田真理子 (1975) 滋賀県大津市田ノ上山産新鉱物益富雲母(Masutomilite). 地学研究, 26, 319-324.
[2] 和田維四郎(1904)日本鉱物誌. 東京築地活版製造所, pp.281
[3] 安田若三郎(1908)近江國田の上山産雲母の分析. 地質学雑誌, 15, 386-394.
[4] 第一文献
[5] 第二文献
[6] Brigatti M.F., Mottana A., Malferrari D., Cibin G. (2007). Crystal structure and chemical composition of Li-, Fe-, and Mn-rich micas. American Mineralogist, 92, 1395-1400.
[7] Rieder M., Cavazzini G., D’Yakonov Y.S., Koval’ P.V., Müller G, Neiva A.M.R., Sassi F.P., Takeda H., Weiss Z., Frank-Kamenetskii V.A., Gottardi G., Guggenheim S., Radoslovich E.W., Robert J.L., Wones D.R. (1998) Nomenclature of the micas. The Canadian Mineralogist, 36, 905-912.
IMA No./year: 1974-060
IMA Status: A(approved)
模式標本:山口大学、櫻井標本、国立科学博物館、Natural History Museum, London (1975,342)、National Museum of Natural History, Washington (133982) (Handbook of Mineralogyから引用)
杉石 / Sugilite
KNa2Fe3+2(Li3Si12)O30
模式地:愛媛県上島町岩城島
第一文献:Murakami N., Kato T., Miúra Y., Hirowatari F. (1976) Sugilite, a new silicate mineral from Iwagi Islet, Southwest Japan. Mineralogical Journal, 8, 110-121.
第二文献:Armbruster T., Oberänsli R. (1988) Crystal chemistry of double-ring silicates: Structures of sugilite and brannockite. American Mineralogist, 73, 595-600.
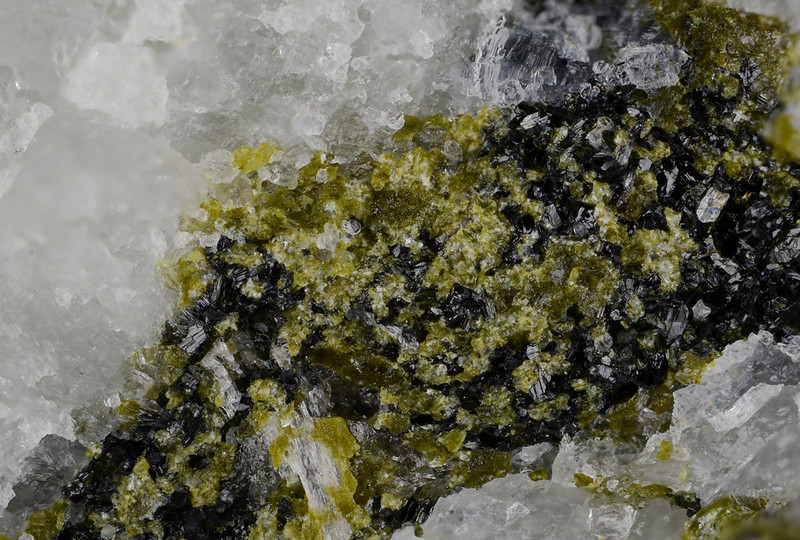
模式地標本
ウグイス色が杉石

Wessels Mine, Hotazel, Kalahari manganese field, Northern Cape Province, South Africa
紫色が杉石
杉石は山口大学の村上允英らによって記載された新鉱物で、愛媛県岩城島から見出された。学名は九州大学の岩石学者である杉健一(1901-1948)に因んで命名されている。杉は岩石学が近代化していくなか変成岩岩石学の最前線で活躍し、村上は杉の指導の元で九州大学を卒業した。杉石発見の業績に基づいて、村上には1983年に鉱物学会から櫻井賞(第22号メダル)が贈られた。
岩城島は愛媛県北東部に位置する離島で、全体としては珪長質の深成岩からなっている。島の東側では、エジリンを含み曹長石を主体とした岩石が狭い範囲に分布し、古くは「モンゾニ岩」と呼ばれていた。しかし1944年にこの岩石を研究した杉健一らによって「エジル石閃長岩」という特徴をとらえた名称が与えられた[1]。その論文の中で杉らは岩石中に肉眼的に目立つうぐいす色の鉱物の存在に気づいている。光学的な特徴からその鉱物をユーディアル石様鉱物として記述したものの、確実な同定は行えなかったようだ。これが後の杉石となる。
山口大学の村上らはそのユーディアル石様の未詳鉱物の同定を試みた。研究の開始時期は定かでないが、1964年から1966年にかけて未詳鉱物は大隅石やミラー石と同じ構造であることが報告されている[2,3]。化学組成もその当時に検討を行っていたようだが、十分な結論に至らなかった旨が第一文献に記されている[4]。正確な化学組成の決定にはさらに10年を必要とした。ユーディアル石様の未詳鉱物が改めて新鉱物・杉石として国際鉱物学連合へ申請されたのが1974年であり、杉らが見出してからちょうど30年が経過していた。記載論文は1976年に出版され[4]、結晶構造の詳細については加藤敏郎が中心となって検討されている[5]。
このように、杉石は岩城島から1944年に見出され、1974年に新種として発表された経緯がある。未詳鉱物であった期間が30年ほどあったわけだが、実はその間に愛媛県内の別の産地からも杉石が見出されていた。愛媛県砥部町にある古宮鉱山において、黒色のブラウン鉱の隙間を埋める鮮やかな紫色鉱物が広渡文利によって1956年に採集されている[6,7]。一方で即座に同定とはならなかったようで、20年以上経た後に杉石と同定された。広渡は岩城島産杉石の著者にもなっているが、色が全く異なっていたため古宮鉱山の標本を杉石と気づくことができなかったと伝わる。また、古宮鉱山産杉石の分析値を解析すると、それはアルミノ杉石(Alminosugilite)という別種に相当する。これもまた当時は認識されていなかった。
海外でも杉石の産出が確認されている。1978年に南アフリカのWessels鉱山から紫色鉱物が見出され、それがはじめソグディア石だと鑑定され[8]、後に杉石であることが判明した[9-11]。Wessels鉱山の杉石について詳細は1988年に報告されており、その論文を読むとこの杉石には三価のマンガン(Mn3+)とアルミニウム(Al)が含まれ、さらに一部ではアルミニウムが完全に卓越している。それはすなわちアルミノ杉石という別種であったが、その当時はまったく注目されていなかった。そして2018年になり、イタリアのCerchiara鉱山を模式地としてアルミノ杉石が新鉱物として誕生した[12]。これもまた山口大学の研究者らによって記載されている。
写真は岩城島とWessels産の杉石を合わせて掲載した。Wessels産についても分析を行い、杉石であることを確認してある。同じ鉱物にはとても見えないが、どちらも杉石である。
[1] 杉健一, 久綱正典 (1944) 愛媛県岩城島産エヂル石閃長岩に就いて. 岩石鉱物鉱床学会誌, 31, 209-224.
[2] 村上允英, 松永征二 (1964) 閃長岩化における交代作用(2). 地質学雑誌, 70, 421.
[3] Murakami N., Matsunaga S. (1966) Petrological Studies on the Metasomatic Syenites in Japan. Part 2. Petrology of the Aegirine Syenite from Iwagi Islet, Ehime Prefecture, Japan. Sci. Rept. Yamaguchi Univ., 16, 17-34.
[4] 第一文献
[5] Kato T., Miúra Y., Murakami N. (1976) Crystal structure of sugilite. Mineralogical Journal, 8, 184-192.
[6] 広渡文利, 福岡正人, 近藤裕而 (1981) 愛媛県古宮鉱山の含マンガン杉石. 日本鉱物学会1981年会講演要旨集, 113.
[7] 広渡文利, 福岡正人 (1988) 日本のマンガン鉱物に関する2,3の問題. 鉱物学雑誌, 18, 347-365.
[8] Bank H., Banerjee A., Pense J., Schneider W., Schrader W. (1978) Sogdianit-ein neues Edelsteinmineral?. Z. Deut. Gemmol. Ges., 27, 104-105.
[9] Dunn P.J., Brummer J.J., Belsky H. (1980) Sugilite, a second occurrence; Wessels Mine, Kalahari manganese field, Republic of South Africa. Canadian Mineralogist, 18, 37-39.
[10] 第二文献
[11] 砂川一郎 (1982) 南部石と杉石 日本で新鉱物として発見され, その後宝石質の結晶がみつかった珍しい鉱物2種. 宝石学会誌, 9, 55-59.
[12] Nagashima M., Fukuda C., Matsumoto T., Imaoka T., Odicino G., Armellino G. (2020) Aluminosugilite, KNa2Al2Li3Si12O30, an Al analogue of sugilite, from the Cerchiara mine, Liguria, Italy. European Journal of Mineralogy, 32, 57-66.
IMA No./year: 1975-003
IMA Status: A(approved)
模式標本:地質標本館(GSJ M17968), 櫻井標本 (第一文献より引用)
神岡鉱 / Kamiokite
Fe2+2Mo4+3O8
模式地:岐阜県飛騨市神岡鉱山(旧:神岡町)
第一文献:Sasaki A., Yui S., Yamaguchi M. (1985) Kamiokite, Fe2Mo3O8, a new mineral. Mineralogical Journal, 12, 393-399.
第二文献:Kanazawa Y, Sasaki A (1986) Structure of kamiokite. Acta Crystallographica, C42, 9-11.
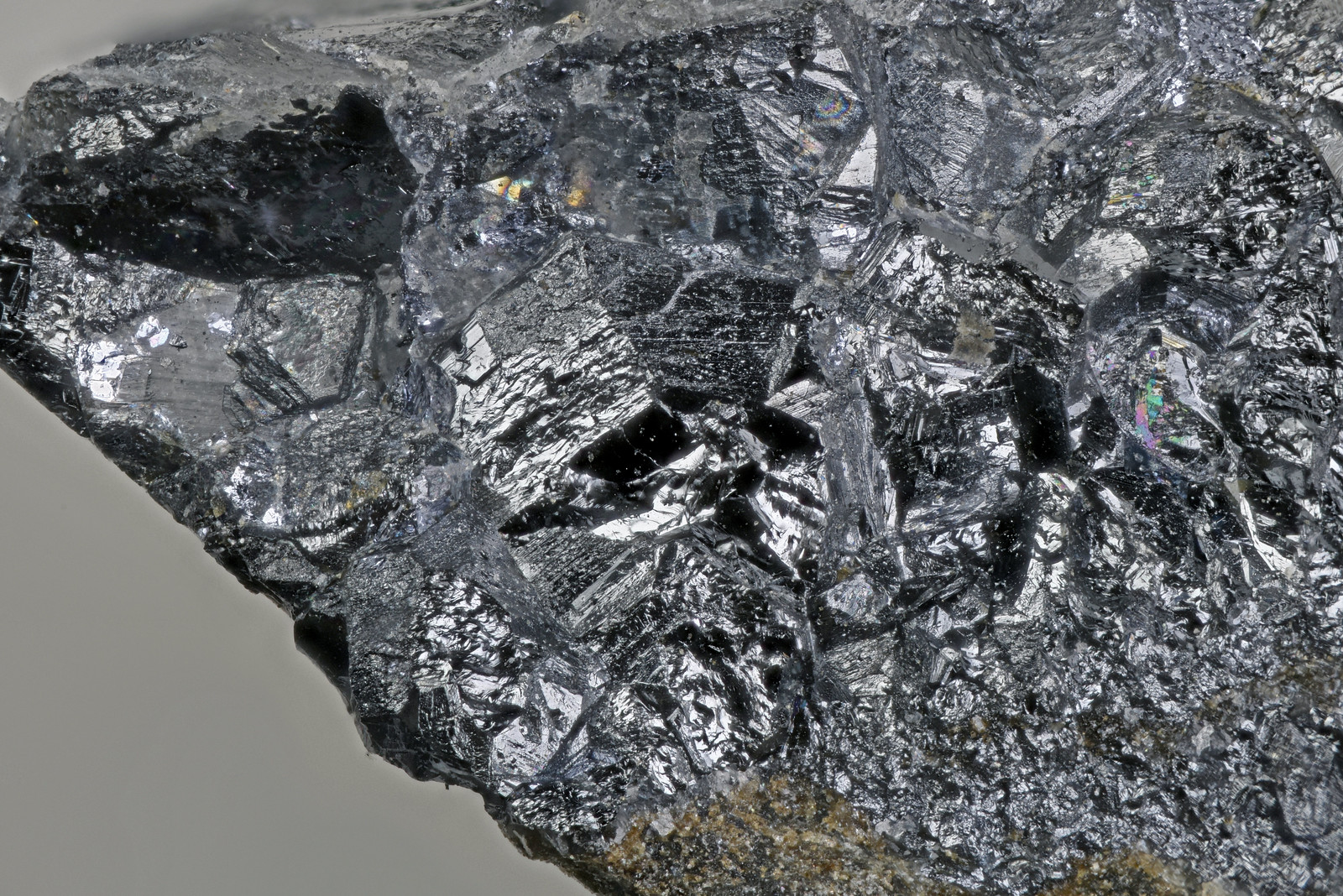
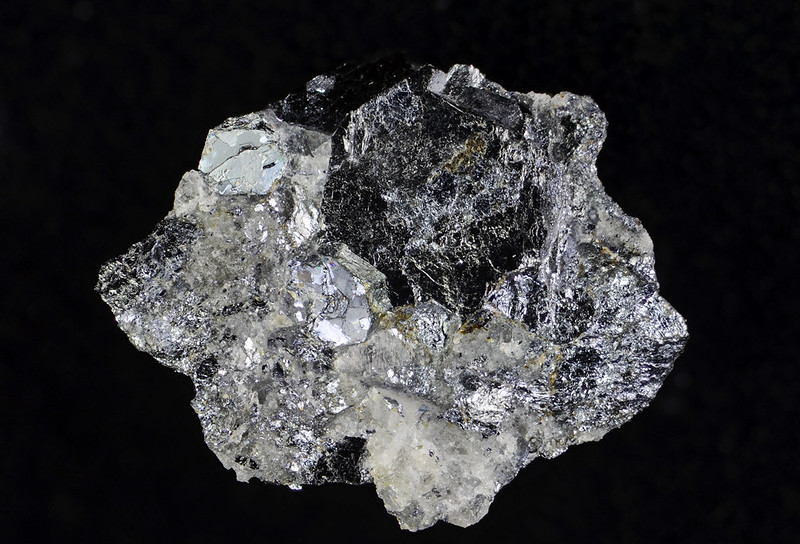
模式地標本 強い金属光沢を示す結晶で、一部にはややひずんだ6角形の断面がみえる
神岡鉱は地質調査所の佐々木昭らによって記載された新鉱物で、発見地である神岡鉱山に因んで学名は「Kamiokite」と命名された。「ite」の前にあるべきの「a」が省略されている形になっており、1952年に発表された神岡石(Kamiokalite)[1]との混同を避けようとしたのかもしれない。なおその神岡石(Kamiokalite)は後にベゼル石と同定され、神岡鉱が承認された当時にはすでに独立の鉱物種という立場を失っていた[2]。
神岡鉱は1975年3月に国際鉱物学連合から新鉱物の承認を受け、その年の鉱物学会において概要が発表されている[3]。また1985年に記載論文が発表されるまでの間にアメリカのMohawk鉱山およびAhmeek鉱山からも神岡鉱の産出が報告されていた[4]。今では中国、チェコ、ブラジルなどにも産地が知られている。ほかにおもしろい産地として、アエンデ隕石中に含まれる太陽系最古の物質(Ca-Al-rich Inclusion)の中にも神岡鉱は見つかっている[5]。今ではニュートリノ研究の前線基地となっている神岡鉱山、そこから見出された神岡鉱が隕石からも見つかるとは、神岡は宇宙と縁があるのだなと感じる。
神岡鉱山の歴史は古く、奈良時代に発見されたとも言われる。近代化以前は銀が主目的の鉱山であったが、明治時代からは日本最大の亜鉛・鉛鉱山となっていた。鉱床はスカルンであり、茂住・円山・栃洞坑という3つの鉱床群が知られる。鉱石鉱物は閃亜鉛鉱や方鉛鉱が主で、栃洞坑では灰鉄輝石を母岩とした「杢地鉱」や、石英や方解石を母岩とした高品位な「白地鉱」を採掘していた。そして坑内では花崗斑岩の貫入が認められ、そこから派生した石英脈にはモリブデン(Mo)を主成分とする鉱物が含まれることが古くから知られていた[6]。モリブデンを主成分とする神岡鉱は栃洞坑-200mレベルにおいて花崗斑岩脈近傍の石英脈から見出されている[7]。
神岡鉱はモリブデンの酸化鉱物であるが、モリブデンの硫化物である輝水鉛鉱を密接に伴う。神岡鉱の結晶がまるごと輝水鉛鉱に置き換わっている例も珍しくないと言われる。これは神岡鉱の安定性と産状に起因している。神岡鉱は石英脈中の硫黄分圧が低い部分で特に初期に晶出するが、硫黄分が供給されると反応して輝水鉛鉱が生じる。天然ではどちらかというと硫黄分圧が高い環境のため、それが神岡鉱が稀少鉱物になっている要因だと考えられている[7]。
神岡鉱の結晶は異極的六方ピラミッドと称され、六方晶系の構造がよく反映されている[8,9]。神岡鉱はMoO6八面体からなるシートとFeO4四面体+FeO6八面体からなるシートが交互に重なる構造となっている。そして、モリブデンや鉄の配置だけをみるとそれらはハニカムに並ぶ。こうした構造はフラストレーション系を研究する物理屋に好まれ、磁性の研究が行われている[10, 11]。
写真の標本は古い時代に採集されたものだが産出の坑まではラベルに記載がなかった。角度によっては典型的な六角形の面が見える。結晶自体は神岡鉱であることを確認しているが、やはり割れ目などには輝水鉛鉱が伴われている。
[1] 櫻井欽一, 長島秀夫, 反田栄一 (1952) 本邦産鉱物の研究, 47, 岐阜県神岡鉱山産:燐酸亜鉛銅鉱物(神岡石). 趣味の地学, 5, 170-175.
[2] 南部松夫 (1978) 日本から記載された新鉱物. 渡辺万次郎先生米寿記念論集, 82-100.
[3] 佐々木昭, 由井俊三, 山口光男 (1975) 岐阜県神岡鉱山産新鉱物, Fe2Mo3O8. 日本鉱物学会年会講演要旨集, 9.
[4] Picot D., Johan Z. (1977) Kamiokite. Atlas des Minéraux Métalliques, Mémoires du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, No. 90-1977, 219. (in French)
[5] Ma C., Beckett J.R., Rossman R. (2014) Monipite, MoNiP, a new phosphide mineral in a Ca-Al-rich inclusion from the Allende meteorite. American Mineralogist, 99, 198-205.
[6] 東尚七 (1967) 神岡鉱山栃洞坑. 日本鉱業会誌, 83, 1800-1808.
[7] 第一文献
[8] 第二文献
[9] Endo Y., Kanazawa Y., Sasaki A. (1986) External form of kamiokite crystal. Bulletin of the Geological Survey of Japan, 37, 367-371.
[10] Nakayama S., Nakamura R., Akaki M., Akahoshi D., Kuwahara H. (2011) Ferromagnetic Behavior of (Fe1-yZny)2Mo3O8 (0≤y≤1) Induced by Nonmagnetic Zn Substitution. Journal of Physical Society of Japan, 80, 104706.
[11] Abe H., Sato A., Tsujii N., Furubayashi T., Shimoda M. (2010) Structural refinement of T2Mo3O8 (T=Mg, Co, Zn and Mn) and anomalous valence of trinuclear molybdenum clusters in Mn2Mo3O8. Journal of Solid State Chemistry, 183, 379-384.
IMA No./year: 1976-003
IMA Status: A(approved)
模式標本:岡山大学理学部地球科学科(ONM-02)、国立科学博物館、National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA (136583)(Hand book of Mineralogyから引用)
布賀石 / Fukalite
Ca4Si2O6(CO3)(OH)2
模式地:岡山県高梁市備中町布賀西露頭
第一文献:Henmi C., Kusachi I., Kawahara A., Henmi K. (1977) Fukalite, a new calcium carbonate silicate hydrate mineral. Mineralogical Journal, 8, 374-381.
第二文献:Merlino S., Bonaccorsi E., Grabezhev A.I., Zadov A.E., Pertsev N.N., Chukanov N.V. (2009) Fukalite: An example of an OD structure with two-dimensional disorder. American Mineralogist, 94, 323-333

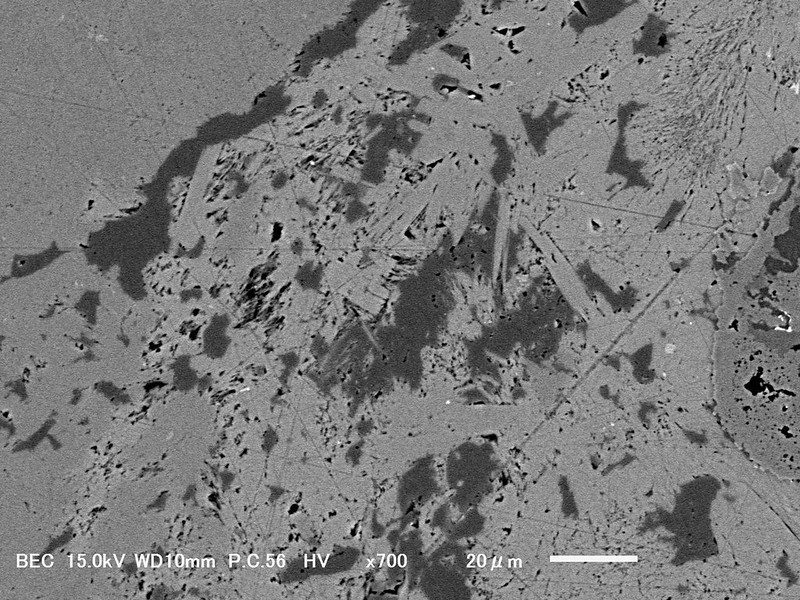
布賀西露頭から得られた標本とそのSEM写真。クリーム色部に布賀石が分布し、ミクロンサイズの針状結晶となっている。
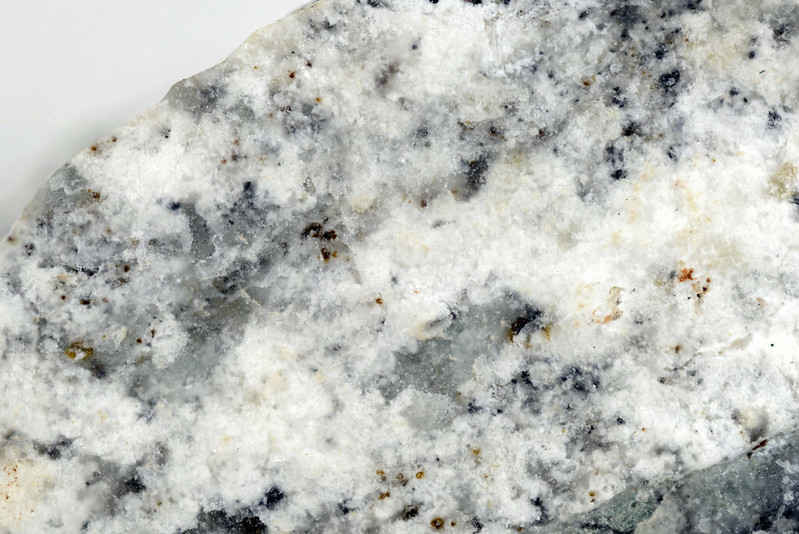
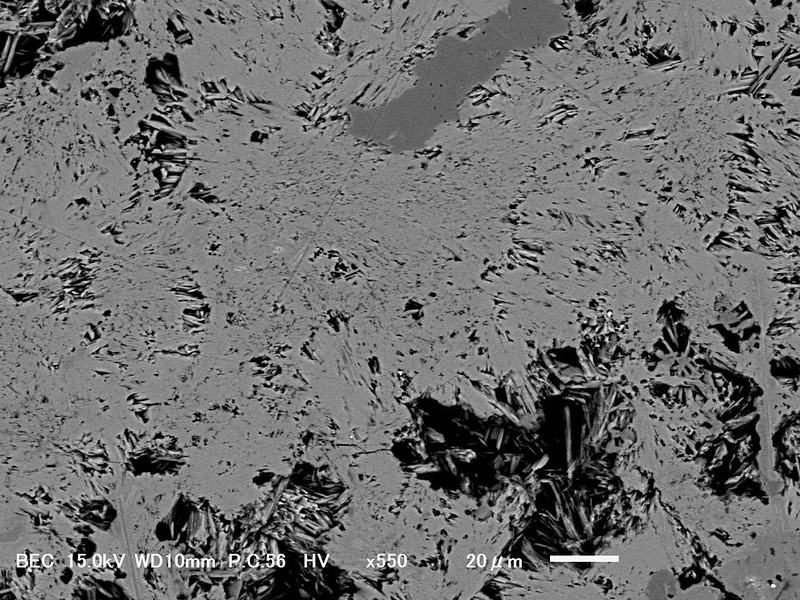
岡山県井原市芳井町三原鉱山から得られた標本とそのSEM写真。白色部に布賀石が分布し、同様にミクロンサイズの針状結晶となっている。
布賀石は岡山大学の逸見らによって発見された新鉱物で、最初に見出された岡山県備中町布賀に因んで命名された。記載論文では岡山県三原鉱山と広島県久代からの布賀石も同時に記載されており、いずれも高温スカルンとして知られていた産地である[1]。筆頭著者の逸見吉之助は布賀石の発見により日本鉱物学会から1978年に櫻井賞(第15号メダル)を受賞した。
布賀において布賀石が発見された正確な産地は論文には記載が認められないが、いわゆる西露頭が産地だと思われる。布賀では石灰岩中にモンゾニ岩脈が走っており、それとの間にコンタミ岩帯やゲーレン石-スパー石帯が認められるが、西露頭ではコンタミ岩帯があまりなく、ゲーレン石-スパー石帯が石灰岩と共に大きな分布を示す。また露頭の西側には安山岩が横切っており、その近傍から得られる紫色のスパー石は標本として有名であろう。この西露頭が学術論文に登場するのは1973年のことで、その際に本邦初産となる灰チタン石(Perovskite)が報告されている[2]。同年にこの西露頭から見つかった備中石が新鉱物として申請され、1976年に申請された布賀石は備中石に続く新鉱物となった。
布賀石は海外でも見出されている。ルーマニアでは布賀と同様に高温スカルンの生成物としての産出が知られる[3]。また、ロシアではスカルン中に生じた水酸エレスタド石を切る脈としての産状(Gumeshevsk鉱山)や、Dovyrenかんらん岩体の変質を被ったゼノリス中に生じることが報告されている [4,5]。そして布賀石の結晶構造はGumeshevsk鉱山から産した結晶を用いて精密に調べられ、いくつかの多形が存在しうることが明らかとなった[5]。
布賀石は高温スカルンに産出するが生成時期は反応の最後期で、スパー石(Spurrite: Ca5(SiO4)2(CO3))の分解物として生じたと考えられている[1]。写真は布賀西露頭および三原鉱山から得られた布賀石の標本となる。西露頭の標本ではベージュ色の濃い部分に布賀石が高密度に存在している。三原鉱山の標本では白色部に布賀石が存在する。布賀石の結晶は肉眼では認識できないが、SEMにおいてはミクロンスケールの板状~柱状結晶が確認できる。
[1] 第一文献
[2] 草地功, 逸見千代子, 逸見吉之助 (1973) 岡山県備中町布賀産ペロブスカイト. 鉱物学雑誌, 11, 219-226.
[3] Marincea S., Dumitras D.G., Ghinet C., Bilal E. (2015) The occurrence of high-temperature skarns from oravita (Banat, Romania): a mineralogical overview. Canadian Mineralogist, 53, 511-532.
[4] Grabezhev A.I., Gmyra V.G., Pal’guyeva G.V. (2004) Hydroxylellestadite metasomatites from Gumeshev skarn porphyry copper deposit, middle Urals. Doklady Earth Science, 394, 196-198.
[5] 第二文献
IMA No./year: 1976-012
IMA Status: A(approved)
模式標本:東北大学理学部、山口大学工学部(第一文献から引用)
三原鉱 / Miharaite
PbCu4FeBiS6
模式地:岡山県井原市三原鉱山(旧:芳井町)
第一文献:Sugaki A., Shima H., Kitakaze A. (1980) Miharaite, Cu4FePbBiS6, a new mineral from the Mihara mine, Okayama, Japan. American Mineralogist 65, 784-788.
第二文献:Petrova I.V., Pobedimskaya E.A., Bryzgalov I.A. (1988) Crystal structure of micharaite Cu4FePbBiS6. Doklady Akademii Nauk SSSR, 299, 123-127.
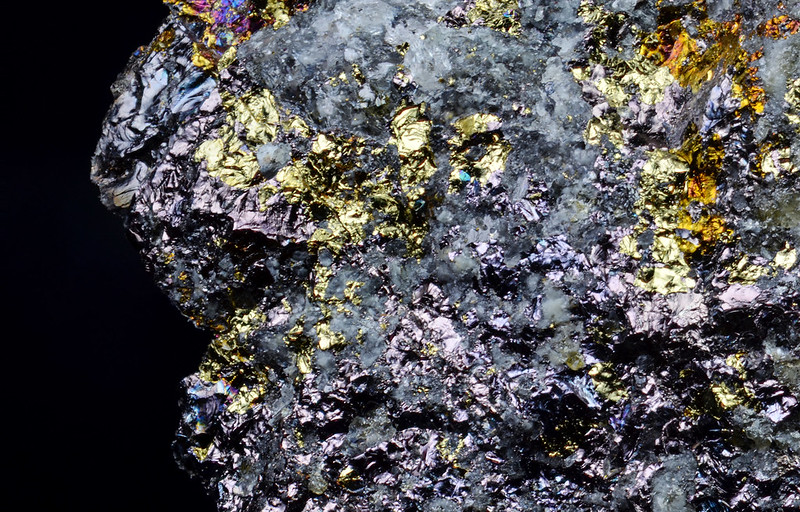
模式地標本 ザラメ状の石英に斑銅鉱と黄銅鉱が散らばるような鉱石が三原鉱の母岩となっている。写真の標本は鉱山の稼働中に得られたもので、こういった鉱石は鉱山のズリでは見かけない。
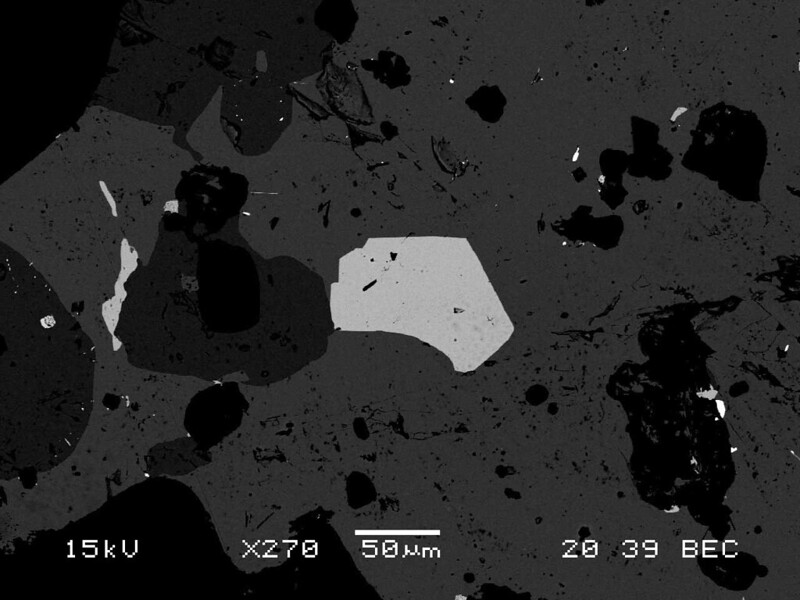
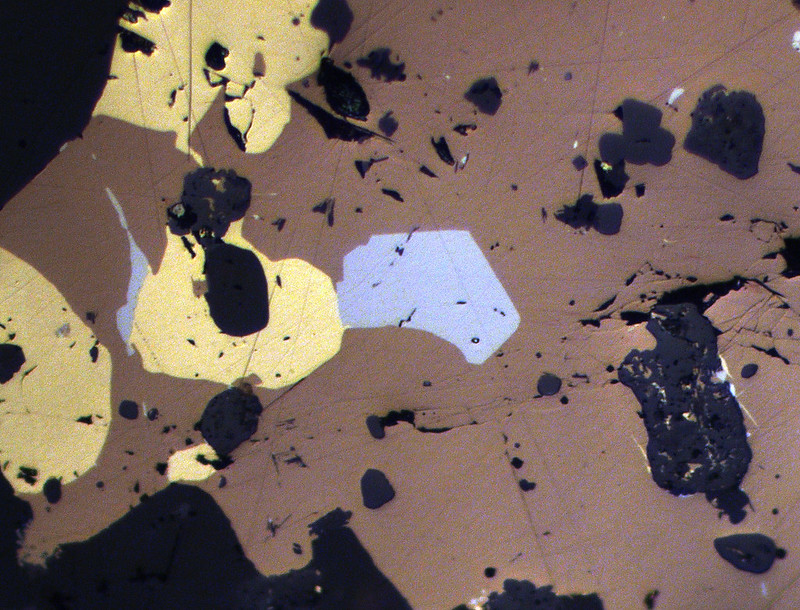
上記標本の薄片SEM写真と反射顕微鏡写真。中央が三原鉱で、その周りは班銅鉱と黄銅鉱。
三原鉱は東北大学の苣木らによって発見された新鉱物で、発見地の三原鉱山に因んで「三原鉱(Miharaite)」と命名された。今でこそ「Miharaite」と言えば三原鉱を指すのだが、古い時代に「Miharaite」は岩石名であった。1910年代、日本の玄武岩や安山岩はことごとくケイ酸過剰な値を示すことが報告されるようになると、異常な現象ということで世界から注目が集まった。そして伊豆諸島・三原島の溶岩はそういった異常な岩石の典型例だったので、東京大学の坪井[1]はその岩石を三原岩(Miharaite)と呼んだ。しかし時代が下って、ケイ酸過剰の原因として石基中のクリストバル石や鱗珪石の存在が理解されるようになると、三原岩として特別扱いする意義は無くなった。三原鉱が発見された1976年ですでに三原岩の名称は過去のものとなっており、鉱物の学名としてMiharaiteが用いられることに何も問題は無くなっていた。
三原鉱山はスカルン型の鉱床で、一部には高温スカルンも伴っている。黄銅鉱を主要鉱石としており、富鉱には斑銅鉱が伴われていた。坑道を深く進むほど銅の品位が高くなるという特徴があり、三原鉱が見つかった鉱石は鉱山の最深部(11-12レベル)から採集されたと記載されている。そこからまず見つかったのがウィッチヘン鉱(Wittichenite:Cu3BiS3)であった[2]。ウィッチヘン鉱は斑銅鉱や方鉛鉱の中に数十ミクロンの不定形もしくは水滴形状で存在していたことから、高温では斑銅鉱に溶け込んでいたビスマス成分が、温度の低下と共に排出された結果の生成物であると考えられた[3]。そして、ウィッチヘン鉱と全く同じ産状で三原鉱が見出された。三原鉱はウィッチヘン鉱よりも一回り大きく、最大で300ミクロンと記載されている。
三原鉱の分析には波長分散形の検出器が付属した走査型電子顕微鏡(EPMA)が用いられている。今でこそEPMAによる鉱物の分析はかなりの信頼性をもって受け止められているが、この時代はEPMAの導入からまだ間もないことから、精度や信頼性など十分とは言いがたいと評価されていた。苣木はEPMA研究チームの一員として積極的にEPMAを用いた研究を展開し[4]、長年かけて硫化鉱物に最適化された分析条件をあらかじめ求め、その上で三原鉱は丁寧に分析されている[5-10]。6点の平均値として、三原鉱の化学式はCu4.09Fe1.00Pb1.01Bi1.00S5.91が得られている。三原鉱の結晶構造については第一文献ではプリセッションカメラで測定が行われ、空間群の候補までは明らかにされていた。その後、ロシア産の試料によって構造が明らかとなった[11]。
三原鉱は1975年に三原鉱山で最初に見つかったが、翌1976年には岡山県伊茂岡鉱山からも見出され、最近では山形県大張鉱山からも報告がある[12-14]。写真の標本は模式地である三原鉱山から産出した標本で、鉱石は鉱山の稼働時に採集されたものだと伝え聞いている。ザラメ状石英の中に黄銅鉱と斑銅鉱が散らばっている鉱石で、こういった鉱石はズリではお目にかかったことがない。破断面から三原鉱を見つけることはほぼ不可能であるが、切断面では特徴的な青みがかった灰色の反射色が観察できる。一方、ズリで採集できる鉱石は粘板岩に斑銅鉱が入っているタイプで、これには三原鉱はまったく見つからなかった。
[1] Tsuboi S. (1918) Notes on miharaite, 地質学雑誌, 25, 47-58.
[2] 添田晶 (1963) 中国地方中央地区における後期中生代の金属鉱化作用. 広島大学地学研究報告, 12, 39-71.
[3] 第一文献
[4] EPMAグループ(1974) EPMAによる鉱物の定量分析に関する基礎的研究. 鉱物学雑誌, 11, 3-75.
[5]苣木淺彦, 島敞史, 北風嵐 (1974) ELECTRON PROBE MICROANALYSERによるCu・Bi・S系鉱物の化学組成に関する研究−−(1)ウィチヘン鉱(クラプロート鉱). 岩石鉱物鉱床学会誌, 69, 32-43.
[6] 苣木淺彦, 島敞史, 北風嵐(1970)Electron Probe Microanalyserによる硫化鉱物の定量分析に関する基礎的研究(I). 山口大学工学部研究報告, 21(2), 209-219.
[7] 苣木淺彦, 島敞史, 北風嵐(1972)Electron Probe Microanalyserによる硫化鉱物の定量分析に関する基礎的研究(II). 山口大学工学部研究報告, 23(2), 39-46.
[8] 苣木淺彦, 島敞史, 北風嵐(1973)Electron Probe Microanalyserによる硫化鉱物の定量分析に関する基礎的研究(III): 天然産Bi-Sb-S系鉱物の化学組成について. 山口大学工学部研究報告, 23(3), 21-26.
[9] 苣木淺彦, 島敞史, 北風嵐(1973)Electron Probe Microanalyserによる硫化鉱物の定量分析に関する基礎的研究(IV). 山口大学工学部研究報告, 24(1), 39-45.
[10] 苣木淺彦, 島敞史, 北風嵐(1973)Electron Probe Microanalyserによる硫化鉱物の定量分析に関する基礎的研究(V). 山口大学工学部研究報告, 24(3), 41-46.
[11] 第二文献
[12] 苣木淺彦, 島敞史, 北風嵐(1975)岡山県三原鉱山産Cu-Fe-Pb-Bi-S鉱物について.日本鉱物学会年会講演要旨集, 35.
[13] 苣木淺彦, 島敞史, 北風嵐(1976)三原鉱(Miharaite)の岡山県伊茂岡鉱山における新産出について. 日本鉱山地質学会・日本岩石鉱物鉱床学会・日本鉱物学会連合学術講演会講演要旨集,138.
[14] Izumino Y., Nakashima K., Nagashima M. (2014) Cuprobismutite group minerals (cuprobismutite, hodrušite, kupčíkite and padĕraite), other Bi-sulfosalts and Bi-tellurides from the Obari mine, Yamagata Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 109, 177-190.
IMA No./year: 1976-016
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(M-24586); National Museum of Natural History, Washington,D.C., USA (136584)(Hand book of Mineralogyから引用)
中宇利石 / Nakauriite
Cu8(SO4)4(CO3)(OH)6·48H2O(第一文献)
(Mg,Cu)x(CO3)y(OH)z•nH2O (文献[6])
(Mg3Cu2+)(OH)6(CO3)・4H2O (文献[8])
模式地:愛知県新城市中宇利鉱山
第一文献:Suzuki J., Ito M., Sugiura T. (1976) A new copper sulfate-carbonate hydroxide hydrate mineral, (Mn,Ni,Cu)8(SO4)4(CO3)(OH)6·48H2O, from Nakauri, Aichi Prefecture, Japan, Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 71, 183-192.
第二文献:設定無し
中宇利石は愛知教育大学の鈴木重人(すずきじゅうじん)らによって発見されたスカイブルーの美しい新鉱物で、発見地の中宇利鉱山に因んで命名された。記載論文の筆頭著者の鈴木は中宇利石発見の功績により、1977年に櫻井賞(第14号)が授けられた。
中宇利鉱山は新城市の南東に分布する蛇紋岩体に胚胎された銅-鉄を資源とする鉱山で、1950年代まで稼働していたようだが[1]、その沿革はあまり詳しく伝わっておらず研究例もほとんど無い。おそらくは戦時中に稼働していたのだろう。鈴木らがこの中宇利鉱山に注目した経緯も論文からは読み取れないが、吉川石の研究が強く関わっていると推測している。中宇利鉱山から数キロ程度北にも小規模な蛇紋岩体が分布しており、そこの蛇紋岩の表面に白色の魚卵状~腎臓状集合の鉱物が生成していた。鈴木らはその詳細を調べ、Mg5(CO3)4(OH)2・8H2Oの化学組成で33.2Åの周期をもつ鉱物であると主張した[2]。そして鈴木らはこの鉱物に吉川石(Yoshikawaite)と命名してIMAへ申請を行ったのだが、1970年に承認されていたダイピング石(Dypingite): Mg5(CO3)4(OH)2·5H2Oとの誤認が疑われ吉川石は承認されなかった[3]。鈴木はその後も蛇紋岩地帯の調査を継続し、1975年には後の中宇利石となる鉱物について「Namaqualith様鉱物」として報告している[4]。
中宇利石はCu8(SO4)4(CO3)(OH)6·48H2Oの化学組成をもつ新鉱物として1976年に承認されている。結晶構造については未だに解かれていないが、粉末のX線回折パターンは非常に明瞭であり、特にd = 7.3Åに強い回折線がある。そのため中宇利石は主に粉末のX線回折パターンによって同定され、今日までに多くの産地が知られている。その一方で化学組成については、鈴木らのデータは誤っていると私は認識している。その点についても記しておこう。
鈴木らは中宇利石の分析にXRFを用いている。均質で大量の試料ならそれも良いが、XRFは透過力が強くビームもブロードなため、どう考えても中宇利石のような鉱物には向かない。そしてデータは中宇利石+混じり物の値「①」であった。そこで鈴木らはその混じり物がクリソタイルのみだと仮定した上で、クリソタイルの値「②」を減算して、中宇利石の化学組成「③」を導出している。そして当初「①」にわずかに含まれていた硫黄(S)については、「②」をさっ引いたこともあって、③ではほとんど主要成分となった。また「①」にあったマグネシウム(Mg)については、「②」ですべて取り去ってしまい、「③」では消滅している。鈴木らのX線回折パターンには明らかに同定できていない鉱物が含まれていたのに、分析についてこのやり方はちょっとムリがある。そして当然だが、中宇利石の化学組成については古くから疑義が投げかけられている。
世界で3番目の中宇利石は1983年にスコットランドで見出された[5]。XRDパターンは模式地の中宇利石と一致するが、スコットランド産については硫黄(S)が検出されなかった。そのため中宇利石には硫黄が含まれない可能性が指摘された。イタリア産の中宇利石を用いた研究では中宇利石の化学組成は「(Mg,Cu)x(CO3)y(OH)z•nH2O」であろうと推測されている[6]。x, y, zやnの数値の詳細ついてはこれからの課題であるが、日本での最近の研究では岡山産中宇利石の分析で(Mg6.19Cu1.77Ni0.02Zn0.01Fe0.01)Σ8(SO4)0.01(CO3)(OH) 13.99・13.44H2Oが報告されている[7]。
ごく最近には鈴木らのIRスペクトルも再検討され、注意深く観察すると鈴木らのIRスペクトルにはSO42-に起因するピークが存在しないことが指摘された[8]。そのため中宇利石の化学組成、特に硫酸塩鉱物であるという主張はもはや受け入れられることはない。文献[8]によると鈴木らのIRスペクトルを素直に解釈すれば化学組成は(Mg3Cu2+)(OH)6(CO3)・4H2Oとなるようだ[8]。写真の標本は模式地および三重県、埼玉県、高知県の中宇利石となる。いずれも分析をしたところ文献[8]の提案とほとんど一致する。中宇利石の化学組成は改訂されなくてはならない。また、第一文献が報告した格子定数は間違っている可能性が指摘されている[9]。構造解析が成功し情報が更新されることを願う。
[1] Matsubara S., Kato A. (1993) Gaspeite, glaukosphaerite, mcguinessite and jiamborite in serpentinites from Shinshiro City, Aichi Prefecture, Japan. Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 88, 517-524.
[2] Suzuki J., Ito M. (1973) A new magnesium carbonate hydrate mineral, Mg5(CO3)4(OH)2・8H2O, from Yoshikawa, Aichi Prefecture, Japan. The Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 68, 353-361.
[3] 鈴木重人, 杉浦孜, 吉岡小夜子(1978)Artinite より”Yoshikawaite”の生成 : 鉱物. 日本地質学会学術大会講演要旨, 第85年学術大会, 328.
[4] 伊藤正裕, 鈴木重人, 杉浦孜(1975)愛知県中宇利産Namaqualith様鉱物について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 70, 139.
[5] Braithwaite R.S.W., Pritchard R. (1983) Nakauriite from Unst, Shetland. Mineralogical Magazine, 47, 84-85.
[6] Palenzona A., Martinelli, A. (2007) La nakauriite del Monte Ramazzo, Genova. Rivista Mineralogica Italiana, 31, 48-51.
[7] 錦郡雄基, 池内大起, 中野良紀, 小林祥一, 岸成具(2017)岡山県北房地域に産するMgに富むnakauriite. 日本鉱物科学会2017年年会講演要旨集, R1-P09.
[8] Chukanov and Vigasina (2019) Some Examples of the Use of IR Spectroscopy in Mineralogical Studies. In Vibrational (Infrared and Raman) Spectra of Minerals and Related Compounds, 1-17.
[9] 錦織雄基, 門馬綱一, 宮脇律郎, 小林祥一, 岸成具 (2018) 岡山県北房産Mgに富むnakuriiteの結晶構造の検討. 日本鉱物科学会2018年年会講演要旨, R2-P03.
IMA No./year: 1976-032
IMA Status: Rn(Renamed)
模式標本:国立科学博物館(M21067); 秋田大学鉱山学部; National Museum of Natural History, Washington,D.C., USA (136398)(Hand book of Mineralogyから引用)
ソーダフッ素魚眼石 / Fluorapophyllite-(Na) (原記載はNatroapophyllite)
NaCa4Si8O20F・8H2O
模式地:岡山県高梁市山宝鉱山(旧:成羽町)
第一文献:Matsueda H., Miura Y., Rucklidge J., Kato T. (1981) Natroapophyllite, a new orthorhombic sodium analog of apophyllite I. Descsription, occurrence, and nomenclature. American Mineralogist 66, 410-415.
第二文献:Miura Y., Kato T., Rucklidge J., Matsueda H. (1981) Natroapophyllite, a new orthorhombic sodium analog of apophyllite II. Crystal structure.American Mineralogist 66, 416-423.

上標本のSEM写真
分析するとカリウム(K)はほとんど検出されず、全体的に端成分に近い標本であった。
ソーダフッ素魚眼石は岡山県成羽町(現:高梁市)に位置する山宝鉱山から見出された新鉱物で、九州大学大学(当時)の松枝大治によって見出された。松枝は九州大学における卒論から博士論文までの長期間を山宝鉱山の調査に費やし、ソーダフッ素魚眼石はその一連の研究過程で見出された新鉱物になる。当初に記載された学名はNatroapophyllite[1]であったが、2008年にApophyllite-(NaF)[2]と改名され、2013年に再度Fluorapophyllite-(Na)[3]へと改名され、これが現在の学名となっている。
山宝鉱山は花崗岩と石灰岩の接触変成作用によって生じた典型的なスカルン鉱床で、磁鉄鉱を主な鉱石とする鉄山であった。石灰岩と花崗岩との接触部は「ホワイトスカルン」と称されており、主に白色の鉱物の集合体からなっていた。その中にゼオフィル石(zeophyllite)やクスピディン(cuspidine)といったフッ素含有ケイ酸塩鉱物と共に帯状構造を成してソーダフッ素魚眼石が産出する。ソーダフッ素魚眼石は主に石灰岩側に多く産出し、花崗岩側では一般的なカリフッ素魚眼石(Fluorapophyllite-(K))が多くなる傾向が認められる。このような傾向は生成時の温度に依存する可能性が記されている[1]。なお、一連のフッ素含有ケイ酸塩鉱物は熱水変質で形成され、それは花崗岩の貫入の後に生じた作用だと考えられている。
いわゆる魚眼石の結晶構造解析は最も多産するカリフッ素魚眼石を用いて行われた[4,5]。わりと特異な構造で、4つのCa-(O,F)キャップドプリズム多面体がフッ素(F)を中心に据えてそれを共有し、c軸方向の上下にあるキャップは中心を開けるように4つのSiO4四面体で囲まれている。そのため結晶構造内に大きな隙間があるのだが、カリウムなど一価の陽イオンはキャップドプリズム多面体の側面に配置する。そのためゼオライトのように陽イオンに自由度は少なく、水分子で囲まれた四角柱の配位多面体を形成する。このような構造が正方晶系の対称性で現れるのが最も普通であるが、ソーダフッ素魚眼石は対称性がやや低下して斜方晶系を示す[1,6]。ただし元素の相対的な位置関係は正方晶系の場合と変わらないため、今後に正方晶系のソーダフッ素魚眼石が見つかったとしてそれは新鉱物になるのではなく、ソーダフッ素魚眼石のポリタイプとして扱われる。例えばFluorapophyllite-(Na)-1Tという表記になるだろう。
山宝鉱山を模式地とする日本産新鉱物は今のところこのソーダフッ素魚眼石のみであるが、研究がはじまった当時(1970年あたり)はさらに二つの新鉱物が期待されていた[7-9]。それぞれ鉄バスタム石(Ferrobustamite:CaFe2+Si2O6)とマンガンバビントン石(Manganbabingtonite:Ca2Mn2+Fe3+Si5O14(OH))である。しかしながら鉄バスタム石のほうは出典を遡ると1937年にスコットランドから見出された例がすでにあり、マンガンバビントン石は1966年にロシアで見出されていた。その時代は新鉱物の審査に先立って記載論文が発表されることもしばしばあり、IMAの承認が遅れることもあった。その間、研究者らは未承認の鉱物として認識することとなり、このような事態が生じることもあった。
写真の標本は模式地である山宝鉱山から採集された標本で、淡褐色部がソーダフッ素魚眼石に該当する。SEMで分析して見たところカリウムをほとんど含まない端成分に近い組成となっていた。この標本は山田滋夫氏に提供していただいた。第一文献によるとホワイトスカルン内には晶洞も見られ、その中にはソーダフッ素魚眼石の結晶も産出したようで、その電子顕微鏡写真が掲載されている。
[1] 第一文献
[2] Burke E.A.J. (2008) Tidying up mineral names: an IMA-CNMNC scheme for suffixes, hyphens and diacritical marks, The Mineralogical Record, 39, 131-135.
[3] Hatert F., Mills S.J., Pasero M., Williams P.A. (2013) CNMNC guidelines for the use of suffixes and prefixes in mineral nomenclature, and for the preservation of historical names. European Journal of Mineralogy, 25, 113-115.
[4] Colville A.A., Anderson C.P., Black P.M. (1971) Refinement of the crystal structure of apophyllite I. X-ray diffraction and physical properties. American Mineralogist, 56, 1222-1233.
[5] Chao G.Y. (1971) The refinement of the crystal structure of apophyllite II. Determination of the hydrogen positions by X-ray diffraction. American Mineralogist, 56, 1234-1242.
[6] 第二文献
[7] Matsueda H. (1973) Iron-wollastonite from the Sampo mine showing properties distinct from those of wollastonite. Mineralogical Journal, 7, 180-201.
[8] Matsueda H. (1980) Pyrometasomatic Iron-Copper Ore Deposits of the Sampo Mine, Okayama Prefecture, Part 1. Geology and Mineralogy. Journal of the Mining College, Akita University, Series A, Mining Geology, 5, 15-77.
[9] 藤田良治, 成田佳子(2012)北海道大学総合博物館ニュース. 24, pp.15.
IMA No./year: 1976-045
IMA Status: A(approved)
模式標本:東北大学(第一文献から引用); 国立科学博物館(M-21492)(Hand book of Mineralogyから引用); National Museum of Natural History, Washington,D.C., USA (136582)(Hand book of Mineralogyから引用)
上国石 / Jôkokuite
Mn2+(SO4)・5H2O
模式地:北海道上ノ国町上国鉱山
第一文献:Nambu M., Tanida K., Kitamura T., Kato E. (1978) Jôkokuite, MnSO4·5H2O, a new mineral from the Jôkoku mine, Hokkaido, Japan. Mineralogical Journal, 9, 28-38.
第二文献:Caminiti R., Marongiu G., Paschina G. (1982) A comparative X-ray diffraction study of aqueous MnSO4 and crystals of MnSO4·5H2O. Zeitschrift für Naturforschung A Physical Science, 37, 581-586.
上国石は東北大学の南部松尾らによって見出された新鉱物で、上国鉱山に因んで命名された。記載論文の著者の一人である加藤栄一によって1976年に見出され、1号脈50mレベルにおいて坑道壁に生じたピンク色を帯びた鍾乳石として試料が採集されている[1]。上国石は後に近隣の稲倉石鉱山からも産出した[2]。
上国鉱山は渡島半島の南西部に位置し、主にマンガン・鉛・亜鉛・銀を対象に稼働されていた。鉱床は広義の浅熱水性鉱脈鉱床で、いわゆる「稲倉石型」と称される鉱床に分類されている。具体的には低硫化系熱水による亀裂充填型の鉱床で、粘板岩やチャートを母岩として菱マンガン鉱を主な沈殿物としている。鉱石鉱物についてはおおむね一般的な種類であるが、二次鉱物に関しては上国石をはじめとした含水硫酸塩鉱物が特徴的に産出している。文献[1,3]には、ズミク石(Szmikite:Mn2+(SO4)・H2O)、アイレス石(Ilesite:Mn2+(SO4)・4H2O)、ローゼン石(Rozenite:Fe2+(SO4)・4H2O)、マラー石(Mallardite:Mn2+(SO4)・7H2O)、緑礬(Melanterite:Fe2+ (SO4)・7H2O)、舎利塩(Epsomite:Mg(SO4)・7H2O)皓礬(Goslarite:Zn(SO4)・7H2O)などが挙げられている。
上国石はMn2+(SO4)・5H2Oの化学組成を持つ鉱物種であり、結晶構造は合成物を使って1982年に解明された[4]。上国石に相当する物質は古くから知られており、合成実験によって1841年にはその存在が知られている[1]。水分量の異なるズミク石やアイレス石などは上国石よりも先に知られていたことから、上国石についても古くから天然における存在が予測されていたのかもしれない。一方で上国石はズミク石やアイレス石からの脱水・加水で生じたのではなく、気温15℃・湿度98%以上の環境において坑道壁からしみ出した地下水から直に堆積したと考えられている。ただし後述するように上国石が安定な環境は非常に限られている。例えば気温20度・湿度50%の室内に回収した時点で上国石は脱水を起こし、標本の表面には粉末状のアイレス石が生じてしまう。そしてそのままの環境では1ヶ月の後には上国石の鍾乳石は完全にアイレス石に変質してしまう。
上国石が室内環境においてはアイレス石に変化してしまうことから、上国石の安定的な保管には高湿な環境を維持することが重要だと言われている。しかしそれだけでは十分ではなく、温度についても注意を払う必要がある。例えば9℃以下で多湿環境に置かれると上国石は不安定となり、より加水されたマラー石へ変質する。また27℃以上ではたとえ高湿度環境であったとしても、上国石は脱水してズミク石に変化してしまう[5]。24.5℃でも上国石は脱水するという報告もあるようだ[1]。ただしその反応は可逆的であるため、多湿かつ10-24℃程度の環境を維持すれば、標本は上国石として保存できる。
写真の標本は上国石として採集された標本となる。室温で保管されていた標本として手に入れたため、その時点ではアイレス石に変質していたと推測される。今はこの標本の一部を多湿環境で密封した上でデシケータに保管してある。そろそろ上国石に戻った頃合いだろうか。
[1] 第一文献
[2] 松枝大治, 茨城誠一, 黒沢邦彦 (1980) 北海道稲倉石鉱山産上国石. 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, P68.
[3] 南部松夫, 谷田勝俊 (1976) 北海道上国鉱山産舎利塩および含マンガン含鉄苦灰石について. 地学研究, 27, 233-240.
[4] 第二文献
[5] Cottrell F.G. (1900) On the solubility of manganous sulphate, The Journal of Physical Chemistry, 4, 637-656.
IMA No./year: 1977(1997s.p.)
IMA Status: A(approved)
模式標本:不明もしくは設定無し
灰単斜プチロル沸石 / Clinoptilolite-Ca
Ca3(Si30Al6)O72·20H2O
模式地:福島県西会津町車峠
第一文献:Koyama K., Takeuchi Y. (1977) Clinoptilolite: The distribution of potassium atoms and its role in thermal stability. Zeitschrift für Kristallographie, 145, 216-239.
第二文献:Coombs D.S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J.D., Liebau F., Mandarino J.A., Minato H., Nickel E.H., Passaglia E., Peacor D.R., Quartieri S., Rinaldi .R, Ross M., Sheppard R.A., Tillmanns E., Vezzalini G., (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names, The Canadian Mineralogist, 35, 1571-1606.
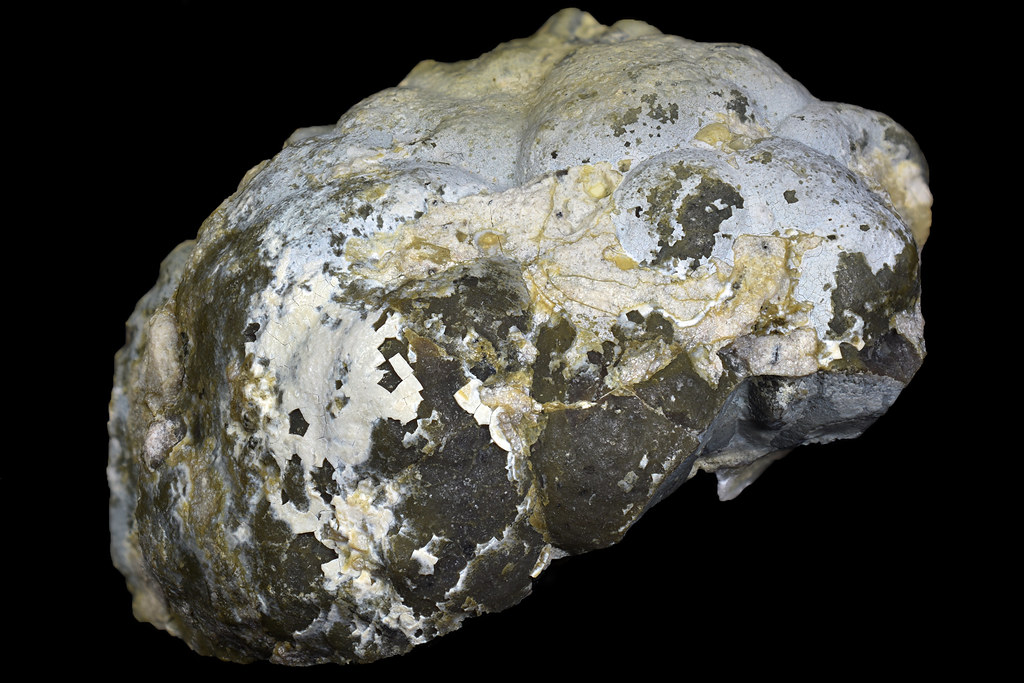

福島県西会津町宝坂
オパール球果中の空隙に灰単斜プチロル沸石が生じる。
沸石族の命名規約が成立する以前、鉱物種は構造のフレームワークにのみ基づいて分類されており、内包される陽イオンでの区別は行われていなかった。近代になり鉱物種を分ける際に化学組成について50%則の適用が原則となったことから、命名規約では陽イオンで種を分けることを基本方針としており、沸石族は一気に数を増やすことになっている。そして灰単斜プチロル沸石であるが、この鉱物は新種として申請された経緯を持たず、沸石族の命名規約が成立した際に誕生した新種である。東京大学の小山和俊と竹内慶夫によって調べられた単斜プチロル沸石がカルシウム(Ca)タイプであったことから、沸石族の命名規約が成立した際に独立の鉱物種として灰単斜プチロル沸石(Clinoptilolite-Ca)が誕生した。
名前の経緯はかなりややこしい。まずモルデン沸石(Mordenite)という沸石が先に知られており、それは毛状の形態を特徴としていた。そしてその形態上の特徴について、ギリシャ語で羽毛を意味する「Ptylon」から、モルデン沸石がプチロル沸石(Ptilolite)と呼ばれるようになった。そのプチロル沸石について詳しく観察すると毛状結晶とは別に、わずかに板状となる結晶が見つかるようになる。そこで、板状の結晶のことをモルデン沸石と呼び、毛状結晶をプチロル沸石と呼ぶことになった。ところが1923年、モルデン沸石と呼ばれた板状結晶はプチロル沸石と呼ばれた毛状結晶とは構造が異なる可能性が示唆され、板状結晶が単斜プチロル沸石(Clinoptilolite)と呼ばれるようになる[1]。そうして古くから知られていたモルデン沸石の名称が消えかかるが、毛状結晶については「モルデン沸石(プチロル沸石)」という両論併記となり、板状結晶である「単斜プチロル沸石」と区別されるようになる[2]。時代が下って、モルデン沸石(プチロル沸石)と単斜プチロル沸石がはっきり区別されるようになると、モルデン沸石(プチロル沸石)の表記は避けられるようになり、モルデン沸石のみの表記で統一されるようになった。さらに単斜プチロル沸石については、命名におけるオリジナルの意味合いはもはや消失しているが、こういった経緯からそのまま単斜プチロル沸石の名称が用いられている[3]。そして現在では単斜プチロル沸石にはカリウム(K)、ナトリウム(Na)、カルシウム(Ca)に卓越する種類が知られ、カルシウムに卓越する単斜プチロル沸石が、ここで取り上げた灰単斜プチロル沸石である。
灰単斜プチロル沸石について、オフィシャルリストに掲載されている第一文献は小山と竹内の論文[4]であるが、その内容は主に構造解析であり、発見自体はまた別の論拠に依っている。第一文献中で構造解析に用いられた結晶は、福島県西会津町車峠から採集された標本であることが紹介されている[5]。それは湊ら[5]によると1968年の夏に東京大学の大塚謙一氏によって採集された、輝沸石によく似た結晶だった。そして、灰単斜プチロル沸石が輝沸石によく似た結晶となるのは極めて当然であった。実は輝沸石系列と単斜プチロル沸石系列の沸石は物質的には同じと言える。両者は共通の結晶構造(骨格タイプコード:HEU)で、組成も連続する。すなわち物質としては輝沸石と単斜プチロル沸石の間に境界線を作ることができないので、単斜プチロル沸石はたんにシリカの多い輝沸石であると考える研究者もいた[6]。しかし、単斜プチロル沸石と輝沸石は明らかに産状が異なる。単斜プチロル沸石は主に沸石岩の構成鉱物として微細な粉として産出するばかりで、その結晶は産出してもかなり小さい。一方の輝沸石は主に熱水で生じ、その結晶は数センチにも成長する。また加熱に対する挙動や、元素置換においてもよく調べればわずかに異なった挙動を示すなど、一緒くたにするのはどうかという議論が続いていた[7]。そうした事情もあって、沸石超族の命名規約は単斜プチロル沸石と輝沸石のためだけの特別ルールを設定することになった。すなわち輝沸石型構造(HEU)においてSi/Al = 4.0を上回る組成を単斜プチロル沸石系列と定義して、輝沸石系列とは分離して扱うことで、それぞれを個別の鉱物として認めている[3]。
沸石族は一価と二価の陽イオンが混在するケースが一般的で、組成式を作る際にその取り扱いに混乱が認められる。たとえばカリウム(K)、ナトリウム(Na)、カルシウム(Ca)に卓越する種類が知られるような場合だと、絶対量をそのまま比較するのではなく、二価の陽イオンについては重みを2倍にして比較する必要がある。例えば灰単斜プチロル沸石を例に出すと、第一文献に掲載されている分析値について二価の陽イオンの重みを2倍にして組成式を組み立てると、次のように表記しなくてはならない;[(Ca0.5)2.80Na1.76K1.05 (Mg0.5)0.34]Σ5.95(Al6.72Si29.20)O72・23.7H2O。CaとNaの絶対量ではCa < Naとなってしまうが、重みをつけた比較では(Ca0.5)=2.8に対してNa=1.76なので、Caに卓越するということになる。
日本から発見された新鉱物について、沸石族は湯河原沸石、灰エリオン沸石、ソーダレビ沸石、そして灰単斜プチロル沸石の4種となっている。その一方で新鉱物だという宣言の元で記載されたのは湯河原沸石のみで、残りの三種については沸石族の命名規約と共に誕生した新鉱物である。こういった種類を新鉱物と見なさない向きもあるようで、鉱物情報が発行している日本産鉱物種などではこの三種は新種の取り扱いとはなっていない。しかしながら国際的には日本産の新鉱物として登録されているため、このページでは灰エリオン沸石、ソーダレビ沸石、そして灰単斜プチロル沸石についても日本産新鉱物種としてカウントしている。
写真は西会津町と桑折町で得られた標本である。西会津町白坂では真珠岩中の小晶洞に微細な灰単斜プチロル沸石が生じている。西会津町宝坂はオパール球果が有名であるが、いわゆるハズレも多い。しかし、内部が空隙の場合はその中に灰単斜プチロル沸石が見られることがあり、むしろこれは標本としてわかりやすい。桑折町もまた古くからの沸石産地でモルデン沸石が著名で、よく見ると灰単斜プチロル沸石ばかりの小晶洞も開いている。新潟県中ノ沢では球果の中に出現し、その結晶はオレンジに色づいている。いずれも輝沸石とは外観が共通であるが、上述のようにSi/Al比で輝沸石とは区別される。
[1] Schaller W.T. (1923) Ptilolite and related zeolites. American Mineralogist, 8, 93-94.
[2] Waymouth C., Thornely P.C., Taylor W.H. (1938) An X-Ray Examination of Mordenite (Ptilolite). Mineralogical Magazine, 25, 212-216.
[3] 第二文献
[4] 第一文献
[5] 湊秀雄, 歌田実, 飯島東 (1971) 福島県車峠産斜プチロル沸石結晶について, 第15回粘土科学討論会講演要旨集, 10.
[6] Hey M.H., Bannister F.A. (1934) Studies on the zeolites. Part VIII. “ Clinoptilolite,” a silica-rich variety of heulandite. Mineralogical Magazine, 23, 556-559.
[7] Bish D.L., Boak J.M. (2001) Clinoptilolite-heulandite nomenclature. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 45, 207-216.
IMA No./year: 1977-020
IMA Status: A(approved)
模式標本:島根大学; 国立科学博物館(M21331)(どちらもHand book of Mineralogyから引用)
加納輝石 / Kanoite
MnMgSi2O6
模式地:北海道八雲町熊石館平町(旧:熊石村)
第一文献:Kobayashi H. (1977) Kanoite, (Mn2+,Mg)2[Si2O6], a new clinopyroxene in the metamorphic rock from Tatehira, Oshima Peninsula, Hokkaido, Japan. Journal of the Geological Society of Japan, 83, 537-542.
第二文献:Arlt T., Armbruster T. (1997) The temperature-dependent P21/c – C2/c phase transition in the clinopyroxene kanoite MnMg[Si2O6]: a single-crystal X-ray and optical study. European Journal of Mineralogy, 9, 953-964.
 小林氏のスケッチによるとA-Dまで以下のようになっている。
小林氏のスケッチによるとA-Dまで以下のようになっている。
A:テフロ石帯(テフロ石+マンバンざくろ石+パイロファン+ガラクス石)
B:炭酸塩帯
C:加納輝石帯(加納輝石+角閃石+マンバンざくろ石+パイロクスマンガン石)
D:角閃石帯(角閃石+マンバンざくろ石+パイロクスマンガン石)
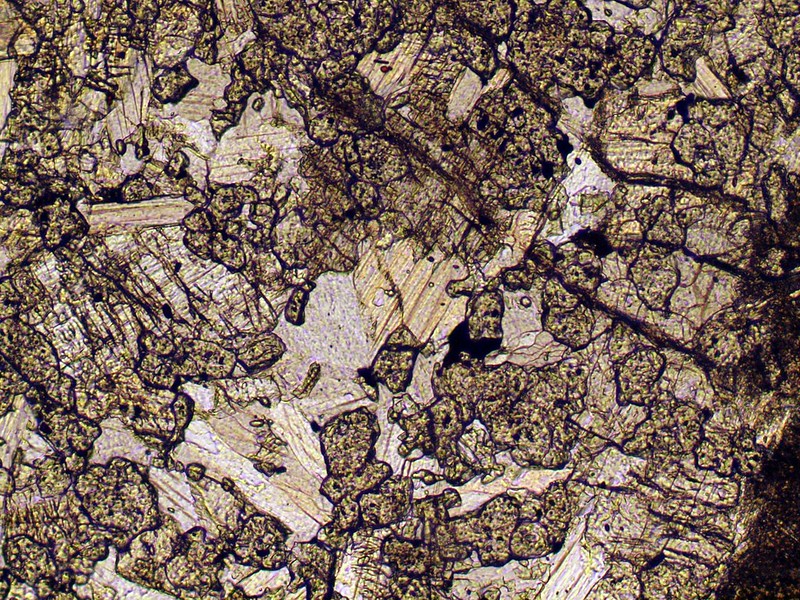
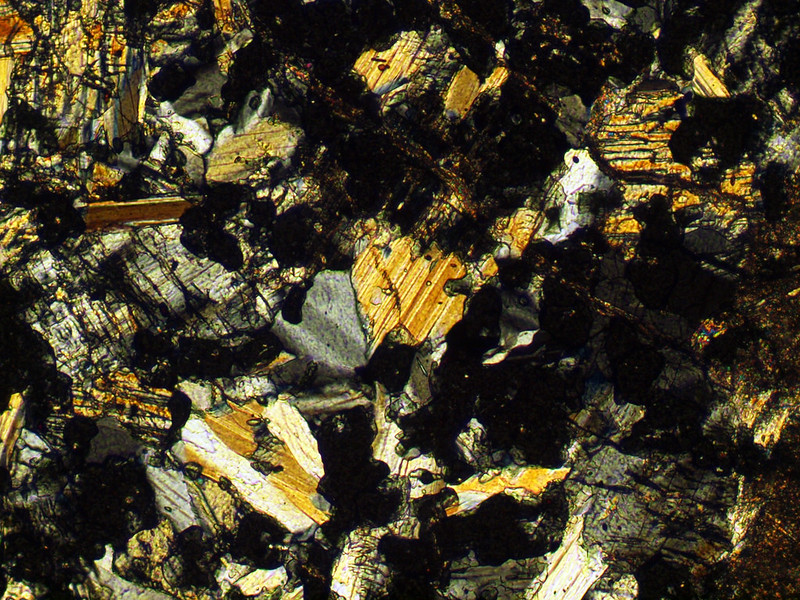
オープンニコル(上)/クロスニコル(下)
中央が加納輝石。加納輝石は100マイクロメートル程度の小粒子の集合となっている。
加納輝石は島根大学の小林英夫によって見出された輝石族の新種で、日本列島基盤岩類の解明に大きく貢献した秋田大学の加納博(1914-2009)に因んで命名された。命名は加納への遅蒔きの還暦祝いであったとされる[1]。日本で発見されている新鉱物のうち、輝石族に属するのは加納輝石のみとなっている(2020年1月現在)。
模式地の館平は渡島半島の日本海側に面しており、付近の海岸には無数の岩礁が点在している。その多くは粘板岩起源の変成岩だが、一部にマンガン鉱物に富む団塊状の岩礁が認められており、加納輝石は一つの岩礁から見出された。現時点でその岩礁を特定することは困難となっているが、第一文献には詳細なスケッチが掲載されており、加納輝石は10m規模の岩礁において西側斜面で見出されている。加納輝石は厚さ数ミリの薄い帯として分布し、園石+テフロ石帯とパイロクスマンガン石+角閃石帯に挟まれる産状を示す[2]。
加納輝石はMnMgSi2O6という理想化学組成を持ち、対称性から単斜輝石であることが示された。この当時、マンガン(Mn)とマグネシウム(Mg)を等量に持つ単斜輝石は合成実験で存在が知られていたものの、天然での産出は加納輝石が初めてであった。結晶構造については合成実験で生成された試料について詳しい検討が行われ、空間群P21/cで示される単斜晶系の構造で、マンガン(Mn)とマグネシウム(Mg)はそれぞれM2席とM1席に分かれていることが明らかとなった[4]。
上述のように加納輝石の存在はMgSiO3―MnSiO3系の合成実験において先に知られており、加納輝石は中間成分で単一相として合成できる。一方で、ややマグネシウムに富む組成を出発物質として合成すると、加納輝石+斜方輝石が出現することもまた知られている[5]。この斜方輝石は理想組成を(Mn,Mg)MgSi2O6として、加納輝石に比較してややマグネシウムに富むという特徴がある。天然においてはSt Joe鉱山(アメリカ)から1984年に見出され、ドンピーコ輝石(Donpeacorite)と名付けられた。1986年には加納輝石の原産地である館平からもドンピーコ輝石が見出されたという報告がある[6]。なお、ややマンガンに富む組成で合成すると加納輝石+パイロクスマンガン石の組み合わせが出現する。館平では主に加納輝石+パイロクスマンガン石の組み合わせが観察される。
上に掲載した写真は模式標本と同じ岩礁から得られた標本で、小林氏の観察スケッチが付属している。加納輝石は「C」で示される幅1センチ未満の帯に濃く含まれており、帯はピンク色を帯びた茶色~ダークマゼンダ色を示す。その色合いは見た目として園石やアレガニー石によく似ている。C帯の一部を分析すると、中身は確かに加納輝石が多いが、角閃石、マンバンざくろ石、パイロクスマンガン石が共存していた。分析値は模式標本と概ね共通でややMn>Mgの特徴を持ち、Mn(Mg,Mn)Si2O6で表すことができる。そのためややMg>Mnとなるべきのドンピーコ輝石はおそらくこの標本中には存在しないだろう。
加納輝石について日本国内の他産地となると文献には続報が見当たらない。一方でMindatによると宮崎県下鶴鉱山が加納輝石の産地として挙げられている。出典は外国人の個人標本となっており詳細はわからなかったのだが、最近になって下鶴鉱山・加納輝石とラベルされた標本を後輩から受け取った。調べてみると確かに加納輝石が入っている。館平のような帯状の分布ではなく、加納輝石は岩石中にやや偏在しながらパッチ状で分布している。結晶サイズは館平よりも小さい。

下鶴鉱山からの加納輝石を含む鉱石の破断面。加納輝石の量は多くないが、アラバンド鉱、テフロ石、マンバンざくろ石、角閃石と共存していた。
[1] 諏訪兼位(2009)元会長 加納 博教授の逝去を悼む. 岩石鉱物科学, 38, 233.
[2] 第一文献
[3] 小林英夫(1977)北海道檜山郡熊石村館平の変成岩(II)Kanoiteの共生関係. 島根大学理学部紀要, 11, 89-95.
[4] 第二文献
[5] Iwabuchi Y., Hariya Y. (1985) Phase equilibria on the join MgSiO3-MnSiO3 at high pressure and temperature. Mineralogical Journal, 12, 319-331.
[6] 山口佳昭, 加納博, 渡辺暉夫, 小林英夫(1986)Kanoiteと共生するdonpeacoriteについて. 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, P70.
IMA No./year: 1977-042
IMA Status: A(approved)
模式標本:九州大学箱崎キャンパス; 国立科学博物館(ナンバー不明); 櫻井標本; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 142945(いずれもHand book of Mineralogyから引用)
種山石 / Taneyamalite
(Na,Ca)Mn2+12(Si,Al)12(O,OH)44
模式地:熊本県矢代市種山鉱山(旧:東陽村)& 埼玉県飯能市岩井沢鉱山
第一文献:Matsubara S. (1981) Taneyamalite, (Na,Ca)(Mn2+, Mg, Fe3+,Al)12Si12(O,OH)44, a new mineral from the Iwaizawa mine, Saitama Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine 44, 51-53.
第二文献:設定無し
種山石は熊本県種山鉱山および埼玉県岩井沢鉱山を模式地とする新鉱物で、種山鉱山にちなんで命名された。九州大学の青木義和らによって種山鉱山の種山石が記載され[1]、岩井沢鉱山の種山石については国立科学博物館の松原聰によって記載された[2]。種山石発見の功績により青木には櫻井賞および第28号メダルが授与されている。
種山石はハウィー石(Howieite)のマンガン(Mn)置換体に相当する鉱物で、ハウィー石が先に鉱物種として確立されている[3]。ハウィー石が1965年にアメリカからの新鉱物として発表されてまもなく、1967年には青木・磯野によって熊本県種山鉱山からハウィー石のマンガン置換体が見出された旨が報告されている[4]。そして1977年になり松原が埼玉県岩井沢鉱山からハウィー石のマンガン置換体を再発見したが、その時点でハウィー石のマンガン置換体はまだ新種として確立されていなかった。そこで松原が新鉱物申請をとりまとめ、鉱物名については先に発見されていた種山鉱山に因んで命名されることになった。種山石自体の構造解析はまだ行われていないが、近縁のハウィー石では構造が解明されている[5]。
ハウィー石-種山石系列の鉱物は高圧低温型の層状マンガン鉱床からしばしば見出され、黒緑色~茶褐色で葉片状または繊維状の集合体となり、それが脈状に分布することが多い。世界的にも産状はほとんど共通で、ハウィー石および種山石は藍閃石片岩相程度の変成作用を受けた鉱床における特徴的な鉱物として知られている[6,7]。日本では御荷鉾帯、秩父帯北帯、黒瀬川構造帯に沿って産地が知られるようになってきた[8]。しかし種山石は依然として世界的には稀産鉱物であり、日本以外では産出例が非常に少ない。
これまでの研究の組成データを眺めるに、ハウィー石-種山石系列は完全固溶体が形成されると思われる。そして外観と組成が連動する傾向があり、黒色が強くなると鉄が多く、黄色みが強いとマンガンが多くなる。高知県加茂山や種山鉱山産の種山石は黒みがかっており、これは分析して見ると鉄がかなり多く、ハウィー石との境界ぎりぎりである。一方で岩井沢鉱山や四国のマンガン鉱床でみつかる種山石は黄色がかっており、こういった色合いだと組成は端成分に近い。
[1] Aoki Y., Akasako H., Ishida K. (1981) Taneyamalite, a new manganese silicate mineral from the Taneyama mine, Kumamoto Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 8, 385-395.
[2] 第一文献
[3] Agrell S.O., Bown M.G., McKie D. (1965) Deerite, howieite, and zussmanite, three new minerals from the Franciscan of the Laytonville District, Mendicino Co., California. American Mineralogist, 50, 278.
[4] 青木義和, 磯野清 (1968) 熊本県種山鉱山産Howieite類似鉱物について. 地質学雑誌, 74, 136.
[5] Wenk H.R. (1974) Howieite, a new type of chain silicate. American Mineralogist, 59, 86-97.
[6] Schreyer W., Abraham K. (1977) Howeite and other high-pressure indicators from the contact aureole of Brezovia, Yugoslavia, peridotite. Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, 130, 114-133.
[7] Wood R.M. (1979) The iron-rich blueschist facies minerals: 2 Howieite. Mineralogical Magazine, 43, 363-370.
[8] 皆川鉄雄, 松田博幸(2002)四国の高P/T型マンガン鉱床および鉄・マンガン鉱床産howieite-taneyamalite系鉱物. 愛媛大学理学部紀要, 8, 1-10.
IMA No./year: 1977-042
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-21727); National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 142978(Hand book of Mineralogyから引用)
長島石 / Nagashimalite
Ba4(V3+,Ti)4(O,OH)2[B2Si8O27]Cl
第一文献:Matsubara S., Kato A. (1980) Nagashimalite, Ba4(V3+, Ti)4[(O,OH)2|Cl|Si8B2O27], a new mineral from the Mogurazawa mine, Gumma prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 10, 122-130.
第二文献:Matsubara S. (1980) The crystal structure of nagashimalite, Ba4(V3+,Ti)4[(O,OH)2|Cl|Si8B2O27]. Mineralogical Journal, 10, 131-142.
模式地:群馬県桐生市茂倉沢鉱山
長島石は国立科学博物館の研究チームにより見出された新鉱物で、日本における鉱物愛好家の草分け的存在である長島乙吉(1890-1969)に因んで命名された。長島氏は1930年頃に鉱物同好会を立ち上げ、「趣味之鉱物」という同人誌を発行して同好の士を募った。その当時は学生であり、後に大家となる櫻井欽一(1912-1993)もまたその会員であった。長島氏は希元素鉱物の採集、発見の功績によって1958年に紫綬褒章を受章している。調査結果は「日本希元素鉱物[1]」という書籍にまとめられ、今では愛好家のバイブルとも言える貴重な書となっている。
1973年の暮れに、群馬県茂倉沢鉱山の鉱石が一般の鉱物愛好家によって国立科学博物館へ持ち込まれた[2]。その鉱石には原田石に類似したエメラルドグリーンの鉱物が伴われており、興味を持った研究チームによって翌年には茂倉沢鉱山の調査が行われた。その際の調査で、青のり状の形態を示すロスコー雲母と緑色板柱状の不明鉱物が見出されている。そして博物館へ持ち帰られた不明鉱物の解明は、松原の博士論文の研究テーマとして扱われることになった。
研究が始まり、この不明鉱物は三価鉄(Fe3+)を主成分にもつタラメリ石(Taramellite)に対してそのバナジウム(V3+)置換体に相当する新鉱物である可能性が高まった。しかし、結晶構造を精密化する段階で問題が生じた。不明鉱物はタラメリ石の構造で解くことができず、内容を精査するとタラメリ石にはないはずの塩素(Cl)とホウ素(B)が存在する可能性がでてきた。そこでEPMA分析と湿式分析によって化学組成の再検討を行ったところ、確かに塩素とホウ素が確認されたのだった。なお、この湿式分析を担当したのが、長島乙吉の息子で筑波大学教授を務めていた長島弘三である[3]。この精度の高い分析によって構造もまた十分な精度で解明された[4]。そして長島石の研究を受けてタラメリ石についても化学組成と構造の再検討が行われることになり、やはり塩素とホウ素が含まれていることが確認されている[5]。
長島石は産出が非常に限られており、その産地は模式地である群馬県茂倉沢鉱山のほかには岩手県田野畑鉱山のみとなっている。茂倉沢鉱山ではある程度の産出があったようで、標本はそれなりにはみかける。バラ輝石などを伴う珪質で低品位のマンガン鉱石において、石英やバラ輝石の粒間に濃緑色の板から柱状結晶として長島石は産出する。田野畑鉱山では長島石は相当な稀産となり、長島石は桃井ざくろ石を密接に伴ってやはりバラ輝石をふくむ珪質なマンガン鉱石に伴われる[6]。写真でだけ見たことがあるが、1ミリ程度の大きさで結晶形は不定形と思われる。
[1] 長島乙吉, 長島弘三(1960)日本希元素鉱物. 日本鉱物趣味の会発行, 長島乙吉先生祝賀記念授業会, pp436.
[2] Matasubara S., Kato A., Yui S. (1982) Suzukiite, Ba2V4+2[O2|Si4O12], a new mineral from the Mogurazawa mine, Gumma Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 11, 15-20.
[3] 第一文献
[4] 第二文献
[5] Mazzi F., Rossi G. (1980) The crystal structure of taramellite. American Mineralogist 65, 123-128
[6] Matsubara S., Miyawaki R., Yokoyama K., Shiggeoka M., Miyajima H., Suzuki Y., Murakami O., Ishibashi T. (2010) Momoiite and nagashimalite from the Tanohata mine, Iwate Prefecture, Japan. Bulletin of the National Museum of Nature and Science C, 36, 1-6.
IMA No./year: 1978-005
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-21385)
鈴木石 / Suzukiite
BaV4+Si2O7
第一文献:Matsubara S., Kato A., Yui S. (1982) Suzukiite, Ba2V4+2[O2|Si4O12], a new mineral from the Mogurazawa mine, Gumma Prefecture, Japan, Mineralogical Journal 11, 15-20.
第二文献:設定無し
模式地:群馬県桐生市茂倉沢鉱山
鈴木石は国立科学博物館の研究チームにより記載された新鉱物で、北海道大学地質鉱物学第一講座(現:岩石学・火山学研究グループ)で教授を務めた鈴木醇(1896-1970)へ献名された。発見の経緯は一つ前の新鉱物である長島石と同様で、1973年の暮れに鉱物愛好家によって未同定鉱物が国立科学博物館へ持ち込まれたことに端を発する。そのときに持ち込まれた石はバラ輝石と菱マンガン鉱を主体とするいわゆるマンガン鉱石で、そこにはエメラルドグリーンの鉱物が伴われていた[1]。これが鈴木石であった。
茂倉沢での発見に遡るほんの数ヶ月前、岩手県田野畑鉱山からバリウム(Ba)とバナジウム(V)を主成分とする未知のケイ酸塩鉱物が見つかったことが学会で発表された[2]。これもまた鈴木石であった。発表では化学組成分析と粉末X線回折から原田石(SrV4+Si2O7)のストロンチウム(Sr)をバリウムに置き換えた鉱物であることが示されていた。研究グループはその新鉱物候補について、鈴木石(Suzukiite)とすることを決めていたとされる。
その理由として、両者の関係性が想定される。まず原田石とは北海道大学において地質鉱物学第四講座で教授を務めた原田準平(1898-1992)に因む新鉱物である。そして原田準平と鈴木醇はほとんど同年代で、北海道大学地質鉱物学教室でそれぞれ第四講座および第一講座の教授を務めた。互いの還暦記念論文集にも互いに寄稿している[3-4]。元素で見ると、ストロンチウムとバリウムは周期表で同族という関係であり、ストロンチウムを主成分とする原田石とバリウムを主成分とする鈴木石は、人物・鉱物どちらをみても対の関係となっている。
第一文献において発見そのものは田野原鉱山が茂倉沢鉱山に先行していたことが触れられてはいるが、模式地としては茂倉沢鉱山のみが設定されている。そして現在(2020年9月時点)でも田野畑鉱山からの鈴木石については記載論文が出版されていないようだ。ともかくも鈴木石のデータは茂倉沢鉱山産の標本から取得された。化学組成については少量のストロンチウムの他に、わずかなチタン(Ti)を含むのみで、これはほとんど端成分に近い。結晶構造については粉末X線回折で検討された。原田石と同構造であることが理解できる内容で、格子定数は原田石よりも鈴木石が大きいという関係であった。これはストロンチウムよりもバリウムが大きいという元素のサイズと整合的でもある。ただし光学的な性質では原田石と鈴木石は区別できないと読める。
鈴木石は原田石と同構造であるものの、その精密な結晶構造解析は永らく報告がなかった。これは原田石が発見早々に構造が解かれたことと対称的である。鈴木石の結晶構造は茂倉沢産の標本を用いた単結晶X線回折で解明され、やはり原田石と同構造で大きな差は無いことが確認された。それは2014年に正式な論文として発表され[5]、いずれこの論文が第二文献として登録されるのだろう。
鈴木石は原田石と同様に産地が少ない。日本では茂倉沢鉱山と田野畑鉱山が鈴木石の産地として知られるほか、浜横川鉱山からも産出が噂されている。産出量としてはおそらく茂倉沢鉱山が多く、これは見かける機会はそれなりにある。一方で田野畑鉱山産となるとまず見かけず、浜横川鉱山の標本となると個人的には見たことすら無い。また2014年にはBavsiite(Ba2V2O2[Si4O12])と名付けられた鈴木石の同質異像がカナダから見つかっている。ただ、これはまだ日本では見つかっていない。
[1] 第一文献
[2] 渡辺武男, 由井俊三, 加藤昭(1973)岩手県田野畑鉱山産Ba-V珪酸塩新鉱物. 三鉱学会連合学術講演要旨集, P24.
[3] 鈴木醇(1958)神居古潭結晶片岩中の特殊鉱物について. 鉱物学雑誌, 3, 660-673. (原田準平教授還暦記念論文集)
[4]原田準平(1958)X線蛍光分析法によるリョウマンガン鉱中の鉄分の測定. 鈴木醇教授還暦記念論文集, 342-357.
[5] Ito M., Matsubara S., Yokoyama K., Momma K., Miyawaki R., Nakai I., Kato A. (2014) Crystal structure of suzukiite drom the Mogurazawa mine, Gunma Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Science, 109, 222-227.
IMA No./year: 1978-040
IMA Status: A(approved)
模式標本:東北大学理学部(第一文献から引用)
古遠部鉱 / Furutobeite
(Cu,Ag)6PbS4
第一文献:Sugaki A., Kitakaze A., Odashima Y. (1981) Furutobeite, a new copper-silver-lead sulfide mineral, Bulletin de Minéralogie 104, 737-741.
第二文献:設定無し
模式地:秋田県小坂町古遠部鉱山
古遠部鉱は秋田県小坂町にあった古遠部鉱山から見出された新鉱物で、東北大学の苣木(すがき)教授を筆頭とした研究グループによって記載された。古遠部鉱の発見により、苣木は櫻井賞(第20号)を受賞した。
古遠部鉱山は1958年(昭和33年)頃から本格的な操業が始まった鉱山で、青森県との県境ちかくの秋田県小坂町字古遠部に位置していた。鉱床はいわゆる黒鉱鉱床であり、6つの鉱体が知られている[1]。採掘されていた鉱石は概ね3つに分類され、それぞれ、黒鉱、半黒鉱、黄鉱と呼ばれた。そして大黒沢東鉱床から産出する黒鉱が最も金・銀に富んでおり、銀を主成分に持つ古遠部鉱はこの大黒沢東鉱床から見出された。第一文献によると、-2mレベル、西1.5、 北3.25地点で採集されている。
古遠部鉱を含む鉱石は斑銅鉱が主体で、輝銀銅鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱が伴われる。古遠部鉱は300ミクロン程度以下の微細な粒子で鉱石中に埋没する産状であるため、観察には反射顕微鏡が必要になる。そして反射顕微鏡下では古遠部鉱と輝銀銅鉱は非常によく似た特徴を示すが、古遠部鉱のほうがわずかに明るく、そしてややオレンジがかった色で観察される。第一文献ではEPMAによる定量分析が行われており、理想化学組成は(Cu,Ag)6PbS4とまとめられた。銅(Cu)、銀(Ag)、鉛(Pb)、硫黄(S)からなる鉱物は現時点(2020年9月)においても古遠部鉱のみである。構造については単結晶X線回折で検討され、単斜晶系(C格子)の格子定数が得られてはいるが、元素の位置関係は報告されていない。そして、古遠部鉱の構造は未だ解かれていない。
古遠部鉱は熱に不安定な鉱物である。95℃までなら変わりないが、100℃を越えると方鉛鉱とCu5AgS3の化学組成をもつ物質へ分解してしまう。このCu5AgS3は温度を下げるとまたさらに分解し、輝銀銅鉱と輝銅鉱になってしまう。そのため古遠部鉱が存在すると言うことは、その鉱石は100℃以下で生成したことを意味している。海底火山から噴出した熱水が海水で冷やされ、硫化鉱物が結晶化して海底に降り積もる。これが黒鉱鉱床の生成モデルであり、低温で生成する古遠部鉱は黒鉱鉱床を代表する鉱物と言えるだろう。そして黒鉱鉱床それ自体が日本列島に特徴的な鉱床であるため、古遠部鉱は日本産新鉱物の代表にもなろうか。
黒鉱中で典型的に生じる古遠部鉱の産地は限られており、日本では古遠部鉱山の他に秋田県釈迦内鉱山が産地として知られる。やはり黒鉱鉱床である。釈迦内鉱山での発見は古遠部鉱山での発見とほぼ同時期で、1978年にCu-Ag-Pb-S組成の不明鉱物として報告されている[2, 3]。その分析値を解析してみると、確かに古遠部鉱に一致している。写真の標本も釈迦内鉱山から産出した黒鉱である。外観では方鉛鉱と閃亜鉛鉱ばかりが目立つが、研磨片を作成すると不定形の古遠部鉱が含まれていることが確認できた。
[1] 黒田英雄(1977)古遠部黒鉱鉱床の生成機構-古遠部鉱山の鉱床と探査(II)-. 鉱山地質, 27, 9-22.
[2] 宮崎敏男, 加藤邦明, 飯田幸平 (1978) 釈迦内鉱山第11鉱体の産状. 鉱山地質, 28, 151-162.
[3] Bernstein L.R. (1986) Renierite, Cu10ZnGe2Fe4S16- Cu11GeAsFe4S16: a coupled solid solution series. American Mineralogist, 71, 210-221.
IMA No./year: 1979-031
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM-M23380);National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 164269(Handbook of mineralogyから引用).
欽一石 / Kinichilite
Mg0.5Mn2+Fe3+(Te4+O3)3·4.5H2O
第一文献:Hori H, Koyama E, Nagashima K (1981) Kinichilite, a new mineral from the Kawazu mine, Shimoda city, Japan, Mineralogical Journal 10, 333-337.
第二文献:Miletich R (1995) Crystal chemistry of the microporous tellurite minerals zemannite and kinichilite, Mg0.5[Me2+Fe3+(TeO3)3]4·5H2O, (Me2+ = Zn;Mn), European Journal of Mineralogy 7, 509-523
模式地:静岡県下田市河津鉱山檜沢樋


模式地標本 こういった外観だと欽一石とゼーマン石は半々くらいの確率で含まれる。
欽一石は鉱物科学研究所(現:ホリミネラロジー)の堀秀道博士を筆頭とする研究チームによって命名された新鉱物で、学名は河津鉱山から産出する各種の鉱物を記載してきた櫻井欽一(1912-1993)に因んでいる。当時、欽一石はゼーマン石(Zemannite)の二価鉄(Fe2+)置換体として新鉱物に認定された。しかし現在においてそれは誤った認識であることが明らかとなっており、第一文献に記載された鉱物はゼーマン石に相当する。そのため第一文献のデータに基づくと欽一石はディスクレジット(抹消)されることになるが、第二文献の取り扱いによって現在でも独立種の立場が保たれている。いったい何が起こったのか。欽一石にまつわる全体像を理解するには、まずは当時のゼーマン石を振り返る必要がある。
ゼーマン石(Zemannite)はMoctezuma鉱山(メキシコ)を模式地とする鉱物で、1968年に承認された。学名はオーストリアの鉱物学者である Josef Zemann(1923-)に因む[1]。EPMAによる化学組成分析と単結晶X線回折法による結晶構造解析によって、ゼーマン石の化学式は(Zn,Fe)2(TeO3)3NaxH2-x・yH2Oとして決定されている[1,2]。しかしながら、化学組成分析と構造解析のいずれにもわずかな見落としがあり、後の研究結果からみるとこの組成式は間違っていた。それでもゼーマン石は産出が極めて稀な鉱物であったため、その誤りにだれも気付かないままに時代が移り、欽一石の研究が始まってしまう。
第一文献で記載された欽一石の化学組成は(Fe2+1.13Mg0.47Zn0.43Mn2+0.17)Σ2.20(Te2.97Se0.03)Σ3.00O9.00(H1.38Na0.22)Σ1.60・3.2H2Oである。これは組成式として(Fe2+,Mg,Zn,Mn2+)2(TeO3)3NaxH2-x・yH2Oのようにまとめることができる。つまり亜鉛(Zn)を主成分とするゼーマン石に対して、二価鉄(Fe2+)を主成分とする欽一石という分類が可能だとして、欽一石は1979年に新鉱物に承認された。1995年に国立科学博物館が「櫻井コレクション―鉱物―」の企画を行った際には、理想化学式はHNa(Fe2+,Mg,Zn) 2[Te4+O3]3・3H2Oであると解説されている[3]。同時に、酸化帯に生じるのに三価鉄(Fe3+)ではなく二価鉄を主成分とすることについて言及があり、研究者はこれについて不思議な現象だと認識していたようだ。
1995年の企画展とほぼ同時期かその直後のことだと推測されるが、ゼーマン石と欽一石について重要な論文が発表された。それが第二文献であり、その主張はMg0.5[Me2+Fe3+(TeO3)3]・4.5H2Oの組成式についてMe2+=Znをゼーマン石とするという内容であった。ポイントはまず鉄の価数。これまで鉄はすべて2価として扱われていたが、実はすべて3価であることが判明した。後から考えるとこれは妥当な新事実であろう。ゼーマン石も欽一石も共に鉱床の酸化帯に生じるので、その環境であれば三価鉄を想定することが本来である。それからマグネシウム(Mg)についてはMe2+とは異なる結晶学的席に位置することが明らかとなり、Me2+には含まれない。ここで第一文献に掲載されている分析値を振り返り、鉄をすべて3価としてさらにはマグネシウムを除いてMe2+の内容を再検証してみよう。そうすると、マンガン(Mn)がやや含まれているもののMe2+では亜鉛が最も多くなる。それだとすると第一文献で記載された欽一石(=模式標本)は新鉱物どころではなく、それは既存鉱物のゼーマン石に過ぎなかったのだ。第二文献は欽一石を消滅させるかと思われた。
一方で第二文献は欽一石についても再検証を行っている。検証に使用された標本は国立科学博物館と東京学芸大学から提供されている。ただし模式標本とは記されていないので、いわゆる欽一石とされる真偽不明の標本であろう。これがある意味で幸運をもたらした。もし第二文献が模式標本を手に入れて検証していたならば欽一石は消滅していただろう。ともかくも4つの標本について10点の分析値が掲載されており、Me2+において亜鉛が卓越する点は2点のみで、あとはことごとくマンガンが卓越していた。すなわち欽一石と称する標本は大部分がMe2+=Mnとなる鉱物で構成されていた。そこで第二文献は模式標本のことについては軽く触れるにとどめ、ともかく欽一石という名前をMg0.5[Mn2+Fe3+(TeO3)3]・4.5H2Oという化学組成の鉱物にズバッと当てはめてしまった。これついて新鉱物・命名・分類委員会(CNMNC)で審査された経緯はないと思われ、日本の研究者が記した戸惑いを感じられる文章が残っている[4]。このようにして第二文献によって欽一石は生まれ変わった。ただし模式標本がゼーマン石であることには違いないので、これは論点のすり替えに相当する。ともかくもゼーマン石と欽一石のすみわけは第二文献によって確定してしまい、第一文献については命名したという立場のみが残った。現在の公式なリストでも第二文献による化学式が掲載されている。いずれにしても模式標本の再設定は今後に必要になるだろう。
欽一石の標本は長らく手に入れることができなかったが、京都の山田滋夫氏から恵与いただいた。さらにもとをたどると児玉亨氏が手に入れたものだと伺った。そして彼らからそれを書いてくれと言われているので経緯をここに記す。欽一石は透明感がある赤色がにじんだ褐色を呈する六角柱状結晶として産出し、単独の結晶や箒かススキに例えられるような先が開いたような集合もみられる。こういった結晶を調べてみるとだいたい半々くらいでマンガンが卓越するので、第二文献よりもだいぶ確率がよろしくない。もう半分は亜鉛が卓越するゼーマン石であるので、こうなると欽一石とゼーマン石を両方ラベルに記すほかない。一方で色の淡い結晶については、調べた範囲ではすべて亜鉛が卓越し、つまりゼーマン石であった。
[1] Mandarino J.A., Matzat E., Williams S.J. (1969) Zemannite, a new tellurite mineral from Moctezum, Sonora, Mexico, The Canadian Mineralogist 10, 139-140.
[2] Matzat E. (1967) Die Kristallstruktur eines unbenannten zeolithartigen Tellurminerals, (Zn,Fe)2[TeO3]3}NaxH2−x • n H2O. Tschermaks Mineralogische und Petrologische Mitteilungen, XII, 108–117.
[3] 櫻井コレクション―鉱物―. 平成7年6月13日~7月16日, 国立科学博物館, pp.76.
[4] 松原聡(1997)日本産鉱物情報(1996). 鉱物学雑誌, 26, 33-35.
IMA No./year: 1979-081a
IMA Status: Rd(redefined)
模式標本:不明
奴奈川石 / Strontio-orthojoaquinite
NaSr4Fe3+Ti2Si8O24(OH)4(オフィシャルリスト)
Sr2Ba2(Na,Fe2+)2Ti2Si8O24(O,OH)・H2O 文献[5]
第一文献:Chihara K., Komatsu M., Mizota T. (1974) A joaquinite-like mineral from Ohmi, Niigata Prefecture, Central Japan. Mineralogical Journal, 7, 395-399.
第二文献:Kato T., Mizota T. (1990) The crystal structure of strontio-orthojoaquinite. Journal of the Faculty of Liberal Arts. Yamaguchi University. (Natural Science). 24, 23-32.
模式地:新潟県糸魚川市橋立(旧:青海町)
 模式地標本 分析値から得られる組成式は文献[5]と非常によく一致する。
模式地標本 分析値から得られる組成式は文献[5]と非常によく一致する。
新潟大学の茅原一也らによって見出された新鉱物には青海石と奴奈川石が知られる。奴奈川石は1979年の新鉱物である。しかし奴奈川石は学名と和名がバラバラであることからもわかるように、その承認の経緯にちょっとした事情がある。
第一文献は奴奈川石の初出となる文献で、1974年に出版された。ただしこれは新鉱物としての記載論文ではなく、ジョアキン石(Joaquinite)に似た鉱物の産出として報告されるのみで、奴奈川石(Nunakawaite)という表記は認められない。それでも発見者はこの鉱物のことを奴奈川石と呼び、新鉱物であることを確信していたことがうかがえる[1,2]。その由来となった奴奈川という名称は新潟県糸魚川市を流れる姫川の古名であり、日本神話に登場する女神の名でもある。奴奈川石の発見地は青海川であるので、女神の方から採用したのだろう。ともかくその美しい響きは愛石家に好まれ、姿形もまた美しいことから奴奈川石の通称は一定の知名度を獲得したと思われる。その呼称は学術界には定着しなかったが、あえて奴奈川石(Nunakawaite)の名称を用いた研究発表がごく最近に行われた[3]。
奴奈川石に先立ってジョアキン石という鉱物が先にあった。そして、単斜晶系のジョアキン石に対して、斜方晶系(直方晶系)でストロンチウムにやや富む奴奈川石という対応である。これが1974年の第一文献の内容であり、著者らは新鉱物として確信しつつもなぜか申請はされないままになっていた。そして1979年になり、二つのジョアキン石類似鉱物がアメリカで見出された。ひとつがジョアキン石よりもストロンチウムに富みかつ単斜晶系となるストロンチオジョアキン石(Strontiojoaquinite)で、もう一つがバリオ斜方ジョアキン石(Bario-orthojoaquinite)である。それらはいずれも化学組成と対称性を学名に当てはめるという合理性が特徴となっている。このやりかたはIMAから承認されており[4]、これまでほったらかしになっていた奴奈川石にもStrontio-orthojoaquiniteという学名が自動的に当てはめられることになった。詳細な解説を省くが、IMA No.もまず間違いなく自動的に付与されている。学名の定まった経緯はこういったことによる。しかし和名は個人の自由で表現すれば良いので、ここでは美しい響きの奴奈川石と表現する。
2001年にはジョアキン石族の再定義というタイトルの論文が発表される[5]。ジョアキン石族は7種に再編され、理想化学式も変更された。その論文に基づくと奴奈川石(Strontio-orthojoaquinite)の理想化学式はSr2Ba2(Na,Fe2+)2Ti2Si8O24(O,OH)・H2Oと定義されている。実際に分析した値もこの化学式と非常によく一致する。しかしなぜかオフィシャルリストには古い組成式が掲載されたままとなっている。ただし、文献[5]の理想化学式が結晶構造に基づいて提案されているかというと、必ずしもそうではない。奴奈川石の場合だと第二文献によってバリウムやストロンチウムの入る結晶学的席は6つあることが明らかとなったが、それぞれの配置と量比は未解明のままとなっている。一つの結晶に複数のポリタイプが混じることもあって[6]、それは構造解析の障壁となるだろう。
奴奈川石は毛状の苦土リーベック閃石をともなう曹長岩中にみられる鉱物で、多くは黄色いシミのような産状であるが、多孔質となった箇所から結晶が顔を覗かせることがある。そこでは奴奈川石は錐状に尖り、多段成長した痕跡がしばしば観察される。奴奈川石は約8900万年前(U-Pb年代)に生成したことが判明しており[3]、地質年代としてそれはとりわけ古くもないが、恐竜が生き生きと活動しているころに誕生しながらも現代になっても凛々しいままであることが奇跡にも思える。奴奈川石の模式標本は文献上では不明になっているが、新潟大学には模式標本が残っている[6]。
[1] 茅原一也, 小松正幸, 溝田忠人 (1981) 青海産新鉱物(ohmilite, nunakawaiteほか)の成因に関する研究–蛇紋岩中のtectonic blockの稀有鉱物共生–. 飛騨外縁帯総合研究飛騨外縁帯研究報告No.2!文部省科学研究費総合研究(A)飛騨外縁帯の地質学的岩石学的研究, 43-56.
[2] 茅原一也(1996)青海自然史博物館とヒスイ. 宝石学会誌, 21, 95-96.
[3] Tsujimori T., Hara T., Shinji Y., Ishizuka T., Miyajima H., Kimura J., Aoki S., Aoki K. (2019) Dating a ‘princess’: U–Pb age determination of ‘nunakawaite’ (strontio-orthojoaquinite). 日本地球惑星科学連合2019年大会, SMP32-14.
[4] Wise W.S. (1982) Strontiojoaquinite and bario-orthojoaquinite: two new members of the joaquinite group, American Mineralogist 67, 809-816
[5] Matsubara S., Mandarino J.A., Semenov E.I. (2001) Redefinition of a mineral in the joaquinite group: orthojoaquinite-(La). The Canadian Mineralogist, 39, 757-760.
[6] 間島寛紀, 赤井純治(2005)HRTEMによる青海産ストロンチオ斜方ジョアキン石の構造多様性 -特にc軸方向四倍周期構造について-. 日本鉱物学会2005年度年会講演要旨集, K8-08
総評_1980s
1980年代のIMAno.をもつ日本産新鉱物で、現在(2023年8月)でも有効な種は19種ある。ただし、データからは釜石石は備中石の正方晶系多形(ポリタイプ)の可能性が強く疑われる。それが確定すれば独立種としての立場は失われるが、いまのところ再検証された形跡はないためか、独立種としてまだ有効なままとなっている。片山石もやっぱり苦しい。片山石は古くからバラトフ石と同一であることが指摘されている。すくなくとも模式標本のデータを客観的に比べると間違いない。一方で、フッ素優占種のバラトフ石、水酸基優占種の片山石として永らく公式リストに載っているので、もはや模式標本のほうを更新するという手段がとれるかもしれない、と勝手に思う。また、すでに独立種としての立場を追われた鉱物もあり、南石が該当する。南石は組成的にはソーダ明礬石の範疇に収まるが、対称性がソーダ明礬石と異なっていたために承認を受けた。ただし、1980年代は鉱物の定義がまだ明確に宣言されていない時代であり、とくに対称性の違いで種を分けるやりかたは後年に否定され、南石はその対象となった。その他のほうに分類した釣魚島石については中身が論外。政治的な問題は度外視としても、人工物であることがほぼ確定している。
この年代で注目すべき日本産新鉱物は逸見石だと思っている。逸見石が発見された(申請された)のが1981年だが、その当時ですでに幻の鉱物と言われていたほど産出量が少なく、手に入りにくかったと聞いている。しかし、2002年に田邊晶洞と呼ばれる大きなポケットが発見されて以降は話が変わった。そこでは壁一面を逸見石の結晶が埋め尽くしており、今では逸見石はもっとも手に入りやすくかつ美しい日本産新鉱物になった。その逸見石を用いて物性研究が行われるなど、新鉱物の発見がほかの研究分野へも派生したというインパクトもある。そして、逸見石は布賀鉱山の専売特許であり、ほかからはいまだに見つかっていないという稀産性があり、全体を通じても日本産新鉱物の顔となる鉱物だと思う。ものが地味であっても個人的にはプロト型角閃石がツボであり、単結晶解析という手法だったからこその発見だろう。日本産新鉱物でアンモニウムを持つものはこれまでに二つあり、そのどちらも1980年代の新鉱物である。外国人によって記載された鉱物もこの年代に二つ入っており、全体を通じてみれば著者の所属は多様にみえる。産地についてはすでに消滅したものが多く、模式地の滋賀石と和田石は美結晶であったので惜しまれる。この年代の新鉱物で豊羽鉱だけ手に入らなかった。
世界的にみると、1980年代、とくにその前半は新鉱物が多く誕生した[1]。1980年と1982年は90種を超え、1983年も80種を超える新鉱物が誕生している。これは2010年前後まで超えられることのない突出した数である。1970年代後半に登場した単結晶X線構造解析ソフトの登場が影響しているかもしれない。ただし、そこをピークとして、1980年代後半になると年あたり50種くらいに落ち着くことになり、1990年代もそのくらいを推移する。「年間どれくらいの新鉱物が誕生するのか?」という問いに対して「50種くらい」という回答がたまに聞こえるが、それは1980年代後半から1990年代あたりの実績からでた回答であろう。
分析手法を見ると、EPMA分析と湿式分析の比率に極端な差が開いたのも1980年代である。1980年代前半にはEPMA分析を使った研究が6割、湿式分析を使った分析が4割といったところだが、後半にはEPMAが9割、湿式が1割まで差が開いている。IR分析が新鉱物研究に使われるケースをそれなりに見かけるようになったのもこのころであろう。一方で示差熱分析などはここから徐々に減っていく。1980年代は分析手法についてトレンド転換期だったように思える。
[1] Barton I.F. (2019) Trends in the discovery of new minerals over the last century. American Mineralogist, 104, 641-651.
IMA No./year: 1980-006
IMA Status: Rn(renamed)
模式標本:国立科学博物館(MSN-M23125);National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 147159, 147160(Handbook of mineralogyから引用)
マンガノパンペリー石 / Pumpellyite-(Mn2+)
Ca2Mn2+Al2(Si2O7)(SiO4)(OH)2·H2O
第一文献:Kato A, Matsubara S, Yamamoto R (1981) Pumpellyite-(Mn2+) from the Ochiai Mine, Yamanashi Prefecture, Japan, Bulletin de Minéralogie 104, 396-399.
第二文献:設定無し
模式地:山梨県南アルプス市落合鉱山(旧:甲西町)
マンガノパンペリー石は国立科学博物館の加藤昭らによって見出された新鉱物で、命名は先に成立していた命名規約[1]に追従している。すなわちPumpellyite-(Mn2+)という学名には「パンペリー石族のパンペリー石シリーズの内で二価マンガン(Mn2+)に卓越する鉱物種」という意味が内包されるようになっている。二価マンガンのことを「マンガノ」と称するため、ここでは和名としてマンガノパンペリー石と呼ぶことにする。シリーズ名はアメリカの地質学者Raphael Pumpelly(1837-1923)に因む。Pumpellyはお雇い技術者として短い期間だが日本に滞在し、北海道の地質を調査している。
当時はパンペリー石族の構造に未解明の部分があったために現在の4倍量で組成式が作られているが[1]、ここでは現在の組成式に基づいてパンペリー石族を述べる。パンペリー石族の鉱物はCa2XY2(Si2O7)(SiO4)(OH)2-nOn・H2Oという化学組成において、Yの元素によってまずそのシリーズが分けられる。たとえば、Y = Alならパンペリー石シリーズ、Y = Fe3+ならジュルゴルド石シリーズ、Y = Mn3+ならオホーツク石シリーズとなる。そして、Xに入る元素によって鉱物種(学名)が決まり、それはXの元素はサフィックスで表すことになる。例えば、Y = AlかつX = Mgの場合だとPumpellyite-(Mg)(苦土パンペリー石)となる。そして、マンガノパンペリー石はY = AlかつX = (Mn2+)の鉱物である。
第一文献が記す内容によれば、落合鉱山は中新世(約2300-500万年前)の地層に発達した層状マンガン鉱床で、ぶどう石-パンペリー石相程度の弱い変成作用を受けている。ブラウン鉱が主要な鉱石鉱物であり、低品位部はいわゆるズリ(廃石)として放置されたようだ。そしてこの研究の調査段階ですでに鉱山は閉山し、坑口もまた不明になっていたため、研究に使用された鉱石はすべてズリから回収されている。調査の際には無名会の会員である愛石家が幾人か参加しており、そのうちの一人(山本)が著者として参画している。
マンガノパンペリー石は明るい灰色を帯びたピンク色と記されているが、ざっくりいえば明るい褐色であろう。それが斑紋や脈としてブラウン鉱に伴われ、最大で1センチほどの塊になる。ただしその塊はかっちりとはしておらず、もさっとしている。マンガノパンペリー石のモース硬度は5ほどもあり、これは燐灰石と同じ硬さであるが、もさっとした集合であるために針が易々と突き刺さる。こういう産状だと普通のスクラッチテストは困難なはずだが、どうやってそれを測定したのかは記されていない。また、個々の結晶は非常に微細で、最長100ミクロン程度の葉片状とされる。その形状を認識するには薄片を作ることになるが、薄片下での光学特性は紅簾石に似つつも多色性が異なることが記されている。組成的には少量のFe3+とMn3+が含まれているが、YにおいてAlが支配的であることが確認でき、XにおいてもMn2+が十分に卓越している。第一文献では構造データは粉末X線回折による格子定数のみの報告であったが、後にイタリア産のマンガノパンペリー石を用いた構造解析が実施されている[2]。パンペリー石構造の次(高圧高温側)に現れる相はサーサス石(Sursassite)やマクファル石(Macfallite)であり、構造的にはこれらはパンペリー石構造からほんのちょっとずらしただけの関係[(a+c)/2シフト]となっている[3]。そしてさらに高温高圧では緑簾石構造が出現し、その構造的な関係もすでに解明されている[3]。
写真の標本は模式地である落合鉱山のズリから得られた標本となる。明るい褐色部がマンガノパンペリー石で、なるほど確かにもっさりしており針を押し付けるとサクッと突き刺さる。分析値は第一文献とほとんど同じ内容で、この産地のマンガノパンペリー石は組成幅が小さいのだろう。落合鉱山のように目で見てわかるマンガノパンペリー石の産出はかなり稀だが、産出自体はそんなに稀ではない。四国のマンガン鉱床を調べていた際には顕微鏡レベルのマンガノパンペリー石はそれなりに見つかった(標本にはならないが)。
[1] Passaglia E, Gottardi G (1973) Crystal chemistry and nomenclature of pumpellyites and julgoldites. The Canadian Mineralogist, 12, 219-223.
[2] Artioli G., Pavese A., Bellotto M., Collins S.P., Lucchetti G. (1996) Mn crystal chemistry in pumpellyite: A resonant scattering powder diffraction Rietveld study using synchrotron radiation. American Mineralogist, 81, 603-610.
[3] Nagashima M. (2011) Pumpellyite-, sursassite-, and epidote-type structures: common principles-individual features. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 106, 211-222.
IMA No./year: 1980-027(2012s.p.)
IMA Status: Rd(redefined)
模式標本:東京大学(M23378)(Handbook of mineralogyから引用)
カリフェロ定永閃石 / Potassic-ferro-sadanagaite(原記載はsadanagaite)
KCa2(Fe2+3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2
第一文献:Shimazaki H., Bunno M., Ozawa T. (1984) Sadanagaite and magnesio-sadanagaite, new silica-poor members of calcic amphibole from Japan. American Mineralogist, 69, 465-471.
第二文献:設定無し
模式地:愛媛県上島町弓削島

模式地標本
カリフェロ定永閃石は細粒であり、肉眼的に一般の角閃石のような柱や板状結晶が見られることはない。

上の標本の薄片写真(クロスニコル)
全体がカリフェロ定永閃石(灰緑色)で、チタン鉄鉱(黒)、鉄スピネル(濃緑色小粒)チタン石(ギラギラ)を伴う。
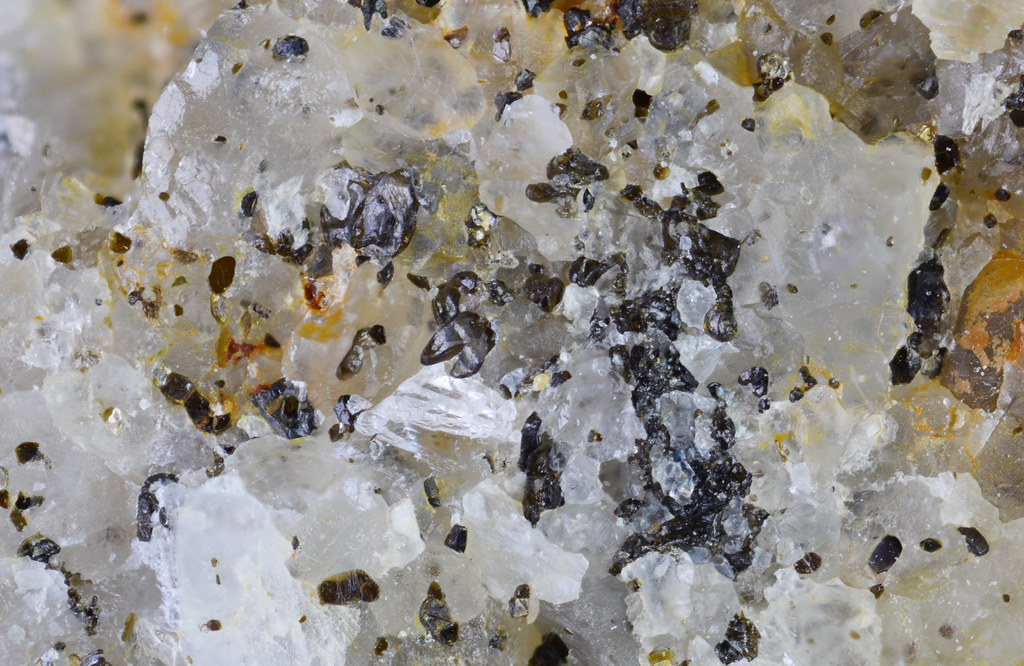
愛媛県松山市睦月島 利休鼠色の不定型な粒として方解石中にまばらに点在する。
カリフェロ定永閃石は東京大学の島崎英彦らによって見出された角閃石族の新種で、東京大学の名誉教授であった定永両一(1920-2002)にちなんで命名された。定永はX線結晶学や実験鉱物学が専門で、日本鉱物学会と日本結晶学会で会長を歴任し、日本学士院会員にも選ばれている。
角閃石族は昔から毎年のように新種が報告され、角閃石族が何種類の鉱物から構成されているか?と聞かれてもすぐに答えられないほどの大きなまとまりとなっている。それらを整理するために命名規約が早くから整備され、カリフェロ定永閃石が発見された当時は1978年版の命名規約が最新であった[1]。その命名規約に基づくと、化学組成からルートネームを名付けることが可能であった。そこで島崎らは定永閃石(Sadanagaite)として新鉱物を申請し、それが承認された。しかし、命名規約が2012年に大改訂された際に命名ルールが厳格化され[2]、そのルールに基づいて今の名称であるカリフェロ定永閃石(Potassic-ferro-sadanagaite)が定まった。
カリフェロ定永閃石は愛媛県弓削島から産出する。弓削島は瀬戸内海に浮かぶ島で、第一文献には秩父帯と領家帯の境界に近いことが図示されているが、瀬戸内海に秩父帯と領家帯の境界など存在しない。おそらくは広島型花崗岩と領家型花崗岩の境界の誤りであろう。ともかくも弓削島は広島型花崗岩の分布域に位置しており、島には石灰岩の採石所が稼働していた。その石灰岩は花崗岩によってよく焼かれており、再結晶化が著しい大理石となっている。また石灰岩には緑色の灰鉄輝石や橙色の灰バンざくろ石からなる色鮮やかな脈状スカルンが非常に良く発達しているが、カリフェロ定永閃石を伴うスカルンはそれらとは全く異なる。カリフェロ定永閃石は小規模な灰黒色の塊として石灰岩中に見出された。内部は主にベスブ石とカリフェロ定永閃石からなり、いずれもチタン(Ti)に富む組成的な特徴がある。また、それらはチタン鉄鉱、鉄スピネル、チタン石を多量に包有する。
この時代にはすでにEPMAが一般化しており、特性X線の補正法はあれこれ模索されていたようだが、分析自体は包有物を避けて難なく行えるようになっている。そして、カリフェロ定永閃石の組成的な特徴が明らかとなった。これは特にTサイトにおいてSi が 5.5を下回る世界初の角閃石であったことから、ルートネームになる定永閃石(Sadanagaite)が提案された。結晶構造については単結晶X線回折で空間群の候補が提案され、ガンドルフィーカメラで格子定数が報告されているものの、構造の精密化は行われていない。弓削島産のカリフェロ定永閃石は包有物が多くまた累帯構造もあるため、均質な組成の結晶を探すことが困難であったと伝え聞いている。
写真の標本は弓削島と睦月島から得られたカリフェロ定永閃石になる。弓削島においては、粗粒な大理石中に黒色の小塊がみられることがあり、これがカリフェロ定永閃石の代表的な産状である。これを持ち帰り分析しようなどとは普通は思わないが、愛媛県明神島において先例があったために、こういった産状の黒色塊はむしろ探し求められていた。後に松山市睦月島からも明神島や弓削島と同様のスカルンが見出され、そこからもカリフェロ定永閃石が見つかった[3]。ただし睦月島ではカリフェロ定永閃石は塊ではなく、個々の結晶が方解石中に散在するという産状を示す。この結晶を使えば構造解析も可能となるかも知れない。
[1] Leake B.E. (1978) Nomenclature of amphiboles. Canadian Mineralogist, 16, 501–520.
[2] Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist 97, 2031-2048.
[3] 西尾大輔, 皆川鉄雄 (2003) 明神島および睦月島に見られるAl質スカルンに産するtitanian esseneitic diopside. 岩石鉱物科学, 32, 68-79.
IMA No./year: 1980-052
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(M23560)(Handbook of mineralogyから引用)
釜石石 / Kamaishilite
Ca2(SiAl2)O6(OH)2
第一文献:Uchida E., Iiyama J.T. (1981) On kamaishilite, Ca2Al2SiO6(OH)2, a new mineral dimorphous (tetragonal) with bicchulite from the Kamaishi mine, Japan, Proceedings of the Japan Academy 57B, 239-243.
第二文献:設定無し
模式地:岩手県釜石市釜石鉱山



同じ視野で、後方散乱電子像(上)、光学顕微鏡像(オープン)(中)、光学顕微鏡像(クロスニコル)(下)。
釜石石は東京大学地質学教室の内田悦生と飯山敏道によって岩手県釜石鉱山から見いだされた新鉱物で、釜石石は備中石と共通の化学組成(Ca2(SiAl2)O6(OH)2)をもつ新鉱物として記載された。その違いは対称性にあり、立方晶系の備中石に対して、正方晶系の釜石石という位置づけがなされている。この当時において対称性の違いは種を分ける基準として機能していた。ところが、1998年に種を分ける基準がより厳密化され、今では「結晶構造について元素の相対的な位置関係が同じであるとき、対称性の違いは種を分けない」ことがガイドラインとして整備されている。一方でガイドラインの適用は即座に執行されるのではなく、後年に超族をまとめる際に改めて精査されることが多い。釜石石についてはガイドラインに従うとその独立性はもはや補償されない可能性が非常に高いと言える。一方で、現時点でメリライトもしくはゲーレン石超族という大きなまとまりはまだ整備されていないので、釜石石の独立性は公式には否定されていない。そのためいまのところ「日本から発見された新鉱物たち(一覧)」に釜石石を区分している。
岩手県釜石鉱山は北上山地の中東部に位置し、石炭紀からペルム紀の石灰岩が白亜紀に花崗岩類の貫入を受けて生成した典型的なスカルン鉱床となっている。明治期以降に本格稼働された鉱山で、鉄を資源とする鉱山として釜石鉱山は日本最大級の規模であった。鉱床は熱源である花崗岩類から石灰岩に向かい、鉄鉱体帯→銅・鉄鉱帯→銅鉱帯と分帯し、とりわけ新山鉱床は鉱床群の中でもっとも規模が大きいことが知られている。釜石石はその新山鉱床の350mレベルにおいて、石灰岩にほど近いベスブ石スカルンの中から見いだされ、共生鉱物としてベスブ石や方解石のほかに、ざくろ石、灰チタン石、磁鉄鉱、黄銅鉱が記されている。写真を見る限りだとスカルンは石灰岩を横切る脈として生じるようで、スカルンは100ミクロン程度以下の結晶粒で構成され、粒の大きさはおおむねそろっているように見える。
一般的には光学特性は対称性の低下に敏感であるが、正方晶系の釜石石についてはほとんど光学的等方体として観察されている。その屈折率は立方晶系の備中石にほぼ等しい。組成的にも不純物は非常に少なく、ほとんど理想的なCa2(SiAl2)O6(OH)2組成となっており、ここまでの特徴で備中石とは区別できない。一方で、釜石石はX線回折パターンにおいて備中石と異なる挙動が観察される。釜石石のX線回折パターンは基本的に備中石とよく似ているが、それぞれのピークをよく観察すると、備中石で一本のピークであるものが、釜石石では二つ以上に割れているものが多い。そして割れたピークの高角側は回折強度が低下するという特徴があり、これは立方晶系から対称性が低下する際の特徴でもあった。そして、それぞれのピークに指数を割り振ると、釜石石について正方晶系(a = 8.85Å & c = 8.77Å)が得られている。これは立方晶系の備中石(a = 8.83Å)の格子がほんのわずかに歪んだ形状であるものの、この程度の変化だと結晶構造の中身である元素の相対的位置が異なる関係とは考えづらい。また、記載論文においても釜石石と備中石の区別は対称性の違いであるという主張である。そのため、1998年のガイドラインに従って後年に釜石石は備中石の正方晶系の多形(ポリタイプ)として扱われる可能性が高いと考えている。
写真の標本は山田滋夫氏から提供された釜石石の標本である。X線回折を行うほどの量がないために光学観察と組成のみ確認している。後方散乱電子像や光学顕微鏡写真の中心が釜石石であり、文献のようにほとんど光学的等方体として観察され、クロスニコルにおいては完全に消光する。ルーマニアの高温スカルン産地においては備中石もしくは釜石石としてその産出が示唆されているが[3]、現時点で釜石石を構造的に追認した報告は知られていない。
[1] 第一文献
[2] Nickel E.H., Grice J.D. (1998) The IMA commission on new minerals and mineral names: procedures and guidelines on mineral nomenclature, 1998. The Canadian Mineralogist, 36, 913-926.
[3] Pascal M.L., Fonteilles M., Verkaeren J., Piret R., Marincea S. (2001) The melilite-bearing high-temperature skarns of the Apuseni Mountains, Carpathians, Romania. The Canadian Mineralogist, 39, 1405-1434.
IMA No./year: 1980-103
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(M23576); National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 148213(Handbook of mineralogyから引用)
大江石 / Oyelite
Ca5BSi4O13(OH)3·4H2O
第一文献:Kusachi I., Henmi C., Henmi K. (1984) An oyelite-bearing vein at Fuka, the town of Bitchu, Okayama Prefecture. Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 79, 267-275.
第二文献:Pekov I.V., Zubkova N.V., Chukanov N.V., Yapaskurt V.O., Britvin S.N., Kasatkin A.V., Pushcharovsky D.Y. (2019) Oyelite: new mineralogical data, crystal structure model and refined formula Ca5BSi4O13(OH)3·4H2O. European Journal of Mineralogy 31, 595-608.
模式地:岡山県高梁市備中町布賀道路際露頭
大江石は岡山県布賀から見いだされた新鉱物で、岡山大学の大江二郎教授(1900-1968)にちなんで岡山大学の草地功らによって命名された。大江石は古くは「10Å(おんぐすとろーむ)トベルモリ石」と呼ばれていたが、それは単独の鉱物種として認識されておらず、草地らが新鉱物へ申請したことで大江石という鉱物種として立場が定まったという経緯がある。現在において大江石は少なくとも微細な鉱物ではなく、立派で大きな標本が特に南アフリカで産出することが知られている。しかし、標本として優れていても構造解析に必須である良質な結晶は近年まで産出がなく、そのために大江石の理想化学式と結晶構造はなかなか解明されなかった。そして2019年になり、ロシア産の大江石を用いた研究によってようやく理想化学式と結晶構造が決定されている。それは大江石の誕生からは約40年、そもそも10Åトベルモリ石の発見からだと約60年にもなる長い道のりであった。
まずトベルモリ石(Tobermorite)は1882年に記載されたカルシウム(Ca)を主成分とする含水ケイ酸塩鉱物で、11.3Åに顕著なX線回折を示す特徴がある。そして大江石の前身である10Åトベルモリ石は1956年に報告されている[1]。それはCrestmore採石所(アメリカ)から得られた標本で、トベルモリ石に近い組成でありながらも10Åの回折ピークが顕著な未詳鉱物として記載された。この時点でこの未詳鉱物は「10Å含水物(the 10Å hydrate)」と呼ばれ、1961年には10Å含水物に少量のホウ素(B)が含まれることが明らかとなっている[2]。さらに、1964年までにトベルモリ石と似た化学組成ながらも回折ピークには、14Å、12.6Å、11.3Å(トベルモリ石)、10Å、9.3Åの5種類があることが知られている[3]。そしてそれぞれが「XXÅトベルモリ石」と呼ばれるようになっていった。そして10Åトベルモリ石については、1977年にイスラエルから産出が報告され[4]、次いで1980年に布賀からも見いだされている[5]。そのときも10Åトベルモリ石として産出が報告された。
布賀の10Åトベルモリ石はいわゆる道路際露頭と称される場所から産出した。ここは日本で初めて灰チタン石(Perovskite)が産出したことで有名であるほか、スカルンの帯状構造が観察できる。そのスカルンを切る細脈としてぶどう石や蛍石、魚眼石などが産出し、10Åトベルモリ石もまた細脈充填鉱物として見いだされている。他に14Åトベルモリ石と11.3Åトベルモリ石の産出もまた記されているが、これらは汚染岩を切ることに対して、10Åトベルモリ石はスパー石帯(主にスカルン)を切るという産状的な差異が述べられている。そして組成分析によって10Åトベルモリ石にはホウ素が含まれ、一方の11.3Åトベルモリ石にはホウ素が含まれないことも明らかとなった。また、カルシウム(Ca)/ケイ素(Si)においても10Åトベルモリ石と11.3Åトベルモリ石には差があり、熱挙動も報告されている。この研究結果を元に、草地らは10Åトベルモリ石は独立の鉱物であるとの核心を得て新鉱物申請が行われた。1980年に提出された申請書には草地および逸見親子の他に、Crestmore産の10Åトベルモリ石を記載したTaylor H.F.W.および分析に貢献した伊藤順もまた著者として加わっている[6]。新鉱物の名称には逸見吉之助および草地功が教えを受けた大江二郎の性が採用された。
大江石は単結晶構造解析が困難であったことから、その理想化学組成は主に分析から推定され、承認された時点ではCa10B2Si8O29・nH2O(n=9.5-12.5)と考えられていた[6]。そして1984年には記載論文が出版されるのだが、そこでは1.0CaO・0.1B2O3・0.8SiO2・1.25H2Oと改訂されている[7]。その後、あたらしい産地が見つかるたびに理想化学組成もまた改訂が提案されている[8,9]。そして2019年に構造解析が成功すると、Ca5BSi4O13(OH)3·4H2Oが理想化学式として定まった。さらに、大江石の結晶構造はカルシウム(Ca)-酸素(O)多面体の配列にトベルモリ石との共通点があり、ケイ素(Si)-酸素(O)多面体の配列にヴィステフ石(Vistepite:SnMn4B2Si4O16(OH)2)との共通点があるという、これまでに知られていない新規の結晶構造であることもまた判明した[10]。
なお、大江石の定義がこのように定まる前の2015年にトベルモリ石超族の命名規約が成立している[11]。各XXÅトベルモリ石について分類が行われ、14Å:プロンビエル石(Plombierite: Ca5Si6O16(OH)2·7H2O)、11.3Å:トベルモリ石(Tobermorite:Ca5Si6O16(OH)2·nH2O)もしくは単斜トベルモリ石(Clinotobermorite:Ca5Si6O17(OH)2·5H2O)、9.3Å:リバーサイド石(Riversidite: Ca5Si6O16(OH)2·5H2O)という分類が記されている。10Åが大江石だったのは上述にあるとおりで、残りの12.6Åについてはタカラン石(Tacharanite:Ca12Al2Si18O33(OH)36)として同定され、この二種についてはトベルモリ石超族に入らないということで落ち着いた。
大江石の結晶は無色透明で細く薄い板状結晶であり、結晶の側面には強い絹糸光沢がみえる。それが放射状に開いた形状で産出することが非常に多く、またしばしば脈として連続する。その外観はトベルモリ石と共通であり、外観だけで肉眼的にこれらを区別することはほとんど不可能である。しかし上述のように産状に注目することで、ひとつの産地では大江石とトベルモリ石を区別することが可能であろう。写真はスパー石中に生じた大江石の標本になる。
[1] Heller L., Taylor H.F.W. (1956) Crystallographic data for the calcium silicates. IV. The 10 Å hydrate. H.M. Stationary Office, London 1956, 37-38.
[2] Murdoch J. (1961): Crestmore, past and present. American Mineralogist, 46, 245-257.
[3] Taylor H.F.W. (1964) The chemistry of cements, 1. London, New York : Academic Press, 460p.
[4] Gross S. (1977): The Mineralogy of the Hatrurim Formation, Israel. Geological Survey of Israel, Bulletin no. 70, 80 pp.
[5] 草地功、逸見千代子、逸見吉之助(1980)岡山県備中町布賀産10Åトバモライト. 鉱物学雑誌, 14, 314-322.
[6] 草地功、逸見千代子、逸見吉之助(1981)新鉱物大江石. 日本鉱物学会1981年年会, P132.
[7] 第一文献
[8] 皆川鉄雄, 稲葉幸郎, 能登繁利(1986)三重県水晶谷産大江石. 岩石鉱物鉱床学会誌, 81, 138-142.
[9] Biagioni C., Bonaccorsi E., Merlino S., Bersani D., Forte C. (2012): Thermal behaviour of tobermorite from N’Chwaning II mine (Kalahari Manganese Field, Republic of South Africa). II. Crystallographic and spectroscopic study of tobermorite 10 Å. European Journal of Mineralogy, 24, 991-1004.
[10] 第二文献
[11] Biagioni C., Merlino S., Bonaccorsi E. (2015) The tobermorite supergrpup: a new nomenclature. Mineralogical Magazine, 79, 485-195.
IMA No./year: 1981-021
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(M23773)(Handbook of mineralogyから引用)
砥部雲母 / Tobelite
(NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2
第一文献:Higashi S. (1982) Tobelite, a new ammonium dioctahedral mica, Mineralogical Journal, 11, 138-146.
第二文献:Capitani G.C., Schingaro E., Lacalamita M., Mesto E., Scordari F. (2016) Structural anomalies in tobelite-2M2 explained by high resolution and analytical electron microscopy. Mineralogical Magazine, 80, 143-156.
模式地:愛媛県砥部町扇谷陶石鉱山および広島県東広島市豊蝋鉱山
砥部雲母は高知大学の東正治によって発見された新鉱物で、愛媛県砥部町扇谷陶石鉱山から見出されたことから砥部町に因んで命名された。記載論文は東のみの単名で記載されており、1984年に東へ櫻井賞(第24号)が授けられた
砥部雲母はその和名が示すように雲母超族の一員となる鉱物である。そして雲母超族の鉱物の一般化学式はIM2-3□1-0T4O10A2であり、IとMの内容によって分類される。まずIに注目すると、そこは一価もしくは二価の陽イオンが支配し、一価だと「純雲母(True mica)」、二価だと「脆雲母(Brittle mica)」に分ける。そして続く下位分類ではMの数に注目する。Mは二価と三価の陽イオンが入り、陽イオンが三個の場合を「3八面体型(Trioctahedral type)」、二個の場合を「2八面体型(Dioctahedral type)」と分ける。個々の鉱物種はその分類の下にぶら下がる。そして砥部雲母の理想化学組成は(NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2であり、一価のアンモニウムイオン(NH4–)と二個のアルミニウム(Al2)なので、砥部雲母は「2八面体型の純雲母」ということになる。純雲母は一般に弾性があり曲げることができるが、砥部雲母も同様なのかは結晶が微細すぎて試すことはできない。しかしながらSEM写真では結晶は曲がっているように見えている。
砥部雲母の位置づけをもっと簡単に述べると、砥部雲母とは白雲母(KAl2(Si3Al)O10(OH)2)からみてカリウム(K)をアンモニウム(NH4)に置換した鉱物である。とりわけ白雲母の一部の産状である絹雲母と強く関連する。絹雲母とは超微細な白雲母の集合を示す俗名であり、流紋岩や安山岩類が熱水変質作用を受けて絹雲母ばかりになることがある。それはもはや資源でもあり、工業原料や化粧品、また陶石に利用される。愛媛県砥部町においてもいわゆる絹雲母鉱床が発達しており、それは優れた陶石として積極的に採掘されたものの、絹雲母の鉱物学的な内容はあまり検討されていなかった。
東は1970年代からいわゆる絹雲母の検討を始めており、黒鉱鉱床からはじまり続いて陶石鉱床を手掛けている。模式地である扇谷鉱山については1976年に粘土科学討論会において最初の発表が行われた。その際に化学組成への言及があり、カリウムに乏しいことからヒドロニウムイオン(H3O–)置換が想定されている[1]。翌年にはさらに検討が進んだようで、カリウムを置換していたのはヒドロニウムではなくアンモニウムであることが明らかとなっている[2,3]。だだし、この段階のデータはまだカリウム>アンモニウムに留まっており、翌1978年にはこれまでの内容が論文にまとめられた[4]。いわゆる絹雲母、それも陶石鉱床から産する絹雲母がアンモニウムを普遍的に含むこと[5]は広く知られることになった。
IMA no.から砥部雲母は1981年に新鉱物として申請されたことがうかがえる。その時までにアンモニウム>カリウムとなる標本が扇谷陶石鉱山から見いだされたということになるだろう。記載論文となる第一文献においては広島県豊蝋鉱山からも砥部雲母が見いだされたことが記されており、二つの産地の砥部雲母が同時に記載された。化学組成や赤外分光のデータに二つの産地で大きな差は見られないが、X線回折パターンでは半値幅が明らかに異なっている。その違いの原因については具体的に言及されていないが、おそらくポリタイプの存在や結晶子のサイズに起因している。
砥部雲母はアンモニウムを含む雲母ということで、それは他の雲母に比べて水素(H)に富む雲母でもある。そのため重水素(2H:D化と言ったりする)への置換が試みられ、その際の挙動などが調査された[6]。結晶構造について検討された例が第二文献であり、そのほかにも構造と結合に関連したいくつかの研究がある[7,8]。
写真はいわゆる愛媛県砥部町万年地域から得られた陶石で、おもに砥部雲母からなる。微細なフレーク状の結晶が折り重なった集合体で、舐めると舌が吸い付けられる感触がある。アンモニウムを含んでいるが砕いても出てこないのか、その臭いを感じることはなかった。
[1] 東正治, 松田栄二(1976)愛媛県砥部町扇谷陶石鉱床の絹雲母鉱物. 粘土科学討論会講演要旨集, 20, P16.
[2] 東正治(1977)愛媛県砥部陶石鉱床産雲母鉱物の層間イオン. 日本鉱物学会講演要旨集, P101.
[3] 東正治(1977)愛媛県砥部陶石鉱床産含アンモニウム雲母鉱物. 粘土科学討論会講演要旨集, 21, P35.
[4] Higashi S. (1978) Dioctahedral mica minerals with ammonium ions. Mineralogical Journal, 9, 16-27.
[5] Yamamoto T. (1967) Mineralogical studies of sericites associated with Roseki ores in the western part of Japan. Mineralogical Journal, 5, 77-97.
[6] Harlov D.E., Andrut M., Pötter B. (2001) Characterisation of tobelite (NH4)Al2[AlSi3O10](OH)2 and ND4-tobelite (ND4)Al2[AlSi3O10](OD)2 using IR spectroscopy and Rietveld refinement of XRD spectra. Physics and Chemistry of Minerals, 28, 268-276.
[7] Ishida K., Hawthorne F.C. (2013) Far-infrared spectra of synthetic dioctahedral muscovite and muscovite-tobelite series micas: Characterization and assignment of the interlayer I-Oinner and I-Oouter stretching bands. American Mineralogist, 98, 1848-1859.
[8] Mesto E., Scordari F., Lacalamita M., Schingaro E. (2012) Tobelite and NH4+ -rich muscovite single crystals from Ordovician Armorican sandstones (Brittany, France): Structure and crystal chemistry. American Mineralogist, 97, 1460-1468.
IMA No./year: 1981-034
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(M23817)(Handbook of mineralogyから引用)
ソーダ南部石 / Natoronambulite
NaMn2+4Si5O14(OH)
第一文献:Matsubara S., Kato A., Tiba T. (1985) Natronambulite, (Na,Li)(Mn,Ca)4Si5O14OH, a new mineral from the Tanohata mine, Iwate Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 12, 332-340.
第二文献:Nagashima M., Armbruster T., Kolitsch U., Pettke T. (2014) The relation between Li ↔ Na substitution and hydrogen bonding in five-periodic single-chain silicates nambulite and marsturite: A single-crystal X-ray study. American Mineralogist, 99, 1462-1470.
模式地:岩手県田野畑村田野畑鉱山(松前沢鉱床)
ソーダ南部石は南部石(Nambulite: LiMn2+4Si5O14(OH))のリチウム(Li)をナトリウム(Na)に置き換えた鉱物で、国立科学博物館の松原聰らによって岩手県田野畑鉱山からの新鉱物として発表された。ナトリウムを主成分とすることから学名はNatoroを接頭語にしているが、和名ではナトリウムをソーダと呼ぶ慣習に基づいてソーダ南部石と表記される。南部石は1971年に、ソーダ南部石はその10年後の1981年に国際鉱物学連合へ申請された新鉱物である。
南部石はリチウム優占種であり、御斎所鉱山などではリチウム端成分に近い南部石が産出する。ただ、模式地である舟子沢鉱山や近隣の大谷山鉱山から産出する南部石はかなりナトリウムに富んだ組成となっており[1,2]、南部石が記載された段階でLi-Na置換の存在は明白であったと言える。特に大谷山鉱山の南部石はナトリウムが支配的となる領域(=ソーダ南部石)まであと一歩であったことから、南部石のナトリウム置換体が存在することは想像し得たであろう。実際に、1978年にはコンバット鉱山(ナミビア)から明確にNa > Liとなる南部石の産出が報告されている[3]。それはつまりソーダ南部石であるのだが、論文タイトルからして「Second find of nambulite」であり、新種としての記載ではなかった。現代では化学組成の真ん中で種を分ける(50%則)ことは制度化されているが、1970年代までは著者らの判断に委ねられている部分があったのだろう。もともとの南部石がLi-Naの真ん中あたりの組成にあったことを思えば、リチウムだろうがナトリウムだろうが同じ、と判断したのかもしれない。
それでも鉱物分類を生業とする研究者は50%則を徐々に意識するようになり、既存の鉱物の元素置換体としての新鉱物は徐々に増えてくる。そうした状況の中、田野畑鉱山から南部石が見いだされ、その一部はナトリウム > リチウムという組成を示すことが明らかとなった。この時点でソーダ南部石に相当する鉱物の報告[3]はあれども新種としてそれは申請されておらず、結果として田野畑鉱山を模式地とするソーダ南部石が新鉱物として申請される運びとなった[4]。後年にリチウム-ナトリウム置換に伴う水素結合様式の変化が報告されている[5]。
(ソーダ)南部石はバラ輝石と同じく準輝石に分類される鉱物であり、結晶形態はお互いによく似るものの、(ソーダ)南部石はバラ輝石よりもオレンジ色が強く出ることが特徴で、肉眼鑑定は難しくない。ただ、ソーダ南部石か南部石かについては分析するしか判別方法はない。そして田野畑鉱山はソーダ南部石と南部石の両方が産出するため厄介である。単独の結晶として産出するほか、層で分布することがあり、片理に沿って割れると一面がソーダ南部石という標本が出来上がる。石英、セラン石、ブラウン鉱、苦土アルベソン閃石など、田野畑鉱山で見られる鉱物とはたいてい共生する。また模式地である松前沢鉱床だけでなく、本坑からも産出を確認している。
[1] Yoshii M., Aoki Y., Maeda K. (1972) Nambulite, a new lithium- and sodium-bearing manganese silicate from the Funakozawa mine, northeastern Japan. Mineralogical Journal, 7, 29-44.
[2] 南部松尾, 谷田勝俊, 北村強, 熊谷進 (1975) 東北地方産ケイ酸マンガン鉱の鉱物学的研究(第17報)–岩手県大谷山鉱山産南部石について–. 北大学選鉱製錬研究所彙報, 31, 27-36.
[3] Von Knorring O., Sahama Th.G., Törnroos R. (1978) Second find of nambulite. Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte, 346-348.
[4] 第一文献
[5] 第二文献
IMA No./year: 1981-050
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(M-24641); National Museum of
Natural History, Washington, D.C., USA, 165482(Handbook of mineralogyから引用)
逸見石 / Henmilite
Ca2Cu[B(OH)4]2(OH)4
第一文献:Nakai I., Okada H., Masutomi K., Koyama E., Nagashima K. (1986) Henmilite, Ca2Cu(OH)4[B(OH)4]2, a new mineral from Fuka, Okayama Prefecture, Japan, American Mineralogist 71, 1234-1239.
第二文献:設定なし
模式地:岡山県高梁市備中町布賀鉱山
逸見石は1981年に申請された日本産の新鉱物で、岡山県布賀鉱山を模式地としている。岡山大学の逸見吉之助(1919-1997)および逸見千代子(1949-2018)親子にちなんで名付けられ、両氏は布賀地域から見いだされた数々のスカルン鉱物を通じて世界でも稀な高温スカルンの詳細を明らかにしたことで鉱物学の発展に大きく貢献した。
逸見石発見の端緒は1977年5月だと伝わる[1-7]。滋賀県に在住の愛石家である岡田久らは布賀への採集行において、とある民家で研究用にと布賀鉱山内で採集された方解石のような結晶を伴う白色の石を譲り受けた。ただそれは方解石にしては軽く、その結晶系もまた方解石と異なっており、益富寿之助の見解を尋ねるべく日本地学研究会(当時)へその標本が持ち込まれている。その未詳鉱物に興味を持った益富は筑波大学の長島弘三研究室へ調査を依頼し、やがてその鉱物は世界で二番目の産出となる五水灰硼石(Pentahidroborite)であることが判明した。これは、それまで粉のような状態しか知られていなかった五水灰硼石が肉眼的な結晶として産出した初めての例であったとされる。1977年末には坑道内で五水灰硼石の露頭が発見され、そこには紫色を呈する非常に小さな鉱物が伴われていた。そして、五水灰硼石の研究がひと段落したのちに紫色鉱物の研究が始まり、1981年に新鉱物・逸見石として申請される運びとなったようだ。
逸見石は非常に小さなほとんどシミに近い状態で産出したと記録されており、そのほとんどが不定形で、自形結晶も最大で0.2mm程度が見つかる程度であった[8]。そのため分析や測定はたいへん困難であったと思われるが、記載論文では単結晶X線構造解析を駆使して精度の高い組成式を導くことに成功している[8]。記載論文に用いられた逸見石はおそらく通称2番坑で得られたと思われ、その後1992年までに3番坑においてある程度まとまった量が産出した。その逸見石を用いて物理的性質や熱的挙動などが報告されている[9]。それでもまだ逸見石の産出はまれと言える状態であったが、2002年には4番坑において幅3m長さ7mにも達する大きな空洞が発見され、その壁の一面には無数の逸見石が自形結晶として付着していたのだった。きわめて大量かつ最大で1cmに達し、平均的にも数mmという結晶を用いて詳細な結晶図が作成された[10]。
化学組成をみると、逸見石は銅(Cu)を主成分としており、そのほかに余計な遷移金属を含まない。これは物性物理分野での研究対象となりうる条件の一つであり、その磁性に注目した物理学的研究が行われた[11]。その際に結晶構造も検討されている。おそらく4番坑で得られた結晶だと思われるが、それは2番坑で得られた結晶とは構造がやや異なっているようで、内容を検証したところ2番坑で得られた従来型を-1aと表記したときに、4番坑で得られた新型は-2aと表記できるポリタイプになっている。ただ、鉱物種の定義からすると、構造が従来型・新型のいずれであっても「種」という単位では逸見石(Henmilite)という単独の鉱物種であって、ラベルを書き換える必要はない。
写真の標本はいずれも4番坑で得られた逸見石で、所有標本の中でもっとも結晶が際立つものを載せている。これは母岩が方解石であるが、五水灰硼石やなにやらよくわからない白いだけの鉱物が母岩になることもあって、全体をみると標本としてのツラはそれぞれ異なる。一方、逸見石それ自体は立派であるほど大きな違いはないようにみえる。大きな結晶は鮮やかで深く透明感のある青色を呈し、形状はまるで氷砂糖である。かつてはシミのような姿でさえ目にすることが難しかったが、今では逸見石は最も目にする日本産新鉱物だと言えるだろう。いまのところ逸見石は布賀鉱山以外からは見つかっていない。
[1] 逸見石物語 その1: http://odamakituusin.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-0a3c.html
[2] 逸見石物語 その2: http://odamakituusin.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/2-45e4.html
[3] 逸見石物語 その3: http://odamakituusin.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-db9c.html
[4] 逸見石物語 その4: http://odamakituusin.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-68c7.html
[5] 逸見石物語 その5: http://odamakituusin.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-cdc8.html
[6] 逸見石物語 その6: http://odamakituusin.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-5523.html
[7] 逸見石物語 その7: http://odamakituusin.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-57c3.html
[8] 第一文献
[9] 草地功 (1992) 逸見石の鉱物学的性質. 鉱物学雑誌, 21, 127-130.
[10] 高田雅介, 草地功, 岸成具, 田邊満雄, 安田隆志 (2005) 岡山県布賀鉱山産硼酸塩鉱物の結晶形態. 岩石鉱物化学, 34, 252-260.
[11] Yamamoto H, Sakakura T., Jeschke H.O., Kabeya N., Hayashi K., Ishikawa Y., Fujii Y., Kishimoto S., Sagayama H., Shigematsu K., Azuma M., Ochiai A., Noda Y., Kimura H. (2021) Quantum spin fluctuations and hydrogen bond network in the antiferromagnetic natural mineral henmilite. Physical Review Materials, 5, 104405.
IMA No./year: 1982-004
IMA Status: A(approved)
模式標本:不明
片山石 / Katayamalite
KLi3Ca7Ti2(SiO3)12(OH)2
第一文献:Murakami N., Kato T., Hirowatari F. (1983) Katayamalite, a new Ca-Li-Ti silicate mineral from Iwagi Islet, Southwest Japan, Mineralogical Journal, 11, 261-268.
第二文献:Andrade M.B., Doell D., Downs R.T., Yang H. (2013) Redetermination of katayamalite, KLi3Ca7Ti2(SiO3)12(OH)2. Acta Crystallographica, E69, i41-i41
模式地:愛媛県上島町岩城島
片山石は山口大学の村上允英らによって記載された愛媛県岩城島を模式地とする新鉱物で、東京大学や九州大学で教鞭を執った片山信夫教授にちなんで命名された。片山石は現状では有効な日本産新鉱物の一つであるが、1990年代には片山石とバラトフ石(Baratovite)が同一の鉱物ではないかという疑義が上がっており、そのことはすでに愛石家の間にも広く知れ渡っている。ただし、現時点(2022年4月)であってもバラトフ石と片山石は別々の鉱物として公式リストに登録されている。ここでは公式リストの現状に基づいて片山石を「日本から発見された新鉱物たち(一覧)」のほうへ掲載することにした。以下に解説を述べよう。
片山石の前にバラトフ石の経緯をおさらいしてみる。バラトフ石は1974年にタジキスタンからの新鉱物として申請された鉱物で、学名は同国の岩石学者であるRauf Baratovich Baratov (1921-2013)にちなんで命名された。1975年に記された論文では、化学組成は4(KCa8Li2Si12O37F)のように表現できたようだ[1,2]。また、この段階で正しい対称性(単斜晶系)と格子定数が得られてもいる。そして、1979年までに正しい結晶構造が判明し、化学組成がKLi3Ca7(Ti,Zr)2[Si6O18]2F2へ改定された[3,4]。ここまでの流れは順当であるように見えるが、実は最初の報告では構造が決まっていなかったこともあって水酸基の量が過小評価されていた。実際のところはOH > Fであるのだが、F優占種として記載されたがために、正しい結晶構造が導かれた際もOHではなくFで組成式が組まれてしまい、その点の改訂がなかった。これがそもそもの発端である。この段階で最初の記載論文の見直しがあったら片山石は誕生しなかったかもしれない。
さて、片山石は1982年に新種として申請されたが、発見そのものはバラトフ石よりもずっと前の1944年までさかのぼる。片山石はかつては単斜灰簾石(斜ゆう簾石)として記載された[5]。いつ頃に単斜灰簾石→新鉱物(片山石)への進捗があったかは定かでないが、1976年には(申請前だが)片山石を発見したと述べられている[6]。記載論文は1983年に発表されており[7]、(K,Na)Li3Ca7(Ti,Fe3+,Mn)2[Si6O18]2(OH,F)2という化学組成が示された。これは現代でも通用するほぼ正しい内容であって、先に報告のあるバラトフ石から見るとF→OH置換体に相当する。また、結晶構造は三斜晶系で解析されている[8]。この当時であっても化学組成としてFかOHかは種を分ける基準であったし、構造についてもこの当時は対称性が異なるだけで別種と扱っていたため、片山石はバラトフ石とは異なる新種として問題なく承認されている。1984年に片山石がAmerican Mineralogist誌で紹介されているが、バラトフ石と片山石は明らかに別種として区別されている[9].
風向きが変わったのは1992年であろう。この年に片山石とバラトフ石は構造的に同一であるという論文が提出された[10]。バラトフ石のほうは先に報告のあった結晶構造で問題なかったが、片山石のほうは結晶軸の選択ミスのために誤って三斜晶系で解析されたものの、結晶軸の選択をやり直すとバラトフ石と結局は同じという内容であった。ただ、この論文中では鉱物種の同一性までは言及しておらず、F種のバラトフ石、OH種の片山石という分け方は維持されている。しかし1993年、American Mineralogist誌でこの論文が紹介される際に同一性が疑われた。対称性や結晶構造が共通、なによりバラトフ石の記載論文のデータを再解析するとFではなくOHが優勢であることが指摘されている[11]。それぞれオリジナルのデータを客観的に見ればバラトフ石=片山石はもう疑いようがない。一方で、模式地からのバラトフ石を再検討したらそれはF種であったという別の報告がある[12]。それならF種のバラトフ石、OH種の片山石という分け方がやはり可能かもしれないが、こういう分類は結局のところ「模式標本がどうであるか」が本質である。逆をつくと、F種のバラトフ石、OH種の片山石という分け方になるように模式標本を再設定すればいいのではないか、という考えがあたまに浮かぶ。
それで結局どうなったかというと、どうにもなっていない、止まっている。オリジナルデータの比較としては1993年の段階でバラトフ石と片山石を分ける根拠は消滅したが、この二つの鉱物のうちどちらを抹消とすべきかについて、新鉱物・命名・分類委員会は何も判断を下していない。鉱物種を抹消するにもまた「抹消の提案書」を新鉱物・命名・分類委員会へ提出し、審査される必要がある。現状ではだれもその抹消の提案書を提出していないので、状況は何も動いていないというのが実情だろう。2013年には再び結晶構造についての研究報告があり、1992年報告からの微修正があったもののこれは大きな動きにはつながらない[13]。結局、いくら疑いがかかろうとも、公式リストにはいまだにバラトフ石はF優占種として、片山石はOH優占種として記されているのが現状である。後世にこの問題がどうなるかはわからないが、一般に後発のほうが不利をこうむることが多い。
片山石は愛媛県岩城島の一部に分布するいわゆるエジル石閃長岩(いまではアルビタイトと呼ばれている)を構成する鉱物の一つとして産出する。無色透明~白色であるために岩石に埋没している状態だとどこにいるのか全く分からないが、短波長の紫外線を照射すると強烈な青色蛍光を示すので暗闇ではその所在がよく変わる。共生鉱物として杉石よりもエジリンを好む傾向があり、経験的にはエジリンが多いほど片山石も多い。
[1] Dusmatov V.D., Semenov E.I., Khomayakov A.P., Bykova A.V., Dzharfarov N.K. (1975) Baratovite, a new mineral, Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva, 104, 580-582.
[2] Fleischer M., Pabst A., Cabri L.J. (1976) New mineral names. American Mineralogist, 61, 1053-1056.
[3] Sandormirskii N.A., Simonov M.A., Belov N.V. (1976) The crystal structure of KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2F2. Soviet Physics – Doklady, 21, 618-620.
[4] Menchetti S., Sabelli C. (1979) The crystal structure of baratovite. American Mineralogist, 64, 383-389
[5] 杉健一, 久綱正典 (1944) 愛媛県岩城島産エヂル石閃長岩に就いて. 岩石鉱物鉱床学会誌, 31, 209-224.
[6] 村上允英 (1976) 本邦産交代性閃長岩質岩石中の鉱物共生. 岩石鉱物鉱床学雑誌, 特別号(1), 261-281.
[7] 第一文献
[8] Kato T., Murakami N. (1985) The crystal structure of katayamalite. Mineralogical Journal, 12, 206-217.
[9] Dunn P.J., Fleischer M., Francis C.A., Langley R.H., Kissin S.A., Shigley J.E., Vanko D.A., Zilczer J.A. (1984) New mineral names. American Mineralogist, 69, 810-815.
[10] Baur W.H., Kassner D. (1992) Katayamalite and baratovite are structurally identical. European Journal of Mineralogy, 4, 839-841.
[12] Pautov L.A., Karpenko V.Y., Agakhanov A.A. (2013) Baratovite-katayamalite Minerals from the Hodzha-achkan Alcaline Massif (Kirgizia). New Data on Minerals, 48,12-36.
[13] 第二文献
IMA No./year: 1982-102(2012s.p.)
IMA Status: A(approved)
模式標本:東京大学(M23378)(Handbook of mineralogyから引用)
カリ定永閃石 / Potassic-sadanagaite(原記載はMagnesiosadanagaite)
KCa2(Mg3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2
第一文献:Shimazaki H., Bunno M., Ozawa T. (1984) Sadanagaite and magnesio-sadanagaite, new silica-poor members of calcic amphibole from Japan. American Mineralogist, 69, 465-471.
第二文献:設定なし
模式地:愛媛県今治市宮窪町明神島
カリ定永閃石は東京大学の島崎英彦らによって見いだされた新種の角閃石で、根源名は東京大学の名誉教授であった定永両一(1920-2002)にちなんでいる。記載論文はカリ定永閃石とカリフェロ定永閃石が同時に記載されているが、旧IMAno.からは申請時期に違いがあったことが読み取れ、先にカリフェロ定永閃石が1980年に、その後にカリ定永閃石が1982年に申請されている。
名称については角閃石命名規約の変遷に伴い何度か変わっている。今でいうカリ定永閃石は最初は苦土定永閃石(magnesio-sadanagaite)の名称で記載された[1]。1997年に角閃石の命名規約が変更になると、次はカリ苦土定永閃石(potassic-magnesiosadanagaite)へ改名されている[2]。しかしこれは中途半端な改名であった。1997年命名規約ではVIAl > 1.0の場合は「alumino」の接頭語を冠する必要があったのだが、定永閃石系の理想式は必ずVIAl > 1.0であるものの、そのルールが適用されなかった。理由は全く不明で、定永閃石系を扱うものにとっては迷惑極まりない命名規約だったと言えよう。この命名規約はほかにも不備がたくさんあり、2012年にまた改められることになる[3]。その際にようやく命名ルールの適用が厳格化され、名称がカリ定永閃石(potassic-sadanagaite)として定まった。以降、現在の名称で本鉱を記す。
カリ定永閃石とカリフェロ定永閃石は同じ論文中で記載されており、それぞれの模式地が明神島および弓削島と記されている。そしてそれらは領家帯と秩父帯の境界近くに位置すると書かれ、さらに境界線が瀬戸内海を南北に分断するように図示されている。しかし、そんなところに領家帯と秩父帯の境界なぞ存在しない。それでも弓削島と明神島の位置関係は正しいと思われ、明神島の北側の石灰岩からカリ定永閃石が産出することは私自身も確認している[4]。産状は弓削島とほとんど共通で、石灰岩に胚胎されるレンズ状の黒色塊にカリ定永閃石は含まれる。自身の卒論~修論で調べた範囲では、明神島からはカリ定永閃石ばかりが産出し、カリフェロ定永閃石はここでは見つからなかった。共生鉱物としては鉄スピネル、イルメナイト、透輝石、ベスブ石が主となっている。
根源名に定永閃石(Sadanagaite)を有する角閃石はカリフェロ定永閃石とカリ定永閃石が始まりで、さらに2種が追加された計4種が今の公式リストに加えられている。そのうち3種が日本から見つかった新種となっている。ついでに述べると、記載論文[1]の表1の末尾に掲載された組成を今の定義で解釈するとカリフェリ定永閃石という新種に相当する。ただそれは最新の角閃石命名規約では取り上げられなかった。それはともかく、いわゆる定永閃石は非常にアルミニウム(Al)に富む組成が特徴で、明神島や弓削島ではボーキサイトやラテライトのようなアルミニウムに富む土壌が変成作用を被ることで生成した。同様の産状は睦月島で確認されており、そこでもカリ定永閃石が産出することを確認している[4]。いずれもほとんどの場合で不定形な黒色粒として産出するため、一見して角閃石らしくないが、明神島からは晶癖が発達したいかにも角閃石らしい標本が得られたことがある。カリ定永閃石は今のところきわめて産出のまれな角閃石のようで、Mindatを参照すると海外にはイタリアに一つ産地があるだけになっている。
[1] 第一文献
[2] Leake B.E., Woolley A.R., Arps C.E.S., Birch W.D., Gilbert M.C., Grice J.D., Hawthorne F.C., Kato A., Kisch H.J., Krivovichev V.G., Linthout K., Laird J., Mandarino J.A., Maresch W.V., Nickel E.H., Rock N.M.S., Schumacher J.C., Smith D.C., Stephenson N.C.N., Ungaretti L., Whittaker E.J.W., Youzhi G. (1997) Nomenclature of amphiboles: report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. The Canadian Mineralogist 35, 219-246
[3] Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist 97, 2031-2048.
[4] 西尾大輔, 皆川鉄雄 (2003) 明神島および睦月島にみられるAl質スカルンに産するtitanian esseneitic diopside. 岩石鉱物科学, 32, 68-79.
IMA No./year: 1983-016
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(ナンバー不明); National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 160484.(Handbook of mineralogyから引用)
ストロナルス石 / Stronalsite
Na2SrAl4Si4O16
第一文献:Hori H., Nakai I., Nagashima K., Matsurbara S., Kato A. (1987) Stronalsite, SrNa2Al4Si4O16, a new mineral from Rendai, Kochi City Japan. Mineralogical Journal, 13, 368-375
第二文献:Liferovich R.P., Mitchell R.H., Zozulya D.R., Shpachenko A.K. (2006) Paragenesis and composition of banalsite, stronalsite, and their solid solution in nepheline syenite and ultramafic alkaline rocks. The Canadian Mineralogist 44, 929-942.
模式地:高知県高知市蓮台

岡山県新見市大佐山
母相であるヒスイ輝石岩を白色の方沸石脈が横切り、その脈中に微細なストロナルス石が点在する。

後方散乱電子像
方沸石脈中において一部が四角形となる微細な粒子としてストロナルス石は産出する。
ストロナルス石は鉱物科学研究所(現:ホリミネラロジー)の堀秀道によって高知県蓮台から発見された長石族の新鉱物で、筑波大学および国立科学博物館を加えた研究チームによって記載された。ストロナルス石はそれより先に知られていたバナルス石(Banalsite: Na2BaAl4Si4O16)のストロンチウム(Sr)置換体に相当する鉱物で、バナルス石が化学組成にちなんで命名されたことを例に、ストロナルス石もまた化学組成にちなんで命名されている。
四国の中央部から南部において東西に分布する黒瀬川帯は蛇紋岩メランジェとなっており、とくに高知県高知市から西にかけては蛇紋岩の露出が見られる。それらは製鉄用や埋め立てなど様々な用途のためにかつては盛んに採掘されていた。1980年にはそうした蛇紋岩(旧:鏡村去坂)から、当時はまだ珍しい鉱物であったスローソン石(Slawsonite: Sr(Al2Si2O8))の産出が報告された[2]。そして後に高知市蓮台の砕石所においてもスローソン石の産出が知られるようになり、興味を持って蓮台を訪れた堀はスローソン石とおぼしき白色の鉱物をいくつか採集している。その中でスローソン石とは外観のやや異なる鉱物が存在することに気づき、簡易的な調査によってバナルス石と共通の構造ながらもストロンチウムに富む未知の鉱物であることが判明した。その後、筑波大学と国立科学博物館の研究者を加えての検討で詳細が明らかとなり、1983年には「未知の長石族鉱物」として学会で発表されている[3]。IMAno.を見ると、学会発表の段階では新鉱物申請が行われていると思われる。
ストロナルス石の第二産地は1984年には見つかっており、岡山県新見市大佐山に分布するヒスイ輝石岩に含まれていることが報告された[4]。記載論文は1987年に記され、そこでは岡山県新見市大佐山からのストロナルス石も同時に記載されている[1]。また、この記載論文に先立って科学博物館の館報にも論文が1985年に記された[5]。正記載論文との順序が逆になっているせいだろうか、ストロナルス石がAmerican Mineralogist誌でレビューされた際には意味深なコメントが残っている[6,7].
ストロナルス石は珍しいと言えば珍しい鉱物であるが、今となっては世界中で10カ所以上の産地が知られる。日本では後に新潟県糸魚川地域から見つかっている。今であっても観察が可能な大佐山を例にすると、ヒスイ輝石を母岩とするものの、やや変質の大きい箇所からストロナルス石が見つかる。おそらくはロジン岩化作用を被る際に形成されたのだろう。模式地である高知市蓮台もまた強いロジン岩化作用を被っている場である。一方それとは異なる成因で生じたストロナルス石が海外で報告されている[8]。
写真は大佐山の標本となる。そのままでは全く所在不明であったが、切断研磨した状態で何となく存在が理解できる。ヒスイ輝石岩を横切る方沸石脈中に、微細ながらもストロナルス石はしばしば含まれる。
[1] 第一文献
[2] 加藤昭, 松原聰 (1980) 高知県土佐郡鏡村産Slawsonite. 日本鉱物学会年会講演要旨集. P141.
[3] 堀秀道, 中井泉, 長島弘三, 松原聰, 加藤昭 (1983) 未知長石族鉱物SrNa2Al4Si4O16高知市蓮台産. 日本鉱物学会年会講演要旨集, P10.
[4] 小林祥一, 三宅寶, 正路徹也 (1984) 岡山県大佐町産jadeite. 三鉱学会連合学術講演要会講演要旨集, P86.
[5] Matsubata S. (1985) The mineralogical implication of barium and strontium silicates. Bulletin of the National Museum of Nature and Science Series C (Geology and Paleontology), 11, 38-95.
[6] Hawthorne F.C., Bladh K.W., Burke E.A.J., Grew E.S., Langley R.H., Puciewicz J., Roberts A.C., Schedler R.A., Shigley J.E., Vanko D.A. (1987) New mineral names. American Mineralogist, 72, 222-230.
[7] Hawthorne F.C., Burke E.A.J., Ercit T.S., Grew E.S., Grice J.D., Jambor J.L., Puziewicz J., Roberts A.C., Vanko D.A. (1988) New mineral names. American Mineralogist, 73, 189-199.
[8] 第二文献
IMA No./year: 1984-015
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(ナンバー不明); National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 165991.(Handbook of mineralogyから引用)
アンモニオ白榴石 / Ammonioleucite
(NH4)(AlSi2O6)
第一文献:Hori H., Nagashima K., Yamada M., Miyawaki R., Marubashi T. (1986) Ammonioleucite, a new mineral from Tatarazawa, Fujioka, Japan, American Mineralogist, 71, 1022-1027.
第二文献:Yamada M., Miyawaki R., Nakai I., Izumi F., Nagashima K. (1998) A Rietveld analysis of the crystal structure of ammonioleucite. Mineralogical Journal 20, 105-112.
模式地:群馬県藤岡市下日野鈩沢(たたらざわ)
アンモニオ白榴石は鉱物科学研究所(現:ホリミネラロジー)の堀秀道によって記載された新鉱物で、白榴石(leucite: K(AlSi2O6))のアンモニウム(NH4)置換体に相当することから学名が定められた。この時点でアンモニウム基を持つ鉱物はアンモニウム長石(buddingtonite: (NH4)(AlSi3)O8)および砥部雲母(tobelite: (NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2)が知られるのみであり、アンモニオ白榴石はアンモニウム基を主成分とする3番目の鉱物となった。アンモニオ白榴石の記載により堀には櫻井賞(第26号メダル)が授けられている。また、欽一石およびストロナルス石を加えた3種の新鉱物の発見と記載により、堀は東北大学により学位(理学博士)を授与されている。
日本列島には中央構造線と呼ばれる第一級の断層が、九州東部から関東にかけて東西に横切っていることがよく知られている。西から東へ見ていくと連続性がよく観察されるのは四国から長野県西部あたりまでで、そこから東のフォッサマグナ地域となると堆積岩の被覆によって中央構造線の分布はいったん追えなくなる。さらに東にすすむと関東山地があり、そこでは再び中央構造線が追えるものの、群馬県下仁田地域あたりでまた徐々に追うことが難しくなる。そこで、下仁田地域における中央構造線の特定が高校教員を主体とする研究グループによって行われていた[1]。その調査の一環として、研究グループの一員である丸橋剛によって群馬県下仁田町の鈩沢で稼働していた砕石所(富岡鉱業)からドーソン石やノルドストランド石などの当時まだ珍しかった鉱物がまず見いだされている[2]。記載論文によると、その発見に続いて堀がアンモニオ白榴石を見出したとされる[3]。
砕石所は三波川変成帯と第三紀砂岩の境界に位置しており、緑色片岩には大小さまざまな炭酸塩脈が走る。そういった脈の一部は空隙となっており、その中から方沸石に似た12面体結晶が見いだされた。その結晶は白濁しながら樹脂光沢を示しており、それは白濁しつつもガラス光沢を保つことが一般的な方沸石とは異なる特徴だった。そうした違いに気が付いた堀によって調査が始まり、この結晶の大部分が白榴石型の構造を持つことが明らかとなった。さらなる調査は筑波大学の研究チームの下で行われ、白榴石に本来あるべきカリウム(K)が少なく代わりにアンモニウム基が多く含まれていることが判明した。この時点でアンモニウム基が置換した白榴石は合成物では知られていたものの[4,5]、天然における産出はまだなかった。そのため化学組成と構造からアンモニオ白榴石という名称を定め、新鉱物として申請される運びとなった。
アンモニオ白榴石の結晶構造は筑波大学の研究チームによって検討された[6]。アンモニオ白榴石は非常に双晶に富むことから、検討は粉末のリートベルト解析によって行われている。その構造は3次元的な籠(ケージ)を編んでおり、シリコン(Si)とアルミニウム(Al)が酸素と結合した四面体が骨格となって、その隙間にアンモニウム基が位置している。白榴石の場合はカリウムとなる。こうした結晶構造は基本的に方沸石と共通であることから、(アンモニオ)白榴石は沸石族の一員に分類される[7]。ただし(アンモニオ)白榴石は構造の隙間に水を含まないことから、加熱をしても一般的な沸石のように泡立つということがない。
写真の結晶は模式地のアンモニオ白榴石となる。白濁している部分がアンモニオ白榴石で、その内部には方沸石が残っていることが多い。記載論文にもその旨が記されている。こういった結晶は、方沸石として成長したのちにアンモニウムを含む熱水による変質を受けて生成したと考えられている。合成実験でもいったん方沸石を作ったのちにアンモニウムで置換するという工程が組まれる。
[1] 鏑沢団体研究グループ (1985) 関東山地北縁からの牛伏山衝上断層(新称)の発見. 地質学雑誌, 91, 375-377.
[2] 木崎喜雄, 丸橋剛, 鏑沢団体研究グループ (1982) 群馬県藤岡市西部から産出するdawsonite,norolstrandite. 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, 136.
[3] 第一文献
[4] Barrer R.M. (1950) Ion-exchange and ion-sieve processes in crystalline zeolites. Journal of Chemical Society, 1950, 2342- 2350.
[5] Barrer R.M., Baynham J.W. and McCallum N. (1953) Hydrothermal chemistry of silicates. Part V. Compounds structurally related to analcime. Journal of Chemical Society, 1953, 4035-4041.
[6] 第二文献
[7] Coombs D.S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J.D., Liebau F., Mandarino J.A., Minato H., Nickel E.H., Passaglia E., Peacor D.R., Quartieri S., Rinaldi .R, Ross M., Sheppard R.A., Tillmanns E., Vezzalini G., (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names, The Canadian Mineralogist, 35, 1571-1606.
IMA No./year: 1984-057
IMA Status: A(approved)
模式標本:National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 122089.(Handbook of mineralogyから引用)
滋賀石 / Shigaite
Mn6Al3(OH)18[Na(H2O)6](SO4)2・6H2O
第一文献:Peacor D.R., Dunn P.J., Kato A., Wicks F.J. (1985) Shigaite, a new manganese aluminum sulfate mineral from the Ioi mine, Shiga, Japan. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte 1985, 453-457.
第二文献:Cooper M.A., Hawthorne F.C. (1996) The crystal structure of shigaite, [AlMn2+2(OH)6]3(SO4)2Na(H2O)6(H2O)6, a hydrotalcite-group mineral. The Canadian Mineralogist, 34, 91-97.
模式地:滋賀県栗東市下戸山五百井鉱山(旧:栗東町)
滋賀石は滋賀県五百井(いおい)鉱山を模式地とする新鉱物で、滋賀県にちなんで命名された。今となっては県名にちなんだ日本産新鉱物は複数知られているが、その先例となったのがこの滋賀石であった。記載論文の筆頭著者はミシガン大学に籍を置くアメリカ人研究者のD. Peacorである。第三著者に国立科学博物館の加藤昭が著者に参画しているものの、日本産新鉱物に海外の研究者が筆頭となる例は非常にめずらしい。
滋賀県五百井鉱山は琵琶湖南東地域に分布する小規模なマンガン鉱床のひとつで、明治期から開発が行われ、1963年(昭和38年)8月31日に閉山に至った。加藤が標本を採取したのは1963年の8月だと記載論文に記されており、閉山直前のことだった。標本はズリから採集されたようで、後に滋賀石となる黄色の六角板状結晶についてはムーア石(mooreite: Mg15(SO4)2(OH)26·8H2O)との関連が暫定的に書き留められただけだった[1]。
IMA Noからすると新鉱物申請はそこから20年後の1984年のことであり、記載論文は翌年に公表されている。記載論文には加藤が採集した鉱物は新鉱物になりうることが判明し、ムーア石やその類縁鉱物であるローソンバウエル石(lawsonbauerite: Mn2+9Zn4(SO4)2(OH)22·8H2O)との関連が確認されたと冒頭に記されている。一方で、滋賀石についてはこの時点で構造解析が成功していない。この段階ではa軸とc軸の比率と{001}に完全なへき開という特徴から、八面体がシート状に並んでいることが予想されるのみであった。また化学組成はAl4Mn7(SO4)(OH)22・8H2Oとなっており、電子顕微鏡による分析ではこれ以外の元素は検出されなかったと記してある。しかし後年、滋賀石にはNaが必須だと明らかになった。
1996年までに滋賀石の産地は海外でいくつか知られるようになっており、カラハリ地区(南アフリカ)のN’Chwaning鉱山から産出する滋賀石を用いて、結晶構造と理想化学組成の再検討が進められた[2]。これによって滋賀石にはNaが必須であることが明らかとなり、理想化学組成は今の表記に改められた。滋賀石は電子線に弱く、Naもまた飛びやすい元素でもあるので分析にはやや注意が必要である。自分の標本ではどうかと試してみたら、電子線を当てた箇所にはやっぱり穴が開く。それでもNaは十分に検出されたので、Peacorらの研究でNaが検出されなかった理由ははっきりしない。
構造としては当初に予想されていた八面体がシート状に並んでいることが確認されたものの、滋賀石はムーア石やローソンバウエル石とは同族にはなりえない構造であった。今ではウェルムランド石族(wermlandite Group)の一員であることが判明しており、その構造はハイドロタルク石型に分類される。2012年にはハイドロタルク石超族(hydrotalcite supergroup)に組み込まれることになった[3]。
模式地からの滋賀石は山田滋夫氏からいただいた。山田氏もまた閉山の間際に訪れたと聞いている。模式地の滋賀石は透明な黄色を示す六角板状結晶で、一部ではロゼッタ集合となる。群馬県栗東鉱山や長野県浜横川からは被膜状の滋賀石が産し、これもかつてはムーア石ではなかろうかとされていた。いずれも高品位鉱石の裂傷に生じる。海外でもアメリカやオーストラリアで黄色の滋賀石の産出が知られるが、南アフリカで橙色を示す滋賀石が多産したこともあって、いまではそれが滋賀石の代表的な標本となっている。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] Mills S.J., Christy A.G., Génin J.M.R., Kameda T., Colombo F. (2012) Nomenclature of the hydrotalcite supergroup: natural layered double hydroxides. Mineralogical Magazine, 76, 1289-1336.
IMA No./year: 1984-073
IMA Status: A(approved)
模式標本:国立科学博物館(M-24513);National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 164269.(Handbook of mineralogyから引用)
イットリウム木村石 / Kimuraite-(Y)
CaY2(CO3)4・6H2O
模式地:佐賀県唐津市肥前町切木(旧:肥前町)
第一文献:Nagashima K., Miyawaki R., Takase J., Nakai I., Sakurai K., Matsubara S., Kato A., Iwano S. (1986) Kimuraite, CaY2(CO3)4·6H2O, a new mineral from fissures in an alkali olivine basalt from Saga Prefecture, Japan, and new data on lokkaite. American Mineralogist, 71, 1028-1033
第二文献:設定なし
イットリウム木村石は希土類元素分析の大家として知られる木村健二郎(1896-1988)にちなんで命名された新鉱物であり、希土類元素鉱物の研究を通じて地球化学と鉱物化学の発展に貢献した業績がたたえられた。木村には新鉱物としての業績として石川石(Ishikawaite)があり、これは日本で最も古い有効な新鉱物として知られている。木村は東京帝国大学(当時)において20年以上も教授職にあって多くの門下生を育てた。イットリウム木村石の筆頭著者である長島弘三もその一人である。研究が行われていた当時、長島は筑波大学で教授を務めていた。しかし、イットリウム木村石が承認された少し後の1985年に病で急逝し、記載論文はさらにその門下生の手にゆだねられた。論文は1986に公表され、著者の一人である中井泉には木村石発見の功績で櫻井賞(第29号メダル)が授けられた。
イットリウム木村石は幾人ものリレーによって実現した新鉱物であろう。記載論文の記述によれば、福岡県古賀町在住の岩野庄市郎が1982年に小さく脆い鉱物を採集したことから始まっている[1]。その標本は櫻井欽一の元に送られ、まず酸や紫外線に対する応答性が調べられた。続いて国立科学博物館の加藤昭と松原聰の協力を得て予備調査が始まっている。そして、ランタン石やロッカ石と似つつも異なる新種である可能性が浮かび上がり、その研究を筑波大学の長島研究室が引き継いだという経緯が読み取れる。その結果、イットリウム木村石が新鉱物として誕生することになり、さらにはロッカ石についても理想化学組成を更新するという成果を得ている。
イットリウム木村石は佐賀県肥前町(当時)に広く分布するアルカリ玄武岩を母岩とする。このアルカリ玄武岩は東松浦玄武岩と呼ばれ、その発生はプレートの沈み込みとは直接関係のないマントル深部からのプリュームに起因すると考えらえている。結果的に、特に晩期の活動で生じた玄武岩は普遍的な玄武岩と異なり、希土類元素に富むという特異な性質を持っている。この玄武岩から発見された新鉱物は現時点で5種に上り、イットリウム木村石がその端緒となっている。
イットリウム木村石はカルシウム(Ca)とイットリウム(Y)を主成分とする含水炭酸塩鉱物で、記載論文ではその分析におそらくその当時の最先端の分析機器である高周波誘導プラズマ発光分光(ICP-AES)が用いられている。これによって希土類元素とカルシウム量が精度よく得られ、希土類元素についてはセリウム(Ce)が極端に少ない特徴が示されている。これは共存するネオジウムランタン石(lanthanite-(Nd))やイットリウムロッカ石(lokkaite-(Y))も同様であった。またこの研究によってイットリウムロッカ石の理想化学組成も再定義されている。厳密に求められた化学組成から、イットリウムロッカ石の加水分解によってイットリウム木村石とネオジムランタン石が生じたことが明らかとされた。
イットリウム木村石はテンゲル石族に分類される。メンバーは、イットリウムテンゲル石(tengerite-(Y))、イットリウムロッカ石、イットリウム木村石、イットリウム肥前石(hizenite-(Y))となっている。これらのうちで構造が解明されているのはイットリウムテンゲル石のみであるが、化学組成(Ca/Y比)と格子定数に規則性が見つかっており、それぞれの構造はおおむね予測されている[2,3]。またイットリウム木村石とイットリウムロッカ石については結晶構造の詳細が報告された[4]。
もう20年以上も前になるが、岩野庄市郎氏の案内でアルカリ玄武岩のいくつかの露頭を巡ったことがある。イットリウム木村石の最初の発見地である切木や、その次の産地である新木場を見た後で満越に案内してもらった。そこには巨岩がそびえており、数人がかりで叩きまくって得られたのが写真の標本であった。イットリウム木村石の結晶は白色で絹糸光沢を示すペラペラな板状だが、それらは放射状に集合して丸くなることが多い。イットリウムロッカ石やネオジムランタン石が内部にいることもある。満越にある巨岩は年々小さくなるどころか掘り下げられるたびに広がるようで、今ではその当時より大きな範囲が露出している。
[1] 第一文献
[2] 田原岳史, 保倉明子, 中井泉, 宮脇律郎, 松原聰 (2003) 木村石-(Y)およびロッカ石-(Y)の結晶構造. 日本鉱物学会2003年度年会, K3-06.
[3] Takai Y, Uehara S (2013) Hizenite-(Y), Ca2Y6(CO3)11·14H2O, a new mineral in alkali olivine basalt from Mitsukoshi, Karatsu, Saga Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 108, 161-165.
[4] 宮脇律郎, 門馬綱一, 松原聰, 田原岳史, 中井泉(2013) 木村石とロッカ石の結晶構造. 日本鉱物科学会2013年年会, R1-14.
IMA No./year: 1985-010a
IMA Status: A(approved)
模式標本:文献上は不明
オホーツク石 / Okhotskite
Ca2Mn2+Mn3+2(Si2O7)(SiO4)(OH)2・H2O
模式地:北海道常呂町国力鉱山
第一文献:Togari K., Akasaka M. (1987) Okhotskite, a new mineral, an Mn3+-dominant member of the pumpellyite group, from the Kokuriki mine, Hokkaido, Japan. Mineralogical Magazine, 51, 611-614.
第二文献:Akasaka M., Suzuki Y., Watanabe H. (2003) Hydrothermal synthesis of pumpellyite–okhotskite series minerals. Mineralogy and Petrology, 77, 25-37.

愛媛県大洲市上須戒鉱山
オープンニコル写真。強い多色性により黄土色~茶褐色を示す。
オホーツク石はパンペリー石族の新種として記載された鉱物で、北海道大学の戸苅賢二と赤坂正英によって見いだされた。命名はオホーツク海にちなむ。記載論文には模式地である国力鉱山がオホーツク海沿いにあるからとのみ簡潔にその理由が述べられているが[1]、国力鉱山はオホーツク海から直線でも20kmほど離れた山中にある。この距離感を海沿い(近い)と感じるのは道民ならではの感性であろう。ちなみにオホーツクとはロシア語で「狩猟」を意味する。筆頭著者である戸苅はオホーツク石発見の功績により櫻井賞(第30号メダル)を受賞した。もう一方の著者である赤坂はパンペリー石族の研究を継続し、その業績で後に櫻井賞奨励賞を受賞することになる。
国力鉱山はマンガン(Mn)を少量含むものの、総体としてはチャートに胚胎される赤鉄鉱鉱床となっている。鉱床は南北に15km東西に10kmにわたって分布しており、重要な鉱床には北光、仁倉、国力、柴山の各鉱山が置かれた[2]。そのうち国力鉱山が最も規模が大きい代表的鉱床とされる。最高品位の鉱石は一般に緻密な黒色塊で、微細な赤鉄鉱を主体とする。そうした鉱石にはかつてペンウィス石と呼ばれた非晶質の珪マンガン鉱が網目状に伴われる。晩期の生成物として脈状に紅簾石や石英が生じ、同様の産状でイネス石も記載されている[1-3]。
化学組成は電子顕微鏡と熱重量分析によって導かれ、鉄(Fe)の価数と結晶学的席をメスバウアー分光で確認するなど丁寧な仕事となっている。得られた組成式は当時のパンペリー石の一般式W8X4Y8Z12O56-n(OH)nに基づいて、W=Ca, X=Mn2+, Y=Mn3+, Z=Siが得られた。当時、Y=Mn3+となるパンペリー石族は知られていなかったため、ルートネームを提案することが可能だった。今のところオホーツク石はX=Mn2+でもあるが、将来的にXがMn2+以外の元素で占有されたオホーツク石が見つかると改名されるだろう。パンペリー石族ではXの元素をルートネームの接尾語に置くことが慣習となっている。そのためもしそうした事態が生じると、今のオホーツク石はマンガンオホーツク石(Okhotskite-(Mn2+))となることが予想される。なお、オホーツク石の理想化学組成については2019年に改定があり、今ではCa2Mn2+Mn3+2(Si2O7)(SiO4)(OH)2・H2Oのようになっている[4]。オホーツク石の第二文献は島根大学に移った赤坂の手による。合成実験を通じてオホーツク石の生成条件を明らかにしようと試みたフォローアップ研究となっている[5]。
模式地においてオホーツク石は黒色緻密な赤鉄鉱を切る脈として産出し、その脈中には濃い赤褐色の葉片状結晶がびっちりとつまっている。脈に沿ってうまく割れるとこれぞという標本になるだろう。オホーツク石は模式地のほかにも産出が知られるが、その規模は小さく、薄片で観察できる程度にとどまる。
[1] 第一文献
[2] 番場猛夫 (1967) 国力鉱山の含マンガン鉄鉱床. 北海道金属非金属鉱床総覧, 92-93.
[3] Togari K., Akasaka M., Kawaguchi Y. (1986) Inesite, from the Kokuriki mine, Hokkaido, Japan. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University. Series 4, Geology and mineralogy, 21, 669-677.
[4] Miyawaki R., Hatert F., Pasero M., Mills S.J. (2019) IMA Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) Newsletter 50. New minerals and nomenclature modifications approved in 2019. Mineralogical Magazine, 83, 615-620.
[5] 第二文献
IMA No./year: 1985-052
IMA Status: A(approved)
模式標本:National Reference Collection of the Geological Survey of Canada nos. 65049, 65050, 65051 and 65052
ペトラック鉱 / Petrukite
(Cu,Ag)2(Fe,Zn)(Sn,In)S4
模式地:兵庫県朝来市生野鉱山ほか
第一文献:Kissin S.A., Owens D.R. (1989) The relatives of stannite in the light of new data. The Canadian Mineralogist, 27, 673-688.
第二文献:設定なし

模式地標本
櫻井鉱と同一の標本。やや緑色を帯びた黒灰鋼色部に櫻井鉱とぺトラック鉱が含まれる。黄金色は黄銅鉱
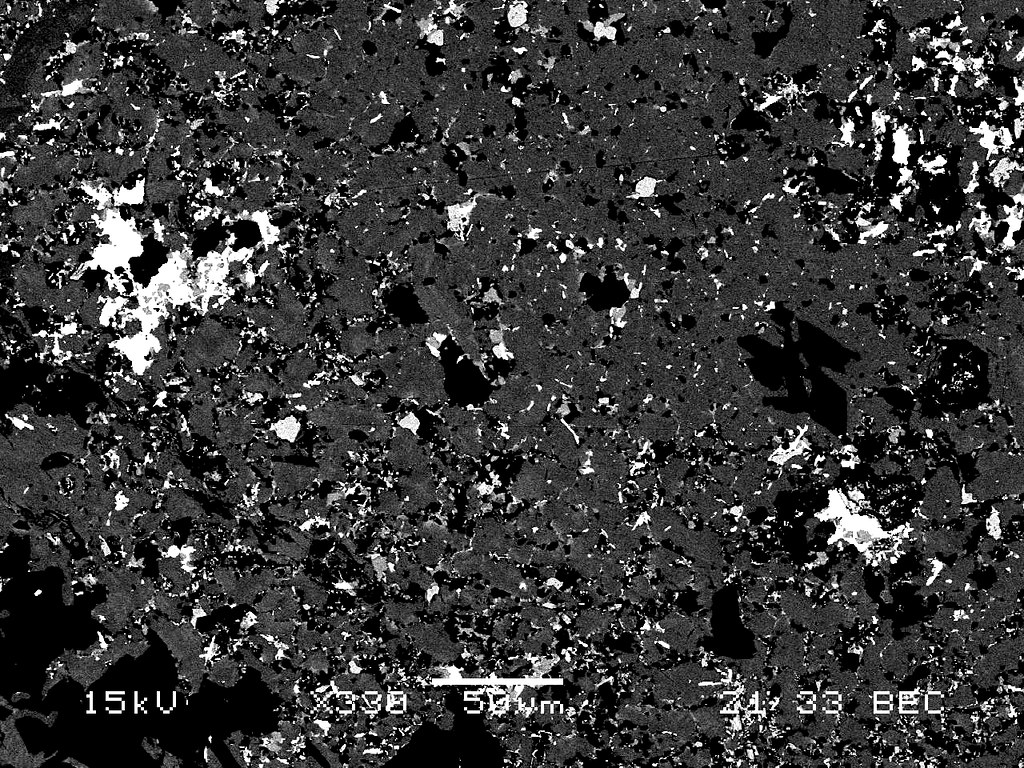
後方散乱電子像
全体的に広がっている暗灰色がぺトラック鉱で、そのなかにシミのように滲んだやや明るい灰色が桜井鉱。全体としてはぺトラック鉱が優勢。
ペトラック鉱はカナダの研究者であるS.A. KissinとD.R. Owensによって記載された新鉱物で、模式地にHerb claim(カナダ)、Mount Pleasant鉱山(カナダ)、生野鉱山が登録されている。学名はカナダ人鉱物学者であるWilliam Petruk(b.1930)への献名として授けられた。PetrukはMount Pleasant鉱山の試料を調べた際に未詳鉱物(後のペトラック鉱)が存在することを指摘していた[1]。
第一文献にはHerb claim→生野鉱山→Mount Pleasant鉱山の順で産状が記され、それぞれ産状は異なる。Herb claimでは花崗岩に貫入した流紋岩に由来する熱水脈中に、方鉛鉱や閃亜鉛鉱を主体とする鉱石中に生じている。Mount Pleasant鉱山はポーフィリー型のタングステン・モリブデン鉱床で花崗岩に付随し、ペトラック鉱はFire Tower North鉱体から見出されている。生野鉱山は中温~高温の熱水鉱脈鉱床で、ペトラック鉱は金香瀬坑の千珠前𨫤で採集された鉱石から見出だされているが、露頭や岩石などの描写は無い。2.5cm径の研磨片中から見出されたとのみ記されているため、分析用の研究試料だけ手に入れてきたように思えるが入手元は論文には記されていなかった。この試料中でペトラック鉱は櫻井鉱と共生した2cmほどの脈で分布する。
ペトラック鉱の化学組成は公式リストでは(Cu,Ag)2(Fe,Zn)(Sn,In)S4のように表現されているが、この理由はよくわからない。カッコ内に二つの元素がカンマで隔てられる場合、このような書き方は、第二成分が必須元素である場合に限る。そうなると例えば銀(Ag)は必須成分のように理解されるが、第一文献では15の分析例のうち銀(Ag)を含むのものは一つだけで、しかもほぼ無視できる程度に少ない。まず間違いなく銀は必須成分ではない。亜鉛(Zn)やインジウム(In)については微妙なところで、それらは必須成分であってもおかしくはない。少なくともCu++Sn4+-Zn2++In3+間の置換関係が見えており、少量の亜鉛とインジウムがペトラック鉱独自の構造を安定化させている可能性がある。そのため(Cu,Zn)2Fe(Sn,In)S4が理想組成としてふさわしいのではないだろうか。これは黄錫鉱(Stannite: Cu2FeSnS4)に非常に近く、それとの区別は亜鉛やインジウムの含有量ならびに構造まで確認したほうが良いだろう。
ペトラック鉱の結晶構造はまだ解明されていないものの、斜方晶系(直方晶系)の対称性と格子定数は報告されている。それは正方晶系の黄錫鉱とは全く異なっているため、粉末X線回折によって区別することができる。対称性と格子定数だけみるとペトラック鉱は硫砒銅鉱(Enargite: Cu3AsS4)に近いがピーク強度が結構異なるため、これとも異なる構造だろう。今のところここに挙げた鉱物は閃亜鉛鉱と基本的には共通の構造をしており、陽イオンの秩序化のタイプが異なった関係になっている。閃亜鉛鉱型構造は近年でも櫻井鉱型[2]やAgmantinite型[3]など新しい秩序タイプが提案されてきている。閃亜鉛鉱型構造の全容を解明するためにはペトラック鉱の構造解析もまた望まれる。
写真は生野鉱山のペトラック鉱の標本となる。櫻井鉱と混合した脈として産出し、含まれるそのほかの鉱物なども記載内容と共通する。櫻井鉱との見分けはできず、電子顕微鏡写真でも櫻井鉱とペトラック鉱のコントラスト差は小さく見分けづらい。ペトラック鉱は日本ではほかに豊羽鉱山からも産出したと聞いたことがある。
[1] Petruk W. (1973) Tin sulphides from the deposit of Brunswick Tin Mines, Limited. The Canadian Mineralogist, 12, 46-54.
[2] 門馬綱一,宮脇律朗,松原聰,重岡昌子,加藤昭,清水正明,長瀬敏郎 (2015) 櫻井鉱の結晶化学的再検討. 日本鉱物科学会2015年年会講演要旨集,R1-09, p.43.
[3] Keutsch F.N., Topa D., Fredrickson R.T., Makovicky E., Paar W.H. (2019) Agmantinite, Ag2MnSnS4, a new mineral with a wurtzite derivative structure from the Uchucchacua polymetallic deposit, Lima Department, Peru. Mineralogical Magazine, 83, 233-238.
IMA No./year: 1986-006(2012s.p.)
IMA Status: Rd(redefined)
模式標本:東京大学総合博物館(UMUT25130, 25136, 25137)
プロトフェロ直閃石 / Proto-ferro-anthophyllite
□Fe2+2Fe2+5Si8O22(OH)2
模式地:岐阜県中津川市蛭川田原
第一文献:Sueno S., Matsuura S., Gibbs G.V., Boisen M.B. (1998) A crystal chemical study of protoanthophyllite: orthoamphiboles with the protoamphibole structure. Physics and Chemistry of Minerals, 25, 366-377.
第二文献:Sueno S, Matsuura S, Bunno M, Kurosawa M (2002) Occurrence and crystal chemical features of protoferro-anthophyllite and protomangano-ferro-anthophyllite from Cheyenne Canyon and Cheyenne Mountain, U.S.A. and Hirukawa-mura, Suisho-yama, and Yokone-yama, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 97, 127-136.
プロトフェロ直閃石は筑波大学の末野重穂と松浦茂らを中心とした研究チームによって記載された新鉱物で、従来の単斜晶系型および斜方晶系型角閃石とは異なる、新たな結晶構造であるプロト型角閃石として発表された。第一文献はプロト型構造の描写を主とした内容であり、1998年に発表されている。プロトフェロ直閃石を発見した功績を持って、翌年の1999年に筆頭著者の末野は櫻井賞(第33号メダル)を受賞した。
プロトフェロ直閃石の第一文献は上述の通り1998年であるが、IMAno.が1986-006となっているように新鉱物申請は1986年に行われている。第一文献には、新種としての承認を受けたものの角閃石の命名規約の改訂作業が進められていたために、当時の新鉱物・鉱物名委員会の委員長によって承認がサスペンド(停止)されたことが記されている。そして11年後の1997年に命名規約の改訂論文が出版され[1]、委員長はそれを受けて記載論文の公表を解禁した。その措置を受けて即座に提出されたのが第一文献であった。このような事情で新鉱物申請と論文発表の時期が大きくずれているが、学会での発表は申請から遅れることなく1986年に行われている[2]。また学名はprotoferro-anthophylliteで発表されたが、2012年の命名規約の再改定によって二つ目のハイフンが追加されてproto-ferro-anthophylliteとなった[3]。
プロトフェロ直閃石は筑波大学地球科学系の大学生だった松浦茂によって見いだされている。蛭川村田原の花崗岩ペグマタイトから採集された鉄かんらん石中に発生するライフン石(laihunite (Fe3+,Fe2+,□)2(SiO4))を調査していたところ、磁鉄鉱の周囲に角閃石が見いだされた。それは組成的にはフェロ直閃石(□Fe2+2Fe2+5Si8O22(OH)2)であったが、単結晶X線回折から従来の直方晶系型構造ではなくプロト型であることが判明した[4]。この時点で角閃石の構造は単斜晶系型および斜方晶系型が一般的であったが、合成実験では実はプロト型が存在することが知られていた[5,6]。すなわち、プロトフェロ直閃石は天然では初めてとなるプロト型角閃石であった。これをきっかけに栃木県横根山や福島県水晶山の角閃石が調査され、やはりプロト型の角閃石が次々と発見される事態となり、一連の研究はプロトフェロ直閃石のマンガン置換体にあたるプロトフェロ末野閃石(当時はプロトマンガノ直閃石の名称)もほぼ同時に見出した。そして、後にマグネシウム置換体のプロト直閃石が日本から記載されるに至り、現時点で「プロト」を冠する角閃石のすべてが日本産の新種となっている。
蛭川村においてプロトフェロ直閃石は磁鉄鉱を伴う鉄かんらん石に密接に関連して生じる。それは第二文献で同時に記載されたアメリカのCheyenne山のものもほぼ同様である。このような産状は鉄かんらん石を伴うペグマタイトであれば珍しくないと思われるが、現状でプロトフェロ直閃石の産地は公式にはこの二か所しか知られていない。しかし、それはプロトフェロ直閃石の産出が少ないのではなく、正しく検出されていない可能性があるだろう。個人的な経験として、透過電子線回折ではプロト型が一意に検出されるのに、同じ試料の粉末X線回折パターンは斜方晶系型だったということがある。つまり、粉末化の過程でプロト型の構造が壊れて、斜方晶系型へ転移したと思われる。これは輝石で観測されることが知られており、おそらく同じ現象が角閃石でも生じるのだろう。共同研究者がいずれ詳細を発表するだろうが、プロトフェロ直閃石の産地はいずれ増えると思われる。
[1] Leake B.E. et al. (1997) Nomenclature of amphiboles: report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. The Canadian Mineralogist 35, 219-246
[2] Sueno S. and Matsuura S (1986) A mineralogical study of the two natural protoamphiboles. 14th International Mineralogical Association Meeting Abstract 14, 241.
[3] Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist, 97, 2031-2048.
[4] 松浦茂, 末野重穂 (1984) Pnmn空間群の鉄直閃石結晶構造について. 日本鉱物学会年会講演要旨集, p128.
[5] Gibbs G.V., Bloss F.D., Shell H.R. (1960) Protoamphibole, a new polytype. American Mineralogist, 45, 974-989.
[6] Gibbs G.V. (1969) Crystal structure of protoamphibole. Mineralogical Society of America, Special Paper, 2, 101-109.
IMA No./year: 1986-007(2012s.p.)
IMA Status: Rd(redefined)
模式標本:東京大学総合博物館(UMUT25130, 25136, 25137)
プロトフェロ末野閃石 / Proto-ferro-suenoite
□Mn2+2Fe2+5Si8O22(OH)2
模式地:栃木県鹿沼市日瓢鉱山
第一文献:Sueno S., Matsuura S., Gibbs G.V., Boisen M.B. (1998) A crystal chemical study of protoanthophyllite: orthoamphiboles with the protoamphibole structure. Physics and Chemistry of Minerals, 25, 366-377
第二文献:Sueno S., Matsuura S., Bunno M., Kurosawa M. (2002) Occurrence and crystal chemical features of protoferro-anthophyllite and protomangano-ferro-anthophyllite from Cheyenne Canyon and Cheyenne Mountain, U.S.A. and Hirukawa-mura, Suisho-yama, and Yokone-yama, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 97, 127-136



模式地標本
プロトフェロ末野閃石は一つ前のプロトフェロ直閃石と同時に発表された新鉱物であり、承認から論文公表までの経緯も共通している。しかし、名称については異なった経緯をたどった。プロトフェロ末野閃石は、1986年の申請時はプロトマンガネーズ直閃石(protomanganese-anthophyllite)という名称であり、そのまま承認された。しかし、命名規約の改定中だったため承認がサスペンド(停止)され、その間に命名ルールが変更されて、1998年と2002年の記載論文においてはプロトマンガノフェロ直閃石(protomangano-ferro-anthophyllite)という名称で発表された[1,2]。角閃石命名規約はその後も小規模な改訂が行われ、2003年にはハイフンをひとつ追加してproto-mangano-ferro-anthophylliteに改名。そして、2012年になると命名規約の大改訂が行われ、こんどはいったん名無しにされてしまった[3]。このとき本種についてはproto-ferro-rootname3という仮の名前が与えられている。
角閃石の組成を簡単に書くとAB2C5T8O22W2と書くことができ、本種の化学組成は□Mn2+2Fe2+5Si8O22(OH)2であり、A = □(空隙)、B = Mn2+、C = Fe2+、T = Si、W = OHということになる。そして、2012年の命名規約はAとC原子だけを名称の接頭語として表現することを定め、B = Mn2+についてマンガノ(mangano)とするというこれまでの命名ルール[4]を廃止した。すなわちB = Mn2+となる本種は新しいルールでは名前が付けられないことになる。そこでまずのproto-ferro-rootname3という仮の名前が与えられ、命名規約を作成していた角閃石小委員会はrootname3の名称について模索することになる。そして、角閃石小委員会は末野閃石(suenoite)とすることを提案した。この時点で末野はすでに亡くなっているため、論文のそのほかの著者らに案が提示され、了承された。そして、本種について、その名称がプロトフェロ末野閃石(proto-ferro-suenoite)となることで最終決着となった[5]。
プロトフェロ末野閃石の名称は申請時とは異なっているとはいえ、これは申請者自らの名前が付けられた鉱物ということになる。新鉱物の大原則として、申請者自らの名前が鉱物名になることはない。しかし、こればっかりは事情が異なる。これは申請者が自ら望んだわけではなく、角閃石小委員会から提案されたのである。結果的に稀有な例となった。
プロトフェロ末野閃石の模式地は栃木県日瓢鉱山であり、そこではバラ輝石と共存することが多く、石英とプロトフェロ末野閃石だけの塊もある。プロトフェロ末野閃石の結晶は乳白色から淡黄色の繊維状で、密に集合すると茶色味が強く出る。プロト型構造の解説はほかのプロト型角閃石で行うとして、一般に角閃石はいくつかの構造が混じっていることがしばしばある。しかし、調べた範囲で栃木県日瓢鉱山ではことごとくプロト型の構造ばかりで、他の構造タイプが混じっていることはなかった。記載論文では福島県水晶山からの産出も報告されている。
[1] 第一文献
[2] 第二文献
[3] Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist, 97, 2031-2048.
[4] Leake B.E. et al. (1997) Nomenclature of amphiboles: report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. The Canadian Mineralogist 35, 219-246
[5] Williams P.A., Hatert F., Pasero M., Mills S.J. (2013) IMA Commission on new minerals, nomenclature and classification (CNMNC) Newsletter 16. New minerals and nomenclature modifications approved in 2013. Mineralogical Magazine 77, 2695-2709.
IMA No./year: 1987-045
IMA Status: A(approved)
模式標本:産業技術総合研究所地質標本館(GSJ M17112)
和田石 / Wadalite
Ca6Al6Si2O16Cl3(承認時)
Ca12Al10Si4O32Cl6(Mayenite超族として)
模式地:福島県郡山市逢瀬町多田野
第一文献:Tsukimura K., Kanazawa Y., Aoki M., Bunno M. (1993) Structure of wadalite Ca6Al5Si2O16Cl3. Acta Crystallographica, C49, 205-207
第二文献:Banno Y, Bunno M, Tsukimura K (2018) A reinvestigation of holotype wadalite from Tadano, Fukushima Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 82, 1023-1031.
和田石は地質調査所(当時)の月村勝宏らによって記載され、その名称は和田維四郎(1856-1920)にちなんで名づけられた。日本の近代地質学の基礎を築いた地質学者であるHeinrich Edumund Naumann(1854-1927)のもとで学んだ最初の日本人が和田であり、明治10年の東京大学創立にあたっては、和田はNaumann教授の助手として金石学を担当した。その後、和田はNaumannと共に地質調査所の設立を建議し、地質調査所が設立した際には和田が初代所長を務め、東京大学でも教授職を兼任している。明治35年には大学や官界を去っているが、むしろそこから活躍が形として残るようになり、明治37年には「日本鉱物誌」を著わした。これは後年に様々発行された「~県鉱物誌」の模範となったと言える。和田は鉱物蒐集にも熱心で、集めた鉱物は膨大かつ高品質のものが多く、このいわゆる「和田コレクション」は三菱の岩崎家が購入した。現在、和田コレクションの大半は三菱マテリアル総合研究所に所蔵されている。このように和田維四郎は日本の鉱物学の創始者として知られていたが、なぜかその名は鉱物名に採用されていなかった。和田石に関して二つの論文の著者になっている豊遙秋はそのことに気づき、多田野からの新鉱物に和田の名前を残すことを提案した。
IMA no.からは和田石は1987年に申請されたことが伺えるが、第二文献によると承認は1989年とのことで一年以上の開きがある。このくらいのスピード感の審査だったのか、何か事情があったのか、文献上からは読み取れない。また、和田石の第一文献は1993年に出版された月村らの論文だが、これは結晶構造に特化しており、世界第二産地であるLaNegra鉱山(メキシコ)の情報があるものの、いわゆる記載論文としての内容となっていない。そのため模式地の和田石については実は記載がないという状態がずっと続いており、2018年になってようやく記載が行われた。それが第二文献であり、その記載がない期間に和田石はMayenite超族に分類された[1]。
Mayenite超族は2013年に成立し、論文は2015年に発表されている[1]。Mayenite超族の一般式はX12T14O32-x(OH)3x[W6-3x]と書くことができ、シリコン(Si)を主成分としないMayenite族と、シリコンを主成分とする和田石族に分けられる。和田石族については和田石(wadalite: Ca12Al10Si4O32Cl6)とその三価鉄(Fe3+)置換体にあたるEltyubyuite(Ca12Fe3+10Si4O32Cl6)が所属するのみとなっている。模式地である多田野からの和田石は三価鉄を含むものの、Eltyubyuiteにはかすりもしない程度の量に留まる。また、多田野の和田石には特定の結晶方位にのみ現れるセクターゾーニングがある[2]。そしてセクターゾーニングがあると言うことは、和田石の結晶は非平衡な状態で急速に成長したことを示唆している。
和田石は初生鉱物ではなく、ゲーレン石(Gehlenite: Ca2Al(SiAl)O7)が和田石よりも先にあって、それを消費するように和田石が成長したと考えられている。そして和田石もまた後期のスカルン活動で変質を受けているようで、結晶の外側はしばしば加藤ざくろ石に置換されている。外形をほぼたもったまま完全に加藤ざくろ石に変化している産状もある。例えば一番下の写真で、薄ピンク色をしめす結晶は加藤ざくろ石に置き換わっている。
模式地である郡山市多田野には安山岩が分布しており、しばしばスカルン質の捕獲岩を伴う。その捕獲岩は分帯しており、中心部に無水のスカルン鉱物を、周辺部に含水のスカルン鉱物を胚胎する。和田石は中心部と周辺部の境界付近の絶妙な領域で主に産出し、黒~黒緑~暗灰色で半透明な四面体結晶となる。郡山市在住の愛石家である橋本悦雄が気づき、地質調査所の豊遙秋へ相談したことが発見のきっかけだと伝わる。
[1] Galuskin E.V., Gfeller F., Galuskina I.O., Armbruster T., Bailau R., Sharygin V.V. (2015) Mayenite supergroup, part I: recommended nomenclature. European Journal of Mineralogy 27, 99-111
[2] 第二文献
IMA No./year: 1989-007
IMA Status: A(approved)
模式標本:地質調査所北海道支所地質標本室(当時)
豊羽鉱 / Toyohaite
Ag2FeSn3S8(承認時)
Ag+(Fe2+0.5Sn4+1.5)S4(2019年からスピネル超族として)
模式地:北海道札幌市豊羽鉱山
第一文献:Yajima J., Ohta E., Kanazawa Y. (1991) Toyohaite, Ag2FeSn3S8, a new mineral, Mineralogical Journal 15, 222-232.
第二文献:設定なし
「未入手」
豊羽鉱は地質調査所(当時)の研究チームが発見した新鉱物で、北海道支所の矢島淳吉が筆頭著者を務めた。学名は発見地である豊羽鉱山にちなむ。豊羽鉱山は明治初期に定山渓付近で鉱脈が記録されたことが始まりと考えられている[1]。その後、明治後半から開発が始まり、大正期から稼働し、幾度かの休止を経て、平成18年(2006年)3月で操業を最終的に休止した。休止の理由は名目的には鉱量枯渇であるが、鉱脈自体は地下にまだ続いていることが確認されているので、実態は技術的・採算的に採掘可能な鉱量の枯渇であろう。また、豊羽鉱山は基本的には亜鉛・鉛の鉱山ではあったが、副産物のインジウム(In)が豊富で、インジウムについて一時は世界第一の生産量を誇った。
豊羽鉱山の鉱床帯は4つに大別され、胆振鉱床帯、長門鉱床帯、本山鉱床帯、通洞鉱床帯がある[2]。それらの鉱床帯に主脈と支脈があり、それぞれ「〇〇𨫤」と呼ばれる。鉱石の特徴としては大まかに3種類で、①方鉛鉱・閃亜鉛鉱・硫化鉄鉱を主体とする鉱脈、②黄鉄鉱・黄銅鉱を主体とする鉱脈、③菱マンガン鉱・方解石を主体とする鉱脈があげられる。それらは前期・後期の生成時期が大まかにわけられ、①が前期、③が後期となっている。②はどちらの場合もあるがどちらかというと後期が多い。このように豊羽鉱山は一概には言えない多様さがあるので、豊羽鉱山産というだけの鉱石に豊羽鉱が含まれている確率は非常に低く、せめて「〇〇𨫤」くらいの情報がないと標本としての意味合いも乏しい。
豊羽鉱が発見されたのは本山鉱床帯の主脈である但馬𨫤の支脈(播磨𨫤)のそのまた支脈の空知𨫤である。空知𨫤の鉱石は方鉛鉱・閃亜鉛鉱・硫化鉄鉱が主体だが、成分としてみるとやたら銀に富む特徴が知られる[1]。鉱石1tあたりに約1kgもの銀が含まれており、これは主脈である但馬𨫤や播磨𨫤の5-6倍に相当するけた外れの量といえる。そして銀(Ag)を主成分とする鉱物であるカンフィールド鉱(Canfieldite: Ag8SnS6)、黄錫銀鉱(Hocartite: Ag2FeSnS4)、ピルキスタス鉱(Pirquitasite: Ag2ZnSnS4)が豊羽鉱に先立って発見されている。そして1987年には銀に富む赤錫鉱の産出が報告され[3]、それがのちに豊羽鉱となった。
豊羽鉱は赤錫鉱(Rhodostannite)の銀置換体に相当する新鉱物と発表されている。当時、赤錫鉱はCu2FeSn3S8の組成で表される鉱物であり、豊羽鉱はAg2FeSn3S8であった。一方で、この化学組成は後に改訂されることになる。豊羽鉱の記載に先立って、赤錫鉱がスピネル構造を持つことはがすでに知られており、1979年には赤錫鉱の化学組成をCu(Fe0.5Sn1.5)S4のように表記するべきだという主張があった[4]。この化学組成になるにはFeが2価、Snが4価であるべきで、それもまた後年に実験的に確認された[5]。そして、2019年にスピネル超族の命名規約が成立した際に、赤錫鉱と共に豊羽鉱の化学組成も改訂され、豊羽鉱の化学組成はAg+(Fe2+0.5Sn4+1.5)S4となった [6]。
結果的に、豊羽鉱は日本で最初のスピネル超族の新鉱物という立場が定まったので、スピネル超族の分類を少し示す。スピネル超族はABX4の化学組成のスピネル構造を有する鉱物群であり、「X」の種類で今のところ3つの族に分けられる:酸化スピネル族(Oxyspinel group: ABO4)、硫化スピネル族(Tiospinel group:ABS4)、セレン化スピネル族(Selenospinel group:ABSe4)。そして、硫化スピネル族の中に「B」の価数によって分けられる亜族がある:カーロール鉱亜族(Carrollite subgroup: AB3.5+S4)とリンネ鉱亜族(Linnaeite subgroup: AB3+S4)。豊羽鉱はカーロール鉱亜族に分類され、同じカテゴリーに最近になって蝦夷地鉱(Ezochiite: Cu+(Rh3+Pt4+)S4)が新たに加わった[7]。どちらも北海道から発見された新鉱物である。
豊羽鉱は黄錫鉱(Stannite: Cu2FeSnS4)の分解生成物だと考えられており、鉱石中に0.2mm以下の不定形な微細粒子として産出し、ヘルツェンブルグ鉱(Herzenbergite: SnS)やベルント鉱(Berndtite: SnS2)を非常に密接に伴うことが第一文献に記されている。採集地点は細かく述べられており、それぞれ5つのサブステージがあり、豊羽鉱が生成されるサブステージは限定的である。つまり、豊羽鉱が発見された場所は非常に限られており、空知𨫤の鉱石でも採掘レベルやサブステージがわずかでも外れると豊羽鉱は出てこないことが推察される。そしてそれは実際に体験した。これまでに空知𨫤の鉱石をさんざん調べたが、豊羽鉱がでてくる採掘レベルやサブステージでなかったためか、豊羽鉱はついに見つからなかった。ヘルツェンブルグ鉱を伴う赤錫鉱まではみつかったのであと一歩のところであろうが、そもそも空知𨫤の鉱石なんて手に入れる機会がほとんどないため、今さら豊羽鉱を見つけることは非常に難しく、未入手のままとなっている。
[1] 宮島健久, 秤信男, 喜多正弘(1971)豊羽鉱山の地質構造と裂罅生成機構に関する最近の考え方. 鉱山地質, 21, 22-35.
[2] 沢俊明(1966)豊羽鉱山の同鉛亜鉛鉱床. 北海道金属非金属鉱床総覧, 82-84.
[3] 太田英順, 矢島淳吉, 金沢康夫(1987)豊羽鉱床産鉱石鉱物の化学組成. 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, P68.
[4] Jumas J.C., Philippot E., Maurin M. (1979) Structure du rhodostannite synthétique. Acta Crystallographica, B35, 2195-2197.
[5] Garg G., Bobev S., Roy A., Ghose J., Das D., Ganguli A.K. (2001) Single crystal structure and Mössbauer studies of a new cation-deficient thiospinel: Cu5.47Fe2.9Sn13.1S32. Materials Research Bulletin, 36, 2429–2435.
[6] Bosi F., Biagioni C., Pasero M. (2019) Nomenclature and classification of the spinel supergroup. European Journal of Mineralogy, 31, 183-192.
[7] [7] Nishio-Hamane D. and Saito K. (2023) Ezochiite, IMA 2022-101. CNMNC Newsletter 71; Mineralogical Magazine, 87, https://doi.org/10.1180/mgm.2023.11
IIMA No./year: 1990-005(2014 s.p.)
IMA Status: Rd (redefined)
模式標本:国立科学博物館(Handbook of Mineralogyから引用)
単斜トベルモリ石 / Clinotobermorite
Ca5Si6(O,OH)18・5H2O(承認時)
Ca4Si6O17(H2O)2·(Ca·3H2O)(理想化学式、2014年~)
模式地:岡山県高梁市布賀道路際露頭
第一文献: Henmi C., Kusachi I., (1992) Clinotobermorite, Ca5Si6(O,OH)18·5H2O, a new mineral from Fuka, Okayama Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 56, 353-358.
第二文献: Merlino S., Bonaccorsi E., Armbruster T. (1999) Tobermorites: Their real structure and order-disorder (OD) character. American Mineralogist, 84, 1613-1621
単斜トベルモリ石は岡山県布賀から見いだされた新鉱物である。斜方(直方)晶系であるトベルモリ石に対して、単斜晶系のトベルモリ石ということで新鉱物に承認された。その当時は晶系の違いは種を分ける基準として機能していた。しかし、今では晶系(=対称性)が異なるだけでは新種として認められないので、対称性が異なるだけだったら命名規約の整備のタイミングで抹消される。ただし、トベルモリ石と単斜トベルモリ石は結晶構造の中身も異なることが明らかとなっており、命名規約が整備された現在でも、単斜トベルモリ石は独立種の立場を保っている。また、単斜トベルモリ石の学名はそのまま「単斜晶系のトベルモリ石」という意味である。しかし、三斜晶系の単斜トベルモリ石も存在することがすでに判明しており[1]、今となってはその学名はもう実態とは合わないかもしれない。でも、変えることはできない。
当時、トベルモリ石族には5種類の鉱物が知られており、それぞれに鉱物名と野外名「〇Åトベルモリ石」が当てられていた。その名称の関係は、トベルモリ石(Tobermorite)=「11Åトベルモリ石」、プロンビエル石(Plombièrite)=「14Åトベルモリ石」、タカラン石(Tacharanite)=「12.6Åトベルモリ石」、大江石(Oyelite)=「10Åトベルモリ石」である。論文によって鉱物名・野外名のどちらかしか出てこなかったり、少数点以下の値出てきたりそうでなかったりと、いろいろややこしい。そして、岡山県布賀ではトベルモリ石、プロンビエル石、大江石の産出が確認されていた。そのうち、トベルモリ石について異常が検出された。トベルモリ石は11.3Åに顕著なX線回折を示す斜方(直方)晶系の鉱物とされていたが、布賀のトベルモリ石には斜方(直方)晶系では指数を付けることができない回折が混じっていることが判明したのだった。それは「単斜晶系トベルモリ石」として1989年に論文で記載され[2]、1990年に新鉱物申請が行われた。
布賀において、トベルモリ石族鉱物は出てくる場所がだいたい決まっており、単斜トベルモリ石は道路際露頭と呼ばれる個所に産出する。中央の石灰岩を挟んだ東部には汚染岩の周囲にスカルンが発達しており、汚染岩およびスカルンが後期生成の鉱物によって脈状に様々貫かれた産状を示す。単斜トベルモリ石はその脈状鉱物の一つとして産出し、汚染岩とざくろ石化したゲーレン石との境界付近の脈中に産出する。脈中にはトベルモリ石も伴われるが、トベルモリ石が最大でも0.5mm以下の針状結晶でしかないのに対し、単斜トベルモリ石は最大で3mmの板状結晶であった。ただし、このような結晶には双晶やc軸方向の積層欠陥が含まれており、単斜晶系での指数付けまでは成功したものの、構造の決定には至らなかった[第一文献]。
化学組成についても、単斜トベルモリ石はトベルモリ石と異なる点が指摘されている。トベルモリ石はアルミニウム(Al)を含みがちだが、単斜トベルモリ石にはアルミニウムがあまり含まれない。またカルシウム(Ca)内容についても、単斜トベルモリ石とトベルモリ石ではやや異なることが示されている。これは両者が単に対称性の異なる関係ではなく、結晶構造まで異なることを示唆しているが、それが明らかになったのは1999年であった[第二文献]。そして2000年により具体的な単斜トベルモリ石の結晶構造が報告された[1]。
トベルモリ石族の結晶構造は、7配位のCa中心多面体のシートとそれに連結するケイ酸塩鎖からなる複合モジュールが基本となっている。そして、トベルモリ石と単斜トベルモリ石では、その複合モジュールの種類や結合の傾斜が異なっていることが示された。単斜トベルモリ石にはポリタイプが二つ想定され、空間群Ccとなる単斜晶系の単斜トベルモリ石と、空間群C1となる三斜晶系の単斜トベルモリ石が導かれている。それぞれその多形を考慮すると、単斜晶系の単斜トベルモリ石はClinotobermorite-2Mとして、三斜晶系の単斜トベルモリ石はClinotobermolite-1Aとして記述されることになる。実際の結晶にはこれらの多形が入り混じり、さらにはふつうのトベルモリ石、さらにはそのポリタイプも混じってくるので、X線回折パターンや電子線回折像はかなり複雑なものになる。よほどどれかが支配的にならないと、その同定はほとんどお手上げだろう。また、分析面でも注意を要する。これだけ複数相が入り混じると、分析値の解析も容易ではない。命名規約では4面体の数、Si + Al = 6 apfuで分析値を規格化することを提案している[3]。そのうえでカルシウムが5 apfuを下回るようだと、ケノ(Keo-)型の鉱物種名が与えらえる。例えばケノトベルモリ石(Kenotobermorite: Ca4Si6O15(OH)2(H2O)2·3H2O)は鉱物種としてすでに確立されている。現時点でケノ単斜トベルモリ石となる鉱物はいまだ確立されていないが、イタリア産の単斜トベルモリ石がケノ型の候補として考えられている[4]。
写真は布賀の道路際露頭から採集された単斜トベルモリ石となる。記載論文のように板状の単結晶ではなく針状結晶の群晶ではあるが、粉末X線回折で単斜トベルモリ石が含まれていることが確認された。第一文献によると、単斜トベルモリ石はトベルモリ石よりも後期の低温環境で生成したと考えられている。
[1] Merlino S., Bonaccorsi E., Armbruster T. (2000) The real structure of clinotobermorite and tobermorite 9Å: OD character, polytypes, and structural relationships. European Journal of Mineralogy, 12, 411-429.
[2] 逸見千代子, 草地功 (1989) 岡山県備中町布賀産単斜晶系トバモライト. 岩鉱, 84, 374-379.
[3] Biagioni C., Merlino S., Bonaccorsi E. (2015) The tobermorite supergroup: a new nomenclature. Mineralogical Magazine, 79, 485-495.
[4] Biagioni, C. (2011) I silicati idrati di calcio: assetto strutturale e comportamento termico. PhD thesis, University of Pisa, Italy.
IMA No./year: 1991-025
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM-M26138)、東京大学総合博物館、ロンドン自然史博物館(E.1400, BM 1992, 238)
渡辺鉱 / Watanabeite
Cu4(As,Sb)2S5
模式地: 北海道札幌市手稲区手稲鉱山
第一文献: Shimizu M., Kato A., Matsubara S., Criddle A.J., Stanley C.J. (1993) Watanabeite, Cu4(As,Sb)2S5, a new mineral from the Teine mine, Sapporo, Hokkaido, Japan, Mineralogical Magazine 57, 643-649.
第二文献: 設定なし

上の標本の一部拡大。基本は亜鉛四面銅鉱だが、石英との接触部に鉄四面銅鉱が広がる。


この標本では亜鉛、鉄のどちらの四面銅鉱にも渡辺鉱は含まれていた。
渡辺鉱は東京大学総合博物館の清水正明を筆頭とした研究チームによって記載された新鉱物で、北海道手稲鉱山から発見された。鉱物名は鉱床学者として著名な渡辺武男(1907-1986)にちなむ。第一文献によると、渡辺は手稲鉱山産の自然テルルとシルバニア鉱を最初に報告したとされる。清水は渡辺鉱を発見した功績をもって櫻井賞(第31号メダル)を受賞した。
渡辺武男は東京帝国大学で鉱床学を学び、北海道帝国大学で助手から教授まで務めた。その後は東京帝国大学教授、名古屋大学教授、秋田大学学長を歴任し、学士院会員にも選ばれた。新鉱物の研究としては小藤石(Kotoite)の発見から始まり、遂安石(Suanite)、吉村石(Yoshimuraite)、神保石(Jimboite)、原田石(Haradaite)を筆頭著者として記載し、木下雲母(Kinoshitalite)の発見にも携わっている。そのほか、渡辺が発表した田野畑鉱山産のBa-Vケイ酸塩新鉱物は[1]、後に鈴木石(Suzukiite)と命名された。
渡辺鉱が発見されたきっかけは、国立科学博物館が海外の研究者から四面銅鉱の標本を提供してほしいという要請をうけて、渡す前に粉末X線回折実験でチェックしたことだった[2]。その標本は藤山家徳氏が採集したもので、陶器質の石英塊に伴われる鋼灰色の四面銅鉱に見えていた。しかし、その標本から得られたX線回折パターンには立方晶系の四面銅鉱ではあらわれないはずのピークが現れており、そのことに国立科学博物館の研究者が気づき、清水に研究の主導が依頼された。その後のことであろうか、第一文献には「最近、滝ノ沢鉱床のズリから渡辺鉱を含む二つの試料が採集された(意訳)」とも記されている。
渡辺鉱の分析はWDSで行われ、精度よくCu4(As,Sb)2S5の化学組成が導かれた。渡辺鉱の結晶構造は第一文献の時点で明らかになっておらず、格子の型も不明ながらも斜方(直方)晶系において指数が割り振られた。その後に渡辺鉱は海外のいくつかの地域で報告されるようになるものの、結晶構造の検討はまったく進んでいない[4-8]。しかし、2024年になってようやく渡辺鉱の結晶構造が解明された[3]。
四面銅鉱と渡辺鉱の主要なX線回折ピークはよく似ていることが暗示するように、その内部構造もよく似ている。どちらもCu3As4Sクラスターが含まれており、四面銅鉱ではそれが三角格子を組み、渡辺鉱では正方格子を組む。もっと大きく見ると、どちらもCu14As4S13の構造モジュールを共通としており、渡辺鉱はそれにCu2As4S7スラブが追加された構造となっている。その関係は1:1であり、式で示すと、Cu14As4S13+Cu2As4S7 = Cu16As8S20 (Z = 2) となって、Z = 8で記述すると、Cu4As2S5という渡辺鉱の化学組成ができあがる。渡辺鉱は一見して簡単そうな化学組成に落ち着くが、結晶の内部は結構ややこしかった。
渡辺鉱は今のところ国内では手稲鉱山のみ、海外ではアルゼンチン、ギリシャ(3か所)、ロシア、中国から産出が報告されている。渡辺鉱は構造を確認することが困難なので、化学組成の比較が重要になるが、四面銅鉱と似ているためそれもまた慎重に行いたい。効果的な見極めとしてCu/As比が注目される。渡辺鉱はCu/As比が2程度であることに対し、四面銅鉱は3である。どちらも2.5までは達しない。その視点でこれまで報告された渡辺鉱を読み解くと、アルゼンチン、ギリシャ、ロシアからの渡辺鉱は四面銅鉱の誤認であることが示された[3]。なお、第一文献や以降の論文でもたびたび指摘のある渡辺鉱のアンチモン(Sb)置換体についても、それはさらなる新鉱物ではなく、ファマチ鉱(Famatinite: Cu3SbS4)だと予想されている[3]。
渡辺鉱は手稲鉱山滝ノ沢鉱床の四面銅鉱からも見つかったと第一文献に記載がある。しかし、その標本の特徴は詳しく述べられておらず、ふつうの四面銅鉱に見える10-20個のうちに一個くらいは渡辺鉱が入っているという口伝が知られていた。それに期待して、手稲鉱山産のいわゆる四面銅鉱はこれまでかなりたくさん調べてきた。しかし、もうめっちゃくちゃ。ここの四面銅鉱は調べるものごとに組成的な特徴が異なっている。ふつうの鉄・亜鉛・安・砒四面銅鉱をはじめ、のちに新鉱物となるマンガン四面銅鉱、マンガン砒四面銅鉱、銅砒四面銅鉱なども見つかった。しかし、渡辺鉱だけがどうしても見つからず、口伝はやっぱり当てにならないことを痛感した。前にも同じようなことあったな。ただし、児玉亨氏から来た写真の標本だけには渡辺鉱が含まれていた。それは亜鉛四面銅鉱が主体で、石英晶洞周りは鉄四面銅鉱になっている標本で、そのどちらの部分にも渡辺鉱が含まれている。反射顕微鏡での鑑定は熟練の観察眼が必要だが、電子顕微鏡下においては組成コントラストでその存在がはっきりと見て取れる。
[1] 渡辺武男, 由井俊三, 加藤昭 (1973) 岩手県田野畑鉱山産Ba-V珪酸塩鉱物. 三鉱学会連合学術講演要旨集, p24.
[2] 松原聰 (2006) 「新鉱物発見物語」 棚の中に眠っていた新鉱物-渡辺鉱、岩波書店.
[3] Biagioni C., Voudouris P., Moëlo Y., Sejkora J, Dolníček Z., Musetti S., Mauro D. (in press) Crystal structure of Pb-bearing watanabeite from Pefka, Greece. Mineralogical Magazine.
[4] Paar W.H., Topa D., Sureda R.J. (2002) Watanabeíta, Cu4(As,Bi,Sb)2S5, con una nueva fase mineral “Cu3AsS3” en Cerro Atajo, provincia de Catamarca, Argentina. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) Mineralogía y Metalogenia, Actas, 2002, 329–332.
[5] Voudouris P., Papavasiliou C., Melfos V. (2005) Silver mineralogy of St. Philippos deposit (NE Greece) and its relationship to a Te-bearing porphyry-Cu-Mo mineralization. Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 43, 155–160.
[6] Voudouris P.C., Melfos V., Spry P.G., Moritz R., Papavassiliou C., Falalakis G. (2011) Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill high-sulfidation epithermal Ag-Ag-Te-Se deposit, Petrota Graben, NE Greece. Mineralogy and Petrology, 103, 79–100.
[7] Sidorov E.G., Borovikov A.A., Tolstykh N.D., Bukhanova D.S., Palyanova G.A., Chubarov V.M. (2020) Gold mineralization at the Maletoyvayam deposit (Koryak Highland, Russia) and physicochemical conditions of its formation. Minerals, 10, 1093.
[8] Zheng S.J., Zhong H., Bai Z.J, Zhang Z.K., Wu C.Q. (2021) High-sulfidation veins in the Jiama porphyry system, South Tibet. Mineralium Deposita, 56, 205–214.
IMA No./year: 1992-015
IMA Status: A (approved)
模式標本:北海道大学総合博物館
三笠石 / Mikasaite
Fe3+2(SO4)3
模式地: 北海道三笠市幾春別奔別川東岸
第一文献: Miura H., Niida K., Hirama T. (1994) Mikasaite, (Fe3+,Al)2(SO4)3, a new ferric sulphate mineral from Mikasa city, Hokkaido, Japan. Mineralogical Magazine, 58, 649-653.
第二文献: Christidis P.C., Rentzeperis P.J. (1976) The crystal structure of rhombohedral Fe2(SO4)3. Zeitschrift für Kristallographie, 144, 341-352.
三笠石は数ある日本産新鉱物の中で唯一の昇華鉱物であり、北海道大学の三浦裕行を筆頭とする研究チームによって記載された。三浦は三笠石の合成も研究し[1]、それらの功績により櫻井賞(第32号メダル)を受賞している。
北海道三笠市幾春別は白亜紀のアンモナイトが多く産出することで有名だが、幾春別を流れる奔別川の東岸には高温のガスが噴出していることも知られる。これは地下の石炭が自然発火して生じた高温の噴気孔であり、その噴気に着目した三笠市職員の松田昇と、三笠市立博物館の小林和男および長谷川浩二が、噴気孔のまわりに生じていた鉱物を採集したことから物語が始まった。
その鉱物は夕張中学校の小林信男を介して、北海道大学の新井田清信に届けられた。しかし、新井田の専門は岩石であり、鉱物の同定は、新井田と同じ学科の、いわゆる鉱物グループに所属する三浦裕行と教養部の平間正男によって検討が進められた。そして、X線回折実験によってこの未詳鉱物が合成実験[2]で得られているFe3+2(SO4)3であることが判明した。しかし、その想定で進められた組成分析はうまくいかず、成分の合計が想定通りなら100wt%になるところが、76wt%程度にとどまるものであった。その一方で23wt%ものH2Oが検出され、X線回折実験との矛盾が生じている[3]。
のちに判明したことによると、これはFe3+2(SO4)3自体は無水であるのに、潮解性を有する物質であることに起因する。試料が採集されてから、三浦らが調べ始めるまで何か月も空気中にさらされていたために吸水していた。そして、こういうケースだと鉱物は結晶構造を失う、もしくは変えてしまうことが多いが、この物質は水が多少加わったところで結晶構造を保つという性質があり、そのためにX線回折実験ではよい結果が出たのに、分析では想定外の過剰のH2Oが検出されるという結果につながった。それでも、こういった因果関係が解明されたことで新鉱物の申請が可能となった。こうして新鉱物は発見地から三笠石(Mikasaite)と名付けられ、承認されたのだった。
三笠石は高温の噴気によって生じる鉱物であり、必要な温度は300℃以上だと見積もられた[3]。しかし、いまでは温度が下がっている可能性が指摘されている。2009年9月に行われた調査では三笠石は見当たらず、かわりにブサンゴー石(Boussingaultite: (NH4)2Mg(SO4)2·6H2O)。ゴドヴィコフ石(Godovikovite: (NH4)Al(SO4)2)、エフレモフ石(Efremovite: (NH4)2Mg2(SO4)3)、ツェルミッヒ石(Tschermigite: (NH4)Al(SO4)2·12H2O)といった鉱物が見いだされた。これらはアンモニア硫酸塩鉱物であり、アンモニアが分解されない200-250℃くらいで生じたと予測されている[4]。
三笠石は、既知のミロセビッチ石(Millosevichite: Al2(SO4)3の三価鉄(Fe3+)置換体に相当する新鉱物である。上で紹介したように潮解性があるため、ほおっておけば溶けてなくなる。そのため、デシケータでの保管が好ましい。写真の標本は、私が北海道大学にいたときに著者よりいただいたものである。
[1] Miura H., Suzaki H., Kikuchi T. (1994) Synthesis and physical properties of system Fe2(SO4)3-Al2(SO4)3. Mineralogical Jpournal, 17, 42-45.
[2] 第二文献
[3] 第一文献
[4] Shimobayashi N., Ohnishi M., Miura H, (2011) Ammonium sulfate minerals from Mikasa, Hokkaido, Japan: boussingaultite, godovikovite, efremovite and tschermigite. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 106, 158-163.
IMA No./year: 1992-017
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館
森本ざくろ石 / Morimotoite
Ca3(TiFe2+)(SiO4)3
模式地:岡山県高梁市備中町布賀北露頭
第一文献: Henmi C., Kusachi I., Henmi K. (1995) Morimotoite, Ca3TiFe2+Si3O12, a new titanian garnet from Fuka, Okayama Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 59, 115-120.
第二文献: Antao S.M. (2014) Schorlomite and morimotoite: what’s in a name?. Powder diffraction, 29, 346-351.
森本ざくろ石はざくろ石超族の新鉱物で、鉱物学者、森本信男(1925–2010)にちなんで命名された。森本はX線結晶学を駆使し、造岩鉱物に離溶や変調などの高次の構造があることを明らかにするなど、昭和を代表する鉱物学者の一人であった。森本が発見した日本産新鉱物の阿仁鉱もそうした一連の研究の中から見いだされている。森本は、大阪大学、京都大学、大阪産業大学で教授職を歴任し、大阪大学と京都大学からは名誉教授を授けられている。
森本ざくろ石は布賀のいわゆる北露頭を模式地とする。そこでは石英モンゾニ岩と石灰岩との反応によってさまざまなスカルン鉱物が生じている。森本ざくろ石もそうしたスカルン鉱物の一つで、チタン(Ti)と鉄(Fe)を主成分に持つという特徴がある。これはショールざくろ石も同様であり、森本ざくろ石とショールざくろ石は、その当時から、そしてわりと最近でも同一かどうかの議論がある[1]。いまのところ、森本ざくろ石の端成分は合成されておらず、構造解析も実施されていない[2]。これが、異論が巻き起こる要因の一つであった。
それでも、ざくろ石超族の命名規約によってこの問題がレビューされ、ストイキオメトリーに基づいた解析により、森本ざくろ石とショールざくろ石をわけることができると提案されている[3]。森本ざくろ石:Ca3(TiFe2+)(SiO4)3およびショールざくろ石:Ca3Ti2(SiFe3+2)O12の理想化学式からわかるように、問題となるのはFeの価数である。そうなると、合計の酸素数と陽イオン数を固定してしまえば、分析値(酸化物重量%)からFeの価数を見積もることは可能となる。このようにして計算された値と境界線がざくろ石超族の命名規約の図5にプロットされており、森本ざくろ石とショールざくろ石はとりあえず区別されている。
北露頭の森本ざくろ石は、石英モンゾニ岩と石灰岩の境界部に生じ、どちらかというと石英モンゾニ岩に見られる傾向がある。結晶は真っ黒で、不定形であることが多いが、まれに12面体が見られる。最近になって北海道日高町千栄の糠平岩体からも森本ざくろ石が見つかっている。そこでは超苦鉄質岩がロジン化作用と熱水作用受けたことにより森本ざくろ石が生じており、12面体の結晶の中で黒色の森本ざくろ石と透明な灰鉄ざくろ石が類帯構造をなしている[4]。この産状は三重県菅島でも見つかっており、どちらもやや加水されている特徴があった。
[1] 第二文献
[2] 第一文献
[3] Grew E.S., Locock A.J., Mills S.J., Galuskina I.O., Galuskin E.V., Hålenius U. (2013) Nomenclature of the garnet supergroup. American Mineralogist, 98, 785-811.
[4] 浜根大輔, 萩原昭人 (2019) 北海道日高町千栄産の森本ざくろ石. 日本鉱物科学会2019年年会, R1P-09.
IMA No./year: 1992-024
草地鉱 / Kusachiite
Cu2+Bi3+2O4
模式地:岡山県 高梁市 布賀鉱山
原著:Henmi C. (1995) Kusachiite, CuBi2O4, a new mineral from Fuka, Okayama Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 59, 545-548
IMA No./year: 1993-049
武田石 / Takedaite
Ca3B2O6
模式地:岡山県 高梁市 布賀鉱山
原著:Kusachi I., Henmi C., Kobayashi S. (1995) Takedaite, a new mineral from Fuka, Okayama Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 59, 549-552
IMA No./year: 1996-051
パラシベリア石 / Parasibirskite
Ca2B2O5・H2O
模式地:岡山県 高梁市 布賀鉱山
原著:Kusachi I., Takechi Y., Henmi C., Kobayashi S. (1998) Parasibirskite, a new mineral from Fuka, Okayama Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 62, 521-525

模式地標本 中央上下に走るややピングがかった白色脈。実際には本鉱+シベリア石の混合で,X線の比率からすると本鉱:シベリア石=2:3くらい。パラシベリア石と名付けられてはいるものの,結晶構造はシベリア石とはとくに関連は無い(Takahashi et al., 2010, JMPS, 105, 70-73)。
IMA No./year: 1997-002
岡山石 / Okayamalite
Ca2B2SiO7
模式地:岡山県 高梁市 布賀鉱山
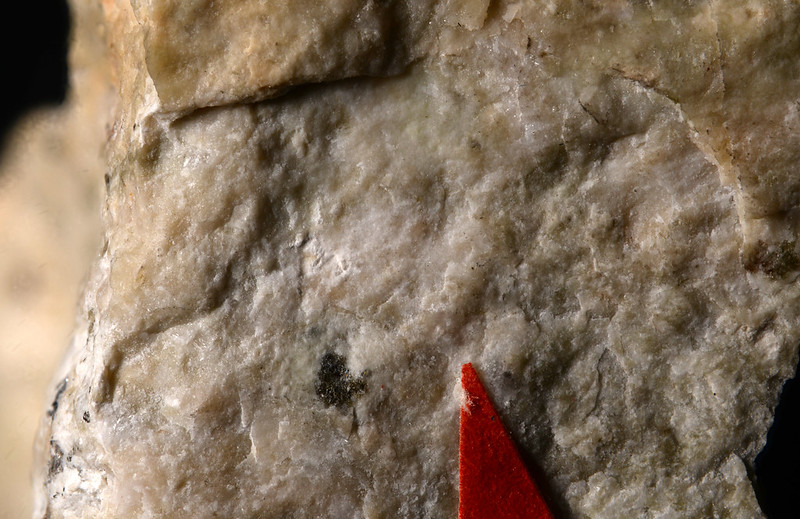
模式地標本 矢印先に岡山石が含まれるが白色なので見た目ではわからない。
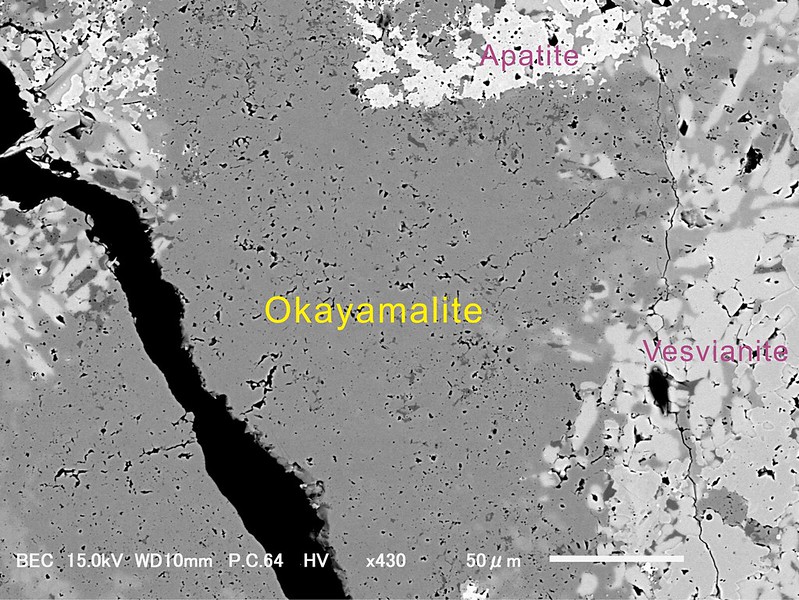
薄片を作りSEMの反射電子像でようやくその存在が確認できる。分析値はCa1.99B2Al0.02Si0.99O7。
ゲーレン石(Ca2Al2SiO7)からみてのAl→B置換体が岡山石となる。
IMA No./year: 1997-010
津軽鉱 / Tsugaruite
Pb4As2S7(当初)
Pb28As15S50Cl(2019~)
模式地:青森県 平川市 湯ノ沢鉱山
IMA No./year: 1998-037
苦土フォイト電気石 / Magnesio-foitite
□(Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
模式地:山梨県 山梨市 三富上釜口 京ノ沢
原著:Hawthorne F.C., Selway J.B., Kato A., Matsubara S., Shimizu M., Grice J.D., Vajdak J. (1999) Magnesiofoitite, (Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4, a new alkali-deficient tourmaline. The Canadian Mineralogist, 37, 1439-1443.

模式地標本 Mg#が90%くらいで鉄はかなり少ない。しっかりと本鉱です。

宮崎県乙ヶ渕鉱山(参考) 色が薄いところが本鉱だと言われているが実はそんなことはない。たくさん分析したが色の濃淡の範囲でMg#が40-45%で,どうやってもMg#は50%を超えることはない。調べた範囲でこの産地のはすべて鉄タイプのフォイット電気石です。
IMA No./year: 1998-039
糸魚川石 / Itoigawaite
SrAl2Si2O7(OH)2・H2O
模式地:新潟県 糸魚川市 親不知海岸
原著:Miyajima H., Matsubara S., Miyawaki R., Ito K. (1999) Itoigawaite, a new mineral, the Sr analogue of lawsonite, in jadeitite from the Itoigawa-Ohmi district, central Japan. Mineralogical Magazine, 63, 909-916.
IMA No./year: 1998-055
蓮華石 / Rengeite
Sr4Ti4ZrO8(Si2O7)2
模式地:新潟県 糸魚川市 姫川 小滝川 親不知海岸
原著:Miyajima H., Matsubara S., Miyawaki R., Yokoyama K., Hirokawa K. (2001) Rengeite, Sr4ZrTi4Si4O22, a new mineral, the Sr-Zr analogue of perrierite from the Itoigawa-Ohmi district, Niigata Prefecture, central Japan. Mineralogical Magazine, 65 111-120.

糸魚川市海岸 松原石と見た目で区別が付かないので分析してみたら(Sr3.97Ba0.09Ca0.05)Ti3.94Zr1.05O8Si3.96O14。Zrがしっかり入っているのでこれは蓮華石。
IMA No./year: 1998-063
ネオジム弘三石 / Kozoite-(Nd)
Nd(CO3)(OH)
模式地:佐賀県 唐津市 肥前町 新木場
原著:Miyawaki R., Matsubara S., Yokoyama K., Takeuchi K., Terda Y., Nakai I. (2000) Kozoite-(Nd), Nd(CO3)(OH), a new mineral in an alkali olivine basalt from Hizen-cho, Saga Prefecture, Japan. American Mineralogist, 85, 1076-1081
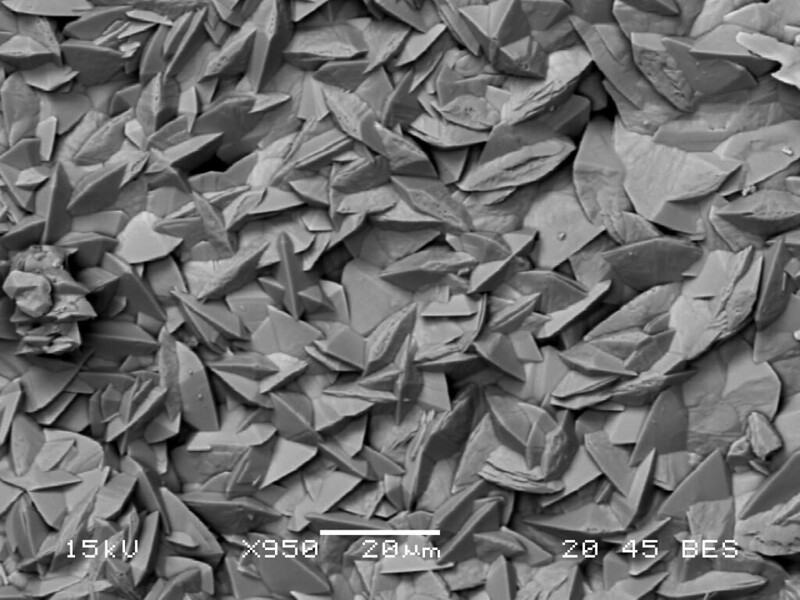
電子顕微鏡写真 上の写真でキラっとしているところは小さい結晶の集合
IMA No./year: 1999-011
多摩石 / Tamaite
(Ca,K,Na)xMn6(Si,Al)10O24(OH)4·nH2O(x = 1-2; n = 7-11)
模式地:東京都 奥多摩町 白丸鉱山
原著:Matsubara S., Miyawaki R., Tiba T., Imai H. (2000) Tamaite, the Ca-analogue of ganophyllite, from the Shiromaru mine, Okutama, Tokyo, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 95, 79-83

模式地標本 分析をするとこの結晶はCaタイプで,多摩石となる。

模式地標本 分析をするとこの結晶はNaタイプで,Eggletonite[(Na,Ba,Ca,K)xMn6(Si,Al)10O24(OH)4·nH2O(x = 1-2; n = 7-11)]となる。多摩石とは見た目で区別できない。
IMA No./year: 1999-025
大峰石 / Ominelite
Fe2+Al3O2(BO3)(SiO4)
模式地:奈良県 天川村 弥山川
IMA No./year: 1999-047
パラ輝砒鉱 / Pararsenolamprite
As
模式地:大分県 杵築市 向野鉱山
原著:Matsubara S., Miyawaki R., Shimizu M., Yamanaka T. (2001) Pararsenolamprite, a new polymorph of native As, from the Mukuno mine, Oita Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 65, 807-812
結晶構造はすでに判明しているようだ。
IMA No./year: 2000-027
松原石 / Matsubaraite
Sr4Ti5O8(Si2O7)2
模式地:新潟県 糸魚川市 小滝川
原著:Miyajima H., Miyawaki R., Ito K. (2002) Matsubaraite, Sr4Ti5(Si2O7)2O8, a new mineral, the Sr-Ti analogue of perrierite in jadeitite from the Itoigawa-Ohmi district, Niigata Prefecture, Japan. European Journal of Mineralogy, 14, 1119-1128

模式地標本
蓮華石とは見た目で区別できなさそうで,分析してみると松原石のほうでした。Sr3.79Ti5.33Si3.76O22,SrとSiがやや不足でTiがやや過剰。でも原著をみてもどうやらその傾向があるようだ。下のBSE像で一部(明るい部分)がTausonite(SrTiO3),これもレアな鉱物。
IMA No./year: 2001-043
わたつみ石 / Watatsumiite
KNa2LiMn2V2Si8O24
模式地:岩手県 田野畑村 田野畑鉱山
原著:Matsubara S., Miyawaki R., Kurosawa M., Suzuki Y. (2003) Watatsumiite, KNa2LiMn2V2Si8O24, a new mineral from the Tanohata mine, Iwate Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 98, 142-150.

模式地標本 黄緑色のところ。色が不安だったので分析してみると,K0.96Na2.28Li1.0(Mn1.41Mg0.44Fe0.07)(V1.38Ti0.56)Si8.04O24(Li=1.0を仮定)。本鉱だろう。茶色のところはバナジウムを含むエジリンでした。
IMA No./year: 2001-045
白水雲母 / Shirozulite
KMn2+3(Si3Al)O10(OH)2
模式地:愛知県 設楽町 田口鉱山
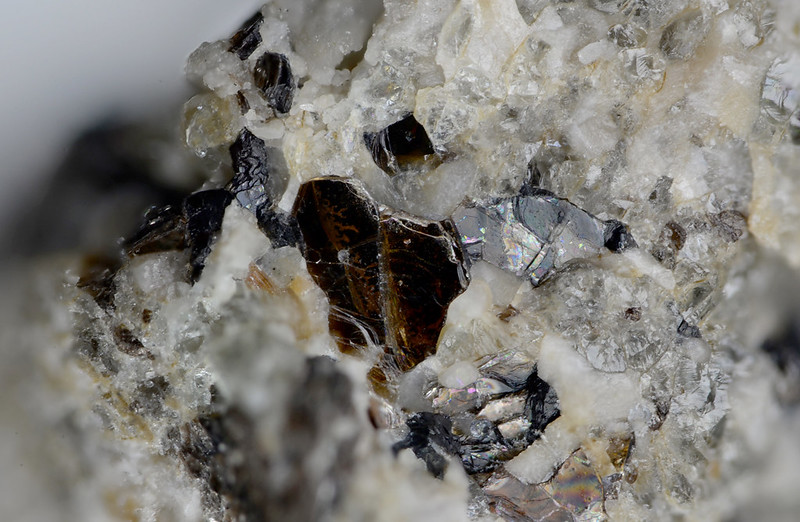
模式地標本 山田滋夫氏から恵与いただいた。金雲母にしか見えないががMnが主成分で本鉱であった。組成はK0.99(Mn1.52Mg0.86Al0.35Fe0.22Ti0.06)Σ3Si2.60Al1.38O10(OH)2.
IMA No./year: 2001-049(2012s.p.)
カリフェリリーキ閃石 / Potassic-ferri-leakeite(原記載はPotassic-leakeite)
KNa2Mg2Fe3+2LiSi8O22(OH)2
模式地:岩手県 田野畑村 田野畑鉱山

Kedykverpakhk Mt, Lovozero Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast’, Northern Region, Russia.
緑色部が本鉱で,ブラウン色はエジリン。
IMA No./year: 2001-055
新潟石 / Niigataite (2016年に復活)
CaSrAl3O(Si2O7)(SiO4)(OH)
模式地:新潟県 糸魚川市 宮花海岸
原著:Miyajima H., Matsubara S., Miyawaki R., Hirokawa K. (2003) Niigataite, CaSrAl3(Si2O7)(SiO4)O(OH): Sr-analogue of clinozoisite, a new member of the epidote group from the Itoigawa-Ohmi district, Niigata Prefecture, central Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 98, 118-129.

模式地標本 中央黄土色結晶は基本的には緑泥石だが,その中に本鉱が含まれていた。薄紫はダイアスポア。
2006年の緑簾石族命名規約によって学名が”Clinozoisite-(Sr)”になっていたが,2016年の命名規約の再改定によって原記載どおりの”Niigataite”が復活することになった。
IMA No./year: 2001-065(2012s.p.)
プロト直閃石 / Proto-anthophyllite
□Mg2Mg5Si8O22(OH)2
模式地:岡山県 新見市 高瀬鉱山
原著:Konishi H., Groy T.L., Dodony I., Miyawaki R., Matsubara .S, Buseck P.R. (2003) Crystal structure of protoanthophyllite: A new mineral from the Takese ultramafic complex, Japan. American Mineralogist, 88, 1718-1723
IMA No./year: 2002-051(2012s.p.)
定永閃石 / Sadanagaite(原記載はMagnesiosadanagaite)
NaCa2Mg3Al2(Si5Al3)O22(OH)2
模式地:岐阜県 揖斐川町 春日鉱山
原著:Banno Y., Miyawaki R., Matsubara S., Makino K., Bunno M., Yamada S., Kamiya T. (2004) Magnesiosadanagaite, a new member of the amphibole group from Kasuga-mura, Gifu Prefecture, central Japan. European Journal of Mineralogy, 16, 177-183

上標本の後方散乱二次電子像。
左側のやや暗いコントラストはパーガス閃石で,右の明るいコントラストが本鉱。この産地の角閃石はことごとくゾーニングしていて,主にはSi量が異なる。こんだけはっきり分かれているなんて,生成条件がある段階でパキッと変わったんだろう。
定永閃石に伴われてソーダ金雲母の産出が知られるが,ソーダ金雲母はこのタイプの石には来ない。理由はよくわからない。
IMA No./year: 2002-054
ランタン弘三石 / Kozoite-(La)
LaCO3(OH)
模式地:佐賀県 唐津市 肥前町 満越
原著:Miyawaki R., Matsubara S., Yokoyama K., Iwano S., Hamasaki K., Yukinori I. (2003) Kozoite-(La), La(CO3)(OH), a new mineral from Mitsukoshi, Hizen-cho, Saga Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 98, 137-141.
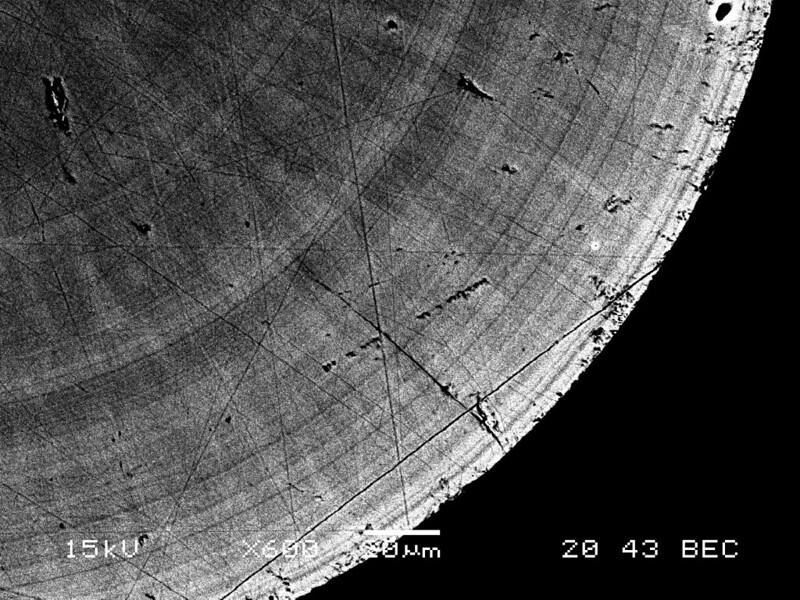
輪切りにしてSEMで見るとこうなる。明るい部分ほどNdが多く,暗いところほどLaが多い。玉の中心部が本鉱となる。
IMA No./year: 2003-036
東京石 / Tokyoite
Ba2Mn3+(VO4)2(OH)
模式地:東京都 奥多摩町 白丸鉱山
原著:Matsubara S., Miyawaki R., Yokoyama K., Shimizu M., Imai H. (2004) Tokyoite, Ba2Mn3+(VO4)2(OH), a new mineral from the Shiromaru mine, Okutama, Tokyo, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 99, 363-367
IMA No./year: 2003-053
イットリウム岩代石 / Iwashiroite-(Y)
YTaO4
模式地:福島県 川俣町 水晶山
原著:Hori H., Kobayashi T., Miyawaki R., Matsubara S., Yokoyama K., Shimizu M. (2006) Iwashiroite-(Y), YTaO4, a new mineral from Suishoyama, Kawamata Town, Fukushima Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 101, 170-177
マメドチ谷の鉱物はメタミクトなのでいわゆるフォーマン石としていったん報告したけど,メタミクトからの構造回復挙動を精査したらこれは岩代石として再結晶化することがわかった。化学組成的にもTa/(Ta+Nb)>0.9と非常にTaに富んでいる。この化学組成だとペグマタイト程度の温度では岩代石の構造しか安定化しない。
IMA No./year: 2004-004
セリウムヒンガン石 / Hingganite-(Ce)
BeCe(SiO4)(OH)
模式地:岐阜県 中津川市 蛭川田原
原著:Miyawaki R., Matsubara S., Yokoyama K., Okamoto A. (2007) Hingganite-(Ce) and hingganite-(Y) from Tahara, Hirukawa-mura, Gifu Prefecture, Japan: The description on a new mineral species of the Ce-analogue of hingannite-(Y) with a refinement of the crystal structure of hingganite-(Y). Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 102, 1-7
IMA No./year: 2004-049
ソーダ金雲母 / Aspidolite
NaMg3(Si3Al)O10(OH)2
模式地:岐阜県 揖斐川町 春日鉱山
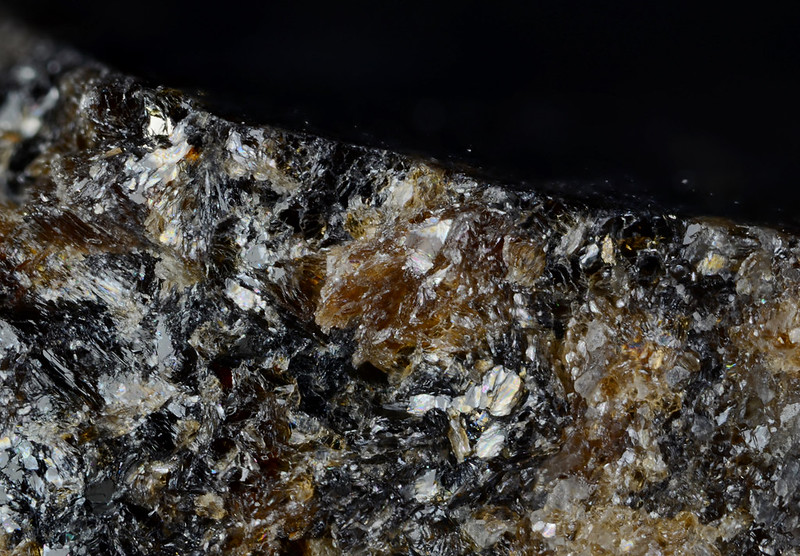
模式地標本 写真中央に代表されるややオレンジがかった雲母が本鉱。周りは定永閃石。
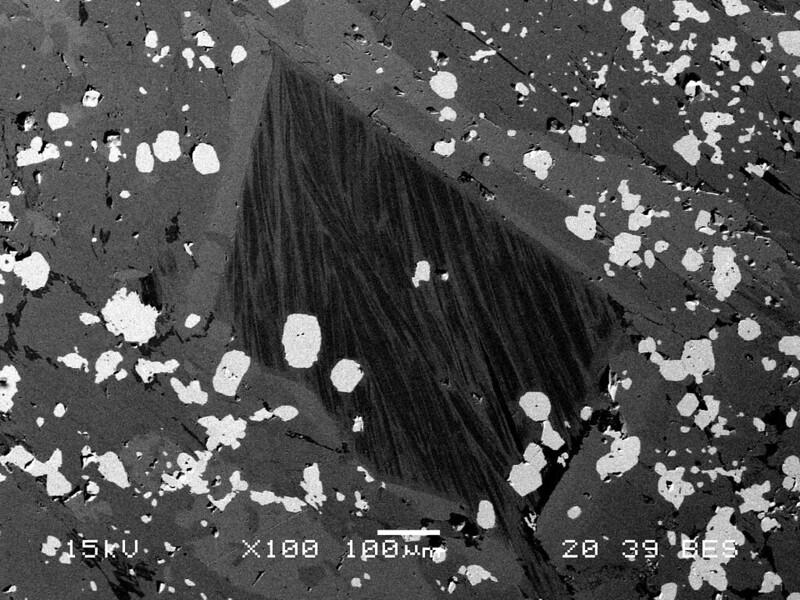
上の標本のSEM写真 上下に筋が入った結晶中の暗色が本鉱で結晶内の明るい筋は金雲母。写真内に白く散らばっているところはチタン石で,基質は定永閃石。
コメント:Aspidoliteという鉱物はオーストラリアで発見され1869年に黒雲母(biotite)-金雲母(phlogopite)系列のNaとMgに富む雲母としていったん記載されていた。だけどもその後にaspidoliteはphlogopite(金雲母)のNa置換体と解釈されて,sodium phlogopiteという名前のほうが有名になってしまいaspidoliteという名前は有名無実化。ところが雲母の命名規約が変わってaspidoliteの名前が復活し,化学組成も上記で定義された。ところがところが,aspidoliteという鉱物にはタイプ標本やちゃんとしたデータが存在していなくて名前だけが存在していたのです。そこでタイプ標本とデータを改めてaspidoliteとして申請して承認を受けたというのが本鉱です。和名は記載者が提案する「ソーダ金雲母」を採用しているけど,学名はギリシャ語のaspidos(盾のような)にちなんでます。直訳すると盾雲母。ついでに書いとくと「黒雲母/biosite」って最新の命名規約では鉱物種としては抹消されてて,それは金雲母(philogopite)-鉄雲母(annite)の固溶体というフィールドネームということになっている。
写真の標本はタイプ標本と同じ岩石から採集されたもので,山田滋夫氏に提供していただいた。いまのところソーダ金雲母はこの標本にしか見つかっていない。どんな定永閃石の標本にも本鉱が伴われると思われがちだが,一般的な定永閃石の標本に本鉱はこない。
IMA No./year: 2005-033
苣木鉱 / Sugakiite
Cu(Fe,Ni)8S8
模式地:北海道 様似町
未入手
IMA No./year: 2005-050
沼野石 / Numanoite
Ca4CuB4O6(CO3)2(OH)6
模式地:岡山県 高梁市 布賀鉱山
原著:Ohnishi M., Kusachi I., Kobayashi S., Yamakawa J., Tanabe M., Kishi S., Yasuda T. (2007) Numanoite, Ca4CuB4O6(OH)6(CO3)2, a new mineral species, the Cu analogue of borcarite from the Fuka mine, Okayama Prefecture, Japan. The Canadian Mineralogist, 45, 307-315
IMA No./year: 2006-022
セリウム上田石 / Uedaite-(Ce)
Mn2+CeAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
模式地:香川県 土庄町 灘山

Heftetjern, Tørdal, Telemark, Norway
この標本は海外の標本を調べているなかで見つけた。
IMA No./year: 2006-049
大阪石 / Osakaite
Zn4SO4(OH)6·5H2O
模式地:大阪府 箕面市 平尾鉱山
原著:Ohnishi M., Kusachi I., Kobayashi S. (2007) Osakaite, Zn4SO4(OH)6·5H2O, a new mineral species from the Hirao mine, Osaka, Japan. The Canadian Mineralogist, 45, 1511-1517


模式地標本 タイプ標本の片割れを著者から恵与。淡い青色の六角板状結晶が本鉱の特徴。
IMA No./year: 2006-055
ストロンチウム緑簾石 / Epidote-(Sr)
CaSrAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
模式地:高知県 香美市 穴内鉱山
原著:Minakawa T., Fukushima H., Nishio-Hamane D., Miura H. (2008) Epidote-(Sr), CaSrAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)(OH), a new mineral from the Ananai mine, Kochi Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 103, 400-406
IMA No./year: 2007-012
宗像石 / Munakataite
Pb2Cu2(Se4+O3)SO4(OH)4
模式地:福岡県 宗像市 河東鉱山
原著:Matsubara S., Mouri T., Miyawaki R., Yokoyama K., Nakahara M. (2008) Munakataite, a new mineral from the Kato mine, Fukuoka, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 103, 327-332
IMA No./year: 2007-019
田野畑石 / Tanohataite
LiMn2Si3O8(OH)
模式地:岩手県 田野畑村 田野畑鉱山
原著:Nagase T., Hori H., Kitamine M., Nagashima M., Abduriyim A., Kuribayashi T. (2012) Tanohataite, LiMn2Si3O8(OH): a new mineral from the Tanohata mine, Iwate Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 149-154.
IMA No./year: 2007-037
幌満鉱 / Horomanite
Fe6Ni3S8
模式地:北海道 様似町

模式地標本 中央から左上の明るい黄銅色が幌満鉱。自然銅を伴うことがある。

幌満鉱の反射顕微鏡写真。中央の結晶の横幅で約250ミクロン。結晶内部に少量のトロイリ鉱(Troilite):FeSを含むことが多い。
平均化学組成は(Fe6.13Ni2.80Cu0.14)Σ9.07S7.93。
IMA No./year: 2007-038
様似鉱 / Samaniite
Cu2Fe5Ni2S8
模式地:北海道 様似町
「未入手」
IMA No./year: 2007-053(2012s.p.)
カリフェロパーガス閃石 / Potassic-ferro-pargasite
KCa2(Fe2+4Al)Si6Al2O22(OH)2
模式地:三重県 亀山市 加太市場
原著:Banno Y., Miyawaki R., Matsubara S., Sato E., Nakai I., Matsuo G., Yamada S. (2009) Potassic-ferropargasite, a new member of the amphibole group, from Kabutoichiba, Mie Prefecture, central Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 104, 374-382
原著を読むとK/(K+Na)が0.5に近い微妙な値。こいつも分析したところやっぱりK/(K+Na)=0.52-0.53とかなり微妙だが,とりあえずK>Naで本鉱の部分が存在している。Na>Kとなる「ferropargasite」もそれなりにあるので,どっちつかずなんだなこの標本は。
IMA No./year: 2008-031
ネオジムウェークフィールド石 / Wakefieldite-(Nd)
Nd(VO4)
模式地:高知県 香美市 有瀬鉱床

上標本の電子顕微鏡写真。最も明るいところに本鉱が含まれる。やや明るいところはカリオピライト,右上部に広がるやや暗いところは方解石。下部分にある鱗片状のやや明るいところは赤鉄鉱。
適当に拾った石を何も考えずに適当に切って観察しただけで簡単に本鉱が見つかったので,この産地の鉱石には普遍的に含まれていると思う。この試料からは他にイットリウムウェークフィールド石,ランタンウェークフィールド石もそれなりに含まれていた。これは分析しないとわからない。いずれにしても顕微鏡サイズ。
IMA No./year: 2008-067
千葉石 / Chibaite
SiO2·n(CH4,C2H6,C3H8,C4H10); (nmax = 3/17)
模式地:千葉県 南房総市 荒川
原著:Momma K., Ikeda T., Nishikubo K., Takahashi N., Honma C., Takada M., Furukawa Y., Nagase T., Kudoh Y. (2011) New silica clathrate minerals that are isostructural with natural gas hydrates. Nature Communications, 2, 196-7
IMA No./year: 2009-026
桃井ざくろ石 / Momoiite
Mn2+3V3+2(SiO4)3
模式地:愛媛県 西条市 鞍瀬鉱山
原著:Tanaka H., Endo S., Minakawa T., Enami M., Nishio-Hamane D., Miura H., Hagiwara A. (2010) Momoiite, (Mn2+,Ca)3(V3+,Al)2Si3O12, a new manganese vanadium garnet from Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 105, 92-96
IMA No./year: 2010-085a
島崎石 / Shimazakiite
Ca2B2-xO5-3x(OH)3x (x = 0-0.06)
模式地:岡山県 高梁市 布賀鉱山
原著:Kusachi I., Kobayashi S., Takechi Y., Nakamuta Y., Nagase T., Yokoyama K., Momma K., Miyawaki R., Shigeoka M., Matsubara S. (2013) Shimazakiite-4M and shimazakiite-4O, Ca2B2O5, two polytypes of a new mineral from Fuka, Okayama Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 77, 93-105

模式地標本 本鉱と方解石が入り交じってますが見た目ではわかりません。

顕微鏡写真(クロスニコル) 顕微鏡下では非常によくわかります。このもやもやが本鉱の特徴で,ポリタイプが混じってます。
IMA No./year: 2010-086
亜鉛ビーバー石 / Beaverite-(Zn)
Pb(Fe3+2Zn)(SO4)2(OH)6
模式地:新潟県 阿賀町 三川鉱山
「未入手」
IMA No./year: 2011-023(2012s.p.)
愛媛閃石 / Chromio-pargasite(原記載はEhimeite)
NaCa2(Mg4Cr)(Si6Al2)O22(OH)2
模式地:愛媛県 新居浜市 東赤石山
原著:Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Minakawa T., Yamaura J., Saito S., Kadota R. (2012) Ehimeite, NaCa2Mg4CrSi6Al2O22(OH)2: The first Cr-dominant amphibole from the Akaishi Mine, Higashi-Akaishi Mountain, Ehime Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 1-7
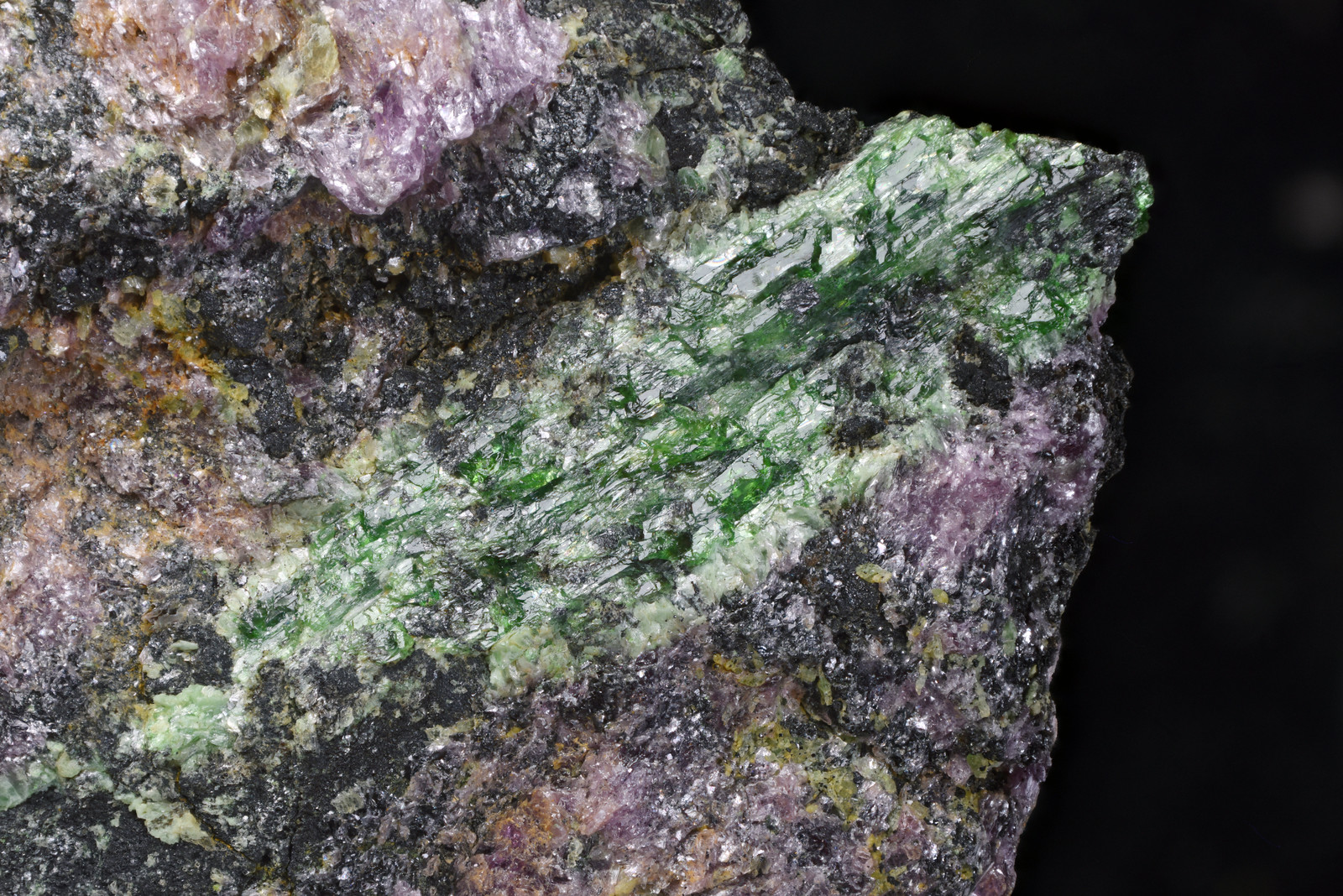

模式地標本
Ehimeiteで申請して承認されたが,すぐに命名規約変更の論文が出て今はchromio-pargasiteが正式名称。ehimeiteだった期間はわずか1年ちょっととあまりにも短命すぎた。
IMA No./year: 2011-030
イットリウム肥前石 / Hizenite-(Y)
Ca2Y6(CO3)11·14H2O
模式地:佐賀県 唐津市 肥前町 満越
「未入手」
IMA No./year: 2011-031
イットリウムラブドフェン / Rhabdophane-(Y)
YPO4·H2O
模式地:佐賀県 玄海町 日ノ出松

SEM写真 エンスタタイト結晶の被膜で産し,六角柱状結晶の放射状集合体。
IMA No./year: 2011-043
宮久石 / Miyahisaite
(Sr,Ca)2Ba3(PO4)3F
模式地:大分県 佐伯市 下払鉱山
原著:Nishio-Hamane D., Ogoshi Y., Minakawa T. (2012) Miyahisaite, (Sr,Ca)2Ba3(PO4)3F, a new mineral of the hedyphane group in the apatite supergroup from the Shimoharai mine, Oita Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 121-126, 181


模式地標本 だいたい同じ視野を写真とBEI像で並べてみた。下のBEI像で白い部分が宮久石で,その中心にあるやや明るい灰色はフッ素燐灰石。
IMA No./year: 2011-099
イットリウム高縄石 /Takanawaite-(Y)
Y(Ta,Nb)O4
模式地:愛媛県 松山市 高縄山
原著:Nishio-Hamane D., Minakawa T., Ohgoshi Y. (2013) Takanawaite-(Y), a new mineral of the M-type polymorph with Y(Ta,Nb)O4 from Takanawa Mountain, Ehime Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 108, 335-344.

模式地標本 この産地のペグマタイトはほとんど雲母を伴わず,高縄石は石英と長石の境界に産する。メタミクト化しており非常に脆いため,岩石を割る際の衝撃でほとんど割れてしまう。結晶面が見えることは稀。放射状に集合する傾向がある。

香川県広島 第二産地の発見(武智・浜根, 2016, 資源地質学会第66回年会講演要旨集,P-10)。
IMA No./year: 2012-010
イットリウム苦土ローランド石 / Magnesiorowlandite-(Y)
Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2
模式地:三重県 菰野町 宗利谷
IMA No./year: 2012-020
伊勢鉱 / Iseite
Mn2Mo3O8
模式地:三重県 伊勢市
原著:Nishio-Hamane D., Tomita N., Minakawa T., Inaba S. (2013) Iseite, Mn2Mo3O8, a new mineral from Ise, Mie Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 108, 37-41.
IMA No./year: 2012-035
箕面石 / Minohlite
(Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10·8H2O
模式地:大阪府 箕面市 平尾鉱山
原著:Ohnishi M., Shimobayashi N., Nishio-Hamane D., Shinoda K., Momma K., Ikeda T. (2013) Minohlite, a new copper-zinc sulphate mineral from Minoh, Osaka, Japan. Mineralogical Magazine, 77, 335-342
IMA No./year: 2012-095
ランタンバナジウム褐簾石 / Vanadoallanite-(La)
CaLaVAlFe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
模式地:三重県 伊勢市
原著:Nagashima M., Nishio-Hamane D., Tomita N., Minakawa T., Inaba S. (2013) Vanadoallanite-(La): a new epidote-supergroup mineral from Ise, Mie Prefecture, Japan, Mineralogical Magazine, 77, 2739-2752.

模式地標本 この産地の褐簾石亜族の新鉱物は見た目では区別できません。なのでとりあえずこの結晶を本鉱としておきましょう。
本鉱が本当にどのくらい実在するかについて国内外の相当コアなマニアや研究者から問い合わせが来ているのでまじめに回答しておくと,存在が確認できているのはタイプ標本のみである。もししそれらしい産状の褐簾石を見つけたとしても結晶内で組成変動が少なからずあるので,種を確定するにあたって結晶のピックアップと化学組成分析は必須。単結晶構造解析があるとベスト。要は,確かなのは分離&研磨&分析したその薄片だけになってしまう。それは個人のコレクションとしては楽しくはない気はする。それでもどうしても確かなものをという人がいるようなので書いておくと,本鉱となるためにはV2O3が最低でも6.5重量パーセントを上回る必要がある。もし分析済みと称した標本を手に入れる際はそれをひとつの目安にすればいい。ただ,この記述が本鉱を保証するものではないのであたりまえですが入手は自己責任でどうぞ。
SEM写真の結晶の分析値は(Ca0.60Mn2+0.40)(La0.59Nd0.15Ce0.12Ca0.05)(V3+0.64Fe3+0.40)(Al0.90Fe3+0.10)(Fe2+0.44Mn2+0.43Mg0.12)Si3.05O12(OH)。やっぱりこういう標本でしかない。
IMA No./year: 2012-101
足立電気石 / Adachiite
CaFe2+3Al6(Si5AlO6)(BO3)3(OH)3(OH)
模式地:大分県 佐伯市 木浦鉱山
原著:Nishio-Hamane D., Minakawa T., Yamaura J., Oyama T., Ohnishi M., Shimobayashi N. (2014) Adachiite, a Si-poor member of tourmaline supergroup from the Kiura mine, Oita Prefecture, Japan, Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 109, 74-78.


模式地標本 一般的には黒色柱状結晶の集合として産出する。不透明というわけではなく,強い光をむりやりあてると小さい結晶なら透明であることが確認できる。実際には鉄電気石と複雑な累帯を成し,その一部が本鉱となる。この産地の電気石はほとんどの場合,本鉱を含んでいる。
IMA No./year: 2013-034
岩手石 / Iwateite
Na2BaMn(PO4)2
模式地:岩手県 田野畑村 田野畑鉱山
原著:Nishio-Hamane D., Minakawa T., Okada H. (2014) Iwateite, Na2BaMn(PO4)2, a new mineral from the Tanohata mine, Iwate Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 109, 34-37.

模式地標本の顕微鏡写真。オープンニコルで白濁してみえる結晶が岩手石。クロスではほぼ消光。
IMA No./year: 2013-069
今吉石 / Imayoshiite
Ca3Al(CO3)[B(OH)4](OH)6・12H2O
模式地:三重県 伊勢市
Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Momma K., Shimobayashi N., Miyawaki R., Minakawa T., Inaba S. (2015) Imayoshiite, Ca3Al(CO3)[B(OH)4](OH)6•12H2O, a new mineral of ettringite group from Ise City, Mie Prefecture, Japan., Mineralogical Magazine, 79, 413-423.
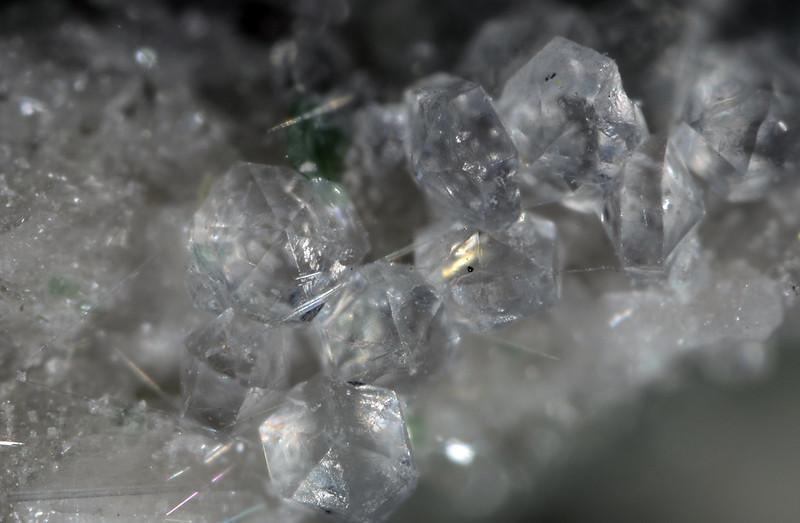
参考までにTatarinovite(ロシア産)の写真。2015年に発見された新鉱物でCa3Al(SO4)[B(OH)4](OH)6·12H2Oの化学組成。これは今吉石のCO3→SO4置換体に相当する。今吉石も結晶するとこんな形になるだろう。
IMA No./year: 2013-126
ランタンフェリ赤坂石 / Ferriakasakaite-(La)
CaLaFe3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
模式地:三重県 伊勢市
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Tomita N., Minakawa T., Inaba S. (2015) Ferriakasakaite-(La) and ferriandrosite-(La): new epidote-supergroup minerals from Ise, Mie Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 79, 735-753

模式地標本 この産地の褐簾石亜族の新鉱物は見た目では区別できません。なのでとりあえずこの結晶を本鉱としておきましょう。

組成分析でしか種を決めることができない上に,かなり狭い範囲でランタンフェリアンドロス石やランタンフェリ褐簾石と隣り合っていたりすることが本当によくある。この標本はたった50ミクロンを隔ててランタンフェリ赤坂石とランタンフェリアンドロス石が共生している。ここには写っていないがこの約500ミクロン上にはランタンフェリ褐簾石がいる。本当にこういう状態なのでラベルにはすべての種を書いておけばよろしかろうと思う。このランタンフェリ赤坂石の化学組成は(Ca0.62Mn2+0.43)(La0.75Ce0.19Nd0.05)(Fe3+0.48Al0.25V3+0.19)Al1.00(Mn2+0.63Fe2+0.37)Si3.05O12(OH)。
IMA No./year: 2013-127
ランタンフェリアンドロス石 / Ferriandorosite-(La)
Mn2+LaFe3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
模式地:三重県 伊勢市
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Tomita N., Minakawa T., Inaba S. (2015) Ferriakasakaite-(La) and ferriandrosite-(La): new epidote-supergroup minerals from Ise, Mie Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 79, 735-753

模式地標本 この産地の褐簾石亜族の新鉱物は見た目では区別できません。なのでとりあえずこの結晶を本鉱としておきましょう。実際のところ,このくらいの集合体になるとたいてい3種が混じっている。

ここの褐簾石亜族の化学組成は中間的で,ほんのちょっとの違いで簡単に種をまたぐ。このランタンフェリアンドロス石は(Mn2+0.54Ca0.46)(La0.65Ce0.14Ca0.13Nd0.11)(Fe3+0.78V3+0.21)Al1.00(Mn2+0.47Fe2+0.26Al0.14Mg0.13)Si2.99O12(OH)。
IMA No./year: 2013-130
伊予石 / Iyoite
MnCuCl(OH)3
模式地:愛媛県 佐田岬半島
Nishio-Hamane D., Momma K., Ohnishi M., Shimobayashi N., Miyawaki R., Tomita N., Okuma R., Kampf A.R., Minakawa T. (2017) Iyoite, MnCuCl(OH)3, and misakiite, Cu3Mn(OH)6Cl2: new members of the atacamite family from Sadamisaki Peninsula, Ehime Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 81, 485-498.


模式地標本 伊予石は草のように見えるものが多く,孔雀石とやや紛らわしかったりもする。愛媛県の旧国名:伊予国,そして佐田岬半島の北岸に面している海域:伊予灘から名前をもらった。
IMA No./year: 2013-131
三崎石 / Misakiite
Cu3Mn(OH)6Cl2
模式地:愛媛県 佐田岬半島
Nishio-Hamane D., Momma K., Ohnishi M., Shimobayashi N., Miyawaki R., Tomita N., Okuma R., Kampf A.R., Minakawa T. (2017) Iyoite, MnCuCl(OH)3, and misakiite, Cu3Mn(OH)6Cl2: new members of the atacamite family from Sadamisaki Peninsula, Ehime Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 81, 485-498.
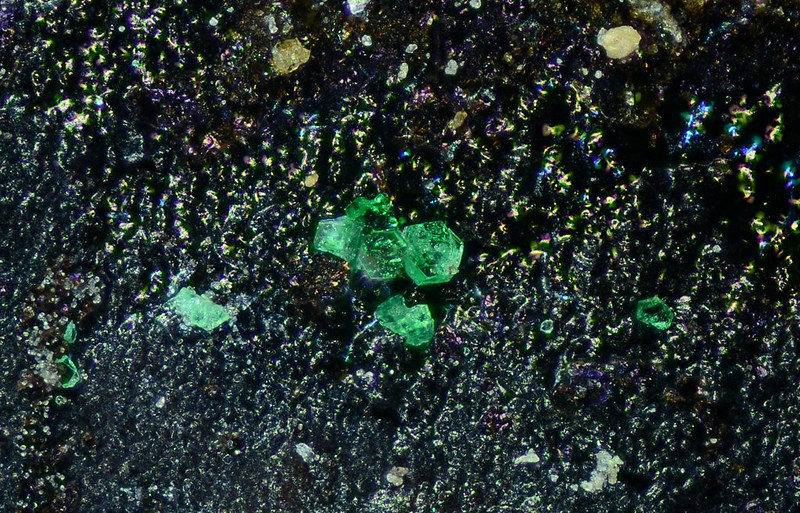
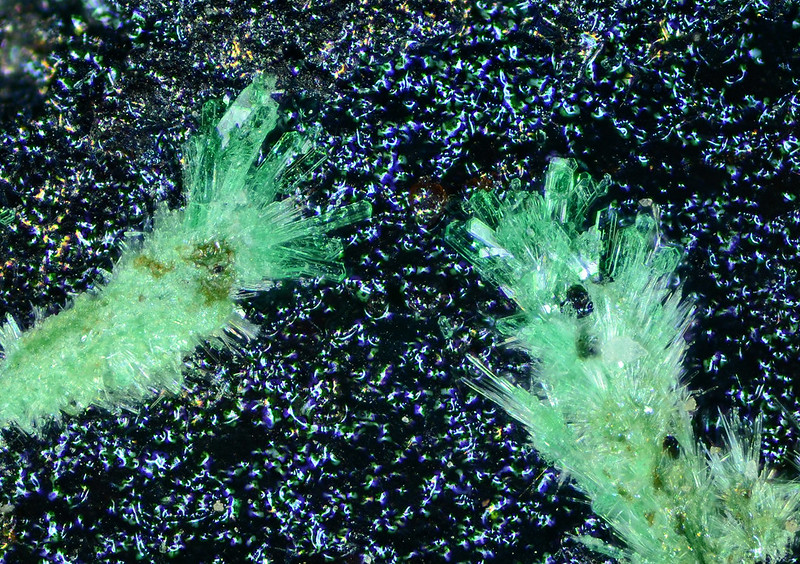
模式地標本 単独だと6角粒状となるが,伊予石と共存する際には一方向にのびて板状になったりもする。近隣住民は佐田岬半島のことを「みさき」と呼ぶし,南岸は三崎灘に面しているからというのを理由にして命名。
IMA No./year: 2014-020
イットリウム三重石 / Mieite-(Y)
Y4Ti(SiO4)2O[F,OH]6
模式地:三重県 菰野町 宗利谷
Miyawaki R., Matsubara S., Yokoyama K., Shigeoka M., Momma K., Yamamoto S. (2015) Mieite-(Y), Y4Ti(SiO4)2O[F,(OH)]6, a new mineral in a pegmatite at Souri Valley, Komono, Mie Prefecture, central Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 110, 135-144.
「未入手」
2014年鉱物学会で宮脇さんより報告される。
IMA No./year: 2014-023
房総石 / Bosoite
SiO2・nCxH2x+2
模式地:千葉県 南房総市 荒川
the early publication:Momma K., Ikeda T., Nagase T., Kuribayashi T., Honma C., Nishikubo K., Takahashi N., Takada M., Matsushita Y., Miyawaki R. and Matsubara S. (2014) CNMNC Newsletter No. 21, Mineralogical Magazine, 78, 797 -804.
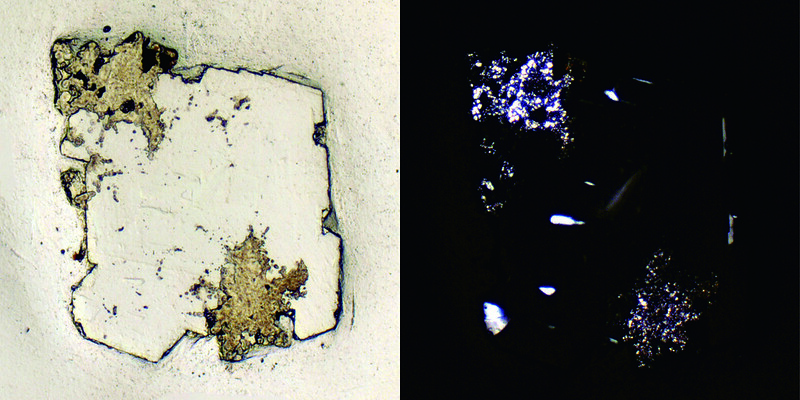
左がオープン,右がクロスニコル。左上と右下のぐしゃっとしたところはオパールと石英。クロスニコル写真で結晶の中央,左下,右側の縁など光が通っている部分が房総石。模式地の千葉石結晶には房総石がほぼ必ず(僕の調べた範囲)含まれていた。
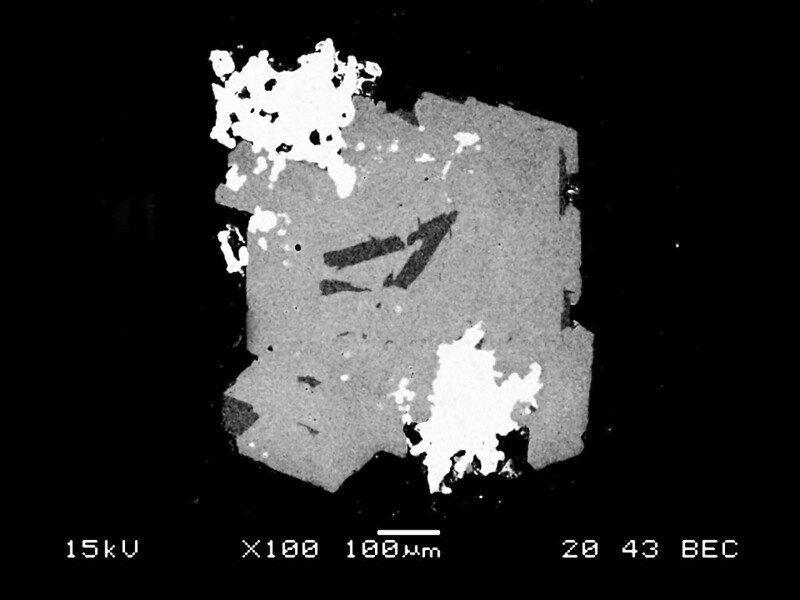
上と同じ結晶のBSI像。房総石は千葉石に比べてやや暗いコントラストとなる。
詳細は2014年鉱物学会で門馬さんにより報告される。
IMA No./year: 2014-054
豊石 / Bunnoite
Mn2+6AlSi6O18(OH)3
模式地:高知県いの町
Nishio-Hamane D., Momma K., Miyawaki R., Minakawa T. (2016) Bunnoite, a new hydrous manganese aluminosilicate from Kamo Mountain, Kochi prefecture, Japan. Mineralogy and Petrology, 110, 917-926.
IMA No./year: 2014-084
阿武石 / Abuite
CaAl2(PO4)2F2
模式地:山口県阿武町日の丸奈古鉱山
Enju S., Uehara S. (2017) Abuite, CaAl2(PO4)2F2, a new mineral from the Hinomaru-Nago mine, Yamaguchi Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 112, 109-115.

白っぽい鉱石中に含まれるが肉眼では判別はできない。鉱石には石英やトパーズがふくまれとにかく堅い。

SEM写真。明灰色の定型な結晶が阿武石。SrOを2-3wt%固溶した部分がありそこはより明るい灰色となっている。周囲の暗い部分は燐ばん土石。中間色は石英もしくはトパーズ。
山口県初の新鉱物となる。かつてMatsubara&Kato(1998, 国立科学博物館専報 30, 167-183)で「gatumbaite-like mineral」とされていたモノで,九大チームの研究で新鉱物と同定された。
IMA No./year: 2015-100
神南石 / Kannanite
Ca4Al4(MgAl)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6
模式地:愛媛県神南山
Nishio-Hamane D., Nagashima M., Ogawa N., Minakawa T. (in press) Kannanite, a new mineral from Kannan Mountain, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences.

赤鉄鉱+ブラウン鉱母岩中に脈状に走る黄褐色~オレンジ色が本鉱。脈中の赤は紅簾石。
IMA No./year: 2016-066
村上石 / Murakamiite
Ca2LiSi3O8(OH)
模式地:愛媛県岩城島
Imaoka T., Nagashima M., Kano T., Kimura J-I., Chang Q., Fukuda C. (2017) Murakamiite, LiCa2Si3O8(OH), a Li-analogue of pectolite, from the Iwagi Islet, southwest Japan. European Journal of Mineralogy, 29, 1045-1053.
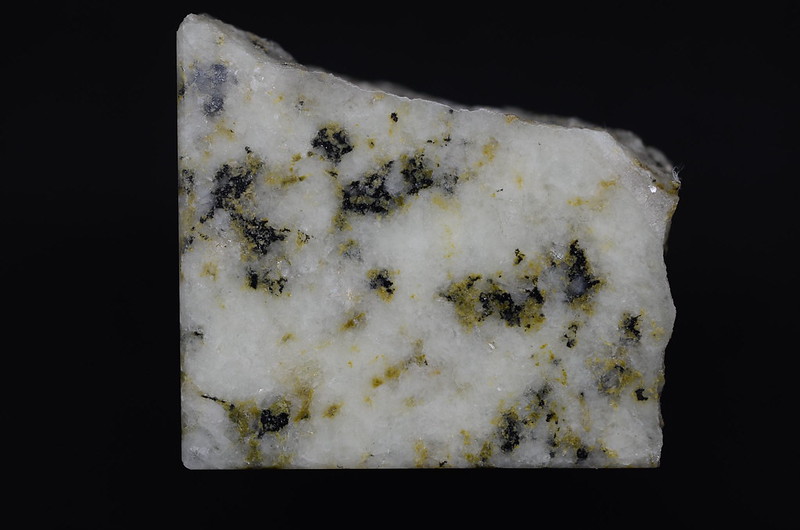
村上石を含む岩石標本。タイプ標本の一部に相当する。村上石は無色透明なため肉眼鑑定が難しいが,紫外線照射がその存在を見極める有効な手段となる。

短波長の紫外線を照射すると全体に蛍光が見られる。青は片山石,赤は曹長石。短波長の紫外線照射では村上石はわからない。
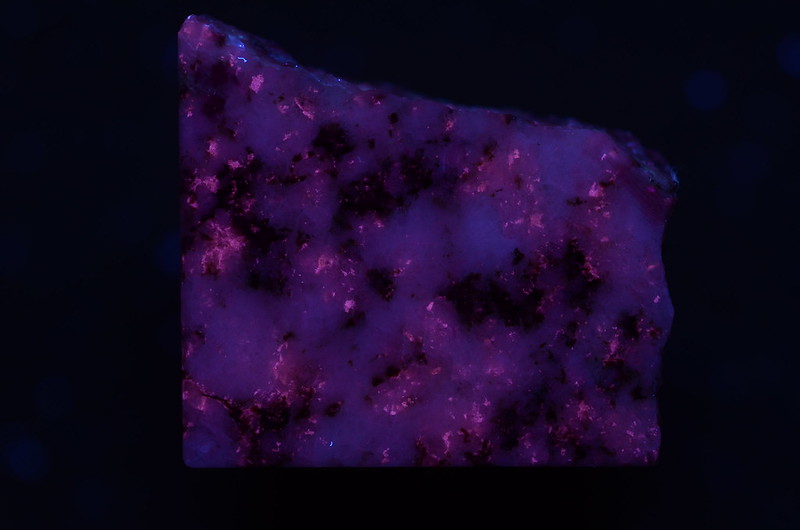
一方,長波長の紫外線をあててみると村上石だけが光る。村上石は長波長の紫外線照射で紫がかったピンク色の蛍光を示すので,実はその存在は非常にわかりやすい。

一部拡大。右側の結晶の分析値:(Ca1.93Mn0.04)Σ1.97(Li0.55Na0.45)Σ1Si3O8(OH)0.94。村上石はペクトライト:Ca2NaSi3O8(OH)から見てNa→Li置換体の鉱物となる。
著者から聞いた話をまとめておこう。ここのアルビタイトならどこでも村上石が存在しているというのは誤解で,じつは村上石はタイプ標本以外では見つかっていない。村上石のタイプ標本となった岩石は全岩組成でみると異様にLiに富んでおり,アルビタイトの中でもLiに偏りがあるようだ。そういった岩石を調べれば村上石は存在しているだろうが,肉眼や顕微鏡観察ではLiの濃度などわかるはずもない。今回の標本をみると杉石が多く入っていることはわかる。ただ私はこういった標本を以前にかなり分析を行ったのだが,Na>Liのモノばかりでことごとくがペクトライトであった。村上石は分析が必須の難しい新鉱物である。
IMA No./year: 2017-003
金水銀鉱 / Aurihydrargyrumite
Au6Hg5
愛媛県
Nishio-Hamane D., Tanaka T., Minakawa T. (2018) Aurihydrargyrumite, a Natural Au6Hg5 Phase from Japan. Minerals, 8, 415.

右の粒は全体が本鉱(ただし表面のみで内部は金)。左の粒は左上の銀色が本鉱で,中央下にあるくすんだ銀色の部分はウェイシャン鉱(Weishanite)。
IMA No./year: 2017-089
ランタンピータース石 / Petersite-(La)
模式地:三重県熊野市紀和町
Early publication: Nishio-Hamane, D., Ohnishi, M., Shimobayashi, M., Momma, K., Miyawaki, R. and Inaba, S. (2018) Petersite-(La), IMA2017-089. CNMNC Newsletter No. 41, February 2018, page 230; Mineralogical Magazine, 82, 229–233.

写真1. 新鉱物、ランタンピータース石のタイプ標本。ウニのような放射状集合が特徴的。
IMA No./year: 2018-027
日立鉱 / Hitachiite
模式地:茨城県日立市日立鉱山不動滝鉱床
Early publication: Kuribayashi T., Nagase T., Nozaki T., Ishibashi J., Shimada K., Shimizu M., Momma K. (2018) Hitachiite, IMA 2018-027. CNMNC Newsletter No. 44, August 2018, Page 879; European Journal of Mineralogy, 30, 877-882.

日立鉱を含有していた鉱石。ほとんど黄鉄鉱からなり黄銅鉱は少ない。わずかに都茂鉱と方鉛鉱が認められ、稀に自然金や閃ウラン鉱も見つかることがある。
不動滝鉱床の特定のレベルからの鉱石には日立鉱が多く入っているようだが、手に入れた写真の鉱石だとほとんど見つからない。それでもSEMで丹念に探せば100ミクロン以下の日立鉱が見つかることがある。肉眼での判別は不可能。
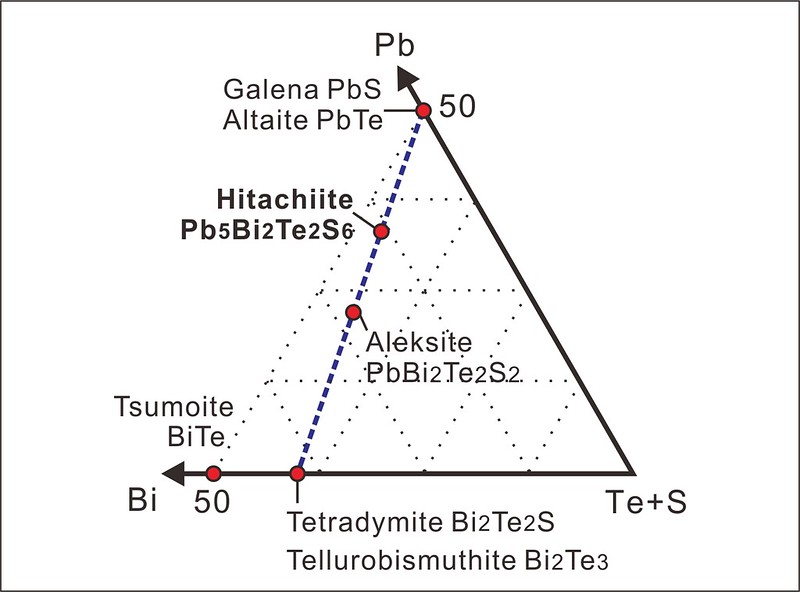
日立鉱の端成分は方鉛鉱(Galena)とテルル蒼鉛鉱(Tetradymite)を足して割ったような組成になっているが、実感としては方鉛鉱と都茂鉱(Tsumoite)を結ぶ線に近づく傾向(組成がBiに富む傾向)がある。実際に共生鉱物として鉱石中に都茂鉱は見つかるが、テルル蒼鉛鉱はみあたらなかった。また少量のテルル-硫黄置換も生じているようで、テルル多め、硫黄少なめの傾向もある。また鉄が少し含まれる。
IMA No./year: 2018-161
留萌鉱 / Rumoiite
模式地:北海道初山別村(初山別川)
Early publication: Nishio-Hamane D. and Saito K. (2019) approved on April 2019..
IMA No./year: 2018-162
初山別鉱 / Shosanbetsuite
模式地:北海道初山別村(初山別川)
Early publication: Nishio-Hamane D. and Saito K. (2019) approved on April 2019..
IMA No./year: 2019-024
皆川鉱 / Minakawaite
RhSb
模式地:熊本県
Nishio-Hamane D. Tanaka T., Shinmachi T. (2019) Minakawaite and platinum–group minerals in the placer from the clinopyroxenite area in serpentinite mélange of Kurosegawa belt, Kumamoto Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 114, 252-262.
IMA No./year: 2019-029a
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-46298:正模式標本、M-46299:副模式標本)
三千年鉱 / Michitoshiite-(Cu)
Rh(Cu1-xGex)
模式地:熊本県
Tanaka T. Shinmachi T., Kataoka K., Nishio-Hamane D. (2019) approved on 5th December 2019.

三千年(Michitoshiite)鉱の写真
全体としては米粒状の「こぶ」をもつ砂白金で、三千年鉱はこぶの最表面の層を構成することが多い。皆川鉱も同様の産状だが、三千年鉱はこぶの内部に発達することもある。
IMA No./year: 2019-054
IMA Status: A (approved)
模式標本:Fersman Mineralogical Museum (5412/1); the Canadian Museum of Nature (CMNMC 87294)
千代子石 / Chiyokoite
Ca3Si(CO3){[B(OH)4]0.5(AsO3)0.5}(OH)6·12H2O (報告時)
Ca3Si(CO3)[B(OH)4]O(OH)5·12H2O(論文)
模式地:岡山県高梁市備中町布賀鉱山
Lykova I., Chukanov N.V., Pekov I.V., Yapaskurt V.O., Pautov L.A., Karpenko V.Y., Belakovskiy D.I., Varlamov D.A., Britvin S.N. and Scheidl K.S. (2019) Chiyokoite, IMA 2019-054. CNMNC Newsletter No. 52; Mineralogical Magazine, 83, https://doi.org/10.1180/mgm.2019.73
Lykova I., Chukanov N.V., Pekov I.V., Yapaskurt V.O., Pautov L.A., Karpenko V.Y., Belakovskiy D.I., Varlamov D.A., Britvin S.N. and Scheidl K.S. (2020) Chiyokoite, Ca3Si(CO3)[B(OH)4]O(OH)5·12H2O, a new ettringite-group mineral from the Fuka mine, Okayama Prefecture, Japan. The Canadian Mineralogist, 58, 653-662.
千代子石は岡山大学の逸見千代子(1949-2018)への献名となっており、海外の研究チームによって2019年に承認された。非常にややこしい分析を精度良く行ったからこその見事な成果であり、そのような研究は彼らにしかできなかっただろう。
いわゆる千代子石という標本にはバラエティーがある。基本的にその多様な色合いは化学組成の違いに起因しており、結晶内部はほとんど必ず組成累帯を示す。調べた範囲で、赤~橙色系統は鉄やマンガンが多くヒ素が少ない。黄色系統は硫黄とアルミニウムが多く検出される。そして全体的に色が濃いものほど複雑な累帯構造になっており、不純物が多く検出される。こういった標本は千代子石ではない部分の方がむしろ多いが、現状では千代子石としておくしかない。逆に色の薄い標本(例えば一番上に掲載した写真)はあまり累帯しておらず、大部分は千代子石として解析できる。
IMA No./year: 2019-129
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-47328)
苫前鉱 / Tomamaeite
Cu3Pt
The Pt analogue of auricupride
模式地:北海道苫前町
Nishio-Hamane D. and Saito K. (2020) approved on 3rd April 2020.

トラミーン鉱中の苫前鉱。代表的なものをひとつ青い矢印先で示した。苫前鉱が埋まっている基質がトラミーン鉱で、コントラストが斜めに分かれている左側は自然ルテニウム。
IMA No./year: 2020-057
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-47662)
フェリぶどう石 / Ferriprehnite
Ca2Fe3+(AlSi3)O10(OH)2
The Fe3+ analogue of prehnite
島根県松江市美保関町北浦
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ito S., Tanaka T. (2020): Approved by CNMNC on November 3rd.
IMA No./year: 2021-041
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-48724)
桐生石 / Kiryuite
NaMn2+Al(PO4)F3
The Mn2+ analogue of Viitaniemiite
群馬県桐生市梅田町津久原
Nishio-Hamane D., Ikari I., Ohara Y. (2021) Kiryuite, IMA 2021-041. CNMNC Newsletter 63; Mineralogical Magazine, 85, https://doi.org/10.1180/mgm.2021.74
IMA No./year: 2021-098
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-49019)
マンガン四面銅鉱 / Tetrahedrite-(Mn)
Cu6(Cu4Mn2)Sb4S12S
Tetrahedrite group
北海道札幌市手稲鉱山
Momma K., Shimizu M., Kusaba Y., Ohki Y. (2022) Tetrahedrite-(Mn), IMA 2021-098, in: CNMNC Newsletter 65, Eur. J. Mineral., 34, https://doi.org/10.5194/ejm-34-143-2022.
マンガン四面銅鉱は四面銅鉱族のうちの四面銅鉱亜族の一員で、マンガンを主成分に持つ新鉱物として誕生した。手稲鉱山ではいわゆる四面銅鉱の産出が古い時代からよく知られていたところであり、それらはアンチモン(Sb)を主成分とする四面銅鉱、ヒ素(As)を主成分とする砒四面銅鉱だと考えられてきた。ただ、近年になって副成分でさらに種を細分することが公式に承認され、いわゆる四面銅鉱という標本は再検討を要する事態となっている[1]。鉱物標本として正しいラベルを書きたいとなるとこれはもう分析するしかない。しかし、四面銅鉱族は分析したところで適切に解析しないと組成式が破綻しがちという難しさがあり、そもそも標準物質の選択にも気を遣う。四面銅鉱族が成立して新鉱物として可能性が増えたとしても手を出しづらいなと思っていた。
そんななか、著者の一人である大木良弥は手稲鉱山で採集したいわゆる四面銅鉱を分析し、著量のマンガンが検出されていることに気が付いた。その同定は科学博物館へ依頼され、門馬を筆頭とした研究チームが組織される。そして、それは最新の命名規約に基づくマンガン四面銅鉱であることが判明した。新鉱物の申請に先立って、その概要は2021年9月の鉱物学会で報告されている。
自らも手稲の四面銅鉱をざっと分析しなおすと、鉄四面銅鉱、亜鉛四面銅鉱、鉄砒四面銅鉱、亜鉛砒四面銅鉱、銅砒四面銅鉱がでてきた。そしてマンガン四面銅鉱もまたすでに手元にあった。このように四面銅鉱族の成立は日本産鉱物種を増やしたが、同時に消えた鉱物もある。例えばゴールドフィールド鉱が消えてしまった。日本産のかつてのゴールドフィールド鉱は、安ゴールドフィールド鉱もしくは砒ゴールドフィールド鉱(未承認)に分類されることになり、前置詞の付かないゴールドフィールド鉱はいまのところ日本には存在しない。一方で砒ゴールドフィールド鉱、特に河津鉱山産のものは新鉱物になり得る資格があるが、分析・解析上のややこしさのためとりあえず一歩引いて状況を眺めている。
[1] Biagioni C, George L L, Cook N J, Makovicky E, Moëlo Y, Pasero M, Sejkora J, Stanley C J, Welch M D, Bosi F (2020) The tetrahedrite group: Nomenclature and classification. American Mineralogist 105, 109-122
IMA No./year: 2022-002
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-49380)
ベタフォ石 / Oxyyttrobetafite-(Y)
Y2Ti2O6O
Pyrochlore supergroup
三重県菰野町宗利谷
Nishio-Hamane D., Momma K., Ohnishi M., Inaba S. (2021): Approved by CNMNC on April 2.
IMA No./year: 2022-020
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM-M49617)
フェロフェリホルムクイスト閃石 / Ferro-ferri-holmquistite
□Li(Fe2+3Fe3+2)Si8O22(OH)2
Amphibole supergroup
愛媛県岩城島
Nagashima M., Imaoka T., Kano T., Kimura J., Chang Q., Matsumoto T. (2022) Ferro-ferri-holmquistite IMA 2022-020, in: CNMNC Newsletter 68, European Journal of Mineralogy, 34, https://doi.org/10.5194/ejm-34-385-2022.
フェロフェリホルムクイスト閃石は山口大学の永嶌真理子を筆頭とする研究チームによって発見された新種の角閃石で、Liを主成分にもつホルムクイスト閃石の二価鉄(Ferro: Fe2+)および三価鉄(Ferri: Fe3+)置換体に相当する。愛媛県岩城島が模式地ということで、愛石家なら杉石や片山石、村上石などと共存すると想像するだろうが、フェロフェリホルムクイスト閃石はそれらとはまったく共存しない。それもそのはずで母岩となる岩石も杉石などを胚胎するアルビタイト岩ではない。アルビタイト岩体を観察しに行く道すがらに転がっている、だれにも見向きもされない一見どこにでもあるただの花こう岩、それがフェロフェリホルムクイスト閃石の母岩である。そういった岩石の、特に石英と腐った黒雲母の境界あたりをよく見ると藍青色の針状結晶が埋没しており、それがフェロフェリホルムクイスト閃石である。非常に微細なためルーペ程度の倍率では観察は難しいだろう。写真の標本は今はドイツにいる永嶌氏から恵与いただいた。
個人的な出来事として、2022年の鉱物学会で日本新産となる福島県羽山岳からのフェロホルムクイスト閃石を報告することを昨年末の段階でもう決めていた。そしてそのタイミングで世界初となるフェロフェリホルムクイスト閃石の話が関係者に通知されたので恐れいった。
IMA No./year: 2022-065
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM-M49723)
浅葱石 / Asagiite
NiCu4(SO4)2(OH)6・6H2O
Ktenasite group
愛知県新城市中宇利鉱山
Nishio-Hamane D., Yajima T., Shimobayashi N., Ohnishi M., Niwa T. (2022) IMA 2022-065, in: CNMNC Newsletter 70, Eur. J. Mineral., 34, https://doi.org/10.5194/ejm-34-591-2022, 2022.
IMA No./year: 2022-080
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM-M49762)
群馬石 / Gunmaite
(Na2Sr)Sr2Al10(PO4)4F14(OH)12
New structure type
群馬県桐生市津久原
Nishio-Hamane D., Yajima T., Ohki Y., Hori H., Ikari I., Ohara Y. (2022) IMA 2022-080, in: CNMNC Newsletter 70, Eur. J. Mineral., 34, https://doi.org/10.5194/ejm-34-591-2022, 2022.
IMA No./year: 2022-101
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-49764)
蝦夷地鉱 / Ezochiite
Cu1+(Rh3+Pt4+)S4
Spinel supergroup
北海道苫前町海岸
Nishio-Hamane D., Saito K. (2023) IMA 2022-101, in: CNMNC Newsletter 71, Eur. J. Mineral., 35, https://doi.org/10.5194/ejm-35-75-2023, 2023..
IMA No./year: 2022-104
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-49763 holotype, M-49765 cotype)
北海道石 / Hokkaidoite
C22H12
Known synthetic analogue
北海道鹿追町然別地域(正模式地); 愛別町愛別水銀鉱山(副模式地)
Tanaka R., Hagiwara A., Ishibashi T., Inoue Y. (2023) IMA 2022-104, in: CNMNC Newsletter 71, Eur. J. Mineral., 35, https://doi.org/10.5194/ejm-35-75-2023, 2023.
「未公開」
北海道石は日本産としては初めてとなる有機鉱物の新鉱物である。ざっくり言うと歴青の一種で、具体的にはベンゾ[ghi]ペリレン(1,12-benzoperylene)と呼ばれる多環芳香族炭化水素の天然での姿に相当し、合成物については固有の識別番号としてCAS191-24-2が与えられている。北海道石の存在に気づき、同定するには有機化学と岩石・鉱物学のいずれにも親しんでいる必要がある。そして三拍子そろった人物がいた。筆頭の田中氏は有機化学的手法を駆使する化学者であり、岩石・鉱物についても本人は趣味だと言っているが、その知見は趣味人の域をはるかに超えている。日本の新鉱物で有機鉱物となると、今後はもう彼の専売特許になっていくだろう。
IMA No./year: 2023-004
IMA Status: A (approved)
模式標本:Fersman Mineralogical Museum, Russian Academy of Sciences, Leninskiy Prospekt 18-2, Moscow 119071, Russia, registration number 5774/1
マンガニエッケルマン閃石 / Mangani-eckermannite
NaNa2(Mg4Mn3+)Si8O22(OH)2
Amphibole supergroup
岩手県田野畑村田野畑鉱山松前沢鉱床
Kasatkin, A. V., Zubkova, N. V., Agakhanov, A. A., Chukanov, N. V., Škoda, R., Nestola, F., Belakovskiy, D. I., and Pekov, I. V.: Mangani-eckermannite, IMA 2023-004, in: CNMNC Newsletter 73, Eur. J. Mineral., 35, https://doi.org/10.5194/ejm-35-397-2023, 2023.
田野畑鉱山の赤々黒々した角閃石について、これはずーっと神津閃石であると思いこまれてきた。しかし、昨年度の鉱物学会で発表したように「赤々黒々した角閃石が神津閃石であったことはただの一度もない」ことを経験していた。ではそれは何だと言われたら、一つはマンガノマンガニアンガレッティ閃石(Mangano-mangani-ungarettiite: NaNa2(Mn2+2Mn3+3)Si8O22O2)で、もう一つはエッケルマン閃石のマンガノマンガニ置換体だった。そして、エッケルマン閃石のマンガニ置換体についてもそういう分析点があるので実在性を確信していたものの、実体をつかむところまでは私は到達できなかった。そうした中でポンと出てきたのがマンガニエッケルマン閃石であり、記載者は外国人のAnatoly Kasatkinである。事情を聞いたところ、神津閃石のラベルで売られていた標本を手に入れてその真贋を確かめるべく分析したら新鉱物だったとのことである。これはしてやられたくやしいという感情はなく、むしろやっぱりなという納得感がしかない。彼は神津閃石が存在しないのではないかと強く疑っているが、個人的な経験談としてはオレンジ色の角閃石には神津閃石が含まれていることが分かっている。しかし問題なのは神津閃石の模式標本が本当に神津閃石なのかというところで、これまでの経験を外挿して憶測すると、たぶんそれ(模式標本)は神津閃石ではないだろうなという予想がある。神津閃石問題はよりくっきりと世にさらけ出されてしまった感がある。論文でどういう主張が出てくるかを待ちたい。
IMA No./year: 2023-072a
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-50086)
不知火鉱 / Shiranuiite
Cu+(Rh3+Rh4+)S4
Spinel supergroup
熊本県美里町払川
Nishio-Hamane D., Tanaka T., Shinmachi T. (2024): Approved by CNMNC on March 2nd.

不知火鉱の写真
IMA No./year: 2024-003
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-51975)
イットリウム宮脇石 / Miyawakiite-(Y)
□Y4Fe2(Si8O20)(CO3)4(H2O)3
New structure type
福島県川俣町飯坂水晶山
Nishio-Hamane D., Momma K., Shimobayashi N., Ohnishi M., Kobayashi T. (2024): Approved by CNMNC on May 3rd.
IMA No./year: 2024-023a
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-52045)
章司閃石 / Shojiite
□Na(NaMg)Mg5Si8O22(OH)2
Amphibole supergroup
北海道士別市温根別マムシ沢
Hamada,M., Ejima T., Hasebe N., Mizukami T., Ishii A., Okamoto K., Nagashima M., Tamura A., and Morishita T.: Shojiite, IMA 2024-023a, in: CNMNC Newsletter 87, Eur. J. Mineral., 37, https://doi.org/10.5194/ejm-37-695-2025, 2025.
IMA No./year: 2024-044
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-52312)
セリウムバナジウム赤坂石 / Vanadoakasakaite-(Ce)
CaCe(V3+AlMn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Epidote supergroup
群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Harada A. (2024): Approved by CNMNC on October 3.
IMA No./year: 2024-056
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-52596)
アマテラス石 / Amaterasuite
Sr4Ti6Si4O23(OH)Cl
New structure type
岡山県新見市大佐山
Nishio-Hamane D., Nagashima M., Ohnishi M., Shimobayashi N. Matsumoto T., Tanabe M. (2024): Approved by CNMNC on November 02.

アマテラス石(黒緑色部)
IMA No./year: 2024-093a
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53294)
日之影石 / Hinokageite
MnMg(SiO4)
Olivine group
宮崎県日之影町下鶴鉱山
Nishio-Hamane D., Nagashima M., Mori Y., Ohnishi M., Tanaka T., Imai H., Fukumoto T. (2025): Approved by CNMNC on September 04.

新鉱物・日之影石の写真
IMA No./year: 2025-001
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53012)
セリウム赤坂簾石 / Akasakaite-(Ce)
CaCe(Al2Mn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Epidote supergroup
群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Harada A. (2025): Approved by CNMNC on May 3.
「写真(後日)」
IMA No./year: 2025-002
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53013)
ランタン赤坂簾石 / Akasakaite-(La)
CaLa(Al2Mn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Epidote supergroup
群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Harada A. (2025): Approved by CNMNC on May 3.
「写真(後日)」
IMA No./year: 2025-003
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53014)
ランタンバナジウム赤坂簾石 / Vanadoakasakaite-(La)
CaCe(V3+AlMn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Epidote supergroup
群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Harada A. (2025): Approved by CNMNC on May 3.
「写真(後日)」