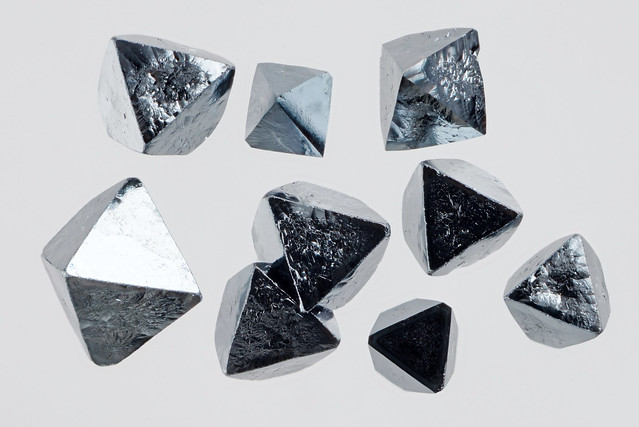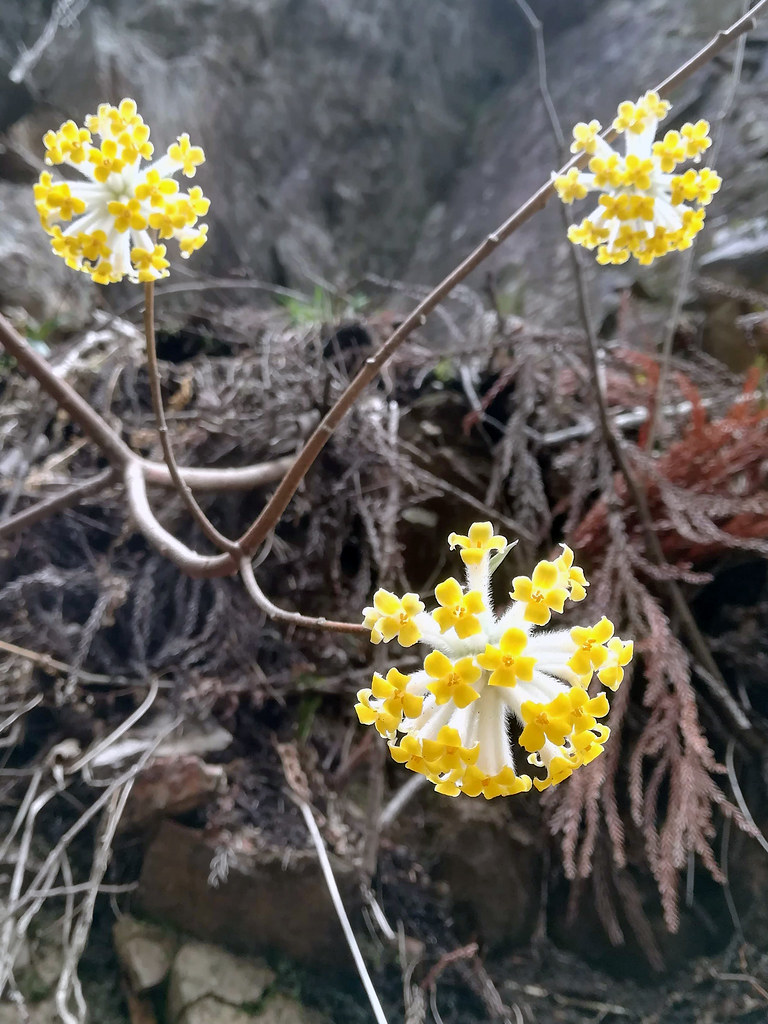自然界に存在する物質のうち、「地質作用によって生じた固体」を私たちは「鉱物」と呼んでいる。宇宙が誕生し、星々が生まれ、地球が形成され、大地や海が姿を整えていく。その壮大なプロセスのなかで生み出された物質が鉱物である。地球に飛来した隕石や月の石、探査機「はやぶさ」が持ち帰った小惑星のかけらも、すべて鉱物から成り立っており、その中には地球や太陽系、さらには宇宙そのものの歴史が刻み込まれている。
鉱物の多くは一定の化学組成と規則的な原子の配列(結晶構造)を持つ。この二つを基準に鉱物を区別することができ、分類学における「種(しゅ)」がその基本単位となる。現在、世界で6,000種を超える鉱物が知られている。地球を「未解読の古文書」にたとえるなら、鉱物はその文書を構成する「単語」にあたり、鉱物の中身であるにあたる。
そして、その単語を形づくる「文字」に相当するのが化学組成と結晶構造である。新しい鉱物の発見は、古文書の解読を進めるための新しいキーワードを見いだすことに等しい。
これまで知られていなかった鉱物種を「新種」と扱い、それを「新鉱物(new mineral)」という。ただし、それを勝手に名乗ることはできない。1958年に国際鉱物学連合(International Mineralogical Association, IMA)が設立され、翌年からは専門の委員会が新鉱物の審査と承認を行うようになった。現在では、新鉱物・命名・分類委員会(Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification)がその任を一手に担っている。新鉱物と認められるには、この委員会による正式な承認が不可欠である。ただし、承認されたからといってそこで終わりではない。論文出版までが、新鉱物を研究するものの責務である。
とはいえ承認は承認。うれしいこと。このページは新鉱物が承認されたら何か書いてみようと思ってつくってみた。内容は、私自身が発見に関わった新鉱物について、論文では書かない背景や研究の裏側などを中心に紹介していきたい。
日本から発見された新鉱物たちの一覧はこちらを参照ください。
- 日之影石 / Hinokageite (2024-093a)
- 堀石 / Horiite (2025-029)
- ランタンバナジウム赤坂簾石 / Vanadoakasakaite-(La) (2025-003)
- ランタン赤坂簾石 / Akasakaite-(La) (2025-002)
- セリウム赤坂簾石 / Akasakaite-(Ce) (2025-001)
- アマテラス石 / Amaterasuite (2024-056)
- セリウムバナジウム赤坂石 / Vanadoakasakaite-(Ce) (2024-044)
- イットリウム宮脇石 / Miyawakiite-(Y) (2024-003)
- 不知火鉱 / Shiranuiite (2023-072a)
- 蝦夷地鉱 / Ezochiite (2022-101)
- 群馬石 / Gunmaite (2022-080)
- 浅葱石 / Asagiite (2022-065)
- ベタフォ石 / Oxyyttrobetafite-(Y) (2022-002)
- 桐生石 / Kiryuite (2021-041)
- フェリぶどう石 / Ferriprehnite (2020-057)
- 苫前鉱 / Tomamaeite (2019-129)
- 三千年鉱 / Michitoshiite-(Cu) (2019-029a)
- 皆川鉱 / Minakawaite (2019-024)
- 初山別鉱 / Shosanbetsuite (2018-162)
- 留萌鉱 / Rumoiite (2018-161)
- ランタンピータース石 / Petersite-(La) (2017-089)
- 金水銀鉱 / Aurihydrargyrumite (2017-003)
- 神南石 / Kannanite (2015-100)
- 豊石 / Bunnoite (2014-054)
- 三崎石 / Misakiite (2013-131)
- 伊予石 / Iyoite (2013-130)
- ランタンフェリアンドロス石 / Ferriandorosite-(La) (2013-127)
- ランタンフェリ赤坂石 / Ferriakasakaite-(La) (2013-126)
- 今吉石 / Imayoshiite (2013-069)
- 岩手石 / Iwateite (2013-034)
- 足立電気石 / Adachiite (2012-101)
- ランタンバナジウム褐簾石 / Vanadoallanite-(La) (2012-095)
- 箕面石 / Minohlite (2012-035)
- 伊勢鉱 / Iseite (2012-020)
- イットリウム高縄石 /Takanawaite-(Y) (2011-099)
- 宮久石 / Miyahisaite (2011-043)
- 愛媛閃石 / Chromio-pargasite (2011-023)
- 桃井ざくろ石 / Momoiite (2009-026)
- ストロンチウム緑簾石 / Epidote-(Sr) (2006-055)
IMA No./year: 2024-093a
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53294)
日之影石 / Hinokageite
MnMg(SiO4)
Olivine group
宮崎県日之影町下鶴鉱山
Nishio-Hamane D., Nagashima M., Mori Y., Ohnishi M., Tanaka T., Imai H., Fukumoto T. (2025): Approved by CNMNC on September 04.

新鉱物・日之影石の写真
新鉱物、日之影石(ひのかげせき)である。有名な産地の多い宮崎県だが、意外にもこれまで新鉱物とは無縁だった。すなわち、日之影石は宮崎県産として初の新鉱物である。その名称は産地である宮崎県日之影町にちなんで名づけた。このように地名由来の命名は新鉱物の王道であり、一見すれば平凡に思えるかもしれない。だが、この地名に秘められた物語を知れば、今回の命名がふさわしいと納得してもらえるだろう。
物語の主役は、初代天皇・神武天皇の兄にあたる三毛入野命(ミケイリノノミコト)。彼は荒神・鬼八(きはち)を討伐する途上、鬼八の神通力による大雨で行く手を阻まれた。そこで三毛入野命が天つ神に祈りを捧げると、雨はやみ、雲間から「日の影」(いまで言うところの太陽の光)が差し込んだ。こうして鬼八を追い詰めたという伝承が知られる。
この伝承にちなみ、当地は「日の影」と呼ばれるようになり、その名は現在の日之影町へと受け継がれた。つまり、日之影という地名そのものがすでに神話の息吹を宿している。そして、その名を冠した日之影石にもまた、土地の歴史と神話が語り継がれているのだ。と言っておこう。

ChatGPTとGeminiに上の物語を読ませて出力されたもの。うーん・・・
今回、日之影石の発見につながったキーワードは加納輝石であろう。加納輝石は北海道八雲町館平の岩礁で発見された日本産の新鉱物である。しかし、その岩礁はすでに失われて久しい。近年になって近い箇所から得られた試料を調べたことがあるが、やはり加納輝石は見つからない。よって、現在では模式地から加納輝石を得るのは不可能。いやまて。これはそもそも北海道の話。それがなぜ宮崎県の新鉱物につながるのか。
実は、鉱物データベースmindatを調べると、加納輝石の日本国内の産地としてもう一カ所、宮崎県日之影町の下鶴鉱山が登録されていた。これならばと期待が高まり、学術文献を調べるが、下鶴鉱山産の加納輝石に関する記録は見つからなかった。まあしかし、こういうことはしばしばアマチュアが先行していたりする。それではと山田滋夫さんの「日本の鉱物産地総覧」をみるも、書いていない。地元ならばと福岡石の会の「九州・山口の鉱物」をみるが、記載なし。地元かつアマチュアの神様みたいな人ならと足立富男先生がまとめた宮崎県の鉱物一覧を読んでも、(なぜか)載っていない[1]。正直、噂レベルでも耳にしたことがなかった。それなのにmindatには載っている。ほんとかよ。

館平の加納輝石。この標本は古老の研究者からいただいた。
そんな折、愛媛大学の後輩・福本辰巳から連絡が入った。下鶴鉱山産の加納輝石という標本を手に入れたので真偽を確かめてほしいという。標本は岩石片であり、見た目で加納輝石とわかるものではない。付随していたラベルは、その標本が足立先生のコレクションであったことを示している。あれ?でもなんで宮崎県の鉱物一覧になかった?? ともかく調べてみると、確かに加納輝石が含まれていた。それにしてもいったい誰がこんな岩石片から加納輝石を見抜いていたというのか。よく見るとラベルには「皆川」の文字。師匠かよ。

日付を見ると40年近く前か。標本があったのに、宮崎県の鉱物一覧に掲載がなかったのはなぜなのか。また、それにもかかわらずmindatに加納輝石の情報が載っていたかのはなぜなのか。そうした事情は今のところわからずじまい。
事情はともかく、標本が手に入ったのでまあいいや。それにmindatの記載が事実であることも裏付けられた。そして、その標本にはもう一つ気になる鉱物が混じっていた。それが日之影石である。しかし当時は太刀打ちできず、標本はいったん「未同定ひきだし」に眠ることになった。そこから数年後の今、協力者たちの力添えを得て、日之影石にようやく日が差した。
日之影町は、宮崎県の中でもっとも多くの鉱山が開発された地域である。このあたりは付加体起源の地質で、もともと石灰岩やチャートなど多彩な岩相。そこへ大崩山花崗岩類がモリっと貫入し、全体がこんがりと焼きあげられた。さらに無数の熱水脈が走ったことで、多種多様な鉱床と鉱物が生み出されている。こうした背景から、宮崎県の著名な鉱物産地はだいたいこのあたりに集中している[2]。下鶴鉱山もそのなかにある。ここは知名度こそ高くないが、バラ輝石や角閃石などが産出することで知る人ぞ知る産地であった[3]。もっとも、いま探そうとしているのはバラ輝石なんぞではないが。

このようにガマに浮いているバラ輝石の結晶や、数cmオーダーのへき開片が見つかる。この写真のバラ輝石は組成的にはフェロバラ輝石に該当する。
文献[4]によると、下鶴鉱山は南北数百メートルという限られた範囲にいくつかの鉱体があり、それぞれ特徴が異なるらしい。ラベルに記された鉱物名を手がかりに調査を開始した。現地にはこの地域の地層に由来するチャートや砂岩が多く見られたが、それに加えて、溶岩とも溶結凝灰岩とも判別しがたい岩石も混じっていた。それよりも肝心のマンガン鉱石はどこだ。マンガン鉱石は見慣れているはずなのに、どうも様子がおかしい。調査に同行してもらった後輩の田中崇裕もむやみにうろついている。やがて徐々に違和感の正体がわかってきた。なるほどな、派手に腐ってやがる。
ここでは、通常のマンガン鉱床ではあまり見かけないアラバンド鉱が、異常なほど多い。気が付いてしまえば、転がっている鉱石はほとんどアラバンド鉱からなっている。そして違和感の原因もこいつ。アラバンド鉱が風化によって硫酸を生じ、自ら崩壊しながら鉱石中に含まれていたケイ酸塩鉱物を表面に露出させてしまうのだと気が付いた。その結果、白色が悪目立ちする塊となり、一般的なマンガン鉱石とは異なる姿になっていた。そして、アラバンド鉱は酸に触れると硫化水素を発生させ、それによる強烈な臭気が鑑定の決め手になっている鉱物である。であるからして、鉱石を割ると、もうマジでほんとくっさい・・

一般的なマンガン鉱石は黒い皮膜ですっかりおおわれるので、こんなふうに白いということは基本無い。
アラバンド鉱は重量比で63%がマンガンを占めるため、数字だけ見れば高品位の鉱石に思える。だが残りの37%は硫黄であり、これは合金や製鋼の品質を大きく損なう厄介者として知られている。そのため、たとえマンガンの含有量が低くても、硫黄を含まないバラ輝石やテフロ石のほうが原料としてははるかに重宝されただろう。おそらく下鶴鉱山において、アラバンド鉱は採掘対象どころかゴミ扱いだったに違いない。だからこそ、ズリにはこれでもかと転がっているのだ。
しかし、私にとってそれは決してゴミではない。日本では、鉱物標本としてのアラバンド鉱は地味で微小なものしかない。だからこそ一塊まるごとがアラバンド鉱となると、それは日本でも屈指の存在感を誇る標本となる。なので、くっさいがゆるしてやる。そして石の全体としては脇役に過ぎないものの、少しだけ入っている白い部分こそが重要である。そこはケイ酸塩鉱物が主体となっており、そうした部分に加納輝石や日之影石が含まれる。まあバラ輝石やマンバンざくろ石であることのほうが多いのだが・・

表面に浮き出た加納輝石の結晶。アラバンド鉱が自壊し、浮き出た結晶は何だろうと調べたら加納輝石であった。ちなみに、加納輝石の同質異像にあたるドンピーコ輝石はこれまで調べた中では見つかっていない。
ということで、加納輝石や日之影石を得るには、まず足元に転がっているアラバンド鉱をてきとうに拾うところから始めればよい。その中にまぎれていることがある。とりあえずダメなものを挙げておくと、あからさまにアラバンド鉱が少なく、テフロ石だなと思える石。これはおそらく本当の鉱石で、少しこぼれたものがズリに残っている。しかし、これには面白いものはなにも無く、ほんとうにただのテフロ石。また、アラバンド鉱がリッチなものでも、割ってみて大きなバラ輝石のへき開片が見えようものなら、日之影石がいる可能性はきわめて低い。ただし加納輝石ならこうした石にも伴われるので、それ目当てならまあいいだろうか。角閃石が目で見えていると、これまた見込みはない。ほかにマンバンざくろ石が見えるが、こいつは誰とでもいっしょになれる八方美人なので、なんの目安にもならない。結局のところ、バラ輝石や角閃石が目立たない石が候補となる。だからといって外見で区別できるわけではなく、黒い石の中にわずかな白い部分が見える程度。それでも加納輝石なら風化面を探せば端正な結晶が見つかることがある。しかし、日之影石はそもそも微細かつ不定形な粒子のため、風化面に出ていてもマンバンざくろ石と区別できない。この地味さゆえに、これまでだれからも注目されることなく埋もれてきた。しかし今、それが新鉱物としてデビューを果たした。これが日之影石であり、手掛けた私にとっては愛着深い新鉱物なのである。



上の写真の白いところは加納輝石、中の写真だと日之影石が主体となっている。はっきり言って全然わからないので、もう分析するしかない。下の写真も日之影石。ちょといい機会だしこれは磊酒会にでも持っていこうかな。
このあたりで、日之影石がどういう新鉱物であるかをさくっと解説しておこう。日之影石(MnMgSiO4)は、テフロ石(Mn2SiO4)の二つあるマンガン(Mn)のひとつを、マグネシウム(Mg)に置き換えた鉱物で、かんらん石族に新たに加わったメンバーである。足立先生のラベルには加納輝石とともにテフロ石が記されていた。そして、このテフロ石こそが、後に新鉱物・日之影石として承認される存在だったのである。思えばこの標本は、師匠たちから弟子へ託された数十年越しの置き土産だったのかもしれない。弟子三人(浜根・田中・福本)はその置き土産を受け継ぎ、共同研究者たち(今井さん、永嶌さん、森さん、大西さん)の力を借りながら、新鉱物という形に結実させることができたのだった。
これはつまり。雨雲を払って差し込んだ「日の影」が三毛入野命を導いたように、長く眠っていた標本に光が差し込み、新鉱物が誕生した話でもある。その名に宿る神話とともに、この日之影石の発見の物語が、新鉱物を追い求める者たちにとっても道を照らす日の影となることを願っている。

上の二節の文章を読ませてChatGPTとGeminiに絵で出力させてみた。うーん・・・
[1] 足立富男(1997)宮崎県産鉱物一覧. 地学研究, 46, 131-149.
[2] 足立富男(1996)宮崎県西臼杵郡日之影町の鉱山. 地学研究, 45, 221-242.
[3] 藤本雅太郎(2006)宮崎県高千穂地方のマンガン鉱山産鉱物−その1下鶴鉱山−. 地学研究, 54, 213-221.
[4] 吉村豊文(1969)日本のマンガン鉱床補遺:後編 日本のマンガン鉱山. 九州大学理学部報告地学之部, 9, 487-1004.
IMA No./year: 2025-029
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53164)
堀石 / Horiite
Ba2Mn2Mn4Ti2(Si2O7)2(PO4)2O2(OH)2
Seidozerite supergroup
愛知県設楽町田口鉱山
Nishio-Hamane D., Nagashima M., Mori Y., Ohnishi M. Ishizaka T., Inoue S. (2025): Approved by CNMNC on July 04.

新鉱物・堀石の写真
濃いピンク色のバラ輝石塊にあらわれる、橙色を示す板状結晶が堀石。赤が濃すぎて黒く見えているところはパイロファン石。
愛知県田口鉱山からの新鉱物、堀石(ほりせき)である。しかし、この写真を見て「あれ?」と首をかしげた愛石家は少なくないだろう。このツラには見覚えが・・、そう、たしか、これはヘイトマン石ではなかったか?と。うん、まあ、そのとおり。実際にこの標本のラベルはヘイトマン石であった。しかしてその実態は・・、なんと新鉱物、というお話。こういう発見例はえてして偶然や幸運がもたらしたドラマチックな展開であることが多い。しかし、今回はそうではなかった。彼らはすでに知っていたのだ。そこに未知の鉱物が潜んでいることを。
愛知県は鉱物産地が豊富な地域とは言えないが、日本でも指折りの有名産地がいくつかある。例えば田口鉱山はその一つだろう。そこはマンガン山であり、明治の終わりごろから採掘が始まり、特に戦後は盛んだったらしい。鉱物標本としては、真っ黒なネオトス石に包まれた紅色のパイロクスマンガン石の美結晶が有名で、良いものは日本を代表する鉱物標本に名を連ねる。実際にこの田口鉱山のパイロクスマンガン石は「楽しい鉱物図鑑2(著:堀秀道)」でも紹介されており、立派な海外産標本が多くを占める同書のなかにあっても、ひけをとらない存在感を放っていた。図鑑を眺めながらこのパイロクスマンガン石に憧れを抱いた人は少なくないだろう。私自身、その一人だった。この図鑑は、私が初めて手にした鉱物に関する書籍であり、現在の自分を形づくるきっかけとなった特別な一冊でもある。

パイロクスマンガン石の写真。小さいが私にとっては価値のある標本。
私の研究テーマである新鉱物という視点からすると、田口鉱山は吉村石(yoshimuraite)の産地として注目に値する。吉村石は岩手県野田玉川鉱山産の新鉱物として1961年に論文が発表された[1]。そして、そのわずか2年後に田口鉱山からも産出が報告されている[2]。後年には原産地ではなく田口鉱山の吉村石を使用した研究で、理想化学式や結晶構造などの詳細が定義された[3]。つまり、実質的には、吉村石は田口鉱山の新鉱物なのである。田口鉱山の吉村石は黄褐色の鱗片状結晶で産出し、常に暗緑色の角閃石を伴うと記されている。この角閃石については論文ではリヒター閃石と述べられているが、後年に発表された分析値は、今の分類ではヤルマー閃石(hjalmarite)に該当する[4,5]。

論文に記されている産状と一致する吉村石(褐色)+角閃石(緑色)の標本。
その後、角閃石を伴わない吉村石の産出が、愛石家の中で徐々に知られるようになっていったようだが、並べてみると違和感を覚える(下の写真)。これらは同じ鉱物でいいのだろうか?と。そして1985年になり、同じではないと報告された[6]。序文には「バラ輝石を主体とする紅色の鉱石中に橙黄色透明板状の鉱物があり、従来吉村石と混同視されていたが、実は別の鉱物である」と記されている。これは堀秀道を筆頭とする研究チームの学会発表であった。

ヘイトマン石の標本
学会で発表されたヘイトマン石はこうしたツラをしていたと思われる。
研究チームはこの鉱物をバフェルチ石(bafertisite)のマンガン置換体に相当する新種とみなして、新鉱物申請を考えていたことが講演要旨から読み取れる。残されていたラベルから推測するに、「田口石」という名称が与えられる予定だったのだろう。しかし、結果として、田口石は実現しなかった。バフェルチ石のマンガン置換体はヘイトマン石(hejtmanite)と名付けられ、アフリカ大陸にあるザンビアからの新鉱物として、1989年にチェコスロバキア(当時)の研究チームが承認を得たのだった[7]。田口鉱山の未詳鉱物について以降の正式な発表は見られないが、やがて上の写真のようなツラをした鉱物はヘイトマン石として認知されるようになったと思われる。ヘイトマン石は後年に岩手県三根鉱山からも産出が報告されている[8]。
いわゆる田口石(=ヘイトマン石)はもしかしたら申請できなかったのかもしれない。実は、堀さんは田口石とは異なるもう一つの未知鉱物が存在することに気づいており、そのことをかつてある人物(パンダさんとしておく)に語っていたという。その話はやがてパンダさんから別の方(ソムリエさんと呼ばせてもらう)へ伝わり、未知の鉱物を含むかもしれないという標本がパンダさんとソムリエさんの二人から私のところへやってきたのだった。結果としてどちらの標本にも未知の鉱物(=新鉱物)が含まれていたが、決定的な分析結果が得られたのはパンダさんから提供された標本だった。そこで、この新鉱物に関するある重大な決定をパンダさんに委ねることにした。
このパンダさんこそ、堀さんと最も縁が深く、長年にわたってホリミネラロジーの番頭役を務めてきた井上真治さんである。そして、このたびの新鉱物の命名が、井上さんに委ねられた。こうして、新鉱物は、鉱物学者の堀秀道博士(1934-2019)にちなんで「堀石(学名:horiite)」と命名された。堀さんは5つの新鉱物の発見に貢献したほか、鉱物同志会の設立・運営や多くの書籍の出版などを通じて鉱物の魅力を広く伝え、直接的にも間接的にも多くの愛石家や鉱物学の後進を育成してきた。逝去後の命名となってしまったが、新鉱物「堀石」の誕生を通じてその事績を改めて思い起こし、共に祝ってもらえることを願っている。

新鉱物・堀石(模式標本)
ヘイトマン石とそっくりだが、これはまるまる堀石。
ここで情報を整理しておこう。田口鉱山からは、吉村石、ヘイトマン石、堀石が産出することが明らかとなった。これらはサイドゼル石超族のバフェルチ石族の一員であり、田口鉱山から産出するのはこの三種。組成や結晶構造はややこしいので具体的に解説しないが、おおざっぱに言えばこれらはサンドイッチのパンや具が異なる関係性だと思えばいい。であるからこそ、これらが混在することは想像に難くないし、実際にそうなることがある。下にいくつかの写真を並べるので、鉱物種や単独・混在・割合などを予想しながらみてほしい。紛らわしい別物もまぜてある。写真をクリックすれば答え合わせが書いてあるのでレッツトライ。












さて、どうだったであろうか? 紛らわしい鉱物として金雲母がある。堀石は単独で産出する場合もあるものの、ヘイトマン石と混在して産出することが多い。堀石と吉村石とはめったに共存しないようで、標本としてこれがそうだというものが無いので紹介できなかった。また、堀石とヘイトマン石は、単独か混在か、その量比にかかわらず、私には見た目で区別がつかなかった。しかし、このテストを通じて、見たらわかるという人も出てくるかもしれない。一方で、吉村石と堀石は、産状も見た目の印象も違う別物どうしであることが、簡単に見てとれる。ただし、これは私にとっては「なんで?」と首をかしげたくなるものであった。
というのも実は、吉村石と堀石の違いは、例えて言えばパンが同じで「具がハム4枚のサンドイッチ」と「具がハム2枚+サラミ2枚のサンドイッチ」くらいの差しかないので、見た目でわからないほどよく似ていると想像してしまう。一方の堀石とヘイトマン石の関係だと、「どちらもサンドイッチだけどパンも具材もその量も違う」くらいの差があるので、見ただけでわかりそうなものである。しかし、現実は逆。外観が共通で、食べ(調べ)てみなければわからないのは堀石とヘイトマン石の関係なのだから、不思議なものである。
田口鉱山は閉山して久しく、いまでは立ち入り禁止になっている。そのため、標本は採りに行くのではなく取引で手に入れるしかない。まあしかし、そんなに悲観したものでもない。それというのも、ヘイトマン石の標本は過去にそれなりに採集されているようで、売り立てなどをぶらつくとふつうに出てたりする。ミネラルマーケット2023の宣伝標本にもヘイトマン石があったな。これはすくなくとも吉村石には見えないので、堀石の可能性があるだろう。ただ、確実な同定は分析する以外にない。それはともかく、今回はヘイトマン石の標本を見つめなおすいい機会である。上のテストを参考にじっくりと観察しなおし、ラベルを書き換える必要があるかどうか検討してみてはどうだろうか。
[1] Watanabe T, Takéuchi Y, Ito J (1961) The minerals of the Noda-Tamagawa mine, Iwaté Prefecture, Japan. III. Yoshimuraite, a new barium-titanium-manganese silicate mineral. Mineralogical Journal, 3, 156-167.
[2] 広渡文利, 磯野清 (1963) 愛知県田口鉱山産の吉村石について. 鉱物学雑誌, 6, 230-243.
[3] McDonald A.M., Grice J.D., Chao G.Y. (2000) The crystal structure of yoshimuraite, a layered Ba–Mn–Ti silicophosphate, with comments on five–coordinated Ti4+. The Canadian Mineralogist, 38, 649-656.
[4] Shoda T., Bunno M. (1973) Optica rotation axes in a manganoan richterite from the Taguchi mine, Aichi Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 7, 159-168.
[5] Holtstam D., Cámara F., Skogby H., Karlsson A. (2019) Hjalmarite, a new Na–Mn member of the amphibole supergroup, from Mn skarn in the Långban deposit, Värmland, Sweden. European Journal of Mineralogy, 31, 565-574.
[6] 堀秀道, 宮脇律郎, 中井泉, 長島弘三, 松原聰, 加藤昭 (1985) 愛知県田口鉱山産Ba・Mn・Ti珪酸塩鉱物(予報). 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, P-8.
[7] Vrána S., Rieder M., Gunter M.E. (1992) Hejtmanite, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral. European Journal of Mineralogy, 4, 35-43.
[8] 鈴木保光 (2010)岩手県三根鉱山産ヘイトマン石. 地学研究, 58, 221-224.
IMA No./year: 2025-001 セリウム赤坂簾石 / Akasakaite-(Ce)
IMA No./year: 2025-002 ランタン赤坂簾石 / Akasakaite-(La)
IMA No./year: 2025-003 ランタンバナジウム赤坂簾石 / Vanadoakasakaite-(La) (2025-003)
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53012, 53013, 53014)
CaCe(Al2Mn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) : Akasakaite-(Ce)
CaLa(Al2Mn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) : Akasakaite-(La)
CaCe(V3+AlMn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) : Vanadoakasakaite-(La)
Epidote supergroup
群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Harada A. (2025): Approved by CNMNC on May 3.

これはランタンバナジウム赤坂簾石
群馬県茂倉沢から発見された新鉱物、赤坂簾石である。今回は3種まとめての申請・承認となった。具体的には、申請順から、セリウム赤坂簾石、ランタン赤坂簾石、そしてランタンバナジウム赤坂簾石である。また、これまではAkasakaiteを赤坂石(あかさかせき)と呼んでいたが、これからは緑簾石超族の鉱物には「簾」をつけて呼ぼうという案がでている[1]。これはざくろ石や電気石や角閃石の鉱物種と基本的に同じ扱いにしようということであり、特に反対でもないので、ここでもこれからは赤坂簾石(あかさかれんせき)と呼ぶことにしよう。ただし、過去の記事での呼び方はそのままにしておく(直すのがめんどくさい)。
今回は前回のフォローアップスタディであるからにして解説はあっさり行く。流れは前回のセリウムバナジウム赤坂簾石で書いたように、原田明氏が見つけてきた。基本的にはその試料をさらに調べているなかでの発見である。ではなぜ一つだけ早く、あと3種がちょっと遅れたのか。原因はそのやっかいな産状にあった。

赤坂簾石はこのようにことごとく石英に埋まっている。ここから一本の結晶をうまく取り出してやらないと、新鉱物申請に必要なデータを集めることができない。しかし、これ、どうやって取り出すよ?
ではそれでどうするかというと、とにかくツラがでるまで石をバンバン割る。単純に運まかせ。しかし、石英という固い壁に阻まれているとなると、これが実はもっとも合理的。運が良ければ一撃でケリが付くのだから。それで最初にうまくツラが出てデータが取れたのがセリウムバナジウム赤坂簾石であり、一足先の申請となった。ほか3種はなかなかいいツラがでない、またはそのものが見つからない、といったところで遅くなった。そして、今回の新鉱物も併せた合計4種の赤坂簾石を見つかる確率で並べると、ランタンバナジウム赤坂簾石>>>セリウムバナジウム赤坂簾石>ランタン赤坂簾石≧セリウム赤坂簾石、になっている。探せどもランタンバナジウム赤坂簾石ばかりに当たるという印象で、それ以外は非常に稀。とはいえ、ランタンバナジウム赤坂簾石だってそんなに簡単には見つからない。
赤坂簾石(Akasakaite)の名称をもつ鉱物は、最初がランタンフェリ赤坂簾石(2013-126)で、三重県伊勢市から見つかった。次が、ピーモント(イタリア)産のランタンマンガニ赤坂簾石(2017-028)とセリウムフェリ赤坂簾石(2018-087)で、それに茂倉沢鉱山産の4種が続く。今のところ、含まれる希土類元素はいわゆる軽希土類ばかりであり、重希土類を主成分とするものは見つかっていない。それでも、最初の発見から10年ちょっとでもう7種類。なんとも大所帯になったもので、ランタンフェリ赤坂簾石の時にはここまで拡大するとは思いもよらなかった。

矢印先の石英中に黒色で薄板状の赤坂簾石の結晶がたくさん埋没している。これは産状をよく示す代表的な標本として、山口大学に収蔵してもらった。これの一部拡大が、上に示した写真。
茂倉沢鉱山の赤坂簾石4種は、石英中に埋没した微細な薄板状の結晶として産出する。上の写真は産状が非常によくわかる標本で、今は山口大学においてある。なんぼたくさん見えていても、石英にがっつり埋まっているようでは個々の結晶がなんであるかを知る手段は割る・切る以外にない。それでもこういう産状や見た目であれば赤坂簾石であることは確かなので、とりあえず全部の名前を書いておくしかないだろう。ただ、4種類がいっぺんに含まれる標本があり得るかというと、なさそうと感じている。これまで見た中での手ごたえからするとあって2種類くらいだろう。また、こんなに結晶が群生していることはめったになく、せいぜい1-2本見えればいいところ。
さて、茂倉沢鉱山。昨年、今年でいまさら新鉱物が4種類加わって、合計6種類の新鉱物の産地となった。これで絞り切ったか。それともまださらに続くか。見落としは無いようにしたいが、さあどうなる。
[1] 松原聡 (2025) 日本産鉱物情報(2024). 岩石鉱物科学, 54, gkk.250328.
IMA No./year: 2024-056
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-52596)
アマテラス石 / Amaterasuite
Sr4Ti6Si4O23(OH)Cl
New structure type
岡山県新見市大佐山
Nishio-Hamane D., Nagashima M., Ohnishi M., Shimobayashi N. Matsumoto T., Tanabe M. (2024): Approved by CNMNC on November 02.

アマテラス石(黒緑色部)
ヒスイから見いだされた新鉱物、アマテラス石である。読んで字のごとく、名前は天照大神(あまてらすおおみかみ)からいただいた。鉱物名は地名、人名、化学組成、色、伝承とさまざまな由来を持ち、少ない例だが神様に由来する鉱物も存在する。日本の新鉱物では、海神(わたつみ)にちなむ「わたつみ石(Watatsumiite)」が知られていた。そして、「アマテラス石(Amaterasuite)」は2例目。それにしても日本の神は八百万である。そのなかにあって天照大神にちなんだ背景は、もちろんヒスイにある。
ヒスイは「翡翠(Jade)」とも書かれることがあり、日本語での発音は「翡翠」と書いて「ひすい」。しかし、「翡翠」と書いたとき、それは宝石として加工されたモノを指す、と、ここでは解釈する。また、翡翠は硬度の違いで「硬玉(こうぎょく)翡翠」と「軟玉(なんぎょく)翡翠」のように呼ばれる。それが略されて単に硬玉や軟玉と呼ばれたりするが、どっちにしろ翡翠。このように「硬玉」や「軟玉」はそもそも宝石に対する名称であり、それを鉱物学・岩石学用語として用いるのは本来は適切ではない(かつては使っていた)。そのため、近代の鉱物学や岩石学では内実に注目して言い分ける。例えば硬玉は、体積のほとんどがヒスイ輝石(Jadeite: NaAlSi2O6)という鉱物で構成されている。すなわち、硬玉は「ヒスイ輝石が主体の石」であって、それは鉱物学・岩石学用語の「ヒスイ輝石岩(Jadeitite)」である。そしてヒスイ輝石岩が、しばしば「ヒスイ」とだけ略される。よって、この記事でも「ヒスイ=ヒスイ輝石岩(Jadeitite)」のことだよと宣言して話を進めよう。軟玉の実質を言いたい場合はネフライト、もしくは透閃石-緑閃石岩と呼ぼう。

翡翠=宝石として加工されたヒスイ輝石岩や透閃石-緑閃石岩の総称であり、硬玉か軟玉かを問わない。
硬玉=宝石として加工されたヒスイ輝石岩のことで、とても硬く(ハード)かつ堅い(タフ)。
軟玉=宝石として加工された透閃石-緑閃石岩のことで、硬玉に比べると軟らかい(ソフト)が、堅さ(タフ)は硬玉に匹敵する。
ヒスイ輝石岩=ヒスイ=ヒスイ輝石が主体の石(岩石)のこと(加工の有無は問わない)。
透閃石-緑閃石岩=ネフライト=(緻密な)透閃石や緑閃石が主体の石(岩石)のこと(加工の有無は問わない)。
ヒスイは世界の各所に点在しているが、どこでも産出するというわけではなく、ヒスイの産出は造山帯(その痕跡を含む)地域に限定される。そして、日本列島はまさしくそういう場のひとつであり、やはりヒスイが産出する。これまでに糸魚川(新潟県)、若桜~関宮(鳥取県~兵庫県)、大佐山(岡山県)あたりで、まとまった量のヒスイの産出が確認されている。そして、日本のヒスイは地球上で最古のヒスイと言えよう。下の図に各地のヒスイがどのくらい古い時代にできたかを示しており、日本のヒスイは糸魚川や大佐山のもので5億7-6千万年前生まれだと報告されている。ロシア産のものがこれに匹敵する可能性がまだ残っているものの、いまのところ数値として報告されているものでは日本のヒスイはぶっちぎりで古い。ほかの地域のヒスイなぞ若造もいいところである。

世界のヒスイ産地と生成年代の概略図(文献[1-4]を参照)。「Ma」とは百万年前を意味している。例えば大佐山の570Maでは「570×百万年前」であり、5億7千万年前を意味する。
ヒスイは硬く(ハード)て堅い(タフ)という特徴を持つ。それはつまり加工が困難だがいったん製品を仕上げれば長持ちするという素材であり、石器として使うにはうってつけ。新潟県大角地(おがくち)遺跡から発見されたヒスイ製のハンマーは7000年前に作られたものだとされ、人類がヒスイを利用した最初の例だとされている[5]。また、ヒスイは白色だけでなく、鮮やかな緑、青、すみれ色、橙色、灰色、黒色までの多様な色調を呈するため、宝石の原石としての資質も持ち合わせる。やがてヒスイは石器だけではなく宝石(翡翠)としても珍重されるようになり、例えば硬玉の勾玉は縄文時代後期には作られ始め、様々な用途でヒスイの利用は奈良時代までざっと6000年間にわたって続いた。しかしそこで宝飾用途の利用はばっさりと断絶し、やがて国産のヒスイは忘れ去られた。
以後、1938年(昭和13年)に糸魚川でヒスイが再発見されるまでの1200年間、日本にヒスイの産地があることは誰も知らない状況が続いた。しかし、再発見されたということはヒスイの産出が現代まで継続していたことを意味しており、地元の人はヒスイと知らないまま漬物石として使っていたとも聞く。ともかく日本は世界最古のヒスイ文化発祥地であり、縄文時代以降の7000年間にもわたってヒスイは日本人の文化や生活にかかわってきた。ヒスイを原石に加工された硬玉は日本産の宝石として最上位に位置し、それは考古学的にも重要なアイテムであるように、ヒスイは鉱物学だけでなくほかの学術分野でもインパクトをもつ存在である。そして、2016年に日本鉱物科学会はヒスイを「国石」として選定した。2017年には日本鉱物科学会が発行する英文誌でヒスイにまつわる特集号が組まれ、万葉集3247番[6]を引用した英訳から、序文には「Gem sparkles deep」というタイトルが付けられた[7]。日本政府広報のオンライン雑誌「Highlighting Japan」においても、2021年10月号で国石としてヒスイが紹介されている[8]。

国石・ヒスイ
海岸や川に流出したヒスイ(左)は表面が常に更新されるのでツルツルだが、山で埋もれたヒスイ(右)はひたすら風化されるだけなので、表面はざらざら。
そんなヒスイは、実は新鉱物探査の対象としてもなかなか魅力的である。これまでに、ヒスイおよびその関連岩から、青海石(Ohmilite, 1974-031)、奴奈川石(Strontio-orthojoaquinite, 1979-081a)、糸魚川石(Itoigawaite, 1998-034)、蓮華石(Rengeite, 1998-055)、松原石(Matsubaraite, 2000-027)、新潟石(Niigataite, 2001-055)が新鉱物として見つかっている。これは一連の岩石からの発見としては多いほうだろう。いずれも糸魚川地域から発見された。2001年から現在まではヒスイから新鉱物発見の報告が無かったのはちょっと意外だが、その間にヒスイには国石という箔がついた。そうなると、国石であるヒスイから次に新鉱物が発見されたらどう名づけるべきか、どんな名前がふさわしいか。そんな皮算用をしながら、いずれは自分がヒスイから新鉱物を見つけてやろうと思っていた。そして、見つけた。

アマテラス石(中央から下と左側に広がる黒緑色部)。
中央の褐色はルチル、そこより上に広がる淡緑色部はチタン石、アマテラス石の周りのあんず色の粒はタウソン石。
さて、国石・ヒスイから発見された新鉱物か。セオリーで考えると、人名についてはヒスイ関連の研究者が幾人か思い浮かぶ。国石という箔もあるので皮算用の段階では人名はふさわしい候補だと思っていた。ただ、今回の新鉱物は結晶構造に二面性があった。これは想定外。内部に二面性があるものに人名を付けたとなると、誤解を招きそうで気が引ける。ピッタリだと言われてもなお困る。では逆に二面性にあやかるのはどうか。その方向性でローマ神話の双面神(ヤヌス)というアイデアが出た。が、日本産でローマか。地方・地域名もいつもなら有力候補だが、今回はこれらでは力不足というか荷が重いというか。それならばと国石を前面に押し出して「日本石」も考えたが、いまひとつしっくりこない。そんなこんなで今回は名前がなかなか決まらなかった。
いっそ全部込みはどうか。日本を連想させ、国石という字面のいかにもな雰囲気にも負けず劣らず、おまけに二面性を併せ持つもの。無茶ぶりのようだが該当するものがある。それは神様、それもビックネームの。そうして、天照大神が候補に挙がった。天照大神は日本神話の中で最も重要な女神の一人であり、荒魂・和魂という二面性を持ち合わせる。このアイデアには当初は戸惑ったが、だんだんと国石・ヒスイからの新鉱物としては良いかなと思えてきた。そうして「アマテラス石」が採用された。新鉱物の申請書を提出した際、新鉱物・命名・分類委員会の委員長からは「Nice Name!」と心強い一言をもらい、審査を経てアマテラス石は正式に承認された。学名はAmaterasuiteと書いて「あまてらすあいと」と発音する。私は「アマテラス石」とカタカナで書いているが、漢字を当ててもいいだろう。ちなみに、観測史上2番目の超高エネルギー宇宙線にも天照大神の名が採用され、「アマテラス粒子(Amaterasu particle)」と名付けられている[9,10]。
端緒を思い出してみると、当初は大佐山のヒスイを切る角閃石が気になるという話だったと思う。2020年の暮れの磊酒会だったかな? ともかく田邊満雄氏からそんな相談があった。その角閃石はとりわけ希少というわけでもないエデン閃石という結果に落ち着いたが、それよりも角閃石と共に大量に伴われているルチルがただものではなかった。一見するとただのルチルでしかなく、その周囲が淡緑色のチタン石で囲まれていることもしばしばというくらいで、これはいわゆる普通の範囲内だったが、中身に驚いた。切ってみると松原石(Matsubaraite: Sr4Ti5O8(Si2O7)2)とタウソン石(Tausonite: SrTiO3)がいくらでも出てくる。続いて蓮華石(Rengeite: Sr4Ti4ZrO8(Si2O7)2)も見つかった。松原石は世界でも二番目の産出で、蓮華石やタウソン石も含めてこれらはこれまでは糸魚川ヒスイだからこそのような鉱物だったが、ちゃんと見てやれば大佐山にこそいっぱいあるじゃないか。

ヒスイを切るエデン閃石とたくさん含まれるルチル
こういう産状のルチルは松原石をはじめ様々なストロンチウム鉱物を含んでいる(とても小さいのが玉に瑕だが)。
さらに検討を進めると未知の鉱物がいくつも検出された。その一つがアマテラス石で、ヒスイの変質が進んだ個所ではアマテラス石がルチルの外側に張り出していることが分かってきた。そのためアマテラス石の存在は、特に切断面では見たらすぐわかるのだが、結晶一つ一つはとても小さく結晶外形もまともに観察されずで、これには困った。構造データを収集するため良い結晶がなかなか見つからず、相当量の試料を消耗しながら長い年月をかけて検討が繰り返され、今年になってようやく日の目を見た。明らかとなったその結晶構造は前述したように二面性があって、解析を担当した山口大の永嶌さんをもうならせた(困らせた)ほどの面白味があるのだが、その詳細は論文で書くことにしよう。ここではアマテラス石の特徴を述べたい。


アマテラス石をまとうルチルの切断面
ルチル(濃褐色)の周囲に生じた黒緑色がアマテラス石で、その周りにあんず色のタウソン石が散らばる。
アマテラス石の産状はおもに二つで、角閃石を伴うヒスイ中のルチルに含まれるものと、角閃石が変質して生じた緑泥石のルチルの周りに生じるものがある。前者の場合、ほとんどすべてのルチルにアマテラス石が含まれ、松原石、蓮華石、タウソン石、さらに未命名鉱物もてんこ盛りで含まれるという状況になっている。ただし、それらはすべて電子顕微鏡でしか認識できないほど小さくせいぜい10μm程度。そうなると確実に入っているとは言えども見たところでわからないので、標本とするにはちょっと頼りないと感じるかもしれない。とはいえ含まれているのだからラベルを書くこと自体は良いだろう。それよりはっきり存在を認識できるものが、変質岩中のアマテラス石である。これはルチルの周囲に生じたもので、肉眼的には黒緑色を呈する。破断面や切断面ではその存在はよりくっきり浮かび上がるが、結晶が認識できることは稀で、微細な針状から毛状のものがなんかむにゃむにゃしてるなと感じる程度。この産状ではアマテラス石は基本的にはチタン石と入り混じっていて、アマテラス石の濃度は実はあまり高くないことがほとんど。そのため、薄片にしても多くの場合でアマテラス石の姿はあまりはっきりと捉えられない。ただし、ごくまれにアマテラス石が高密度にあつまるものがあり、そうしたものを薄片にすると強烈な多色性が観察できる。

薄片で見るアマテラス石(ルチルをぐるっと取り囲む)
アマテラス石は多色性が非常に強く、偏光顕微鏡下では紺色から橙色まで変化する(左右で偏光板を90°回転して撮影)。
これまでヒスイからの新鉱物はすべて糸魚川ヒスイから誕生していたが、このたび初めて大佐山ヒスイから新鉱物が生まれた。そうなると捲土重来というかなんというか、アマテラス石に関しては糸魚川ヒスイはお呼びでない状況になるのかなと思っていたのだが、そんなこともなかった。自分の標本のことになるが、糸魚川市青海海岸から得られたヒスイにも、ごく少量ながらもアマテラス石が存在することを確認している。具体的にはヒスイに含まれる松原石に伴われる。若桜のヒスイはモノがないので調べようがないが、大佐山だけでなく糸魚川からも産出を確認できたということは、アマテラス石は国石・ヒスイを象徴する鉱物としてよりふさわしくなっただろうか。

アマテラス石を伴う松原石(糸魚川ヒスイ中)
電子顕微鏡でしか確認できないほどの微量だが、アマテラス石は糸魚川ヒスイからも産出する。
[1] Harlow G.E., Tsujimori T., Sorensen S.S. (2015) Jadeitites and plate tectonics. Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences, 43, 105-138.
[2] Jadeitite (jadeite jade) from Japan: history, characteristics, and perspectives. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 112, 184-196.
[3] Kunugiza K., Nakamura E., Goto A., Kobayashi K. Ota, T., Miyajima H., Yokoyama K. (2017) In–situ U–Pb zircon age dating deciphering the formation event of the omphacite growth over relict edenitic pargasite in omphacite–bearing jadeitite of the Itoigawa-Omi area of the Hida-Gaien belt, central Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 112, 256-270.
[4] Fu B., Valley J.W., Kita N.T., Spicuzza M.J., Paton C., Tsujimori T., Bröcker M., Harlow, G.E. (2010) Multiple origins of zircons in jadeitite. Contributions to Mineralogy and Petrology, 159, 769-780.
[5] 加藤学,杉田和弘,近藤慎子,相羽重徳,松永篤知 (2006):大角地遺跡 北陸新幹線関係発掘調査報告書V, pp. 85, 新潟県教育委員会, 新潟.
[6] 原文は「沼名河之底奈流玉求而得之玉可毛拾而得之玉可毛安多良思吉君之老落惜毛」であり、現代語訳では「沼名川の底にある玉、探し求めて手に入れた玉よ、拾ってもっている玉よ。その如く大切なあなたの老いてゆくのが惜しいよ。(https://manyo-hyakka.pref.nara.jp/db/detailLink?cls=db_manyo&pkey=3247)」。この歌が現代でのヒスイの再発見につながった。
[7] Tsujimori T. Miyajima H., Miyawaki R. (2017) Gem sparkles deep: Preface of the special issue on ‘Jadeite and jadeitite’. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 112, 181-183.
[8] https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202110/202110_02_en.html
[9] Telescope Array Collaboration (2023) An extremely energetic cosmic ray observed by a surface detector array. Science, 382, 6673.
[10] 藤井俊博(2024)天与の加速器からの「アマテラス粒子」の検出. 高エネルギーニュース, 42 (4), 151-158.
IMA No./year: 2024-044
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-52312)
セリウムバナジウム赤坂石 / Vanadoakasakaite-(Ce)
CaCe(V3+AlMn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Epidote supergroup
群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Harada A. (2024): Approved by CNMNC on October 3.

セリウムバナジウム赤坂石
群馬県桐生市茂倉沢鉱山からの新鉱物、セリウムバナジウム赤坂石である。そう、またグンマー、そして桐生市。桐生市では新産地にあたる梅田町の山中から桐生石と群馬石が見つかったかばかりだが、今では古典産地となった菱町茂倉沢鉱山のほうから新鉱物が今さら見つかった。申請ベースでみると、1977年に長島石が、1978年に鈴木石が見つかっており、今回の新鉱物は茂倉沢鉱山からは46年ぶりとなる。私の人生がすっぽりその空白期間に入ってしまう。一つの産地において新鉱物の発見に何十年も間が空くことは、なくはないが、やっぱり珍しい。例えば浅葱石のように二次鉱物ならばそのくらいの時間がむしろ必要なのだろう。しかし、今回は二次鉱物ではない。それなのに今さら新鉱物が見つかったということは、何があったというのだろう。
これも磊酒会(らいしゅかい)の席だったか。原田明氏の立て板に水ような話しっぷりに対して、その8割くらいを右から左へ流していくなかで「黒色の板状結晶が・・」という言葉がめずらしくひっかかった。ああ、それはたぶんアレだ。マンガン鉱床にはいろんな鉱物が出るが、経験がないと思い至らず考え込んでしまうものがある。例えば褐簾石はその好例かもしれない。褐簾石は意外にもマンガン鉱床にも顔を出す。ただ、以前はマンガン鉱床からの褐簾石はあまり知られていなかったので、古参ほどかえって知らないかもなと思いつつ「褐簾石」という予想が浮かんだ。しかし、それを口に出すよりも早くほかの話がぐわわっと押し寄せてきて、気がついたら余計なものをいろいろと詰め込まれた標本を受け取っていた。

栃木県鹿沼市横根山鉱山のバラ輝石・菱マンガン鉱に伴われる褐簾石
これは古参コレクターが褐簾石とは思わずに保管していた標本。この標本は褐簾石シリーズの中でもっともありふれたセリウム褐簾石であった。
後日に標本を観察するとそれはやっぱり褐簾石に見えたが、ラベルには茂倉沢鉱山と書いてある。はて、茂倉沢? 茂倉沢鉱山は多くの人が知っているように長島石や鈴木石の模式地である。これまで茂倉沢鉱山から褐簾石は聞いたことがなかった。ただ、岩手県田野畑鉱山では長島石・鈴木石に加えて褐簾石が産出したという報告がある[1]。そうなると茂倉沢のこれも見た目どおりの褐簾石か、はたまた褐簾石ぽく見えるだけの別物か・・。
それから少しして、我々は茂倉沢鉱山に向かって車を走らせていた。道中の会話の内容は9割ほど記憶から抜けている。が、まあいいや。今回は新鉱物申請にあたり産地の現状を確認することが目的である。くだんの標本には新鉱物だけでなく、日本では初めての産出となる鉱物も含まれていたのだった。なんといってもここは古典産地。長島石や鈴木石が発見されてから今日までに半世紀ほどにもなり、その間に訪れた愛石家は数知れず。すでに沢の下流から上流まで総ざらいされ、あげく「もうなにもないよ」という捨て台詞まで聞かされるのが定番の産地。そんなところから今さら新鉱物や新産鉱物が見つかるのだから、未発見の鉱床に行きついたか、現地の様子に大きな変化があったとでもいうのだろうか。念のため見ておかねばなるまい。
茂倉沢鉱山にたどり着くまでは杉林。それにしてもなぜ岩の真上に植えた? それで立派に成長しているのだから逞しい。その生命力よろしく花粉も大量に舞い散っている時期だったが、深呼吸をしてもいまだなにも感じない。鉱山までに転がっている石や露頭はほとんどがチャート。これはおもしろくないので、たどり着く先に期待したい。茂倉沢鉱山にはいくつかの鉱体があるようで、未知の場所が開拓されたのかと思いきや、案内されてたどり着いてみれば現場は昔からよく知られている南入坑。坑道はいくつかまだ空いており、テラスとなっている個所から下の斜面がズリ場。大水が出た痕跡もなく、経年変化でズリ場が崩れているだけ。なにもかも過去からたいして変わっていない。それなのに今日まで報告がない鉱物がここにきて見つかった。やっぱりこれは・・・。

岩の真上に植えてある杉
岩の直上に生えている杉は屋久島でよく見かけたが、それは屋久島ならではの多湿+苔という環境だからこそ可能という説明だった。しかし、ここグンマーでも普通に生えていた。植えた後に表土が剥げただけかもしれないが、それでも立派に成長するとはたくましい。
ある産地で新鉱物もしくは珍しい鉱物が発見されてしばらくたつとどうなるか。実はこれも定番で、よく似た全く別の鉱物があるかもという発想が出なくなる。それどころかいつしか盲目的になり、多少の違和感があってもこれはきっとあの鉱物だと決めつけてしまう。結果的に真相に迫る機会は失われる。しかし、そういう事態になっていることにだれも気が付かないのだからめったに表ざたにならない。そして、ようやく話が表ざたになったとき、それはたいてい手遅れの報告としてケリがつく。例えば御斎所鉱山のヒ酸塩鉱物(ミゲルロメロ石、カステラロ石、コラロ石)なんかはその典型例だと思う[2]。これらは別の名前で呼ばれている間に海外産のものが新鉱物になっていた。今回もそうなりかねないところでまずはひとつ間に合った。本題に入ろう。まずは茂倉沢鉱山を代表する鉱物から見ていこう。

長島石(Nagashimalite: Ba4(V3+,Ti)4(O,OH)2[B2Si8O27]Cl)
長島石は長辺に沿って条線の入る板状の結晶として産出し、その板が何枚も積み重なった姿にもなる。細ければ針状にも見えるかもしれないが、拡大してよく見れば結晶の形はやっぱり板状。クラックが入りやすく、クラックの多い結晶は濁ってみえる。大きな結晶ほど黒色に見えるが、貧弱な結晶はかなり緑色が強い。この結晶も遠目には黒色だがところどころで緑色が透けている。バラ輝石、石英、菱マンガン鉱などに埋もれて産出する。

鈴木石(Suzukiite: BaV4+Si2O7)
鈴木石は板状の結晶が本来の姿だと思われる。ただ、いつも小さいためにルーペでの観察では粒状にも見えてしまう。いずれにせよピンクのバラ輝石塊の中にある鮮やかな緑色は小さくとも非常によく目立つ。しかし、緑色を追いかければ良いというものではなく、アラバンド鉱や緑マンガン鉱なども割ってすぐだと案外ギクッとなる。ただそれらは冷静に眺めると違うとすぐわかる。一方で、ここではくそ紛らわしいヤツが存在している。それは二ム石(Nimite: (Ni,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8)と言って、簡単に言うとニッケル(Ni)を主成分とする緑泥石。これはルーペ程度では見分けがつかないほど鈴木石によく似ている。しかし、よく見れば鈴木石にはパリッと感があるのに、ニム石はちょっとズルッとしている。また、二ム石のそばには針ニッケル鉱(やや太い)がいることがあり、それらが見分けるポイントになるだろう。

ロスコー雲母(Roscoelite: KV2(Si3Al)O10(OH)2)
ロスコー雲母は茂倉沢鉱山を代表する鉱物のひとつで、「青のり」と称されるように緑色のペラペラ。石英やバラ輝石の隙間にいることが多く、たまに脈状にも分布する。いずれにしても出てくればその特徴からすぐわかる。わりと厚めの結晶もあって、六角板状で深い緑色はさすがに青のりとは言えない。そして、こういう結晶はまわりや内部にセルシアン(Celsian: Ba(Al2Si2O8))をたっぷり伴っている。当然ながら、ロスコー雲母もバリウム(Ba)をかなり含む。そして、部分的にはバリウムがカリウム(K)を完全に置き換えており、そこはもはやロスコー雲母ではなくチェルニフ雲母(Chernykhite: BaV2(Si2Al2)O10(OH)2)であった。ただ残念ながら一つの結晶がまるまるチェルニフ雲母ということにはならないようで、チェルニフ雲母は今回は補欠。
さてと。茂倉沢鉱山を代表する鉱物である長島石・鈴木石・ロスコー雲母はバナジウム(V)を主成分にもつことが特徴で、それらをまとめてV3(ブイスリー)と呼ぶことがある。誰が言い出したのかわからないが、時代的に仮面ライダーV3がよぎったのかもしれない。それはそれとして、バナジウム鉱物と言えば東京都白丸鉱山もまた有名で、2024年は白丸鉱山が久しぶりにダム湖から顔を出したために多くの愛石家が沸き立っていた。おそらくバナジウム鉱物の出現を期待してのことだろう。しかし、ほとんど同じタイミングで、白丸の喧騒をよそに、もはや訪れる人の少なくなった古典的な茂倉沢鉱山のほうから新たなバナジウム鉱物が見つかっていたのだった。では、茂倉沢鉱山の新V3メンバーを紹介していこう。

マンナード鉱(Mannardite: Ba(Ti6V3+2)O16)
新V3メンバーのひとつ目。マンナード鉱はマンガン鉱床ではわりと見かけることのあるホランド鉱(Hollandite: Ba(Mn4+6Mn3+2)O16)のチタン(Ti)と三価バナジウム(V3+)の置換体にあたる。長島石がバリウム(Ba)、チタン、三価バナジウムを含むように、環境的にはマンナード鉱が出てきて全く不思議ではない。特徴をまとめてみたい。結晶は棒状で、ほうきのような束状結晶をなすことが多い。へき開は感じられない。出てくる場所はバラ輝石や石英中。産状としては長島石と共通だが、よく見ると色や姿かたちは長島石とはすこし異なる。特に色。色は完全に黒色で、緑色はかすりもしないところが長島石と見分けるポイントとなる。しかし、長島石だと言われると納得してしまいそうな雰囲気がある。これまでマンナード鉱の産出報告がなかったのは、長島石と誤認されていたからであろう。それでもいったん気が付いてしまえばわりといろんな姿で産出することが分かった。産出頻度は長島石よりずっと高い。下にマンナード鉱の別の産状も載せておく。

ロスコー雲母(青のりみたいなやつ)に突き刺さるマンナード鉱(黒色の束状集合)。

針状結晶がほうき様に集合したマンナード鉱(石英中に埋没)。毛鉱に見えたがそうではなかった。
マンナード鉱は1983年に新鉱物として承認されたカナダ産の鉱物である。長島石は1977年だから、その6年後。存在に気が付けば茂倉沢の新鉱物になる可能性はあったのだろう。しかし長島石があったから、または毛鉱にしか見えないから誰も気が付かなかった。長島石やマンナード鉱の主成分であるバリウムとバナジウムは割と仲が良く、その二つを含む鉱物は今では20種類ほど知られている。多くの産地で数種類が産出するのがふつう。そして、茂倉沢でもさらなるバリウム・バナジウム鉱物が隠れていた。それが新V3の二番手、ゾルタイ石。

ゾルタイ石(Zoltaiite: BaV4+2V3+12Si2O27)(黒色部)。緑色はロスコー雲母。
ゾルタイ石は2003年にカナダから発見された。茂倉沢でのゾルタイ石は黒色で不定形ながらもやや棒状に伸びた姿となり、石英に埋没して産出する。長島石やマンナード鉱のようなパリッとさがなく、どことなくズルんとした印象。長辺でも1ミリ以下だったがルーペがあれば見える。針で触ってみたがへき開はあまり感じられない。また、周りのロスコー雲母はともかく、ゾルタイ石にはやはり緑色みが欠け、ただ黒い。しかし、これも貧弱な長島石として誤認されてきただろう。くりかえすが、長島石は緑色である。それなのにただ黒い結晶ということは、長島石ではないことを意味している。小さいとはいえそういった違和感に気が付けばこれもまた茂倉沢産の新鉱物になり得たのだろうが、まあしょうがない。ここまでは手遅れの話。しかし、今回、幸運にもまだ残っていた。それが新V3のラスト、新鉱物・セリウムバナジウム赤坂石であった。

セリウムバナジウム(Vanadoakasakaite-(Ce):CaCeVAlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH))
新V3のリーダー、新鉱物・セリウムバナジウム赤坂石である。長辺に条線が入る板状結晶で、遠目には黒色だが、ルーペや顕微鏡で観察すると茶色を帯びていることがわかる。へき開がほぼなく、割れ口は貝殻状になりやすい。これが花崗岩から出ていれば多くの人が褐簾石と判断するだろう。しかしここはマンガン鉱床。マンガン鉱床の褐簾石を知らなければこれも長島石と思うのは致し方ないかもしれない。それでも、注意深く観察すれば赤坂石のほうには緑色は感じられないことや、割れ方がまったく異なることが判別の手掛かりになる。赤坂石は小さく、岩石中の濃度もかなり低い。入っている場合でも握りこぶし大のバラ輝石塊の中に1ミリ以下の結晶が数本ある程度で、そういう塊を数センチ以下にまで全部ばらしてもその数本以外は入っていなかったりする。いまのところ赤坂石がほかのバナジウム鉱物と接することは確認できていない。なぜかひとりぼっち。そのため目印があまりない。あえていうなれば母岩に注目したい。バラ輝石が母岩ではあるが、バラ輝石だけの塊は赤坂石の期待値が低い。バラ輝石だけだと鈴木石や長島石が来ることはあっても、赤坂石はちょっと見たことがない。バラ輝石塊が石英を噛むことが重要。それに加えてバラ輝石は粗粒な方が良い印象。こういう鉱石について、一発割って何か見えなくとも、数センチ程度までは期待を持ってバラしていく。赤坂石は結晶が2-3個見えればそれが最上の標本。一本だけぽつんと入っていることもしばしばあるので、見落としに注意したい。ともかくじっくり観察して探す以外の方法はない。しかし、それにもまして今持っている長島石標本の再観察もやはり必要だろう。それは本当に長島石ですか? 緑色が感じられるか否かでラベルを変えなくてはならない。また、茂倉沢鉱山に限ったことではないが、良標本を採集するたびに古いものとはすぐさまお別れする人がいる。長島石の場合でもその例を耳にした。そうする場合でも別れを惜しむように最後にじっくり観察することをおすすめする。お別れしようとしていたそれが、実は新V3、今回の補欠、またはさらなる追加メンバーになるかもしれない。茂倉沢鉱山の鉱物種は今また改めて調べなおす必要が出てきており、まだ新鉱物候補が眠っていることを確信している。ただ、それらを形にできるかどうかはまた別の問題。
今回の新鉱物が赤坂石の系譜に連なるものだとわかったとき、頭に浮かんだのは山口大の永嶌さんだった。伊勢での前例もあったことだし、筆頭でとりまとめてくださいとお願いして引き受けていただいた。また、このたびは原田氏のお手柄である。もうなにもないと言われたところからの大どんでん返しで、新V3の発見に至った。原田氏は今回の白丸鉱山にもちゃっかり顔を出しているようにわりと無節操で、いつも本筋から逸れがちで、ついでに話が長いことが困りものだが、なにはともあれ、セリウムバナジウム赤坂石は原田氏にとっての初めての新鉱物。ひとまずはおめでとう。それにしても白丸か。今回は行かなかったが、でもなぜか「白丸」にたどり着いたな。
茂倉沢鉱山を出て桐生市内で忠治漬をお土産に買ったあと、飯でも食って帰ろうと佐野を経由した。ただ、ちょっと時間帯が早かったのだろう。佐野ラーメン店はことごとく営業時間外。そして、町をさまよいながら佐野厄除大師を通り過ぎて右折した先にあったのは、佐野ラーメンではなく、博多ラーメンの一風堂(営業中)。この地に出店するとはいい度胸だ。もうたまらん。腹ペコの我々は迷うことなくそこへ入り、お互い「白丸」に舌鼓を打った。それからの帰りの会話は10割おぼえてない。
[1] 宮島宏, 松原聰, 宮脇律郎, 横山一己, 石橋隆(2002)岩手県田野畑鉱山産含V珪酸塩鉱物. 日本鉱物学会創立50周年記念年会講演要旨集, KA-07.
[2] 浜根大輔, 鈴木保光(2018)福島県御斎所鉱山産含水ヒ酸塩鉱物の再検討. 日本鉱物科学会2018年年会講演要旨集, R1-P09.
IMA No./year: 2024-003
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-51975)
イットリウム宮脇石 / Miyawakiite-(Y)
□Y4Fe2(Si8O20)(CO3)4(H2O)3
New structure type
福島県川俣町飯坂水晶山
Nishio-Hamane D., Momma K., Shimobayashi N., Ohnishi M., Kobayashi T. (2024): Approved by CNMNC on May 3rd.

宮脇石の写真
福島県水晶山からの新鉱物、宮脇石である。これは小林寿宣氏が見つけてきた。彼は水晶山から産出する鉱物種の全貌を明らかにすることをライフワークとしている。その活動の中で、まずは1999年に不明鉱物が採集される。それは後に岩代石(Iwashiroite-(Y): YTaO4)と名付けられ、「水晶山産」ということが論文の題目に明記された初めての新鉱物となった[1]。その後、彼はまたしても正体不明の鉱物を見つけてしまったようだ。それをどうしようかと相談を受けて今ここでの話につながる。そのころ彼とは神田の「ぼたん」で定期的に開催される、磊酒会(らいしゅかい)と銘打った飲み会で隣席する仲になっていた。そういえば、初めて顔を合わせたとき尋ねられたのは「あなたのフィールドはどこですか?」だったかな。
ちょっと自分のやってきたことを改めて思い返してみよう。そうするとやはり偏りが見えてくる。例えば自分の新鉱物を産状別でカテゴライズしてみると、正直、ペグマタイト鉱物には縁が薄い。この相談があった時点ではペグマタイト鉱物は高縄石たったひとつだけだった(のちにベタフォ石が加わったけど)。それから、これまで二次鉱物の新鉱物も何個かあるが、伊予石・三崎石以外はかなりの受け身仕事。積極的に手を出していない。その理由はシンプルで、実は二次鉱物を調べるのが苦手。そして、今回のブツはペグマタイト鉱物かつ二次鉱物。あー・・これは不得手の詰め合わせセット。弱ったなぁ・・というのが本音だった。それでも周りから協力を得てどうにかなってしまった。これはまさに私の人徳のたまもの! ではなく、それがあるとすれば鉱物名の由来の方です。

岩代石(Iwashiroite-(Y): YTaO4)
水晶山からの新鉱物としては阿武隈石、飯盛石、プロトフェロ末野閃石に次ぐ発見だったが、論文のタイトルに「水晶山産」と明記された新鉱物は岩代石が最初。結晶構造は宮脇先生によって明らかにされた。
国立科学博物館の宮脇律郎先生は希土類鉱物の結晶化学を専門にしており、その業績で日本鉱物科学会賞を受賞された。それだけでなく、多くの新鉱物の記載にも携わり、新鉱物・命名・分類委員会(CNMNC)の国際委員長に就任し、その任期中に並行して日本鉱物科学会の会長職を勤め上げるなど、鉱物学へ多大な貢献を果たしている。また、CNMNCの歴代の名誉委員長はことごとく新鉱物へ献名されていることもあって[2]、宮脇先生もそうなるべく適切な新鉱物を探していたが、希土類という縛りのもとではかなり難易度が高い。どうしようかと悩んでいた中で小林氏からの相談。これはもしかして千載一遇かも。その旨を伝えて共著者の方々へ協力を依頼し、このたび無事に承認された。おめでとうございます。正式名称はイットリウム宮脇石(Miyawakiite-(Y))と言い、イットリウム(Y)という希土類元素を主成分にもつ鉱物である。
水晶山は阿武隈高地の北西部の丘陵地帯に位置する川俣町の中にあり、全体がペグマタイトで構成されている。この辺りではもっとも規模の大きいペグマタイトだったようで、水晶山ではかつてガラス原料や製鉄用として石英や長石が盛んに採掘されていた。第一水晶山や第二水晶山をはじめ計5つの鉱体がある[3]。また、こういうペグマタイト鉱山には希土類鉱物がつきもので、黒雲母の平板からにょきにょきとタケノコのように生えるフェルグソン石の結晶は水晶山の特産として古くから著名。ほかにも飯盛石や阿武隈石の産出が古くから知られ、わりと新しい知見としてはイットリウムを主成分とする褐簾石やカイシク石などがある[4]。しかし、これらは鉱山からしてみれば商品である石英や長石を汚すゴミだったので、かつてはズリ場(くず石を捨てた場所や斜面)にてきとうに捨てられた。鉄かんらん石も同じ扱いでズリ場に転がっており、それには角閃石が含まれる。その角閃石は後に新鉱物であることが明らかとなり、最終的にプロトフェロ末野閃石と名付けられた[5,6]。鉱物探査という観点ではズリ場はむしろ魅力的な場だったりする。宮脇石もズリ場から採集された。

飯盛石(Iimoriite-(Y): Y2(SiO4)(CO3))
飯盛石の模式地は二つあり、一つが水晶山。発見された当初は塊状のものばかりだと思われていたが、後年にこのような結晶が見いだされた。塊状標本は長石とものすごく似ていて困るが、結晶なら長石とは全く異なる姿になる。

プロトフェロ末野閃石(Proto-ferro-suenoite: □Mn2+2Fe2+5Si8O22(OH)2)
水晶山産の新鉱物だが、そのことが論文にちょっとしか触れられていないので知らない人も多いかもしれない。良し悪しや大小を問わなければここの鉄かんらん石にはわりと普通に伴われている。名称は今でこそプロトフェロ末野閃石と定まっているが、そうなるまでに長い年月がかかり、紆余曲折もあった。
「日本希元素鉱物」[7]によれば、水晶山は大正初めごろに山頂付近の露天掘りから採掘が始まり、徐々に坑道掘りへとなったとされる。その露頭掘り跡は今では断崖なので近づかないほうがいい。そのあたりの足元には玄武岩(安山岩かも)が転がっており、これらは岩脈として入ってきていたらしい。露天掘り跡より下にいくと埋もれる寸前の穴や朽ちたレールなども残っていた。これが坑道掘り跡だろう。黒雲母は坑道わきのズリ場に捨てられ、大きいものは一畳ほどもあったという。この黒雲母にフェルグソン石が伴われ、そのフェルグソン石にはしばしば閃ウラン鉱が刺さる。そのために黒雲母についてはウランを目的に戦時中に数百トンという単位で回収された。褐簾石も水晶山の特産であり、かつては50キログラムもの大塊が産出した。そういう産地だったが、今ではズリ場にすら落ち葉が積もり、草木が根を張っている。ほかのズリ場も見たが、こちらは大水で流されたようで、もはやズリ場とすらわからないほどの荒れもよう。そのため今さら新しいものを見つけるのは難しいはずだが、近代になっても岩代石や宮脇石が見つかっているのだから、一つの産地にこだわって探し続けることもまた新鉱物の見つけかたのひとつであろう。もちろんポテンシャルがあってこそなので、そこを見誤るとこの戦略は破綻する。


ポッツ石(Pottsite: (Pb3Bi)Bi(VO4)4·H2O)
模式地(Linka鉱山)では多産するようだが、ほかの産地がほとんどないのでバリエーションがよくわからない。とりあえず水晶山ではオレンジ色の微細粒か柱状結晶。周りの黄色は緑鉛鉱。

「アンキル石」はもともとストロンチウム(Sr)を主成分とする鉱物シリーズだが、これがカルシウム(Ca)に置き換わると「灰アンキル石」という別のシリーズとなる。そして、さらに主成分の希土類によって種が決まり、写真の標本はネオジム種だった。ちょっとひずんだ八面体のような結晶で、透明感があると心強い。というのも外形が粘土や褐鉄鉱に置き換わって中身がすっからかんのものがある。
水晶山は二次鉱物の産出がそれなりに多く、さらに肉眼鑑定も難しい。今回はその相談も含まれていた。いやだから苦手なんだってば二次鉱物・・。それでも、ポッツ石がひとつ明らかになった。組成的にはそんなに珍しくなさそうな印象をうけたが、実は世界的に産地が非常に少ない鉱物。最初はオレンジ色の被膜でしかなかったが、後に結晶が見つかっている。また水晶山にはロッカ石やテンゲル石の産出が既に知られているように、希土類炭酸塩の二次鉱物が産出する。そこで八面体ぽい形状の結晶がみつかり、なんだろうと調べたらネオジム灰アンキル石だった。灰アンキル石はロッカ石やテンゲル石の近縁種なので、出てきて全く不思議ではないが、ネオジム灰アンキル石もまた世界的に産地が非常に少ない。こういう世界でも産出が稀な鉱物が一堂に会する特異な場が水晶山というところで、まだ全貌は明らかになっていないと思う。そして、やはりと言うべきか、そこには稀どころではなく人類が初めて遭遇する鉱物が眠っていた。

真ん中から左側が褐簾石、右側が阿武隈石
この標本の褐簾石はセリウム種で、阿武隈石がイットリウム種であった。イットリウム種である宮脇石はこの標本の中では阿武隈石のほうに生じていた。

宮脇石
裂傷にへばりついている姿で、明瞭な結晶形はみえない。また褐色に汚れている箇所が多い。しかし本体は黄色なので視認性は良い。

宮脇石
四周完全の結晶は見いだせていないが、ところどころ結晶面の一部がなんとか見えている。最初は板状に見ていたが、いろいろな側面を観察して本来の姿を予想すると、ベスブ石の結晶に近い形になると思っている。たぶん。汚れてなければガラス光沢で透明感のある鮮やかな黄色。
それが宮脇石だったのだが、よくもまあ見つけたなあというのが素直な感想。最初の標本は全体が5-6センチの塊で、黒色の褐簾石と褐色の阿武隈石からなっていた。かつては水晶山の阿武隈石は数十センチほどの塊が産出したと記録があるが[8]、数センチ程度の大きさでさえ私はこれまで見たことがなかった。それがまだ採集できたか、という驚き。そういう標本は多少汚れていても「阿武隈石」の標本として大事にしまわれるだけになりそうなものだが、これはもう経験なのだろう。一見して汚れに見える箇所でも何かしら意味を持っているとことを、小林氏は何度も経験しているようだ[9]。だから気が付いた。とは言え、これに気が付くか?というほどのささやかな存在が宮脇石。もう一つだけ別の標本をみたが、それもやはり褐簾石と阿武隈石が混合した5センチ程度の塊状標本で、こちらは褐簾石のほうががかなり多かった。ただどちらにしても宮脇石の産状は変わらず、極めてちっぽけでしかない。二次鉱物ということもあって隙間や裂傷にほんの少しだけ張り付いているだけで、ほとんどは被膜と言える姿。それでもよく見るとガラス光沢のある結晶らしき姿が断片的に観察され、完全に成長すればベスブ石のような姿になりそうだなと予想しているが、いまのところその痕跡だけしか見えていない。結晶は1ミリにもならない大きさだが、幸いに黄色に色づいているので視認性は悪くない。こういうペグマタイト産地で黄色というとリン灰ウラン石が思い浮かぶが、それと混同することはおそらくないだろう。似ているのは色だけで、質感は異なる。また、短波の紫外線でリン灰ウラン石は鮮烈な緑色蛍光を放つが、宮脇石は全く蛍光しない。しかしそれはそれで困るか。モノ自体に派手な特徴が無ければ母岩を目安に探すしか手段がない。阿武隈石やイットリウム褐簾石の塊など今ではなかなかお目にかかれない。であればむしろ過去の標本をじっくりと見直したほうが効率的かもしれない。あと、共存鉱物としてカイシク石がほんのわずかに伴われる場合がある。実は宮脇石もカイシク石も「希土類元素をもつ炭酸塩ケイ酸塩鉱物」という点で共通している。

手元にある宮脇石の標本
全体は褐簾石の小結晶からなる集合体。阿武隈石もちょっと伴われている。ただそれはこの写真ではわからない。Uと書いてある赤矢印先の黄色部が宮脇石だが、ただの黄色い汚れに見えた。褐簾石が主体なのでその標本として扱おうとすれば、こういう黄色は見落とすかただの汚れとして無視するのが普通。しかし小林氏はこの矢印を貼って寄こした。

宮脇石
上の写真のUと書かれた赤矢印の先にある箇所を拡大。全体は黄色の被膜であるが、写真の中心部にはガラス光沢の結晶面がほんのわずかに見えている。実体顕微鏡下で針先で触ってみると被膜に見えている部分もそんなに脆弱ではなく、方解石かそれよりもう少し硬めの手ごたえがある。


カイシク石(Caysichite-(Y): (Ca,Yb,Er)4Y4(Si8O20)(CO3)6(OH)·7H2O)
カイシク石は無色から白色で板状から柱状の結晶となり、束状に集合する。イットリウムを主成分に持ち、炭酸基とケイ酸基を持つことから、組成的には宮脇石にそれなりに近く、成因もほとんど共通なのだろう。上の写真はカイシク石だけだが、下の写真は宮脇石(黄色結晶)を伴うカイシク石(まわりの透明結晶)。
こういう観察を経た後だからこそ思うに、2004年に水晶山からイットリウム褐簾石とカイシク石が見いだされたその時点で、新鉱物まであとほんの少しだったのだろう。どちらも宮脇石と強く関連している。ただ、そのほんの少しの先にある新鉱物にまでたどり着ける人はやっぱり稀である。水晶山の各鉱物の姿や産状を網羅するだけでなく、常に疑問を持ち続けていた小林氏だからこその今回の成果だと思う。それをお手伝いできた私としては、ペグマタイトからの新鉱物は愛媛から福島にまたがりこれで3つになった。もう縁が薄いとは言わない。「あなたのフィールドはどこですか?」 この問いに対して今ならこう答える。手当たり次第です。なんかごめん。
[1] Hori H., Kobayashi T., Miyawaki R., Matsubara S., Yokoyama K., Shimizu M. (2006) Iwashiroite-(Y), YTaO4, a new mineral from Suishoyama, Kawamata Town, Fukushima Prefecture, Japan, Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 101, 170-177.
[2] Akira Kato (Chairman 1975-1982): Katoite Ca3Al2(OH)12, Joel D. Grice (Chairman 1995-2002): Griceite LiF, Ernst A.J. Burke (Chairman 2003-August 2008): Ernstburkeite Mg(CH3SO3)2·12H2O, Peter (Pete) A. Williams (Chairman September 2008-2014): Petewilliamsite (Ni,Co)30(As2O7)15, Ulf Hålenius (Chairman 2014-2018): Håleniusite-(La) LaOF, Ritsuro Miyawaki (Chairman 2018-2022): Miyawakiite-(Y) Y4Fe2(Si8O20)(CO3)4(H2O)3.
[3] https://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/ugoki/geppou/V01/N04/19560822V01N04.HTML
[4]山田隆, 松原聰, 宮脇律郎, 鈴木保光, 小菅康寛, 西久保勝己(2004)福島県水晶山から産するイットリウム鉱物. 日本鉱物学会2004年度年会, K08-01.
[5] Sueno S., Matsuura S., Bunno M., Kurosawa M. (2002) Occurrence and crystal chemical features of protoferro-anthophyllite and protomangano-ferro-anthophyllite from Cheyenne Canyon and Cheyenne Mountain, U.S.A. and Hirukawa-mura, Suisho-yama, and Yokone-yama, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 97, 127-136.
[6] Williams P.A., Hatert F., Pasero M., Mills S.J. (2013) IMA Commission on new minerals, nomenclature and classification (CNMNC) Newsletter 16. New minerals and nomenclature modifications approved in 2013. Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.
[7] 長島乙吉, 長島弘三(1960)日本希元素鉱物. 長島乙吉先生祝賀記念事業会, pp.436.
[8] 大森啓一, 長谷川修三(1953)福島縣伊達郡飯坂村水晶山ペグマタイト産イツトリア石と阿武隈石. 岩石鉱物鉱床学会誌, 37, 21-29.
[9] http://albedo039.o.oo7.jp/page-suisyoyama.htm
IMA No./year: 2023-072a
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館 (NSM M-50086)
不知火鉱 / Shiranuiite
Cu+(Rh3+Rh4+)S4
Spinel supergroup
熊本県美里町払川
Nishio-Hamane D., Tanaka T., Shinmachi T. (2024): Approved by CNMNC on March 2nd.

不知火鉱の写真
熊本県払川からの新鉱物、不知火鉱である。皆川鉱(Minakawaite)と三千年鉱(Michitoshiite-(Cu))に続いてこの産地から3つめの新鉱物ということで、合わせて御三家と言っておこう。自分の新鉱物は、砂金・砂白金からではこれで8つめ(1つめ: 金水銀鉱、2つめ: 留萌鉱、3つめ: 初山別鉱、4つめ: 皆川鉱、5つめ: 三千年鉱、6つめ: 苫前鉱、7つめ: 蝦夷地鉱、8つめ: 不知火鉱)。砂金・砂白金から新鉱物を見つけるにはデンケン(電子顕微鏡)を使いこなす必要があるが、ここがデンケン室であることが幸いしたようで当初に思っていたよりもたくさん見つかった。そして、時代もあってきた。不知火鉱は、なんというか、時代に即した新鉱物なのだろう。
まず名前、不知火鉱。いかにもな字面だが、「不知火」と書いて「しらぬい」と読むことを知っているのは適齢期の男子ばかりではないだろう。今の季節ならみかんが思い浮かぶだろうか。それ以外にも相撲、ゲーム、漫画など、ほかでもいろいろ見かけるその名称は、熊本県の古称「火の国」にまつわる逸話に由来する。日本書紀をはじめとした歴史書に記されている逸話はこんな感じ → 第12代天皇にあたる景行天皇が九州を巡幸した際に、海上で闇に覆われて危うく方向を失ってしまった。しかし、遠方に火の光が見え、それを頼りに海岸にたどり着く。その際に天皇は周囲の者に「あの火はなにか」と尋ねたが、皆は「だれが燃やしているかわからない火だ = 知らぬ火」と答えた。そうして「不知火」の名称が生まれた。そしてこれが「火の国」の由来となり、そう呼ばれた地域の一部が今でいうところの熊本県。熊本を名づけた加藤清正公には申し訳ないが、面白い逸話なので熊本生まれの新鉱物の名称としてこの不知火を提案したのだった。
不知火鉱はスピネル超族の新鉱物である。そして、このスピネル超族というまとまりが成立したのはわりと最近(2019年)のこと[1]。

まずは分類の方法と不知火鉱の立ち位置をさっくりと。スピネル超族はAB2X4という化学式とスピネル構造をもつ鉱物のまとまりであり、「X」の種類によってまずは3つの族に分けられる。そのなかで白金族元素を主成分に持つのは硫化スピネル族(X = S)だけ。それはさらに二つの亜族、リンネ鉱亜族とカーロール鉱亜族に分けられ、不知火鉱はカーロール鉱亜族の新種という立ち位置。上の図を見れば立ち位置は視覚的にわかるだろう。

2019年より前と後の分類
それにしても昔の分類は単純だった。それは例えば上の図の左側のように。(Cu,Fe)B2S4という化学組成だと、「B」のところがロジウム(Rh)なら硫銅ロジウム、イリジウム(Ir)なら硫銅イリジウム鉱、プラチナ(Pt)ならマラン鉱、といった古式ゆかしい分け方。ところが命名規約はそれを変えた(図の右側)。変更の要点だけをまとめると、昔の硫銅ロジウム鉱は、今では①リンネ鉱亜族の硫銅ロジウム鉱、②カーロール鉱亜族のRhPt(後の蝦夷地鉱)、③カーロール鉱亜族の2Rh(後の不知火鉱)、④カーロール鉱亜族のRhIr(未命名)、という4つの可能性に分離し、②~④が新鉱物候補となった。それなのにこの命名規約は新鉱物候補があらわれたことにはまったく触れていない。要は自分で気が付くしかないが、逆に気が付いてしまえば、これはもう新鉱物発見に至るロードマップ。硫銅ロジウム鉱という宝箱を開けてみればいい。そこには新鉱物がきっと入っている。
ではそれはどこにある。硫銅ロジウム鉱という宝箱は砂白金というダンジョンにたまに転がっている。さらには宝箱には産地ごとにクセ(組成の傾向)があることが、デンケンによる観察と分析からわかっていた。そして、北海道産のものはプラチナ(Pt)に富む傾向があった。つまり②(カーロール鉱亜族のRhPt)が狙い目で、そしたらやっぱりあっさりちゃんと②が見つかった。それを新鉱物として申請して、蝦夷地鉱が誕生した。そして熊本産のもの。これにはやたら銅(Cu)とロジウム(Rh)に富むものが混じっていた。それは調べ始めた当初は新鉱物になりえなかったが、命名規約が成立した今となってはそれが③(カーロール鉱亜族の2Rh)であり、このたび不知火鉱として承認された。
このような事情で、不知火鉱とは(蝦夷地鉱もだけど)、スピネル超族が成立した時代だからこそ誕生した新鉱物であり、それが最初に述べた「時代に即した新鉱物」の意味であった。古くから白金族鉱物を研究してきた研究者は、命名規約によって変化した内容ではなく「変化」それ自体に抵抗しているように感じられる[2]。しかし、世の中は変化するものだと割り切って、変化した内容を見定めてさっさと行動したほうが得るものがある、かもしれない。それが今回(前回も)のケースで、これもまた新鉱物クエストである。
残った④(カーロール鉱亜族のRhIr)はむしろ海外の産地に期待したい。ダンジョン探索をがんばって宝箱を見つけても、国内産ではもはやそれはきっとミミック。そこにあえて挑むなら暗いよ―怖いよーとなる覚悟はいるだろう。しかし1%くらいの確率でなら可能性は残っているとは思う。
ここからは写真を題材にして現場や現物のあれこれを書いてみよう。

上流部の盤
産地は美里町払川を流れる小河川。「払川」というのは地名であって、河川の名称ではない。川幅は平均的に2-3メートルくらいで、場所によって6-7メートル程度まで。そこは釈迦院川の支流にあたる。砂金・砂白金の探査は盤を探すのが定石なのでまずはその分布を把握したい。上流に行けば盤が出ており、小規模な滝下は深くえぐれて土砂がたまっていた。これより上流は急峻で、川幅もせまい。逆に下流に向かうとすぐ広くかつ緩やかになるが、盤が出ている箇所はもうあまりない。また、てきとうに河床を掘って盤に到達するのは難しい。一抱えもある石がそこかしこにあって易々と掘れるものではない。さて、どこをどう攻めるか。

一日で採れる砂白金の量(一マス = 1ミリ)
そりゃまあ好きに攻める。しかし、ここはどれほど効果的に攻めても量を期待できる産地ではない。昨年(2023年)は夏と秋に採集に行き、一日あたり写真ほどの量。重さで換算すると毎回1グラムにも満たない。それでも個数が採れることは幸いで、小さかろうともこれだけあれば研究はやりようはある。また、経験的にはこのくらいあれば御三家(皆川鉱、三千年鉱、不知火鉱)のうちのどれか1,2個は期待していいだろう。もちろん運次第だが。

最大サイズの砂白金(一マス = 1ミリ)
これまで採集した中で最大サイズが写真のもの。多くがこのサイズであればとても魅力的なのだが、現実は厳しい。ここの砂白金は平均的には0.5ミリを下回り、1ミリを超えるものはかなり少ない。形状はだいたい不定形。おそらくは現地性に近い状態で、川擦れの影響は少ないように感じられる。また、大小を問わずモノはおなじ。ほとんどの砂白金が鉱物種としてはイソフェロプラチナ鉱(Isoferroplatinum: Pt3Fe)をベースとしている。イソフェロプラチナ鉱はプラチナ(Pt)と鉄(Fe)を主成分とする白金族鉱物であり、そればっかり採れるということは、払川はプラチナが主体の砂白金鉱床であることを意味している。しかし、鉱床規模が小さすぎるため資源利用どうこうは考えづらい。

イソフェロプラチナ鉱(左)とトラミーン鉱(右)(一マス = 1ミリ)
一粒の砂白金がまるまるイソフェロプラチナ鉱(左)であるものは銀白色を呈する。一方、右のほうは並べてみればやや茶色を帯びている。これは粒の表面層(数十マイクロメートル厚)がトラミーン鉱(Tulameenite: Pt2CuFe)に変化しているためである(中身はイソフェロプラチナ鉱)。一般に砂白金は地表に出てくるまでに母岩ともども蛇紋岩化作用に巻き込まれている。イソフェロプラチナ鉱はその過程でわりと変質しやすく、一部の粒子は表面層がトラミーン鉱へ変質する。テトラフェロプラチナ鉱(Tetraferroplatinum: PtFe)が生じる場合もあるが、見た目はトラミーン鉱と区別ができない。いずれにしても、つや消し状の砂白金粒子が銀白色であればイソフェロプラチナ鉱、やや茶色ならトラミーン鉱もしくはテトラフェロプラチナ鉱と判断しておおむね間違いない。が、粒子サイズが0.5ミリを下回ってくると見分けづらい。

自然オスミウムと自然イリジウム(写真幅1ミリ)
払川では砂白金粒子としての自然オスミウムはすごく稀(包有物ならふつう)。自然オスミウムからなる砂白金粒子が得られたのはこれまで10粒もない。自然オスミウムはモース硬度が7-8とケイ酸塩鉱物並みかそれ以上に硬く、摩耗しにくい。そのため、自然オスミウムの粒子は傷があまりなく、つるっとしており、光沢にはやや青みも感じられるので、見れば一発でわかる。ただし払川ではいつも小さく、御三家よりも出会う確率が低い隠れキャラ。写真の標本は自然イリジウムを噛んでいるというさらなるレアケース。

ラウラ鉱とエルリッチマン鉱(写真幅3ミリ)
ラウラ鉱(Laurite: RuS2)とエルリッチマン鉱(Erlichmanite: OsS2)はそれぞれ黄鉄鉱(Pyrite: FeS2)のルテニウム(Ru)およびオスミウム(Os)置換体にあたる鉱物で、ここではけっこう見かける。写真のように砂白金粒子に伴われ、一粒の砂白金に5-6個も付属することがある。こうした産状は鉱物の晶出順序と安定性に関連している。ラウラ鉱やエルリッチマン鉱は融点が高いので真っ先に結晶化し、その次に結晶化するイソフェロプラチナ鉱がこれらを包みながら成長し、包みきれなかった部分が顔を出す。そのような部分は当たり前に蛇紋岩作用にさらされるが、ラウラ鉱やエルリッチマン鉱はそうした作用にはめっちゃ耐性が高いことで知られる[3]。結果、変質なんかせずに生き残る。ただし、削れたり割れたりすることは普通にある。

バウィー鉱と硫銅ロジウム鉱(写真幅1ミリ)
払川の砂白金はいろんな白金族鉱物を包有している。硫化物だと最頻出はラウラ鉱やエルリッチマン鉱であり、次に多いのがバウィー鉱(Bowieite: Rh2S3)。いずれも絡み合うことがあるので、晶出順序もほぼ同じくらい。ただ、ラウラ鉱やエルリッチマン鉱が砂白金粒子の表面によく顔を出すのに対して、バウィー鉱が表に顔を出すことは珍しい。これは包有物で見かける頻度からするとアンバランスで奇妙に思えたが、それにはバウィー鉱が実は内弁慶という事情がある。外に出るとこいつはめっちゃ弱い。例えば上の写真の中央、つやのある灰黒色の部分がバウィー鉱であるが、周囲がちょっとモコモコしており、そこは硫銅ロジウム鉱。つまりこの標本は、バウィー鉱から硫銅ロジウム鉱へ変質する途上にあり、それでもバウィー鉱が何とか生き残っているという姿になっている。

硫銅ロジウム鉱(写真幅3ミリ)
硫銅ロジウム鉱(Cuprorhodsite)の典型的な産状は砂白金粒子に伴われるざらついたコブであり、大きめだと灰黒色で、小さめだと真っ黒に見える。こういう硫銅ロジウム鉱はラウラ鉱やエルリッチマン鉱に次いで見かけることが多い。それは当たり前。包有物としてラウラ鉱やエルリッチマン鉱の次に多いバウィー鉱、それが内弁慶のくせに表に出たあげく、改変された成れの果てが硫銅ロジウム鉱だからである。つまり、払川においての硫銅ロジウム鉱は、バウィー鉱を元に二次的に生成した鉱物。イソフェロプラチナ鉱(Pt3Fe)がトラミーン鉱(Pt2CuFe)やテトラフェロプラチナ鉱(PtFe)に変質するように、変質には銅(Cu)や鉄(Fe)の付加反応が伴われる。バウィー鉱(Rh2S3)に銅や鉄を加えて、ちょびっと硫化(S)させると硫銅ロジウム鉱((Cu0.5Fe0.5)Rh2S4)ができあがる。

不知火鉱(写真幅5ミリ)。真ん中が不知火鉱。
では不知火鉱はというと、硫銅ロジウム鉱と同じくバウィー鉱の成れの果てのひとつ。ただし、見た目は硫銅ロジウム鉱とまったく変わらないので、デンケンで分析しないと区別できない。また、不知火鉱はめったに見つからない。硫銅ロジウム鉱が20-30くらいあっても不知火鉱はひとつとか、感覚的にはそのくらい。払川御三家の中でも不知火鉱が最も希少。おそらく不知火鉱が生成する環境はかなり限定的だったのだろう。また、産状の類似性とロジウム(Rh)を主成分に持つという共通性から思うに、皆川鉱や三千年鉱、希少鉱物のフェロトリーウェイゼル鉱やアンドリーズロンバード鉱などもバウィー鉱が出発点と思われる。ただ、観察しているとそれらの生成場や反応順序、経路は単純ではなくいくつも分岐がありそうで、考え始めるときりがない。が、考え始めると面白くてあれこれ考え続けてしまう。
さて、払川からあとひとつ見つかれば新鉱物・四天王。その可能性はどうか。フェロトリーウェイゼル鉱やアンドリーズロンバード鉱は払川で見つけた時点では名前がついていなかったので、その時はもちろん新鉱物候補であり、これらをカタチにできていれば四天王や五大なんとかみたいなことがあり得たのだろう。しかしそこは力及ばず。二つとも海外に先を越された。まあそれでも御三家→四天王→五大・・→七崩・・と、まとまりが大きくなると内格差がつきがちで、全体として小物感もにじんでくる。それならば大物感あふれる御三家で終わったとしても悪くない。それに一式のコレクションを目指すにしても3つくらいならガンバレルだろう。ガンバレ。
[1] Bosi F., Biagioni C., Pasero M. (2019) Nomenclature and classification of the spinel supergroup. European Journal of Mineralogy, 31, 183-192
[2] Cabri L.J., McDonald A.M., Oberthür T., Vymazalová A. (2023) An Examination of Platinum-Group Element Thiospinel. The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology, 61, 1109-1121.
[3] Cabri L.J., Oberthür T., Keays R.R. (2023) Origin and depositional history of platinum-group minerals in placers – a critical review of facts and fiction. Ore Geology Reviews, 144, 104733.
IMA No./year: 2022-101
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-49764)
蝦夷地鉱 / Ezochiite
Cu1+(Rh3+Pt4+)S4
Spinel supergroup
北海道苫前町海岸
Nishio-Hamane D., Saito K. (2022): Approved by CNMNC on December 5.

蝦夷地鉱の反射顕微鏡写真
北海道苫前町海岸の砂白金から見いだされた新鉱物、蝦夷地鉱である。実は10月、11月、12月と3か月連続で新鉱物チャレンジをしていて、蝦夷地鉱が無事に掉尾を飾ってくれた。ベタフォ石から始まって今年だけで4種を筆頭でまとめた。あーしんどかった。北海道の地名は独特なものが多いので、新鉱物を見つけたら地名からその名をもらう方針だったところで苫前町海岸から二つ目がでた。どうしよう。ここまで苫前町→苫前鉱、留萌管内→留萌鉱とすでにこの辺りの名前は使ってしまっていた。地名だと残るは大物、北海道しかない。今回は金属鉱物ということで和名は「鉱」で結ぶ必要があって、そうなると北海道鉱(ほっかいどうこう)か。うーん、これはちょっと言いづらいぞ。だったら北海道の旧名はどうかと調べたら蝦夷地。そして蝦夷地鉱(えぞちこう)は、うん、すっきりと発音しやすい。こっちにしよう。しかし漢字はややこしいのでラベルは書きづらい。
コロナ禍の中にあって外出は少なく、砂白金もしばらく採集に行っていなかった。そしてストックがいよいよ少なくなってきたこともあって、試料確保のために久しぶりにマイフィールド、北海道留萌管内へ向かう。今回の目的は通称で浜白金と呼ばれる浜辺で取れる砂白金。浜白金は一般に0.5ミリにも満たない非常に小さい粒子であり、どれだけ採ったところで重量に換算すると微々たるものにしかならない。ほんの0.1グラムを採るにもたぶん数か月はかかる。それではあまりにも儚いためか愛好家といえども浜白金を積極的に採集する人は少ない。一方で、時間当たりに採取できる個数としてカウントすると浜辺での効率は河川に圧倒的に勝る。そして、重量ではなく個数こそが重要な私にとって浜白金は都合が良かったりする。今回もまた斎藤勝幸氏に案内をお願いした。

1マス1ミリの方眼紙の上にのせた浜白金
浜辺で採集できる砂白金(いわゆる浜白金)はとても小さく、多くは0.2-0.3ミリ程度の大きさしかない。しかし時間あたりに採集できる個数そのものはとても多い。
浜白金の産地は重砂もまた濃集しているため、黒く染まった箇所は浜白金を探す際の一つの目印になる。一方で大量の重砂は困りもの。重砂と浜白金とはネコ板やパンニング皿などを用いた比重選鉱によって分けるが、重砂があまりに多いと浜白金が重砂の上を滑ってこぼれ落ちてしまう。そもそもこの浜白金はどこから来たのか。嵐の日に海の中から打ち上げられると聞いたか読んだか、そんなおぼろげな記憶があるが、そうなるからには浜白金を供給する地層が近くにあるはず。下の写真左はある海岸に露出した礫岩層で、全体的に緑色を帯びている。あ、たぶんこいつだ。しかし岩石を砕いて取り出すのは厳しい。そこで周辺を掘り下げて粘土化した箇所を採ってパンニングしたところ、やはり浜白金が出てきた。地層を見極めて攻めるか、重砂の効率的な処理を工夫するか、ひたすら汗をかくか、アプローチの仕方はいろいろある。

海岸で観察できる礫岩の露頭(左)とそれが粘土化したかたまり(右)。
露頭のほうでは直に確認していないが、露頭の延長を掘りこんで出てきた粘土化したかたまりを崩してパンニングすると砂白金(浜白金)が得られる。粘土化したところでも礫は頑丈なままなので礫以外の部分(マトリックス)に浜白金が含まれていると思われる。
自分で採集したものと斎藤氏から提供された砂白金を持って内地に戻る。研究はここから実験室内での作業へと進む。砂白金を本格的に調べるためには、研磨片を作る必要がある。それは砂白金をスライドガラスの上に樹脂で固定し、平面が出てピカピカになるまで研磨する工程になる。このとき砂白金が大きいと実はかなり困る。特に北海道の砂白金の多くは硬いため、数ミリもあると研磨片の作成が難しく時間もかかる。それに、数ミリもある砂白金を消し飛ばすように加工する作業はやりながら心が痛くなる。技術的な問題と気持ちの問題の両方をクリアしたのが浜白金だった。たくさん採れる0.数ミリの粒ならいくら消えても悲しくない。またそのくらいのサイズになると硬いとはいってもその抵抗はたかが知れており、浜白金なら研磨片は数分で作れる。浜白金は収集物とするには物足りないが、調べるにはうってつけなのでたくさん調べた。その結果として、苫前町海岸から新鉱物が二つ見つかったのだった。
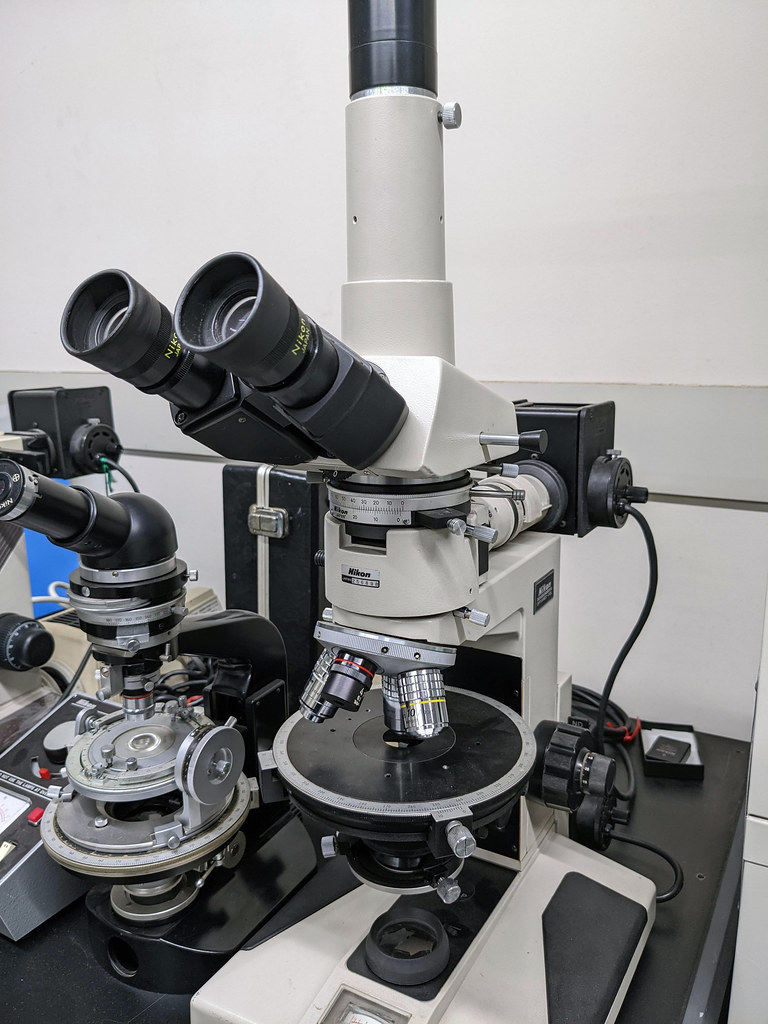
透過光と反射光の両方が組み込まれている顕微鏡。ジャンク品を3つほど買い集め、必要なパーツをとって一台の顕微鏡として組み直した。写真のものは30年以上前に製造された顕微鏡で、有限遠光学系という古いタイプの設計だが問題なく良く見える。
砂白金をはじめ、金属鉱物はまずは反射顕微鏡で観察することがセオリー。反射顕微鏡は研磨面に垂直に光を当ててその反射光を観察するタイプの顕微鏡であり、光学的性質でモノを識別する。観察では主に色と形に注目する。反射色や干渉色はモノの違いをよく現し、形や周りとの関係は晶出順序のヒントを与えてくれるように、昔から反射顕微鏡による観察は、特に金属鉱物の研究には欠かせない手段となっている。反射顕微鏡に限らず顕微鏡を正しく使いこなすことができるようになると、分析せずとも確度の高い鑑定ができるようになる。

蝦夷地鉱を含む砂白金(初山別川産)の反射顕微鏡写真。
狭い範囲にブラッグ鉱やトリーウェイゼル鉱といったレアもの白金族鉱物と共存している。いずれも非常に小さいが白金族鉱物としては実は標準的なサイズ。
私が砂白金の研究に手を付ける前までには日本産の白金族鉱物は15種ほどしか知られていなかった。世の中で知られている(名前のついている)白金族鉱物はだいたい160種なので、これはかなり少ないなという印象。白金族鉱物の母岩となる超苦鉄質岩に海外と日本で違いがあることが一つの要因なのだろうが、探し方の問題かもしれないと感じた。探し方にはたいていコツがある。それを模索しながら手を付けて数年。そして、今の段階では日本産の白金族鉱物は70種くらいまで増えている。なんだ、日本もたくさんあるじゃないか。すべての白金族鉱物種の半分くらいまでは行ってほしい。とりあえず現時点で判明している白金族鉱物を一覧にして下に出してみる。産地はここでは北海道や熊本とだけ記した。産地の詳細は学会発表や論文でいずれ明らかにしようと思う。
_ |
さて、これだけ多種類の白金族鉱物が見つかっているが、砂白金として単独の粒子で得られるものは少ない。自然イリジウム、自然オスミウム、自然ルテニウム、ルテニイリドスミンは北海道では単独の粒子として得られる。イソフェロプラチナ鉱もまた単独の粒子として得られ、北海道ではあまり多くないが熊本では多産する。その一方で自然プラチナの産出は北海道、熊本ともに極めて少なく、単独の粒子で存在することは実はめったにない。そのほか、トラミーン鉱、テトラフェロプラチナ鉱、フェロニッケルプラチナ鉱、承徳鉱などは主に砂白金粒子を覆う、もしくは付着するといった産状で、実体顕微鏡なら観察できる。それからラウラ鉱とエルリッチマン鉱なら熊本でわかりやすいものが産出し、皆川鉱、三千年鉱、硫銅ロジウム鉱もまた熊本で砂白金のコブとして伴われるため、実体顕微鏡があれば捉えることができる。しかし、それ以外となるとほとんどが非肉眼的な微小な包有物として産出し、多くがせいぜい10μm程度の大きさでしかない。10μmとは0.01ミリである。あまりにも小さいと思うだろう。しかし、この程度の大きさが実は白金族鉱物の世界標準。そのために世の中の鉱物の情報を網羅するMindatであっても白金族鉱物は写真が載っていないことが多い。白金族鉱物は約160種という大きなまとまりでありながらも、その姿はベールに包まれており、まるで秘密結社のような集まりでもある。たとえば100以上の地域で産出が記録されている普通種であってもその姿を知る者が誰もいなかったりする。白金族鉱物はどんな産状で現れてどんなツラをしているのか。それがまとめて見られると良いのだが・・


無いなら作ればいいということで、しまうまプリントを利用してとりあえず作ってみた。冊子のサイズや印刷の質を選べるのが良い。せっかくなので白金族鉱物だけでなく砂金や関連鉱物、命名由来や小ネタ、コラムも入れて遊んでいる。あまりにもニッチな72ページの試作品。
作ってみたらけっこう便利。こうやってまとめて白金族鉱物を眺めて見てみたかった。A5サイズにして顕微鏡のそばに置いとくとハンドブックとして観察の参考にもなる。そして肝心の蝦夷地鉱であるが、その産状はだいたい固定されているため候補をみつけるところまではそんなに難しくない。蝦夷地鉱は必ずイソフェロプラチナ鉱の包有物として産出する。一方で一粒だけがすっぽり含まれるということがあまりない。ほとんどのケースで円形から楕円形集合の構成鉱物の一つとして含まれる。(楕)円形集合は蝦夷地鉱のほかに、黄銅鉱、ブラッグ鉱、バシル鉱、ウソツキ鉱などが伴われやすい。そしてブラッグ鉱、バシル鉱、ウソツキ鉱は蝦夷地鉱と判別しにくいほど光学的性質がよく似るが、並んで産出すると蝦夷地鉱のほうがやや色が濃いことから鑑定できる。また共生関係はそのままに構成鉱物の量比はモノによってけっこう異なり、蝦夷地鉱が大半を占める(楕)円形集合が存在する。究極的には分析する以外には完全に見分ける手はないものの、反射顕微鏡でおおよそのあたりをつけることができるのはありがたい。一家に一台、顕微鏡。あってもいいと思う。蝦夷地鉱や関連鉱物の反射顕微鏡写真をいくつか下に挙げる。

蝦夷地鉱はイソフェロプラチナ鉱の包有物として産出する。ひとつの包有物が蝦夷地鉱だと、周りの包有物も蝦夷地鉱。苫前海岸産。

硫銅ロジウム鉱は蝦夷地鉱の鉄-ロジウム置換体に相当する。産状と色かたちは蝦夷地鉱と全く同じであるため見た目で区別できない。その一方で蝦夷地鉱と硫銅ロジウム鉱が共存することはなかった。必ずどちらか一方しか含まれない。苫前海岸産。

マラナ鉱は蝦夷地鉱のイリジウム置換体に相当する。世界的に産出は稀ではないが、日本では極めて稀で、蝦夷地鉱よりも見かけることが少ない。マラナ鉱は蝦夷地鉱や硫銅ロジウム鉱と異なり単独の粒子がイソフェロプラチナ鉱に包有される。近くには田村鉱が伴われることがある。小平町海岸産。
このたびの蝦夷地鉱は苫前町海岸の砂白金から得られたが、北海道内に産地はいくらかある。また、蝦夷地鉱は日本のもう一つの砂白金鉱床である熊本からは産出しないので北海道を現す名前はなかなか良かったと思う。そしてこれから日本の白金族鉱物がどうなるかというところだが、種類については確実にまだ増える。一覧表には掲載していないが、追加であと20種ほど名前がついていない白金族鉱物が見つかっている。それらが日本産の新鉱物となるか、海外で先にまとめられて日本新産というかたちに落ち着くか。それはつまり新鉱物としてのデータを取得できる標本が得られるかどうかである。どんなに小さくとも苫前鉱や蝦夷地鉱くらい濃集して出てきてくれるなら何とかなる。そうであれば手持ちの砂白金なぞ全部潰して探す。くらいの気概でやっていきたいが、でかい砂白金はやっぱり手も心もしんどい。まずは浜白金からで。
IMA No./year: 2022-080
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-49762)
群馬石 / Gunmaite
(Na2Sr)Sr2Al10(PO4)4F14(OH)12
New structure type
群馬県桐生市津久原
Nishio-Hamane D., Yajima T., Ohki Y., Hori H., Ikari I., Ohara Y. (2022): Approved by CNMNC on November 2.

群馬石の写真
群馬県桐生市津久原からの新鉱物、グンマー石ならぬ群馬石である。この産地名にすでに聞き覚えがある人もいるだろう。ここは桐生石の産地でもあり、群馬石は桐生石に引き続いて当地から発見された二番目の新鉱物になった。それにしても今回は当初から頭を抱えることが多く、たびたび跳ね返され手を焼いた。そして、名前を付ける段になんとかたどり着いたときには「これもうグンマーだよな」などと説明しがたいよくわからない心情になっていて、誰に相談することもなく一人で勝手に群馬石に決めてしまっていた。心にググっと群馬石。でもまあ桐生石が先にあったためどちらも地名ということでバランスは取れている。
心情のまま名付けてしまった群馬石。この「群馬」という名称は古い時代の名乗りに由来している。この辺りは古代では上毛野国(こうずけのくに、かみつけぬのくに、かみつけののくに、かみつけのくに等)と呼ばれており、その中に車(くるま)と呼ばれる地域があった。それは当時の行政区域の単位としては評(こおり、ひょう)というまとまりであり、車評という地域名になっていった。その後、大宝律令(710年)が制定された際に評から郡(こおり)への改訂があって車郡となり、奈良時代のはじめごろに二字の好字で地名を表すことになったとき群馬郡(くるまのこおり)に改名されたと推測されている。その字面からして往時は馬の産地であったのだろう。そして「くるま」の読みは江戸時代まで使われており、「ぐんま」と読むようになったのは明治期以降。グンマーと言い出したのはかなり最近のことで、それは群馬県の秘境感を印象付けるネットスラングである。しかしどういうわけかしっくりくるし、おそらく広く受け入れらている。地元の上毛新聞には「グンマー」のカテゴリーがわざわざ用意されているし、SNSでは「#グンマー」もたくさん投稿されている。いっそグンマーを正式名称にしちゃえばいいのに。
さて、群馬石や桐生石につながった一連の研究は津久原鉱山跡から産したゴヤズ石から始まっている(桐生石の項を参照)。これは小原氏からの依頼がきっかけだったので私にとっては小原氏が起点だったが、その前があったことを後に知った。今回は小原氏よりも前にあった出来事に触れながら述べていこうと思う。
2005年のこと。その当時に壮年だった(今では中年の)愛石家、伊藤剛氏と高橋秀介氏は、地質調査月報の報文[1]を参考にして「石英脈中の(層状マンガン鉱床からでない)マンガン重石」を求めて、津久原鉱山跡にたどり着いた。彼らはそこで狙い通りにマンガン重石を得たほか、今でいうところのゴヤズ石を採集した。それは国立科学博物館へ送られ、ゴヤズ石(SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6)に近いがアルミニウム(Al)とリン(P)が少し足りないという結果が得られた。これについて電子線による分析では検出が困難な軽い元素が含まれている可能性が考えられたようだ。そして松原先生はこのゴヤズ石を博物館の館報に記載したい旨を伊藤・高橋氏に伝え、彼らも了承したものの、ゴヤズ石が館報に載ることはついになかった。そして何の発表もなかったからこそ2013年に小原氏が当地を訪れてゴヤズ石を再発見して記載した。それが桐生石や今回の群馬石までつながっていくのだから、端緒となった両氏をみるとちょっとおやげない展開といえるかもしれない。まあ私が悪いわけではないが。

2005年時に得られたゴヤズ石
透明感があってほどよく色づいた端正な形をしており、標本としてはわかりやすい。しかし、研究対象としてこれはなかなかの困りもの。
最近になって当時の標本を伊藤氏から送ってもらい、それを調べてみた。すると電子顕微鏡写真で累帯構造が観察された。外形の白いコントラストはセグニット石(Segnitite: PbFe3+3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6)であり、セグニット石を伴う結晶は写真のように黄色を帯びる。中身についてはじめは均質に見えていたが、装置を調整してコントラストを強めると霜降り肉のように細かく模様が入り乱れている様子が見てとれた。これは実はゴヤズ石と別の鉱物(ゴヤズ石様鉱物としておく)がナノスケールで入り混じっているせいである。そしてゴヤズ石様鉱物が混じっているからこそ組成式を組み立てようとすると、ゴヤズ石としてまとめていいのかとちょっと悩む程度にズレる。また、ゴヤズ石とゴヤズ石様鉱物は粉末X線回折ピークに共通するものがかなり多い。つまり分離・区別できない。こうした事情から「ちょっと変だけどゴヤズ石」という違和感の残る結論に落ちざるを得なかっただろう。そのために松原先生は館報への記載をためらったのかもしれない(ほかの事情かも)。その後、幾人もがこの場を訪れて標本を採集したようだが、伊藤・高橋氏らは他の方とは現地状況について話が食い違うことが多かったようで、皆がそれぞれ複数ある石英脈の別の部分を採ったと彼らは推測している。それはまず間違いなくその通りだと思う。加えて、伊藤・高橋氏の採った2005年の結晶は始末に負えないヤツで、後年に小原氏の採ったものはわりと素直なヤツだったと思われる。

2005年の伊藤・高橋ゴヤズ石の走査型電子顕微鏡写真(組成像)
コントラストの違いが組成の違い(≒モノの違い)を示しており、複雑に細かく入り乱れている様子が見てとれた。おそらくこの像で見えているよりも小さいスケールでも入り乱れていると思われる。調べるうえではかなりたちが悪いと言える。
その後、林道工事が進んだこともあって、さらに奥地で新鉱物・桐生石が見つかったところまでが昨年の話になる。そして、そろそろ論文を書かなければと思っていた2022年明け、桐生石のあった脈よりもちょっと奥でゴヤズ石が見つかったと小原氏から連絡が入った。母岩をみるとそれは白雲母の芋。これは昨年の現地調査の時に桐生石脈よりちょっと上で見かけた粘土脈中のものであろう。ふーん、そこにも出てくるのか。そう思った程度で分析に進み、そして頭を抱えた。

白雲母芋の中から出てきた六角板状の結晶
まるでドロップを思わせる姿かたち。これはゴヤズ石もしくはバリウム(Ba)置換体のゴルセイ石だろう。まあ分析すれば簡単にわかると思っていたが・・
結晶はやや黄色を帯びた六角板状で、一部はロゼット状に集合している。黄色の原因は表層のセグニット石もしくはキントレ石(Kintoreite: PbFe3+3(PO4)(PO3OH)(OH)6)なので、これはいままで見てきたいわゆるゴヤズ石の標本とかわらない。問題はその中身。伊藤・高橋ゴヤズ石を上回る凶悪な累帯構造があらわれた。モブと思ってエンカウトしたらラスボスだったくらいの衝撃。一目見て唖然・・。ここまでめちゃくちゃなヤツにであったことがなかった。それでも少しずつ分析を始め、暗いコントラストの部分だけからナトリウム(Na)が検出されることが分かった。暫定的な化学組成を組み立てると新鉱物(=のちの群馬石)の可能性がみえたものの、すぐ敗退。どうにもできなかった。これは難物である。小原氏には新鉱物だけのすなおな結晶があればできるかもと伝えた。さすがに難しいだろうと思いながらも万が一を期待していた。
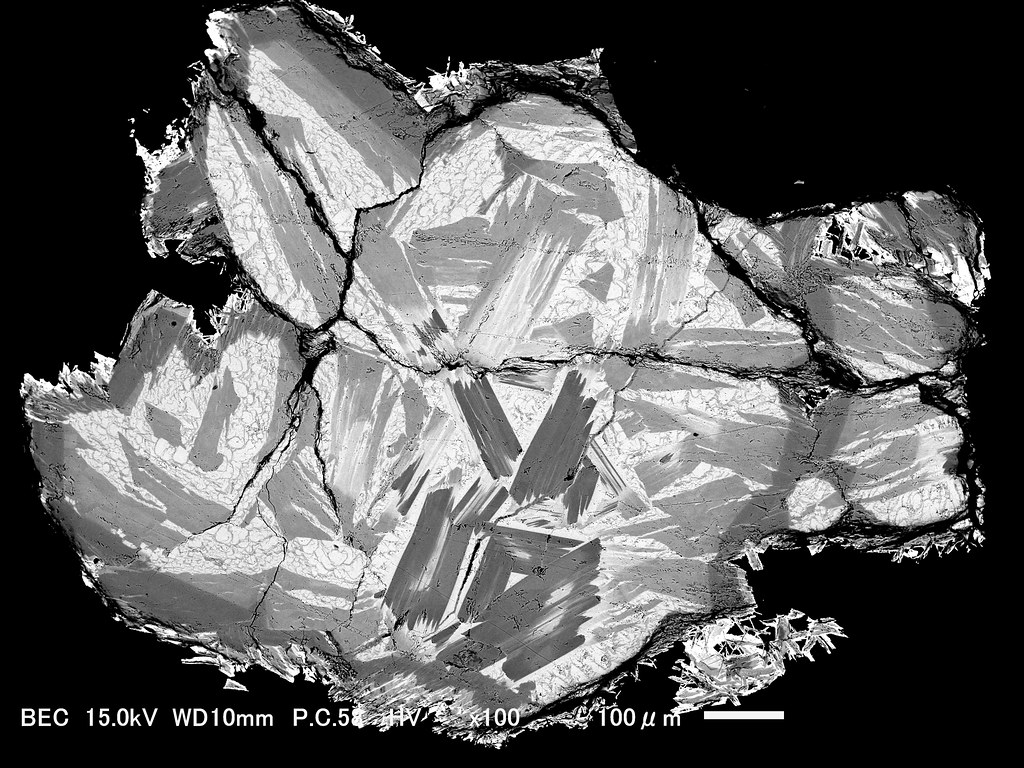
群馬石を伴う結晶の走査型電子顕微鏡写真(組成像)
この結晶は光学顕微鏡ではほぼ一様なものに見えていた。しかし、電子顕微鏡で見える累帯構造はすさまじく乱雑。第一印象は2Dロールプレイングゲームのラスボス。群馬石はこの写真で中央から下にある暗いコントラストの部分。
この標本が採集されたとき、小原氏のほかには大木良弥氏と堀浩文氏が同行していた。彼らは一連の脈で異なる場所にとりついていたようで、採集された結晶の様子がわずかばかり異なっていたと言う。そこで各々に標本を提供してもらって、それらを色や形状でざっと分類して調べ始めたところでやはりラスボス。太刀打ちできずにほとんど返り討ちにあった。いずれも累帯構造が複雑に入り組んでいて手が出せない。結局、結晶がむやみに消費されるばかりだった。ただ群馬石は必ず存在するので引くに引けない。それでも限界がきて、もうムリ・・と根を上げる寸前で大木氏提供の標本からギリギリいけるかもという結晶が見つかった。その結晶は無色の六角板状。それを走査型電子顕微鏡で観察した時、群馬石となる部分がこれまでと異なって結晶の外側に位置していた。これなら何とかできるかもしれない。群馬石である部分は数十μm程度しかなかったが、慎重に切り取って構造解析に進むことができた。あと少しで倒せる。そう思ったが結果を受け取ったときまた頭を抱えた。

模式標本となった大木氏提供の標本。この標本についている結晶だけは群馬石が外周を構成しており、それは何とか分離できる組織だった。
構造解析は物性研の矢島氏にお願いし、出てきた結果はとても信じがたい内容だった。格子定数のc軸が50Åもあり、これは構造が解明されているリン酸塩鉱物としてはたぶん史上3番目くらいに大きい。1番2番の鉱物は全く参考にならなかったため、前例がない問題に向き合わなければならなかった。ラスボスが変態を遂げて最後の課題をぶつけてきた。構造モデルをちゃんと解明しないと新鉱物申請はできない。それでいったん嫌になって現実逃避でゴヤズ石の標本やその結晶構造を眺めていたらなんかひらめいた。ちぎっちゃえ。ゴヤズ石の構造をいくつか用意して、その一部をちぎって並べてみたら何となく雰囲気が似てくる。そして構造の隙間にナトリウムをぐいっと押し込めばおおむね群馬石構造になるではないか。基本的な骨格がゴヤズ石と共通なのだから、外観もあたりまえにほぼ同じ。これで群馬石の全容が解明された。ここまで苦しかったがなんとかやっつけた。そして最後の〆で名前を決めるとなったとき、グンマーが自分の中でしっくりきた。今回は秘境の中でふいに遭遇したラスボスを倒して宝物(=新鉱物)を手にしたような心持ち。そして秘境≒グンマーだと(無礼)。群馬石の学名(Gunmaite)を私はグンマーアイトと発言するだろう。それではグンマーアイトの標本をいくつか並べよう。





いろいろな姿かたちのグンマーアイト
六角板状が基本だが、球状の集合体もある。黄色に色づいているものが見つけやすい。
まず産地の概要を整理したい。当地でゴヤズ石っぽい六角結晶が産出する脈はおもに三カ所。①鉱山跡脈、②桐生石脈、③群馬石脈。①→③の順で奥にある。そして、鉱山跡脈や桐生石脈に群馬石が出現することは一切なかった。その一方で、群馬石脈からでた結晶には群馬石は大なり小なり必ず伴われハズレなしというように、極端に産出が偏る。つまり、群馬石であるかどうかは群馬石脈から得られた標本かどうか、ただそれだけにつきる。群馬石の母岩は白雲母の芋であった。その芋が石英を含んでおり、水晶となっている部分の隙間に群馬石を含む結晶が産出する。典型的な姿は黄色で六角形。この黄色はセグニット石やキントレ石が結晶の最表層に生じているためであり、厚いほど黄色味が強い。しかし色づいているからこそ視認性は高く、ルーペがあれば現地でも判別できる。無色の六角形もあるがこれは現地では見分けづらいだろう。実体顕微鏡でさえわかりづらかった。群馬石はこうした六角結晶の中心部に存在することが多いが、ごくまれに外側を構成することがある。しかし見たところでそれは全くわからないし、含まれているのなら標本としてはどっちだっていい。ほかに含まれている鉱物はゴルセイ石といわゆるゴヤズ石様鉱物。また、六角ではなく球状の集合体も産出する。これは球の際外層が群馬石できているため、こっちのほうが群馬石の標本として実はふさわしいかも知れない。ただし六角結晶より産出がわかりづらく、蛍石か?とすら思える姿。この球も黄色に染まることがあり、それはやはりセグニット石やキントレ石が原因である。こうなるとかえってわかりやすい。
2度目の現地調査は小原氏と堀氏に案内をしてもらい、向かう前に堀氏のとっておきの標本を見せてもらった。それは丸箱に収まるほどの大きさで、半分に割れた真ん丸の芋の中心には水晶があり、その上に六角形の結晶がコロコロとついていた。見てきた中でこれが標本として最もバランスが良い。よしこれを採ろう。そう心に決めて現地に向かう。現場はやわらかい粘土が発達しておりそこから小芋がいくらでも出てくる。粘土はやはりセリサイトで、口に放り込むとまるで生キャラメルのごとくなめらか。しかし味はしないのでマズイ。それにあとから毒鉄鉱が出てきたのでやるべきではなかった。モノとしては白雲母が主体の白からやや緑の芋で、水晶が混じり込んでいるやつが良い。褐色に汚れている水晶は粗粒なものが多かったがそれに群馬石来ることはほとんどないようで、六角板状結晶あったがそれは白雲母だった。まぎらわしい。紫色の蛍石も少しだけあったが標本とするほどの質ではない。まれに灰色でカッチカチの芋が出てくるが、それはトパーズと石英の塊で特に面白いものは入っていない。日が暮れ、当地を後にして後片付けついでにと立ち話。聞くと、堀氏は愛知県の出身で先般の伊藤剛氏とは同級生だったとのこと。津久原というこの場をあとにする最後の一瞬に、一連の始まりである伊藤氏の名前が出てくるとは思わなかった。それにしても、なんというか、なんといえばいいのか、うーん・・・。

道すがらトリカブトの群生があった。ヤマカガシや大きなヒキガエルにも出会うなどやはりグンマー、森が深い。
群馬石は当地のラスボスであり、それをなんとかカタチにするところまで持って行けたのでこれでいったんゲームクリアとしたい。しかし、まだ裏ボスに相当するやつが残っている。それはここまで少しだけ出てきたいわゆるゴヤズ石様鉱物のことである。こいつは確実に群馬石よりも厄介で、なにしろ単独相かどうかすらまだ確信が持てない。なんかおかしいという感覚(データも)がずーっと付きまとっていて、まともに姿を現さないくせにいやらしく刺してくる。伊藤剛氏と高橋秀介氏は最初の犠牲者だったようだ。今回いったんクリアしたとはいえ裏ボス(ゴヤズ石様鉱物)を倒すにはまだまだレベルアップが必要で、強力な武器もほしい。パーティメンバーの追加さえも必要となるだろう。それらが手に入ったとき、私はまたここグンマーの秘境に足を踏み入れるかもしれない。
[1] 林昇一郎, 五十嵐俊雄 (1962) 群馬県勢多地区の放射能調査. 地質調査法月報, 13, 573-582.
IMA No./year: 2022-065
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-49723)
浅葱石 / Asagiite
NiCu4(SO4)2(OH)6・6H2O
Ktenasite group
愛知県新城市中宇利鉱山
Nishio-Hamane D., Yajima T., Shimobayashi N., Ohnishi M., Niwa T. (2022): Approved by CNMNC on October 3.
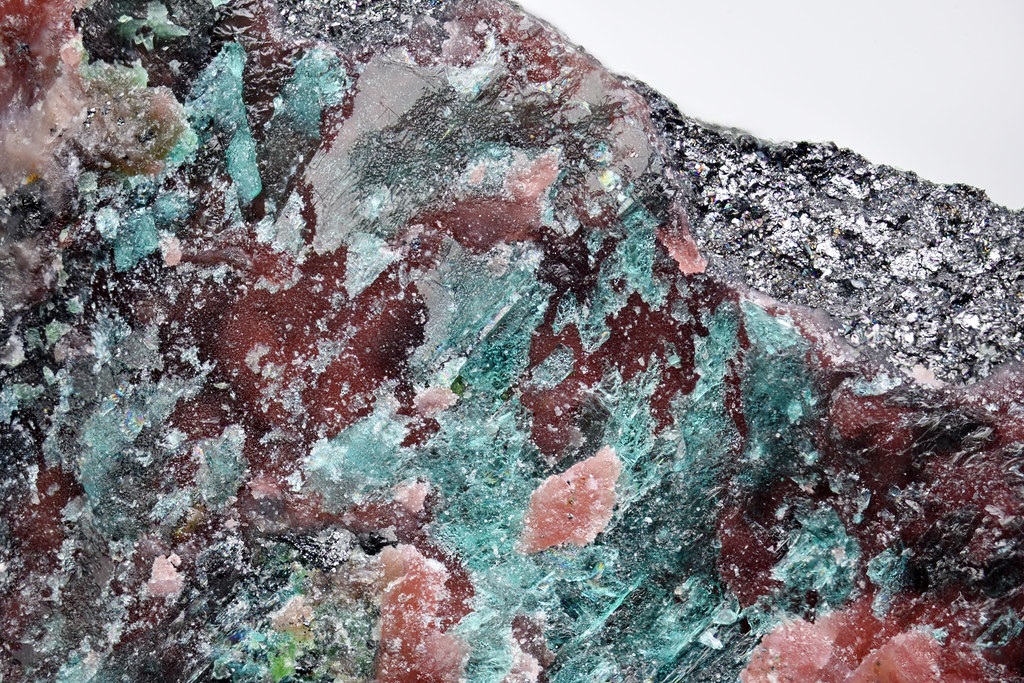
浅葱石の写真
愛知県中宇利鉱山を模式地とする独特な青緑色が鮮やかな新鉱物、浅葱石である。中宇利鉱山と言えば当地の名を冠する中宇利石(Nakauriite)がすでに有名であるが、このたび銘品がさらに一つ加わった。それにしてもしばらくぶりであろう。中宇利石が承認されたのが1976年なので、中宇利鉱山としては46年ぶりの新鉱物になるか。一つの産地から複数の新鉱物が見つかることはままあることだが、40年以上も間隔が空くことはめったにない。しかし、今回に限ってはそのくらいの時間が必要だったように思う。では時系列をたどってみよう。
中宇利鉱山の沿革について、伝え聞くところでは銅やニッケルを採掘していた鉱山とされる。ニッケルの利用は明治期以降に始まっているので、一般にニッケル鉱山の歴史はそう古いものではない。ではいつ頃かというのを調べてみると、1979年(昭和54年)の文献には「第二次世界大戦中(1939-1945年)に稼働していた」と書いてあり[1]、同じ著者は1993年(平成5年)には「40年前(1953年)まで稼働していた」と記した[2]。あれ?ズレてる。ほかの文献では「1953年(昭和28年)6月まで数か月試掘された」と記されており[3]、Mindat.には3か月と書いてある[4]。ただ、坑道のひとつは50mほども進んでいるらしいので3か月で至る規模にしてはちょっと大きい。そうしたところで書籍にもう一つ言及があり、「第二次世界大戦中にニッケルを採掘し、戦後の一時期に銅を試掘した」と記されていた[5]。文献からは詳細は分からずじまいだったが、大ざっぱな沿革としてはまあこんなものだろう。
中宇利鉱山に限らず、戦時中はニッケル目的の採掘が日本全土で盛んに行われていた。ニッケルは重要な軍事物質だったにも関わらず海外から輸入する道が断たれたからである。そのために商業コストは度外視であった。裏を返すと平時では経済価値に乏しい鉱床にすぎないため、戦後はあたりまえにことごとくが閉山となる。中宇利鉱山も戦後は山中で朽ち果てるのを待つだけだった。しかし、石というのは時間経過とともにたんにボロボロになるのではなく、その過程には様々な化学反応が伴われる。その化学反応はときに新たな鉱物を生み出すことがあり、そうして生まれた鉱物のことを二次鉱物と呼ぶ。そして、後年に中宇利鉱山はさまざまな二次鉱物の産地として注目を浴びることになった。その端緒は中宇利鉱山の近隣に位置する吉川鉱山から産出する白い鉱物だと思う。

ダイピング石
風化浸食をうけた蛇紋岩の裂傷などに生じることがある。日本では吉川鉱山で最初に見いだされ、すわ新鉱物かと期待されたものの・・
吉川鉱山もまた戦時中にニッケルを目的に稼働した鉱山で、中宇利鉱山の数kmほど北に位置する。同じく戦後は放置され、年月を経てその露頭には白色の魚卵状~腎臓状集合の二次鉱物が生成していた。その二次鉱物に注目したのが愛知教育大の鈴木重人だった。1973年(昭和48年)にネスケホン石(Nesquehonite: Mg(CO3)·3H2O)と未知の含水マグネシウム炭酸塩鉱物の産出を報告した[6,7]。1975年(昭和50年)にはそれが吉川石(Yoshikawaite)として学会などで報告され、この時点で新鉱物申請も行っていた旨の記述が認められる[8,9]。しかし吉川石は承認されなかった。吉川石の化学組成はMg5(CO3)4(OH)2·5H2Oであり、これは1970年(昭和45年)に承認されたダイピング石(Dypingite)と同じであった。構造データを比べるとダイピング石と吉川石は区別できるというのが鈴木の主張ではあったが、「だったらダイピング石を調べなおしたらいいじゃない(意訳)」と反論され、後年にやっぱり同じという結果が報告されている[10]。それを見るとデータとしては鈴木のほうがむしろ正しかった。しかし、先に発見・命名されているという優先権はいかんせん強く、ダイピング石の構造データが上書きされたことで決着となった。
ダイピング石は吉川鉱山に続いて中宇利鉱山からも見つかり、その際に鈴木はのちに中宇利石となる鉱物について「Namaqualith様鉱物」として産出を報告している[11,12]。そして、1976年(昭和51年)には新鉱物・中宇利石(Nakauriite)が申請され、年内に承認をうけた。中宇利石を発見した功績において、1977年(昭和52年)に鈴木は櫻井賞第14号メダルを受賞している。ただ残念ながら、鈴木が提案した化学組成は間違っていることが今や明白である[13-16]。さらには構造データも誤っている可能性が指摘されるに至り[17]、中宇利石は種の定義の根幹たる化学組成と結晶構造の両方が危うい状況になっている。ここまでだと優先権というものがどの程度の効力を発揮するかわからない。中宇利石を確たる鉱物種にとどめておくには強力なフォローアップ研究が必要になるだろう。

中宇利石
中宇利石は数ある日本産新鉱物のなかでも際立って美しく、発表当時はセンセーショナルなニュースとして石人界に受け止められたことだろう。
でもまあとりあえずその問題は置いといて、中宇利石は愛知県では初めての新鉱物であった。鮮やかなスカイブルーがとても美しく、産状もわかりやすい。中宇利鉱山はたちまち有名になり、そこからようやく産出鉱物がまともに記載されるようになった。蛇紋岩に含まれる初生的な鉱物について、1979年(昭和54年)に当時まだ珍しかったヒーズルッド鉱(Heazlewoodite: Ni3S2)とコバルトペントランド鉱(Cobaltpentlandite: Co9S8)が報告された[1]。戦時中はおそらくこれらを資源としていたのだろう。その後しばらくは何もなかったが、1993年(平成5年)になると菱ニッケル鉱(Gaspéite: Ni(CO3))、ニッケル孔雀石(Glaukosphaerite: CuNi(CO3)(OH)2)、マックギネス石(Mcguinnessite: CuMg(CO3)(OH)2)、ジャンボー石(Jamborite: Ni2+1-xCo3+x(OH)2-x(SO4)x·nH2O [x ≤ 1/3 n; ≤ (1-x)])などの産出が確認されている[2]。今度はいずれも二次鉱物であり、母岩である蛇紋岩の割れ目に着床する被膜として生じていた。初生鉱物であるヒーズルッド鉱やコバルトペントランド鉱、さらには輝銅鉱などが循環地表水と反応して生成したのだろう。1979年(昭和54年)の段階では軽く触れられるにとどまっていた二次鉱物が14年を経て目に見えるほどに成長した、ということでもあるだろう。そして、1993年(平成5年)からさらに約30年を経て令和の時代に突入した今、新たな二次鉱物がひっそりと誕生していた。

ヒーズルウッド鉱とコバルトペントランド鉱
肉眼的には一様に見えるが必ずこのペアになっている。
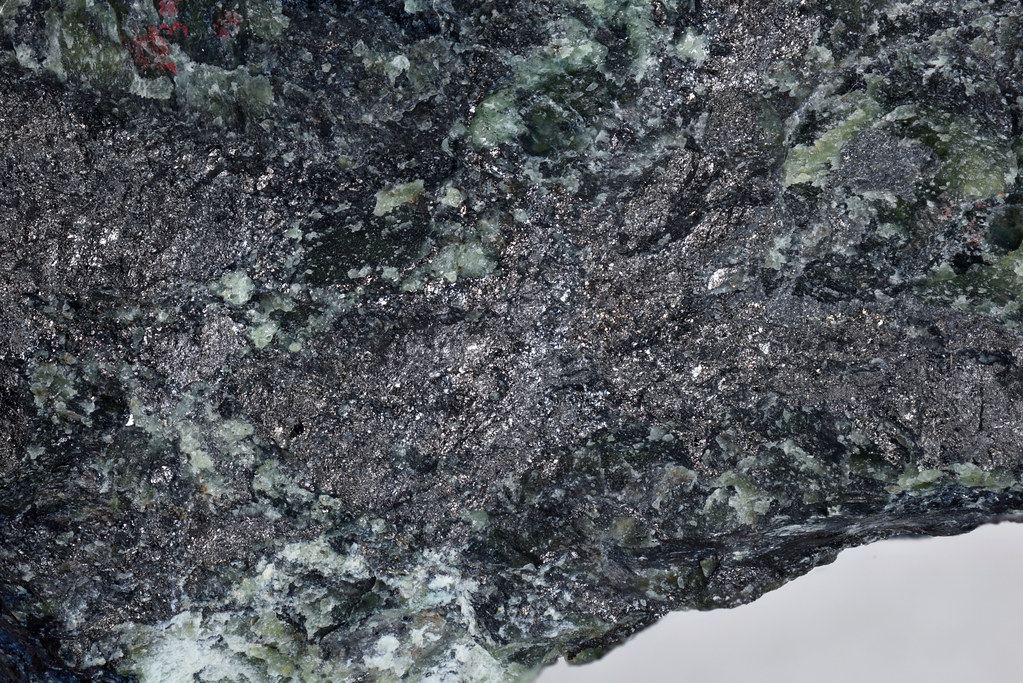
輝銅鉱
方輝銅鉱(Digenite)と言われることもあるが、X線粉末回折データを取ろうとして輝銅鉱をメノウ乳鉢でスリスリすると方輝銅鉱に相転移するため、そうしたデータが元になった産出記録だとほんとうに方輝銅鉱が産出するかどうかはわからない。ここでは輝銅鉱としておく。ジュルレ鉱(Djurleite)のこともあるだろうがよっぽど真面目に検証しないと区別は困難。

ニッケル孔雀石
標本としてはこうしたモコモコしたものがわかりやすいが、のっぺりとした被膜であることも多い。

水苦土石
中宇利鉱山の特産品ではなく風化した蛇紋岩には非常によく伴われる二次鉱物。

アルチニ石
これも蛇紋岩の風化に伴って典型的によく生じる二次鉱物。

カズナクト石(Kaznakhtite: Ni6Co3+2(CO3)(OH)16·4H2O)
中宇利鉱山のジャンボー石とされる標本はこのような色かたちをしている。そしてこうした標本のうち、硫黄が全く検出されずニッケルとコバルトの比率がきっちり3:1でぶれないものがある。それはジャンボー石ではなくカズナクト石に該当する。実はロシアで発見されて2021年に承認を受けたばかりの鉱物。

リーブス石(Reevesite: Ni6Fe3+2(CO3)(OH)16·4H2O)
これは皮膜状のジャンボー石とされる標本で、黄色が強いなーというもの。これもまた硫黄が全く検出されず、鉄がコバルトより多く含まれていた。これはリーブス石になる。

デソーテルス石(Desautelsite: Mg6Mn3+2(CO3)(OH)16·4H2O)
橙色部がデソーテルス石で、中宇利石(青)とアルチニ石(白)を伴う。ジャンボー石、カズナクト石、リーブス石、そしてデソーテルス石はすべてハイドロタルク石超族の鉱物。後半三つは以前には産出が知られていなかった。一方で過去に産出記録のあるジャンボー石にはついに出会うことがなかった。中宇利鉱山の二次鉱物は往時とはまた異なったものに変化してしまっていると思う。
平成の終わりから令和に入ったころの中宇利鉱山にはまた変化が訪れていた。1993年(平成5年)に産出報告のあった緑色の菱ニッケル鉱を覆うように、今度は赤~ピンク色の鉱物が成長していた。その独特な色とコバルトペンランド鉱が母岩にいることからそれは菱コバルト鉱と思われていたようだが、調べてみるとコバルトは検出されるものの量は多くなく、鉱物種としてそれは菱亜鉛鉱であった。これまで中宇利鉱山から亜鉛(Zn)を主成分とする鉱物は産出例がないため、まったくの不意打ちでちょっと驚いた。とは言え、これは学会や論文で発表するほどの新規性・重要性はない。写真をホームページで紹介するだけにしていた。

菱ニッケル鉱(緑色)と菱亜鉛鉱(ピンク色)
菱亜鉛鉱は皮膜状の菱ニッケル鉱の上に生じており、菱亜鉛鉱は明らかに後発の生成。
さて。鉱物を採集するだけでなく自ら科学的に検証する市井の愛石家は昔から少なからずいて、そうした方が自ら新鉱物を発見することがある。今回もそうだった。2020年(令和2年)も末のこと、丹羽健文氏はピンク色被膜の上に生じたガラス光沢を示す青緑色の鉱物を採集し、自らラマン分光法という手法でそれを調べた。そして亜鉛を含む二次鉱物であるクテナス石(Ktenasite)の可能性が浮かんだところで電顕室のホームページでピンク色被膜が菱亜鉛鉱ということを知り、その上に生じるのなら妥当だと納得した。続いて、クテナス石である確証(化学組成と結晶構造)を得るために詳細の検討が京都大学の下林氏に依頼され、化学組成分析によって亜鉛の存在が確認されると共に、ニッケル(Ni)もまた多く検出された。そしてこの少し前、クテナス石の化学組成の定義が変わっていた。

クテナス石(ノルウェー産)
ギリシャで最初に見つかった鉱物で、ヨーロッパには産地が多いものの日本にはなぜか少ない。
クテナス石はもともと(Cu,Zn)5(SO4)2(OH)6·6H2Oという化学組成式で表現されていた。こういった書き方だと「銅(Cu)と亜鉛(Zn)が結晶構造の中で同じ場所にあってかつ銅が多い」と解釈される。これだと他の元素が銅より多くならなければ新鉱物にはならない。しかし事情が変わっていた。研究が進んだ結果として、クテナス石の化学組成式はZnCu4(SO4)2(OH)6·6H2Oへ改訂されていた。それが2019年(令和元年)のことで[18]、銅と亜鉛は結晶構造内で別の場所にいることが判明した結果だった。そうなると亜鉛を別の元素が置き換えたならば新鉱物になる。そうして丹羽氏の採集した鉱物の組成をあらためて眺めると、明らかに「ニッケル>亜鉛」の組成であり、クテナス石のニッケル置換体として新鉱物の可能性が浮かんでいた。
一方で、事態は急を要していたとも言える。丹羽氏がその鉱物を見出した2020年(令和2年)、実はすでにオーストラリアの研究チームによってクテナス石のニッケル置換体の研究が進められていた[19]。そして、下林氏から私のところへ詳細を詰めてほしいという依頼があったのが2021年(令和3年)の12月。これはもはや手遅れかと思いきや、この時点でもクテナス石のニッケル置換体はなぜかまだ申請されていなかった。なにか問題があって進んでいないのだろうか。わざわざ論文に検討中である旨を記したあたり、唾をつけているのだから手を出すなという意味合いなのかもしれない。だが断る。新鉱物は競争であり、本来だまってただ申請書を出せばいい。さあ間に合うか。我々の申請書は2022年(令和4年)6月に提出され、クレームもなく受付された。どうやら優先権争いには勝ったようだ。今回は物性研の矢島氏と愛石家の大西氏の協力も得て申し分のないデータがそろっていたため、そこに不安は全くない。しかし、ひとつ読めないことがあった。新鉱物は鉱物学的データと名前(+理由)、そのどちらもが審査を受ける。
このたび申請した新鉱物、その名を浅葱石(Asagiite)という。実はこの名前がどうなるか読めなかった。新鉱物の名称は学術関係者や産地にちなむことが多く、奇抜な由来は撥ねられる。そして浅葱石の由来は「浅葱色」であった。浅葱色(あさぎいろ)とは蓼藍(たであい)で染めた明るい青緑色を指し、それを薄い葱(ねぎ)の葉にちなんでそう呼んだ。平安時代にはその名が見られる日本古来の伝統色となっている。そして、色にちなんだ鉱物名はたしかに過去に例がある。ただ、それらはギリシャ語やラテン語が元となっており、分類学という古典的な性格からしてそういった古いヨーロッパ言語は好まれる。しかし、今回はヨーロッパ言語とは縁もゆかりもない日本語での色表現を由来としており、当然、記載鉱物学史を振り返っても過去に例がない。そんなところで丹羽氏は浅葱色をさくっと提案してきた。そのアイデアは新鉱物申請の経験者からはかえって出ないものだろう。その柔軟で無邪気な発想に乗っかり、初めての挑戦へ向かっていった。

浅葱石(模式標本)と浅葱色の見本(右上)
新鉱物の申請書にはこのように写真に色見本をつけて説明した。
そして、2022年(令和4年)10月。浅葱石は満票で承認された。結果的に名称への心配は杞憂に終わった。日本の委員会からのアドバイスに従って浅葱色の見本を写真に挿入したのも功を奏したと思う。こうして中宇利鉱山から46年ぶりとなる新鉱物が誕生したのだった。という流れである。では浅葱石の解説に移ろう。

浅葱石(第二標本)
模式標本とは色合いが違う。これが最初に出てきた標本だったらどういう名前になっていただろうか。
浅葱石の標本は二種類ある。というよりまだ二つしか見つかっていない。模式標本は蛇紋岩を母岩として見える範囲には磁鉄鉱や輝銅鉱があった。そして、赤色のやや深い菱亜鉛鉱の被膜があり、その上に浅葱石が生じている。模式標本の浅葱石は不定形な結晶だったが、へき開が完全なのでその部分でチカっときらめく。それはルーペがあれば認識できるサイズで、ガラス光沢を示す透明感のある浅葱色が典型的だった。聞いた話だと中宇利鉱山にはブロシャン銅鉱が産出するらしい。その標本は個人的に見たことがないが、それは紛らわしいかもなと予想する。また、もしそれが菱亜鉛鉱の上に来ているのならもしかするともしかして・・なのかもしれない。また、申請したのちに出てきた第二標本はちょっと色合いが異なり、青みが弱く緑がやや強く出ているため、第二標本が先にあったら浅葱石という名称は提案されなかったかもと感じた。第二標本の浅葱石の下地は一見して褐鉄鉱のように見えるが、やはり菱亜鉛鉱~菱ニッケル鉱であり、その上に生じる点で模式標本と共通する。そのため成因もおそらくは同じと思う。例えば蛇紋岩中に生じたポケット状の亀裂に天水が留まり、まず炭酸塩鉱物が生じ、その後に浅葱石が生成したのだろう。ただし、化学組成について模式標本と第二標本はやや異なっていた。模式標本はニッケル>亜鉛>>コバルトの組成だが、第二標本はニッケル≧コバルト>マグネシウム>亜鉛という組成であった。こうした化学組成の違いがおそらく色に影響している。ちなみに、コバルトが支配的だとゴベリン石(Gobelinite)、マグネシウムが支配的だとフェアー石(Fehrite)という。中宇利鉱山からは浅葱石のほかにはゴベリン石の産出が確認されている[20]。その見た目は第二標本そのものであり、浅葱石かゴベリン石かというのは肉眼で区別はできない。もし見つけたらラベルには両方の名を書いておけばいいだろう。ただし、現地に探しに行くにしても急峻な露頭には近づかないようにしてほしい。坑道が残っていたとしてもそれは絶対に入るべきではない。蛇紋岩はとんでもなく恐ろしい岩石で、叩いた場とはまったく無関係に思っていた後方がいきなりバサッと落ちたりもする。鉱山近くの露頭ではかつて崩落事故があった。それにピンク色の菱亜鉛鉱はすでに姿を消したと聞いている。今となっては手持ちの標本から探すしかなく、それで見つからなければ浅葱石についてはすっぱりあきらめよう。
愛知県の新鉱物としてみたとき、浅葱石は中宇利石と白水雲母(Shirouzulite)に続いて3例目。有効な日本産新鉱物というカウントだと浅葱石でちょうど150種になった。それだけあって色を由来としたのは浅葱石のみ。新鉱物にいつも根源名を授けられるとは限らないが、これまでは発想があまりにも硬直化していたようだ。それに気づけたことが今回のよかったところ。これで新しい扉が開いた。
[1] Matsubara S., Kato A. (1979) The occurrence of heazlewoodite and cobaltpentlandite from the Nakauri mine, Aichi Prefecture, Japan. Memoirs of the National Science Museum (Tokyo), 12, 3-11.
[2] Matsubara S., Kato A. (1993) Gaspeite, glaukosphaerite, mcguinessite and jamborite in serpentinites from Shinshiro City, Aichi Prefecture, Japan. Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 88, 517-524.
[3] 安形昭夫 (1954) 中宇利銅鉱山およびその付近の銅鉱床について. 地学しずはた, 4, 11-12.
[4] https://www.mindat.org/loc-2191.html
[5] 加藤昭, 松原聰, 野村松光 (1979) 鉱物採集の旅 (5) 東海地方をたずねて. 築地書館, pp.169.
[6] 鈴木重人, 伊藤正裕 (1973) 愛知県吉川産Nesquehonite. 日本地質学会第80年学術大会講演要旨, P246.
[7] Suzuki J., Ito M. (1973) A new magnesioum carbonate hydrate mineral, Mg5(CO3)4(OH)2・8H2O, from Yoshikawa, Aichi Prefecture, JAPAN. The Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 68, 353-361.
[8] 鈴木重人, 伊藤正裕, 杉浦孜 (1975) “Yoshikawaite”, HydromagnesiteのDTA発熱ピークの解釈. 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, P76.
[9] 鈴木重人, 杉浦孜, 伊藤正裕, 都築芳郎 (1975) “Yoshikawaite”愛知県吉川産の含水マグネシウム炭酸塩鉱物の一つ,
[10] Canterford J.H., Tsambourakis G., Lambert B. (1984) Some observation on the properties of dypingite, Mg5(CO3)4(OH)2·5H2O, and related minerals. Mineralogical Magazine 48, 437-442.
[11] Suzuki J., Ito M., Sugiura T. (1976) A new copper sulfate-carbonate hydroxide hydrate mineral, (Mn,Ni,Cu)8(SO4)4(CO3)(OH)6·48H2O, from Nakauri, Aichi Prefecture, Japan. Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 71, 183-192.
[12] 伊藤正裕, 鈴木重人, 杉浦孜(1975)愛知県中宇利産Namaqualith様鉱物について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 70, 139.
[13] Braithwaite R.S.W., Pritchard R. (1983) Nakauriite from Unst, Shetland. Mineralogical Magazine, 47, 84-85.
[14] Palenzona A., Martinelli, A. (2007) La nakauriite del Monte Ramazzo, Genova. Rivista Mineralogica Italiana, 31, 48-51.
[15] 錦郡雄基, 池内大起, 中野良紀, 小林祥一, 岸成具(2017)岡山県北房地域に産するMgに富むnakauriite. 日本鉱物科学会2017年年会講演要旨集, R1-P09.
[16] Chukanov N.V. and Vigasina M.F. (2019) Some Examples of the Use of IR Spectroscopy in Mineralogical Studies. In Vibrational (Infrared and Raman) Spectra of Minerals and Related Compounds, 1-17.
[17] 錦織雄基, 門馬綱一, 宮脇律郎, 小林祥一, 岸成具 (2018) 岡山県北房産Mgに富むnakuriiteの結晶構造の検討. 日本鉱物科学会2018年年会講演要旨, R2-P03.
[18] Miyawaki R., Hatert F., Pasero M., Mills S.J. (2019) IMA Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) Newsletter 52. New minerals and nomenclature modifications approved in 2019. Mineralogical Magazine 83, 887-893.
[19] Mills S.J., Kolitsch U., Favreau G., Birch W.D., Galea-Clolus V., Henrich J.M. (2020) Gobelinite, the Co analogue of ktenasite from Cap Garonne, France, and Eisenzecher Zug, Germany. European Journal of Mineralogy, 32, 637-644.
[20] 下林典正, 高谷真樹, 浜根大輔, 大西政之, 丹羽健文 (2022) 愛知県中宇利鉱山から産出するゴベリン石およびそのNi置換体. 日本鉱物科学会2022年年会, R1P-12.
IMA No./year: 2022-002
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-49380)
ベタフォ石 / Oxyyttrobetafite-(Y)
Y2Ti2O6O
Pyrochlore supergroup
三重県菰野町宗利谷
Nishio-Hamane D., Momma K., Ohnishi M., Inaba S. (2022): Approved by CNMNC on April 2.
マダガスカルにその名のルーツを持つ三重県生まれの新鉱物、ベタフォ石(oxyyttrobetafite-(Y))である。年季の入った愛石家ならベタフォ石の名は聞いたことがあるだろう。それもそのはずで、もともとベタフォ石は1912年(明治45年/大正元年)に発表された古典的な鉱物であった。マダガスカルのベタフォ地区から最初に発見されたことから名称が定められ、かつては日本を含め世界各国から産出が報告された。ところが紆余曲折あって、実はこれまでに報告されたベタフォ石のすべてが無効とされている。つまり、今回の新鉱物を申請した時点でベタフォ石の名を冠する鉱物は公式にはひとつも存在しなかった。その状況にあって初めての有効なベタフォ石として承認されたのが今回の新鉱物である。学名はOxyyttrobetafite-(Y)であり、この学名をそのまま和名にすると「イットリウムオキシイットロベタフォ石」もしくは「イットリウム酸化イットロベタフォ石」となるだろう。が、長い、うっとうしい。そこで、この記事ではたんに「ベタフォ石」と呼ぶことにして、必要に応じて「最初の」や「今回の」という修飾語などを用いて区別する。今回は鉱物分類の話から入ろう。
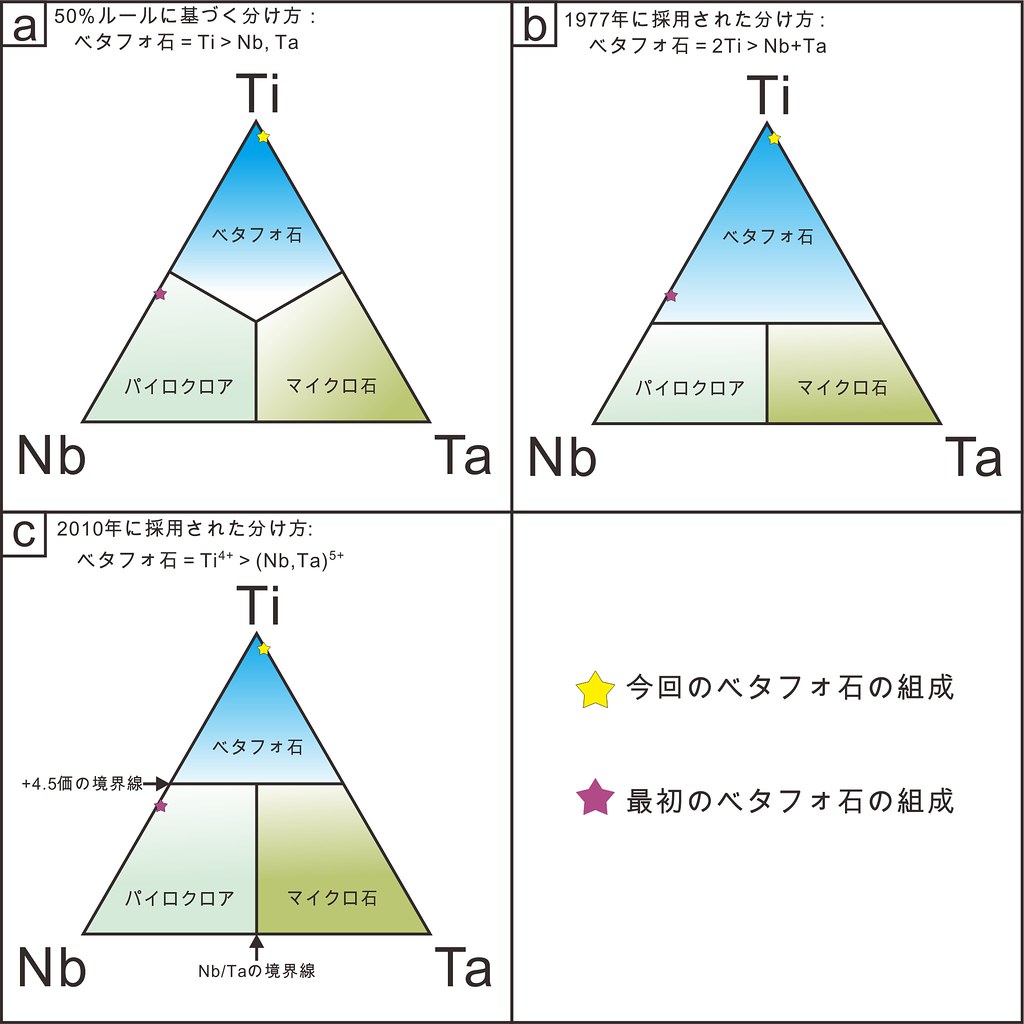
パイロクロア―マイクロ石-ベタフォ石分類の考え方
「c」が最新の分類・境界線であるが、過去にはこれとは違った考え方もあった。
さて、ベタフォ石はパイロクロアやマイクロ石の仲間である。その違いを簡単に述べると、チタン(Ti)に富むベタフォ石、ニオブ(Nb)に富むパイロクロア、タンタル(Ta)に富むマイクロ石という住み分けである。上の図「a」は化学組成の中間(50%)で種を分ける考え方で、最初のベタフォ石の分析値[1]を紫の星で示した。見てのとおりで、中間で種を分けるなら最初のベタフォ石はそもそも新種などではなくパイロクロアである。ただ、古い時代は化学組成の中間で種を分けることがそもそも共通認識ではなかった。それどころか境界をもっと細かく刻む傾向が強く、ちょっとした差異を過大に喧伝して独立種を主張することもしばしばあった。1912年(明治45年/大正元年)という時代に発見されたベタフォ石もその例に漏れない。最初のベタフォ石は端成分のパイロクロアに比べるとTiに富んでおり、ウラン(U)もまた副成分として多く含まれていた。それらを理由にベタフォ石はパイロクロアとは異なる独立の鉱物だと主張されたのだった[2]。
しかし、時代が下ると上述のような主張は受け入れられなくなる。そこで1977年に命名規約が誕生した[3]。その考え方を図「b」に示している。ぱっと見でベタフォ石の領域が大きいことがわかるだろう。この命名規約は「NbやTa端成分はたくさん報告があるが、Ti端成分はまったく報告がない」ことを理由としてTi(ベタフォ石)を優先することを決めた。今後は2Ti > Nb+Taをベタフォ石にするという宣言であり、最初のベタフォ石の組成であってもこれならばパイロクロアとは別の種として分けられた。しかし、どうだろう。これはベタフォ石ありきとなるよう都合の良い報告を理由としてこじつけただけにも見える。昨今でそんな主張をしようものならむしろ叱られるが、ともかくこれでベタフォ石の定義がいったん固まった。この時代以降は電子顕微鏡による分析が急速に発達・普及したこともあいまって、ベタフォ石の産出は世界中から報告されるようになっていく。
さらに時代が下り、1990年代後半になって鉱物の定義や分類が明文化されると、過去の危うい分類体系・命名規約が見直される機会が次第に多くなっていく。そして、ベタフォ石をみだりに優遇した1977年分類がついに槍玉に挙げられ、2010年に命名規約はまた改められた[4]。このときに登場した新たな分類が図「c」であり、これは化学組成について中間で分けることを提案し、中間ということを価数でも考慮してある。つまり「チタン(4価)とニオブやタンタル(5価)の中間は4.5価」という考え方であり、混合価数の固溶体はこのやり方(Dominant-valency rule)が今では公式に推奨されている[5]。ともかくこの2010年命名規約によって最初のベタフォ石はやっぱりパイロクロアに分類されることが確定した。そして、これまでにベタフォ石を冠していた鉱物も精査され、そのあげくにことごとく一掃される事態が起きている[6,7]。つまりベタフォ石は2010年でいったん消滅した。それでも「ベタフォ石=Ti端成分」という概念だけは有効のままとされ、ベタフォ石は実体がないものの名称のみが生き残った。その後、ベタフォ石の名称を冠する鉱物がまったく存在しない状態が12年も続き、2022年の今になってようやく誕生したのが今回のベタフォ石(oxyyttrobetafite-(Y))である。現状では当然ながらベタフォ石を冠する唯一の鉱物でもある。その化学組成は黄色の星でプロットしてあり、Ti端成分の近くにプロットされる。端成分はちゃんと天然に存在するのだから、1977年分類の根拠になった考え方はやっぱりただの屁理屈に過ぎなかったのだ。

パイロクロア型構造
パイロクロア超族の結晶構造にはA, B, X, Yの4つの結晶学的席があり、さまざまな元素の組み合わせが可能で、空孔や水分子すらも許容する。
さて、ベタフォ石はパイロクロア構造を有する鉱物であり、分類としてはパイロクロア超族として括られる。パイロクロア超族はA2B2X6Yという一般式において、BとXの内容でさらに族が細分され、いまのところ、パイロクロア族(B = Nb5+, X = O)、マイクロ石族(B = Ta5+, X = O)、ベタフォ石族(B = Ti4+, X = O)、エルスモア石族(B = W6+, X = O)、ローメ石族(B = Sb5+, X = O)、ラルストン石族(B = Al3+, X = F)、コウルセリ石族(B = Mg2+, X = F)がある。さらにA、X、Yの内容によって個々の種が分けられ、学名のつけ方にまでガチガチの縛りがある。学名はY→A→(B+O)の順で表すことが決められている。今回のベタフォ石を例にとると、Y =酸素(O); oxy、A =イットリウム(Y); yettro、B = チタン(Ti) & X = 酸素(O); betafiteで「oxyyettrobetafite」となる。さらにこれにLevinsonルール[8]が適用されるため、含まれている希土類元素を接尾語で「-(REE)」で追加しなくてはならない。ここではイットリウムなので「-(Y)」となり、yettroと意味が重複するものの、最終的に「oxyyettrobetafite-(Y)」が正式な学名になる。このような命名ルールのためにまるで「頭痛が痛い」ような違和感のある学名にならざるをえなかった。そして、このような決まり事がほかの業界へ浸透するはずもない。例えば今回のベタフォ石の化学組成はY2Ti2O7であり、これに構造名を加えて「Y2Ti2O7パイロクロア」と呼ぶほうがずっと簡単でわかりやすい。実際に「化学組成+構造名」という用法はかなり広く普及しているため、正式な鉱物名が定まったからといって他の分野では使ってもらえるとは限らない。今回のベタフォ石は間違いなくその典型で、記載鉱物学以外の分野では登場しない名称になる。
パイロクロア超族の鉱物は今回のベタフォ石を含めて33種類が知られている。これはなかなかの数で、複雑な元素組み合わせや空孔を易々と受け入れる構造の柔軟性ゆえであろう。合成物質に目を向けると、物性物理業界では実にさまざまなパイロクロア物質が開発されている。上に掲載したのは私が所属する物性研究所で研究されているCd2Re2O7とHg2Os2O7の組成をもつパイロクロア物質である。天然物を扱う身からすればこのような珍妙な元素組み合わせは変態的にすら感じられるが、いずれも妖しく美しい結晶となる。今回のベタフォ石の姿はというと、それはまあもうちょっと後で。
ここからは新鉱物との出会いについて述べていく。今回のベタフォ石は共著者の稲葉氏からやってきたのだった。稲葉氏は三重県在住の愛石家であり、今回の新鉱物を含めた三重県産の新鉱物10種のうち7種の発見に携わっている。それほどの稲葉氏であっても三重県菰野町宗利谷から報告された二つの新鉱物、苦土ローランド石(magnesiorowlandite-(Y))と三重石(mieite-(Y))の発見には縁がなかった。そこで稲葉氏は三重県産鉱物を網羅するべく、それらが報告されてすぐさま産地である菰野町宗利谷の探索を始めた。それからしばらくして稲葉氏から標本が送られてきた。たしか2016年の夏のことで、二つの標本にはそれぞれ苦土ローランド石および三重石ではなかろうかというメモが付せられていた。
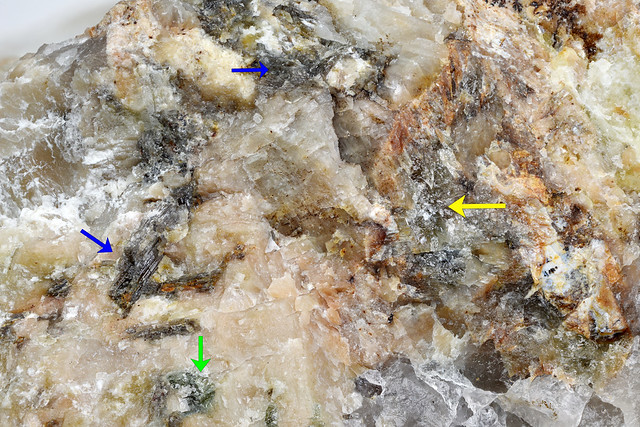
稲葉氏から来た一つ目の標本
青矢印:褐簾石、黄色矢印:苦土ローランド石、緑矢印:ガドリン石
一つ目の標本についてはメモ通りに苦土ローランド石を引き当てていた。さすがである。苦土ローランド石は新鮮な場合だとやや緑色を帯びた灰色で、ガラス光沢を示す。破断面は貝殻状に近いようで明瞭なへき開は感じられないものの、形状は板状に見える。他に何もいなければ割ってすぐわかると思う。ただし、周りに褐簾石がいると区別はけっこう悩ましい。褐簾石に典型な柱面が出ていれば判別しやすいが、破断面だとどちらも貝殻状なのであとは色をあてにするしかない。褐簾石のほうがやや色濃く、微妙に褐色が感じられる。また苦土ローランド石については乳白色に変質することがあり、ガラス質の部分をぐるっと取り囲むことも鑑定ポイントだろうか。そのほかにガドリン石も同席することがあるが、これは上の二つとは異質なのでそれはまあ見ればわかる。いずれにしても産状はペグマタイトであり、長石質であった。

稲葉氏から来た二つ目の標本
当初は左側の乳白色の部分だけが表に出ていた。後に割ってみると中身は棒状の組織で、そのわきには緑色のガドリン石が来ていることが分かった。最終的に上が模式標本となり、下は分析のために一面を研磨して手元に残した。
さて、二つ目の標本には三重石?というメモがついていた。当初、この標本は上の写真のように割れておらず、赤丸で示した箇所の一部が見えているだけで、調べたがそこは何かの分解物なのか複数相が混合していた。結局よくわからずじまいで、標本は「未同定」の引き出しに収まることになった。分析してもすぐに答えが出ないことは実はそれなりにあって、後になにかのきっかけで事態が動き出すこともある。とは言え、いつ訪れるとも限らないきっかけを永遠に待つこともまたできない。このたびは2021年の春先に引っ越したことを契機にいくらか整理することにした。そうして約5年ぶりに目にしたこの標本には未来がないように思え、それでは処分しようとハンマーで小突いたらきれいに真っ二つに割れた。一部しか見えていない状態では気づきようもなかったが、全体は棒状の集合体だったようで、その中に褐色の粒がまばらに入っている。外周部の緑色はガドリン石にみえるが、さて、褐色粒はなんだ?フェルグソン石か? なんか気になる・・

ベタフォ石(oxyyettrobetafite-(Y))の写真。
ベタフォ石はガラス光沢を示す透明感のある不定形な褐色粒として産出する。ベタフォ石が埋まっている基質はタレン石(thalénite-(Y))。褐色粒はほかにエシキン石(aeschynite-(Y))があり、それより黒色の微細粒はトール石(thorite)や方トリウム石(thorianite)で、いずれも見た目での区別は難しい。ベタフォ石は棒状集合の中心付近に集中する傾向がある。
これが今回の新鉱物ベタフォ石であった。処分するつもりで割ったらなんと新鉱物。しかも、かのベタフォ石。マダガスカルにその名のツールを持つ110年前に命名された古典鉱物で、希元素鉱物愛好家ならば知らぬ人のない鉱物でありながら、存在を否定されて幻となった鉱物、それがベタフォ石。その幻がほぼ端成分で日本産の新鉱物として生まれ変わったわけだから、さすがに驚いた。その後にほかの標本を稲葉氏に探してもらってあと数個体だけなんとか見つかり、その標本は稲葉氏と共著者の一人である大西氏に託した。また共生関係として先の新鉱物である苦土ローランド石がいるとベタフォ石はいないようだ。調べた範囲では苦土ローランド石にも褐色粒は伴われるがそれはエシキン石ばかりで、まれにフェルグソン石がいる程度であった。それにしても三重石がついに見つからなかったことは心残りである。
産地である宗利谷は地質図をみると堆積岩にできた谷になっている。近隣には花崗岩が分布しているようだが、現在ではそれが転がってくるような地形になっていない。それなのに、花崗岩ペグマタイトを母岩として三種もの新鉱物が発見されていることは奇妙だと感じていた。それでも実際に訪れてみると河原にはたしかにペグマタイトが転がっている。しかし非常に少なくいずれも小さい。観察や聞いた話なども総合するに、ペグマタイトは現時点で上流に露頭があるのではなく、今の地形になるよりもずっと以前に土砂もろとも堆積し、それが谷地形となった今になってようやく顔をのぞかせたという状況である。これだとおいそれとは石が更新されない。ただ、周囲の植林はよく管理されておりいずれ出荷されるようにみえた。その際は林道が開削されるだろうから、大きな変化はそれに期待することになるだろう。
最後にまた分類の話に戻るが、ベタフォ石についてもう少し述べておく。2010年命名規約はベタフォ石をいったんすべて抹消したが、実在する可能性の高いベタフォ石を二つ挙げている。そのひとつが酸化灰ベタフォ石(oxycalciobetafite)であり、(Ca,□)2Ti2O6Oが理想化学式となる。それはアポロ14号の着陸地点である月のFra Mauro高地で最初に発見されたが、構造データが取得されていなかった[9,10]。そして、酸化灰ベタフォ石は日本からも見つかっており、2012年には愛媛県弓削島から産出が報告されている[11]。ただこれもまた組成だけの報告であって構造データは無い。構造データまで検討された酸化灰ベタフォ石は福岡県糸島市御床のものがある[12]。こうした状況から酸化灰ベタフォ石については実在性がほぼ確実である。もうひとつ実在しそうなのは(U,□)2Ti2O6Oを理想化学組成とする酸化ウラノベタフォ石(oxyuranobetafite)であり[13]、これもまた月(Luna 24 landing site)で見つかったが構造データがないために鉱物種として認められていない。ともかく、ベタフォ石を冠する鉱物が今後に増える可能性は十分にあって、酸化灰ベタフォ石については日本産として誕生するところまであと一歩まで迫っており、それがカタチになることを願っている。
[1] Lacroix A. (1912) Quelques nouvelles observations sur les minéraux uranifères de la province d’Itasy (Madagascar). Bulletin de Minéralogie, 35, 233-235.
[2] Hogarth D. D. (1961) A study of pyrochlore and betafite. The Canadian Mineralogist, 6, 610-633.
[3] Hogarth D. D. (1977) Classification and nomenclature of the pyrochlore group. American Mineralogist, 62, 403-410.
[4] Atencio D., Andrade M.B., Christy A.G., Gieré R., Kartashov P.M. (2010) The pyrochlore supergroup of minerals: nomenclature. The Canadian Mineralogist: 48: 673-698.
[5] Bosi F., Hatert F., Hålenius U., Pasero M., Miyawaki R., Mills S. (2019) On the application of the IMA-CNMNC dominant-valency rule to complex mineral composition. Mineralogical Magazine, 83, 627-632.
[6] Christy A.G., Atencio D. (2013) Clarification of status of species in the pyrochlore supergroup. Mineralogical Magazine, 77, 13-20.
[7] Atencio D. (2021) Pyrochlore-supergroup minerals nomenclature: an update. Frontiers in Chemistry, 9, 713368.
[8] Bayliss P., Levinson A.A. (1988) A system of nomenclature for rare-earth mineral species: revision and extension. American Mineralogist, 73, 422–423.
[9] Meyer C., Yang S.V. (1988) Tungsten-bearing yttrobetafite in lunar granophyre. American Mineralogist, 73, 1420-1425.
[10] 文献[9]はyttrobetafiteという名称で報告したが内容はCa>Yであり、現在の命名規約ではこの組成はoxycalciobetafiteになる。
[11] 大越 悠数, 皆川 鉄雄(2012)愛媛県弓削島産ベタフォ石グループ鉱物. 岩石鉱物科学, 41, 129-132.
[12] 上原誠一郎, 延寿里美, 岩野庄一郎(2013)福岡県糸島市御床産”ベタフォ石-パイロクロア石”の再検討. 日本鉱物学会2013年年会, R1-06.
[13] Mokhov A. V., Kartashov P. M., Bogatikov O. A., Ashikhmina N. A., Magazina L. O., Koporulina E. V. (2008). Fluorite, Hatchettolite, Calcium Sulfate,and bastnasite-(Ce) in the Lunar Regolith from Mare Crisium. Doklady Earth Sciences, 422, 1178-1180.
IMA No./year: 2021-041
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-48724)
桐生石 / Kiryuite
NaMn2+Al(PO4)F3
The Mn2+ analogue of Viitaniemiite
群馬県桐生市梅田町津久原
Nishio-Hamane D., Ikari I., Ohara Y. (2021): Approved by CNMNC on August 4th.
群馬県桐生市から見出された新鉱物、桐生石である。私自身はこれまで関東からの新鉱物に縁がなかったので、ようやくたどり着いたという感慨がある。関東の中で群馬県はこれまで最も多くの新鉱物が見つかっている県であり、若林鉱(1969年)からはじまり、長島石(1977年)、鈴木石(1978年)、南石(1982年:後年に亜種へ分類)、アンモニオ白榴石(1984年)が知られている。それから永らく続報がなかったが、群馬県産として6番目で37年ぶりに桐生石が新鉱物として誕生した。こうして並べると気づく人もいるだろう。群馬県の地名が鉱物の名前になったのは桐生石が初めてになる。新鉱物の申請書は猪狩一晟氏と小原祥裕氏との連名で提出された。
桐生については「桐が多く自生する土地」から「桐生」、もしくは「霧が多く発生する土地」から「霧生」が由来だと伝わっている。そして、鎌倉時代に成立した吾妻鏡において桐生の名称は初めて歴史に登場し、桐生六郎なる人物が記された。古来より地名を苗字とする例は多く、想像するに鎌倉時代までには桐生という地名は定まっていたのだろう。今ではその頃の桐生や飛び地も巻き込んでの桐生市であり、群馬県に所属する。そして新鉱物の名前について今回は地名から採用しようと思い立ったところで、候補を考えるものの、発見地を含む集落名ではあまりにも小規模な印象があった。かといって大きく出て県名にすると境目問題とまではいかなくとも沿革が頼りない。境目を気にしないやり方としてはかつての文化圏としての「毛野」があるが、これは呼び名が定まってないことが悩ましい。ともかく地名の候補をいろいろ並べて考え、ここはやはり古来より名が知れて音の響きもよい桐生にしようと最終的に決断して、産地である桐生市にちなんで桐生石と命名した。
産地は桐生市の北東部に位置する梅田町津久原(つくばら[1])にある。その津久原にはかつて鉱山があり、津久原鉱山や梅田鉱山と呼ばれたと伝わっている。そこで地質図Naviを用いて20万分の1地質図(宇都宮)を見ると、一帯にはマンガン(Mn)鉱山ばかりたくさんあるなかで、当地のみタングステン(W)鉱山の印が打たれている[2]。ところがある文献[3]には銅(Cu)や銀(Ag)を目的に採掘されたと記されており、タングステンの記述はない。また別の文献[4]では珪石鉱床とだけあって金属資源には触れられていないなど、文献だけ見るとわけがわからない。それでも当地を訪れてみると、とにかく石英脈に沿って開発が行われていたことが残された坑道から見て取れた。この辺りは付加体(堆積岩)であるが、近隣に花崗岩が貫入しているため全体的にやや熱変成を受けている。鉱床を伴う石英脈も花崗岩の影響で派生したのだろう。ただし、桐生石はかつての鉱山跡ではなく、そこからやや離れた地点に走る石英脈から見出された。そして、その石英脈にはタングステン、銅、銀は伴われず、むしろこの一帯では当たり前のマンガンが伴われていた。そう、桐生石はマンガン鉱物なのである。
前置きはこのくらいにして、今(2021年)から8年前の出来事から述べていこう。今回の話の主人公である小原氏は地質図を参照し、マンガンばかりの中にあって異彩を放つタングステンの印に興味を持ったことで2013年の真夏に津久原鉱山を初めて訪れた。津久原鉱山はこの時点で閉山して久しくあまり注目されていなかったが、水晶が得られる場として知る人ぞ知る産地であった。当地で得られる水晶は群晶となるものの茶色に汚れていることが多く、一般にこういった水晶はいきなりシュウ酸溶液に入れて汚れを除いてしまいがちであるが、小原氏は汚れた標本であっても注意深く観察を行い、ちいさな隙間に二次鉱物が伴われていることに気が付いた。スコロド石、毒鉄鉱や洋紅石が伴われていることが判明し、さらに黄色の六角形を示す見慣れない鉱物がひそんでいた。

褐色に汚れた石英
こういった石英はそもそも採集対象にならないか、採集しても観察するまでもなく洗浄されることが多い。そうした手慣れた行動の裏にこそ新しい発見が隠れている、かもしれない。
それから約5年後の2018年春、福島県御斎所鉱山を訪れた際に私は小原氏と知り合った。そのときに津久原鉱山の未詳鉱物のことを相談されたので、ひとまずやってみましょうと答えて、後日にそれがゴヤズ石(Goyazite: SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6)であることが判明する。ゴヤズ石はこの時点ですでに国内二カ所で産出が知られる鉱物だが、結晶の姿を認識できるゴヤズ石の産出はこれが初めてだろう。結果を伝えて「数年来のもやもやが晴れた」と折り返しの返信があり、栃木県地学愛好会の会報[5]で報告するとのことであった。この会報への掲載が後に迎える展開のきっかけとなるが、この時点で知るよしもなく、その時はともかくこれにて一件落着だと思っていた。

ゴヤズ石
結晶は黄色に染まることが多く、内部や表面にキントレ石(Kintreite: PbFe3(PO4)(PO3OH)(OH)6)がみられることがある。ゴヤズ石とキントレ石は共に明礬石超族の一員。
私と小原氏が知り合うまでの間、津久原鉱山をふくむ一帯の状況に変化が訪れていた。津久原鉱山の周辺は人工林となっており、出荷や管理のためだろうか、ともかくいつのまにか大規模に林道が開削されていた。小原氏はその噂を聞きつけ、2019年の正月明けに数人の仲間と共に状況確認のため当地を訪れている。そして林道はゴヤズ石が産出した石英脈までわずか2メートルのところを走り、さらに上へ延びていたものの、このときは石英脈や廃石の調査が優先された。ただし六角板状のゴヤズ石はもう見つからなかった。その一方でピンク色の鉱物が現れる。それは数ミリ程度の微小塊に過ぎず、現場では粘土鉱物のモンモリロン石が想定されたが、持ち帰った後の実体顕微鏡観察では菱マンガン鉱やバラ輝石、または紅色の石英のようにも見えた。しかし、どうもそれらとは違いそうで、かといって他に思いつかない。そんな相談を受け、一度手を出した縁もあってそのピンク色の鉱物も調べることにした。

トリプロイド石
ぱっと見でピンク色であるほか拡大するとガラス光沢が観察される。自形結晶はこれまで確認できておらず、塊状のみ。結果的にこれはトリプロイド石であったが、そんなレアもの予想すらしていなかった。
ピンク色の鉱物を一見する。菱マンガンと言われるとそうかもという雰囲気があるが、針で触ると思ったより硬い。しかし石英やバラ輝石ほどではなく、うんうんなるほど、わからん。そこで塊を一つ外して調べたところそれはトリプロイド石(Triploidite)であった。トリプロイド石はマンガンを主成分にもつ含水リン酸塩鉱物で、Mn2+2(PO4)(OH)の化学組成をもつ。トリプロイド石はその名を耳にしたことはあれども、私も含め多くの人が見たことがないという鉱物であり、出てきたところで見てわかるはずもない。その産出はどうやら日本では二番目となるもよう。日本で最初のトリプロイド石は茨城県雪入のペグマタイトから報告されており、今回は堆積岩中の石英脈という違いがある。そのため、分析例をもっと増やして産状や共生鉱物の関連を調べてみたかったが、十分な標本がなくそれはできなかった。この時点で小原氏が確保できていたのは小さな石が5~6個だけだったようで、結果を伝えてから数日後に小原氏は再調査に赴いたものの、もはや産出は途絶えていた。かわりに透明な八面体結晶が採集できたというので調べてみたところ、これもまたゴヤズ石だった。蛍石にしか見えないそのツラ構えは肉眼鑑定に困る。そして2019年の夏頃だったか、トリプロイド石も含めて全体的な結果を益富地学会館が発行する地学研究[6]へ投稿したいと小原氏から連絡が入った。

ゴヤズ石
このツラなら蛍石だろうと思っていたがゴヤズ石ということで、肉眼鑑定がどうにも難しい。
そこから1年ちょっと何事もなく、2020年の終わりが近づいたころにもう一人の主人公が現れて新たな局面を迎えることになる。小原氏と同じく栃木県地学愛好会の会員である猪狩氏は、会報[5]を読んで津久原鉱山に興味を抱き、仲間と共に2020年の晩秋に当地へ赴いた。そしてまずはゴヤズ石を目的に石英脈にとりついたそうだ。しかし早々に不毛である気配を感じ取った猪狩氏はそこを切り上げてひとり探索へ出る。そうして歩き回っていたところで人頭大ほどの大きさで真っ黒に汚れた石英塊に出くわし、一部を割ると目にも鮮やかなピンク色の鉱物が姿を現した。レアもの、トリプロイド石である。ところが猪狩氏はすました様子で参考程度の少量を回収しただけでその場を離れた。実はこの時点でも地学研究の報文は未掲載だったためにトリプロイド石は知られておらず、現場ではありふれた菱マンガン鉱やバラ輝石だろうと判断された。しかしのちに違和感を覚えた猪狩氏は、会報を記した小原氏にピンク色の鉱物について意見を伺い、それが驚くほど立派なトリプロイド石だと伝えられた。これまでトリプロイド石は数ミリ程度でしかなかったが、猪狩標本は手のひら大の石に数センチのピンク塊が鎮座する素晴らしいものであった。それなのに大半が放置されたままだという。ようやくあわてた猪狩氏は小原氏を伴ってすぐさま当地に赴いた。そして、後日の実体顕微鏡観察で石英の隙間にまた何か見つかったということで、これまでの縁で転石からの標本も私のもとへやってきた。この地点はもはや鉱山とは関係がないため、産地は津久原とのみ記す。
そうしてやってきた津久原の標本には、透明で小さな丸っこい粒、六角形の粒、六角形の板に矢印が打ってある。調べてみるとそれぞれ蛍石、フッ素燐灰石、ゴルセイ石であった。ゴルセイ石(Gorceixite: BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6)はゴヤズ石のバリウム(Ba)置換体となる鉱物で、その産出は山口県日の丸奈古鉱山に続いて日本では二番目となるだろう。一方でゴヤズ石の時もそうだったが、目に見える結晶として産出するゴルセイ石は津久原が初めてだと思われる。そしてぱっと見でわかるはずのトリプロイド石であったが、それも念のため分析をしてデータを見ているとフッ素(F)がかなり多く検出されることがある。おや? つまりこれはトリプロイド石ではなく、そのフッ素置換体にあたるトリプル石(Mn2+2(PO4)F)である。どうりで蛍石がそばにいるはずですわと納得。トリプル石だと福岡県長垂山に続いて日本で二番目となろうか。しかし、こうなるともはや詳細な分析無しにはどちらか決められないため、ラベルにはトリプロイド石とトリプル石の両方を書いておくことにした。それにしても鉱山跡そばの石英脈とは似つつも少しずつ異なる結果で、これもまたおもしろい。

蛍石
立方体結晶がころっとした球形に集合した姿で産出し、この球を頭にして棒状に伸びることもある。短波長紫外線で蛍光が見られなかった。

フッ素燐灰石
六角形の粒状結晶。これもまた短波長紫外線による蛍光は見られない。


ゴルセイ石
六角形の薄板が何枚も重なり合った姿で見られた。上の写真の結晶はゴルセイ石のみであったが、下の写真のほうは累帯構造でゴルセイ石とゴヤズ石からなっており、ゴルセイ石の領域が優勢。組成に飛びがあるので完全固溶体を形成しないのかも知れない。津久原鉱山ではゴルセイ石はまったく見られなかったが、津久原ではゴヤズ石はむしろ少なくゴルセイ石が主体という違いがある。
そうして転石を調べ終わったところで、猪狩氏が露頭を見つけたと連絡が入った。その流れで露頭の石も調べることになったが、その一つには妙な箇所に矢印がついている。矢印は小原氏がつけたものだったが、それは猪狩氏が気になった箇所だと後に聞いた。ともかく矢印は二箇所ある。しかしどちらもそのすぐ先には白い塊があるだけで、それは針でつついた感触からするとただの貧弱な蛍石塊である。蛍石を越えた先にあるピンク色塊は見てわかるトリプル(トリプロイド)石なので、矢印が示すのはやはりこの蛍石か。正直なにが気になったのかわからなかったが、ともかく調べてみることに。そして、それはやっぱり蛍石であった。ただしまったく予想していなかったもうひとつ別の鉱物が検出された。それはヴィータニエミ石(Viitaniemiite: NaCaAl(PO4)F3)と言って、フィンランドを模式地とするリン酸塩の二次鉱物である。世界的にも稀産の部類だが、日本では福岡県長垂山から産出がすでに知られており[7]、津久原は国内で二番目の産地となった。しかしよくよく比べてみれば長垂山のヴィータニエミ石はマンガンをほとんど含まず、津久原のヴィータニエミ石はマンガンを多く含むという違いがある。そして分析点を精査するといくつかの点はマンガンがカルシウムを上回ることに気がついた。ここまで日本で二番目や三番目という鉱物ばかりで、もちろんそれでも十分めぼしい成果ではあるが、もしマンガンが常に上回る結晶や塊があるならばそれは世界初、つまり新鉱物になる。そのことを伝えたのは2021年の正月明けだった。そして地学研究への報文もようやくそのころに掲載となったと後に聞いた[6]。著者の立場を鑑みた一般論として、出版が遅いことは気分の良い話ではない。しかし、今回に限ってそれは怪我の功名というか、塞翁が馬というか。もしこの報文が迅速に出版されていたなら、はたして桐生石が誕生する展開になっていただろうか。

白いガサガサした塊を指す矢印
針でさわった感触から蛍石であると判断でき、実際にそれはやはり蛍石であったものの、ヴィータニエミ石も混じっていた。あとになって写真に写っているトリプル(トリプロイド)石の中に桐生石+ゴルセイ石の集合体がいることがわかった。
標本の特徴とデータを整理して一定の傾向が見えてきたところで「ぼろっちい石をください」と伝えた。ヴィータニエミ石は二次鉱物なので風化の進行した石に望みをかけたのだった。そうしてやってきたのは透明感が失われてスカスカになったトリプル(トリプロイド)石が伴われる標本であり、狙い通りにその標本からヴィータニエミ石のマンガン置換体が見いだされた。それが桐生石である。桐生石は無色透明かつ不定形で、単結晶となることはほとんどなく、たいていの場合で微小結晶の集合体である。また、単独の集合体となることは少なく、蛍石や燐灰石、さらにはゴヤズ石あるいはゴルセイ石などと混合した集合体となるほうが多い。見た目を簡単に説明すると、いずれの場合であっても白かやや黄色味を帯びたガサガサした物体でしかなく、それを見たところで区別できない。そのため、標本に花を添えてくれているトリプル(トリプロイド)石の状態を当てにしてラベルを書くことになるだろう。上述したようにトリプル(トリプロイド)石がぼろっちいほど、その中もしくは近辺に桐生石やヴィータニエミ石が存在する確率が高い。ただし、桐生石とヴィータニエミ石は組成的に連続し、特に分けられる傾向や特徴はないので両方をラベルに記すことになろうか。一方、トリプル(トリプロイド)石がガラス光沢を保つ場合だと、そばにいる白い物体は蛍石+燐灰石の集合体であることが非常に多いので、これには桐生石のラベルは付さない。いまのところ一個体だけであるが、トリプル(トリプロイド)石中に生じた晶洞に桐生石が立っている姿を確認している。

スカスカになったトリプル(トリプロイド)石
桐生石はこの写真の中央、裂傷上の白い微粉末の箔状集合体。

板状に見える桐生石
これも単結晶ではなく微結晶の集合体で、少量のゴヤズ石を伴っている。やや黄色味を帯びるのは他の二次鉱物が含まれるからと思われるが、検出できるほどの量ではなかった。
現地には2021年の春先に赴いたのでそのときの様子も述べていこう。首都圏の緊急事態宣言が解除されるタイミングにあわせて小原氏と猪狩氏に案内をお願いし、猪狩氏とは当日に初顔合わせとなった。準備を整えたあと、猪狩氏の後輩氏も加えた計四人組にて産地へと向かう。まず桐生川を越えて林道へ入った。道すがら津久原鉱山跡の坑道を確認して、少し上へ向かう。そこはゴヤズ石やトリプロイド石を産出した石英脈の露頭であり、足下には砕けた石英が散らばっていた。その一つを小原氏がなにげにひょいと拾い上げたところ、なんとトリプロイド石が付いている。あるじゃないか。しかし、目的地はまだ先ということで早々にその場を後にして林道をさらに奥へ進む。そして猪狩氏が人頭大の転石を見つけた現場にたどり着き、露頭はどこかと上を見て黄色い花が咲いていることに気がついた。枝が必ず三つに分かれる特徴をもつミツマタという低木のようで、かつて桐生和紙の原料になったと小原氏から教わる。そして産地はここから真上の地点だと指をさされたが、こんなところ登りたくない。しかしなんのことはない。道沿いに行けば到着する。
たどり着いてみると露頭は林道沿いに切り立つ凝灰質砂岩であった。そして、地面すれすれに白い脈が水平方向に走っており、緩い傾斜をもって地面へ刺さっている。脈はやや厚みが変動するがおおむね20cm程度の小規模なもので、大部分は粘土化していた。何気に粘土をほじるといわゆる芋がいくつも出てくる。後で調べたら粘土はセリサイトで、芋は白雲母の塊であった。芋白雲母は個人的には初めてみた。いやいやそれより桐生石であり、それを伴うトリプル(トリプロイド)石はどこだ。それらはこの脈の端っこ、地面に突き刺さるあたりで見られた。しかし、そのあたりから脈は粘土ではなく石英質になっている。つまりくそ硬い。若者二人が汗をかき、それを横目に涼しい顔の小原氏がひょいと道ばたの石を拾い上げたところ、またしてもトリプル(トリプロイド)石が付いている。そこは露頭より上段だったので粘土から落ちてきたのか、もっと上から来たのかと皆で首をかしげる。ともかくそれをきっかけに転石探しが始まり、結果としてむしろ転石から良い標本が得られた。林道はまだ上へと延びていたので、露頭を見ながらひとりぶらぶらと歩く。そして芋を伴う粘土脈は上でもあっさり見つかった。しかし芋はそっくりでもその露頭からはマンガンの気配が感じられない。追い込めばマンガンが顔を出すのか、林道工事の際にすでに切削されたのか、そもそも不毛な脈か。転石はどうかとそこから下を覗くも、こんなところ下りたくない。ともかく産状は把握できた。

桐生石を産した脈の延長からでた芋(左)、そこよりも上の露頭からでた芋(中)、とりあえず並べたじゃがいも(右)。この芋はほとんど白雲母からなり、そのほかは少量の石英のみ。このようにごろんとしたまとまりで産出する岩石や鉱物は、その形から「芋」や「餅」に例えられる。
ヴィータニエミ石のマンガン置換体を新鉱物・桐生石とする旨の申請書は、国際鉱物学連合の新鉱物・命名・分類委員会(IMA-CNMNC)の委員長へ4月5日に提出された。そして8月4日に承認の連絡を受け取り、桐生石が誕生した。あとは論文という仕上げが残っているがそれは脇役である私の務め。小原氏それから猪狩氏の二人を主人公とする桐生石発見物語はこれにて閉幕となる。
最後に話題を名称のところに戻して補足を加えておきたい。産地である津久原の沿革について文献[1]も参照して次のように解釈している。今の津久原の領域で、桐生川の東側はもともと築原(つくばら)の名乗りであった。そして、桐生川をはさんで西側にあった群馬県山地村の集落がその読みを模倣して、いつしか津久原(つくばら)を名乗るようになっていた。こうした経緯を家制度で例えると、築原が本家で、山地村の津久原は分家だと言えるだろう。そして明治9年の地租改正によって、築原を拠点に「ナンジキ」と「ゐど入」を加えて一つにまとめることが決まり、その区域の新名称を決める際に今度は本家が分家を模倣して津久原を名乗る事態が生じている。互いに名称が模倣された背景として、築原と津久原は生活圏が共通で長い付き合いがあったからだと推測されている。ただし、この明治9年時点で誕生した津久原(かつての築原であり本家)は群馬県ではなく、栃木県上彦間村に所属していた。そのため群馬県の津久原(分家のほう)と栃木県の津久原(本家のほう)が桐生川を挟んで並立していたことになる。その後、明治22年の町村制施行では上彦間村が飛駒村へと名称変更となり、栃木県の津久原(本家のほう)は飛駒村入飛駒に組み込まれた。その飛駒村は昭和31年に栃木県田沼町へ編入となり、昭和43年には栃木県田沼町入飛駒のみが県をまたいだ群馬県へ編入される。ここに至り群馬県と栃木県に分かれて二つ在った津久原が合流し、現在まで続く桐生市梅田町津久原が成立した。このような沿革となっており、産地である津久原は古来より名を知られる桐生と異なる(関係がない)と指摘されたら、全くもってその通りである。その一方で、今となっては桐生市の一部であることもまた相違ない。そのために桐生石(Kiryuite)は桐生市(Kiryu City)にちなんで名づけられた。市の名称のもとになった桐生の本領やその由来はまた別にあることは理解いただきたい。まあともかくも、桐生石は群馬県産としては初めて地名(自治体名)にちなんで命名された新鉱物である。
[1] 島田一郎 (2000) 桐生市地名考. 桐生市立図書館, pp.237.
[2] https://gbank.gsj.jp/geonavi/
[3] 小山一郎 (1940) 東京鉱山監督局管内 金属鉱山. 工業叢書; 第3篇, 鉱業社.
[4] 井上秀雄 (1992) ALCと関東地方のチャート資源. 地質ニュース, 458, 28-36.
[5] 小原祥裕 (2018) 群馬県桐生市 津久原鉱山の鉱物-稀産のストロンチウムリン酸塩鉱物ゴヤズ石など-. 栃木地学愛好会会報, 65, 32-38.
[6] 小原祥裕, 興野喜宣 (2021) 群馬県桐生市津久原鉱山産の燐酸塩鉱物ゴヤズ石とトリプロイド石. 地学研究, 66, 63-70.
[7] Shorose Y., Uehara S. (2014) Secondary phosphates in montebrasite and amblygonite from Nagatare, Fukuoka Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 109, 103-108.
IMA No./year: 2020-057
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-47662)
フェリぶどう石 / Ferriprehnite
Ca2Fe3+(AlSi3)O10(OH)2
The Fe3+ analogue of prehnite
島根県松江市美保関町北浦
Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ito S., Tanaka T. (2020): Approved by CNMNC on November 3rd.

フェリぶどう石の写真
島根県美保関町から見出された新鉱物、フェリぶどう石である。「ぶどう石」という名前なのに「ぶどう」らしさをまったく感じることができない、ちょっと困った名前の新鉱物。ここしばらくは金属系の新鉱物が続いていたので、透明な清々しい結晶がとても新鮮に感じられた。フェリぶどう石は申請ベースで見ると2020年代では最初の日本産新鉱物になる。幸先よく新しい10年代が幕を開けた。今回は山口大学永嶌研究室の主導で行われた共同研究であり、研究発表はそちらにお願いしよう。ここではフェリぶどう石の背景や、私のほうでの発見の経緯などを中心に述べていく。今回の物語を何かに例えるならそれはマーフィーの法則なのだろう。
フェリぶどう石は「ぶどう石」の三価鉄(Fe3+ : フェリ)置換体に相当する新鉱物なので、まずはぶどう石について述べて行く。最初に名前の表記について。和名での表記については漢字(葡萄石)・ひらがな(ぶどう石)・カタカナ(ブドウ石)、いずれも使用される。論文では学名のカタカナ読みでプレーニットやプレーナイトという表記もまた見られる。いずれにしても鉱物の和名については決まったルールは存在しないため、誰かが使った表記が多くの人々に好ましくあれば、それがそのうち定着することが慣習になっている。そして近世ではひらがなの「ぶどう石」表記が多いと感じる。私はどうかというと、やはりひらがなを使っている。ラベルを書くときに画数の多い漢字は煩わしいという実情が大きい。ともかくここではひらがなの「ぶどう石」と記すことにしよう。
さて、ぶどう石は学名をPrehniteと書き、18世紀に実在したドイツ軍大佐のHendrik Von Prehn (1733–1785)に因む。大佐が南アフリカの喜望峰から産出した標本をヨーロッパへ持ち帰り、地質学者であるAbraham Gottlob Werner(1749-1817)によって1788年に命名された[1,2]。これは人名に因んで名付けられた最初の鉱物とも紹介されている[2]。このような経緯であり、学名はフルーツのぶどうに因んでいる訳ではない。では、なぜPrehniteのことを和名で「ぶどう石」と書くのだろうか。

マリ共和国産のぶどう石
外国産のぶどう石にはマスカットぶどうのような標本が知られている。
そこで、日本で初めて産出したぶどう石がどのように記されているか調べてみた。学術文献では1894年(明治27年)に大分県豊後大野市の尾平鉱山から見出されたぶどう石が最初になるだろう[3]。そのなかでぶどう石の解説を読むと「色は暗緑色」と書かれているのみで、形状については言及が無い。一方で「葡萄色の斑紋ありて美麗なり」とも書かれている。「葡萄色」は「えびいろ」と読み、熟したヤマブドウのような赤紫色を指す。ただし、斑紋であるからにしてその部分はぶどう石とは別の鉱物であろう(おそらく蛍石)。まあしかしモノの真偽はともあれ、ここで知りたいのはぶどう石という和名が誕生した時期と由来である。尾平鉱山での発見と同時の命名であれば、形ではなく斑紋の色(葡萄色)に由来することになる。しかし、それ以前にすでに和名が存在した可能性はどうか。まず上の写真で示したように海外にはまさにぶどうと言える標本が存在している。そしてPrehniteという学名は1885年(明治18年)には文献に登場しているため[4]、日本産ぶどう石の発見以前にその存在はすでに認識されていたとみて良いだろう。そうなると、輸入された海外産標本のマスカットのような見てくれに因んで「ぶどう石」という和名が先に成立していたことはあり得る。ただし残念ながら和名についてその経緯を具体的に記している文献は存在しなかった。
さて、現代においてぶどう石はあまたある鉱物の中にあってもたいへんめずらしい、ということはまったく無く、むしろ極めてありふれた鉱物であることがわかっている。例えば、弱い変成作用を受けた苦鉄質岩ではぶどう石はまさに主要な構成鉱物であって、そのような岩石は日本国内に限らず世界中に分布している。ただし、岩石中のぶどう石は主要とはいえども微細な存在に過ぎず、岩石学者には重宝されるとしても、それでは鉱物標本にはならない。鉱物標本としてのぶどう石は変成作用や火成作用の晩期に生じるモコモコした集合体である。そして国内では静岡市上徳倉や山梨県岩欠から産出するぶどう石が古くから有名であった。しかしながら、良標本の採集は1980年代にはすでに困難になっていたと聞いている。一方でその頃にまた新たな産地が島根県から報告されるようになった。
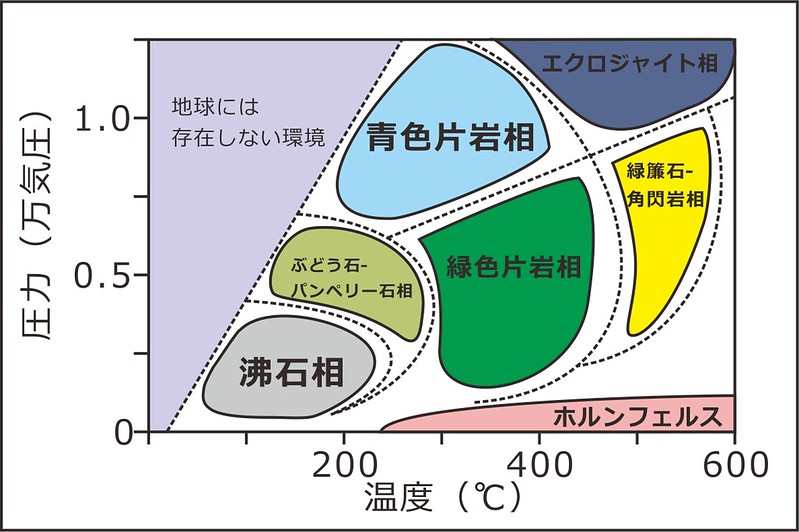
変成相の区分(文献[5]を参考に加筆)
変成作用を被った苦鉄質岩に生じる鉱物組み合わせに基づいて変成相が提案されている。例えば苦鉄質岩が0.5万気圧200℃程度の環境にさらされると、ぶどう石とパンペリー石が岩石の主要構成鉱物となる。
島根県東部は地震予知研究の上で緊急性がある重要な地域として指定されており、1980年代初頭から地質調査が行われ、1985年(昭和60年)には「境港地域の地質図(5万分の1)」が公開された[6]。その中に今回の産地があり、境港出身である私についても生家がプロットできる。ちなみに境港は島根県ではなく鳥取県である。それはさておき、この地質図作成の調査において島根半島からぶどう石が産出することが明らかとなり、1986年(昭和61年)の学術論文において詳細が報告されている[7]。
島根半島は最大標高500mちょっとで、おおむねは200-300mの標高になっている。数字で見るとたいして高くないように感じられるが、平均海抜2mの境港から見えるそれは大きな山だった。そして半島の北側は日本海に面し、多くは荒々しい海岸や崖となっている。人が降り立つことのできるポイントはそもそも少ない。それでも出雲市三津町、松江市鹿島町、松江市美保関町笹子などからぶどう石の産出が報告された[7]。その論文の中で1点のみの分析値ではあるが、三津町の標本は今回の新鉱物であるフェリぶどう石に相当している。しかしながらこの当時にはぶどう石の三価鉄(Fe3+:フェリ)置換体という概念はまだ存在しなかった。海外においても同様である。フェリぶどう石に相当する分析値は報告されども、新鉱物どうこうという動きはなかった[8]。

境港市(海浜公園:通称は中野公園)から北を望む
見えている範囲の最も高いところが高尾山(標高328m)。直線的に山を超えた先の、日本海に面した側が美保関町七類となる。七類から1-2km西が笹子で、さらに西へ5kmほどで北浦にたどり着く。
美保関町笹子から西へ5kmほど行くと北浦という地域があり、そこは主に海水浴客や釣り人が訪れる。どういう目的かは知らないが愛石家がたどり着いたようで、北浦からもぶどう石が産出することが突き止められた[9]。文献としては1984年(昭和59年)の報告であり、これ以降はぶどう石というと北浦の標本が図鑑で紹介されることが多くなる。そしてこの北浦のぶどう石について国立科学博物館の研究チームが1992年(平成4年)の鉱物学会で研究発表を行った[10]。結晶の一部に三価鉄が卓越する箇所が見つかり、「ぶどう石の三価鉄置換体という概念を世界で初めて提唱した」とまとめられている。これはつまりフェリぶどう石のことである。この発表をもとにして、フェリぶどう石という新鉱物があり得ることは研究者や愛石家に知れ渡った。しかしそこからの進捗に困難があったようで、新鉱物の申請はついに行われることがなかった。フェリぶどう石を概念からカタチ(=新鉱物)にするという挑戦は、次の世代に託されたと言えよう。





北浦産のぶどう石
北浦において、ふつうのぶどう石はクラスター(集合体)の姿で産出する。それは淡青色から淡緑色を帯びた曇りガラス様の板状結晶が密に集まってできている。遠目で見るとぶどうのように丸く見える集合体もあるが、全体としてはあまりぶどうっぽくない。一番下の写真でコロコロ丸いのはぶどう石ではなくトムソン沸石。ぶどう石はその下地。
以上が要点を抜粋したフェリぶどう石の研究背景である。このように30年ほども前にフェリぶどう石が存在するところまではわかっていた。しかしそれ以降の進展が誰からも何も聞こえてこない。ひとまずは結論から述べよう。図鑑でよく紹介される北浦産ぶどう石、例えば上に掲載した写真のような標本、それらにはフェリぶどう石はひとかけらも含まれない。前評判ではこういった標本の一部がフェリぶどう石ということだったが、だれが言い出したのか一部という表現はあまりにも針小棒大であった。それはひとかけらですらなく、一つの分析点(1-2ミクロン)として極めて稀に見つかる程度が実態である。確かにそれだと概念という表現が妥当だろう。図鑑などでは色味への言及があるのでそれが手がかりになるかと調べてみたのだが、それもまた空言であった。結果的にフェリの度合いと色味はまったく関係がない。それではフェリぶどう石の結晶やその集合体は果たして存在するのか、そしてそれはどこにあるのか。ちょっと現地の様子を思い出してみよう。
ぶどう石が産出するポイントは古浦ヶ鼻と呼ばれている。そこは海へ突出した岩場で、不定型な穴が岩石中にまばらに開いている。これは自然が成したことなので当たり前に形も配置も不規則であるが、なんとなく町並みのように各住居に様々な住人がいる様子にたとえられよう。例えばある小さな穴(住居)はぶどう石(住人)だけだが、ご近所の大屋敷には方解石という同居人がいる。ちょっと離れたところのお宅はどうかとひょいと尋ねてみると、黒色で鋭い光沢のあるバビントン石や、乳白色で柔らかい光沢をもつ丸っこいトムソン沸石が居を構えている。もちろん住人の面構えや住居の趣はそれぞれ異なる。そのため、フェリぶどう石ばかりの住宅があることを期待して見るからにぶどう石という標本をともかく分析した。一連の調査で分析した標本は昔に自分で採集したもの、購入したもの、提供していただいたものである。そして、折を見てだが長年かけてフェリぶどう石を探してきた。しかしついに見つけることは叶わなかった。もうあきらめよう。そうなってからほかの鉱物を見てみようと思えるようになり、それで標本箱から取り出した石が「トムソン沸石」のラベルがついた標本であった。それは友人からもらったと記録されている。その標本には少量のバビントン石が伴われるだけで、見るからにぶどう石はいないが、そんなことはもはやどうでもいい。

手に取ったトムソン沸石の標本
トムソン沸石は透明感のある灰白色の球状集合で産出し、脇に黒色バビントン石を伴う。

トムソン沸石標本の裏側
産地は海沿いであるために標本は藻や苔で汚れていることも多い。ぱっと見で苔だと思った。
まずは写真を撮ろうと標本をひっくり返す。そこは写真撮影のために粘土で固定する側になるが、なんとなく観察する癖がついている。見ると苔まみれでなんとも小汚い。腐ってないかと疑いつつ前後左右に動かす中で、苔と思っていたものが光の加減でわずかにチカチカする。ん? そして実体顕微鏡でみたとき、これが苔ではなく鉱物であることに気がついた。それにしてもどこかで見たような面構えをしている。そうだこれはパンペリー石族だ。調べてみるとやはりパンペリー石族であり、鉱物としてはジュルゴルド石であった。おー、これはすごい。小汚いなどとは申し訳なかった。実はジュルゴルド石は日本では北浦でのみ産出が知られている鉱物でありながらも、これもまた永らく(30年近く)再発見の報告がないために幻の鉱物となっていた。写真を撮ったあと、この標本はお迎えしたときとは真逆の、つまりはジュルゴルド石が見えてトムソン沸石が隠れる配置で標本箱に収容された。ラベルには「ジュルゴルド石」が追加され、標本としてひとつ箔がついたといったところだろう。これが2019年(令和元年)の10月末のこと。ちなみにトムソン沸石には注目すべき特徴は何もなかった。

ジュルゴルド石の写真
ジュルゴルド石はパンペリー石族のなかで最も三価鉄(Fe3+)に富む鉱物。厳密にはフェロジュルゴルド石とフェリジュルゴルド石にさらに分けられるが、ここではそれはあまり重要ではないため単にジュルゴルド石としておく。濃い緑色で透明感のある微細な板状結晶で、小さいながらも極めてパリっとした端正な姿をしている。
振り返ってみると、私にとってフェリぶどう石の探査は山口大の永嶌さんがきっかけだった。7-8年ほど前になろうか。実験のために物性研に来られた際に「結晶化学研究のためにフェリぶどう石を探している」という話をされて、「では私の方でも探してみます」と答えたことが始まりである。そのくせにあきらめてしまったことは上にあるとおりだが、年が明けた2020年(令和2年)1月に事態が動く。永嶌さんからのメールに「研究継続中。EPMAオーダーでジュルゴルド石とフェリぶどう石を確認しました。」とある。EPMAオーダーというのは数ミクロン程度のとても小さいことを意味している。それはともかくもジュルゴルド石だと!? それはつい最近にようやく拝顔が叶ったばかりではないか。そういえばと思い返すとジュルゴルド石には透明な板状結晶が伴われていた。しかし、これはトムソン沸石が球状集合になりきれなかった哀れな姿だと思っていたので、わざわざ分析していない。ところがそれこそが探し求めていたフェリぶどう石であった。しかも数ミクロンどころではなく、写真に収まるほどの大きさである。こんなところにおったんかーい。そこから永嶌研究室主導の本格的な研究が始まり、2020年(令和2年)11月3日の文化の日に新鉱物の承認通知が届いた。ラベルには「フェリぶどう石」がさらに追加され、ただのトムソン沸石でしかなかった標本がついに新鉱物にまで到達した。それでは現物の解説に移っていこう。

フェリぶどう石(透明な板状結晶)とジュルゴルド石(緑色)
写真を撮っておきながらもこの透明な板状結晶は球形になり損なったトムソン沸石だと思い、分析をしないままほったらかしていた。このフェリぶどう石の#Fe3+[ = Fe3+/(Fe3++Al) (八面体サイト)]は最大で0.8に達する(#Feが0.5を超えればフェリぶどう石で、0.5未満はふつうのぶどう石)。
まずはふつうのぶどう石について。北浦のぶどう石は肉眼でも観察可能な大きさで産出し、それは非常に優れた鉱物標本になる。なんといってもそのまま見て美しく、虫眼鏡でもあればさらに大迫力の画が見える。全体は透明感が感じられる曇りガラス様であり、色味はわずかだが爽やかな青から緑色を常に帯びる。ひとつの結晶としての産出はこれまで見たことがないが、集合体の断面から推測できる結晶の形状は四角形の薄板や厚板であろう。その結晶が束状、扇状、球状に集合し、さらにそれらが密にモコモコと集まった姿になる。集合体の表層が一様に丸く滑らかであることは非常に稀で、ほとんどがギザギザしている。ぶどう石という名前のくせにぶどうっぽく見えない標本ばかりだが、それでもこういった姿が北浦産ぶどう石の典型である。たまにコロコロと丸い球がギザギザ頭の上にたくさんくっついた姿が見られ、いかにもぶどうっぽい丸みだが、それらはぶどう石ではなくトムソン沸石である。いずれにしても、こういった標本はその色味も相まって見る者に涼やかな印象を与える。その印象から化学組成は均質であることを(勝手に)期待したが、見事に裏切られた。実際はむしろ逆で、数ある鉱物の中でもこれほど複雑なものはそうはない。結晶の内部には三価鉄の濃淡による累帯構造がきわめて著しくかつ複雑に発達しており、分析点ごとに値が大きく異なる。そして#Feが0.52くらいまでは到達することがある。#Feが0.5を越えたのだから、その分析点は確かにフェリぶどう石である。しかしその領域はせいぜい数ミクロン。つまり全体としては99.99%以上がふつうのぶどう石に過ぎない。そのような標本にフェリぶどう石のラベルをつけることはしたくない。フェリぶどう石のラベルはこういった標本ではなく、フェリぶどう石が主体の標本に授けたい。そしてそれは確かに存在する。それでは上の標本とはまた異なる姿のフェリぶどう石をいくつか掲載する。

フェリぶどう石
冒頭に掲載した写真。完全なる無色透明な結晶。いわゆるぶどう石は単結晶として見られたとしても四角形の平板になることが多いが、この結晶は頭がとがっている。いわゆるぶどう石とみても例外的な姿であるために、見た目でぶどう石とすら鑑定し得なかった。この結晶には累帯構造がないため、全体がフェリぶどう石。
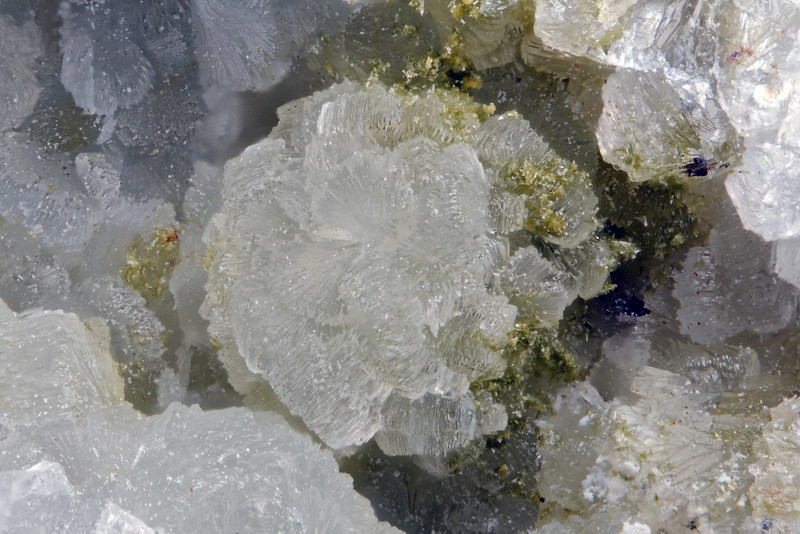
フェリぶどう石
上の写真のすぐ近くの晶洞にあり、板状結晶がいったん扇状に集合した束となり、それがさらに球形に集まった集合体となっている。これはぶどう石よりも沸石がまず頭に浮かぶ姿。伴われる黄緑色はパンペリー石族。内部には累帯構造があるがフェリぶどう石が主体。極めてわずかにだが、緑色味が感じられる。

フェリぶどう石
これも球形集合だが、上に掲載した球とはまたすこし様子が異なるが、やはり沸石を思わせる姿と言えよう。この晶洞にはパンペリー石族は伴われない。内部には累帯構造はあるが、フェリぶどう石が主体。色味は感じられず無色と言える。

フェリぶどう石
球形にならず束状にとどまる姿。これもぶどう石よりは束沸石を思わせる。累帯構造はあったが、フェリぶどう石の領域が大多数。無色だが小さいので下地の緑がすけている。その緑色をした微細粒子はパンペリー石族。
フェリぶどう石の結晶やその集合体を見つけるには、あからさまにトムソン沸石という標本をまずは用意することだ。そこにバビントン石や方解石が伴われることはまったくかまわない。それでは標本の裏や脇をよく見てみよう。するとふつうのぶどう石の標本とは比べるべくもないほどだが、小規模な晶洞が見つかると思う。そこにフェリぶどう石がいる。ごくまれに頭のとがった西洋剣のような結晶が出現し、それがふわっと集合する。それはいわゆるぶどう石とはかけ離れた姿だが、ともかくも清々しい。それでも密な集合体となることがやはり多い。たとえば四角形の板状結晶がまず中心がきゅっと締まった束状に集まり、それらがさらに球状に集合する姿が見られる。束のままのこともある。そのほか、薄板結晶が乱雑に球形に集まる姿もあった。初めて見いだしたフェリぶどう石には多量のパンペリー石族(ジュルゴルド石)が伴われていたが、それはむしろ稀な例であったようだ。いずれにしてもフェリぶどう石からなる集合体は小さく、1ミリあれば大きいと言える。ただ困ったことに小さなトムソン沸石が同様の産状や形態を示すため、それとは区別しがたい。これは乱暴なやり方だが、塩酸を使いトムソン沸石を溶かしてしまえば誤認はなくなるだろう。共存するバビントン石を目立たせるために塩酸処理された標本を見かけるので、それを手に入れるのもいいだろう。結論として、この産地におけるフェリぶどう石の存在度は稀ではない。なんのことはない。おおきなトムソン沸石の下にはフェリぶどう石が満ち満ちており、ときおり現れる小さな晶洞にその結晶が顔を覗かせてもいた。それに気づいていないだけだったのだ。しかしいったん気づいてみれば愛石家にとって見分けはそんなに難しくないだろう。すでにある標本を見直すだけでもフェリぶどう石はあっさり見つかると思う。自身でも20年以上も前に採集したトムソン沸石の標本をよく見たら、フェリぶどう石の晶洞がふつうに伴われていた。あとは規格外であるが、パンペリー石族を多量に含むことで緑色に染まった結晶が存在する。これもまたトムソン沸石の周りにいることがある。ただしその姿は愛石家が親しんできた北浦産ぶどう石とはあまりにもかけ離れており、それは全く別の鉱物、例えば透輝石のように見えていた。しかしこれもまたフェリぶどう石であり、その姿はぶどうの葉っぱにならまあ見えなくもない。こういった姿はふつうのぶどう石の集合体にも伴われることがあるが、そちらでは外形のみを残して中身はすべてパンペリー石族に置き換わっている。

フェリぶどう石
透輝石と思えたがトムソン沸石の周りにいるとなるとそれは環境的に考えにくい。おかしいなと思って調べたところ、これもまたフェリぶどう石であった。仮晶なのかも知れない。緑色であるのはきわめて多量のパンペリー石族を内部に伴うため。いまのところ2ミリ程度の結晶を確認している。また、透輝石はふつうのぶどう石には伴われることがある。
さいごに、終わってから気づくという間抜けっぷりを晒しておくと、ぶどう石の標本からフェリぶどう石を探す方針が見当外れだった。ヒントは島根半島からのぶどう石を報告した論文にすでにあった[7]。この論文で、パンペリー石族に含まれる三価鉄は変成度の低い沸石相で多く固溶されるとある。それだとすると、パンペリー石族にあって特に三価鉄が多いジュルゴルド石は、沸石相にこそ出現するとまず考えられる。そしてジュルゴルド石の学会発表には「ジュルゴルド石はフェリぶどう石に伴われる」という記述があった[11]。これらを合わせて考えると、フェリぶどう石を探すならばジュルゴルド石を目印に「沸石が主体となる標本」こそまずは調べる価値があったのだ。それなのに「ぶどう石が主体となる標本」ばかりを調べるという下手を打っていた。それでは当たり前に見つかるはずもなく、ついにあきらめて探すことを止めてしまった。そうしたところで、いや、だからこそなのだろう。探すのを止めたとき、それは見つかる。こういったよくある話を何と言ったか。ああそうだ、思い出した。これはマーフィーの法則だ(哀愁ただよう経験則)。調査を継続していた永嶌さんの努力があったからこそたどり着いた成果だが、マーフィーの法則こそがこのたびの私にとっての新鉱物発見物語であった。
[1] Hoffmann C.A.S. (1789) Mineralsystem des Herrn Inspektor Werners mit dessen Erlaubnis herausgegeben von C.A.S. Hoffmann. Bergmannisches Journal 1, 369-398
[2] https://www.mindat.org/min-3277.html
[3] 篠本二郎(1894)豐後尾平礦山紀行. 地質学雑誌, 1, 221-224.
[4] 杉村次郎(1885)製錬ニ適良ナル亜鉛鑛ト砂錫産出ノ廣野トノ發見 (承前). 日本鑛業會誌, 1, 416-426.
[5] Spear F.S. (1993) Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-Time Paths (Monograph (Mineralogical Society of America). Mineralogical Society of America, pp.799.
[6] 鹿野和彦, 吉田史郎(1985)地域地質研究報告5万分の1図幅岡山(12)第7号 境港地域の地質. 地質調査所, pp.57.
[7] Kano K., Satoh H., Bunno M. (1986) Iron-rich pumpellyite and prehnite from the Miocene gabbroic sills of the Shimane Peninsula, Southwest Japan. The Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 81, 51-58.
[8] Zolotukhin V.V., Vasil’yev Y.R., Zyuzin N.I. (1965) Iron-rich modification of prehnite and new diagram for prehnites. Doklady Akademii Nauk SSSR (Earth Science Section), 164, 138-41.
[9] 野村松光, 松原聰, 坂野靖行(1984)島根県美保関町古浦ヶ鼻のバビントン石について. 地学研究, 35, 153-156.
[10] 加藤昭, 松原聰, 神谷俊昭(1992)島根県古浦ヶ鼻産葡萄石のFe3+置換体. 日本鉱物学会1992年年会講演要旨集, C19, p160.
[11] 松原聰, 加藤昭, 神谷俊昭(1992)島根県古浦ヶ鼻産julgoldite-(Fe2+). 日本鉱物学会1992年年会講演要旨集, C20, p161.
IMA No./year: 2019-129
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-47328)
苫前鉱 / Tomamaeite
Cu3Pt
The Pt analogue of auricupride
北海道苫前町
出典:Nishio-Hamane D. and Saito K.: Tomamaeite, IMA 2019-129, in: CNMNC Newsletter 55, Eur. J. Mineral., 32, https://doi.org/10.5194/ejm-32-367-2020, 2020.

苫前鉱を含む砂白金(テトラフェロプラチナ鉱)の写真。
苫前鉱は単独で産出することはなく、プラチナ系砂白金の包有物として見出される。苫前鉱の実体は後述。
北海道苫前町の砂白金から見出された新鉱物、苫前鉱(とままえこう)である。近年は砂金や砂白金を集中的に調べているので、見つける新鉱物も必然的にそれらに伴われるものが続いている。そのためにまた砂の新鉱物かと揶揄されそうだが、いやいやむしろ砂粒ほどの大きさであったならばどれほど良かったのにと思う。それは後述するとして、新しい発見をまずは素直に喜びたい。苫前鉱が承認されたのは2020年4月のことだが、IMA No.が示すように申請ベースでみると苫前鉱は日本産新鉱物種について2010年代の大トリとなる新鉱物である。それにしても現在は新種のコロナウイルスによってたいへんなことになっており、申請時はこんな未来を予想していなかった。新種の鉱物についてはひっそりと更新しておくことにする。
砂白金を調べ始めたころにトラミーン鉱(Tulameenite)の中に変な鉱物がしばしば入っていることを海外の友人から教えてもらった。その時点ではトラミーン鉱なぞ見たことのない鉱物であったが、最近になって熊本県の砂白金を扱うようになると、トラミーン鉱に変な鉱物の究極である新鉱物(皆川鉱、三千年鉱)が伴われることを体験した。さらにテトラフェロプラチナ鉱(Tetraferroplatinum)もやはり変な鉱物を伴うことがわかってきた[1]。なるほど、どうやら新鉱物を効果的に探すにはその二つが目印になりそうだ。しかし実際に探すには実物のイメージが必要であろう。そこで今回は北海道の砂白金について、その種類や外観の特徴をまずはまとめていきたい。

北海道の砂白金
白金族元素をイリジウム系(Ru, Os, Ir)とプラチナ系(Rh, Pd, Pt)と勝手に分けたとき、北海道ではイリジウム系を主成分とする砂白金が圧倒的に多く産出し、プラチナ系は非常に少ない[2]。このあたりは先に三千年鉱の項目を先に読んでいただけると理解しやすいと思う。ひとまず上の写真のように北海道産砂白金をざらっと並べたときにイリジウム系:プラチナ系の量としての比率は感覚的に95:5くらいであろうか。ただしプラチナ系は単独の粒として産出するよりもイリジウム系砂白金にわずかに伴われるという産出が多い。そのためプラチナ系を伴う砂白金の個体数は5%よりは多いと感じられる。それは実物(写真)で説明しよう。それではそれぞれの砂白金と、それに伴われる白金族鉱物を以下に並べよう。

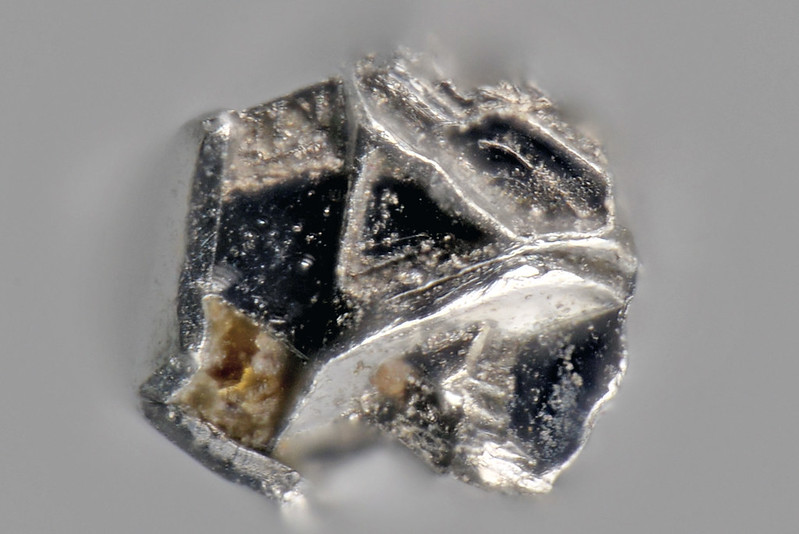
自然ルテニウム / Ruthenium
自然ルテニウムは北海道を原産地とする白金族元素鉱物であり、ルテニウム(Ru)で代表される化学組成をもつ[3]。合金としてしばしばオスミウム(Os)やイリジウム(Ir)を多く含む。結晶構造は六方晶系に属し、結晶で産出する場合は三角~六角形を基本とした面が出現する。しかし砂白金としてはほとんどが不定形の塊状として得られる。なお単体元素と鉱物種を区別するために鉱物には「自然」を冠して呼ぶことになる。


自然オスミウム / Osmium
自然オスミウムはオスミウム(Os)で代表される化学組成を持ち、しばしばイリジウム(Ir)を多く含み、ほとんどの場合で少量のルテニウム(Ru)も含まれる。結晶構造は自然ルテニウムと共通で六方晶系に属する。六角形で扁平な結晶は経験上はまず間違いなく自然オスミウム。砂白金としてはほとんどが不定形の塊状で得られるが、どこかしらにツルっとした箇所があることが非常に多い。またオスミウムに非常に富む個体は全体に青みが感じられる。


自然イリジウム / Iridium
自然イリジウムはイリジウム(Ir)で代表される化学組成を持ち、オスミウム(Os)やルテニウム(Ru)も含まれるがその含有量は一般に少ない。ごく稀に鉄(Fe)やレニウム(Re)を多く含むことがあるが通常それらは検出限界を下回る。結晶構造は立方晶系に属し、サイコロ形の結晶で産出することがある。イリジウムに富む個体はほかの砂白金に比べて白っぽい。砂白金としては単独の塊状で産出することは少なく、多くは自然オスミウムやルテニイリドスミンが主体となる個体の一部に付着して産出する。例えば上の写真は自然オスミウムを下地にして自然イリジウムが上に乗っている。
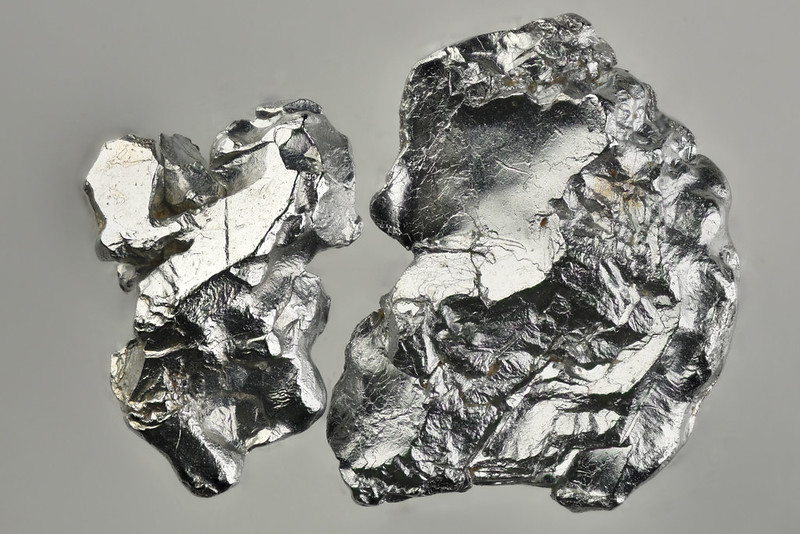


ルテニイリドスミン / Rutheniridosmine
ルテニイリドスミンは北海道を原産地とする新鉱物で砂白金として見いだされた[4]。イリジウム(Ir)、オスミウム(Os)、ルテニウム(Ru)からなる白金族鉱物であり、理想式は(Ir,Os,Ru)と設定されている。組成的にはイリジウムが最も卓越するため、それだけに注目すると自然イリジウムの範疇にはいるが、自然イリジウム(立方晶系)とは結晶構造が異なる。ルテニイリドスミンは六方晶系の鉱物であり、三角や六角の晶癖が発達することがある。しかしほとんどの場合は不定形塊として得られる。かつてイリドスミンと呼ばれた砂白金の多くは現在のルテニイリドスミンに該当する。なお元素鉱物は元素そのものと区別するため「自然」という接頭語を置き鉱物と区別するが、ルテニイリドスミンは単体元素の鉱物ではないため「自然」の接頭語は不要である。
ここまでが代表的なイリジウム系砂白金であり、これらはプラチナ系元素をほとんど含まない。いずれも非常に硬い。摩耗に強いためにときおり結晶が得られることがある。不定形塊の個体も表面には傷がほとんどないので、それはおそらく岩石中に存在したときから不定形塊だったのだろう。外観的な特徴から、自然オスミウムと自然イリジウムについては典型的なものであれば肉眼鑑定はそんなに難しくない。一方で自然ルテニウムとルテニイリドスミンは塊状、結晶のどちらも区別がつかない。産出量はルテニイリドスミン>自然オスミウム>自然ルテニウム>自然イリジウムの順というのが個人的な感覚。続いては代表的なプラチナ系砂白金を示す。

自然プラチナ / Platinum
自然プラチナはプラチナ(Pt)で代表される化学組成であるが、砂白金として見いだされる場合だとすべてのケースで鉄(Fe)を原子比で20%ほど含んでいた。鉄を含まない純度の高い自然プラチナもあるにはあるが、それはほかの鉱物の包有物で出現するため非肉眼的である。立方晶系の構造で、プラチナと少量の鉄は同じ席に位置する。結晶形を保った個体は見たことがない。やや茶色を帯びた銀色を示し、表面には細かい多くの傷がついているため輝かない。ネオジム磁石にほんのわずかに反応する。


イソフェロプラチナ鉱 / Isoferroplatinum
イソフェロプラチナ鉱はプラチナ(Pt)と鉄(Fe)からなり、化学組成はPt3Feで表される。原子比で見ると鉄が25%程度含まれる。イリジウム系砂白金の一部に付着する産状が非常に多いが、楕円球形粒の単独の砂白金として産出することもある。結晶構造は自然プラチナと共通だが、結晶構造の内部でプラチナと鉄の存在する席が決まっている点が自然プラチナと異なる。やや茶色を帯びた銀色で、表面には細かい傷が多くつや消し状態になっている。ネオジム磁石に弱く反応する。

トラミーン鉱 / Tulameenite
トラミーン鉱はプラチナ(Pt)と鉄(Fe)および銅(Cu)からなり、化学組成はPt2CuFeで表される。イリジウム系砂白金の一部に付着するという産状で主に見られる。楕円形状で単体の砂白金として得られた個体が、切ってみたら中身はイリジウム系砂白金やイソフェロプラチナ鉱だったことがある。以下に挙げるフェロニッケルプラチナ鉱と共通の結晶構造(正方晶系)であるため、同じ産状で両者が混在する場合がある。外観は茶色~褐色をやや強く帯びた銀色。表面には細かい傷や凹凸が多いためつや消し状態。ネオジム磁石には非常に強く反応する。

フェロニッケルプラチナ鉱 / Ferronickelplatinum
フェロニッケルプラチナ鉱はプラチナ(Pt)と鉄(Fe)およびニッケル(Ni)からなり、化学組成はPt2FeNiで表される。イリジウム系砂白金の一部に付着するという産状でのみ見られ、単体の砂白金としての個体はまだ見たことがない。写真だとルテニイリドスミンを下地にしてその上を覆うようにフェロニッケルプラチナ鉱が生じている。結晶構造は正方晶系。外観は茶色~褐色を強く帯びる。表面はつや消し状態。ネオジム磁石には非常に強く反応する。

テトラフェロプラチナ鉱 / Tetraferroplatinum
テトラフェロプラチナ鉱はプラチナ(Pt)と鉄(Fe)からなり、化学組成はPtFeで表される。イリジウム系砂白金の一部に付着する産出と、一見して単体の産出がある。しかし単体の場合だと中心にイソフェロプラチナ鉱の核が必ずある。フェロニッケルプラチナ鉱やトラミーン鉱と共通の結晶構造で正方晶系。単体の個体には正方~直方体の面が残っているように見えるが、それは中身のイソフェロプラチナ鉱の晶癖であろう。外観は明るい茶色で、表面はつや消し状態。ネオジム磁石には非常に強く反応する。
ここまでが代表的なプラチナ系砂白金となり、その特徴を一言で示すと「つや消し加工された金属」。それぞれの鉱物はイリジウム系元素をほとんど含まないが、産状としてはイリジウム系砂白金に密接に伴われることが非常に多い。単体の砂白金として得られた場合は自然プラチナとイソフェロプラチナ鉱の区別はできない。またイリジウム系砂白金に付着する産状だと、イソフェロプラチナ鉱、フェロニッケルプラチナ鉱、トラミーン鉱は外観からは区別できない。しかしネオジム磁石を使うとイソフェロプラチナ鉱かそれ以外かは判別できる。テトラフェロプラチナ鉱だけは色が独特なためすぐわかる。観察した範囲内において、産出量はイソフェロプラチナ鉱>トラミーン鉱>フェロニッケルプラチナ鉱>テトラフェロプラチナ鉱>自然プラチナの順。意外かもしれないが実は自然プラチナは最も少ない。せっかくなのでその他のレアもの砂白金も以下に掲載する。

輝イリジウム鉱 / Irarsite
輝イリジウム鉱はイリジウム(Ir)、ヒ素(As)、硫黄(S)からなり、化学組成はIrAsSで表される。結晶構造は黄鉄鉱もしくは輝コバルト鉱と考えられている。イリジウム系砂白金の表面を覆う、もしくは一部に付着するように産出する。褐色から黒色。もともと光沢の強い鉱物だが、細かい粒子の集合となるとつや消し状となる。

トロフカ鉱 / Tolovkite
トロフカ鉱はイリジウム(Ir)、アンチモン(Sb)、硫黄(S)からなり、化学組成はIrSbSで表される。輝イリジウムのアンチモン置換体に相当するのだが、観察した範囲内では組成や分布が輝イリジウム鉱とは連続せずに飛びがある。イリジウム系砂白金の表面を覆う、もしくは一部に付着するように産出する。濃灰色~黒色で、写真だと左側に多く分布する。

エルリッチマン鉱 / Erlichmanite
エルリッチマン鉱はオスミウム(Os)と硫黄(S)からなり、化学組成はOsS2で表される。自然オスミウムやルテニイリドスミンの一部に付着する産状でみられる。黒色で強い光沢を示すが、粒子が細かいとざらっとした印象になる。写真では左下の区画になっている部分がエルリッチマン鉱。それより右上側も同様に黒色だが、そこは輝イリジウム鉱。

承徳鉱 / Chengdeite
承徳鉱はイリジウム(Ir)と鉄(Fe)からなり、Ir3Feの化学組成を持つ。イソフェロプラチナ鉱からみてイリジウム置換体に相当する。自然イリジウムやルテニイリドスミンの一部に付着する産状でみられる。写真では中央下に位置する。灰黒色で細かい凹凸があるためつや消し状態となっている。
レアもの砂白金はおおむね黒くざらっとしている。そのため黒い砂白金を狙って拾い上げるとレアものに遭遇する確率は高くなる。ただし演色性が低い光源だとレアもの黒砂白金であっても白く反射してしまうので、そういった光源の下では一般の砂白金との区別が非常に難しい。そのため砂白金の観察には高演色の光源を用いることが重要となる。今回掲載した写真はいずれもRa95の高演色光源で撮影している。
さて、こうして並べてみると砂白金としてひとまとめにされていたものがある程度は肉眼的に分けられそうである。ひとまずイリジウム系砂白金、プラチナ系砂白金、レアもの黒砂白金くらいは区別できる。まずはそれで十分。新鉱物を狙うのだからプラチナ系砂白金に狙いを絞る。数は多くないが目で見てそれっぽいモノをまずは選別し、その後は色と磁性に注目すればイソフェロプラチナ鉱や自然プラチナとそれ以外もまた区別できる。そうやってトラミーン鉱、フェロニッケルプラチナ鉱、テトラフェロプラチナ鉱を集中選別し、中身を調べていくなかで見つかったのが苫前鉱である。
このたびの新鉱物である苫前鉱は、北海道苫前町の海岸で採集された砂白金から見いだされた。そのため学名を苫前町から採用して「Tomamaeite」と定め、金属鉱物なので和名を「苫前鉱」とした。「とままえ」はアイヌ語のトマ・オマ・イ(エゾエンゴサクの・ある・ところ)が由来とされる[5]。例えば苫前町香川地区の金刀比羅神社や九重地区の九重神社ではエゾエンゴサクの群生が見られるそうだ。苫前鉱を申請した時点の目論見では2020年4月末ごろの開花に合わせて現地を訪れるつもりだった。しかしながら今になって思いもよらない事態が生じた。これを書いている時点で(2020年4月)新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から首都圏には非常事態宣言が発令されており、外出自粛が呼びかけられている。そして北海道としても二度目の非常事態宣言が発令されるに至った。残念ながらこのたびの訪問は控えるほかない。騒動が収まった暁には是非ともまた訪れたい。

苫前町の海岸
苫前町から北の海岸線沿いには海岸段丘が発達している場所が多い。苫前町でも海岸線沿いに盛り上がった堆積層が分布している。
苫前町に分布する海岸段丘は礫混じりの砂や泥を主として、海岸線の露頭では全体的に弱いながらも層理がみえる。またところどころに亜炭が挟まっており、粘土と一体化している領域も多い。本州以南で砂金・砂白金の採集を経験して思ったが、こんな地層が砂金や砂白金を輩出するとはとても思えない。しかし案内人はここが産地だと言い、しかもたくさん得られる場所であるとのこと。そんなまさか信じられない。そんな気持ちを抱きながらも、ともかくじっくり見てみるかと露頭を観察しながら海岸線を歩く。そして地層の切れ目から水が流れている箇所を見つけたので、その流路をじっと見つめてみる。すると砂金や砂白金があるぞ。それもぱっと見の範囲で一粒二粒でない。なるほどとようやく認識を改め、地層から削り取った土砂や露頭直下にたまっている砂をパンニングしてみる。そうすると砂金や砂白金がたくさん得られる。後に文献を調べて知ったが、苫前から北の天塩地域まで海岸段丘を構成する堆積物中に砂金や砂白金が広く分布するようだ[6]。
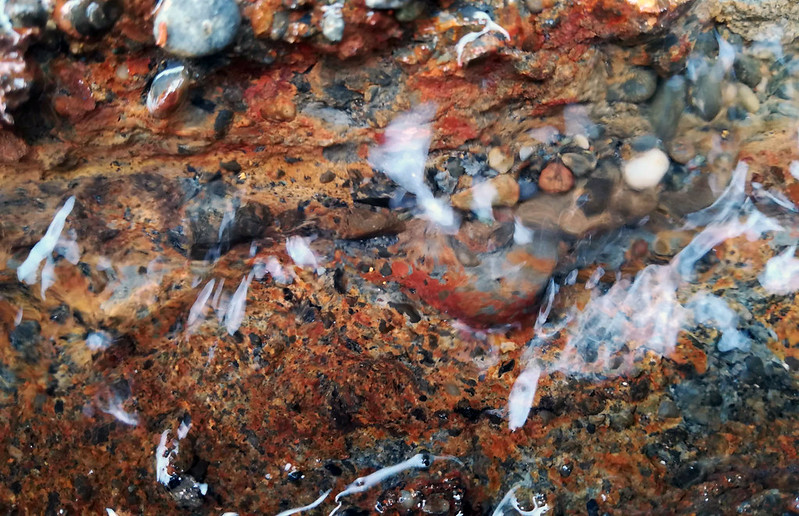
流路に散らばる砂金と砂白金
中央に小さな砂金と砂白金が見えるだろうか。写真内にはほかにも散在している。段丘堆積層の下は第三紀の締まった礫岩となっており、堆積層からこぼれた砂金や砂白金がこの盤に引っかかる。こういったのはスポイトやピンセットで回収する。
苫前町の海岸から得られた砂白金を観察して、トラミーン鉱などを伴うプラチナ系砂白金のみを分別した。そしてその研磨片を作成して光学顕微鏡で観察すると、かなりわかりづらいがトラミーン鉱とは微妙に異なるコントラストが認識できる。なんだろうと走査型電子顕微鏡に試料を入れて後方散乱電子像で見たとき、トラミーン鉱の中に10ミクロン程度かそれ以下の粒が散らばっていることがわかった。これが苫前鉱であった。分析をしてみると銅(Cu)とプラチナ(Pt)のみが検出され、化学組成としてCu3Ptの値になる。銅とプラチナからなる鉱物はいくつかあるが、Cu3Ptの化学組成となる鉱物種はまだ無い。そうなるとこれは新鉱物だ。調べていくうちにテトラフェロプラチナ鉱からも苫前鉱が見つかるのだが、産状やサイズがことごとく同じ。こいついつもちっちゃいな。さあどうしよう。

自然ルテニウムに付着したトラミーン鉱の断面写真
トラミーン鉱中に苫前鉱が散在しており、代表的なものをひとつ青い矢印先で示した。苫前鉱が埋まっている基質がトラミーン鉱で、コントラストが斜めに分かれている左側は自然ルテニウム。
調べてみると1986年にロシアの砂白金から今回と同様な産状とサイズでCu3Pt組成の鉱物(=苫前鉱)が見いだされてはいたが、新鉱物として申請はされていない[7-9]。おそらく構造データの取得ができなかったのだろう。確かにこのような産状かつ10ミクロン程度以下のサイズしかない鉱物からどうやって構造データを取得すればいいのか。通常それはとても難しい問題である。しかし幸いなことにこの場は電子顕微鏡室であり、私の管理する透過型電子顕微鏡は10ミクロンどころか1ミクロン以下であっても構造データを得られる装置である。適切な試料を作成するほうがむしろたいへんだったが、果たして無事に構造データを取得できた。新鉱物の申請書を提出したのが2019年12月。そして2020年4月3日、苫前鉱の承認通知が届いた。

透過型電子顕微鏡で見た苫前鉱とそのシミュレーション
透過型電子顕微鏡はその名が示すとおり顕微鏡の一種で、簡単に言うと超高性能な拡大鏡である。点分解能は1ナノメートル(=1/1,000,000ミリ)をさらに一桁下回る。そのため条件を整えて観察することで原子の並びまで見ることができる。
最後に苫前鉱について総括する。苫前鉱はトラミーン鉱とテトラフェロプラチナ鉱の包有物としてみつかった。ただしトラミーン鉱とフェロニッケルプラチナ鉱は連続するし、ロシアではイソフェロプラチナ鉱から苫前鉱が見いだされているので、それらも苫前鉱を持ちうると考えて良いだろう。つまりはプラチナ系砂白金である。苫前鉱が見つかる確率が高いのはテトラフェロプラチナ鉱であった。そのためテトラフェロプラチナ鉱の標本については「苫前鉱を含みうる」という注意書きをラベルに書くのはかまわないと思う。幸いにテトラフェロプラチナ鉱はプラチナ系砂白金のなかでもちょっと異質な存在なため、見分けることはそんなに難しくない。産地については北海道内の他産地からもテトラフェロプラチナ鉱に伴う苫前鉱を見いだしている。しかしテトラフェロプラチナ鉱はプラチナ系砂白金の中でもかなり数が少ないという難点がある。その点をカバーするのはやはり産地。海岸段丘から得られる砂金や砂白金はそれぞれ浜金・浜白金とも呼ばれ、細かいのだが個体数それ自体は多い。結果的に河川で採集するよりも効率よくテトラフェロプラチナ鉱を得られたと思う。また熊本県ではトラミーン鉱やテトラフェロプラチナ鉱は多産するのだが、どういうわけかそこでは苫前鉱は見つからない。

苫前町の海岸で採集された砂金と砂白金。
海岸で採集された砂金や砂白金を浜金・浜白金と呼んだりもする。これらはとても小さいが個体数としては多く採集できる。私の技量では重砂との完全なより分けは困難。
白金族元素を主成分とする日本産新鉱物は1970年代までに見いだされたルテニイリドスミンと自然ルテニウムだけであったが、2010年代になって皆川鉱、三千年鉱、そして今回の苫前鉱の3種が加わった。北海道において苫前鉱は砂白金から見いだされた新鉱物としては自然ルテニウム以来の発見であり、実に45年ぶり。さらに続くかと聞かれたらそれは厳しいと言わざるを得ない。そのためしばらくは、もしかするともうこれ以上は砂白金からの新鉱物を出せないだろう。また出せたとしてここで書くネタがもうないこともまた悩ましい。日本産砂白金の歴史は皆川鉱で、砂白金の起源などは三千年鉱で、そして砂白金の種類をこの苫前鉱で書いてしまった。次の新鉱物はどう書くか。いやいやそもそもそんな機会が訪れるのか・・
[1] Nishio-Hamane D. Tanaka T., Shinmachi T. (2019) Minakawaite and platinum–group minerals in the placer from the clinopyroxenite area in serpentinite mélange of Kurosegawa belt, Kumamoto Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 114, 252-262.
[2] Mertie J.B. (1969) Economic geology of the platinum metals. Geological Survey Proferrional Paper, 630, 1-120.
[3] Urashima Y., Wakabayashi T., Masaki T., Terasaki Y. (1974) Ruthenium, a new mineral from Horakanai, Hokkaido, Japan. Mineralogical Journal, 7, 438-444.
[4] Aoyama S. (1936) A New mineral “Ruthenosmiridium”. The Science reports of the Tohoku Imperial University. Series 1, Mathematics, Physics, Chemistry, Anniversary Voume dedicated to Professor Kotaro Honda, 527-547.
[5] 苫前町の宝ガイドブック(http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kikakushinko/l6j8rd0000000qt0-att/l6j8rd0000000qvo.pdf)
[6] 対馬坤六, 松野久也, 山口昇一(1954)5万分の一地質図説明書 苫前(旭川-第33号). 地質調査所, pp.16.
[7] Distler V.V., Kryachko V.V., Laputina I.P. (1986): Evolution of platinum-group parageneses in Alpine-type ultramafics. Geol. Rudnykh Mestorozhdeniy: 1986 (5), 16-33/
[8] Jambor, J.L. (1989): New mineral Names. American Mineralogist, 74, 1217.
[9] 苫前鉱は承認される以前はUM1986-17-E:CuPtとして未命名の鉱物として登録されていた:→未命名鉱物リスト
IMA No./year: 2019-029a
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-46298:正模式標本、M-46299:副模式標本)
三千年鉱 / Michitoshiite-(Cu)
Rh(Cu1-xGex)
CsCl-type structure
熊本県美里町
Tanaka T., Shinmachi T., Kataoka K. and Nishio-Hamane D. (2020) Michitoshiite-(Cu), IMA2019-029a. CNMNC Newsletter No. 53; Mineralogical Magazine, 84, https://doi.org/10.1180/mgm.2020.5

三千年(Michitoshiite)鉱の写真
全体としては米粒状の「こぶ」をもつ砂白金で、三千年鉱はこぶの最表面の層を構成することが多い。皆川鉱も同様の産状だが、三千年鉱はこぶの内部に発達することもある。
熊本県の砂白金鉱床から見出された日本産新鉱物三千年鉱(みちとしこう)である。三千年鉱は愛媛大学の教授を務めた宮久三千年(みやひさみちとし)先生への献名となっており、RhX (X = Cu, Fe, Ge)という化学組成をもつ鉱物に対するルート名として採用した。今回の三千年鉱はXの部分で銅(Cu)が最も多い。そうなると正式な学名は「Michitoshiite-(Cu)」となる。和名はどうしようか。今回のケースだと「三千年銅鉱」もしくは「銅三千年鉱」とするのが誤解の無い表現になるだろうが、今のところは単に「三千年鉱」と呼ぶほうが良い。繰り返すが「さんぜんねんこう」ではなく「みちとしこう」と読む。

宮久三千年教授(1928-1983)
宮久先生(左)は九州大学工学部において木下亀城教授の指導を受け、大分県尾平鉱床をはじめとした九州地方の各種金属鉱床の研究に精力を注いだ。後に愛媛大学に移り、理学部、そして地球科学科の設立に尽力した。
私はかつて大分県下払鉱山から見つかった新鉱物に宮久先生の業績を称えて「宮久石(Miyahisaiite)」という名前をつけたことがある。この宮久石で櫻井賞を受賞するなど私には思い出のある新鉱物なのだが、古老の愛石家は「宮久”鉱”であればもっと良かった」と手厳しかった。日本では鉱物名について学名そのままを呼ぶのではなく、金属系の鉱物に対しては名前の最後に「鉱」を付けて呼び、透明な鉱物には「石」を付ける。そして宮久石はその名が示すように透明な鉱物であった。一方で宮久先生の研究は主に金属が対象だったので、「石」で締める鉱物名はミスマッチだと感じられたのだろう。そのことが10年近くも気になっていたのだが、このたび田中君が主体となってまとめる三千年鉱に貢献できたことでようやく肩の荷が下りた。一つ前の新鉱物である皆川鉱の記事の最後で形にしたいと書いたのがこの三千年鉱である。今回は発見の経緯や背景についても話題を提供しよう。
さて、ここのところ砂鉱に興味を移していたこともあって、今回も砂白金から見出された新鉱物である。まずは一般的な疑問として砂白金の起源について触れてみたい。日本では砂白金は明治時代の中頃に北海道の夕張川と空知川から初めて見出され、その上流には大きなかんらん岩体が位置していた。そのため古くから砂白金の起源はかんらん岩だと推測されていた。そして1928年(昭和3年)にまとめられたレポートには「白金層を含むかんらん岩の標本が得られたので、砂白金の起源がかんらん岩であることは明らかだ(意訳)」と記されている[1]。経験的な推測であった「砂白金のかんらん岩起源説」はこの時点で現物によって確認済の内容となった。そして1991年(平成3年)にも白金族元素鉱物を胚胎する蛇紋岩(=変質したかんらん岩)が見つかったことから[2]、砂白金の起源はやはりかんらん岩であることが再確認された[3]。そしてかんらん岩は大まかに言うと地球深部を構成する上部マントルそのものである。つまり砂白金は元をたどると上部マントル由来の鉱物であり、今でこそ砂白金は地上で見られるが、もともと地球のずっと奥深いところを起源とする鉱物である。

レルゾライトという種類のかんらん岩(一部を研磨してある)
かんらん石(灰色)を主として単斜輝石(緑色)と斜方輝石(茶色)を少量含むかんらん岩をレルゾライトと呼ぶ。地球の地下400キロメートル程度の深さまでは大部分がかんらん岩で構成されており、そのうちレルゾライトが多数を占めると考えられている。フランスのピレネー山脈にあるLherz山塊の主要岩石だったことから名付けられた。
北海道の場合、砂白金の母岩はかんらん岩やそれが変質した蛇紋岩であった。次はかんらん岩について関連する事項を簡単にまとめたい。かんらん岩とは「かんらん石を主成分とする岩石」のことである。そしていわゆる超苦鉄質岩に相当する。下の図に示すように、超苦鉄質岩をかんらん石-斜方輝石-単斜輝石の量比で区分したとき、かんらん石を40%以上含む岩石がかんらん岩である。かんらん石が40%以下だと輝石岩と呼ぶ。そしてかんらん岩と輝石岩はその構成鉱物の量比によってさらに細分される。たとえば、かんらん岩については、ダナイト、ハルツバージャイト、ウェールライト、レルゾライトに細分される。輝石岩も同様に細分されるので下の図を参考にしてもらいたい。とにかく超苦鉄質岩とはこのように細かく分けられるのだが、その一方で境界は便宜的なものであって、岩石としての本質が境界をまたいでガラッと変化するというわけではない。基本的には見た目でざっくりと岩石名を判断してかまわない。

超苦鉄質岩の分類図
超苦鉄質岩を大雑把で良いので頭に入れておくと、砂白金の産地を開拓する上で重要な指針が得られる。
蛇紋岩についても触れておこう。超苦鉄質岩の主成分であるかんらん石は変質に弱く、低温・低圧・含水環境下においてはあっさり蛇紋石に変化してしまう。地球深部に超苦鉄質岩があったとして、それが地表に上がってくるまでの活動で含まれていたかんらん石はすっかり蛇紋石に変化してしまうことが多い。そして蛇紋石が含まれる岩石のことを蛇紋岩と呼ぶのだが、実はそこには明確な定義や細分はない。つまり上のように細かく分類された超苦鉄質岩であったが、それがひとたび変質してしまえば一様に「蛇紋岩」として一緒くたに扱われる。それでも野外では蛇紋岩という名称を用いて調査を行うことは非常に有用であろう。しかし、いざ砂白金のことを真面目に考えようとした際に蛇紋岩を一様の岩石と認識しているようでは、当たり前だが何も理解が進まない。そこで変質に強い鉱物に注目して蛇紋岩を観察してみる。すると蛇紋岩の元になった超苦鉄質岩が何であったのかが推測できることがある。そうすることでようやく理解が一つ進む。つまり蛇紋岩から供給された砂白金であっても、その本質を理解するためにはその蛇紋岩が元はどんな超苦鉄質岩であったかを知ることが第一歩である。逆に言うと、岩石から白金族鉱物についてある程度の予測を立てることができる。

ダナイトという種類のかんらん岩
かんらん石が9割以上含まれるかんらん岩のことをダナイトと呼ぶ。かんらん石ばかりで輝石はほとんど入っていない。ニュージーランドのRichmond山脈にあるDun山から命名された。Dunとは茶色の意味であり、風化したダナイトが示す典型的な茶色(写真右端)に因んでいる。

ダナイトを起源とする蛇紋岩
ダナイトを構成していたかんらん石がことごとく変質して蛇紋石と磁鉄鉱に変化してしまった蛇紋岩。暗黒緑色でつるっとした印象が特徴。この質感が蛇の皮に類似していたことから、ラテン語で蛇を意味するSerpensから蛇紋岩(Serpentinite)と名付けられた。
たとえば、北海道の砂白金産地のかんらん岩にはかんらん石ばかりが含まれており、輝石があまり入っていないか、たまに入っていても斜方輝石である。こういったかんらん岩はダナイトからハルツバージャイトに該当する。そして「かんらん石ばかり」というのは、いわゆる「涸渇した」特徴でもある。マントル内部の平均的なかんらん岩は主にレルゾライトと考えられており、かんらん石のほかに斜方・単斜輝石がそこそこ含まれているが、メルトが抜けるほどかんらん岩はダナイトに近づいていく。そして、メルトが抜けることを涸渇すると言う。ではそのメルトの代表的な成分とは何かというと、かんらん石と対極にある斜方輝石や単斜輝石のことであり、それらが特に集まった斜方輝石岩や単斜輝石岩はマグマだまりで生じる。そこに白金族元素のうち「ロジウム(Rh)-パラジウム(Pd)-プラチナ(Pt):プラチナ系」はマグマ(液相)に濃集しやすく、「ルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir):イリジウム系」は岩石(固相)に残されがちという性質を考慮するとどうだろうか[4]。涸渇したかんらん岩から得られる砂白金はイリジウム系が多く、マグマ由来の輝石岩ではプラチナ系が主体となりそうだ。実際はどうかというと、涸渇したかんらん岩を起源とする北海道の砂白金はやっぱりイリジウム系ばかりである。

かんらん岩の部分溶融とマグマだまりの(勝手な)イメージ。
部分溶融によって生じたメルトは輝石成分やプラチナ(Pt)系元素を取り込みながらマグマだまりを形成する。マグマだまりの中では鉱物の結晶化・沈降・集積によって、底部に輝石岩が形成される。この図ではクライノパイロキシナイトを例に描いている。また白金族元素鉱物(PGM)としてはマグマだまり中のものはPt系元素に富み、涸渇したかんらん岩のものはイリジウム(Ir)系に富むことになる[4]。
日本列島にも超苦鉄質岩は様々な地域に分布している。しかしながら日本の超苦鉄質岩はかんらん岩が多く、特に北海道では砂白金の母岩はダナイトやそれに近いハルツバージャイトといった涸渇したかんらん岩である。砂白金というテーマに絞って簡単に述べると、北海道でプラチナ系砂白金を探そうという試みはそもそもムリスジと言って良い。そうと知らずにプラチナ系砂白金の収集を試みたのが旧日本軍。プラチナ系砂白金がどうしても必要だった旧日本軍は、戦時下において強制労働を含めて述べ80万人以上をも動員して、北海道をとことん掘りまくって、ついにプラチナ系砂白金の鉱床を見つけることができなかった。そして日本全体を見渡してもプラチナ系砂白金の鉱床はこれまで見つかっていない。ところが平成から令和に切り替わろうという時代になってプラチナ系砂白金の鉱床が初めて見つかった。場所は北海道ではなく熊本県。そして後から調査に加わった私から見ると、そこはまさにプラチナ系砂白金が出るべくして出る場所だった。いつものように余計な話も挟むが以下に経緯を記してみよう。

ハルツバージャイトという種類のかんらん岩
ダナイトに近いハルツバージャイトで、かんらん石(緑色)の他に斜方輝石(中央の茶色)を含むかんらん岩。単斜輝石はほぼ入っていない。Harzburg(ドイツ)に因んで名付けられHarz Mountainのかんらん岩を構成する。
田中君と私が砂金や砂白金に興味を持ったのは金水銀鉱の共同研究がきっかけだった。その研究が一段落した後に私は砂白金をもっとよく知るために北海道を調べはじめ、一方の田中君は道外で砂白金の新しい産地を探すという目的を持って行動を始めた。経験を積むために本州で砂白金の産出が噂されている産地にも赴いたようだが、採集された試料はことごとく人工物だった。公式な記録がないのはまあそういうことなのだろうと、少なくとも私は納得した。それでも探査は続けられ、その派生で鹿児島県山ヶ野金山の下流域から棒状の砂金が見いだされた。これは物質としてのウェイシャン鉱であり、水銀と自然金が川の落ち込みにたまり、そこで反応して生じている。しかしその水銀はかつての金山で精錬のために人の手によって持ち込まれた物質である。そうなるとその水銀が反応して生成したウェイシャン鉱は鉱物とは呼べない[5]。それでも原物質がどうであれ、産出に至るプロセスには天然の比重選別が大きな役割を果たしており、これもまた自然が生み出した物質であることに違いない[6]。

ウェイシャン鉱(Weishanite)の写真
「山ヶ野の棒状砂金」としてその存在は以前から知られていたようだが、これは自然の金ではなく、金と水銀の化合物である物質としてのウェイシャン鉱に該当する。山ヶ野金山では明治時代に水銀を用いた金の回収を行っており、そのときに持ち込まれ、のちに河川に流出した水銀と自然金が川底で反応してウェイシャン鉱が形成される。そして水銀それ自体をフラックスにしてゆっくり成長するので、写真のような棒状の結晶ができあがる。人為起源の水銀が関わっているため鉱物とは呼べないがモノ自体は興味深い。
そしていつしか九州の黒瀬川帯をターゲットに探査が行われるようになっていた。黒瀬川帯は超苦鉄質岩をはじめとして様々な岩相が混在する地質帯で、南北分布は狭いが東西には九州から四国を経て、果ては関東山地まで断続的に分布している。九州では熊本県内で南北にやや肥大しており、全体としては蛇紋岩メランジュに相当する地質となっている[7]。八代市あたりを見ると、東の山地に超苦鉄質岩が東西に分布し、複数の河川がその岩体を切るように南北に流れる環境が形成されている。こういった地質分布と地形は砂白金の探査には好都合と言えよう。しばらく連絡がなかったが、ある日に先頭の著者二人による共同探査で得られた少量の砂白金が届いた。その見た目から期待したように、調べてみると砂白金はやはりすべてプラチナ系であった。これは日本における砂白金の開拓史において初となるプラチナ系鉱床だ。

方眼紙の上に置いた砂白金。
最長で4ミリ程度の粒を確認しているが平均的なサイズは1ミリを下回る。すべてイソフェロプラチナ鉱(Isoferroplatinum)がベースになっており、それを包むようにトラミーン鉱(Tulameenite)やテトラフェロプラチナ鉱(Tetraferroplatinum)が発達していることが多く、また多様な鉱物を包有している[8]。ここでは自然プラチナ(Platinum)は産出しない。
私にとって最初の現地調査は真冬だった。南国熊本とはいえ山中は凍えるほど寒く、それなのに川の中をジャブジャブ進み、水の中に手を突っ込んでパンニングをするのだからまさに苦行。しかし冬期は水量が少なく河川の踏査には最適な時期なので、苦行だとしてもひたすら続けるのみである。調査前に地質図を見て予想していたように現場には特定の石が非常に多い。そして寄せ場を探し、三カ所ですごく良いところが見つかった。寄せ場とは砂金や砂白金などの重鉱物が集中してたまっている場所で、調査では寄せ場を見つけることができるか否かが明暗を分ける。今回の寄せ場はいずれも手つかずのようで、私が愛用する10インチ皿を一振りするだけで砂白金が数粒は入ってくる。14インチ皿では一振り10粒ということもあった。そしてこの際に採集された砂白金について、田中君が担当した寄せ場から三千年鉱が、私が担当した寄せ場から皆川鉱が見いだされた。そういった経緯から三千年鉱の記載は田中君に委ねることにした。田中君との共同研究による新鉱物は三千年鉱で3種目となり、現場はもとより論文までも任せられるというのは本当に頼もしい限りである。
産地のあたりを地質図で眺めると山中には超苦鉄質岩が東西に分布しているように見える[9]。また5万分の1地質図によって岩相の詳細はすでに判明しており、調査地を地質図上にプロットすると凡例記号「px」となる岩体に投影される[10]。「px」とは輝石岩(Pyroxenite)の略号であり、実際に現場には大量の輝石岩が転がっていた。ここの輝石岩体は体積の9割以上が透輝石(Diopside)であり、超苦鉄質岩の分類からするとこれはクライノパイロキシナイト(Clinopyroxenite)に相当する。地質図の作成者らによると日本最大の輝石岩体とされる[11]。実は世界を見渡すとプラチナ系が主体となる鉱床には実は必ず輝石岩体が伴われている。世界最大のプラチナ系の鉱床として超有名なブッシュフェルト(南アフリカ)も同様で、輝石岩体が主要な母岩の一つとなっている。もちろんマグマに由来する鉱床である。上で触れたようにマグマ由来の輝石岩体はプラチナ系を期待させるため、資源的な意味でも砂白金探査において目印となる重要な岩体である。

輝石岩体の露頭
変質が著しいが10センチの透輝石の結晶が見出されたと報告されている[11]。もともとカンブリア紀にマグマだまりで形成されたと考えられているが、それが大きな岩体として現在のように定置している。
この輝石岩体は1952年(昭和27)にはすでに存在が示されていたが、そこから半世紀も注目されず、地質図作成のための踏査で2003年(平成15年)に改めて認識されたと紹介されている[11,12]。その地質図は2005年に出版されており、それは砂白金の新産地開拓を行う上ではもはや宝の地図にも等しい。なにせこれは「プラチナ系砂白金を探すならまずはここ」と教えてくれているようなものであった。ただし私が研究に参画した時点で地質図の発行からすでに十数年が経っている。当初これはたいへん気がかりだった。それというのも「寄せ場は掘り尽くすもので、自らの後にまだ採れるようならそれは恥」と考える強烈な堀り師もおり、いずれにしても新産地開拓は早いもの勝ちの側面が非常に強い。もし海外に同じ条件があったらそれはもう瞬殺だろう。そういう事情の中で十数年という年月はあまりにも長く、もはや開発の余地が少ないことを覚悟していた。ところが実際には良質の寄せ場が手つかずのまま何か所も残っているほど注目されていない。現場では首をかしげたものだが、落ち着いて考えるとすこし思い当たる節がある。砂白金探査において北海道の例や蛇紋岩だけがむやみに意識されてはいないだろうか。

クライノパイロキシナイトの写真
巨大な透輝石の結晶からなる輝石岩。こういった岩石は「異剥石(いはくせき)」とも呼ばれる。写真は文献[11]とは異なる場所で採集された。この標本は左右12センチほどになる。砕けてしまったが現場では最大で20センチの結晶を確認している。
日本では永らく北海道のみが現実的な砂白金の産地だった。そのため道外で砂白金を探す際であっても、北海道をベースに物事を考えがちになる。しかし砂白金を総合的に考察する上で大切なのは北海道を基本に据えることではなく、上で述べたように「超苦鉄質岩と白金族元素の挙動」にまずは注目することにある。ところがこういった解説は図鑑や一般向けの書籍では見かけず[13-15]、北海道の産出例だけがやみくもに紹介される傾向がある。その中で砂白金の母岩について超苦鉄質岩よりも蛇紋岩という記述が目立つことが多い。上述したように蛇紋岩と銘打っただけではその本質は漠然としている。それを理解していれば問題ないが、蛇紋岩とだけ強調されていることを真に受けて砂白金の新産地開拓に奮起したとすると、どうだろう。砂白金探査においてプレシャスであるはずの輝石岩が魅力的に思えない。それどころか蛇紋岩でないから目にも留まらない。砂白金産地の開拓でとにかく蛇紋岩を目指せば良かろうという方針は、北海道内ならまあそれでもいいが、道外では狙いを定めているつもりが必ずしもそうではない。そもそも不毛な蛇紋岩も多い。
それでも探索活動を継続すれば今回のように面白い砂白金に出くわすことがあるだろう。そういったときのためにも超苦鉄質岩が頭にあると良い。たとえば今回の砂白金がプラチナ系ばかりだったことについて、母岩を蛇紋岩とだけ一辺倒に捉えているとすぐ手詰まりになる。もしくは、北海道ではイリジウム系が多いので、それとの違いについて地域性で答えを見出そうとするだろう。日本列島の形成史と地質に基づけば地域性による違いというアイデアはあながち外れでもないが、それは本質ではない。一方で超苦鉄質岩を知っていれば地域性という着想よりも先に「ひとまずは当然」とすぐに看破できよう。そしてプラチナ系鉱床であればおそらくあれも・・と次の展望が見えくる。そうやってさらに深く調査を進める中で出くわす予想外が新鉱物の皆川鉱であり、三千年鉱であった。特に三千年鉱は全世界の砂白金研究史を通じてもその存在は全く示唆されていなかったので、我々も非常に驚いた。

黒瀬川帯の超苦鉄質岩体を起源とする砂鉱
熊本の黒瀬川帯で、特にその北部に分布する蛇紋岩メランジュには小規模な単斜輝石岩を含む超苦鉄質岩が点在する。それらを横切る河川でも砂白金の産出が期待できる。現時点でいくつかの河川で砂白金の産出を確認している[7]。
近年に砂白金から見つかる新鉱物については、先に存在が知られている例が少なくない。たとえば一つ前の日本産新鉱物である皆川鉱も同様である。皆川鉱はRhSbを端成分とする鉱物で、それ自体が初めて発見されたのは実は40年も遡る。世界で初めてのRhSb鉱物はTulameen川(カナダ)からの砂白金に包有される10ミクロン以下の粒として1979年に見出され、2014年にはロシアや南アフリカでも見つかっている。しかしいずれも新鉱物として申請されなかった。そういった事情の中、我々が見つけたRhSb鉱物はこれまでのものとは産状が異なり、研究も滞りなく進めることができたので、新鉱物・皆川鉱として承認を受けることになった。なお皆川鉱として承認される以前は、RhSb鉱物については「UM1979-19-Sb:Rh」というコードが附された未命名鉱物として扱われる。こういった未命名鉱物も国際鉱物学連合によって管理されており、その一覧はホームページで公開されている[16]。

皆川鉱(Minakawaite)の写真
ローズグレイの光沢を持つこぶの部分が皆川鉱に該当する。皆川鉱はロジウム(Rh)とアンチモン(Sb)を主成分とし、端成分がRhSbとなる新鉱物である。愛媛大学の皆川鉄雄教授への献名となっている。
では三千年鉱はどうかというと、未命名鉱物の中にも該当がなく、合成実験の研究を通じても三千年鉱に相当する物質は知られていなかった。つまり、天然・合成の研究を通じても、世界でまったく新規に見出された鉱物(物質)であった。そして三千年鉱の定義は結果的にややこしい。三千年鉱とは「Rh(Cu1-xGex) 0 < x ≤ 0.5という理想式において、bcc型、CsCl型、ホイスラー型の結晶構造を採用しうる鉱物」である。そして多形を考慮した今回の三千年鉱における呼称については「Michitoshiite-(Cu)-cP1a1b1c」とするように審査員から提案を受けた。ここを読むくらいの愛好家でもすぐに理解するのは困難であろう。我々も同じである。とにかく三千年鉱のめんどくささには手を焼いた。小さいが故に調べること自体が一筋縄ではなく、一般的な記載に加えて合成実験まで行うことになった。そして今後のための分類まで提案した上で審査に望んでいる。鉱物についての詳細な解説はここの趣旨では無いので、あとは田中君がまとめてくれる論文に任せよう。議論が乱雑となることを避けるために記載と合成で論文を分けるかも知れない。こういうスタイルはたまにある。

三千年鉱(Michitoshiite)の写真(再掲)
右上にあるローズグレイの光沢を持つ米粒状の「こぶ」の最表面層が三千年鉱となる。外観は皆川鉱と酷似しており、組成分析を行うしか両者を区別する方法は無い。一方でこのようなローズグレイの光沢のこぶは皆川鉱か三千年鉱のどちらかになる。ただし三千年鉱は皆川鉱に比べても非常に数が少なく、砂白金が2-300粒あって一つあるかどうかという割合。
結果のほうから思い起こすと、このたびの砂白金鉱床は、これほどにあからさまな例は他に類を見ないと言えるほどの典型的なプラチナ系の鉱床である。理想的な事例とも言えるかもしれない。それほどの好例でありながらも今日まで注目されてこなかった何らかの所以があって、幸運にも我々が巡り合うことになった。この成果に至ることが出来たのはフィールド屋の頑張りが非常に大きい。田中君の場合だと無駄骨に終わることの多い現地調査を東京から通いで数年も続けていた。そして前向きな結果が出始めたタイミングで新町氏の協力が得られることになり、その直後に私が参画した。そのタイミングや役割分担もよかったのだろう。遂には調査結果と学術的な考察が回合し、プラチナ系鉱床の発見という日本の砂白金史上で初となる事績につながった[8]。二つの新鉱物はおそらくこの鉱床の成因的な特徴を代表するものであろう。その記載において、念願だった皆川鉱をこのたび為し得たことは本当に感慨無量である。三千年鉱の記載は技術的にいろいろ難しいところがあったが、合成実験において片岡氏(物性研)にサポートをいただいた。そして2019年12月5日、三千年鉱が正式に承認された。驚いたことにその日は皆川鉱の記載論文が出版された日でもある[17]。浜根・田中の共通の師匠である皆川先生の名を冠する鉱物の記載論文が出版されたその日に、 皆川先生の師匠である宮久三千年先生の名を冠する新鉱物が承認された。 狙ってやったわけではなく結果論に過ぎないが、奇跡だなこれは。三千年鉱は私の鉱物人生の中でひとつのゴールになった。やりきった。
引用
[1] 松本彬 (1928) 北海道に於ける砂金及砂白金に就て. 日本鑛業會誌, 44, 737-745. 740ページの左カラムに「橄欖岩(Dunite)に白金層を含有せること最近札幌鉱山監督局技師渡瀬正三郎氏の調査により其の標本を得、明白となれり(原文まま)」と記されていることから、ここでは「砂白金のかんらん岩起源説」ついて本文献を初出として扱う。
[2] Nakagawa M., Ohta E., Kurosawa K. (1991) Platinum-group minerals from the Mukawa serpentinite, southern Kamuikotan belt, Japan. Mining Geology, 41, 329-335.
[3] 文献[2]は「日本で初めて蛇紋岩(変質したかんらん岩)から白金族元素鉱物(山白金)を見つけた」ことを主張した。一方で中川らは文献[1]を引用していない。ここでは文献[2]については「砂白金のかんらん岩起源説を再確認した」という立場で取り扱う。
[4] Leblanc, M. (1991) Platinum-group elements and gold in ophiolite complexes: distribution and fractionation from mantle to oceanic floor. In Ophiolite Genesis and Evolution of the Oceanic Lithosphere, Proceedings of the Ophiolite Conference, held in Muscat, Oman, 7–18 January 1990 (Peters Tj., Nicolas A. and Coleman R.G. Eds.). pp. 905, Springer, Dordrecht, 231-260.
[5] 鉱物の定義は「地質作用で生じる、一定の化学組成と結晶構造をもつ固体物質」であるため、人の手によって持ち込まれた物質が自然環境で反応して新たな物質を生み出したとしても、それは鉱物とは呼べない。
[6] 田中崇裕,浜根大輔(2017) 鹿児島県山ヶ野(永野)鉱山下流産棒状「砂金」について. 日本鉱物科学会2017年年会, R1-P13.
[7] 蛇紋岩を基質として、地球深部で形成された岩石や、その変成岩など、様々な年代や起源を持つ岩石を巻き込みながら分布する岩体のこと。分布・産状をひっくるめて蛇紋岩メランジュと呼ぶ。
[8] 田中崇裕, 浜根大輔, 新町正(2019)熊本県に分布する黒瀬川帯の超苦鉄質岩体における白金族元素含有鉱物および元素鉱物について. 日本鉱物科学会2019年度年会, R1P-06.
[9] 地質図は地図と地層の合成図であり、様々な色や線などで岩相や断層などが表現されている。Webで利用できるシームレス地質図が非常に便利:https://gbank.gsj.jp/seamless/v2full/
[10] 斎藤眞, 宮崎一博, 利光誠一, 星住英夫(2005) 砥用地域の地質.地域地質研究報告(5万分の1地質図幅).産総研地質調査総合センター,218 p.
[11] 斎藤眞, 宮崎一博, 塚本斉(2004)九州中部、熊本県泉村-砥用地域の“黒瀬川帯”蛇紋岩メランジェ中の単斜輝石岩. 地質調査研究報告, 55, 171-179.
[12] 勘米良亀齢 (1952) 熊本縣氷川流域における上部石炭系および下部二畳系. 地質学雑誌, 58, 17-32.
[13]論文や記事で白金族元素の挙動について簡単な解説が記されているが(例えば[14,15])、図鑑や書籍などになるとこういった言及は見当たらない。
[14] 中川充, 太田英順(1993)北海道のオフィオライト産砂白金. 石井次郎教授追悼論文集, 133-141.
[15] 中川充(1994)砂白金の宝庫-北海道はイリジウムの時代. 地質ニュース, 480, 23-26.
[16] International Mineralogical Association, COMMISSION ON NEW MINERALS, NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION (http://cnmnc.main.jp/)
[17] Nishio-Hamane D. Tanaka T., Shinmachi T. (2019) Minakawaite and platinum–group minerals in the placer from the clinopyroxenite area in serpentinite mélange of Kurosegawa belt, Kumamoto Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 114, 252-262.
IMA No./year: 2019-024
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-46296:正模式標本、M-46297:副模式標本)
皆川鉱 / Minakawaite
RhSb
The Sb analogue of cherepanovite
熊本県美里町
記載論文:Nishio-Hamane D. Tanaka T., Shinmachi T. (2019) Minakawaite and platinum–group minerals in the placer from the clinopyroxenite area in serpentinite mélange of Kurosegawa belt, Kumamoto Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 114, 252-262.

皆川鉱の写真
全体としては「こぶ」をもつ砂白金で、皆川鉱はローズシルバーの金属光沢で、こぶの最表面層を構成する。
令和時代最初の日本産新鉱物、皆川鉱(Minakawaite)である。皆川鉱は愛媛大学教授を務めた皆川鉄雄先生への献名となっている。ちょうど20年前のことになる。大学の2年時で進路を振り分ける際に、私は(成績が芳しくなかったので)強制的に地球科学系へ回された。しかしそれは結果的に皆川先生に師事する機会となり、そこで初めて鉱物にふれて、私の鉱物人生が始まり、今がある。すなわち皆川先生との出会いが私の人生の再出発点でもあった。これまでずっと二人三脚でやってきて、皆川先生との共同研究による新鉱物は17種になる。皆川先生に教えてもらったことを駆使して私ができる恩返しは、やはり新鉱物への献名しかないと思っていた。ようやく念願が叶った。これまでご指導いただき、誠にありがとうございました。
今回の著者の一人、田中君もまた愛媛大学(大学院)で皆川先生から鉱物を学び、私の後輩に当たる。田中君との共同研究による新鉱物は、金水銀鉱に次いで皆川鉱が二つ目になった。今回の皆川鉱の発見につながる試料はまずは彼が見つけてきた。皆川鉱は「砂白金(さはっきん、すなはっきん)」から見出された新鉱物である。そこで今回は日本の砂白金をテーマに話を進めてみよう。
まずは言葉を整理したい。一般には「白金」というと「プラチナ(Pt)」という単独の元素もしくは金属を指す。一方で「砂白金」という単語の構成要素としての「白金」は「白金族元素を主成分とする金属(鉱物)」のことである。そして「砂」は漂砂という意味を持つ。つまり「砂白金」とは「漂砂として堆積した、白金族元素を主成分とする金属(鉱物)」の総称となる。また調べた範囲では明治時代の文献では「砂白金」という文字は見あたらず、大正3年以降で「砂白金」が確認できた[1]。公的な文面では大正5年の砂鉱法改正案の議事録で初めて「砂白金」が登場する[2]。それから砂白金は日本語では単語になっているが、砂白金に対応する英単語は存在しない。例えば「Placer Platinum-group metals (minerals)」や「Alluvial Platinum-group metals (minerals)」などが砂白金の英訳になる。論文では省略して「Placer PGM」とされることも多い。

白金族元素の一覧
融点の高い順に左から右に並べている。地球化学ではOs-Ir-RuとRh-Pt-Pdに分けてその挙動を考えることが多い。ここではイリジウム系(Os-Ir-Ru)とプラチナ系(Rh-Pt-Pd)と呼んで話を進める。
次に学術文献から読み取れる日本の砂白金の発見史をたどってみる。多少の食い違いがあるが文献[3-7]を総合すると、砂白金は明治23年(1890年)頃に夕張川・空知川で初めて見出され、夕張産の砂白金について明治25年(1892年)にはイリジウム-オスミウム合金であることが判明する。そして明治26年(1893年)には砂白金の産地として、現在の宮城県気仙沼市、茨城県大子町、銅山川(愛媛県~徳島県)が挙げられている。ただしそれらの産地の砂白金は続報に乏しく、昭和25年(1950年)の段階で砂白金の確実な産地は北海道のみだと認識されている[3]。現時点においては、北海道以外の産地として埼玉県荒川や愛媛県小田川が学術文献から確認できるが [8,9]、産出量はごく微量に過ぎない。その他の産地についても噂はあれども、学術文献からは確実な情報は拾えなかった。いずれにしても北海道外では砂白金は産出しても微量ということは共通している。
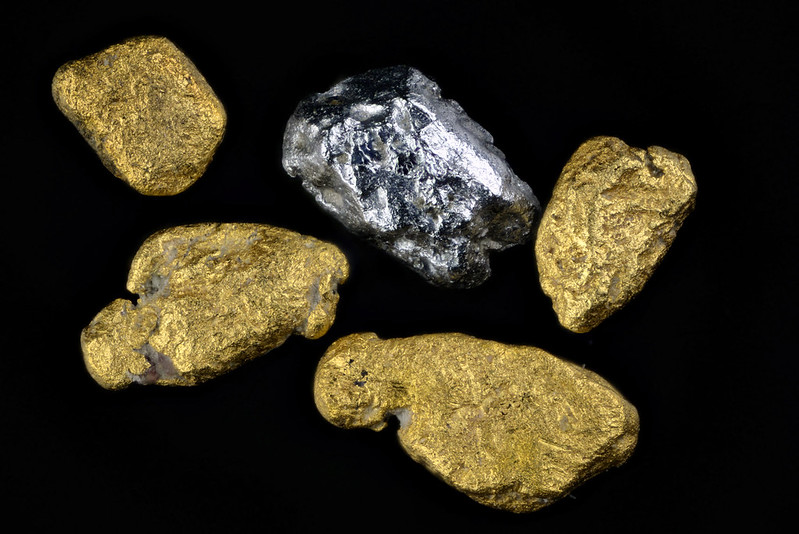
愛媛県小田川で採集された砂金と砂白金
この産地からの砂白金はこれまでに自然オスミウムと自然イリジウムの産出を確認している。自然イリジウムの一部には輝イリジウム鉱も伴われていた。
砂白金の産地が北海道に集中しているということは、日本における砂白金の開拓史は北海道が舞台だったことを意味している。北海道の砂白金はオスミウム(Os)-イリジウム(Ir)-ルテニウム(Ru)を主成分とする合金がほとんどで、ロジウム(Rh)-プラチナ(Pt)-パラジウム(Pd)はかなり少ない。ここでは簡単に前者3つを「イリジウム系」と呼び、後者3つは研究では「パラジウム系」と呼ばれるがここでは「プラチナ系」と言っておこう。そして、北海道産砂白金の開拓史において、最初期では砂白金はゴミに等しく、ある時期からイリジウム系砂白金の需要が生まれ、晩期はプラチナ系砂白金の確保ために無茶な開発が行われた。続いて北海道を舞台とした砂白金の利用と開拓史について述べたい。

北海道産の砂白金
この写真の中に移っている砂白金はほとんどがイリジウム系の合金で、いわゆるイリドスミンと呼ばれるもの。個人的に分析してきた経験を元にすると、プラチナ系砂白金は大雑把に見積もって5%程度の存在度だろう。
北海道でよく採れたイリジウム系砂白金は通称で「イリドスミン」と呼ばれ、耐摩耗性に優れ、酸にも強く融点も非常に高いといった特徴をもつ。つまり加工が困難なやっかいな金属であり、それ故にイリドスミンは当初は用途が無いばかりか、それが混じった砂金は買い手がつかなかった。イリドスミンが混じった砂金から作られた地金を彫刻するとノミが欠けてしまうことから、とりわけ彫金師には嫌われたようだ[10]。そんな邪魔者のイリドスミンであったが、大正初め頃から大きな需要が生まれてくる。その用途は万年筆であり、北海道産砂白金の大部分を構成する堅くて摩耗しにくいイリドスミンは万年筆のペンポイントには最適な素材だった。一方で万年筆のペンポイントとして使えるちょうど良い大きさ・形の砂白金は当然だが少なく、天然物をそのまま利用するやりかたは歩留まりが悪かった。そのため、砂白金を溶かして小球に加工する技術が必要になる。

PILOT社の万年筆
ペンポイントの素材は各社で異なっているが、PILOT社の金ペンにはイリドスミンに該当する合金が使用されている。分析してみたところペンポイント(銀色部)はOs44Ir36Ru20組成の合金で、北海道産イリドスミンとよく似た組成になっている。また地金は14Kと表記されているが、実際は15Kを少し上回る品位だった。ものによっては14K表記でも20Kを越えることがある。何らかの手違いか、追加で金メッキを施してあるのだろうか?
海外では砂白金を溶解させる方法(ホランド法:強熱中の砂白金にリンをぶち込む)はすでに確立されていたが、その当時の日本にはホランド法は伝わっておらず、日本人は独自に溶解技術の開発を試みた。そこで黒鉛の上に設置したイリドスミンに大電流を流す方法が試されたが、良質な小球は得られなかったようだ。あるとき岡田陽と並木良輔はイリドスミンの加工にライムライトを思いついた。ライムライトは酸水素炎で石灰を強熱して得られる強烈な白色光を指し、大正期には舞台照明として用いられていた。酸水素炎の温度は2800℃にも達するため、純粋なオスミウムでもない限りたいていは溶かすことができる。岡田と並木はライムライトの技術を習得するため、写真屋を装って映写技師に師事したという話がある[10]。結果的に彼らはペンポイントに適した良質な小球の量産を可能にした。並木は後に並木製作所(現:PILOT社)を設立して国産万年筆の販売を始めた。PILOT社は今ではプラズマ溶解でペンポイントを作っている。

万年筆のペンポイント
左はPILOT社の製品で18K地金にOs40Ir40Ru20組成のペンポイント。右は別会社の製品で同じく18K地金であるが、ペンポイントはIr32Re27Ru21Pt13Co8組成。
国産万年筆が誕生したころの北海道では島田千代松が頭角を現し、北海道産イリドスミンについて、現場からの買い付けと道外への販売を独占するようになっていた。千代松は自身もかつては採掘人だったこともあり、同僚の性質をたいへん良く理解していた。例えば、古い時代には砂金に混じる砂白金は嫌がられ、砂金を主に掘る人たちは夜になると囲炉裏端で砂白金を選別・廃棄していたことを千代松はよく知っていた。そして千代松は採掘人の住居跡から囲炉裏の灰を集めて砂白金を回収することがあった[11]。また彼は選別についても独自の技術を持っていた。西洋皿に砂白金とその他が混じった重砂を入れ、皿を傾けて片側を筆の柄で軽くたたくだけなのだが、イリドスミンとその他は挙動が異なるため楽に選別できる[10]。自分の試料でも真似して選別していたところ、イリドスミンとは別に明らかに挙動がおかしい粒があった。拾い上げて調べてみたところ、それはQusongiteという極めて珍しい鉱物であった。先人の知恵は試してみるものである。
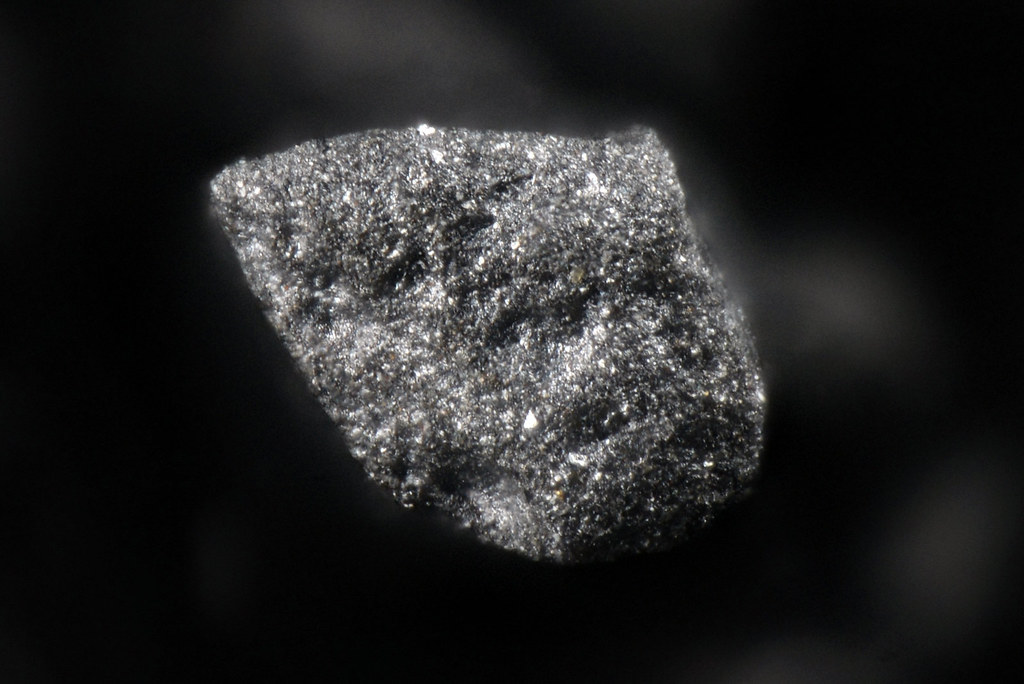

炭化タングステン鉱(Qusongite)の写真(上)とSEM画像(下)。
Qusongiteは天然で生じた炭化タングステン(WC)なので、和名は炭化タングステン鉱で良いだろう。写真の標本は北海道産砂白金に伴われて見つかった。粒は小さい結晶の集合体で、その表面には四面体結晶が見られる。炭化タングステン鉱は最初にチベットの超苦鉄質岩からみつかった鉱物。
昭和12年(1937)の日華事変を契機として、昭和15年までには民間への砂白金の提供は止まってしまう。そして戦前では個人操業の域を出なかった砂白金の採掘は、戦時下では国策事業として大規模に行われた。砂白金の採掘のために設立された帝国砂白金開発有限会社では昭和17-20年(1942-1945)の期間に延べ約85万人を動員したようだ[10]。他にもいくつかの採掘会社が設立され、それらによって河床が何キロにもわたって数メールも掘り下げられ、砂白金は本当に根こそぎ回収された。国策事業だったことから、北海道大学では自ら演習林を解放して職員を採掘に当たらせたこともある[12]。昭和17-20年で北海道全体から生産された砂白金は合計で約76kgと記録されている[3]。この時代、砂白金は重要な軍事物資であった[13]。
旧日本軍が砂白金を求めた理由のひとつに「秋水(しゅうすい)」というロケット戦闘機が関係している。秋水はアメリカのB-29爆撃機を圧倒的に優位な立場から確実に撃墜できる決定的な戦闘機となるはずだった。私が勤務する東京大学柏キャンパスには道路を挟んで「柏の葉公園」が隣接しており、この公園はかつての柏飛行場の跡地に作られている。戦時下において、この柏飛行場は秋水の基地だった。秋水の燃料はメタノール、過酸化水素、ヒドラジン[14]。当時は高濃度過酸化水素を電解法で生産しており、戦時下においては電極用のプラチナを国産でまかなうしかなかったが、上で述べてきたように北海道産砂白金にはプラチナ系の含有量が非常に少ない。あれほど無茶な開発をしても必要量は確保できなかったようだ。そのあげく、ついに秋水は完成に至らない。そして終戦と共に北海道産砂白金の開拓史も終焉を迎える。産業用途の白金族元素は、以降は輸入品が使用されている。

陽春の柏の葉公園
公園から東大柏キャンパスの方を向いて撮影。公園は軍用飛行場の跡地に作られ、今では市民の憩いの場となっている。
北海道の砂白金にプラチナ系が少ない理由は何だろうか。それは白金族元素の性質と、砂白金の原岩に原因がある。白金族元素は地球深部のマントルを構成するかんらん岩に平均的に分布していたとしても、あるときに部分溶融が生じると、相対的に融点の低いプラチナ系白金族元素はマグマ内に移動しやすく、融点の高いイリジウム系白金族元素はかんらん岩に取り残されがちとなる。そして北海道の砂白金の原岩は、マグマが抜けきった「涸渇したかんらん岩」である。つまりプラチナ系はすでに抜けた後のかんらん岩が原岩なので、そこからこぼれ落ちた砂白金がイリジウム系ばかりというのはあたりまえであった。一方でそういった特徴だからこそ、北海道の砂白金からルテニイリドスミンおよび自然ルテニウムという新鉱物が発見された[15,16]。いずれもイリジウム系が主成分である。
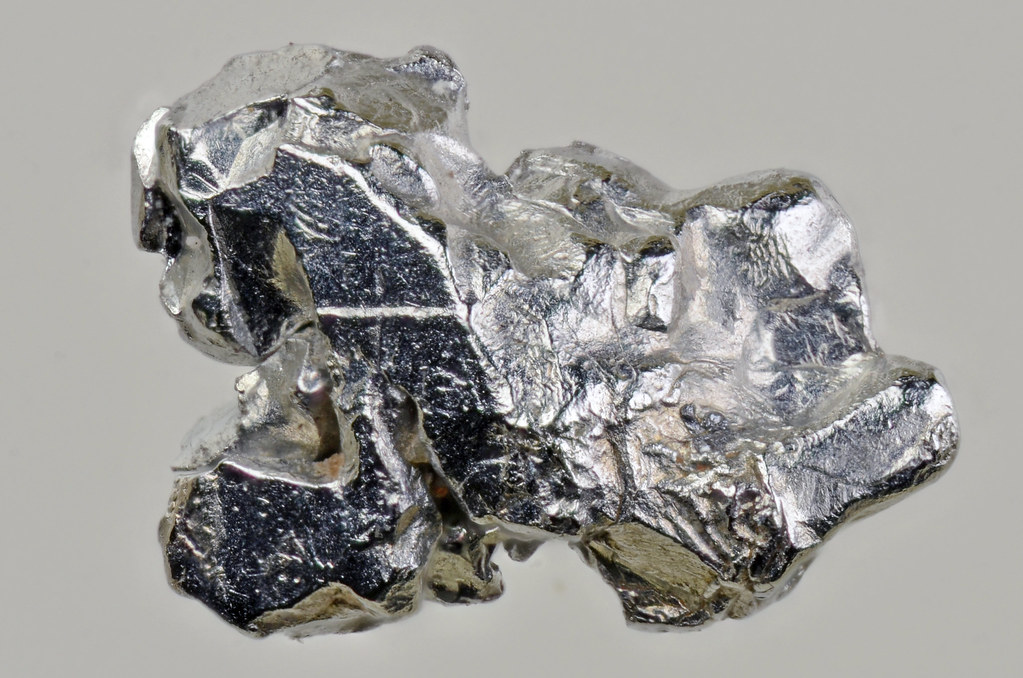
ルテニイリドスミン/ Rutheniridosnime
北海道産砂白金から見出された新鉱物の一つ。ルテニイリドスミンが新鉱物となった経緯はやや複雑なので、日本の新鉱物・ルテニイリドスミンを参照してください。

自然ルテニウム / Ruthenium
これも北海道産砂白金から見出された新鉱物。写真の標本は自然ルテニウムの結晶となる。新鉱物となった経緯は日本の新鉱物・自然ルテニウムを参考にどうぞ。
北海道の砂白金はイリジウム系ばかりで、とんでもない無茶な開発を行ってもプラチナ系砂白金の鉱床はついに見つからなかった。そして砂白金の鉱床それ自体がこれまで北海道に限られていたので、日本全体として考えてもプラチナ系砂白金の鉱床は期待できない、はずだった。一方で下に掲載する写真は今回の研究で得られた試料で、写真中の粒は砂金を除いてすべてプラチナ系砂白金である。旧日本軍が血眼になって探し求めたプラチナ系砂白金の鉱床は、北海道ではなく九州は熊本県に存在したのだ。明治23年(1890年)頃に北海道で初めて認識された日本の砂白金、そこから100年以上を経て、日本では初めてプラチナ系砂白金の鉱床が見つかったことになる。また、北海道外の砂白金としては最も多産する鉱床でもあろう。数日かけて調査して、ネコ板をかけずにパンニング皿を振るうのみだったが、それだけでも全体で1000粒以上が採集された。ちなみに私が愛用しているパンニング皿は10インチである。

熊本県から見つかった砂白金
これらはことごとくプラチナ系の砂白金であった。砂金の産出はむしろ非常に希で、全体で10粒程度しか得られていない。観察結果から判断するとこの産地の砂金は砂白金とは起源が異なると考えられる。

銀白色の強い粒(右)と、やや褐色を帯びた粒(左)
右はイソフェロプラチナ鉱(isoferroplatinum:Pt3Fe)で、左はトラミーン鉱(tulameenite:Pt2CuFe)もしくはテトラフェロプラチナ鉱(tetraferroplatinum:PtFe)。(肉眼では判別できない)。またトラミーン鉱やテトラフェロプラチナ鉱の内部にはイソフェロプラチナ鉱が必ず存在し、いわゆるコア-シェル構造になっている。
熊本の砂白金はプラチナ系であるばかりでなく、多様な白金族元素鉱物を伴うこともまた特徴である。例えば、バウィー鉱(Bowieite:Rh2S3)、チェレパノフ鉱(Cherepanovite:RhAs)、エルリッチマン鉱(Erlichmanite:OsS2)、硫銅ロジウム鉱(Cuprorhodsite:(Cu0.5Fe0.5)Rh2S4)、キングストン鉱(Kingstonite:Rh3S4)、ミアス鉱(Miassite:Rh17S15)、モンチェ鉱(Moncheite:PtTe2)、パラディ鉱(Palladinite:PdO)などが見いだされた。いずれも日本では初めて見つかったものばかりである。バウィー鉱、エルリッチマン鉱、硫銅ロジウム鉱なら砂白金表面で見かける。この三種は世界的に稀産鉱物というわけではないが、Mindat.にもまともな写真が無いことからわかるように、そのものを示す標本が世界的にもほとんど存在しない。ところが熊本ではそれぞれが見てわかるという状態で産出し、個別の標本として扱うことができる。
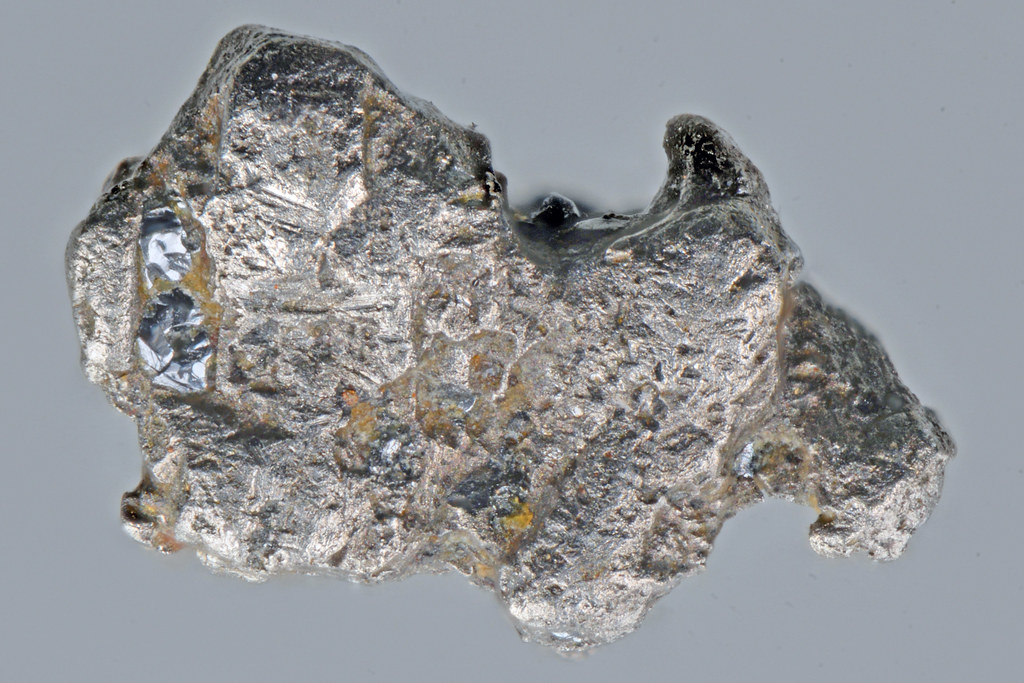
バウィー鉱を伴う砂白金
バウィー鉱は砂白金に包有され、写真では左側に位置する灰黒色で強い光沢をもつ粒が該当する。断面では棒状の結晶形となっていることが多い。

硫銅ロジウム鉱を伴う砂白金
硫銅ロジウム鉱はざらついた黒色の不定型な塊として写真の中央に位置する。その脇にある強い光沢の粒はエルリッチマン鉱。

エルリッチマン鉱をともなう砂白金
エルリッチマン鉱はラウラ鉱(Laurite:RuS2)と固溶体を形成する。どちらも産出し、見た目で両者は区別ができないが、エルリッチマン鉱のほうが多い。エルリッチマン鉱は黒色で強い光沢を持つ粒として生じる。見た目はバウィー鉱に似ているが、バウィー鉱に比べて光沢はさらに強く、色もより黒い。
皆川鉱は上記の鉱物とはやや異なった産状を示す。皆川鉱は砂白金に伴われる楕円形~やや不定形の「こぶ」として産出する。そのこぶの内部は別の鉱物の集合体であるのだが、こぶの表面を覆うように皆川鉱が分布している。皆川鉱は必ずコブの最表面の薄い層として産出し、皆川鉱からなる層の厚さは最大でも5ミクロン程度である。一方でこぶの全体が皆川鉱で覆われているため、分布範囲は広い。実体顕微鏡があれば肉眼でも皆川鉱は十分に認識できる。皆川鉱はRhSbを端成分とし、チェレパノフ鉱(Cherepanovite:RhAs)からみてAs→Sb置換体に相当する。皆川鉱は構造もチェレパノフ鉱と同じくMnP型構造となっている。そんな皆川鉱だが、産出量はどうかというと、残念ながら少ない。この産地でもこれまでに見つけた皆川鉱を含む砂白金は、合計で20粒にも達していない。皆川鉱が非常に少ない原因はおそらくその産状にあるだろう。この産状だと真っ先に川擦れしてしまうので現存数が結果的に少なくなる。こぶ付きの砂白金でも硫銅ロジウム鉱だったというケースは稀ではない。

皆川鉱を伴う砂白金
ローズシルバーの光沢を持つ「こぶ」の部分が皆川鉱となる。この標本では左右にふたつのこぶがある。皆川鉱はそのこぶの最表面層(最大厚み5ミクロン)であり、それより内部は硫銅ロジウム鉱や未命名鉱物からなっている。
皆川鉱に相当する化学組成をもつ鉱物は、未命名のRhSb鉱物としていくつかの産地からすでに報告がある。これまでにトラミーン川(カナダ)とウラル地方(ロシア)の砂白金の中から、そしてブッシュフェルト岩体(南アフリカ)からの鉱石中に、最大で10ミクロン程度の粒として産出が報告されている[17-19]。そして、実はまだ学会でも報告していないのだが自分でもRhSb鉱物を先に見つけていた。(個人的な順番付けでは)日本で最初のRhSb鉱物は北海道の苫前海岸から見つかっており、それはイソフェロプラチナ鉱を主体とする砂白金の外縁部に伴われていた。ただしそのRhSb鉱物は過去の例と同様に数ミクロン程度の大きさだったので、新鉱物として申請するために必須な構造データが得られる見込みがなかった。そのために諦めていたのだが、熊本県の皆川鉱はこぶの最表面を覆うという特殊な状態で産出したため、微小部X線回折計によって結晶構造データの取得が可能だった。新鉱物の審査は全く問題なくあっさり承認された。

今回の研究の前に見つけていたRhSb鉱物(= 皆川鉱)
苫前海岸の砂白金から見いだされた。イソフェロプラチナ鉱を主体とする砂白金の外縁部がフェロニッケルプラチナ鉱に置換されており、その中に数ミクロン程度のザッカリーニ鉱と皆川鉱の微少粒が含まれている。
さて、ここまで産地や鉱床のことについて全くふれていない。しかし申し訳ないが今回はこれでおしまいとする。実は次があることを期待しており、そちらでまとめて書きたい。そこにつなげるように今回は日本の(実質は北海道の)砂白金をテーマに話を進め、まずは「熊本の砂白金鉱床は、日本の砂白金の開拓史上初めてとなるプラチナ系の鉱床」であることを伝えたかった。そして皆川鉱で覆われたこぶの中に未命名鉱物があったことに軽くふれたが、それ以外にもいくつかの未命名鉱物が見つかっている。その中からあと一つはなんとか新鉱物として形にできるかもしれない。もしそれが新鉱物となったときに、鉱床の地質的な背景やその発見の経緯から入っていき、その新鉱物が形になっていく過程なども紹介しよう、という青写真を描いている。しかし、取らぬ狸の皮算用で終わるかもしれない。そんなもの期待できん、という方は 日本鉱物科学会2019年年会@九州大学伊都キャンパス へぜひともお越しください。田中君が鉱床や産出鉱物についてポスター発表することになっている。私もそばにいる、はず。
引用
[1] 著者不明 (1914) 日本鑛業會誌, 30, 729-747.
[2] 砂鉱法議事録
[3] 鈴木醇 (1950) 北海道の砂白金鉱床. 北海道地質要報, 14, 1-41.
[4] 松本彬 (1928) 北海道に於ける砂金及砂白金に就て. 日本鑛業會誌, 44, 737-745.
[5] 近藤 (1892) 地学雑誌, 4, p534a.
[6] 石川貞治 (1895) 北海道産二三の稀有鉱物(イリドスミン、白金、辰砂、クローム鉱物). 地質学雑誌, 3, 245-246.
[7] 鈴木敏 (1893) 日本の鉱物産地, 地学雑誌, 5, 176-180.
[8] 井伊博行, 井伊洋子, 岡田昭彦 (1991) 埼玉県長瀞町樋口の砂鉱床中の白金属鉱物について, 鉱物学会1991年年会講演要旨集, P119.
[9] 浜根大輔, 皆川鉄雄 (2017) 新鉱物 金水銀鉱(Aurihydrargyrumite). 日本鉱物科学会2017年年会講演要旨集, R1-17.
[10] 弥永芳子 (2006) 砂白金~その歴史と科学~. 文葉社, pp233.
[11] 北村順次郎(1977)士別の砂金掘り物語 及川善之進翁のこと. 続.士別よもやま話, 士別郷土研究会, pp.192(p.89-102)
[12] 北大演習林80年(1981)北海道大学農学部附属演習林, pp.172.
[13] 熊谷忠三郎(1944)闘ふ鉱物. 朝日新聞社, pp.277.
[14] 松岡久光(2004)日本初のロケット戦闘機「秋水」-液体ロケットエンジン機の誕生. 三樹書房, pp.246.
[15] Aoyama S. (1936) A New mineral “Ruthenosmiridium”. The Science reports of the Tohoku Imperial University. Series 1, Mathematics, Physics, Chemistry, Anniversary Voume dedicated to Professor Kotaro Honda, 527-547.
[16] Urashima Y., Wakabayashi T., Masaki T., Terasaki Y. (1974) Ruthenium, a new mineral from Horakanai, Hokkaido, Japan. Mineralogical Journal, 7, 438-444.
[17] Dunn P.J., Cabri L.J., Chao G.Y., Fleischer M., Francis C.A., Grice J.D., Jambor J.L., Pabst A. (1984) New mineral names. American Mineralogist, 69, 406-412.
[18] Varlamov D.A., Murzin V.V. (2014) The PGE minerals from placers of Verkh-Neyvinsk ultrabasite massif (the Middle Urals) – new mineral phases and complex of secondary minerals. RMS Annual Session combined with the Fedorov Session 2014, 89-91. (in Russian with English title)
[19] Oberthür T., Weiser T.W., Melcher F. (2014) Alluvial and eluvial platinum-group minerals from the Bushveld complex, South Africa. South African Journal of Geology, 117, 255-274.
No. IMA2018-161 留萌鉱 / Rumoiite
No. IMA2018-162 初山別鉱 / Shosanbetsuite
模式標本:国立科学博物館(NSM M-46178, 46179)
AuSn2, Orthorhombic (Rumoiite)
Ag3Sn, Orthorhombic (Shosanbetsuite)
Known synthetic analogue
北海道初山別村(初山別川)
出典:Nishio-Hamane, D. and Saito, K. (2019) Shosanbetsuite, IMA 2018-162. CNMNC Newsletter No. 49: Mineralogical Magazine, 83, doi:10.1180/mgm.2019.35

留萌鉱および初山別鉱を含む砂金。この裏側は研磨してあり、新鉱物はそこから見つかった。
平成時代最後の日本産新鉱物 となった「留萌鉱(Rumoiite)」および「初山別鉱(Shosanbetsuite)」である。日本産新鉱物の研究史をたどると、平成時代は開幕も閉幕も北海道が舞台となっている。平成で最初の新鉱物は北海道札幌市豊羽鉱山から見出された豊羽鉱(Toyohaite)であり、平成時代の最後を飾る新鉱物が北海道初山別村から見出された留萌鉱と初山別鉱になる。これらは平成31年4月3日に国際鉱物学連合から承認を受けた。
さて、このたびの新鉱物は初山別村を流れる初山別川から採集された砂金の中から見出され、それぞれ金(Au)と銀(Ag)を主成分に持つ。それだけ聞くときらびやかな印象を受けるだろうが、実はその姿は肉眼では捉えられないほどものすごく小さい。さらにこの新鉱物たちは砂金に包まれており、外見からはその存在が全くわからなかった。実際のブツの写真はあとで掲載するとして、ひとまずは経緯から書いていこう。
研究のきっかけは数年前にさかのぼる。以前に愛媛県南予をフィールドとして調査を行っていた中で、想定外の場所から砂金・砂白金を見出すことができた。そしてその活動は新鉱物「金水銀鉱(Aurihydrargyrumite)」の発見という成果にもつながった。このときの研究は主に3人で取り組んだが、その後は各々の興味に基づいた活動を始めることになった。一人は地元でより深く調査を行うことを指向し、もう一人は自身のアイデアを元にして新産地(特に砂白金)を探し始めた。そして私はといえば、砂金や砂白金の持つ情報が例えば生成環境のトレーサーとして使えるかどうかを見極めたく、まずはその実物を調べる経験を積むことにした。

2017年に見出された新鉱物・金水銀鉱(銀白色部)。これを見出したところから砂金・砂白金について興味を持ち始めた。
そのために、なるべくいろんな産地から試料を手に入れて分析するということをしていた。その過程で改めて感じたが、砂金・砂白金の研究は試料の入手がやっかいだ。思ったようにはコトが運ばないと言ったほうが妥当かもしれない。それでもなんとか試料を確保して小さな理解が少しずつ進んできた。そこで、いくつかの産地の砂金・砂白金について色・形と化学組成をいつでも見られるようにしておくと(自分が)便利だなと思い、自然金のページを作って情報をいくつか並べていた。
この自然金のページは産地・写真・組成という内容を主としているが、自分用のメモのつもりだったので他にもさまざま並べた雑多な内容になっている。他の人にはあまり役立つものではないだろうが、これが新鉱物への縁となった。今回の研究に参加している齋藤勝幸さん(留萌市在住)は、不定期に更新されるこの自然金のページに注目していたようだ。
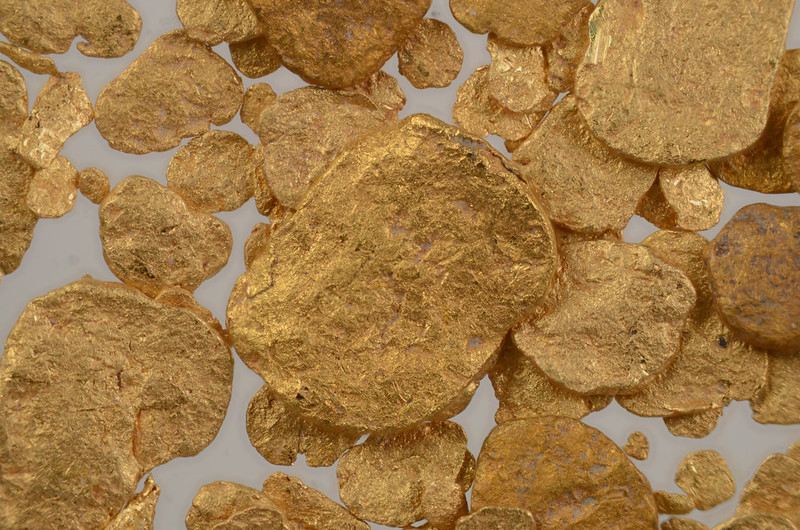
多摩川で採集した砂金。自然金のページにはこのようにいくつかの産地について砂金・砂白金の写真とその分析値を並べていた。
齋藤さんは砂金堀りコーディネーターとして独自の理論と経験があり、自然金のページについてコメントがあるということで連絡が来た。そして砂金・砂白金について話をする中で考えを共有できる部分もあり、北海道・留萌管内の産地を案内してもらう交渉がまとまった。北海道の砂金・砂白金について、特に砂白金は特定の蛇紋岩体から産するものがすでにたいへん有名で、鉱物学的な研究もそういった産地のものに対して行われてきたが、その他の産地となると情報がとたんに乏しくなる。そして留萌管内の砂金・砂白金というのは弥永氏の著作[1]に産出が記されおり写真も掲載されているのだが、具体的な研究例が見当たらない。そのため、留萌管内の砂金・砂白金について私はその実体をまったく把握できていなかった。
留萌管内の地質は年代の異なる地層が組み合わさっているが、ざっくり言うとどこも堆積岩ばかりである。そして変成や変質作用をあまり受けておらず、この地域は保存状態が良好な化石を豊富に産出する。たとえばアンモナイトなどさして珍しくもない。河川の上流にも火成岩や蛇紋岩の分布は全くないため、本州・四国を調査してきた自分の経験からすると、こういった地域では砂金や砂白金の産出はまず期待できない。しかしながら実際は簡単に採集できる。ここで?という場所で砂金や砂白金が採集でき、この地域では自分の見立てが役に立たないことを思い知った。驚いたことに、ある場所では磁鉄鉱やクロム鉄鉱を主体とした重砂がほとんどなく、パンニングで残る砂は白い石英ばかりという状況にも関わらず、唐突に立派な砂白金がゴロっと出てくる。一方で砂金は全く出ないなど、もうわけがわからない。

初山別川から得られた砂金(左)と化石(右)。砂金を採集する過程で黄鉄鉱化した化石も混じることがある。ただしこの化石が何であるのかは専門でないのでわからない。
初夏の季節に齋藤さんの案内で留萌管内において調査を行った。初山別村ではいくつかの川で上流~中流域をざっと見て、所々でいわゆる「盤(ばん)」が出ていることを確認した。初山別川では採集を行いやすい場所を案内してもらい、そこでもやはり盤は露出している。見晴らしも良く、ここならもし熊に出くわしても逃げる余裕がありそうだなと気持ちが落ち着いた。そして改めて足下の盤を観察すると、層理が水流と平行であり、川底や溝にたまっている土砂はほとんどない。草が生えている部分にはもちろん多少の堆積があるが、良質な寄せ場とはちょっと思えなかった。それでも川岸の土砂をパンニングすると予想外に多くの砂金・砂白金が入ってくる。あいにく小雨が降る日であったが、時間が過ぎるのも忘れるほど集中して採集ができた。そして数日かけて留萌管内のいくつかの場所で採集を行い、以前に齋藤さんが採集した試料も少し分けていただいた。

初山別川の下流域。盤は凸凹の少ない砂泥質岩で、層理は水の流れと平行している。堆積物は基本的に薄ぺらい。
こうして留萌管内の砂金・砂白金が手元にやってきた。そしてまずは砂白金の方に手を付けた。すでに有名となっている蛇紋岩地域から得られる砂白金はルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)を主体とした合金が圧倒的に多い。それに少量のプラチナ(Pt)-鉄(Fe)合金が伴われ、それ以外となると非常に稀となっている。この特徴は砂白金の供給源となっている蛇紋岩がいわゆる枯渇したマントル物質であることに由来する。つまり相対的に液相濃集元素であるパラジウム(Pd)-ロジウム(Rh) -プラチナ(Pt)成分はすでに抜けたあとの蛇紋岩が起源だから、相対的に固相濃集元素であるルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)ばかりが多くなる。この傾向が堆積岩が主体の留萌管内ではどうかと思って調べているところである。まだ途中の段階ではあるが、これまでに日本では報告されていない白金族の鉱物が砂白金の中にパラパラと見つかるという成果は得られている。この結果はまた近いうちに鉱物学会などで報告するとして、では砂金の方はどうだろうか。

初山別川で採集した砂金と砂白金。留萌管内の特定の場所からの砂白金にはザッカリニ鉱(Zaccariniite)という珍しい鉱物も含まれていた。
砂金(砂白金もそうだが)に対して何を調べるかというと、表面や内部の組織および化学組成を見ていくことがまずは基本となる。表面だけなら砂金は壊さずにそのまま調べることが可能だが、内部はそうはいかない。内部を調べるためには、砂金をスライドガラス上に樹脂で固定して、おおむね元の半分程度の厚みになるまで手で研磨する。そうやってできた試料を観察するため、単純に半分は消し飛んでいる。このような過程で現れたのが今回の新鉱物、留萌鉱と初山別鉱であった。砂金の厚みが100ミクロン以下であっても手の感覚だけを頼りにざっくり研磨していたので、加減が少し違っていれば今回の新鉱物は気づかれることなく消滅していただろう。
できあがった研磨薄片には金とは異なる鉱物が含まれていた。電子顕微鏡でその部分を観察すると、数ミクロンの粒状の鉱物とその隙間を埋めるいくつかの鉱物からなっている。粒状の鉱物からは金(Au)と錫(Sn)が同じ割合で検出され、これは元江鉱(Yuanjiangite)という鉱物であった。元江鉱は中国で1994年に見出され、今でもまだ世界に数例しか報告のない非常に珍しい鉱物となる。そして元江鉱の隙間を埋めている不定形の鉱物は何かというと、大部分は自然鉛(Lead)であったが、さらによく見ていくと自然鉛とはコントラストの異なる部分が二箇所ある。それらが留萌鉱と初山別鉱になる(下の写真)。数ミクロンからそれ以下というとんでもなく小さいサイズだが、これまでの経験を駆使して何とか新鉱物の申請に必要なデータが集まった。

留萌鉱および初山別鉱を含む部分の電子顕微鏡写真。留萌鉱と初山別鉱は本当に小さな小さな新鉱物となる。
留萌鉱と初山別鉱は砂金の内部に存在した。こういった産状はなにも留萌鉱や初山別鉱に限ったことではなく、砂白金の方でも珍しい鉱物はその内部に存在することが多い。そのため研磨薄片を作ることは砂金・砂白金研究の基本となる。ただし薄片を作れば粒の半分ほどは消し飛び、うまく研磨できたとしても特に何にも見いだせないこともまた多い。その場合はさらに研磨と観察を繰り返し、何も無ければ最終的にすべて失せる。入手に苦労した貴重な砂金や砂白金が、なんら新しい知見も無しに消滅することを何度か体験した。特に初期の段階では手加減の練習もかねていたので、けっこう消えた。うーん、つらい。それでもごく稀に今回のようなことあるので、新しい発見のためには必要なコストだと割り切るしかない。
留萌鉱や初山別鉱の学名について。今回の新鉱物は特に何かのグループに属している訳ではなく、学名については著者が自由に決めることができる。そして今回は地名を採用した。金を主成分に持つ留萌鉱に関しては、産地が留萌管内にあるという理由から学名を「Rumoiite」と決めた。銀を主成分とする初山別鉱のほうは、産地の初山別村に因んで学名を「Shosanbetsuite」とした。そして留萌および初山別はアイヌ言葉に由来する。北海道庁の解釈では、留萌はアイヌ語の「ルルモッペ」から来ており、「潮汐がいつも静かな川」という意味らしい。初山別についてはアイヌ語の「ソエサンペ」に由来し、「滝がそこで流れ出ている川」という意味をもつとされる。ただし地名の漢字表記は単にアイヌ語の発音に漢字を当てただけのようで、個々の漢字の持つ意味から本来の意味はたどれない。
天然に産出する留萌鉱や初山別鉱の実体はせいぜい数ミクロンしかない。私がこれまでに見つけてきた新鉱物の中でも最小のサイズとなる。光学顕微鏡でも見えないほどで、なんとも寂しいとしか言いようがない。その一方で留萌鉱や初山別鉱と同じ化学組成・結晶構造を持つ物質はすでに合成されている。逆に言うと、合成物の研究がすでにあったからこそ今回の研究が可能でもあった。それはともかくとして留萌鉱や初山別鉱は合成できるということなのだから、身近な研究室の学生さんに作ってもらった。

留萌鉱の合成結晶(by Y. Matsubayashi)。やや鈍い銀色。
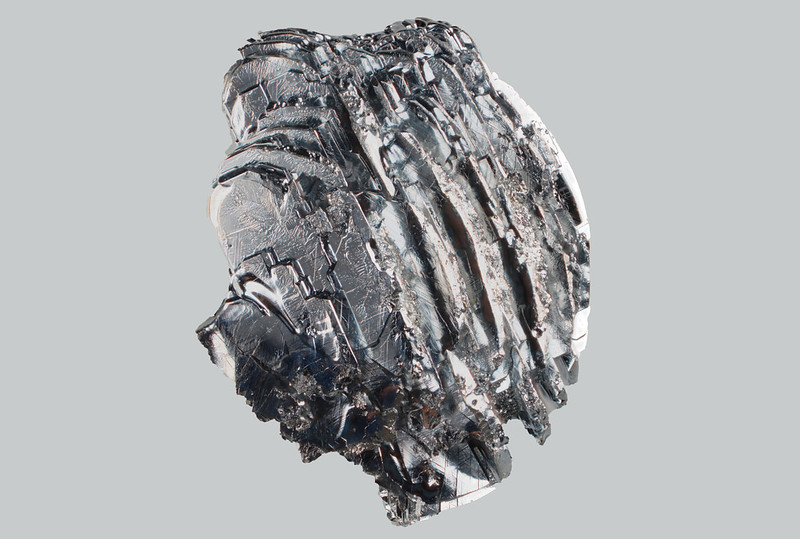
初山別鉱の合成結晶 (by Y. Matsubayashi)。明るい銀色。
留萌鉱は金(Au)と錫(Sn)からなり、AuSn2の化学組成をもつ物質に相当する。金を主成分とするため黄色っぽくなるかと思いきや、できあがった結晶は予想外に銀色の物体であった。そして金は叩けばいくらでも薄くなるが、留萌鉱は叩くと木っ端みじんになる。初山別鉱のほうは銀(Ag)と錫からなっており、Ag3Snの化学組成をもつ物質が該当する。結晶が成長しやすいようで、合成物は平板が何枚も重なった姿で得られた。なかなか格好がよいが、衝撃に対してこちらもやはり脆い。留萌鉱や初山別鉱について風化環境での耐性はまだよくわからないが、天然で見つかったのは砂金が梱包材の役割を担っていたからだと思う。また留萌鉱に相当する鉱物や類似の金-銀-錫鉱物はスイスやロシアのカムチャツカ半島から実はすでに報告されており、いずれもやはり砂金に伴われて産出する[2-4]。特にカムチャツカ半島のほうは今回の研究とよく似た産状となっている。
当初のもくろみであった「トレーサーとしての砂金や砂白金」について。留萌管内というのはそのポテンシャルを評価するのに良いフィールドであると思う。留萌管内の砂金・砂白金はいま露出している蛇紋岩が直接その起源になっておらず、供給源となったはずの岩石はすでに消滅している。過去にあったはずの岩石については想像するしかなく、そういった時に砂金や砂白金の持つ情報は役立つはずである。例えば今回の新鉱物が現世のカムチャツカで見つかったものと同じ成因なら、それは大規模に熱水変質を受けた超苦鉄質岩がかつての北海道に存在したことを意味するのかもしれない。すでに消えた岩石であってもそこから供給された物質が現世に残っていれば、それを調べることによってオリジナルの姿を再現することはできるはずで、そのために今はまだ砂金や砂白金のデータを集めている。そういった思惑の中で新鉱物という予想外の結果が出たことは本当に喜ばしい。平成時代最後の日本産新鉱物というおまけもついた。
引用
[1] 弥永芳子 (2006) 砂白金~その歴史と科学~. 文葉社, pp233.
[2] Meisser N. and Brugger J. (2000) Alluvial native gold, tetraauricupride and AuSn2 from Western Switzerland. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 80, 291-298.
[3] Sandimirova E.I., Sidorov E.G., Chubarov V.M., Ibragimova E.K., Antonov A.V. (2013) Native metals and intermetallic compounds in heavy concentrate halos of the Ol’khovaya 1st River (Kamchatsky Cape, East Kamchatka). Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchestva, CXLII, N6, 79-89.
[4] Sandimirova E.I., Sidorov E.G., Chubarov V.M., Ibragimova E.K., Antonov A.V. (2014) Native metals and intermetallic compounds in heavy concentrate halos of the Ol’khovaya 1st River, Kamchatsky Mys Peninsula, Eastern Kamchatka. Geology of Ore Deposits, 56, 657-664.
IMA No./year: 2017-089
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-45621)
ランタンピータース石 / Petersite-(La)
Cu6La(PO4)3(OH)6・3H2O
Mixite group
三重県 熊野市 紀和町
記載論文:Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Shimobayashi N., Momma K., Miyawaki R., Inaba S. (2020) Petersite-(La), a new mixite-group mineral from Ohgurusu, Kiwa, Kumano City, Mie Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Science, 115, 286-295.

写真1. 新鉱物、ランタンピータース石のタイプ標本。ウニのような放射状集合が特徴的。
三重県熊野市からの新鉱物「ランタンピータース石 / Petersite-(La)」。ミクサ石グループ(Mixite group)の一員で、レアアースのランタン(La)を主成分とする銅リン酸塩鉱物である。三重県というのは多くの鉱物産地がある割には新鉱物がなかなか見つからない、そんなことを言われていた時期がかつてあった。ところがこの10年ほどの期間で最も多くの新鉱物が発見された都道府県は三重県になる。2007-2017年の間で、今回のランタンピータース石を併せて9種の新鉱物が三重県から発見されている。潜在性はそもそも大きかったということだろう。
ランタンピータース石は二次鉱物というカテゴリーに分類される。二次鉱物というのはもとあった鉱物が環境の変化によってまた別の異なる鉱物になったものを指す。いろんな環境で様々な姿で出現するために人目を引くことも多く、全体的に色彩豊かであることから二次鉱物は鉱物愛好家には人気がある。ランタンピータース石は気に入ってもらえるだろうか。
今回は新鉱物が誕生するまでの過程を時系列で振り返ってみようと思う。私にとっての始まりはたしか2015年の秋頃だったと記憶している。愛媛大の皆川氏を経由して3点の試料を受け取った。それは今回の著者の一人である稲葉氏が皆川氏へ鑑定を依頼したが、皆川氏のところでは出来ないということで私に回ったきた(丸投げされた)話である。送られてきたブツは砂岩の空隙に淡緑色のほっそい針が不完全な放射状でパラパラ散らばっている標本であった(写真2)。

写真2.皆川氏経由で送られてきた最初の標本。不完全な放射状集合で、結晶も非常に細かった。これはほとんどがセリウムピータース石であった。
結晶はとても細い上に脆く、さらには量が少ないので分析が難しい。それでも何とか分析してみると、「セリウムピータース石」と同定された。この産状でレアアースを主成分とするピータース石が出ることにまず驚いたが、その当時、セリウムピータース石はアメリカでほんの1年前に発見されたばかりの鉱物だった。これにも驚いた。皆川氏のもとへ最初に試料が渡ったのはさらに数年遡るということだったので、私のところへ来るのがもう少し早ければもしかしてと思ったが、まあしょうがない。2015年末頃には本邦初産、世界でも二番目のセリウムピータース石ということを稲葉氏に伝えた。
年が明けて2016年。その年の鉱物学会で「本邦初産のセリウムピータース石」を発表しようと考え、3月に現地調査をした。このあたりには砂岩と泥岩ばかりが分布しており、泥岩はたまに石炭を胚胎する。そういった堆積岩に熊野酸性岩類と呼ばれる火成岩がドカンと貫入し、硫化物を伴う熱水が発生したようだ。熱水が堆積岩を様々に貫き、大規模に発達した黄銅鉱・黄鉄鉱鉱床を採掘していたのが紀州鉱山になる。ところが紀州鉱山からみて北側に位置する河川は同様の地質ながらも一見して鉱石は見あたらず、不毛な砂岩と泥岩がただ転がっているばかりであった。それでもよーく見て歩くとたまにやたら錆びた石がみつかる。その本体はやっぱり砂岩・泥岩であるが、中に少量の黄銅鉱を含み、割ってみると青や緑色の二次鉱物が見えた(写真3)。自分で採集した石や以前に稲葉氏が採集した石なども持ち帰り、もう少し調べることにした。

写真3.新鉱物が見つかった河原の石。砂岩と泥岩ばかりだが、まれに黄銅鉱を含み、二次鉱物を伴う石が見つかる。そういった石の表面は例外なく褐色に錆びている。
当初は参考程度のつもりだったのでいくつか適当に結晶をピックアップして分析を始めた。そうした中でセリウムよりもランタンが多い試料があることに気付いた。実のところ最初の試料でもいくつかランタンが多い結晶はあったのだが、全体的にはセリウムのほうが多数派だったので、あまり重要視はしていなかった。ところが今回は明らかにランタンが多数派を占める試料が存在している。ランタンピータース石なら新鉱物になる。改めて試料とそのミリ単位の空隙の一つずつにも番号を振って、記録を取りながらさらに調べ始めた。「もしかしてランタンピータース石という新鉱物になるかも」という旨を稲葉氏に伝えたのは2016年の初夏だったと思う。そして鉱物学会への発表も見送り、調査に専念することにした。
期待が生まれたあと、時間はかかったがどうにかデータがそろった。申請書を提出したのは2017年の秋になる。そして2017年12月に承認通知を受け、ランタンピータース石が誕生した(写真4)。最初の試料を受け取った時から数えて2年あまりが経過していた。

写真4.タイプ標本の写真。不完全な放射状集合には絹糸光沢がよく見える。クリソコラの上にランタンピータース石は産出する。
さて各論に入ろう。まずはピータース石。種類としてはランタンとセリウムに富む二種類があるが、共存することもあり見た目ではわからない。そのため見つけたらラベルは両方を記すことでよいだろう。ここではピータース石としての特徴を記す。ピータース石は黄緑色の六角柱状結晶が本来の姿であるが、あまりに細いのでルーペ程度では針状に見える。もしルーペでも六角が確認できたらそれは最上級の標本であろう。いずれにせよ結晶が放射状に集合し、ウニのようになっている状態が欠損のない完璧な姿である。しかし多くは不完全な集合体であり、ほうきのように見える集合も多いほか、数本の針が散らばっている貧弱な状態も見かける。それでも不完全な集合体では特徴的な絹糸光沢がむしろよく見える。半球状の集合体では中心と外側では色味が異なっているように見えるが、それは結晶の密度の違いであってモノは同じである。産状としてピータース石は例外なくクリソコラの上に生じる。下地となるクリソコラの厚みは様々だが、それを剥ぐと下には水晶がいることが多い。銅成分を溶かし込んだ液体が晶洞にとどまり、クリソコラを沈殿させ、最後にピータース石が生じたと思われる。同様の産状でアガード石、孔雀石、擬孔雀石、ブロシャン銅鉱も生じている。これらも写真を見ていこう。
「アガード石」について。この鉱物はピータース石のヒ素置換体に相当し、ピータース石とは連続的に組成が変化する。多くの場合はアガード石側の組成にうっかり足を踏み込んだという結晶であり、そういったモノはピータース石と全く判別がつかないので肉眼鑑定ではどうにもならない。その一方でアガード石ばかりの晶洞も見つかっている。そのアガード石はピータース石に比べて緑色の質がやや異なる印象をうける(写真5)。産状や姿形は共通だが微妙な色加減は異なるので、両方をならべて比べると目の肥えた愛好家なら判別できるかもしれない。アガード石はランタンアガード石が見つかっているが、ピータース石に比べてアガード石だけの産出は例が少ないので調査はあまり進んでいない。また、観察した範囲内ではアガード石はこの産地で唯一の砒酸塩鉱物である。

写真5.ランタンアガード石(写真幅約3ミリ)。ピータース石とはわずかな色味の違いしかない。並べて比べてもその差は微妙。非常に薄いがアガード石の下もやはりクリソコラ。
クリソコラ上にはピータース石(アガード石)と同じ産状で、似たような放射状集合で産出する紛らわしい鉱物がいる。本来なら真っ先に想定するありふれた二次鉱物だが、ピータース石を先に見ると思い浮かばない(写真6)。これは「孔雀石」である。ピータース石(アガード石)に比べると明らかに青みが強いが、野外においてルーペで観察するという状況で思いこみもあると初見で判別できなかった。ピータース石(アガード石)と並んで生じることもあり、それだと違いはまあわかる(写真7)。当たり前だが孔雀石の産出は多い。産出場所はクリソコラ上に限定されず、褐色にさびた空隙にクリソコラの下地なしに入っていることもある(写真8)。惑わされないように。

写真6.孔雀石。ピータース石やアガード石は色の系統が異なるが、形状はかなり似ている。ルーペではなかなか判別しづらい。特にクリソコラが下地になっている場合だと肉眼鑑定は難しい。

写真7.孔雀石。中央にいる鉱物が孔雀石で、周りに散らばっている針が束になったような集合体はピータース石(アガード石)。並んで産出するとこれらはやっぱり違うものと認識できる。

写真8.孔雀石。形と色はピータース石(アガード石)と非常に紛らわしいが、クリソコラの下地が全く無い産状で放射状になる鉱物は孔雀石と判断して差し支えない。
クリソコラの上には一見して濃緑色の皮膜に見える部分が存在することがある。それを拡大して見ると実体は透明感のある球形の集合で、孔雀石を伴っていることが多い(写真9)。これは「擬孔雀石」であった。擬孔雀石は銅のリン酸塩鉱物なので組成的にピータース石に近いと言えるのだが、共存する例は少なく、一見して被膜に見える擬孔雀石にピータース石が伴われる試料はまだ見つけていない。擬孔雀石とピータース石が共存する場合は、ピータース石はかなり貧弱であり、そのとき擬孔雀石自体は被膜様のモノよりもちょっと大きな球になっており色味も異なっている(写真10)。

写真9.擬孔雀石。透明感のある濃緑色の小さな球。孔雀石(左上と右下の淡緑色部)を伴うことが多い。このタイプの擬孔雀石にはピータース石はこないようだ。下地は厚めのクリソコラ。

写真10.擬孔雀石(濃緑色球状)とピータース石(黄緑色針状結晶)。このタイプの擬孔雀石にはピータース石が伴われることがある。
また、クリソコラ上には「ブロシャン銅鉱」も見つかった(写真11)。透明感のある濃緑色の結晶で、やはり放射状に成長している。板状結晶であることから、ピータース石(アガード石)との判別は比較的容易だろう。硫酸塩鉱物のブロシャン銅鉱が鎮座する晶洞ではピータース石(アガード石)は見つからない。

写真11.ブロシャン銅鉱。透明感のある濃緑色の結晶で、ブロシャン銅鉱としてはわりと普通の姿。ピータース石(アガード石)との判別は難しくない。
クリソコラを伴わない産状の二次鉱物では「緑鉛鉱」が見つかっている。褐色に錆びた晶洞に六角柱状の結晶として産出する(写真12)。この緑鉛鉱は黄色の透明結晶であった。緑鉛鉱を産出する石は表面も内部もただひたすら褐色であり、銅の二次鉱物を伴わない。このタイプの石には白色の塊状の部分もあり、それは燐灰石や石英であった。

写真12.緑鉛鉱。褐色に錆びた空隙に黄色透明結晶として産出する。
目立った二次鉱物に関してはおおむねを述べたので、続いて野外に転がっている石の特徴をまとめておこう。産地の河原に転がっている石は灰色の砂岩・泥岩ばかり。これらを叩いても鉱物は基本的には何も出てこない。ノジュールが出てくることがあるが中心には何も残っていなかった。また小さい石炭を層やレンズで含む泥岩がそれなりに見つかるので、モノによっては標本になるかもしれない。二次鉱物を探すなら褐色に変化した転石が目印になる。つるとしたモノはダメでカラミのことがある。空隙がありザラついた印象の石がよい。そして青い二次鉱物が表面にまで生じている例は案外少ないので、とりあえず割ってみるとことが肝要になる。一目見て水晶を伴いクリソコラがみえるようならキープ。ここではクリソコラを見つけることが大事。こういった石は大小様々な晶洞をもつので、慎重にバラして確認するとよいだろう。そのどこかに新鉱物がいる可能性がある。また全体の産状を見るに、転石となってから二次鉱物が生成したわけではないだろう。すでに二次鉱物が生じている露頭があって、そこから転がってきたという印象を受ける。まだその露頭にはたどり付いていないが、あんがい近くにあるのかもしれない。
この産地からは以前に「ザレシ石」が見つかったという話を聞いた。ザレシ石はピータース石やアガード石と同じくミクス石グループの一員で、ミクス石グループの鉱物たちはどれも似たような見た目になる。そのため、分析を用いない鑑定では産状からその種類を推定するしかない。そして今回の産状ならレアアースという発想は生まれないので、レアアースを含まず、カルシウムと砒素を主成分とするザレシ石という鑑定は合理的である。それでも今回調べた範囲でザレシ石は見つかっていない。個人的にはそのザレシ石は実はピータース石の可能性が高いと思っている。何かの即売会でも置いてあったと聞いているので、すでに持っている方もいることだろう。それはラベルを書き換えても良いだろう。繰り返すが今回の産状でレアアースを主成分とするピータース石(アガード石)は予想外である。そしてこれはいつものことなのだ。新鉱物は予想外のところから見つかる。
IMA No./year: 2017-003
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-45047)
金水銀鉱 / Aurihydrargyrumite
Au6Hg5
Known synthetic compound
愛媛県 内子町 小田川
記載論文:Nishio-Hamane D., Tanaka T., Minakawa T. (2018) Aurihydrargyrumite, a Natural Au6Hg5 Phase from Japan. Minerals, 8, 415.

Fig.1.金水銀鉱の写真。右の粒は全体が本鉱(ただし表面のみで内部は金)。左の粒は左上の銀色が本鉱で、中央下にあるくすんだ銀色の部分はウェイシャン鉱(Weishanite)。
愛媛県から発見された新鉱物、Aurihydrargyrumiteである。記載分類学においては種名はラテン語を基本とするという古い習わしがあり、今回はその例に倣うことにした。この学名は「あうりひゅどらるぎゅるむあいと」と発音し、化学組成が由来となっている。金はラテン語で「Aurum」。これを「Auri」と変形し、水銀を意味する「hydrargyrum」とあわせ、最後に石を意味する「ite」をつけて、「Aurihydrargyrumite」となる。日本産の新種でラテン語由来の学名を持つ鉱物は初めてなのでやってみた。が、日本人には発音しにくい。それでも日本には和名という文化がある。私は和名の「金水銀鉱(きんすいぎんこう)」で呼ぶ。
川や砂浜には比重の高い鉱物や物質が集まる場所がどこかしらあるもので、そういった場所に溜まる砂のことを砂鉱(さこう)と言う。砂鉱にはきれいな結晶や宇宙塵もたくさん入っているのでなかなか楽しませてくれる。そういった砂鉱を採集していると、まったく想定外の場所でも(きわめて少量ではあるが)砂金や砂白金が見つかることがわかってきた。しばらくして、そのわずかにしか採れなかった砂金の内のさらに数粒だけだが、なんだか変だと気づく。砂金ではあるが一部がざらついた銀色になっており、全体が銀色の粒もあった(Fig.1)。初めはこれも砂白金のたぐいかと思ったが、やっぱりざらついた質感は砂白金と判断するには違和感がある(Fig.2)。
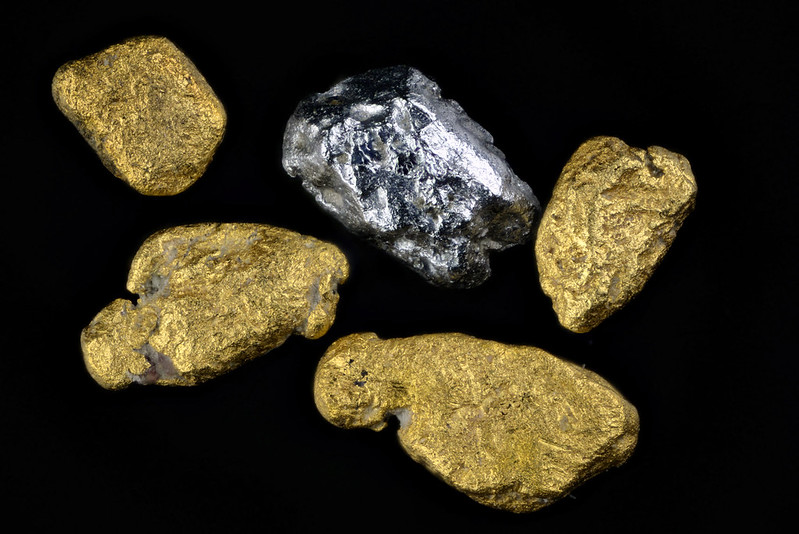
Fig2.砂白金(さはっきん)の写真。この産地では砂白金もみつかる。写真の砂白金の組成はオスミウム、イリジウム、ルテニウムが含まれており、オスミウムが最も多いため鉱物種としては自然オスミウムになる。金水銀鉱と砂白金は質感が異なることが見て取れるだろう。
やっぱりこれは砂白金とは異なるという思いが強くなる。いわゆる銀(silver)が砂金のように産出しないことはよく言われているので、このざらついた銀色粒はもしかしてアマルガムではなかろうかと思いつく。アマルガムとは水銀と他の金属との化合物を指し、今回の場合では金と水銀の化合物になる。そこで粒の表面を電子顕微鏡で分析してみると予想どおり金と水銀が検出された。ほらやっぱりという満足感で心が満たされ、その日の分析を終えた。しかしこれはなんとも情けない話である。山勘が的中したというつまらないことに安堵し、その時点では新種の可能性に全く気づいていなかった。
分析までして気付かなかった原因は私の思いこみだった。アマルガムとは金と水銀が任意の割合で混じり合った柔らかい金属もしくは液体である、ろくに調べもせず私はそう思いこんでいた。しばらくして、そういえばアマルガムを扱ったことはないから調べてみようとようやく思い立つ。こんなときには相図(そうず)を見るようにしている(Fig.3)。これを見るとある条件でどういった相(物質)ができるかが一目でわかる。
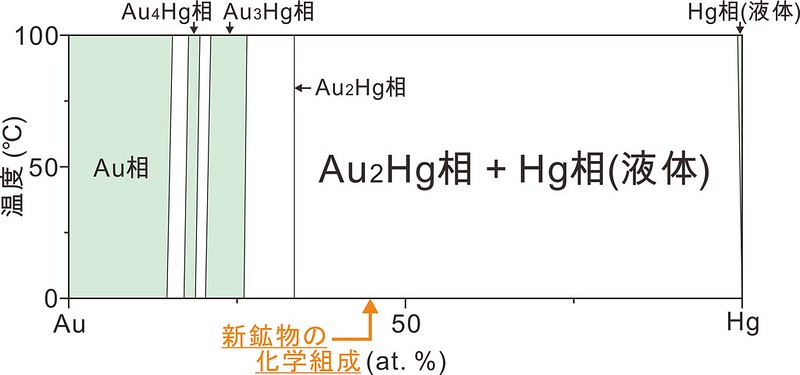
Fig 3. 0-100℃までの金-水銀系相図。データ元[1]はNIMSのMatNavi[2]などから無料で見ることができる。書物にはよく「水銀は金を溶かす」とさっくり書いてあるが、実は液体水銀そのものに金はほとんど溶け込まない。実態としては「水銀と金との微細な化合物が速やかに形成され、さらに液体水銀が多ければ化合物との混ざりモノになる」ということだろう。
[1] Okamoto H., and Massalski T.B., Au-Hg (Gold-Mercury), Binary Alloy Phase Diagrams, II Ed., Ed. T.B. Massalski, Vol. 1, 1990, p 376-379
[2] http://mits.nims.go.jp/
上の図(Fig.3)には今回の新鉱物の化学組成の場所も示した。その場所ではAu2Hgという相(固体)とほとんど金を含まない液体水銀の混合物になることを相図は意味している。だが今回の新鉱物は分離しておらず明らかに一つの個体物質である(Fig.4)。この化学組成を持つ物質は相図には載っていない。これはどういうことだろう。

Fig4。SEM写真。このスケールでも液体水銀は確認できず一つの固体物質に見える。
相図はたしかに一つの結論ではある。ところが相図には出現しない物質でもなんとか合成できることがある。そういったムリヤリ作ったモノは準安定相と呼ばれる。調べたところ金-水銀の系にはそんな物質が存在していた。それはAu6Hg5相である。こいつは金と液体水銀を混ぜただけではできない。こいつを作るには金を溶かした王水と水銀酸化物を溶かした硝酸を混ぜた液体を用意して、それをアンモニア水溶液中でヒドラジンを使って還元するという処理を行う必要がある。1970年にはその合成を記した論文が出版されている[3]。だがこの論文はこれまでにほとんど引用されていない。Au6Hg5相は今ではほとんど忘れ去られた物質と言える。
[3] Lindahl T. (1970) The crystal structure of Au6Hg5. Acta Chemica Scandinavica, 24, 946-952.
そんなAu6Hg5相に今ここで出会うことになるとは思っていなかった。この相の化学組成を100分率で表すと金54.5%と水銀44.5%の割合で、私が調べた銀色もまったく同じだった。そうなると我々が見つけた銀色のブツはAu6Hg5相に相当する天然モノに違いあるまい。そいつをちょんぎって中身を見てみると、銀色の部分は表面の2ミクロン以下の厚さしかないこともわかった。全体としてはほとんどが「金」という鉱物なのだ。それでもその薄皮一枚は新鉱物のはず。どうにかその薄皮からX線回折パターンを取ることに成功し、予想どおり合成されたAu6Hg5相と同じパターンが出てきた。データを整理して国際鉱物学連合の新鉱物・命名・分類委員会へ申請書を提出し、承認を得た。新鉱物「金水銀鉱」の誕生である(Fig 1.)。
誰しもが思いつくひとつの疑念がある。昔にアマルガム回収法で金を回収した際の残り物という可能性。ただ模式地には上流に金鉱山は無く砂金の産出もこれまで知られていなかった。一部の場所で凸凹岩の隙間にたまった少量の砂鉱からほんのわずかに砂金が見つかるのみである。少量の砂鉱しかなく、微々たる量しか砂金が産出しない川でアマルガム回収法は普通はやらない。これは砂金を含む砂鉱がある程度まとまって存在する場所でやる方法である。その場所ではもっと大きな地域としてみても記録はない。その一方で、場所はやや離れているが同じ地質帯の露頭から金と水銀を含む石英脈を発見している。こういった状況でこのたびの新鉱物は天然物であると判断した。
それでも人工ではムリヤリ作るしかない金水銀鉱がなぜ天然では産出するのだろうか。仮に別々にやってきた液体水銀と砂金が反応したとする。だがそれでは金水銀鉱はできないことは相図が教えてくれる。いまのところ成因は自己電解精錬(self-electrorefining)のたぐいと考えている。これは天然の砂金の表面が高濃度の金で覆われている現象の元になる反応のことで[4]、砂金を構成する金属のイオン化と自己触媒による還元が関わっている。イオンからの還元でのみ合成できる金水銀鉱を説明するには、この自己電解精錬が自然なシナリオに思える。
[4] Groen J.C., Craig J.R., Rimstidt J.D. (1990) Gold-rich rim formation on electrum grains in placers. Canadian Mineralogist, 28, 207-228.
ざっくり言うと、いくぶんか水銀を含む砂金があったとして、そういった砂金は水中での自己電解精錬によってやがて表面に金水銀鉱を生じることになる。そこに至る中間段階に相当する砂金は見つかっているし、自己電解精錬がさらに進んだと思われる物質も報告がある[5]。それらはまだ新種として確立されていないので、Au-Hg系の鉱物種は今後に増える可能性は高い。ただし「水銀を含む砂金」が人工物か天然物かという問題はつきまとうので、産地の地質や歴史は重要な判断基準となるだろう[6]。
[5] Atanasov V.A. and Jordanov J.A. (1983) Amalgams of gold from the Palakharya river alluvial sands, district of Sofia. Doklady Bolgarskoi Akademii Nauk, 36, 465-468.
[6] Barkov A.Y., Nixon G.T., Levson V.M., Martin R.F. (2009) A cryptically zoned amalgam (Au1.5-1.9Ag1.1-1.4)Σ2.8-3.0Hg1.0-1.2 from a placer deposit in the Tulameen-Similkameen river system, British Columbia, Canada: Natural or Man-made?. The Canadian Mineralogist, 47, 433-440.
ネットで「砂金 アマルガム」と検索してみると銀色の粒が表示される。砂金掘り師たちの間では銀色の砂金はすでに知られていたようだ。ただすべてがアマルガムの一言でくくられている。人工物か天然物かの問題はひとまず置いて、こういった銀色砂金は中身の検証も大切だと思う。まずは一粒だけで良いからその銀色の砂金にカッターナイフを押し当ててちょん切ってみよう。普通は容易に切断できるはずだが、もし切断できなければそれは砂白金や他のモノだ。さて、切断出来たとして中身が金色に輝いていたら、その銀色は表面だけの事象であり金水銀鉱の可能性がある。また砂金の一部が銀色という産状も多いようだ。それも金水銀鉱だろう。
見てる限りの印象だが、銀色の砂金が見つかったとしてがっかりする砂金掘り師は多いと感じる。捨てたとか焼いて金に戻した猛者もいるようだ。まあその気持ちはわからんでもない。一方で金水銀鉱それ自体は紛れもなく天然が生み出した芸術だと思っている(たとえ人工アマルガムが元になっていたとしても)。なので捨てるくらいならどうか譲ってもらえないだろうか。ほかの産地を調べてみたいという事情もあるが、私は自然の芸術作品である金水銀鉱が好きなのだ。
IMA No./year: 2015-100
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-44527)
神南石 / Kannanite
Ca4[(Al,Mn3+,Fe3+)5Mg](VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6
Ca analogue of ardennite-(V)
愛媛県 神南山
記載論文:Nishio-Hamane D., Nagashima M., Ogawa N., Minakawa T. (2018) Kannanite, a new mineral from Kannan Mountain, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 113, 245-250.

Fig. 1. 神南石のタイプ標本。赤鉄鉱+ブラウン鉱母岩中に脈状に走る黄褐色~オレンジ色が本鉱。脈中の赤は紅簾石。
愛媛県神南山から見いだされた新鉱物「神南石 / Kannanite」である。そして今、これを書き始めたところで採集した日のことを思い起こしている。本来ならその日は愛媛にはいるはずはなかったが、とある事情で愛媛にとどまり新鉱物が誕生することとなった。以前の新鉱物・伊予石&三崎石も実はこの事情に絡んでいる。
神南山に上る当日、本来なら私は広島にいるはずだった。ところがその計画が前日にポシャってしまい次の日も愛媛に留まるハメになった。それで夜の居酒屋で急遽設定したのが神南山の調査であった。そして明くる日。午前中で神南山の調査を終え、腹が減った我々は思いつきで佐田岬半島の「しらす食堂」へ向かった。その際に近辺にマンガン鉱石が転がっているというので、腹ごなしついでにふと立ち寄った。私にとってそこは初めての産地だったが、マンガン鉱石は容易に採集でき、幸運にもその鉱石から新鉱物・伊予石&三崎石が生まれることになった。そしてその日の午前に採集した神南山からの鉱物が今ここで新種・神南石となった。できすぎた話である。
そういえば当初の計画が直前でポシャった事情は何だったかな。たしか著者の一人が「ネコたちが腹を空かせて泣くからやっぱり遠征できない」と、よりにもよって遠征に向かった先の中間地点でいきなり言い出したせいだ。確か弓削島あたりだったように覚えている。あと少し進んだら広島県に入りそこで一泊のはずだったが、「帰ろう」と彼はのたまう。抵抗したが彼のネコ愛には勝てなかった。割を食った私はその晩の宿が取れず散々だったが、それが一連の成果につながるのだから不思議なものである。あのとき私を愛媛へ留めてくれた腹ぺこネコ様たちには高級缶詰でも献上せねばなるまい。
さて、気を取り直して。神南山(かんなんざん)は大津市と内子町五十崎にまたがり肱川とその支流に囲まれている独立峰である。険しい山ではないが森は深い。東西に頂がありそれぞれを女神南(おなごかんなん:710m)と男神南(おとこかんなん:654m)と呼び、神が宿る山としてその地域の霊山という扱いであろうか。そしてその神南山の東側中腹には大久喜鉱山という愛媛県で屈指の銅鉱山がかつて在った。
大久喜鉱山は愛媛県では別子鉱山に次ぐ規模のキースラーガ型銅鉱床で、愛媛県西部では最大の銅鉱山になる。その沿革や経緯は詳しくないが約200年前に開発されたようだ。金の含有量がかなり高く平均で4~6g/トンもあるらしい。それはともかくもここの鉱石は他のキースラーガ型銅鉱山のモノとはやや異なって見える。あいかわらず小さな標本しか持っていないが、全体的に細粒なために破面が柔らかい印象で(Fig.2)、それが別子鉱山のキースラーガ鉱石とは一味ちがう。大久喜鉱山には広大なズリ山がまだ残されているので鉱石の採集は容易だし、今はどうか知らないが以前は緑礬(Fig.3)が生じている場所もあった。

Fig. 2. 大久喜鉱山産のキースラーガ鉱石。黄鉄鉱が主体で黄銅鉱が脈状に入っている。全体的に粒度が小さいことやたまに閃亜鉛鉱も来ることが特徴で、他産地のキースラーガ鉱石とは印象が異なる。それ故にモノをみたらこれは大久喜とすぐわかる。ただ写真ではそれがうまく写せなかった。

Fig. 3. 緑礬の結晶。この緑礬のなかにはボトリオーゲン石 / Botryogen [MgFe3+(SO4)2(OH)•7H2O]が含まれることがある。写真中の黄色~オレンジ色の部分が該当するかもしれないがそれは調べていない。
このように大久喜鉱山のことをすこし書いたが、今回の新鉱物には大久喜鉱山は関係がない。というより大久喜鉱山との関連があまりよくわからない。大久喜鉱山の本体は神南山の東側中腹に在るが、その周りにも支山がたくさんあるとされる。以前に何度も現地を訪れたことがあるが、たしかに大小様々な堀跡が方々に認められた。ただあまりに数が多く、現地の人に尋ねてもそれぞれの鉱山名や大久喜鉱山との関連は定かでない。それから銅鉱床だけではなくいわゆる鉄マン鉱床も点在している。鉄マン鉱石にはマンガンは含まれてはいるものの品位は全体的に低く、マンガン資源としてはほとんど役立たずに思える。おそらくは鉄を目的に掘ったのだろう。これらも名前や大久喜鉱山との関連は定かでない。
神南山の地質に目を向けるとこれはなかなか複雑で、地質図とその解説があるのでそれを参考にしてほしい(坂野ほか、2010、大洲地域の地質)。神南山の地質は御荷鉾緑色岩類に相当し、ざっくり言っていいかわからないが、全体的に弱変成を受けた苦鉄質岩とチャートが混じっている地層になっている。そして銅鉱床は苦鉄質岩に、鉄マン鉱床はチャートに胚胎されている。ただほとんどの堀跡は明確なズリや貯鉱が残っているわけではない。山中に(なぜか)点々と散らばっている鉱石をたどっていくと露頭に行き着くといった具合である。そこは(試)掘跡なのかもしれないが、それが定かでないほど苔むして自然に戻っていることがほとんどである。
今回の目的は鉄マン鉱床(鉱石)だった。我々は以前に三重県伊勢市の鉄マン鉱床から4種の新鉱物を見いだしており、鉄マン鉱床というのは新鉱物に関して言うと魅力的な場である。豊石も鉄マン鉱床から出ている。そして神南山は労せずとも何かしらの鉄マン鉱床にはぶち当たるという場である。はたして午前中の調査であっさりと多量の鉄マン鉱石が手に入った。なんとも冴えない重たいだけの石ころである(Fig. 4)。

Fig. 4. 神南山の鉄マン鉱石でこれは破断面。全体は赤鉄鉱やブラウン鉱なのだが破断面ではどちらかさっぱりわからない。愛石家といえどもこれを目的に採集する人は(ほぼ)いない。逆にこういった鉄マン鉱石はほとんどまともに調べられていない。
こういった石は割ったところで破面から判断できることは少ない。石英くらいは割らなくてもわかるが、それは別にただの石英である。石英に伴われる紅簾石もまあわかるが、それもやっぱりたかが紅簾石である。たまに自然銅がいるのでそれ見つけるとちょっと安心するが、コレクションにするほどではない。このような一見残念にな石はぶった切るのが一番で、切断面を見るといろいろわかってくる。石をぶった切って初めてわかったが、石英脈に伴われるのはなにも紅簾石ばかりではない。黄褐色葉片状の鉱物が石英脈に散らばっている(Fig. 5)。何だろうと思って分析してみると、これはバナジウムアルデンヌ石であった。ちょっとうれしい。よく見ると細脈にもこれが来ている(Fig. 6)。それにしてもこの細脈中のモノはものすごく小さい結晶で、ルーペ程度では切断面でも存在を認識するのが難しい(Fig. 7)。分析してみるとバナジウムアルデンヌ石に近いがそれよりもかなりカルシウム(Ca)が多い。あれ?と思って組成式をよく考えるとこれはバナジウムアルデンヌ石のマンガン(Mn)をカルシウム(Ca)に置き換えた鉱物に相当する。うわ、これ新鉱物だ。

Fig. 5. 鉄マン鉱石の切断面。黄褐色葉片状結晶はバナジウムアルデンヌ石(Ardennite-(V))。肉眼的に認識できるような石英脈中には黄褐色葉片状結晶があったとしてもすべてバナジウムアルデンヌ石。

Fig. 6. Fig1の再掲載。この黄褐色はすべて神南石。
ということで、これが新鉱物であるというのは実は比較的早い段階からわかっていた。だが困ったことに細脈にしか神南石は出ない。量があまりないことと純粋な結晶を分離するのが難しいために、データを集めるのにかなり時間がかかってしまった。名前に関しては地名・人名からいくつか候補を考え悩んでいたのだが、産地の神南山からとって「神南石」とした。ネコの飼い主からの助言でそう決めた。ネコ様が導いた新鉱物なのだからそれが良い。
鑑定ポイントはまずは鉄マン鉱石であること。赤鉄鉱やブラウン鉱が来ている鉄マン鉱石を切る石英脈中に神南石はいる。その中の黄褐色~オレンジ色が特徴的なのでそれが目印になるだろう。ただし肉眼的な脈の中の結晶はバナジウムアルデンヌ石で安定しており、どういう訳か神南石は見えるような石英脈には来ない。神南石は太さ100ミクロン以下の細い石英脈にだけ来ており、その結晶はものすごく小さい。このサイズになると観察にはそれなりの実体顕微鏡が必要になる。それと現地では細脈の中身どころか、細脈が来ているかどうかも判別が困難なので、やはり切断&研磨するしか手はない。研磨は#400くらいで十分で、透明なマニキュアを塗ると観察しやすくなる。ただいくら愛石家といえども岩石カッターをもっている人はごく少数で、それなりの実体顕微鏡を持っている人も多くはないだろう。神南石はどうやっても愛石家泣かせの新鉱物である。
話は変わるが、この冬は東京都白丸鉱山が数年ぶりに顔を出した。そこでは国産新鉱物の多摩石や東京石を初め珍しい鉱物が出る。私も白丸鉱山を訪問し、最近はそこの石を調べることに夢中になっていた。そうした中で神南石を申請していたことを実はすっかり忘れており、承認通知を受けて思い出した次第。そうして他にも思い出したことがある。実は神南山の鉄マン鉱床にも白丸鉱山と似たような鉱物が出る。まずは次の写真を見てほしい。

鉄マン鉱石の切断面の写真。中央から右上に向かうルーズな緑色と、中央から左下と右下部に点在する赤色が見て取れる。自然銅だけは初見でもわかるだろう。
この緑と赤を見ただけで鉱物名がわかる人はまずいないだろう。もちろん私にもわかるはずがない。調べたところ緑はコニカルコ石(Conichalcite)、赤はガマガラ石(Gamagarite)とブラッケブッシュ石(Brackebuschite)であることが判明した。まずはコニカルコ石がこんな産状でも出るなんて知らなかったので、これは良い経験になった。それからガマガラ石とブラッケブッシュ石は白丸鉱山からの新鉱物・東京石(Tokyoite)の近縁種である。それぞれが東京石の三価鉄(Fe3+)置換体と鉛(Pb)置換体に相当する。東京石はまだ見つけていないが、これらが出てくるならじっくり探せばそのうち見つかるような気がする。こういった例もあるように、鉄マン鉱石は外見が冴えなくともその中身は案外おもしろい。
IMA No./year: 2014-054
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-44106)
豊石 / Bunnoite
Mn2+6AlSi6O18(OH)3
New structure type
模式地:高知県 いの町 加茂山
記載論文:Nishio-Hamane D., Momma K., Miyawaki R., Minakawa T. (2016) Bunnoite, a new hydrous manganese aluminosilicate from Kamo Mountain, Kochi prefecture, Japan. Mineralogy and Petrology, 110, 917-926.

Fig.1.豊石を含む鉄マン鉱石。右側のやや緑がかった部分と、左側の上下に走る石英脈に伴われる緑がかった部分が本鉱。標本の左右10センチ。

Fig.2.Fig.1の右側を拡大。暗緑色の葉片状結晶の集合。

Fig.3.Fig.1の左側を拡大。上下に走る石英脈に豊石(暗緑色)は伴われる。

Fig.4.写真全体がほぼ豊石からなっている。基本は深い暗緑色で、結晶がすこし浮いたところではやや黄色味を帯びて見える。

Fig.5.これも全体がほぼ豊石でやや粗粒結晶。結晶が粗粒になるとむしろ褐色を帯びる。松脂光沢が艶めかしい。
高知県からの新鉱物、「豊石/Bunnoite」になる。玉露の茶葉をぎゅっと固めたような標本。渋いと言ってほしい。豊石はシンプルな構成元素でありながらも新規の化学組成&結晶構造だった。鉱物は化学組成と結晶構造で定義されていて、そのどちらか、もしくは両方が新規なら新種(新鉱物)となる。これまでに自分が筆頭で記載してきた新鉱物は、化学組成が新規で結晶構造は既に分かっている(推定できる)というものばかりだった。私が関わった新鉱物は豊石を含めて合計16種、そのうち筆頭を務めたものでは10種目となるのだが、ここにきてようやく、私にとっては初めての新鉱物となったとも言える。
名前のことから書いていこう。本鉱は和名が「豊石」、学名が「bunnoite」である。「豊」と書いて「ぶんの」と発音する。なので「豊石」は「ぶんのせき」と読む。九州の豊前市とか豊後高田市のように「豊」を「ぶ(ん)」と発音するのに似ている。ただ本鉱は高知県産。それに地名ではなく人名に由来しており、豊遙秋(ぶんのみちあき)(1942-)の名前に因む。「豊(ぶんの)」名字はすごく珍しいと思うのでそのルーツを本人に聞いてみたところ、江戸時代より前は「豊原(とよはら)」が正式名称で、それを「豊(ぶん)」と略して名乗っていたと聞いている。そして、「平将門(たいらのまさかど)」を読むときの「たいらの」の「の」と同じような感じで、「ぶんの」と発音していたせいもあって、明治維新でいざ名字をつくろうとなったときに「豊(ぶんの)」になったようだ。それでこの家は代々「笙(しょう)」を家業としてきたとのことで、ご自宅におじゃましたときにぶ厚い家系図を見せていただいたことがある。webにはその家系図をまとめているサイトがあったりもする(http://houteki.web.fc2.com/toyohara.html)。家系図がネット検索で出てくる人物はそうはいないだろう。本人もおっしゃていたが名前の「秋」も通字である。伝統がありすぎる・・
豊先生は家業とはまったく異なる鉱物の道に入った。産総研(旧:地質調査所)地質標本館の館長を務め(2003年退官)、これまでに6種の新鉱物の発見に貢献してきている。とは言え、自分で論文をゴリゴリ書くタイプではなく、仕事に定評のあるタイプの研究者である。その定評のある仕事というのはキュラトリアルワークと言って、一部だけを抜き出して簡単に言うと標本の収集・整理である。ほら、愛石家の皆さんにおなじみの採集&ラベル作りですよ。研究機関においては標本入手の手腕というのは大事なことではあるが、もっと大切なのはラベルのほう。例えば標本を手に入れたとしてラベル(情報)を残さなかったらどうなるか?個人蔵なら耳が痛い話ですむし、まあそれは気が向いたときにやれば良いだろう。ところが研究機関でそんな怠慢をやってしまうと研究標本としての価値は消失しゴミと化す。そうしないためには情報を即座にラベルに記し、データベース化してわかりやすいように分類・登録することが大切である。さらには必要なときに取り出せるように管理することも大事で、研究機関はそのように標本を取り扱う義務がある。なにを当たり前のことをと思うかもしれないが、こういう体制を整えるにはセンスが必要で、体制が整ってないところは実は結構ある。豊先生はそうした体制を確立してその経験を元に様々なところで指導をしてきた。ただ、論文のように広く公表される内容ではない。それでも豊先生が長年キュレーターとして活躍してきたことは業界人には周知の事実で、その業績から新鉱物の名前となるにふさわしいと思ってお願いしたのです。
そんなこんなで新鉱物のデータが形になって、豊さんの名前をいただきましょうという段になった。存命の方の名前を新鉱物に採用するには本人の承認が必要なのだ。さあ誰に伝えてもらうのが良いかなと考えて、豊さん自身が畏友と称している皆川先生からが良いだろうと皆川先生にその大役をお願いしたのだが、今思えばそれが失敗でした。あろうことか2014年4月1日のエイプリルフールに伝えやがった。研究者ならまず間違いなく注目するあの日。そう、理研が例の記者会見を開くその日でございます。よりにもよってそんな日に「新鉱物は、ありま~す」ってメッセージを受け取ったほうの動揺はいかばかりであっただろうか。しばらくして皆川さんは「OKだってよ」とのたまったが、豊さんから後日に「本気でエイプリルフールの冗談かと思った」と聞かされてゴメンナサイした次第であります・・・。もちろん悪意はありません。でもゴメンナサイしながらも、「やっぱり冗談でした」が承認されなかったときの言い訳に使えるなとひそかに思ってた。幸いなことにその言い訳を使う機会は訪れず、無事に承認通知が来ましたよ。通知確認!よかった。
高知県いの町、JR線より北側の山地の地質は変成度の低い緑色岩でそれが東西に数キロほど分布している。この緑色岩中に鉄マン鉱床が伴われ、地質調査所四国出張所の古い資料からはこのあたりに「加田」、「南田」、「伊野」という名前の鉱山(もしくは鉱床)があったことが伺える。ただそれ以上の情報はなく、実際に現地を歩いて調査を行った。現地にはぽっかり空いた坑道が方々に残っており、試掘しただけなのかもしれないが小規模な露天掘り跡もちらほら散見される。ただし全体的にズリは非常に薄くて一見それとはわからない。谷筋まで出ている鉱石も少ない。かつて加藤らはこの地域からハウィー石や種山石を報告しており(Kato et al., 1984, Proc. Japan Acad., 60, 65-68)、豊石が見つかった場所も領域的にはだいたい同じ。でも具体的な場所はハウィー石や種山石を産した鉱床とは異なるのだろう。それというのも調べた範囲で豊石が来ている鉱石にハウィー石や種山石が来ることはなかった。逆はどうだろう。ハウィー石・種山石がメインの鉱石はこのときの調査ではむしろ見つからなかったので確定的なことは言えないが、化学組成がそれなりに違うので共生は無いと予想している。たぶん生成のステージが違っており、一つの鉱石中で共存が見つかるとしても脈でぶった切っているケースだろう。
さて、鉱石はいわゆる鉄マンと称されるもので、基本的に真っ黒。主には細粒の赤鉄鉱とスティルプノメレンからなり、肉眼では判別不能だがごく少量のバラ輝石が含まれている。鉱石の所々には石英の脈やレンズが見え、その中にはまれに紅簾石が含まれている。それでもこの鉱石中のマンガン成分は相当少ないように思える。通常マンガンが多い鉱石の表面は真っ黒に汚染されていることが多いが、ここのはむしろ鉄さびの褐色に汚れていることが多い。そんな鉱石を割ると中は真っ黒で、ときおり暗緑色の葉片状結晶がへばりついている。それが豊石である。ところが暗い場所で観察した場合や水で濡れていたりするとさっぱりわからないので、現地での判別には相当の注意力を要する。また、豊石は細かい結晶が密な集合を作る場合だと玉露の茶葉のような深緑になるが、粗粒結晶になると褐色を帯びてくる。いずれにしてもリッチな標本は背景の黒と混じり、ぱっと見てそれと判別するのがくそ難しい。逆に貧弱なものや結晶がすこし浮いたところは黄緑色を帯びるので、それがひとまずの目安になる。石英脈に伴われることがほとんどだが、たまに鉱石中に豊石だけのレンズになっているようだ。そのレンズがうまく割れると1-3センチの範囲が全て豊石ということもあり、これくらいになるとルーペはいらない。豊石はハウィー石や種山石と共存することはないと思っているが、いずれの鉱物も葉片状結晶が集合するため、全部並べてさあどれが豊石かと言われると判別は難しいかもしれない。ただこの地域のハウィー石なり種山石は鉄を多く含み(Kato et al., 1984)、それ故に見た目はかなり黒いと推測されるので、葉片状の鉱物を見つけて判断に迷ったときはきっと緑色が鑑定の助けになると思う。
実は豊石はすでに報告がある。鉱物学会2000年年会で報告されたアカトレ石/akatoreiteが結果的には豊石だった。そうとう前に発表されているのですでに標本を持っている人もいるかもしれない。そういう方は遠慮無くラベルを書き換えてください。このアカトレ石に疑いを持ち、まじめに調べ直すきっかけは写真だったように思う。実は数年前から標本の写真撮影(主にはマクロ撮影)を始めており、とりあえずは自分の標本から撮影をしているのだが、今に至る過程で大苦戦するものがいくつかある。その中には昔に皆川さんからもらったアカトレ石も含まれていた。今回掲載した写真は最近に撮影したものなのでだいぶ改善してはいるが、本物よりはやっぱりまだちょっとコントラストが低いように思う。それでも豊石(当時はアカトレ石と思っていた)の写真を撮り始めた当初よりはだいぶマシにはなっている。写真写りが非常にむずかしいのでほかの産地のはどうなってんのかな?と比較しようとWebで調べたところ、なんだか見た目や色が全く異なる。別ものを渡されたか?と手持ちの試料を組成分析してみると講演要旨と同じ値になるのでやっぱりアカトレ石か。でも良く検討するとこの元素比はアカトレ石とはすこしズレてるぞ。それではと粉末X線回折実験もやってみたら、対称性が低いせいでやたらめったらピークが出てくる。それらはアカトレ石に当てはまらなくもないが、インデックスしていくとなんだかムリがでて誤差も大きくなる。むむむ?ってことで門馬君に協力してもらってよく検討したら新鉱物でした。それも新規の化学組成&結晶構造というおまけ付きだったのです。それで、結局、実は、アカトレ石は皆無でした。まあこういう新鉱物(再)発見物語もあるってことです。
承認通知をもらった日、豊先生は奥様同伴で皆川先生と鉱物談義に花を咲かせていたらしい。その日は図らずも中秋の名月で愛媛は晴れだったようだ。きっと一献傾けていたことでしょう。おめでとう、豊先生。
IMA No./year: 2013-130(Iyoite), 2013-131(Misakiite)
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43864)
伊予石 / Iyoite
MnCuCl(OH)3
Mn-Cu ordered analogue of botallackite
三崎石 / Misakiite
Cu3Mn(OH)6Cl2
Mn-rich analogue of kapellasite
模式地:愛媛県 伊方町 大久
記載論文:Nishio-Hamane D., Momma K., Ohnishi M., Shimobayashi N., Miyawaki R., Tomita N., Okuma R., Kampf A.R., Minakawa T. (2017) Iyoite, MnCuCl(OH)3, and misakiite, Cu3Mn(OH)6Cl2: new members of the atacamite family from Sadamisaki Peninsula, Ehime Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 81, 485-498.

Fig. 3. 伊予石と三崎石の共存その1。伊予石はしばしば樹状集合(デンドライト)となる。先端部には三崎石を伴うことが多い。

Fig. 4. 伊予石と三崎石の共存その2。上の写真の先端部はこんな感じで,針状結晶の伊予石の先端に六角形の三崎石が生じている。

Fig. 5. 伊予石と三崎石の共存その3。同じく伊予石のデンドライトで,こちらは荒々しい。先端部には三崎石が伴われることがある
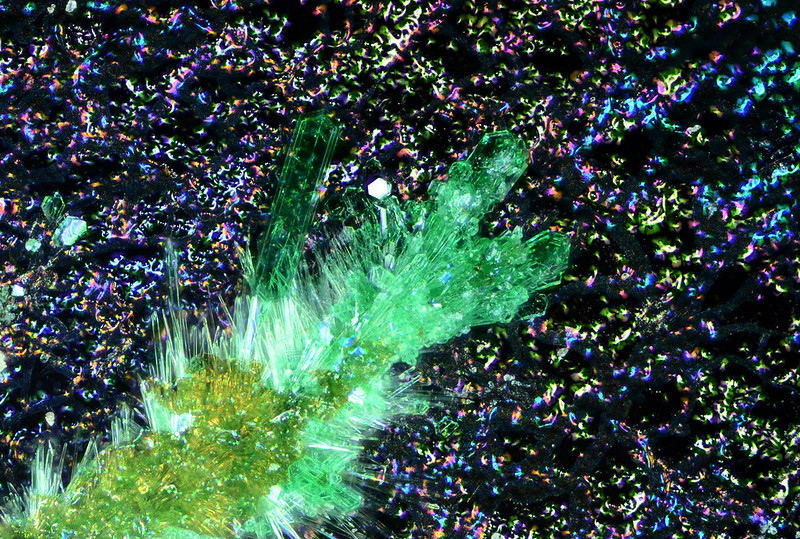
Fig. 6. 伊予石と三崎石の共存その4。伊予石は淡緑の針~板状結晶がデンドライトになっていて,デンドライトの終わりに三崎石の集合体ができている(中央)。三崎石は六角粒状が基本だが,伸びて板状になることがある(中央やや左)。

Fig. 7. 鉱石の破断面。内部には自然銅が多く含まれる。

Fig. 8. アタカマ石。緑が深い。今のところ明瞭な結晶は見いだせてない。共生している黄色がかった白い球状はクトナホラ石。

Fig. 9. パラアタカマ石。やっぱり緑が深い。こちらはたいてい結晶しており伊予石・三崎石とは形が異なるので簡単に区別はできる。米粒みたいなのはクトナホラ石
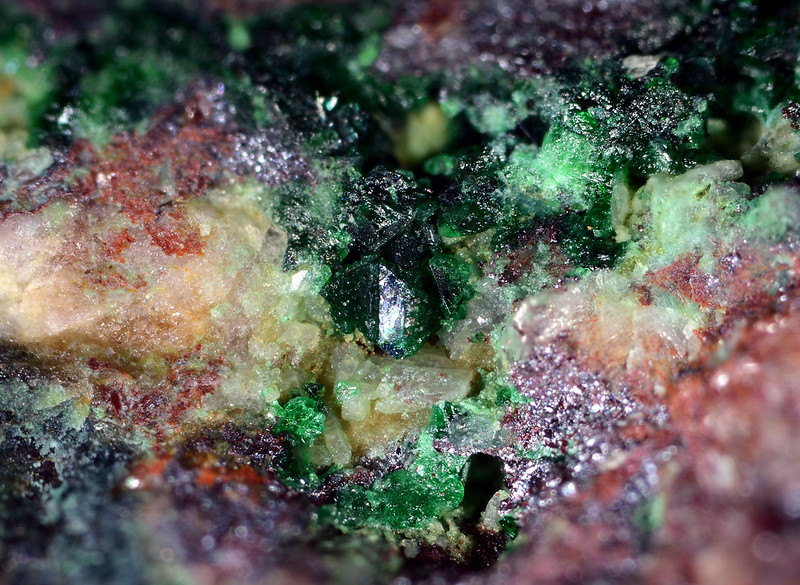
Fig. 10. 単斜アタカマ石,たぶん本邦初産。こいつもやっぱり緑が深い。スピネルみたいな結晶面が見える。赤いギラギラは赤銅鉱,白っぽいのはやはりクトナホラ石。

Fig. 11.これは三崎石。結晶が不定型だとアオサノリに見える。
愛媛県佐田岬半島からの新鉱物「伊予石(Iyoite)と「三崎石( Misakiite)」である。黒色を背景にして翠緑色の新鉱物たちがぱぁっと展開する様はなんとも美しい。二つの新鉱物の名前は佐田岬半島が面している二つの海域、伊予灘と三崎灘にちなんで命名した。この新鉱物たちの生成には海が深く関わっているので、海の名前をいただいた理由の一つである。そして偶然にも「いよ」と「みさき」って女性の人名にも通じる響きで、そうなるとほら、愛媛といったらマドンナですよ。さらには二つの新鉱物はほとんど姉妹みたいなものだから、もういっそのこと鉱物界のマドンナ姉妹ってことでどうかな。
愛媛県佐田岬半島は四国の最西端に位置する日本一細長い半島で、リアス式の海岸には緑色片岩と呼ばれるささくれ立った緑の岩肌が林立しており、高台からの景色は実に風光明媚。2013年春、我々は調査の足をその佐田岬半島に伸ばしたところだった。目的は海岸線にある銅鉱床の調査で、転がっている鉱石をかち割ると内部には自然銅がたくさん含まれている。一般的に銅鉱石が海水の影響で風化する際に生じる二次鉱物として、いわゆる「アタカマ石」というのが知られている。アタカマ石は透明感のある濃緑色の結晶で、銅鉱石と海水の成分をたせばできあがるし、たいして珍しくはない。もちろん今回の調査地でもアタカマ石が産出することはずっと以前から知られていた。それでもこの場所を訪れたのは「しらす食堂」が近くにあったから・・、いやいや、その鉱床が普通とは異なり多量のマンガンを含んでいたからだ(普通の銅鉱床にはマンガンは少なく鉄が多い)。どっちが本音かは読者の想像にゆだねよう。まあしかしこういった鉱石が海水の影響で風化されると普通の銅鉱床とはなにか違いがあるだろうか。
野外に放置された鉄の多い銅鉱石は表面が赤茶けた色に変色するのに対し、マンガンを多く含む鉱石は真っ黒に変色するのが特徴である。現地にも真っ黒な石が多数あった。目的はこの石の表面ではなく、ちょっと内側にある。風化作用にはざっくりと機械的風化と化学的風化があり、前者は破砕的な作用で後者には溶解や分解といった化学反応が伴われる。例えば海岸や河川の石がまるくなっているのが機械的風化の一つで、しばしば化学的風化の影響をはぎ取ってしまう。一方で石のちょっと内側は機械的な作用が及びにくく、化学的風化の影響が強く残ることが多い。そんなわけでとりあえず手近な真っ黒な石をハンマーで割ってみたら、さっそく苔みたいな緑の物体がへばりついていた。「ああ、アタカマ石だな」と。さて他にはどんなのがいるかなといくつか割ってみるも、緑のモノ以外はせいぜい赤銅鉱が見える程度で、これも銅鉱石の風化で生じる鉱物としては一般的。なんだ普通の銅鉱床と変わらないなあという感想を持って野外調査は終了。でもその感想は結果的にはハズレだった。
試料を実体顕微鏡で観察したところ、思わず息をのんだ。苔のような物体はまったくの予想外に美しかったのだ。それでも最初にこの結晶を見てすぐには新鉱物を連想できなかった。ところが写真を撮り始めるとなんだか違和感が・・。結晶の形もまあそうだが、色がすこし変に思える。自分の知っているアタカマ石にしては色が淡い。鉱物の形はケーズバイケースだけども、色は元素の種類が反映されるので色に違和感を覚えたらそれは要注意のシグナルである。ここでアタカマ石の化学組成を見てみよう。その化学組成はCu2Cl(OH)3で、特徴的な濃緑色は主成分の銅(Cu)に由来している。この銅が他の元素に置き換えられているなら色は変化しても良いはずである。そして今回の結晶は二酸化マンガンの上に鎮座している。となるとそうですよ、よくよく見れば状況証拠はそろっているじゃないですかい。そう思って分析してみたらやっぱりマンガンが検出されたのである、それもことごとくCu:Mn=1:1か3:1とかいう割合。さらに詳細を調べて二つとも新鉱物であることが確定した。
伊予石・三崎石はどちらもアタカマ石類縁鉱物ではある。しかしそれにしてもアタカマ石類縁鉱物は構造の種類が多い。まず、Cu2Cl(OH)3組成にはアタカマ石型、ボタラック石型、単斜アタカマ石型、アナタカマ石型がある。Cuが完全にMnに置き換えられた鉱物としてはKempiteという鉱物がすでにあって、これはおそらくアタカマ石型構造。ただこいつは今回は見つからなかったな。まあそれはおいといて、伊予石はMnがややCuを上回るものの、だいたいCu:Mn=1:1の組成をしていた。この割合には意味があって、構造中でCuとMnが異なる席に着いている(対称化)。結果的に伊予石はMnCuCl(OH)3組成のボタラック石型構造の新鉱物だった。さて、Cu3M(OH)6Cl2(Mに2価陽イオン)という化学組成だとパラアタカマ石型、ハーバードスミス石型、カペラス石型がある。三崎石はM = Mn組成のカペラス石型の新鉱物で、こちらもCuとMnは異なる席にいる。二つの新鉱物の構造は密接に関連していて、同時に産出するというのは納得いくのだが、説明は専門的になりすぎるのでその役目は論文に託そう。
さあ肉眼鑑定のポイントに移ろう。伊予石・三崎石以外に確認できたアタカマ石類縁鉱物は、アタカマ石、パラアタカマ石、単斜アタカマ石(Fig9-11)。これらは伊予石・三崎石とはあまり共生しない。それは含まれるマンガン量がまったく違うからだと思う。実際にパラ・単斜・アタカマ石に含まれるマンガン量は微々たるものであった。また産状的に伊予石・三崎石は二酸化マンガンの上に直接いることが圧倒的に多いが、他の3種はクトナホラ石を背景に置く場合が多い。鑑定ポイントはそういう産状と、色(透明感も)と形。伊予石・三崎石はパラ・単斜・アタカマ石よりも淡く透きとおった緑が特徴です。二酸化マンガンを背景にフェンネルのような造形が見えたらそれが伊予石だ。伊予石は放射状になったりもする。三崎石は六角形の板が見えたら確実だが、結晶形が不定の場合はアオサノリのようになる(Fig.11)。でもそれはパラ・単斜・アタカマ石とは異なるので区別できると思う。他にはそうそう、どうやら単斜アタカマ石は本邦初産になるのかな。濃緑色のスピネルみたいな形なのでこっちはすぐに判別できると思う。でもここに書いたのはあくまで典型例。微妙なやつも多いから総合的には肉眼鑑定は難しい。
ついでに鉱石本体のほうも書いておこう。鉱石の表面は真っ黒であるが、内部は新鮮で、かなりの部分を紫がかった褐色のハウスマン鉱が占め、若干赤みを帯びてくるようなところにはヤコブス鉱も含まれる。そういったハウスマン鉱(+ヤコブス鉱)集合体を切るようにテフロ石(灰緑色)+バラ輝石(淡紅色)の脈が入っており、所々でレンズ状に拡張している。最終的には全体を方解石や菱マンガン鉱の細脈が切っている。自然銅はその細脈にきているようで、うまく割れると一面に独特な銅色がぶわっと展開する。その他に特徴的なのはパイロファン石だろうか、やはり細脈にともなわれることが多い。サイズがかなり小さいので肉眼だとチカチカするだけだが(ルーペでも厳しい)、実体顕微鏡下では赤褐色の鱗片状結晶がみえる。
銅+海水->(パラ)アタカマ石というのはほとんど常識になっていて、鉱物に慣れた人ほどあっさりそう断定してしまう。もちろん私もそう、偉そうに言える立場ではない。それでも多くの人がこの産地の鉱物を(パラ)アタカマ石だと常識的に判断していたことは、なんというかラッキーだった(申し訳ない気もするが)。というのも、私はこの産地を初めて訪れたのだが、ここは昔に採集会が開かれたこともあるらしく、すでに標本を持っている人も多い。実際に昨年のミネラルマーケットでも模式地標本がアタカマ石のラベルで並んでいたのを見かけた。そしてその標本を手に取っておもわず苦笑い。だって、すでに標本が流通している状況で誰かがふとアタカマ石類縁鉱物の多様性に気づけば、産状からMnを含んだアタカマ石類縁鉱物を連想するかもしれない。その可能性を疑って標本を観察するとそれはもうアタカマ石には見えない。我々より前に他の誰かが新鉱物を見いだしてしまうことは十分にあり得た話である。それにその標本を見たときはまだ新鉱物の申請をしてなかったのだ。それでも私はそのワンコイン標本を売り場に戻して、ちょっと動揺しながらも売り子さんには「これは良いものですよ」と言った。「じゃあ買えよ」って顔されたけど。
いざ採集っと席を立つ前にまずは手持ちの標本をよっく見てみようよ、それすでに新鉱物じゃない?
追記>
伊予石・三崎石とは無関係だが、鉱石の破断面にチカチカする鉱物について追記。どうやら2種類あることが判明し、一つは前述のパイロファン。もう一つはクレドネル鉱(crednerite, CuMnO2)でした。以下、写真。
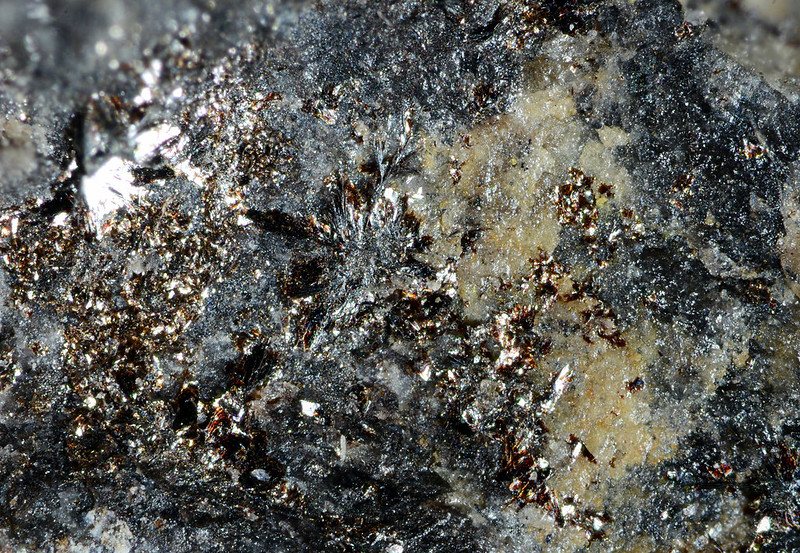
これはパイロファン。赤い。
IMA No./year: 2013-126(Ferriakasakaite-(La)), 2013-127(Ferriandorosite-(La))
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43919)
ランタンフェリ赤坂石 / Ferriakasakaite-(La)
CaLaFe3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
ランタンフェリアンドロス石 / Ferriandorosite-(La)
Mn2+LaFe3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Epidote supergroup
模式地:三重県 伊勢市 矢持町菖蒲
記載論文:Nagashima M., Nishio-Hamane D., Tomita N., Minakawa T., Inaba S. (2015) Ferriakasakaite-(La) and ferriandrosite-(La): new epidote-supergroup minerals from Ise, Mie Prefecture, Japan. Mineralogical Magazine, 79, 735-753.


模式地標本 この産地の褐簾石亜族の新鉱物は見た目では区別できない。実際のところ、集合体になるとたいてい3種が混じっている。

ここの褐簾石亜族の化学組成は中間的でほんのちょっとの違いで簡単に種をまたぎ、それ故にこんな狭い範囲で共存することが良く起こる。
またもや三重県伊勢市からの新鉱物、「ランタンフェリ赤坂石( Ferriakasakaite-(La))」と「ランタンフェリアンドロス石(Ferriandrosite-(La))」である。今回も山口大学からプレスリリースを出してもらったのでそちらもご覧ください。このページはいつものとおり写真と雑記。今回の新鉱物が承認されたのは2月3日。その日は私自身が研究代表を務めた新鉱物・伊予石&三崎石の承認通知も来ており、一日で4通も承認通知を受け取った。鬼は外、福は内。
それにしてもこの産地(矢持町菖蒲)からはよく新鉱物が見つかる。今回のものは「伊勢鉱」、「ランタンバナジウム褐簾石」に続いて第3・第4の新鉱物となった。ランタンバナジウム褐簾石の発見後、もう少し研究用試料を確保したくて同様な外観を持つ鉱物を調べていたら、さらに二つも新鉱物が見つかった。そして伊勢市の別の産地からは「今吉石」という新鉱物も見いだしているので、ほんの3年くらいで合計5種もの新鉱物が伊勢市から発見(承認)されたことになる。これだけあるともはや新鉱物は伊勢の名物と言っても良いだろう。そしてこれらすべてが一人の愛石家・稲葉幸郎による発見から始まっている。縁あって私は「伊勢鉱」と「今吉石」の研究代表を務めさせてもらい、「ランタンバナジウム褐簾石」「ランタンフェリ赤坂石」「ランタンフェリアンドロス石」は緑簾石族全般に詳しい&研究実績のある山口大・永嶌真理子さんに仕切ってもらった。その経緯は「ランタンバナジウム褐簾石」の項目も参照してください。
今回の新鉱物たちと前に見つけているランタンバナジウム褐簾石は、緑簾石族の褐簾石亜族というものに分類される。鉱物とは化学組成と結晶構造で定義される天然の固体物質のことで、化学組成もしくは結晶構造が新規のものなら新鉱物となる。そして今回みつけた新鉱物は結晶構造が同一で、化学組成がそれぞれ違っている。こういった集まりを「族 / group」という。その中で特定の化学組成を持つものがさらに「亜族 / subgroup」として分類される。その「族」や「亜族」の中身や説明はそれだけで一つの論文になっているくらい膨大なのだが、せっかくなので褐簾石亜族のさらにその一部に限定して取り上げてみよう。ただこれだけでもちょっと長くなる。
ではひとまず下の表1を見てほしい。横並びのA1~M3席というのは結晶構造中の元素の存在する席で、その下にそれぞれの新鉱物がもつ元素を記した。
_
表1.褐簾石亜族鉱物の結晶学的席と元素
| 学名 | 和名 | A1席 | A2席 | M1席 | M2席 | M3席 |
| Ferriakasakaite-(REE) | REEフェリ赤坂石 | Ca | REE | Fe3+ | Al | Mn2+ |
| Ferriandorosite-(REE) | REEフェリアンドロス石 | Mn2+ | REE | Fe3+ | Al | Mn2+ |
| Vanadoallanite-(REE) | REEバナジウム褐簾石 | Ca | REE | V3+ | Al | Fe2+ |
まず緑簾石族というのはA1A2M1M2M3(Si2O7)(SiO4)O(OH)という化学組成をもつ鉱物たちのことを言う。A1、A2、M1、M2、M3という席にいろんな元素が入る。そして、A1に二価陽イオン、A2席にレアアース(REE)、M1とM2席に三価陽イオン、M3に二価陽イオンが入るものを褐簾石亜族という。さらにA1・M2・M3席の元素の組み合わせによって基準となる名前(ルートネーム)が定義される。そして褐簾石亜族の学名は「化学組成ルートネーム-(REE)」となっていることを念頭に、まずはルートネームの命名を説明しよう。A1・M2・M3がカルシウム(Ca)・アルミニウム(Al)・マンガン(Mn2+)だとルートネームは「赤坂石/akasakaite」となる。Mn・Al・Mnならルートネームは「アンドロス石/andorosite」で、Ca・Al・二価鉄(Fe2+)なら「褐簾石/allanite」というルートネーム。もしMn2+・Al・Fe2+というものを見つけたらそれは新しいルートネームをつけることができる。で、続き。そのあと「化学組成」の部分はM1席の元素種類で決まる。M1席には3価の陽イオンが入り、三価鉄(Fe3+)なら「フェリ/ferri」、バナジウム(V)なら「バナジウム/vanado」が「化学組成」の部分につく。もしM1席がアルミニウム(Al)なら何もつかない。そして最後に、A2席のレアアースの種類は「―(REE)」をルートネームの後ろにつける。ランタン(La)なら「-(La)」、セリウム(Ce)なら「-(Ce)」がルートネームの後ろにくっつく(サフィックスという)。このように褐簾石亜族の学名は「化学組成ルートネーム-(REE)」という順序になっている。
ただし、和名にするときは「REE化学組成ルートネーム」という順番にする。その理由は学名の直訳だと収まりが悪いから。たとえば学名の「Ferriakasakaite-(La)」を直訳すると「フェリ赤坂石ランタン」となるが、なんだか鉱物っぽくない。やっぱり鉱物名なんだから最後は「石」で締めたい。ということで、「Ferriakasakaite-(La)」というのは「ランタンフェリ赤坂石」という和名になる、というか、そうします。
さて、ここで「ランタンフェリ赤坂石」の元になった「赤坂」についてちょっと述べておこう。この名前は島根大学教授の赤坂正秀に因んでいる。赤坂先生の業績はたくさんあるが、今回の新鉱物と関係する業績を紹介すると、緑簾石族を再定義しようという国際作業部会が立ち上がった際に、その研究実績を買われて赤坂先生は唯一の日本人研究者として参画している。となると日本で緑簾石族の新鉱物が見つかった場合は赤坂先生の名前はルートネームの有力な候補となるだろう。また赤坂先生は今回の筆頭研究者・永嶌さんが学位を取得したときの指導教員で、永嶌さんが緑簾石族マニアになったのは赤坂先生のせい(おかげ)でもある。こうなると永嶌さんが研究代表を務める国産の緑簾石族の新鉱物、その名前には「赤坂石」しか考えられない。新鉱物には自ら発見に関わったものに自分の名前をつけることはできないというルールがあるが、師匠の名前をつけることには何ら制約はない。今回の新鉱物の命名は弟子から師匠への恩返しなのだ。
せっかくなのでもう一つの新鉱物「ランタンフェリアンドロス石」の元になった「アンドロス」についてもふれておこう。ルートネーム「アンドロス石」は、エーゲ海キクラデス諸島(ギリシャ)で2番目に大きな島、「アンドロス島」に由来している。そのアンドロス島の最も高い山(Mt. Petalon)にマンガン鉱石を目的とした試掘後があって、そこから産出した新鉱物にルートネーム「アンドロス石」が命名された。この鉱物は緑簾石族命名規約の改定を経て、「ランタンマンガニアンドロス石 / Manganiandrosite-(La)」という正式名称となる。そのフェリ(Fe3+)置換体に相当するのが、今回、我々の見つけた新鉱物「ランタンフェリアンドロス石」である。
さあいつものように鑑定のポイントを紹介しよう。といってもほとんどはランタンバナジウム褐簾石のときに書いてしまった。今回はその補足&訂正になる。まず、この産地に出る褐簾石亜族の鉱物には上に紹介した三種の新鉱物の他にランタンフェリ褐簾石がある(化学組成は上の説明から考えてみよう)。そしてこれら計四種は残念ながら見た目で区別することはできない。そしてマニアにはさらに残念なことに産状からの鑑定もあまり当てにならなくなった。ランタンバナジウム褐簾石はテフロ石に伴われるものだけしか見つかっていないというのは確かなのだが、あとの三種は困ったことに、ベメント石、テフロ石、菱マンガン鉱脈中であればどこにでも顔を出す。さらには数ミリ四方の小さな領域にランタンフェリ褐簾石・ランタンフェリ赤坂石・ランタンフェリアンドロス石の三種がいることは全然珍しくはない。見た目はおろか産状でさえ区別できないことになった。もはや全部の鉱物種を書いたラベルをつくれば良いだろう、きっとそれは正解だ。全体としてはランタンフェリ褐簾石≧ランタンフェリ赤坂石>ランタンフェリアンドロス石 >>> ランタンバナジウム褐簾石である。
この産地に限らず西南日本秩父帯に胚胎される鉄マンガン鉱床の起源は過去の海洋底の堆積物である。そして、その堆積物は太平洋の深海底にある中央海嶺の火成活動に伴って噴出する熱水が関係している。おおざっぱなストーリーは次。①中央海嶺の火成活動により噴出した熱水が海水中に拡散→②熱水に含まれる鉄・マンガンが酸化され懸濁物質になる→③懸濁物質が海水中に溶け込んでいるレアアース&レアメタルを吸着→④深海底に堆積→⑤プレート運動で日本側に移動→⑥ちょっと変成を受けた後に地上に上がり(付加体)、これが秩父帯中の鉄マンガン鉱床となる。こんな流れで、中央海嶺から熱水が噴き出して現在に至るまでのタイムスケールは数億年。要は伊勢の鉄マンガン鉱床中のレアアースやレアメタルは、もともとは太古の海洋に溶け込んでいたものだ(と考えている)。そういえば以前に「ランタンバナジウム褐簾石」のバナジウムの起源について、「海底に住んでいるホヤが体内にバナジウムを蓄積するからそれである」というコメントをもらったことがある。無邪気な発想ではあるがたぶんそれは無い。
IMA No./year: 2013-069
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43749:holotype, M-43750:cotype)
今吉石 / Imayoshiite
Ca3Al(CO3)[B(OH)4](OH)6・12H2O
Ettringite group
模式地:三重県 伊勢市 水晶谷
記載論文:Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Momma K., Shimobayashi N., Miyawaki R., Minakawa T., Inaba S. (2015) Imayoshiite, Ca3Al(CO3)[B(OH)4](OH)6•12H2O, a new mineral of ettringite group from Ise City, Mie Prefecture, Japan., Mineralogical Magazine, 79, 413-423.

絹糸光沢を示す繊維状結晶が今吉石。重量の50%以上が水でできている鉱物。
三重県伊勢市からの新鉱物,今吉石(Imayoshiite)である。鉱物コレクター・今吉隆治(1905-1984)にちなんで命名されたこの鉱物は弟子(稲葉)から師匠への贈り物。それにしても昨年以降、伊勢市からは新鉱物の発見(承認)が相次いで、式年遷宮の日に承認された今吉石は伊勢鉱・ランタンバナジウム褐簾石に続いて3種目となる。いずれも超稀産の3種なので三種の神器にあやかって宣伝したいところだが、今後も続くかな?
さて新種を発見したら命名権は発見者にあるというのはなんとなく理解できるだろう。生物の新種の学名では誰が発見したかがわかるように、学名の一番最後に発見者の名前が入っていることが多い。こういうのを二名法と言う。ところが鉱物の場合は「自分が発見した新鉱物には自分の名前をつけることができない」 というルールがある。そのため新鉱物はたいていは地名とか鉱物学に関連する人物の名前にちなんで命名される。地名の場合はシンプルにその鉱物が発見された鉱山・集落・市町村・県の名前というのが候補になるが、人名の場合は基本的には何らかの形での鉱物学へ貢献したこと、もしくは鉱物学と深く関わっていることが命名の理由となる。前者のケースだといわゆる研究者が行った仕事が該当し、後者だと様々だが一つの関わり方として鉱物収集がある。そして今吉隆治(Takaharu Imayoshi)は間違いなく熱狂的な鉱物収集家の一人であった。それは亡くなるまでに集めた標本が一万点を越えていたというすさまじさからもわかるだろう。しかも佳品が多かったと聞いている。現在ではその多くは地質標本館へ収蔵されて研究のために有効に活用され、一部は展示で来館者の目を楽しませてくれる。まだ訪れたことはないが静岡県の奇石博物館には今吉隆治が最後まで手放さなかった秘蔵標本が展示されているらしい。そのうちこっそり行ってみよう。
前置きがちょっとズレたが、鉱物収集というのはたしかに個人の趣味として捉えられるものである。がしかし、鉱物収集は鉱物学との一つの重要な関わり方でもあって、それに突出した人物はやっぱり新鉱物名の候補となる。今回の新鉱物の名前を考える段になって、発見者の稲葉から提案された自らの師匠「今吉隆治」の名前は共著者みんなが納得のいくものであった。足立電気石のところでも紹介したが、日本では研究者ではない人物が鉱物名として採用されたのは、長島乙吉、櫻井欽一、益富寿之助、足立富男につづいて、今吉隆治が5人目となる。今後も鉱物収集家やローカルガイドは新鉱物名の候補となるだろう。
この鉱物の発見はざっくり30年前にさかのぼる。稲葉が伊勢市山中の蛇紋岩地帯を探索中に見つけたもので、産状は蛇紋岩中のゼノリス(捕獲岩)。発見当初からエットリング石グループの一種だとは考えられてはいたのだが、試料が少ない上に当時では分析が難しくて,う~んという状態がそこからなんと30年。まあずっと検討してたわけではなくてそれはほとんどあきらめていた期間に等しいが、昨年(2012)の夏くらいからいろんな人に協力してもらい、ようやく新鉱物としてのデータがそろって今回の承認となった。
全体の産状は皆川ほか(1986)に詳しいのでそれを参考にしてもらいたいが、今吉石の母岩は蛇紋岩中の斑糲岩ペグマタイト質のゼノリスで斜方輝石や斜長石が粗粒化している。そして今吉石は斜長石が熱水変質を受けた部分に産出する。要は真っ白でちょっとボロくなっている岩石の一部なのだが、今吉石は絹糸光沢を示す透明な繊維集合が脈状で産出する。稀にはその繊維状集合が六角形に配列する。また繊維状集合の一部では透明な塊状に粗粒化することもある。この岩石中で透明感のある結晶を形成するのは今吉石だけで、他の共生鉱物(加水ざくろ石、ゾノトラ石、トベルモリ石、バルトフォンテン石)はのぺっとした不透明白色塊の中にある。ごく一部に大江石がみられるが、これはちょっとパサっとした繊維状集合なのに対して今吉石は瑞々しい集合体なのでその違いはぱっと見で区別できる。それに今吉石は共生鉱物に比べて圧倒的に華奢でもろいので、これも鑑定ポイントである。いずれにしても今吉石は入っていればルーペが無くとも肉眼でも簡単に判別可能なのだが、一度は現物を見ておかないと初見での判別は難しいかもしれない。ところが今吉石を見る機会はそうそうやってこないと思う。と言うのも産地には今吉石を含むゼノリスが極端に乏しい。少しくらいあるだろうと現地に行ってみたがこれが無いんだな、ほんと~に無い、見事に無い、どうしようもない。あるのは霰石ばっかり。こうなるともはや肉眼鑑定以前の問題で今吉石のレアさは伊勢鉱の比でなどではない。いずれにしても新産地が見つかるまでは今吉石は最も見かけることの少ない新鉱物になるかもしれない。
今吉石はエットリング石グループに所属している。2008年に岡山県布賀鉱山からエットリング石グループであるチャールズ石のCO2置換体という鉱物の報告があり、我々も今吉石の再検討を始めた当初はこいつとイコールかと思っていた。しかしそれらは似て非なるもので、今吉石と布賀産の鉱物とは全然違うものとわかった。ついでに書いておくと布賀の鉱物はとりあえずまだ何者でもない。今後これが新鉱物となるかUnnamed Mineralのままでいるか、今後の推移を注意深く見ていこう。
IMA No./year: 2013-034
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43779)
岩手石 / Iwateite
Na2BaMn(PO4)2
Glaserite structured mineral
模式地:岩手県 田野畑村 田野畑鉱山
記載論文:Nishio-Hamane D., Minakawa T., Okada H. (2014) Iwateite, Na2BaMn(PO4)2, a new mineral from the Tanohata mine, Iwate Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 109, 34-37.

顕微鏡写真。オープンニコルで白濁してみえる結晶が岩手石。クロスではほぼ消光。
「あまちゃん」人気で盛り上がっている岩手県からの新鉱物岩手石(Iwateite)である。岩手県田野畑鉱山を模式地とする新鉱物は多く、これまでに神津閃石、鈴木石、ソーダ南部石、わたつみ石、カリリーク閃石、田野畑石が発見されている。岩手石は7番目となる。岩手県からの新鉱物としては14種目か・・、ようやく岩手の名前がついた。私にとっては10種目、二桁に到達したメモリアル。
最初にちょっと脱線(長くなるけど)。田野畑鉱山のからの新鉱物で岩手石の共生鉱物である神津閃石だが、実はその名前が消滅してしまった。命名規約の変更で「神津閃石(Mn2+4Fe3+)」は「マンガノフェリエッケルマン閃石」となった。これがまた一見混乱する命名なのです。名前の後半の「エッケルマン閃石」というのは(Mg2+4Al3+)組成で,このFe3+置換体(Mg2+4Fe3+)には「マグネシオアルベソン閃石」という名前がすでにある。そうなると「(旧)神津閃石(Mn2+4Fe3+)」は「マグネシオアルベソン閃石(Mg2+4Fe3+)」のMg→Mn置換体、つまり「マンガノアルベソン閃石」に改名されるはずだとふつうは思ってしまう。ところがそうではない。なぜか?その理由はたった一つ、今回の命名規約改訂のキモはMgAlの優占種をルーツネームとして扱うことだから。つまり「(旧)神津閃石(Mn2+4Fe3+)」は「マグネシオアルベソン閃石(Mg2+4Fe3+)」のMn置換体という扱いではなくて、「エッケルマン閃石(Mg2+4Al3+)」というルーツネームのMn(マンガノ)とFe3+(フェリ)置換体にあたるので「マンガノフェリエッケルマン閃石」となったのだ。そうだとするとエッケルマン閃石というルーツネームのAl→Fe3+置換体に相当するはずの「マグネシオアルベソン閃石」はなぜ「フェリエッケルマン閃石」ではないのか?という疑問が生じる。ところがこの命名規約は「リーベック閃石、アルベソン閃石、アクチノ閃石、ヘスチング閃石などは消すと岩石学者が混乱するから例外的に名前を残してやる!んで、アクチノ閃石以外にはMg優占種にマグネシオってつけるから!ついでにふつう角閃石はMgAl優占種のルーツネームだけどこれにも例外的にマグネシオつけるから覚えとけよ!!」などとなっている。もうアホかと・・。どうせ分けるなら中途半端な例外なくして一つのルールできっちり仕分けてください。むしろ混乱を助長しとるわ。愛媛閃石も消されたしコノメイメイキヤクボクダイキライ。神津閃石→マンガノフェリエッケルマン閃石は病膏肓に入った鉱物マニアでも理解できてなくて、たとえばマニアの集まりMindatでもマンガノアルベソン閃石になってる(2013/07/01現在)。それまちがっとるよ。
さて本題。日本の場合では新鉱物の申請を行うにあたり必須ではないが推奨される手順がある。日本の鉱物学会には新鉱物・命名・分類委員会というのがあって、そこでは本申請に先立って申請書を事前にチェックしてコメントをくれるので、まずはそこに提出するのがお奨めのやりかた。新鉱物申請の経験者ばかりで構成されているので、この委員会のコメントを参考に修正した申請はたいてい本番でも問題なく通ることが多い。もちろん今回の岩手石も申請に先立ってこの委員会からのコメントを求めたのだが、鉱物データ以外の思いがけない指摘を受けてしまった。
実は委員会にコメントを求めた時点ではこの鉱物はみちのく石(Michinokuite)としていた。産地が岩手、つまり東北なんで「東北」=「みちのく」ってことで良いじゃない。石そのものは地味だとは思うが「みちのく石」は「わたつみ石」に匹敵するくらいすてきな名前だとも思っていた。ところがその「みちのく」がよろしくないというコメントであった。要は「みちのく」って場所がいろいろ変わってきてるし、岩手県田野畑村がその代表とはちがうんじゃない?それにこの鉱物が東北で普遍的に産出するものでもないだろうから、まあやめときなよと言うものでした。未知の苦じぇじぇじぇっ!?
そうなると名前は再考、次の候補は人名・地名である。人名で真っ先に思い浮かぶのは石っ子賢ちゃんこと宮沢賢治、地名だと岩手。でも待てよイーハトーブもとい岩手あっての宮沢賢治だろ?そして鉱物には岩手の名前ががまだない、ということで岩手を先に採用しました。もちろん岩手石ができたからには次は宮沢賢治の名前を採用したい。
さあ、岩手石の肉眼鑑定ポイントに移ろう。胸を張って言うが絶対無理!!。夢のない発言だが肉眼鑑定はもうあきらめてください。薄片にすればそれなりにわかるが、肉眼では無色透明で小さく結晶外形もこれといって特徴が無いのでどれがなにやらさっぱりわかりません。ただそれでもどうしても手に入れたいという熱心な愛石家はいると思う。そのような方々のために一つだけ朗報がある。なぜか岩手石はセラン石の結晶中にいることが多く、セラン石のかたまりから薄片を作ると50%くらいの確率で見つかる。まあたまたまかもしれんけど。
田野畑鉱山からの新鉱物はこれまでにたくさん発見されていて色や特徴的な産状が目につくが、実はそれが盲点になっている。結果として研究者もアマチュアも目につくモノだけしか調べて(採って)いない。まあ当然だろう。だが田野畑にはおもしろい元素が目白押しなので、組み合わせによっては白とか透明とか目立たない形の新鉱物があるだろうと思って研究が始まった。ではどうやって目に見えない鉱物を見つけるのか?そればかりは研究者の特権かもしれない。研究者の使う走査型電子顕微鏡(SEM)は重たい元素を持っている鉱物が明るく、軽い元素からできている鉱物は暗く写る。その明暗が強くなるように調整すると、岩手石のように重たい元素(BaやSr)を持っている鉱物だけがまるで夜空の星のように白く輝く。ここは私たちだけがたどり着いた銀河の河原。この礫(こいし)はみんな新鉱物だ。中で小さな火が燃えてゐる。
IMA No./year: 2012-101
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43748)
足立電気石 / Adachiite
CaFe2+3Al6(Si5AlO6)(BO3)3(OH)3(OH)
Tourmaline supergroup
模式地:大分県 佐伯市 木浦鉱山
記載論文:Nishio-Hamane D., Minakawa T., Yamaura J., Oyama T., Ohnishi M., Shimobayashi N. (2014) Adachiite, a Si-poor member of tourmaline supergroup from the Kiura mine, Oita Prefecture, Japan, Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 109, 74-78.


模式地標本 一般的には黒色柱状結晶の集合として産出する。不透明というわけではなく、強い光をむりやりあてると小さい結晶なら透明であることが確認できる。実際には鉄電気石と複雑な累帯を成し、その一部が足立電気石となる。この産地の電気石はほとんどの場合で足立電気石を含んでいる。
電気石グループの新種,足立電気石(Adachiite)で、いわゆるチェルマック置換型の電気石となる。チェルマック置換型の電気石は足立電気石が世界初となる。世界でもっともシリコンの少ない(逆説的にアルミニウムの多い)電気石ということ。チェルマック置換型は輝石とか角閃石ではよくあるのに電気石ではなぜか知られていなかった、不思議だね。
世界初となる電気石の鉱物名には足立富男 氏(1923-) の名前をいただいた。氏は宮崎県延岡市在住で御年90歳。宮崎県下の高校で教鞭をとっておられた方で研究機関の研究者ではない。しかし氏は鉱物だけではなく地質や化石などいわゆる地学全体に対する造詣が深く、また宮崎県内だけでなく九州各地を踏破してその地質・鉱山を知り尽くしている。地学教育の普及活動にも熱心で、学生を連れて地学巡検を積極的に行っていたとも聞いている。こういった地域に根ざした活動を行う人を「Local guide」と言って、研究者はこのような方に現地を案内してもらって研究を行うことが多い。とうぜん氏のこれまでの活動による鉱物科学への貢献は大きく、九州産の新鉱物の名前にふさわしいと思って関係者に提案してみた。もちろん異論なし!皆川先生を通じて足立先生へお伝えし、ご本人の了承をいただいた上で申請した。無事承認されてよかった。
日本産新鉱物はこの時点で120種に達しようというところであるが、プロ研究者ではない人物の名前が鉱物名に採用された例は長島乙吉(1890-1969) [長島石(Nagashimalite:IMA1977-045),桜井欽一(1912-1993) [桜井鉱(Sakuraiite:IMA1965-017)、欽一石(Kinichilite:IMA1979-031)],益富寿之助(1901-1993) [益富雲母(Masutomilite:IMA1974-046)] だけで、非常に希である。欽一石以来、実に34年ぶりとなる。足立電気石が承認された日は2013年4月2日、その日は下に掲載したランタンバナジウム褐簾石のプレスリリース日でもあったため、取材の電話がガンガン鳴っている中でのもうひとつのうれしい通達だった。
足立先生の名前は既にクサリサンゴ化石の一種にも採用されており、石・鉱物の両方に名前が採用されることはたいへん稀である。おめでとう足立先生。
大学4年生~修士過程の私の研究テーマは「ラテライト質変成岩中の鉱物」で、大分県木浦鉱山のエメリーはまさにそのものだった。そんなわけで木浦鉱山のエメリーから新鉱物を発見できたことは原点回帰のようにも思う。もう10年以上まえになるが初めて訪れる木浦鉱山を案内してくれたのが足立先生だった。足立先生は覚えてないだろうが、クソ狭い道を軽バンでカっ飛ばして一日で広い木浦鉱山を5カ所くらい案内してくれた。坑道にも入って公民館の展示も見てとあわただしかったが、その健脚にはおどろくばかり。最後に川のほとりの雑貨屋でお茶を出してもらってようやく落ち着いた。
さて、足立電気石はエメリー鉱石を貫く熱水脈中に真珠雲母や緑泥石、たまにダイアスポアを伴って産出する。エメリー鉱石はコランダムとスピネルで主にできていて、その堅さがウリの商品である。純度の高いエメリー鉱石はうっすら青みを帯びた黒色緻密な塊であり、ハンマーでたたくとキンキンと音がしてまあまず割れない。逆に真珠雲母や緑泥石を伴うような鉱石は変質を受けていて比較的柔らかくて割れやすく、それ故に売り物にもならずで出荷できないゴミとして捨てられてしまう。事務所の人からもいくらでも持って行けと言われるここの真珠雲母は手に入りやすかった古典標本なので一度は手にした人も多いと思う。その真珠雲母や緑泥石に埋もれるかたちで黒色柱状結晶が入っており、これが足立電気石だ。外観は一般的な鉄電気石そのものなので愛石家なら間違えることはまず無いだろう。実際には鉄電気石と類帯しているのだが、ほとんどすべての試料に足立電気石が含まれるから遠慮無くラベルをつけてしまおう。映える標本はむしろ風化しきったモノが良い。一見泥をかぶった標本は亀の子たわしで遠慮無くガシガシこすると頭付きの結晶が出てくるので、小汚く見えるモノのほうが実は宝物だったりする。ステキな結晶もズタボロの真珠雲母をツンツンしてたらポロッとでてきた。
エメリー鉱の産出は日本ではこの木浦鉱山のみと地元では説明されているが実はそんなことはなく、愛媛県小大下島(こおおげしま)にも立派なエメリー鉱が産出する。ただ小大下島エメリーには電気石は無かった。まあそれはさておいてもエメリー鉱を「ラテライト質変成岩」ととらえると産地はもっと広く、愛媛県弓削島、明神島、睦月島にも産出が認められる。足立電気石の発見を受けてラテライト質変成岩っておもしろいなと改めて思うし、新鉱物がでる手がかりをつかんでいるのでなんとか形にしなければ・・。
このページを読んでいるくらいの深刻な鉱物マニアなら堀秀道先生の「楽しい鉱物鉱物図鑑2」はすでにもっていると思う。この本は私が初めて買った鉱物の本で,36ページに出てくるA氏が足立先生であることを知ったのは本当にごく最近だった。
IMA No./year: 2012-095
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43737)
ランタンバナジウム褐簾石 / Vanadoallanite-(La)
CaLa3+V3+AlFe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Allanite subgroup in Epidote group
模式地:三重県 伊勢市 矢持町菖蒲
記載論文:Nagashima M., Nishio-Hamane D., Tomita N., Minakawa T., Inaba S. (2013) Vanadoallanite-(La): a new epidote-supergroup mineral from Ise, Mie Prefecture, Japan, Mineralogical Magazine, 77, 2739-2752.

模式地標本 この産地の褐簾石亜族の新鉱物は見た目では区別できないので、とりあえずこの結晶を本鉱としておきましょう。

模式地標本 タイプ標本からのピックアップした結晶のSEM写真
ランタン(La)とバナジウム(V)に富む褐簾石の新種・ランタンバナジウム褐簾石(Vanadoallanite-(La))である。緑簾石グループの中の褐簾石サブグループに分類される。この仲間は命名規約(ルール)があるので名前に選択肢は無く、ちょっと長いこの名前になった。発見地は伊勢鉱と同じところ。山口大からプレスリリースを発信してもらったのでそちらも参考にどうぞ。
さて筆を進めよう。稲葉が地元の祭りに参加した際に山道の脇に放置された鉱石を偶然に目にしたのがきっかけで、ここから一連の研究が始まった。ここの鉱石はまあ地味で、熟練の鉱物マニアでさえ蹴飛ばすような一見つまらない鉄・マンガン鉱石なのだが、稲葉は東海地域の鉱物の研究を長年続けている愛好家で、このつまらなさそうな鉱石でさえ注意深く観察した。そしてその観察眼はさすがと言うべきだろう,稲葉はテフロ石・ベメント石脈中に見慣れない黒褐色の板柱状鉱物に気づいた。これが今回のランタンバナジウム褐簾石の発見につながった。ただ研究そのものは後に見つかった伊勢鉱の方が先に進んでしまい、新鉱物としてはこの産地で二番目となった。
ここは秩父帯という地質でそもそもは太平洋海底の堆積物が起源。その堆積物がプレートテクトニクスによって数億年かけて日本列島の方へ移動し、はぎ取られ、再び地表に現れたのが今の姿。こうやってできた地質を付加体という。秩父帯の元になった堆積物が溜まった数億年前と現在堆積しつつある海洋底の条件が同じとは限らないが、近年話題の南鳥島近海のレアアースをふくむ泥は数億年後には今の秩父帯のような地質になるかもしれない。まあ付加体にはなるだろう。いずれにしてもかつて海洋底堆積物だったはずの付加体でもレアアースの資源調査は望まれる。ただしこういった類の調査がどの程度進んでいるかに関しては論文が少なくてよくわからない。それに鉱物屋としては海底の泥もそうだが、変成度の低い秩父帯ではどんな鉱物にレアアースが含まれるかを明らかにすることのほうが気になる。四国の秩父帯の鉄マン鉱床からはちょっとまえにもレアアースを含む新鉱物が発見されたばかりなので、今回新たに三重県から見つけた秩父帯の鉄マン鉱床についてもレアアース鉱物の調査を行う価値は十分にある。
そんな事情もあって伊勢の鉄マン鉱床からもレアアースのホストである褐簾石が産出したというのはやっぱり新しいかつ重要な発見となるだろう。そこで褐簾石を詳細に検討して鉱物種を確定させようと試みたところ、多くの褐簾石はランタンと3価鉄(Fe3+)に富む種類の褐簾石、すなわちランタンフェリ褐簾石(Ferriallanite-(La))と同定された。ランタンフェリ褐簾石はごく最近発見されたばかりでものすごく珍しい。さらに詳しく調べていくと一部の褐簾石は3価鉄よりもバナジウムに富むことがわかってきた。ランタンとバナジウムに富む褐簾石となると珍しいどころか新種である。一方でこれを新鉱物として申請するには困難が予想された。実際に手間取ったせいで後に見つかった伊勢鉱のほうが新鉱物として先に世に出ることになった。
褐簾石を含む緑簾石グループの鉱物を記載するには今ではしっかりとした命名規約(ルール)があるが、昔はこのルールが無かったせいもあり種の同定は研究者でも勘違いや間違えたりするくらいややこしかった。科博の松原先生が勘違いでストロンチウム紅簾石を日本産新鉱物にしそこねた話は有名(?)である。まあややこしいからルールができたと考えれば良いだろう。いずれにせよこのグループは新しい組成を発見しただけでは新鉱物としては承認されない。各元素、今回はランタンとバナジウムが結晶構造の中のどこにいるかを決めることが必要なのだが、これがまた難しくてこの新鉱物候補は私の手に余った。そこで褐簾石を含む緑簾石グループを広く研究して学位を取得し、その業績で鉱物学会の奨励賞も受賞している山口大学の永嶌真理子さんにコンタクトをとり協力をお願いした。さすがは名うての緑簾石族マニア、彼女の活躍で晴れて新鉱物の承認を得ることができた。
名前について触れておこう。「褐簾石」とは京都の大文字山に産する結晶の外観から命名された和名で、褐色をした簾のような石という意味である。1903年(明治36年)に名付けられ、,そこからこの和名が慣習となり現在に至っている。しかし褐簾石の学名である「allanite」というのは、スコットランド人の鉱物学者 Thomas Allan (1777-1833) にちなんでいることは心に留め置こう(発見は1812年にGreenlandから)。和名はしばしばオリジナルを踏襲しない。かといって今更「アラン石」なんて馴染まんので和名としては「褐簾石」をもつかうことにする。ゴメンよAllanさん。和名はいつも悩ましいが、統一的な見解や用法はまだ整備されていないという現実がある。
そうそう一般的な褐簾石はレアアースの他にトリウム(Th)やウラン(U)を含んでおり、それらから生じる放射線のダメージで結晶構造が壊れていることが多い。しかしこの産地の褐簾石はトリウム・ウランを持っていないので結晶構造はしっかりと保たれている。
さあ鑑定ポイントに移ろう。この産地の褐簾石はベメント石やテフロ石脈中に最大1ミリ程度で、おおむね0.1ミリくらいの黒褐色の板柱状結晶としてポツポツと埋没している。松脂質にぎらつく割れ口や表面のテリは褐簾石特有のものである。この鉱物は割れやすくて新鮮な母岩を叩いて完全な結晶を得るのは困難なのだが、ベメント石やテフロ石が風化してネオトス石+粘土みたいになっているところでは褐簾石は完全な結晶を見せることがある。このような標本はなかなか見栄えが良い。いずれにしても10倍のルーペでも観察は比較的容易だし、似たような鉱物は産出しないので間違えることはないだろう。ただ伊勢鉱とは産出がまったく無関係なのでそちらに気が向いているとまず見落とす。
もう一点ポイントを追加しておく。ここの褐簾石は同じ脈中のモノでも組成が異なる。鉱物種がランタンフェリ褐簾石~ランタンバナジウム褐簾石の間で変化して、これらを肉眼で区別することはできない。そのため確実なランタンバナジウム褐簾石は薄片なり単結晶構造解析に使った粒だったりして標本として適さないのだが、ある程度の経験則はある。ベメント石よりもテフロ石脈中の結晶のほうがバナジウムを多く含む傾向がある。そんなわけで私はテフロ石脈中のものや、それが風化してネオトス石に変質した産状のものにランタンバナジウム褐簾石のラベルをつけている。確実な標本とは言えないが、個人で愉しむ分には産状を目安にして分類するのがよいだろう。
この産地の新鉱物はこれでふたつ。それにしてもここの鉄マン鉱床は不思議。伊勢鉱で明らかとなったマンガン(Mn)とモリブデン(Mo)という組み合わせもそうだが、これまでになかった元素の組み合わせがどんどん見つかる。レアアースにしても通常のレアアース鉱床はセリウム(Ce)に富むことが多いが、この鉱床のレアアースはセリウムが少なくランタンに富むモノがほとんど。環境を考えるとセリウムだけが選択的に消え去ったのだろう。そうなると現在のレアアースの堆積場である南鳥島近海の泥のレアアースの種類や量比とリンクしていなと感じる。いずれにしても天然の地質作用の必然なのだろう。
IMA No./year: 2012-035
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43670:holotype, M-43671:cotype), 京都大学博物館(#KUM-M00001:cotype)
箕面石 / Minohlite
(Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10・8H2O
Chemically related to schulenbergite
模式地:大阪府 箕面市 平尾
記載論文:Ohnishi M., Shimobayashi N., Nishio-Hamane D., Shinoda K., Momma K., Ikeda T. (2013) Minohlite, a new copper-zinc sulphate mineral from Minoh, Osaka, Japan. Mineralogical Magazine, 77, 335-342.
大阪府箕面市から発見されたアップルグリーンのきれいな新鉱物・箕面石(Minohlite)。大阪府からの新鉱物としては2例目となる。大阪初の新鉱物は大阪石(Osakaite)で、これも大西氏が発見し研究も筆頭でとりまとめている。鉱物の学名は最後に「ite」もしくは「lite」をつけることになっている。これはラテン語で「石」という意味から来ており、どっちをつけるかは著者の好み。日本産では昔は「lite」が多かったが最近は「ite」が多い。世界の傾向もそうなっている。箕面石には「lite」がついた。
箕面石や大阪石のような鉱物はいわゆる二次鉱物に分類される。元々あった鉱物が水や空気やなんやかやと反応して別種に変わったものを指すが、何回変わっても二次と言う。幾度の反応を経由したことがわかっていても三次鉱物、四次鉱物とは言わない。「二番目」ということではなく「派生的な」という意味でとらえるとちょうど良いだろう。箕面石の場合は黄銅鉱や閃亜鉛鉱が分解してできたと推測される。
「鉱物」の定義をざっくり言うと「天然の地質学的作用で生じる固体物質」となる。一方で二次鉱物は鉱山跡:人間が掘った坑道や石捨て場(ズリ)で生じることがしばしばある。そのような人の手が加わったところで生じる二次鉱物は果たして「天然」という条件を満たすか?という疑問は素直な感覚だと思う。それでも二次鉱物は鉱物として扱われる。人間が掘ったからこそ生じたモノであっても人間が掘った後に進行した作用は天然の地質学的作用であるからOKという扱いである。
「天然」をどこまで適用するのかは難しいが、「からみ」から派生したモノはアウト。「からみ」とは鉱石から必要なモノを取り出した後の搾り滓のことで、鉱山跡にはよく放置されている。石垣に使われることもある。そしてその「からみ」が変質を受けて何らかの派生的な物質を生み出すことがしばしばある。たとえば海岸に放置された銅鉱石の「からみ」をたたき割るとその空隙には緑鮮やかな(パラ)アタカマ石が見事に結晶化している。しかしこれは鉱物としては認められない。世界初の物質であっても「からみ」中のモノは鉱物としての資格がない。その理由は、「からみ」は元素を濃集させる作用を「人工的」に行っているから。ただし「からみ」中には非常に珍しいモノが結晶化していることもあり、採集のターゲットとしては結構おもしろい。
今回の箕面石は鉱山の堀跡から採集された二次鉱物である。白色の母岩は主には菱亜鉛鉱と緑泥石(シャモス石)の混合体で、黄銅鉱がちらほらと見える。箕面石はアップルグリーンの皮膜状や粒状で母岩の上にちょこんと乗っている。粒のサイズは100ミクロンくらいあるのでルーペ無しでもなんとか視認はできる。20倍くらいのルーペでがんばれば鱗片状の組織が見えるかもしれない。またサーピエリ石やラムスベック石が箕面石の粒集合の中にポツンといたりする。全体的には白地の母岩にアップルグリーンの箕面石ばかりという産状なので鑑定はそれほど難しく無いように思えるが、同様の産状のシューレンベルグ石と並べられたら鑑定は難しい。組成的にも構造的に関連が疑われるので当然だが、箕面石の方がわずかに緑色が強く、かたちもほんのわずかにしっかりしている様に感じられる。
IMA No./year: 2012-020
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43652 )
伊勢鉱 / Iseite
Mn2Mo3O8
Kamiokite Group
Mn-dominant analogue of Kamiokite
模式地:三重県 伊勢市 矢持町 菖蒲
記載論文:Nishio-Hamane D., Tomita N., Minakawa T., Inaba S. (2013) Iseite, Mn2Mo3O8, a new mineral from Ise, Mie Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 108, 37-41.
三重県伊勢市から発見された新鉱物「伊勢鉱/Iseite」である。ちょうど一ヶ月前に科博の研究チームによる新鉱物・イットリウム苦土ローランド石(Magnesiorowlandite-(Y))が三重県からの新鉱物として承認され、我々の発見した伊勢鉱はそれに引き続いての承認となった。こんなの滅多にない。伊勢鉱も新聞報道され、平成24年7月3日中日新聞朝刊で紹介されている。
2013年時点で鉱物種は約4700種あるが、実はマンガン(Mn)とモリブデン(Mo)を主成分とする鉱物は伊勢鉱が世界初。一見あり得そうなこれら元素の組み合わせがこれまで天然ではなかったことは意外だった(合成物は存在する)。まあとにかく天然の地質作用は我々の想像より多様性に富んでいたということで、それを体現する伊勢鉱は学術的にもおもしろい鉱物だろう。
三重県からはこれまで3種の新鉱物が発見されている。カリ鉄パーガス閃石、イットリウム苦土ローランド石、そして今回の伊勢鉱となる。三重県からの新鉱物では3種目にして初めてルートネームがついた。旧国名「伊勢国」、現在の「伊勢市」から見つかった鉱物なので「伊勢鉱」と名付けた。「三重鉱」も候補だったがここはやはり「伊勢」の方がふさわしいだろう。「伊勢海老」や「伊勢神宮」のおかげもあって「伊勢」という名前には高級感と神秘的なイメージがすでにある。そういえば「伊勢」は神様の名前に由来しているらしい。そう思うとこの一見地味なこの新鉱物も神々しく輝いて見える気がしてきた。
金属光沢を持つ鉱物の和名は最後に「鉱(こう)」がつき、それ以外には「石(せき)」をつけるのが一般的なのだが昔はちょっと違った。その鉱物が有用な金属を含むかどうかが「鉱」・「石」の判断基準だった。例えば共生鉱物の菱マンガン鉱。化学組成はMnCO3でピンク色した透明な鉱物であるので菱マンガン石となるべきところが、なぜか菱マンガン「鉱」である。命名されたのは明治時代。そのころマンガンは重要な金属だった。鉱物になぜ「石」・「鉱」がついてるかを歴史に照らし合わせるとおもしろいかもしれない。日本から鉱山がすごい勢いでなくなってきだしたころから「石」・「鉱」の付けかたが今のセンスとなっている。
伊勢鉱は単独で菱マン中に集合体を作り、伊勢鉱と輝水鉛鉱の共存はむしろレアケース。その理由として硫黄がちょっとでも存在するとモリブデンは真っ先に硫黄と反応して輝水鉛鉱を作るのでそのなかでモリブデン酸化物は存在しにくい。それでも輝水鉛鉱との共存も無いことはなく、共存する標本は集合体の中で伊勢鉱の結晶面にコントラストがつくのでむしろ見分けやすい。一方で輝水鉛鉱の標本にむやみに「伊勢鉱を含む」といったラベルを貼るのはお奨めしない。基本的にはそれくらい輝水鉛鉱中には無いのだ。そもそもここでは輝水鉛鉱すら希産。「同じ脈に伊勢鉱が発見された」とか「伊勢鉱が見つかった石の一部」とか書いてある標本も当てにならない。
鉱石は磁鉄鉱・赤鉄鉱・カリオピライトが基質のいわゆる鉄マン。ベメント石・テフロ石・菱マンガン鉱が様々に基質を貫いており、菱マン脈中に輝水鉛鉱がまれに含まれる。伊勢鉱も菱マン脈中にきわめて希に含まれるが伊勢鉱は輝水鉛鉱とものすごく紛らわしい。なんというか、輝水鉛鉱はわかるのだが伊勢鉱がわからない。一見それっぽいモノでも詳しく調べると輝水鉛鉱だけというのがほとんど。硬度(伊勢鉱は4-5,輝水鉛鉱は1)が鑑定のポイントになると思うだろうが、引っ掻こうにも菱マン(硬度4)がじゃましてよくわからないし手加減を間違えると標本がふっとぶ。菱マン混じりの輝水鉛鉱ほど伊勢鉱そっくりに見えるから始末が悪い。伊勢鉱のほうがやや黒っぽく結晶片が大きくキラつくいて見えるのが輝水鉛鉱との違い。でもまあその程度。伊勢鉱の肉眼鑑定難易度はレベルMAX。金をかけずに伊勢鉱を手っ取り早く鑑定するには研磨薄片を作れば良い。一部をひっかいて接着剤でガラスに固定して紙やすりで#6000くらいまでスリスリすると輝水鉛鉱は周囲の菱マンよりくぼむけど伊勢鉱はくぼまない。
先にも述べたように特異な地質作用の証拠である伊勢鉱はおもしろそうで,もっと詳しく研究をしたいのだがいかんせんあまりにも希少。一方で伊勢鉱を胚胎する鉱床は秩父帯の層状鉄マン鉱床で、同じような層状鉄マン鉱床は四国に広く分布している。そのため四国にも産出の可能性はあると思っているが,伊勢と名付けてしまったからには伊勢でしか産出しないというほうがおもしろいかもしれない。
IMA No./year: 2011-099
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-43517)
イットリウム高縄石 / Takanawaite-(Y)
YTaO4
Polymorph of:Formanite-(Y), Iwashiroite-(Y), Yttrotantalite-(Y).
M-type polymorph.
模式地:愛媛県 松山市 高縄山
記載論文:Nishio-hamane D., Minakawa T., Ohgoshi Y. (2013) Takanawaite-(Y), a new mineral of the M-type polymorph with Y(Ta,Nb)O4 from Takanawa Mountain, Ehime Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 108, 335-344.

模式地標本 この産地のペグマタイトはほとんど雲母を伴わず、高縄石は石英と長石の境界に産する。メタミクト化しており非常に脆いため岩石を割る際の衝撃でほとんど割れてしまう。結晶面が見えることは稀。放射状に集合する傾向がある。
高縄石/takanawaite-(Y)。またしても愛媛県からの新鉱物となった。和名を正確に表現すると「イットリウム高縄石」だろうか。とりあえずツールネームの「高縄」を強調しよう。2011年は当たり年だったようで3つ目の新鉱物を申請することができた。
鉱物の名前の付け方にはいくつかルールがある。今回は希元素を含む鉱物名の付け方のお話。Takanawaite-(Y)は見てのとおり前「Takanawaite」と後「Y」に分かれている。前をルートネーム、後ろをサフィックスと呼ぶ。まずはルートネームのほうから説明しよう。簡単に言うとルートネームは希元素以外の化学組成と構造のことを指している。例えば希元素をREEで表したとする。そうすると「takanawaite」とはREE(Ta,Nb)O4で結晶構造が単斜晶系( I 2/a)のという意味になる。岩代石(Iwashiroite)だとREETaO4の単斜晶系( P 2/a)、フォーマン石(Formanite)だとREETaO4の正方晶系( P 格子)、イットロタンタル石(Yttrotantalite)だとREETaO4の斜方晶系ということになる。次にサフィックスについて。要は含まれる希元素で最も多いものを指す。最後に(Y)がついていればイットリウムが、もし(Gd)だったらガドリニウムが一番多く含まれているという意味となる。仮にGd(Ta,Nb)O4の化学組成の鉱物が見つかったとする。このとき結晶構造が単斜晶系( I 2/a)なら問答無用でそれはtakanawaite-(Gd)である。結晶構造が上記のいずれでも無い場合は新たルーツネームをつけられる。
合成実験ではY(Ta,Nb)O4には3つの安定相があることが知られており、それらはT, M, M’相と記述される。Y(Ta,Nb)O4鉱物はこれまでフォーマン石、イットロタンタル石、岩代石があり、岩代石はM’相にあたる。では,高縄石は何に相当するかというと,M相である。残りはT相なのだが、実はまだ発見(承認)されていない。
そうなるとフォーマン石とイットロタンタル石はいったい何者なのか?実はこの二つは合成実験では存在が確認されていない。記載年代も非常に古く、結晶構造と化学組成に関してデータが曖昧なままとなっている。しかしながらそれでも有効な鉱物種(valid species)となっているので非常に困る。さらには紛らわしい論文が存在し、そのせいで誤解する審査員もでてきて、高縄石の審査にはちょっと時間がかかった。まあともかく高縄石は新鉱物である。さあ論文を書こう。
高縄石は2002年の鉱物学会で一度はフォーマン石として報告している。加熱によるメタミクトからの構造回復の挙動がフォーマン石とやや異なることに当時から違和感を感じていたのだが、そのときは決定打がわからなかった。こういうのを「見落としていた」「勘違いをしていた」という言い方もあるが、簡単にはそのときの私には「見抜けなかった」のである。おかげで10年もほったらかすことになってしまった。
高縄石の産地・高縄山はもともとガドリン石の産地として有名だったが、私が愛媛大にいたときにはすでに産出が絶えて久しかった。そんな中2001年3月24日 芸予地震が発生した。各地で様々な被害を出しつつ高縄山でもいくつか崩落があった。そのうちガドリン石を産出するペグマタイトがピンポイントで大ダメージをうけ、道をふさぐほど大量に崩落したのである。その際に一時的にガドリン石の産出が復活し、そこに高縄石(当時はフォーマン石と思っていた)が多産した。それから約10年後、2011年3月11日の大震災を受けて今年度に予定していた研究がいくつかストップしてしまった。さてどうしようかと思いあぐねていたところに地震つながりでやや曖昧なままになっていたこの鉱物のことを思い出した。災い転じて福となす。昔に採集した試料を用い、当時よりは成長したであろう知識・技術で再検討したところ、新鉱物としての再発見につながった。
この産地で高縄石とやや間違えやすい鉱物はジルコンである。ともに放射状に集合する。しかし高縄石が板状結晶集合体であるのに対し、ジルコンは棒状の集合体である。ルーペがあれば間違えることはないだろう。黒緑色の最大2cmはある粒状結晶はガドリン石だ。結晶面が見えるものも多い。ものすごくレアだが灰色の棒状結晶がまれに見つかることがある。トルトベイト石を期待したのだがこれは褐簾石であり、すべてセリウムタイプだった。結晶の周囲に白色粉状のものが認められるのでセリウムラブドフェンが期待できるのだが手持ちの試料に乏しくまだ詳しく検討できていない。
さて愛媛閃石に引き続き高縄石も産経新聞に掲載された。翌日にはあいテレビ(NEWSキャッチあい)で報道され、さらに翌々日には愛媛新聞にも掲載された。「レアアースの新鉱物」という見出しで予想外に注目された。さあ次にいこう。 目指すのは日本発世界初。まずは発見しなければ何事も始まらない。
IMA No./year: 2011-043
IMA Status: A (approved)
模式標本:国立科学博物館(NSM M-41299)
宮久石 / Miyahisaite
(Sr,Ca)2Ba3(PO4)3F
Apatite supergroup
模式地:大分県 佐伯市 下払鉱山
記載論文:Nishio-Hamane D., Ogoshi Y., Minakawa T. (2012) Miyahisaite, (Sr,Ca)2Ba3(PO4)3F, a new mineral of the hedyphane group in the apatite supergroup from the Shimoharai mine, Oita Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 107, 121-126.


模式地標本 だいたい同じ視野を写真とBEI像で並べてみた。下のBEI像で白い部分が宮久石で,その中心にあるやや明るい灰色はフッ素燐灰石。
愛媛閃石の新鉱物承認からちょうど1ヶ月後に承認された新鉱物宮久石/miyahisaiteである。タイミング的に2011年の鉱物学会の予稿提出〆切に承認が間に合わなかったので2012年の鉱物学会で発表しようと思っているが、論文の方が先になってしまった。
名前の由来は愛媛大学教授であった宮久三千年(みちとし)にちなむ。共著者・皆川には二人の師匠がおり,一人は桃井ざくろ石の名前の由来となった桃井斉、もう一人が宮久三千年になる。私は皆川先生を通じて宮久先生と桃井先生の孫弟子にあたる。宮久先生は九州大分の出身で、九州の地質・鉱山の研究を通じて日本の鉱物学の発展に大きく貢献された。九州もしくは大分県からの新鉱物に名前をつけたいと思っていたところであった。
この鉱物を発見した当初は別の鉱物名を考えていた。というより命名規約から一意に決まってしまうと思っていた。この鉱物の組成をもっとも単純に考えると(Ba,Sr,Ca)5(PO4)3Fと書くことができる。これは既存鉱物・アルフォース石/alforsite,Ba5(PO4)3Clのフッ素置換体に相当する。そうなるとこの鉱物は「フッ素アルフォース石」と名付けるしか無い。もちろんこの場合でも新鉱物であるがちょっと冴えないと思っていた。しかしこの鉱物の構造は特殊で組成と構造を詳しく検討すると(Sr,Ca)2Ba3(PO4)3Fと表現すべき鉱物であるというのがわかった。そこで本鉱の産地・九州大分県ゆかりの人物で、皆川の師匠である「宮久」をルーツネームとして提案した。我々の期待通りに宮久石/miyahisaiteは無事に承認された。
母岩は一見はチャートである。ほとんどは石英だが、やや紫に見えるのはナマンシル輝石が含まれているからである。そういった母岩に入ってくる褐色の脈は主にエジリンからできており、この脈中に様々なBaに富む鉱物が存在する。宮久石はエジリン脈に沿うように紫色部に見つかることが多い。宮久石は無色透明であるが、細かい集合体であるため粒界効果によって全体はぼんやりとした白色に見える。それでも切断・研磨した上で、かなり拡大してようやく認識できる程度である。確実に宮久石を得るには分析装置付きの走査電子顕微鏡を使うしかないが、それでも簡単には見つからない。
この宮久石の記載によって2014年に日本鉱物科学会から櫻井賞(第41号メダル)を受賞した。受賞にあたり、宮久石についての研究紹介を岩石鉱物科学誌に書いているので、興味がある方はリンク先を参照してください。宮久石はこれまでの自分の経験が無駄じゃなかったなあと思い出させてくれる新鉱物である。もらったメダルについてもちょっとした後日譚を書いている。
IMA No./year: 2011-023 (2012s.p.)
IMA Status: Rd(Re-defined)
模式標本:国立科学博物館(NSM-M41160)
愛媛閃石 / Ehimeite(~2012)/ Chromio-pargasite(2012~)
NaCa2(Mg4Cr)(Si6Al2)O22(OH)2
Amphibole supergroup
模式地:愛媛県 新居浜市 東赤石山 赤石鉱山
記載論文:Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Minakawa T., Yamaura J., Saito S., Kadota R. (2012) Ehimeite, NaCa2Mg4CrSi6Al2O22(OH)2: The first Cr-dominant amphibole from the Akaishi Mine, Higashi-Akaishi Mountain, Ehime Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 107, 1-7.
愛媛県から発見された新種の角閃石(かくせんせき)、愛媛閃石/ehimeiteである。角閃石は現在120種以上が知られ、数え間違いでなければ愛媛閃石は124番目の角閃石となる。角閃石の新種は毎年のように発見されるし角閃石そのものは珍しくない(人気もあまりない)鉱物だが、クロムを主成分にもつ角閃石は愛媛閃石が初となる。そもそもクロム鉄鉱鉱床から角閃石が産出したのはこれが初めての例ではないだろうか。
角閃石の命名には多くのルール(規約)があり学名は化学組成に制約されるが、愛媛閃石の化学組成は命名規約の範疇になかった。命名規約に従うと名前がつかないのである。そういう事情からひとまず新しいルーツネームを提案してみたところ、問題なく承認された。産地から見える景色は壮大で緑豊か。さらに大きくきれいな鉱物なので名前も大きなものがよかろうと「愛媛」を提案した。なかなか良い名前だと思っている。この新鉱物は角閃石なので、和名はルートネーム(愛媛)+閃石で愛媛閃石となる。
さて、愛媛閃石は産経新聞で取り上げられることになり、「宝石のような新鉱物」というタイトルで写真が掲載された。宝石になるかどうかはともかく、見て映える新鉱物はひさびさという印象をもつ。「愛媛閃石がみかん色だったらもっとよかったね」とのちに言われたが、夏のみかん畑は緑一色であるから緑だってみかんの色でいいじゃないか。
写真を見たからというわけではないだろうが、新鉱物が承認された後すぐに「ほしい」という連絡があった。論文が公表されてからと伝えていったん引き下がったが、論文がオンライン公表されて数日後には「公表されたよね」と同じ彼からコンタクトがあった。なかなかの観察力・行動力である。その行動力を賞してせっかくなので差し上げることにした。彼は外国人。日本人から「よこせ」という知らせはまだ無い。(いまさら言われてもうない。)
愛媛閃石の鑑定ポイントは色・形と産状にある。色・形は見ての通りで、多産する淡緑色の透輝石とは一線を画している。だが実物を見たことがないと透輝石となかなか判断がつかないかもしれない。もし透輝石と判断がつかないようなら結晶の周囲を見てみよう。愛媛閃石には必ず金雲母が伴われている。実は愛媛閃石は透輝石との共存はかなりまれであるので慣れてくるとすぐ鑑定できる。
さて追記。2012年に角閃石命名規約の変更があり、学名がEhimeiteからChromio-pargasiteに変更になった。Ehimeiteの学名は承認されてたった一年で消滅と相成った。それでも日本には和名という文化があり、これは学名と一致する必要はない。たとえばカブトムシをあえて学名で呼ぶ文化はない。つまり学名としてEhimeiteは消滅しているが、命名者としては和名の愛媛閃石をずっと使い続けるつもりである。
私は修士課程まで愛媛大学で鉱物学を学び、博士課程は北海道大学へ進んで専門も地球深部科学へ転向した。学位を取った後の学振ポスドク時代も地球深部科学を専門としていたが、物性研究所の電子顕微鏡室へ就職して周りの環境を俯瞰すると、そこは地球深部科学よりむしろ記載鉱物学に向いた環境が整っていた。そういった中で改めて記載鉱物学に取り組む機会に恵まれ、自身では初筆頭著者として記載した新鉱物がこの愛媛閃石であった。
IMA No./year: 2009-026
IMA Status: A (approved)
模式標本:北海道大学総合博物館(Mineral-07401)
桃井ざくろ石 / Momoiite
Mn2+3V3+2(SiO4)3
Garnet supergroup
模式地:愛媛県 丹原町 鞍瀬鉱山(現:西条市)
記載論文:Tanaka H., Endo S., Minakawa T., Enami M., Nishio-Hamane D., Miura H., Hagiwara A. (2010) Momoiite, (Mn2+,Ca)3(V3+,Al)2Si3O12, a new manganese vanadium garnet from Japan, Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 105, 92-96.

緑色部に桃井ざくろ石が含まれる。
愛媛大と名古屋大の学生が中心となって発見されたざくろ石の新種、桃井ざくろ石である。愛媛と名古屋大学の研究チームが独自に別産地から発見しており、学会でほとんど同時期に発表した。新鉱物申請は共同研究という形でとりまとめられ、模式地は愛媛県鞍瀬鉱山となった。名古屋大学チームが見出した京都府法花寺野鉱山と福井県藤井鉱山からの桃井ざくろ石については、記載論文の際にデータを掲載した。桃井ざくろ石は岩手県田野畑鉱山からも産出が報告されており[1]、今のところ世界を見渡しても日本国内でしか産出が確認されていない。
桃井ざくろ石はマンガン(Mn)とバナジウム(V)を主成分としており、マンガンがカルシウム(Ca)に置き換わった鉱物はゴールドマンざくろ石(goldmanite)という名前がついている。桃井ざくろ石という名前についてその経緯を説明するには、このゴールドマンざくろ石について触れることになる。
ゴールドマンざくろ石はニューメキシコのSandy鉱山から1963年に見いだされ、アメリカ地質調査所のMarcus Isaac Goldman(1881-1965)に因んで命名された。ゴールドマンざくろ石は日本でもほぼ同時期に鹿児島県奄美大島大和鉱山から見つかっており、これを記載したのが九州大学にいた桃井斉であった[2]。大和鉱山のゴールドマンざくろ石はマンガンに富んでおり、あとちょっと多ければ今の桃井ざくろ石となるところだったが、残念ながらゴールドマンざくろ石の範囲に留まった。しかしゴールドマンざくろ石のマンガン置換体の存在が十分に予見可能ということで、桃井らは今の桃井ざくろ石に相当する仮想的な端成分にたいして大和ざくろ石(Yamatoite)の名前を当てて新鉱物として提案した。しかしながら現実として未見のモノにお墨付きは与えられないということで、大和ざくろ石の提案は否決されている。
こういったいきさつと桃井先生の思いがあったので、今回の申請にも最初は大和ざくろ石を考えていたが、再命名は混乱を招きそうでもあった。いくらか協議して最終的には桃井先生のこれまでの業績をたたえてMomoiiteと命名することにした。
さて非金属の鉱物の和名は「~石」となるのが慣例となっている。そしてこの「石」は「セキ」と読むということは実は意外に知られていない。多くのひとは「イシ」と読む。職場の人に説明するときに「それはセキと読むんだよ。鉱物学の基本ですな。」などと言っていたがざくろ石は例外的であることを忘れてた。ざくろ石グループに属する鉱物の和名は「~ざくろ石」となり、こいつはザクロ「イシ」と読む。つまり桃井ざくろ石は「モモイザクロイシ」と読む。
桃井ざくろ石は緑色が美しいざくろ石であるが、緑色部がかならず桃井ざくろ石という訳ではない。むしろ桃井ざくろ石は少数派でほとんどはゴールドマンざくろ石もしくはマンバンざくろ石である。鑑定のポイントは色の濃さと産状。経験的だが緑色が濃いものやテフロ石中にくるものは桃井ざくろ石を高確率で含む。ごくまれに黒色微小粒でヴォーレライネン石(vuorelainenite)がともなわれるが、それは分析しないとわからない。また黒い粒の99%以上は石墨である。それ故に黒いつぶつぶが伴われているから桃井ざくろ石ということにはならないし、その逆もまたしかりなので注意が必要。
[1] Matsubara S. Miyawaki R., Yokoyama K., Shigeoka M., Miyajima H., Suzuki Y., Murakami O., Ishibashi T. (2010) Momoiite and nagashimalite from the Tanohata mine,Iwate Prefecture, Japan. Bull. Natl. Mus. Nat. Sci, Ser. C, 36, 1-6
[2] Momoi H. (1964) A new vanadium garnet, (Mn,Ca)3V2Si3O12, from the Yamato mine,Amami Islands, Japan. Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University, Series D, 15, 73–78.
IMA No./year: 2006-055
IMA Status: A (approved)
模式標本:北海道大学総合博物館(Mineral-07400)
ストロンチウム緑簾石 / Epidote-(Sr)
CaSr(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH)
Epidote supergroup
模式地:高知県 香美市 穴内鉱山(鳳ノ森坑・長川原坑)
記載論文:Minakawa T., Fukushima H., Nishio-Hamane D., Miura H. (2008) Epidote-(Sr), CaSrAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)(OH), a new mineral from the Ananai mine, Kochi Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 103, 400-406
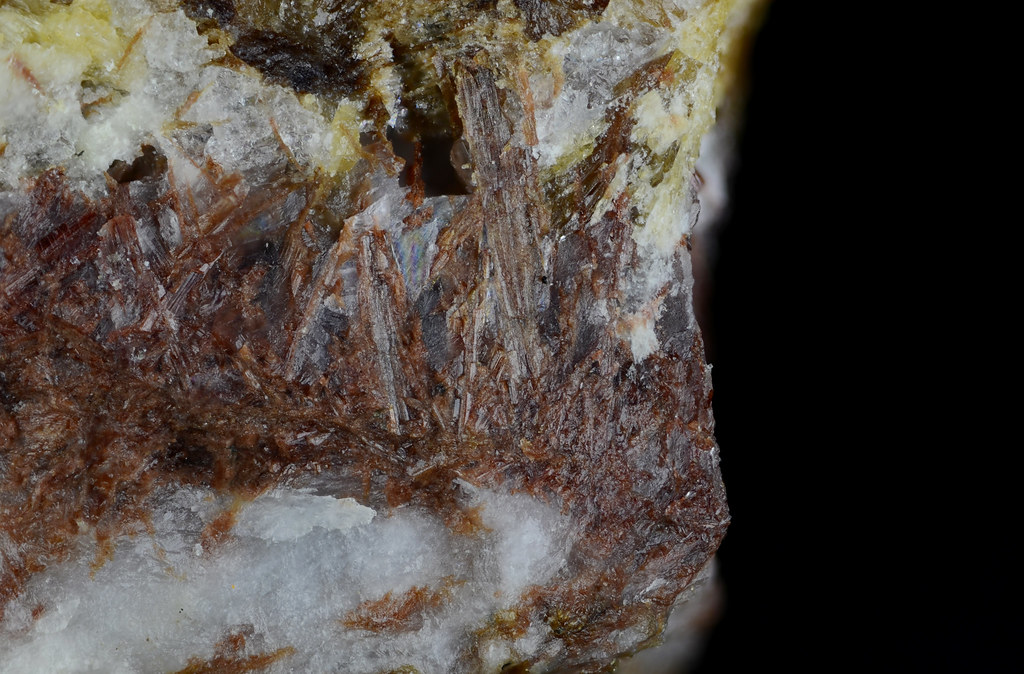
長川原坑から産した紅色のストロンチウム緑簾石
ストロンチウム緑簾石は私が初めて発見に関わった新鉱物で、紅いのに緑の名前をもつ変な鉱物である。肉眼鑑定に慣れた人ならこの鉱物を見て「紅簾石」と即答するだろう。我々もそのつもりで調べ始めたが結果は新鉱物/ストロンチウム緑簾石(リョクレンセキ)となる新種であることが明らかとなった。紅いのに緑を名前に持つ変な鉱物であるが、名前の付け方が命名規約で決まってしまっているのでいかんともしがたい。
見た目と名前のミスマッチはしばしば思いこみを誘い、せっかくのお宝を見過ごすことがある。ストロンチウム緑簾石を例に挙げてみる。
愛媛大学に保管してあった古い標本から「穴内鉱山長川原坑、紅簾石、チンゼン斧石」とラベリングされた試料がみつかった。見たところ確かに「紅簾石」である。しかし何となく気になって調べてみたところ、なんとこの「紅簾石」は新鉱物:ストロンチウム「緑簾石」そのものであった。そしてこの標本にはもう一つのラベルがあり、「標本玉手箱」と書かれていた。「標本玉手箱」は益富地学会館が鉱物趣味の普及の一環として会員に配布している標本である。つまり新鉱物はそれとは気づかれずに昔にすでに配布されていたことになる。その標本を手に入れた人は見た目から疑いもなく紅簾石だと思っただろう。しかし一度そのように思ってしまうと、改めて調べてみるきっかけはなかなか訪れない。
この経緯があって、いくつかの産地のいわゆる紅簾石についてその真贋を調べたことがある。結果はほとんどの場合は緑簾石という鉱物の範疇に入っていた。
さて、ストロンチウム緑簾石を見ただけでそれと鑑定するのは難しいが、穴内鉱山産に限っては産状によってある程度の鑑定ができる。鳳ノ森坑産はほとんど塊状の標本であり、その塊が角れき状に分断されている。その中に入っている数十~百ミクロンの結晶はストロンチウム緑簾石-ストロンチウム紅簾石の範囲で複雑な累帯構造となっている。一方でで長川原坑の標本については、特に黄色の斧石脈の中にある紅色の放射状の集合体は均質な組成となっており、そのほとんどはストロンチウム緑簾石であった。鳳ノ森坑のものは生成後に変質を受けているのに対し、長川原のものは初生的なのだろう。確実にストロンチウム緑簾石といえる標本を手に入れるためには産状も含めた鑑定が重要と思う。
この一連の研究は皆川の指導の下で、福島の修士論文の一環として行われた。彼の卒業後は北海道大学にいた私と三浦でデータを補強し、新鉱物申請という運びとなった。このストロンチウム緑簾石で皆川先生は日本鉱物学会から櫻井賞(第39号メダル)を受賞した。私にとっての新鉱物研究はこのストロンチウム緑簾石のお手伝いから始まっている。